第2節 国際交渉・フォーラム、国際アジェンダへの取組
1. G7/G20
(1) G7
イタリア議長年(2024年)
① 首脳会合
(i) G7プーリア・サミット
2024年6月13日から15日にかけて、イタリア・プーリアで、G7プーリア・サミットが開催された。岸田総理大臣は、世界が複合的な危機に直面している中、前年のG7広島サミットで強調した、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の堅持、グローバルサウスを始めとするG7を超えた国際的なパートナーへの関与の強化という二つの視点は、我々がロシアによるウクライナ侵略の継続や中東情勢の緊迫化などの新たな挑戦に直面している中で一層重要である旨述べた。また、こうした視点がG7伊議長下でも引き継がれていることを歓迎し、国際社会が直面する諸課題への対応をG7が主導するとの姿勢を改めて世界に示したいと述べた。
セッション1「アフリカ、気候変動、開発」では、気候変動について、岸田総理大臣から、アフリカの持続可能な開発を確保する観点からも、世界全体で気候変動対策を推進する必要があり、G7が引き続き先頭に立ちつつ、主要排出国も排出削減を実行することが重要である旨述べた。また、アフリカを含む脆弱国に対する適応及び強靱性強化のための支援に戦略的に取り組む必要があると述べた上で、気候資金の世界的取組に関して、日本の取組も紹介しつつ、先進国以外の主要経済国も然るべく貢献するような枠組みの設定が必要である旨指摘した。G7首脳は、アフリカの声に寄り添いながら、気候変動や開発を始めとする諸課題への対応においてG7が一層緊密に連携していくことを確認した。
セッション5「インド太平洋・経済安全保障」では、岸田総理大臣から、インド太平洋及び経済安全保障は、G7が国際社会をリードし続ける上で戦略的に重要である旨述べた。経済安全保障について、岸田総理大臣は、この課題における連携の在り方について、日本としての考えを説明した。G7首脳は、過剰生産や非市場的政策及び慣行に関する課題、経済的威圧への対処、サプライチェーンの強靱化、重要・新興技術の保全等について、今後も連携して取り組んでいくことを確認した。
セッション6「AI、エネルギー/アフリカ、地中海」では、AIのガバナンスに関し、岸田総理大臣から、前年広島AIプロセスで策定した国際指針や国際行動規範を実践するとともに、G7を超えてAIガバナンスに関する取組を進めていくことが重要である旨述べ、2024年5月に広島AIプロセス・フレンズグループを立ち上げ、既に50か国・地域以上の参加を得たことを紹介し、今後も協力を進めていきたい旨を述べた。また、その前提となる、DFFT(信頼性のある自由なデータ流通)の重要性についても強調した。加えて、エネルギーについては、岸田総理大臣から、AIの活用に伴い電力需要が急増する見込みであり、全ての社会・経済活動の土台であるエネルギーの安定供給確保は重要な課題であることを指摘した上で、エネルギー安全保障、気候危機、地政学リスクを一体的に捉え、経済成長を阻害せず、各国の事情に応じた多様な道筋の下で、ネット・ゼロという共通のゴールを目指すことが引き続き重要であり、日本は水素を含むあらゆる技術やエネルギー源を活用してイノベーションを推進し、世界の脱炭素化に貢献していく旨述べた。さらに、エネルギー移行に伴い需要が増す重要鉱物については産出国との協力が重要である旨指摘した。その上で、日本は「鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)」や「強靱で包摂的なサプライチェーンの強化(RISE)に向けたパートナーシップ」等を通じ、産出国での付加価値の創出を推進するとともに、多くの国から鉱業の研究者や行政官を招聘して人材育成を進めてきたことを紹介し、今後も協力していきたい旨述べた。
[参考]参加国・国際機関
<G7メンバー>
日本、イタリア(議長国)、カナダ、フランス、米国、英国、ドイツ、EU
<招待国>
アルジェリア、アルゼンチン、ブラジル(G20議長国)、バチカン、インド、ヨルダン、ケニア、モーリタニア(AU(アフリカ連合)議長国)、チュニジア、トルコ、UAE(※別途ゲストとして、ウクライナも参加。)
<国際機関>
AfDB(アフリカ開発銀行)、IMF(国際通貨基金)、OECD(経済協力開発機構)、国連、世界銀行
(ii) その他G7首脳会議
2024年には、議長国であるイタリアの主催により、サミット以外に計4回のG7首脳会議が開催された。このうち、ロシアによるウクライナ侵略が開始されてから2年となる機会を捉えて開催された同年2月24日のG7首脳テレビ会議では、岸田総理大臣から、2月19日にシュミハリ・ウクライナ首相及び多くのウクライナ政府・企業関係者を東京に迎え、日・ウクライナ経済復興推進会議を開催したことを紹介した。また、その際に、地雷対策など緊急復旧支援から中長期的な生活再建、デジタル・IT分野等の産業高度化のフェーズに至るまで、官民一体となってウクライナを力強く支援していく姿勢を表明し、計56本の協力文書を成果として発表することができたことを説明した。
② 貿易大臣会合
(i) 2024年第1回G7貿易大臣会合
2024年2月7日、齋藤経済産業大臣は、辻󠄀外務副大臣とともに、G7貿易大臣会合(テレビ会議形式)に出席した。会合では、同年2月26日からUAE・アブダビで開催される第13回WTO閣僚会議(MC13)に向けて、紛争解決制度(DS)改革、電子的送信に対する関税不賦課モラトリアム、「貿易と産業政策」を含む、G7としての優先事項等について議論を行い、G7貿易大臣声明を取りまとめた。
齋藤経済産業大臣からは、日本からG7議長国を引き継いだイタリアに祝意を表するとともに、前年の貿易大臣会合で確認した経済的威圧や非市場的な措置にG7が連携して対応することや、WTO改革や機能強化にしっかり取り組むことについて、イタリアがこれらの取組を引き継ぎ、発展させることへの期待を述べた。また、WTOの個別論点として、①DS改革について、MC13で有意義な成果を出せるよう、各国が最大限の努力を続けるべき、②「貿易と産業政策」について、MC13での審議の場創設を支持しており、当該審議の場での成果も念頭に、MC13後に具体的な対応策の検討を深めるべき、③電子的送信に対する関税不賦課モラトリアムについて、MC13で商業的に有意義な成果を得るべく、恒久化、少なくとも延長を実現することが不可欠であり、関係各国との調整を進めるべき、④電子商取引交渉について、2024年の適時に妥結することが重要であり、共同議長国として、交渉を加速すべくG7各国とも協力していきたい、と発言した。
(ii) 2024年第2回G7貿易大臣会合
2024年7月16日及び17日、イタリア・カラブリア州でG7貿易大臣会合が開催され、日本からは、齋藤経済産業大臣及び上川外務大臣が出席した。会合では、前年のG7日本議長年や6月のプーリア・サミットの成果も踏まえ、(1)WTO及び公平な競争条件、(2)貿易と環境持続可能性、(3)経済的強靱性と経済安全保障、をテーマにしたG7メンバー間の三つのセッション、及び(4)パートナー国・機関や産業界(※以下の「招待国・機関」を参照)を交えた、サプライチェーン強靱化に関するアウトリーチセッションが開催され、最後に、G7貿易大臣声明が採択された。
各セッションについて、(1)WTO及び公平な競争条件のセッションでは、齋藤経済産業大臣より、国際経済体制を「弱肉強食」の世界に戻さないためにはWTOの機能回復・強化が必須である旨述べた上で、①DS改革について、MC13で確認した2024年までの完全なかつよく機能する紛争解決制度の実現に向けて取組を加速すべきこと、②WTO電子商取引交渉について、電子的な送信に対する関税賦課の恒久的な禁止を含めた商業的に有意義なパッケージでの早期妥結を目指すべきこと、③「公平な競争条件」について、WTOにおける「貿易と産業政策」に関する対話をできるだけ多くのメンバーが参加する形で進めるとともに、WTOの外でも、改訂版OECD国有企業コーポレートガバナンスガイドライン等を活用してグローバルな規範形成に取り組むべきことを述べた。また、上川外務大臣より、MC13で合意に近づいた案件について早期に成果を得る必要性を強調し、これまでにない新たな発想を持ってWTO改革を進めていくべきと指摘した。(2)貿易と持続可能性のセッションでは、齋藤経済産業大臣より、貿易関連の気候変動措置が、不当に貿易制限的にならない形で設計されるよう、特に国境を越える製品の炭素集約度の計測手法のあるべき姿について具体的な検討を進めるべきことや、貿易と環境持続可能性の両立にはグローバルサウスとの連携が極めて重要であること等を発言した。また、上川外務大臣からは、貿易政策が環境持続可能性と相互補完的となるよう、G7が主導的な役割を果たしていく必要性を強調するとともに、貿易への女性の参加促進の重要性を指摘し、日本がアフリカやウクライナなど世界各国で実施している女性の就労・企業支援の取組を今後も続けていく旨述べた。(3)経済的強靱性と経済安全保障については、齋藤経済産業大臣より、市場において価格以外の要素が正当に評価されることが必要であり、「持続可能性」や「信頼性」などの「共通の原則」に照らして、脱炭素、安定供給、サイバーセキュリティ等の「クライテリア」を政府調達や補助金といった政策ツールに実装していく必要がある旨発言したほか、最近の重要鉱物に対する輸出管理措置について、日本として極めて強い懸念を有しており、G7として一致したメッセージを発信すべき旨述べた。上川外務大臣より、過剰生産能力について、それを生み出す非市場的政策・慣行(NMPP)に適切に対処する重要性を指摘するとともに、経済的威圧への対処に向けて、G7自身の対抗力の強化及びG7を超えた連携の重要性を強調した。(4)サプライチェーン強靱化に関するアウトリーチセッションでは、齋藤経済産業大臣より、「強靱で信頼性のあるサプライチェーン原則」も踏まえて、G7自身が、信頼できるパートナーとして途上国の持続的な成長にコミットしていくことが重要であり、日本としても、各国との協力のために確保した予算も活用しながら、途上国とともに強靱なサプライチェーンの構築に取り組む旨述べた。また、上川外務大臣より、①G7広島サミットにおいて首脳間で確認した「信頼性」の原則を共有する同志国間の連携や官民連携、②鉱物サプライチェーンの生産・加工・投資における高い環境・社会・ガバナンス(ESG)基準のグローバルな推進、③G7として資源国への積極的な支援が重要である旨強調した。
[参考]招待国・国際機関
<招待国>
豪州、ブラジル、チリ、インド、ケニア、韓国、ニュージーランド、トルコ、ベトナム
<招待機関>
WTO、OECD
③ 産業・技術・デジタル大臣会合
(i) 2024年G7産業・技術・デジタル大臣会合
2024年3月14日及び15日の2日間にわたり、イタリア・ヴェローナ及びトレントで、G7産業・技術・デジタル大臣会合が開催され、日本から、石井経済産業大臣政務官と、河野デジタル大臣、長谷川総務大臣政務官が参加した。
本会合では、(1)産業におけるAIと新興技術、(2)安全で強靱なネットワーク、サプライチェーン及び主要な投入要素、(3)デジタル開発-共に成長、(4)公的部門におけるAI、(5)広島AIプロセスの成果の前進、(6)デジタル政府に関する議論が行われ、会合の成果として、閣僚宣言が採択された。
石井経済産業大臣政務官からは、14日の会合で、デジタル技術の産業利用の観点から、AIの開発促進と規律確保、量子の早期の産業化について発信するとともに、公正なデジタル競争環境に向けた国際連携の重要性を強調した。また、半導体のサプライチェーン強靱化に向けたG7諸国間の連携強化や、戦略物資の持続可能で信頼性のある製品が選択されるマーケット作りに向けた協力の重要性について発言した。また、15日の会合では、AIガバナンスの観点から、我が国におけるAIセーフティ・インスティテュートの立上げについて紹介するとともに、AI安全性評価手法の策定やAIガバナンス枠組み間の相互運用性の確保に向けた国際協調の重要性を発信した。
[参考]招待国・国際機関
<招待国>
ブラジル、韓国、ウクライナ、UAE
<国際機関>
ITU(国際電気通信連合)、OECD、UNDP(国連開発計画)、UNESCO(国連教育科学文化機関)、国連
(ii) 2024年G7産業・技術イノベーション大臣会合
2024年10月10日にG7産業・技術イノベーション大臣会合が開催され、日本から、上月経済産業副大臣及び竹村総務省国際戦略局長がオンラインで出席した。
本会合では、同年3月に採択されたG7産業・技術・デジタル閣僚宣言において、年内に作業を継続することとした取組の作業結果を確認するとともに、①重要部門におけるグローバル課題新時代への対応ツールとしての産業政策、②企業におけるAI導入の推進要因及び課題等について議論が行われた。会合終了後に議長国イタリアから発出された議長国サマリーでは、半導体産業における非市場的政策及び慣行について、緊急かつ喫緊の課題として閣僚間で議論した旨言及された。また、6月のプーリア首脳コミュニケにおいて、持続可能性や信頼性等の価格以外の要素も考慮した基準の検討についてG7で連携する必要がある旨言及されたことに留意し、特に半導体に関して、包括的で多様な政策ツールを活用し、強靱で信頼性のあるサプライチェーンを構築及び強化する重要性が強調された。
「重要部門におけるグローバル課題新時代への対応ツールとしての産業政策」セッションにおいて、上月経済産業副大臣からは、サプライチェーン強靱化や重要な産業分野における非市場的な政策・慣行と過剰生産能力の監視など、G7メンバー間の連携を深化すべき重要項目として6月のプーリア・サミットで合意した内容について、G7産業大臣会合でも具体化すべきであること、その一環として、一部の国への過剰な依存に伴うリスクの低減とサプライチェーン強靱化に向けて、「持続可能性」や「信頼性」など価格以外の要素が市場で正当に評価されるよう、必要な取組を進めていくべきであること、などについて発言した。また、「企業におけるAI導入の促進のための推進要因及び課題」セッションにおいて、我が国からは、国内におけるデジタルスキルの向上に向けた取組について紹介し、特に中小企業がAIを始めとするデジタル技術を活用するために、G7メンバー間で連携することの意義について発言した。
[参考]招待国・国際機関
<招待国>
オランダ、インド、韓国
<国際機関>
ITU、UNDP
(iii) 2024年G7デジタル・技術大臣会合
2024年10月15日に、イタリア・チェルノッビオ(コモ)で、G7デジタル・技術大臣会合が開催され、日本から、浅沼デジタル監、今川総務審議官、渋谷大臣官房審議官(IT戦略担当)が参加した。
本会合では、2024年3月に採択されたG7産業・技術・デジタル閣僚宣言において、年内に作業を継続することとした取組の作業結果を確認するとともに、二つのテーマ(「公的部門におけるAIツールキット、デジタル政府サービス大綱及びデジタル・アイデンティティ・アプローチのマッピング演習」、「広島AIプロセスの成果の前進について」)について議論が行われ、共同声明が採択された。
[参考]招待国際機関
<国際機関>
OECD、UNESCO
④ 気候・エネルギー・環境大臣会合
2024年4月29日、30日に、イタリア・トリノにおいてG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、齋藤経済産業大臣及び伊藤環境大臣、八木環境副大臣が出席した。気候・エネルギー分野においては、2023年のG7広島サミットからの継続性とCOP28で決定されたグローバル・ストックテイク(GST)の実施に重点を置きつつ、ネット・ゼロの加速、エネルギー安全保障の確保、途上国との連携等について議論が行われ、気候・エネルギー・環境大臣会合として、閣僚声明が採択された。閣僚声明には、2030年までの世界全体の再エネ容量3倍目標に向けて既存の政策等を通じたエネルギー貯蔵の世界目標1,500GWへの貢献、2030年までの世界のエネルギー効率改善率2倍目標に向けた省エネ関連の情報開示や中小企業支援の促進、2025 年までの非効率な化石燃料補助金の廃止、2035年までの電力部門の完全又は大宗の脱炭素化、2023年のG7日本で一致した「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」の実施、水素・アンモニアにおける「炭素集約度」の概念を含む国際標準、認証スキーム構築の重要性、鉄鋼製品及び製品の排出に関する「グローバルデータ収集フレームワーク」の実施、削減貢献量の価値の確認に加え、天然ガス投資の必要性やガスセキュリティに関するIEA(国際エネルギー機関)の機能強化、クリーンエネルギー技術のサプライチェーン強靱化の重要性、革新技術(ペロブスカイト、浮体式洋上風力、革新炉、フュージョンエネルギー等)、トランジション・ファイナンスの重要性等について盛り込まれた。
[参考]招待国・国際機関
<招待国>
アルジェリア、ケニア、ブラジル、UAE、アゼルバイジャン
<国際機関>
IEA、IRENA、OECD、国連、UNEP(国連環境計画)、UNDP、UNFCCC(国連気候変動枠組条約)事務局、AU、AfDB、ODI(海外開発研究所)
(2) G20
ブラジル議長年(2023年12月~2024年11月)
① 首脳会合
(G20リオデジャネイロ・サミット)
2024年11月18日及び19日、ブラジル・リオデジャネイロにてG20リオデジャネイロ・サミットが開催された。
セッション1「飢餓と貧困との闘い」では、石破総理大臣から、気候変動に関し、世界の温室効果ガス排出量の約8割を占めるG20は、世界のリーダーとして、気候変動対策、経済成長、エネルギー安全保障の同時実現に責任を有し、1.5℃目標と整合する総量削減目標を含む、野心的な次の「国が決定する貢献(NDC)」を策定し、実行することが重要であり、各国の事情に応じた多様な道筋の下で、2050年ネット・ゼロという共通目標を達成したいと考える旨述べた。
セッション2「グローバル・ガバナンス機構改革」では、WTO改革やAIに係る国際協力を含むグローバル・ガバナンス改革について議論が行われ、石破総理大臣から、WTO改革について、デジタル化が進む国際貿易の世界において、WTO改革は喫緊の課題であり、共に政治的な推進力を与えたいとした上で、特に、紛争解決機能の回復は急務であり、WTOが目の前の課題を着実に実現していくことも重要と述べた。
セッション3「持続可能な開発とエネルギー移行」では、1.5℃目標達成に向けた気候変動・エネルギー移行の取組や持続可能な開発等について議論が行われた。G20メンバーは、G20が世界の温室効果ガス排出の80%を占めていることを踏まえ、G20が果たすべき主導的役割を認識しつつ、気候変動・エネルギー移行に向けた取組を強化することへのコミットメントの重要性を共有した。
[参考]参加国・招待国・国際機関
<G20メンバー>
日本、ブラジル(議長国)、アルゼンチン、豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、メキシコ、韓国、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、英国、米国、AU、EU
<招待国>
アンゴラ、ボリビア、チリ、コロンビア、エジプト、マレーシア、モザンビーク、ナイジェリア、ノルウェー、パラグアイ、ポルトガル、カタール、シンガポール、スペイン、タンザニア、UAE、ウルグアイ、ベトナム、バチカン
<国際機関>
AfDB、AIIB(アジアインフラ投資銀行)、CAF(ラテンアメリカ開発銀行)、FAO(国連食糧農業機関)、FSB(金融安定委員会)、IDB(米州開発銀行)、ILO(国際労働機関)、IMF、LAS(アラブ連盟)、NDB(新開発銀行)、国連、UNCTAD(国連貿易開発会議)、UNESCO、世界銀行、WHO(世界保健機関)、WTO
② 貿易・投資大臣会合
2024年10月23日から27日にかけて、G20貿易・投資大臣会合がブラジルで開催され、松尾経済産業審議官及び片平外務省経済局長が出席した。本会合では、(1)WTO改革と多角的貿易体制の強化、(2)国際貿易における女性、(3)貿易と持続可能な開発、(4)投資協定における持続可能な開発について議論がなされた。
松尾経済産業審議官からは、(1)WTO改革と多角的貿易体制の強化について、①紛争解決(DS)制度改革については、第13回WTO閣僚会議(MC13)で確認した2024年までの完全なかつよく機能する紛争解決制度の実現に向けて取組を加速していく必要がある旨、②公平な競争条件の確保については、「貿易と産業政策」に関する対話の場も活用して、現行のWTOルールが適切に機能しているのか検証し、機能していない部分についてはどう改善すべきか議論を深めていくべき旨、③有志国による新たなルール形成の取組である共同声明イニシアティブ(JSI)については、WTO協定への組込みに向けて、政治的モメンタムが必要である旨を述べた。また、(2)国際貿易における女性については、日本が実施している女性活躍推進に優れた企業を銘柄として選定し投資家に紹介する取組や、女性起業家のための海外派遣、資金調達支援等を紹介したほか、国際貿易センター(ITC)を通じたアフリカ等でデジタル技術を活用した女性の就労・起業支援についても触れ、今後もこうした取組を推進していきたいと発言した。
[参考]招待国・国際機関
<招待国>
チリ、エジプト、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、ポルトガル、シンガポール、スイス、スペイン、UAE、ウルグアイ
<国際機関>
WTO、世界銀行、OECD、ITC(国際貿易センター)、UNCTAD、CAF、FAO、IDB、ILO
③ デジタル経済大臣会合
ブラジルが議長国を務め、2024年9月13日に、G20デジタル経済大臣会合がブラジル・マセイオで開催された。本会合には、日本から石川デジタル副大臣、今川総務審議官が参加し、①デジタル包摂性、普遍的で意味のある接続性、②デジタル政府と包摂的なデジタル公共インフラ(DPI)、③オンライン上の情報インテグリティとデジタル経済における信頼性、④包摂的で持続可能な開発と不平等削減のためのAIが議題され、会合の成果物として、閣僚文書及び付属書議論の内容を踏まえた成果文書及び議長総括が発出された。
[参考]参加した招待国・国際機関
<招待国>
デンマーク、ナイジェリア、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、UAE
<国際機関>
ITU、OECD、UNDP、UNESCO、UNIDO(国連工業開発機関)
④ エネルギー移行大臣会合
2024年10月4日、G20エネルギー移行大臣会合がブラジルのフォス・ド・イグアスにて開催された。G20エネルギー移行大臣会合では、①新興・発展途上国のエネルギー移行のためのファイナンス、②エネルギー移行の社会的側面、③持続可能燃料などの論点について議論され、閣僚声明及び付属文書が採択された。
[参考]参加した招待国・国際機関
<招待国>
デンマーク、ポルトガル、スペイン、シンガポール、UAE、チリ、ノルウェー
<国際機関>
AU、CAF、CEM(クリーンエネルギー大臣会合)、GECF(ガス輸出国フォーラム)、ILO、IEA、IRENA、ISA(太陽に関する国際的な同盟)、MI(ミッション・イノベーション)、世界銀行、WEF(世界経済フォーラム)、OPEC(石油輸出国機構)、SEforALL(万人のための持続可能なエネルギー)等
2. OECD
(1) 経済協力開発機構(OECD)閣僚理事会
① 2024年OECD閣僚理事会
2024年5月2日及び5月3日、OECD閣僚理事会(Meeting of the Council at Ministerial Level: MCM)が、「変化の流れの共創:持続可能で包摂的な成長に向けた客観的で高い信頼性に裏付けられたグローバルな議論の先導」というテーマの下、開催された。OECD加盟60周年を迎えた日本が議長国を務め、日本からは、岸田総理大臣、上川外務大臣、齋藤経済産業大臣、新藤内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、松本総務大臣、河野デジタル大臣及び森屋内閣官房副長官ほかが参加した。
開会セレモニーでは、岸田総理大臣が議長国基調演説を行うとともに、OECD東南アジア地域プログラム(SEARP)10周年記念式典に出席した。議長国基調演説において、岸田総理大臣からは、国際経済がインフレ、エネルギーや食料の供給途絶、サプライチェーン分断等のリスクに直面する中、「変化の流れの共創」の精神の下に結束し、国際社会が直面する危機を乗り超える重要性を強調した。また、日本のOECD加盟から60年が経ち、国際社会が多極化や分断と紛争に直面する中、「共通の価値」を持つOECDが、東南アジア地域を始め、世界の様々な地域の非加盟国へアウトリーチしていく重要性を指摘した。さらに、日本は数少ないアジアの加盟国として、OECDとアジア地域の架け橋となり、OECDが将来にわたって世界経済を主導するための貢献を果たしていく考えを発信した。
続くSEARP10周年記念式典でのスピーチでは、岸田総理大臣から、信頼できるデータと分析というOECDの強みを東南アジアの持続可能な成長につなげるため、「日本OECD・ASEANパートナーシップ・プログラム(JOAPP)」の立上げを発表した。さらに、東南アジア地域におけるOECD の関与を強化するERIA(東アジア・ASEAN経済研究センター)との覚書の改訂が歓迎された。
会合では、マクロ経済、自由で公正な貿易・投資、経済的強靱性、OECDによる非加盟国へのアウトリーチ、環境問題・気候変動、持続可能な開発、AI・DFFTを含むデジタル等のトピックについて、日本が議長国として議論を主導した。
齋藤経済産業大臣は、自由で公正な貿易・投資に関するセッション、経済的強靱性のセッションに出席し、特に、経済的強靱性のセッションでは、議長として、サプライチェーン強靱化、経済的威圧への対処、非市場的政策及び慣行への対応等の議論を牽引した。
会合の最後には、閣僚理事会の成果として、閣僚声明が採択された他、「国有企業のコーポレートカードガバナンス・ガイドラインについてのOECD勧告」の改訂版などの成果文書も併せて採択された。
[参考]キーパートナー国・招待国・国際機関
<キーパートナー国>
ブラジル、中国、インド、インドネシア、南アフリカ
<招待国・地域>
アルゼンチン、ブルガリア、香港、クロアチア、エジプト、ラオス、モロッコ、ペルー、ルーマニア、シンガポール、タイ、ウクライナ、ベトナム
<その他>
ASEAN、AU、BIAC(経済産業諮問委員会)、TUAC(労働組合諮問委員会)、IEA他
3. WTO全体の動向
(1) WTO389全体の動向
WTO設立後初のラウンド交渉として、2001年にカタールのドーハで開催された第4回WTO閣僚会議(MC4)において、途上国の要求に配慮する形で立ち上げられたドーハ開発アジェンダ(以下、ドーハ・ラウンド)(交渉項目は以下の第III-2-2-1表を参照)は、その後、交渉分野や参加国の多さ、先進国と新興国の意見の懸隔といった理由から、交渉が長期化した(第III-2-2-2図)。
第Ⅲ-2-2-1表 ドーハ・ラウンド一括受託の交渉項目と主要論点390
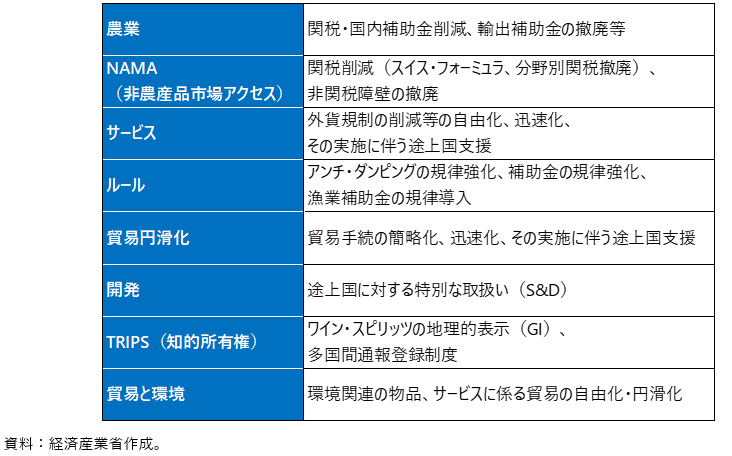
第Ⅲ-2-2-2図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯
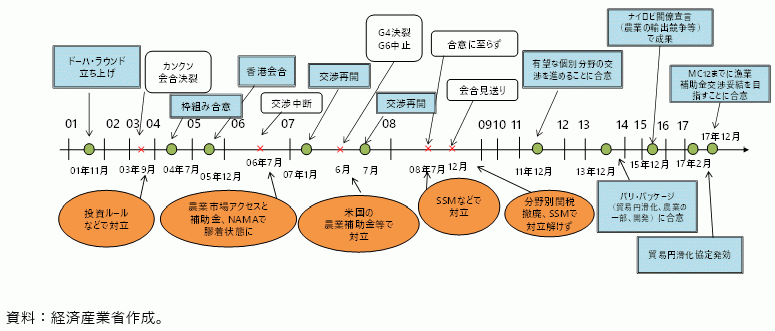
2017年12月にアルゼンチンのブエノスアイレスで行われた第11回WTO閣僚会議(MC11)でも、主要分野では大きな前進が得られず、成果文書も議長声明の発出にとどまったが、各加盟国からはWTOに関与し続ける姿勢が示された。漁業補助金について、第12回WTO閣僚会議(MC12)に向けて議論を継続することとなったほか、電子商取引、投資円滑化、中小零細企業(MSMEs)、サービス国内規制といった今日的課題について、今後のWTOにおける議論を後押しする有志国の共同声明が発出された。
現状の貿易を取り巻く問題は、市場歪曲的な措置やデジタル保護主義の広がりなど多様化しているが、WTOはこれらに十分に対応できず、一方的な貿易制限措置や対抗措置の応酬や紛争解決機能の一部停止の誘因の一つになっていることから、WTOの機能改善に向けた「WTO改革」の機運が高まっている(後述)。WTO改革の議論の加速が期待される中、2020年春以降のコロナ禍により、MC12は複数回延期となったが、まず2021年12月にはサービス国内規制、投資円滑化、電子商取引、貿易と環境持続可能性といった多様な分野で有志国による共同宣言・声明が発出された。その後、2022年6月にスイスのジュネーブでMC12が開催された。会議では、特に新型コロナウイルス感染症によるパンデミックや食料安全保障等の喫緊の危機への対応が焦点となり、6年半ぶりに全加盟国での閣僚宣言を採択した(MC12までの具体的な成果については、通商白書2024を参照)。
MC13は、2024年2月にアラブ首長国連邦(UAE)のアブダビで開催された。会議では、DS改革、審議機能強化、電子商取引、開発、漁業補助金、農業等に焦点を当てて議論が行われ、成果として、閣僚宣言と個別の閣僚決定を採択する形となった。多くの国にとって最も大きな関心事項のひとつであるDS改革については、これまでの進捗を土台として議論を加速させ、MC12で合意した2024年までの目標の達成に向け、上訴/レビューやアクセシビリティを含む未解決の論点に取り組むことが合意された。また、電子的送信に対する関税不賦課モラトリアムについては、第14回WTO閣僚会議(MC14)又は2026年3月31日のいずれか早い日まで延長することが決定された。また、WTOにおける途上国の声の拡大に伴い、途上国の経済発展や開発に着目した決定もなされた。例えば、LDCから卒業した国に対しては、一定の移行支援を実施することが確認されたほか、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)及び貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)の効果的な実施を支援するため、LDCを含む途上加盟国に対する技術支援、訓練及び能力構築の重要な役割等について確認する閣僚宣言が採択された。一方で、日本を含めて多くの国が追求していた論点の中には、一部加盟国の反対により合意できなかったものもある。例えば、審議機能の強化の一環として目指していた新たな審議課題に関する議論の場の立上げや、漁業補助金協定の追加規律への合意は実現されなかった。
また、MC11で発出された共同声明に基づいて交渉が進められた共同声明イニシアティブ(JSI)のうち、サービス国内規制に関しては、有志国間での規律案の議論を経て、GATS の約束表に、追加的な約束として新たな規律を取り込む手続を進めた。その結果、2024年2月、我が国やEU 27 か国を含む52か国・地域について、WTOの手続が完了した。投資円滑化に関しては、2023 年 7 月に「開発のための投資円滑化に関する協定」のテキスト交渉が妥結し、MC13で、交渉妥結の宣言と協定条文を公表する旨の閣僚宣言を発出した。さらに、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書 4に同協定を組み込むよう要請したが、 WTO 加盟国によるコンセンサスを得られておらず、その後、一般理事会でも議論が行われている。
MC13後には、2024年5月に行われた OECD閣僚理事会及びAPEC 貿易担当大臣会合、同年7月のG7貿易大臣会合、同年10月のG20貿易・投資大臣会合などで、MC13の成果が改めて確認されたほか、WTO改革をさらに進めていく旨の合意が繰り返しなされている。
MC13で審議の場の立上げが実現されなかった「貿易と産業政策」については、2024 年 9 月以降、ジュネーブにおいて非公式な形で議論が実施されている。各国が持ち回りでセッションを実施し、各セッションとも多くのメンバーの参加を得ており、2025年2月には、日本も、EU及びケニアと共催する形で、「産業補助金の透明性」についてのセッションを実施した。また、2024年内の実現が目指されていたDS改革については、年内での改革実現は果たされなかったが、上訴/レビューやアクセシビリティ等の論点について多くの議論が重ねられた。加えて、電子的送信に対する関税不賦課モラトリアムについては、2024年9月以降毎月、電子商取引作業計画に関する特別会合が開催され、主に開発の側面に関する議論が行われている。
389 1930年代にまん延した保護主義が第二次世界大戦の一因となったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し、1948年に、最恵国待遇・内国民待遇を大原則とするGATT(関税及び貿易に関する一般協定)が発効した。1995年には、GATTを発展的に改組してWTOを設立した。現在166か国・地域が加盟するWTOは、①交渉(ラウンド交渉などによるWTO協定の改定、関税削減交渉)、②紛争解決(WTO紛争解決手続による貿易紛争の解決)、③監視・透明性(多国間の監視による保護主義的措置の抑止)の機能を有し、多角的な貿易を規律する世界の貿易システムの基盤となっている。
390 ラウンド立上げ当初は、投資、競争、貿易円滑化、政府調達の透明性のいわゆる「シンガポール・イシュー」が検討の対象として含まれていたが、カンクン閣僚会議で貿易円滑化のみにつき交渉を始めることとされた。
(2) WTO改革の必要性及び現状
1995年にWTOが設立されてから、四半世紀が経過した。その間の新興国の台頭や産業構造の変化により、WTOは現状の貿易を取り巻く問題に十分に対応できていないとの批判があり、一部の国による一方的な貿易制限措置や対抗措置の誘因の一つになっている。このため、保護主義を抑止し、自由で開かれた貿易体制を維持するためにも、WTOの機能改善に向けた「WTO改革」の機運は引き続き高まっている。
WTOは、①交渉、②紛争解決、③監視・審議の三つの機能を有しており、以下、それぞれの機能改革について、その必要性及び現状について概観する。
① 交渉機能
交渉機能改革について、ドーハ・ラウンド交渉立上げから20年以上経過する中で、2022年のMC12では漁業補助金に係る協定に全加盟国で合意するとの成果があったものの、全加盟国による全会一致(コンセンサス)の原則の下でのルール形成は困難な状況となっている。全ての加盟国によるラウンド交渉が進まない中、情報技術協定(ITA)拡大や電子商取引交渉といった有志国による個別ルール・分野毎の複数国間(プルリ)交渉が積極的に行われてきた。例えば、ITAについては、新型半導体など新たな品目を盛り込んだ拡大ITAが2015年に妥結されている。我が国は現在、APEC域内におけるITAの重要性や意義について再確認するためのAPECプロジェクトを実施するなど、ITAの取組の推進と拡大を図っている。また、2017年のMC11において、電子商取引、投資円滑化、中小零細企業(MSMEs)、サービス国内規制といった、現在の世界経済が直面する課題に即した分野に関する有志国による四つのJSIが立ち上がる等、交渉機能向上に向けて取り組んでいる。
電子商取引と投資円滑化それぞれのJSIの詳細は以下のとおりである。
(A)電子商取引共同声明イニシアティブ交渉
MC11で発出された共同声明にもとづき、2018年3月から、将来のWTO電子商取引ルールに含まれるべき要素について議論を行う探求的作業が開始された。同年12月までに、約80以上の加盟国が参加して計9回会合が開かれ、電子署名、オンラインの消費者保護、データ流通等幅広い論点について議論が行われた。
2019年1月、スイス(ダボス)において、日本は、豪州、シンガポールと共に、WTOの電子商取引に関する非公式閣僚級会合を主催した。同会合で各国代表は、WTOにおけるルール作りの意義等について意見交換を行い、会合後、国際貿易の約90%を代表する76の加盟国391で、電子商取引の貿易側面に関する交渉を開始する意思を確認する共同声明を発出した。同年6月、G20大阪サミットの機会に、安倍総理大臣が「デジタル経済に関する首脳特別イベント」を主催し、トランプ大統領、ユンカー欧州委員会委員長、習近平中国国家主席など27か国の首脳及びWTOを始めとする国際機関の長が出席した。「大阪トラック」を立ち上げる旨の「デジタル経済に関する大阪宣言」が発出され、電子商取引JSIに参加する78か国・地域と共に、電子商取引JSI交渉について、MC12までに実質的な進捗を得ることを目指す旨合意した。
2023年12月には、サイバーセキュリティやオンライン消費者保護等の13条文について交渉が実質的に妥結したこと、残された条文の収斂に向けて引き続き努力すること、さらに、2024年の適時に交渉妥結するために努力することについて宣言する共同議長国声明を発出した。2024 年 7 月、共同議長国は、交渉参加国・地域を代表して、電子商取引に関する協定に係る安定化したテキストを達成した旨の共同議長国声明を発出するとともに、テキストを公表した。合計 38 条文からなる同テキストは、①貿易書類の電子化や規制の透明化等を通じた電子決済の促進による電子商取引の貿易円滑化、②政府データの公開やインターネットのアクセス・使用を通じた開かれた電子商取引の確保、③サイバーセキュリティ、オンライン消費者保護や個人情報保護による電子商取引の信頼性向上にかかる規律を含む。特に商業上有意義な規定として、我が国の産業界が長年求めていた、電子的送信に対する関税賦課の恒久的な禁止も含まれている。同声明においては、参加国・地域は、交渉の成果を WTO の法的枠組みに統合することを目的に、参加国・地域と連携していくことが記載された。
2025年2月の一般理事会において、71 の交渉参加国・地域が共同提案国となり、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書4に同協定を組み込むよう要請したが、WTO 加盟国によるコンセンサスは得られなかった。引き続き、同協定のマラケシュ協定への組み込みについて、議論が行われている。
(B)投資円滑化協定
現在、包括的な投資に関するルールを定めた多国間協定は存在せず、二国間投資協定や経済連携協定で対応している。
2017年12月のMC11で、有志国による閣僚共同声明を発出(日本、EU、中国を含む70加盟国・地域が参加。米国、インド、南アフリカは不参加)した。当該声明を受け、開発のための投資円滑化に関するオープンエンド交渉会合(以下、オープンエンド交渉会合)にて、全WTO加盟国・地域が参加するマルチの枠組み作りを目指すとの前提で、投資に関わる措置のうち、①透明性・予見可能性等の向上、②事務手続の簡素化・迅速化、③情報共有等の連携、④開発途上国の特別待遇等について議論を行った。
2019年11月、上海でのWTO非公式閣僚会合にて「開発のための投資円滑化に関する有志国会合」が開催され、我が国を含む92の有志国・地域が、MC12での具体的な成果を目指すとの閣僚共同声明を発出した。その後、2020年9月からオープンエンド交渉会合が開始された。
2021年12月、有志国・地域の大使級による共同声明が発出され、交渉開始以降の進展を評価し、2022年末までの交渉の妥結を目指して交渉する意思とともに、全てのWTO加盟国・地域に対して本交渉への参加を呼び掛けた。2022年12月の有志国・地域会合にて議長声明が発出され、交渉に実質的な進展が達成されたと評価し、2023年7月には、協定の実体規定の文言が妥結した。
2024年2月に行われたMC13で、有志国・地域は「開発のための投資円滑化に関する協定」の交渉の妥結の宣言と協定条文を公表し、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書4に同協定を組み込むよう要請したが、WTO加盟国によるコンセンサスを得ることはできなかった。以降に開催された一般理事会においても、125か国・地域を超える共同提案国・地域が、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の附属書 4 に同協定を組み込むよう累次要請したが、一部の国の反対により、WTO 加盟国によるコンセンサスは得られていない。同協定のマラケシュ協定への組み込みについては、引き続き議論が行われている。
391 WTO, ‘DG Azevêdo meets ministers in Davos: discussions focus on reform; progress on e-commerce’, 25 January 2019, https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dgra_25jan19_e.htm![]() .
.
② 紛争解決機能
紛争解決機能について、WTOでは、小委員会(パネル)と上級委員会の二審制が導入されている。上級委員会は、紛争解決機関(DSB)によって設置された「小委員会(パネル)が取り扱った問題についての申立てを審理する」常設機関であり、「7人の者で構成するものとし、そのうちの3人が一の問題の委員を務める」とされている。
通常、上級委員の任期終了前に、次の委員の選任が行われるが、2017年6月以降、DSBにおいて、上級委員選任プロセスを開始するためのコンセンサスが形成されていない。これにより、次々と委員が任期を終える一方で、新たな委員の選任がなされない状況が続いた。2019年12月には残る上級委員が3人を下回り、新たに審理を行うことができなくなった。2020年11月には、残っていた最後の1名の任期も切れ、上級委員は現在空席となっている。上級委員会がWTO協定に定められた(加盟国の)権利・義務を追加・縮減していると批判を強めている米国の問題意識も踏まえ、2019年1月より、ウォーカーNZ大使(DSB議長)がファシリテーターとなり、上級委員会の機能を改善するための解決策(「ウォーカー原則」)の採択が目指されたが、一部加盟国の反対により採択には至らなかった。
上級委員会の機能回復に向けた実質的な議論は、米国の関与を得て進捗するに至っていない。そのため、紛争解決手続では、パネル判断について上訴されるが、上級委員会の審理がなされないため、パネルによる判断が確定しない事案(いわゆる空上訴)が累積してきている。こうした中、WTO加盟国は、2022年6月に開催されたMC12で、「2024年までに全ての加盟国が利用できる完全なかつよく機能する紛争解決制度の実現を目的として議論を行うこと」に合意し、これはMC13においても確認された。その後、2024 年内での改革実現は果たされなかったが、上訴/レビューやアクセシビリティ等の論点について多くの議論が重ねられた。2025 年以降の議論の進め方については、今後、検討していく予定となっている。
また、EU等の一部の加盟国は、2020年4月に、MPIA(多数国間暫定上訴仲裁アレンジメント)を立ち上げ、DSBに通報した。MPIAは、上級委員会が完全に機能するまでの間に限り、パネルの判断を不服とする場合には、機能停止中の上級委員会に上訴するのではなく、仲裁により解決することを定める紳士協定である。日本も、2023年3月に参加した(2025年3月時点で、日本を含め54か国・地域が参加)。
③ 監視・審議機能
監視・審議機能とは、多国間の監視・審議により、ルールの遵守を促すものであるが、現在、効果的な監視メカニズムの構築が求められている。現実とルールのギャップを埋めるべく、特に新たな課題への対応に向けて議論が行われており、ここでは、「貿易と産業政策」と「貿易と環境」の分野における取組の状況を概観する。
(A)「貿易と産業政策」
近年、各国で産業補助金等の産業政策が実施されるようになり、その重要性は増している。他方、そうした各国の産業政策が貿易に悪影響を及ぼすことを防ぐべく規定された既存のWTOルールでは、現代における産業政策の実態を捕捉し効果的に対処することができなくなってきている。例えば、加盟国が貿易に影響を与える措置(補助金等)を導入した際にWTOに通報する義務が各協定で規定されているが、この通報義務が遵守されていない場合も多い。措置の透明性の低さは、市場歪曲的な政府支援等を助長しやすく、例えば過度な補助金が過剰生産能力の問題をもたらすなど、貿易に悪影響を及ぼすおそれが高まる。このため、通報義務の適切な履行を促す、より効果的な監視メカニズムの構築に向けて、2018年11月、物品の貿易に関する理事会へ日米欧等が共同提案を示した。その後、共同提案国以外のコメントを踏まえ、米国が主導して2021年7月と2022年7月の二度にわたって改訂案を提示したが、合意に至っていない。
こうした中で、WTOの各委員会の運営を通じた状況改善を志向する動きがあり、2023年3月の一般理事会で、EUから透明性の向上も視野に入れた審議機能改善に係る提案が示された。本提案は、多くの国が産業補助金を始めとする様々な産業政策上の措置をとりつつある中、「貿易と国家介入」の分野について、WTOにおける審議機能を強化する目的で提出された。
各国による産業政策上の措置に関しては、従前より、各委員会等で、個別協定の実施にかかる議論が行われている。例えば、「補助金及び相殺措置に関する協定」(SCM協定)に関する論点は補助金委員会で、「貿易に関する投資措置に関する協定」(TRIMs協定)に関連する課題についてはTRIMs委員会で、それぞれ議論されてきた。他方、近年実施されている産業分野への政府支援には、既存協定では規律を適切に及ぼすことができないものや、逆に複数の協定の適用が及ぶ複合的なものなど、様々な政策・措置が取られているほか、各措置が相互に関わりを持つことも多く、産業政策はますます複雑化している。
この状況を受けて、こうした政策・措置について適切に議論をする場を設け、産業補助金や国有企業等を含めた産業政策全般が貿易にもたらす影響を横断的に議論すべきであるという問題意識に基づき、2024年2月末に開催されたMC13において、「貿易と国家介入」に関する審議の場の立上げが提案され、日本やEU、カナダ等を始めとする国々が支持し、その重要性を主張した。WTO閣僚会議における初の試みとして実施された「貿易と産業政策・政策余地を含む持続可能な成長」に関する対話形式の議論でも、日本は、「貿易と産業政策」に関する審議の場を立ち上げるべきと主張し、途上国を含めた多くの国の賛成があった。最終的には、一部の加盟国の反対によりMC13における立上げは実現しなかったものの、2024 年 9 月以降、ジュネーブにおいて非公式な形で議論が実施されている。
2024 年 9 月には、カナダが補助金協定の歴史についてのセッションを開催し、同10月には、コスタリカ、ベトナム、南アフリカが経済発展の歴史や産業政策の役割について、同11月には英国とタイが産業政策と国際貿易について、それぞれセッションを共催するなど、各国が持ち回りでセッションを実施しており、各回とも多くのメンバーの参加を得ている。2025年2月には、日本も、EU及びケニアと共催する形で、「産業補助金の透明性」についてのセッションを実施した。
(B)貿易と環境
環境問題への意識の高まりを受け、1994年にWTOの通常委員会として、貿易と環境委員会(CTE)が設置された。毎年3~5回ほど会合が開催され、「多国間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿易体制との関係」等の項目について検討が行われている。2023年からは、貿易と環境にまつわる様々なテーマを取り上げるテーマ別会合が実施されており、特に貿易関連気候措置(TrCMs)に関する議論が活性化している。2024年10月のCTEでは、日本より、各国の異なるTrCMsが断片化し、必要以上に貿易制限的になることを防ぐ観点から、体化排出量の計測手法に関する国際的なガイダンスの策定に関する提案を行った。
また、2020年11月には、MC12に向け、日本を含む53か国・地域が、CTEやその他の関連するWTOの各委員会の作業を補完及び支援することを目的として、貿易と環境問題に関する様々な論点を議論していく「貿易と環境持続可能性に関する体系的議論」(TESSD)を立ち上げる提案を行い、2021年、WTOにおける議論を開始した。同3月には、日本より、温室効果ガス削減に資する製品・技術の普及を円滑化するため、関税撤廃や規制面に関するルール作り、途上国の能力構築を柱とした提案をオタワグループ閣僚級会合において行った。
2021年12月、貿易と環境持続可能性に関する閣僚声明を71か国・地域(日本・米国、EU、中国等)で発出し、環境物品・サービスの貿易を促進するためのアプローチの検討、WTOルールに合致した気候変動対策についての専門的な議論の開始など、TESSDで継続して議論することに合意した。2022年は、同年初めに合意された作業計画に基づき、①貿易関連気候措置、②環境物品・サービス、③循環経済、④補助金の四つのWG(ワーキンググループ)で議論が行われた。2024年2月に行われたMC13では、それまでの議論の成果を踏まえて、共同議長声明、作業計画のアップデート、四つのWGの成果文書が発出された。参加国・地域は2025年3月現在で78に拡大している。
EGA(環境物品協定)交渉については、2016年12月の閣僚会合以降、交渉再開の目途は立っていないが、TESSD等で関連の議論が継続されている。
なお、一部の加盟国からは、途上国地位の在り方について議論が提起されている。WTO協定上、発展途上国は、無差別原則及び相互主義に対する例外として「特別かつ異なる待遇」(協定上の義務の一部猶予、補助金削減目標の緩和、技術的支援等)を受けることができる。しかし、WTOには、これらの待遇の対象となる途上国について明確な基準がなく、各国は自己申告により当該待遇を享受できる(自己宣言方式)。経済発展を実現した途上国がこのような待遇を享受することを問題視する意見がある中、ブラジル、シンガポール、韓国、台湾、コスタリカは現在・将来の交渉でこのような待遇を求めないことを宣言している。一方、「特別かつ異なる待遇」は途上国の発展に不可欠であると多くの途上国が主張しており、各交渉分野において「特別かつ異なる待遇」の対象及び程度についても議論されている。また、途上国に対して、産業化のための「政策余地」を求める提案もある。既存のWTO協定の適用緩和を求めるものだが、これについても、先進国を中心に一律に全ての途上国に対して柔軟性を導入することには反対する声があり、議論が続いている。
(3) WTO協定(ルール)の実施
WTO協定は、加盟国・地域間に通商摩擦・紛争が生じた際に、ルールの解釈・適用を通じてその解決を図る紛争解決手続に係る規律を備えている。WTO協定では、履行監視手続や履行されない場合の対抗措置等も用意されており、紛争解決手続による措置の是正勧告は履行率が高く、実効性が高いものとなっている。また、通商摩擦を政治問題化させずに解決することができるという点でも有益である。1995年のWTO発足以来、紛争解決手続が利用された案件は634件(2025年3月現在。協議要請が行われたがパネル設置に至らなかったものを含む。)に上っている。
我が国が当事国としてWTO紛争解決手続に付託している案件のうち経済産業省が関与して、解決を図っている最近の事例の詳細は、下記を参照されたい。
① 韓国の日本製ステンレス棒鋼に対するアンチ・ダンピング措置
2016年6月、韓国政府は、日本からのステンレススチール棒鋼に対する第3次サンセット・レビューを開始し、2017年6月、3年間課税措置を延長する旨の決定をした。
本措置は、日本産品が韓国産品やインド産品と競争関係にない可能性や、中国等第三国産品の輸入が増加している点を考慮せず、日本産品に対する課税を継続しなければ損害が再発する可能性があると認定しており、アンチダンピング(AD)協定に非整合である可能性がある。
我が国は、2018年6月、韓国に対してWTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、同年9月に、我が国はパネル設置を要請し、同年10月にパネルが設置された。以後、パネルにおいて審理が行われた。
2020年11月に発出されたパネル報告書は、日本産輸入品が韓国産品より相当程度高価であることや中国等からの低価格輸入が大量に存在していることが適切に考慮されていないため、日本産輸入品に対するAD課税の撤廃により、韓国国内産業への損害が再発する可能性があるとする認定に瑕疵があり、AD協定第11.3条に非整合的であると判断した。
2021年1月、韓国は、WTO上級委員会に申し立てたが、上級委員会は既に機能を停止していたため、審理がなされていない(いわゆる空上訴)。
また、2020年1月に第4次サンセット・レビューが開始され、2021年1月に3年間課税措置を延長する旨決定された。第5次サンセット・レビューについては、国内生産者からの要請がなく行われず、2024年1月に課税が終了した。
② インドのICT製品に対する関税引上げ措置
2014年7月以降、インド政府は、自国のWTO協定譲許表において無税としている一部のICT製品(携帯電話、基地局、通信機器、電話機・通信機器部品等)について、予算法案(並びにその後の予算法)及び関連通達により10~20%の関税引上げ措置を導入した。
インドは、同国のWTO協定譲許表において、当該ICT製品の譲許税率を無税と定めているにもかかわらず、それを超える関税を賦課しており、譲許税率を超えない関税率の適用を義務付けるGATT第2条に非整合的である可能性がある。
我が国は、前出の品目について、2019年5月にWTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、インドと二国間協議を実施した。しかしその後も、インド側からは、状況の改善に向けた見通しが示されなかったため、2020年3月に、我が国はパネル設置を要請し、同年7月にパネルが設置された。なお、インドは、パネル設置要請後、2020年2月の予算法案及び関連通達、2022年1月の実行関税率表の改訂において、電話機・通信機器部品の一部の関税をさらに引き上げた。2023年4月、パネルは我が国の主張を受け入れ、インドの措置はWTO協定に非整合的であるとし、インドに対して同措置の是正を勧告するパネル報告書が公表された。2023年5月、インド政府はパネル報告書を不服として、上級委員会へ申し立てたが、上級委員会は機能停止中のため、上級委員会に申し立てられたまま審理が行われない状態となっている(いわゆる空上訴)。
③ 中国のステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置
2018年7月、中国政府は、我が国を含む4か国・地域(日本、韓国、インドネシア及びEU)からのステンレススラブ、ステンレス熱延鋼板及びステンレス熱延コイルの輸入に対しアンチ・ダンピング(AD)調査を開始し、2019年7月に課税措置が開始された(当初期間:2019年7月23日~2024年7月22日)。
我が国は、2021年6月に、中国に対してWTO紛争解決手続に基づく協議要請を行い、同年8月に、パネル設置を要請し、同年9月にパネルが設置された。2023年6月、中国の措置がAD協定に非整合的であることを認定し、中国に是正を勧告するパネル最終報告書が公表され、翌7月、WTO紛争解決機関(DSB)により採択された。履行のための期間は2024年5月8日までと日中間で合意されたが、その後も措置が継続していたため、日本は措置の早期撤廃を促しつつ、WTO協定上更なる手続(勧告履行の有無・適否を確認する手続、及び、対抗措置を申請する手続等)の検討を進め、5月29日には、今後の手続の遂行順序(「シークエンス合意」)をWTOに通報した。
当初期間末日の2024年7月22日、措置延長調査が開始されたが、同延長調査の対象には日本は含まれなかった(韓国、インドネシア、EU、英国(2020年にEUから離脱したため)のみ対象)。したがって、日本製ステンレス製品に対する本AD措置は、同日の経過をもって終了・撤廃された。
4. APECを通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進
(1) APEC
2024年のAPECは、ペルーが議長を務め、全体テーマ「EMPOWER. INCLUDE. GROW」の下、(1)包摂的で連結性のある成長のための貿易・投資、(2)フォーマルかつグローバル経済への移行を促進するイノベーション及びデジタル化、(3)強靱な発展のための持続可能な成長の三つの優先課題を掲げ、各種取組を行った。
同年5月17日及び18日のAPEC貿易担当大臣会合では、「WTOの全ての機能の改革・強化」や「質の高いインフラ開発及び投資の重要性」について議論し、共同声明を発出した。5月17日には、APEC初の貿易・女性担当大臣共同会合も開催され、「貿易を通じた女性の経済的エンパワーメント」や「多様な背景を持つ女性の経済及び貿易への完全で平等な参加」について議論した。
また、同年11月13日から16日にかけてのAPEC閣僚会議・首脳会議では、「自由で開かれた貿易・投資の推進やWTOを中核とする多角的貿易体制の支持」について議論がなされたほか、「脱炭素化等のエネルギー移行、包摂的デジタル経済の促進、女性のエンパワーメントの重要性」が共有された。首脳によるマチュピチュ宣言と閣僚共同声明がそれぞれ発出されるとともに、「アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)アジェンダの新たな視点に関するイチマ声明」及び「フォーマルかつグローバル経済への移行を促進するリマ・ロードマップ(2025-2040年)」が採択されたほか、ウクライナ・中東情勢に関する議長声明が発出された。
2025年のAPECは、韓国が議長を務め、全体テーマ「Building a Sustainable Tomorrow」の下、(1)連結(CONNECT)、(2)革新(INNOVATE)、(3)繁栄(PROSPER)の三つの優先課題に取り組んでいる。
日本としては、2010年の「横浜ビジョン」を基礎とした議論の流れを着実に引き継ぐとの方針に基づき、FTAAPを始めとするアジア太平洋地域の経済統合の実現、質の高いインフラ開発・投資の促進、全ての人の利益のため安全かつ包摂的なAIの実現に向けた協力領域の拡大、中小企業、女性、障がい者を含む社会的弱者の経済参加の支援のためのスマート技術の活用に関する議論の実施などを通じ、この地域の力強い成長力を取り込みつつ、我が国経済に豊かさと活力をもたらすことを目指している。また、WTO発足時には貿易投資ルールの対象として想定されていなかったデジタル貿易・電子商取引分野に関する具体的な取組を進め、市場歪曲措置の是正や公平な競争条件の確保にも取り組む。
5. 経済連携協定・投資関連協定
(1) 経済連携協定
① 経済連携協定(EPA/FTA)の意義
経済連携の推進には、締結国間の貿易投資を含む幅広い経済関係を強化する意義がある。より具体的には、輸出企業にとっては、関税削減・撤廃等を通じた輸出競争力の強化の面で意義があり、外国に投資財産を持つ企業やサービスを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義がある。輸出の面では、関税削減・撤廃によって我が国からの輸出品の競争力を高められる。例えば、タイ向け自動車部品(20%)、インドネシア向け完成車(60%)、インド向け鉄鋼製品(5%)や電気電子機器(10%)といった産品の関税が撤廃されたほか、日ASEAN包括的経済連携協定、RCEP(地域的な包括的経済連携)協定、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)といった広域経済連携協定によって、企業のサプライチェーンの効率化や強靱化が実現している。海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、海外事業で得た利益を我が国へ送金する自由の確保、現地労働者の雇用等を企業へ要求することの制限・禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約の金額及び有効期間への政府の介入の禁止等の約束を政府同士で行うことにより、海外投資の法的安定性を高めている。また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で安心して事業を行うためのルールを定めている。
この他にも、我が国のEPAでは、締約国のビジネス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環境の整備に関する委員会」の設置に係る規定を設けていることが多い。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点について、相手国政府関係者と直接議論することができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、貿易・投資の促進、電力・ガスの安定供給、模倣品対策の強化、関税・税務に関する事務手続の簡素化・透明化、外資規制緩和等につき議論し、ビジネス環境整備の一助となっている。
さらに近年、重要性を増しているグローバルサウス諸国等との経済連携も活発に推し進めるべく、トルコ、バングラデシュ、GCC、UAE等の新興国とEPA交渉を行っている。サプライチェーン強靱化や保護主義への対応等が求められる状況も踏まえ、交渉を通じ、自由貿易圏を拡大するのみならず、我が国企業の市場獲得・競争環境を有利にするべく、貿易・投資関係の強化に取り組んでいくことが重要となっている。
② 経済連携協定(EPA/FTA)を巡る動向
世界を見渡すと、これまでに幅広い国々が数多くのEPA/FTAを締結してきている。WTOへの通報件数を見ると、1948年から1994年の間にGATTに通報されたRTA(FTAや関税同盟等)は124件であったが、1995年のWTO創設以降、多くのRTAが通報されており、2025年1月末時点でGATT/WTOに通報された発効済RTAは615件392に上る。
特に、アジア太平洋地域では、2010年3月にTPP協定交渉が開始され(我が国は2013年7月に交渉に参加)、その後、米国を除く11か国での交渉を経て、2018年3月にはCPTPPが署名、2018年12月に発効した。2021年6月に開始された英国の加入手続は、2024年12月に加入議定書が発効した。2013年3月には日中韓FTA、5月にはRCEP協定についてそれぞれ交渉が開始され、RCEP協定は2022年1月に発効した。また、APEC参加国・地域との間で、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)など地域経済統合の推進に関する議論が継続している。
2019年2月には、日本とEUの間で日EU・EPAが発効するなど、各地域をつなぐ様々な経済連携協定の取組も進行している。
近年の動きとして、中国・韓国両国が、多様な国々とFTA交渉を推進している。例えば中国は、2023年5月にエクアドルと、9月にニカラグアと、10月にセルビアとのFTAに署名し、2024年1月にシンガポールとの改定FTAを発効した。また、2024年10月に中ASEAN・FTA3.0交渉の実質妥結を発表した。韓国は、2023年1月にインドネシアとのCEPA(包括的経済連携協定)が発効している。また、2024年1月にはタイとEPA交渉を開始、6月にはタンザニアとのEPA交渉開始に合意した。
UAEも、輸出拡大のため、複数国とCEPA締結に向けた交渉を加速させている。2021年以降、インド、イスラエル、インドネシア、トルコ、カンボジア、ジョージアとの協定が発効し、2024年には韓国、チリ、モーリシャス、セルビア、ヨルダン、豪州、ケニア、ニュージーランド、マレーシア、コスタリカ、コロンビア、ベトナム、中央アフリカ、ウクライナ と署名をおこなった。UAEは、最終的に日本を含む103か国までCEPA締結対象を広げ、貿易総額のうち最大95%がカバーされることを目指している。
地域大の取組でも、CPTPPやRCEP協定の動向に加えて、多様な動きが見られる。2021年のASEAN首脳会議議長声明では、いくつかのASEAN+1FTAの改正に係る交渉と議論の進展(豪州・ニュージーランド、中国、インド、韓国とASEAN)について言及された。アフリカでは、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)が2021年1月から運用開始された。また北米では、カナダ・米国・メキシコによる、NAFTAの後継となるUSMCAが2020年7月1日に発効している。南米地域では、南米南部共同市場(メルコスール)とEUとのFTA交渉が、2024年12月にメルコスール4か国(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)とEUの間で政治合意に至った。
上記の包括的なEPAに加えて、分野別の協定を締結する動きも活発になっている。デジタル分野では、シンガポール、ニュージーランド、チリの3か国によるデジタル経済パートナーシップ協定(Digital Economic Partnership Agreement)が2020年6月に署名され、2021年1月(チリは2021年11月)に発効した。2024年5月には、韓国の正式加入が発表された。同協定には、中国、カナダ、コスタリカ、ペルー、UAE、エルサルバドル、ウクライナが加入申請の動きを見せている。このうちコスタリカは、2025 年 1 月に加入に関する議論の実質妥結が発表された。この他にも、星豪DEA(2020年12月発効)、星英DEA(2022年6月発効)、星韓DPA(2023年1月発効)、EU星・デジタルパートナーシップ協定(2023年1月発効)など、様々なデジタル経済協定(Digital Economic Agreement: DEA)やデジタルパートナーシップ協定(Digital Partnership Agreement: DPA)を締結する動きが活発化している。
環境分野では、グリーン経済協定(Green Economy Agreement: GEA)を締結する動きが見られる。2022年10月に星豪グリーン経済協定が署名され、17の協力イニシアティブの概要が附属書として公表されている。うち3分野は、アーリーハーベストとして成果物も同時に公表された。また2023年1月に、シンガポールとマレーシアの間でデジタル経済とグリーン経済における協力に関する枠組み(FoC)が署名された。
392 WTO, ‘Regional trade agreements’, https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm![]() (Accessed April 2025).
(Accessed April 2025).
③ 我が国経済連携協定を巡る取組
我が国は、2024年3月現在、24か国・地域との間で21の経済連携協定を署名・発効済みである。2022年1月には、RCEP協定が発効した。(第III-2-2-3図)。
第Ⅲ-2-2-3図 日本のEPA交渉の歴史
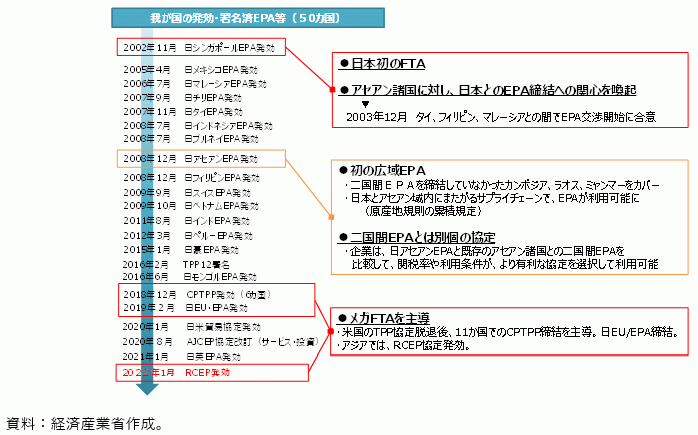
また、第III-2-2-4図のとおり、我が国の貿易におけるFTA等のカバー率は、中国や米国、EU等と比較しても高い水準である。自由貿易の拡大、経済連携協定の推進は、我が国の通商政策の柱であり、世界に「経済連携の網」を張り巡らせることで、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくことが、我が国の成長にとって不可欠といえる。
第Ⅲ-2-2-4図 各国・地域のFTA等のカバー率
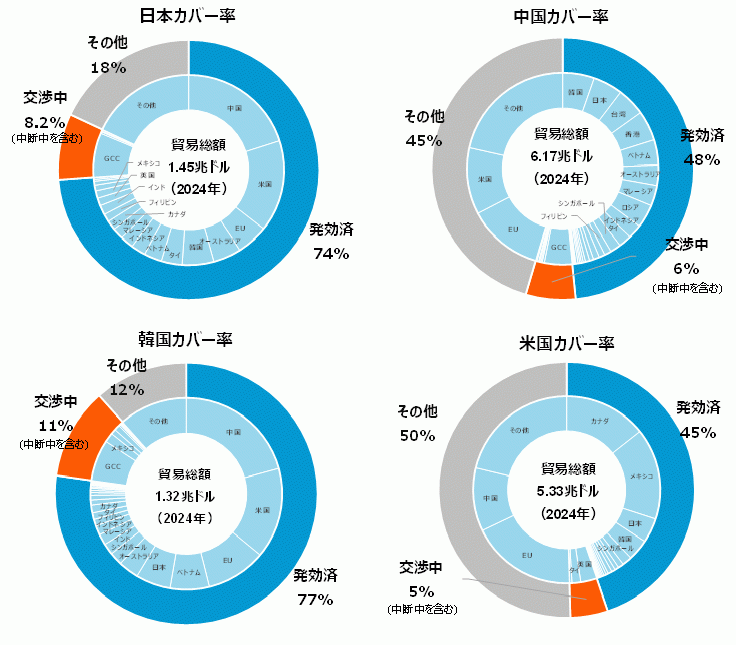
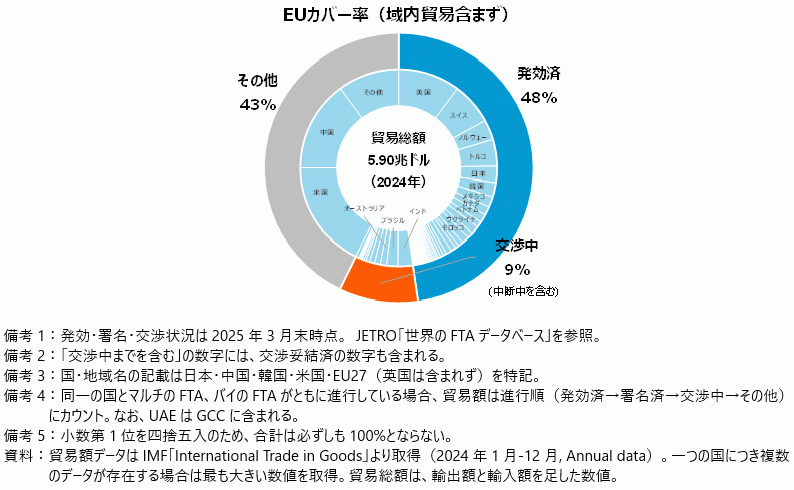
2024年6月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2024~賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現~」(骨太方針2024)において、「自由で公正な経済圏の拡大やルールに基づく多角的貿易体制を維持・強化する。高いスタンダードの経済連携協定であるCPTPPをより開放的かつ先進的なものとするため、新規加入への対応や協定の一般的な見直しを主導し、もって経済的利益及び地域・世界の繁栄と安定に資するものとする。」と記載され、RCEP協定の透明性のある履行の確保、WTO体制の強化、EPAの拡大等への取組が掲げられているとおり、我が国はインド太平洋地域での協力等を通じ、経済連携を更に推進し、自由で公正な貿易・投資ルールの実現を牽引する。
(i) 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)(2018年12月30日発効)
(a)CPTPPの概要
我が国は、TPP協定に関し、2013年3月に交渉参加を表明、同年7月から豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの11か国との交渉に参加した。その後の交渉を経て、2015年10月に米国アトランタで大筋合意に至り、2016年2月4日に署名がなされた。日本国内では、2016年12月9日に、TPP協定が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。その後、2017年1月20日、TPP協定原署名国12か国の中で最も早く、国内手続完了の通報を、協定の寄託国であるニュージーランドに対して行った。
2017年1月30日に、米国がTPPからの離脱を参加各国に通告した後は、米国以外の11か国の間で協定の早期発効を目指して協議が行われた。その結果、同年3月や5月の閣僚会合等を経て、同年11月9日、ダナンでの閣僚会合で大筋合意に至り、2018年3月8日にCPTPPが、チリで署名された。その後、メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、豪州が国内手続を完了させ、2018年12月30日にこれら6か国間で発効した。その後、2019年1月14日にはベトナムを加えた7か国間で、2021年9月19日にはペルーを加えた8か国間で、2022年11月29日にはマレーシアを加えた9か国間で、2023年2月21日にはチリを加えた10か国間で、2023年7月12日にはブルネイを加えた11か国間で効力を生じた。
CPTPPの着実な履行によって、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業、環境など、幅広い分野で新たな共通ルールを世界に広め、自由で公正な経済秩序の拡大に資することが期待される。
(b)TPP委員会
CPTPP第27.1条・27.4条に基づき、協定の実施・運用等の検討や締約国の連携の定期的見直し等を目的としたTPP委員会が、CPTPPの発効後8回開催された。2024年11月に開催された第8回TPP委員会では、コスタリカの加入作業部会設置が決定されたほか、CPTPPが貿易協定の「ゴールドスタンダード」であり続けるためにも、協定の一般的な見直しを着実に進めていることが報告された。
(c)CPTPPへの加入要請
2021年2月1日、英国が寄託国であるニュージーランドに対して加入要請を通報した。我が国は、2021年のTPP委員会の議長国として、ハイスタンダードかつバランスのとれたCPTPPの着実な実施及び拡大に向けて議論をリードしていく旨表明した。
2021年6月2日、テレビ会議形式で第4回TPP委員会を開催し、英国の加入手続の開始及び英国の加入に関する作業部会(議長:日本、副議長:豪州及びシンガポール)の設置を決定した。2021年9月28日以降、第1回英国加入作業部会が開催され、英国からCPTPPの義務の遵守について説明を聴取した。2022年2月18日に、市場アクセス交渉を開始すべく、同加入作業部会の議長国である日本から、英国に市場アクセスオファーの提出を指示した。2023年3月、英国のCPTPPへの加入交渉が実質的な妥結に至り、2023年7月16日、英国議定書が署名されたのち、2024年12月15日、同議定書が発効した。
2021年9月に中国、台湾、12月にエクアドル、2022年12月にウルグアイ、2023年5月にウクライナ、2024年9月にインドネシアが、寄託国であるニュージーランドに対して加入要請を通報した。我が国としては、加入関心を持つエコノミーが本協定のハイスタンダードを満たす能力と意図があるのかどうか、しっかり見極める必要があると考えており、戦略的観点や国民の理解も踏まえて他のCPTPP参加国とも議論していく。
(d)CPTPPの一般的な見直し
CPTPP第27.2条1(b)では、同協定の効力発生の日から3年以内に、及びその後は少なくとも5年ごとに、締約国間の経済上の関係及び連携を見直すこととされており、2021年以降、CPTPPの一般的な見直しに関する議論が行われてきた。2023年11月15日のCPTPP閣僚会合では、一般的な見直しの作業方針である付託事項(TOR)が承認され、2024年11月の第8回TPP委員会において、協定の一般的な見直しを着実に進めていることが報告された。
(ii) 交渉中FTA(日中韓FTA・日コロンビアEPA・日トルコEPA・日GCCEPA・日バングラデシュEPA・日UAEEPA)
(a)日中韓FTA
日中韓3か国は、世界における主要な経済プレイヤーであり、3か国のGDP及び貿易額は、世界全体の2割超393を占める。
2013年3月に交渉を開始して以降、2019年11月までに計16回の交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、税関及び手続円滑化、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投資、競争、知的財産、衛生植物検疫(SPS)、貿易の技術的障害(TBT)、法的事項、電子商取引、環境、協力、政府調達、金融サービス、電気通信サービス、自然人の移動等の広範な分野について議論を行ってきた。
直近の動きとして、2024年5月に開催された第9回日中韓サミットで、交渉を加速していくための議論を続けることを確認した。その後の2025年3月に開催された日中韓経済貿易大臣会合でも同様に、交渉を加速していくための議論を続けることで一致している。
393 Trilateral Statistic Hub, https://data.tcs-asia.org/ja![]() .
.
(b)日コロンビアEPA
コロンビアは、太平洋と大西洋に面する北米と南米の結節点に位置し、豊富なエネルギー・鉱物資源を有する。また、中南米第3位である約5,200万人の人口を有する394ほか、平均経済成長率は2.9%(2014年~2023年)である395。中南米地域で自由開放経済を主導する太平洋同盟のメンバーであり、米国・カナダ・EU及び韓国とのFTAも発効済である。日コロンビアEPAを通じた貿易・投資環境の改善により、輸出入及び日本企業によるコロンビアへの投資の拡大が期待されている。
2012年9月に行われた日コロンビア首脳会談で、両国はEPA交渉を開始することで一致した。同年12月に第1回交渉会合が開催され、2015年8月から9月にかけて第13回交渉会合が開催された。
394 世界銀行「World Development Indicators」
395 IMF「WEO」(2023年10月)。
(c)日トルコEPA
トルコは、人口8,500万人396を超え(2023年末時点)、国民の年齢中央値が30歳台前半397と若い魅力的な国内市場を持っている。加えて、欧州及び周辺国市場への生産拠点として注目されている。日トルコEPAによって、欧州企業や韓国企業といった競合相手との競争条件の平等化が図られ、トルコへの日本企業の輸出が後押しされるとともに、トルコの投資環境関連制度の改善により、トルコへの日本企業の投資促進も図られることが期待される。
トルコと我が国は、2012年7月に第1回日トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコEPAの共同研究を立ち上げることで合意した。これを受けて、同年11月に第1回、2013年2月に第2回の共同研究が開催され、同年7月に、日本・トルコの両政府にEPA交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。
共同研究報告書を受けて、2014年1月に行われた日トルコ首脳会談で、両国はEPA交渉を開始することで一致し、同年12月に第1回交渉会合が開催された。その後、2019年10月までに計17回の交渉会合を開催した。特に、2019年は1月・6月に閣僚級で議論するとともに、同年中に5回の交渉会合を実施するなど交渉が加速した。直近では、2023年9月に西村経済産業大臣とボラット貿易大臣が、EPA交渉加速化を含む貿易・投資の促進及び経済関係強化に関する協力覚書に署名した。同月に行われた日トルコ首脳会談でも、両首脳はEPAの早期妥結に向けて協議を続けることで一致した。
397 同上。
(d)日GCC・EPA
GCCは、中東6か国(バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE)から構成され、5,640万人398の人口を擁する。同地域は、世界の原油埋蔵量の約3割399を有し、原油生産量の約2割400、天然ガス生産量の約1割401を産出する重要な地域である。また、我が国は原油の約9割402、天然ガスの約1割403を同地域から輸入している。
GCCと我が国は、経済関係の強化に向け、2006年9月にEPA交渉を開始し、2009年までの間に2回の交渉会合及び4回の中間会合を開催した。2009年以降、交渉がGCC側の都合で中断していたが、2023年7月に岸田総理大臣がサウジアラビアを訪問した際、ブダイウィGCC事務総長と会談し、日GCC・FTA交渉を2024年中に再開することで一致し、これを受け、2024年12月に交渉再開後第1回交渉会合を実施した。
398 外務省「湾岸協力理事会(GCC)概要」、2023年5月18日、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page23_000547.html![]() 。2021年。
。2021年。
399 BP, ‘Statistical Review of World Energy 2021’, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf![]() . クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAEの5か国の数値。2020年末時点。
. クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAEの5か国の数値。2020年末時点。
400 同上。クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAEの5か国の数値。2020年末時点。
401 同上。バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAEの6か国の数値。2020年末時点。
402 財務省「貿易統計」
403 同上。
(e)日バングラデシュEPA
バングラデシュは、1億7,000万人もの人口を有し404、一大消費市場として注目されており、その経済成長に伴い、進出日系企業も大幅に増加している。日バングラデシュEPAの締結によって、関税の撤廃や投資環境の整備が実現し、両国間の貿易及び投資が拡大することが期待される。また、両国企業によるビジネスの活性化、さらには両国の政治・外交関係を強化することにもつながると考えられる。
404 世界銀行「World Development Indicators」
外交関係樹立50周年である2022年12月、日本国政府とバングラデシュ政府は、「あり得べき日バングラデシュEPAに関する共同研究」を立ち上げることで一致し、2023年4月、7月、9月に計3回にわたって共同研究会合を開催した。同年12月にはその成果をまとめた共同研究報告書を発表し、EPA 締結のための交渉を開始することを提言した。2024年3月に、両政府はEPAの交渉開始を決定し、同年5月に第1回交渉会合を開催し、2025年2月までに計4回の交渉会合を実施した。
(f)日UAE・EPA
UAEは、我が国第2位の原油調達先国であり、日本の自主開発油田の約4割が存在するエネルギー安全保障上の最重要国の一つである。中東・北アフリカ地域で、日本企業が最も進出するビジネス拠点でもあり、2021年にはドバイ国際博覧会を開催し、併せて成長戦略、ネット・ゼロ戦略を発表するなど、新たな成長機会がもたらされる可能性が大きい国である。野心的で、バランスの取れた、包括的な日UAE・EPAの締結により、貿易及び投資の拡大を始めとする両国間の経済関係の強化が期待される。
2024年9月18日、日本国政府とUAE政府は、日UAE・EPA交渉の開始を決定した。これを受け、2024年11月に第1回交渉会合、2025年2月に第2回交渉会合を開催した。
(iii) 日EU経済連携協定(日EU・EPA)(2019年2月1日発効)
アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組として、EUとのEPAが挙げられる。我が国とEUは、世界人口の約1割405、貿易総額の約3割406、名目GDPの約2割407を占める重要な経済的パートナーであり、日EU・EPAは、日EU間の貿易投資を拡大し、我が国経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの先導役を果たすものといえる。EUは、近隣諸国や旧植民地国を中心としてFTAを締結してきたが、2000年代に入り、韓国等の潜在的市場規模や貿易障壁のある国とのFTAを重視するようになった。さらに、2017年から先進国であるカナダとの包括的経済・貿易協定(the Comprehensive Economic and Trade Agreement: CETA)が暫定発効されている。また、南米南部共同市場(メルコスール)との貿易協定(EU-Mercosur Trade Agreement)は、2023年12月6日、政治合意に至っている。
日EU・EPAについては、2013年3月に行われた日EU首脳電話会談で、日EU・EPA及び戦略的パートナーシップ協定(SPA)の交渉開始に合意し、2017年4月までに計18回の交渉会合が開催された後、同年7月に大枠合意、同年12月には、安倍総理大臣とユンカー欧州委員会委員長が電話会談を実施し、交渉妥結に達したことを確認した。その後、2018年7月17日に署名、同年12月21日に日EU双方は本協定発効のための国内手続を完了した旨を相互に通告し、2019年2月1日に発効した。
日EU・EPA発効後は、2019年4月に合同委員会(閣僚級)を実施したのを始めとして、これまでに計5回の合同委員会を実施し、また、その間に物品貿易や政府調達、サービス貿易、投資の自由化及び電子商取引等12分野の専門委員会及び作業部会を実施し、協定の適正かつ効果的な運用を確認してきている。
2022年10月には、「データの自由な流通に関する規定」を同協定に含めることについて日EU間の正式交渉を開始し、2023年10月28日の第4回日EUハイレベル経済対話で、日EUの閣僚(日本:上川外務大臣・西村経済産業大臣、EU:ドンブロフスキス上級副委員長)が同交渉の大筋合意を確認した。2024年1月31日、「データの自由な流通に関する規定」等を含めるEPA改正議定書が署名され、同年7月1日に発効した。
405 外務省「日EU経済関係資料」、2025年4月、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100510867.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。2024年。
(2025年6月5日閲覧)。2024年。
406 同上。貿易総額は、日本の輸出額及び輸入額とEUの輸出額及び輸入額を足した数値。EUの貿易総額には、EU域内の貿易総額を含む。
407 同上。
(iv) 地域的な包括的経済連携協定(RCEP(アールセップ):Regional Comprehensive Economic Partnership)協定(2022年1月1日発効)
RCEP協定は、世界のGDP、貿易総額及び人口の約3割408、我が国の貿易総額の約5割409を占める広域経済圏を創設するものであり、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェーンの効率化・強靱化に向けて、市場アクセスを改善し、発展段階や制度の異なる多様な国々間で知的財産、電子商取引等の幅広い分野のルールを整備するものである。
東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築されているが、この地域内での更なる貿易・投資の自由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。
この地域全体を覆う広域EPAの実現により、企業は最適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワークを構築することが可能となり、東アジア地域における産業の国際競争力の強化につながることが期待される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によって、EPAを活用する企業の負担軽減が図られる。
2012年11月のASEAN関連首脳会議で、「RCEP交渉の基本方針及び目的」が16か国(ASEAN10か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)の首脳によって承認され、RCEPの交渉立上げが宣言された。
基本方針には、「現代的な、包括的な、質の高い、かつ、互恵的な経済連携協定」を達成すること、物品・サービス・投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決を交渉分野とすることが盛り込まれた。第1回RCEP交渉会合は、2013年5月にブルネイで開催され、高級実務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易及び投資に関する各作業部会が開催された。
第1回交渉会合が開催されて以降、3回の首脳会議、19回の閣僚会合及び31回の交渉会合の開催を経て、2020年11月15日の第4回RCEP首脳会議の機会に署名に至った。インドは、交渉立上げ宣言以来、2019年11月の第3回RCEP首脳会議に至るまで、7年間にわたり交渉に参加してきたが、その後交渉への参加を見送った。我が国を始め各国は、その戦略的重要性から、インドの復帰を働きかけたが、2020年の署名は、インドを除く15か国となった。しかしながら、RCEP協定署名の際、RCEP協定署名国は、RCEP協定がインドに対して開かれていることを明確化する「インドのRCEPへの参加に係る閣僚宣言」を発出し、インドの将来的な加入円滑化や関連会合へのオブザーバー参加容認等を定めた。
署名後、各国の国内手続を経て、2022年1月1日より、日本、豪州、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナムの10か国についてRCEP協定が発効し、続いて、韓国(同年2月1日)、マレーシア(同年3月18日)、インドネシア(2023年1月2日)、フィリピン(同年6月2日)についても発効した。
2022年9月17日には、RCEP協定発効後初めてとなるRCEP閣僚会合を開催した。2024年9月22日に行われた第3回RCEP閣僚会合では、RCEP協定の運用に関わる諸事項について議論されたほか、RCEPサポート・ユニットの事務局長の採用、並びにRCEP協定への加入のための手続規則が採択されたことを歓迎した。また、吉田経済産業大臣政務官から、地域における自由で公正な経済秩序の実現に向けて、協定の透明性のある履行の重要性を強調し、閣僚間でその重要性を再確認した。
408 外務省、財務省、農林水産省、経済産業省「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に関するファクトシート」、2021年4月、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100115475.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。貿易総額は輸出額ベース。
(2025年6月5日閲覧)。貿易総額は輸出額ベース。
409 同上。
(v) あり得べきEPAに関する共同研究
(a)イスラエル
日イスラエル外交関係樹立70周年となる2022年の11月に、日本政府とイスラエル政府は、「あり得べき日・イスラエルEPAに関する共同研究」を立ち上げることで一致し、2023年3月、8月、9月に共同研究会合を開催した。
(vi) EPAの一層の利用推進に向けた取組
グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、上述の新たな協定締結に向けた取組に加えて、EPA/FTAの利用の促進、既存EPAの見直し等も重要である。
CPTPP、日EU・EPA、日米貿易協定及び日英EPAに加え、RCEP協定が発効に至り、以前にも増して、EPA等の利活用が重要な段階にある。そこで、経済連携協定等を最大限に活用するとともに、コロナ禍に生じた社会経済活動の変化や明らかになった課題に対応するため、2020年12月に「総合的なTPP等関連政策大綱」が改訂され、中堅・中小企業等の新市場開拓のための総合的支援体制を強化し、原産地証明書等のデジタル化を含む貿易に係るビジネス環境の整備に取り組む旨が明記された。こうした背景も踏まえ、経済産業省は、JETROや関係省庁と協力して、EPAの利活用促進を目的として、①原産地証明書のデジタル化による利便性向上、②EPA関連の国内手続のデジタル化、③きめ細やかな中小企業支援等に取り組んでいる。
(a)原産地証明書のデジタル化による利便性向上
まず、海外と連携して取り組んでいる課題として、原産地証明書(以下、CO)のデジタル化が挙げられる。これまでCOは紙でやりとりされることが多く、事務コストが高いこと、COの紛失・遅延等のリスクがあることから、EPA等を利用する事業者からは、貿易円滑化の観点からデジタル化の要望が高まっている。このため、前述の「総合的なTPP等関連政策大綱」でも、COのデジタル化に政府一丸となって取り組むこととされている。日本国税関は、既にCOのPDFファイル等による提出を認めているが、日本で発給するCOも、2024年度までに八つのEPA(日インドCEPA、日豪EPA、日タイEPA、日チリEPA、日ベトナムEPA、日マレーシアEPA、AJCEP(ベトナム・マレーシア向け)、RCEP)について、PDF ファイルでのCO発給が実現した。さらに、2025年5 月より日モンゴルEPAについてのPDF ファイルでの発給が開始された。また、CO情報を電子的に交換するデータ交換(輸出国の発給当局から輸入国税関にCOの電子データを送付)は、取引コストを更に引き下げることが期待されている。日インドネシアEPAにおけるCOのデータ交換については、2023年6月より運用を開始したほか、日タイEPAでは、2025年3月から、パイロット運用が開始され、AJCEP協定では、データ交換の導入に向けた協議を進めている。
(b)EPA関連の国内手続のデジタル化
国内での取組として、2021年8月、JETROがCOの申請書類作成を支援するソフト(通称、「原産地証明書ナビ」)を公表し、同ツールの無償提供を開始した。これにより、輸出に当たってEPAを利用・検討している企業(特に中小企業)が、CPTPPを含むEPAのCOを簡易かつ効率的に作成できるようになった。
また、令和3年度補正予算で、中堅・中小企業が簡易かつ低コストでEPAを利用するためのデジタルプラットフォームを整備するための実証を実施した。当該実証を通じて、①輸出品及び原材料に対応するHSコードの検索、②各EPAの関税率・品目別原産地規則(PSR)の比較による最適なEPAの選択、③原産性の証明に必要な書類の準備、④原産性の証明に必要なサプライヤーからの情報提供等のプロセスをワンストップでサポートするプラットフォーム(プロトタイプ)を開発した。さらに、実証プロセスで、EPAの利用が多い10業種の業界団体と協力し、業界ごとに、①EPA利用マニュアル、②原産性の証明に必要な根拠書類の標準フォーマット、③業界専門用語とHSコードの候補の組み合わせに係るデータセットを作成した。
(c)きめ細やかな中小企業支援等
中堅・中小企業等の新市場開拓のための、総合的支援体制の強化に取り組んでいる。具体的には、TPP等を活用した中堅・中小企業等の市場開拓のための新輸出コンソーシアムの活用、RCEP協定・CPTPP・日英EPA・日EU・EPA・日米貿易協定等のEPAの利用に関するセミナーの実施、相談窓口の充実、解説書等の作成・配布、YouTubeやWEB広告等のSNSを通じた周知等の取組を通じて、EPA/FTAの利活用支援・海外展開支援を行っている。
また、中小企業を含めた我が国企業によるEPA利活用をきめ細かく支援するために、経済産業省と業界団体で連携した取組も進めている。例えば、特に部品点数が長く、サプライチェーンが複雑な自動車業界については、経済産業省の「自動車産業適正取引ガイドライン」で、EPA利用拡大のために、COの申請準備に係る完成車メーカーと部品メーカーの協力や、関連書類作成に当たってのデジタルプラットフォームの活用による省力化を、ベストプラクティスとして推奨している。
さらに、EPAの利活用を推進するための手法について検討するために、2022年7月に、「EPA活用推進会議」を設立し、10業種の業界団体・企業や関連サービスを提供する民間企業、学識者、政府関係機関が一同に会し、前述のデジタル・ワンストップサービスの開発や、広報周知、運用改善等について議論している。
(2) 投資関連協定
① 世界の投資協定を巡る状況
1980年代以降、世界の対外直接投資は急速に拡大しており、世界経済の成長を牽引する大きな役割を果たしている。
対外直接投資の拡大を踏まえ、世界各国は、投資受入国での差別的扱いや収用(国有化も含む)などのリスクから自国の投資家とその投資財産を保護するため、投資協定を締結してきた。投資ルールは、貿易に関するWTO協定のような多国間協定がなく、二国間若しくは地域協定が中心となっている。
世界の投資協定数は、2023年末時点で約2,831件となっている(第III-2-2-5図)。
第Ⅲ-2-2-5図 世界の投資協定数の推移
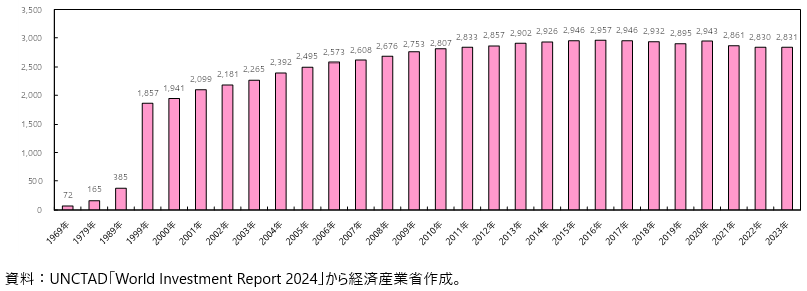
② 投資協定の主な規定内容
従来の投資協定は、投資受入国における投資財産の収用や法律の恣意的な運用等のカントリーリスクから投資家を守り、保護することを主目的として締結されてきた。こうした内容の協定は「保護型」の投資協定と呼ばれ、投資財産設立後の内国民待遇や最恵国待遇、収用の原則禁止及び合法とされる収用の要件と補償額の算定方法、自由な送金、締約国間の紛争処理手続、投資受入国と投資家との間の紛争処理等を主要な内容とする。1990年代に入ると、そのような投資財産保護に加えて、投資設立段階の内国民待遇や最恵国待遇、パフォーマンス要求410の禁止、外資規制強化の禁止や漸進的な自由化の努力義務、透明性確保(法令の公表、相手国からの照会への回答義務等)等を盛り込んだ「自由化型」の投資協定が出てきた(第III-2-2-6図)411。
第Ⅲ-2-2-6表 投資協定の主な内容
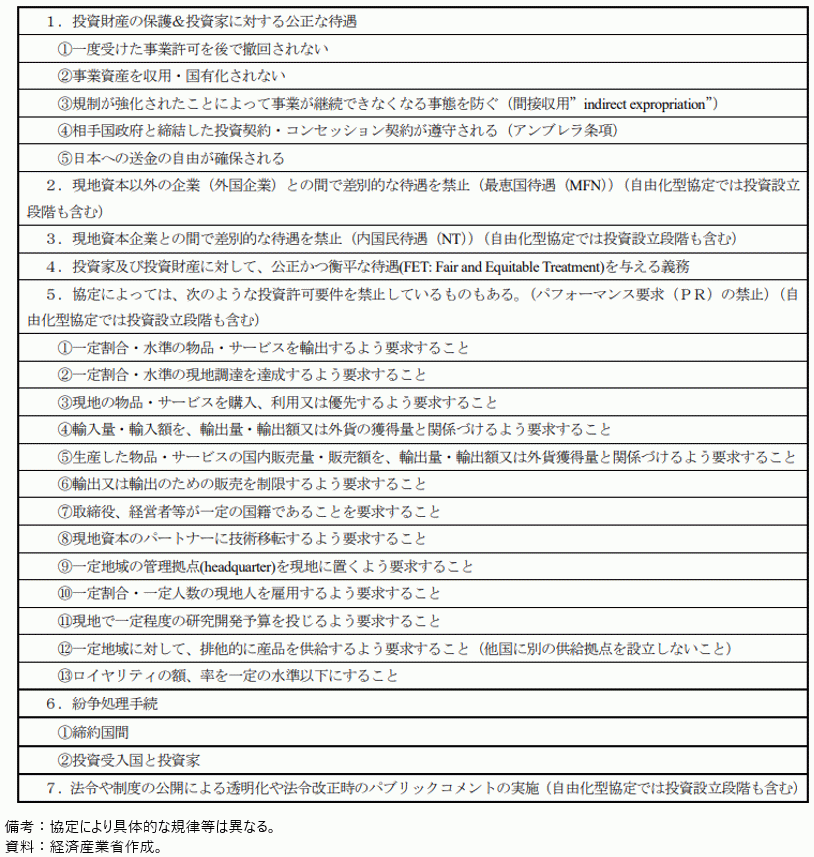
410 例えば、投資受入国が一定の現地部材(ローカルコンテンツ)比率を満たすことや、製造したものの総量のうち一定の比率を輸出すること等を投資活動に関する条件として要求すること。
411 代表的なものとして我が国の場合、二国間EPAの投資章や、日韓、日・ベトナム、日・カンボジア、日・ラオス、日・ウズベキスタン、日・ミャンマー投資協定等がこのタイプにあたる。
③ エネルギー憲章条約の主な規定内容
投資協定と同じように、投資に関して国際仲裁への付託を可能とする多国間の条約として、エネルギー憲章条約(ECT)がある。1998年に発効したエネルギー憲章条約は、エネルギー分野における投資の保護及び自由化に関し、一般的な二国間の投資協定と類似の内容(締約国が外国投資家の投資財産に対して内国民待遇又は最恵国待遇のうち有利なものを付与すること、一定の要件を満たさない収用の禁止、送金の自由、紛争解決手続等)について規定している。発効から20年以上経過している本条約については、改正等が必要な条項を検討する条約の近代化の議論が2017年から開始され、2020年から本格的な交渉が行われた。その結果、2022年6月に実施された臨時エネルギー憲章会議で、近代化交渉の実質合意がなされ、改正ECTでは、水素やアンモニア等の新たなエネルギー原料が投資保護規律の対象に加えられるとともに、EU及び英国における化石燃料関連投資が原則として投資保護の対象から外れることとなったほか、投資保護に係る締約国の義務の明確化、投資家対国家の紛争解決手続の詳細の明文化、持続可能な開発と企業の社会的責任に係る条文の新設、通過の自由をさらに促進させるための努力義務等が含まれることが合意された。
2022年11月22日にエネルギー憲章会議第33回会合、2023 年 11 月にエネルギー憲章会議第 34 回会合が開催されたが、ECT を取り巻く状況を踏まえて各国で議論した結果、近代化された改正 ECT の採択を延期して議題として取り上げないこととなったため、採択は行われなかった。
この状況の中、2022 年 12 月にはフランス、ドイツ、ポーランドが脱退を通告、2023年にはルクセンブルク(6月)。2024年にはポルトガル(2月)、スペイン及び英国(4月)、EU 及び欧州原子力機関(Euratom)及びオランダ(6月)、デンマーク(9月)が脱退の通告をした。
この間、2024年5月には、EU理事会は、EU及びEuratomがECTから離脱する一方、EU加盟国が次回のエネルギー憲章会議でECTの近代化を支持することを妨げない旨を決議した。こうした経緯を経て、2024 年 12 月 3 日に開催されたエネルギー憲章会議第 35 回会合で、改正 ECT が採択された。なお、「ECT本文の改正」並びに附属書NIセクションC及びその他の附属書の修正・変更は、2025 年 3 月 3 日までに暫定的適用を受け入れない旨の宣言をしない締約国間では、2025 年 9 月 3 日から暫定的に適用される。我が国は、2025 年 3 月 3日に、暫定的適用を受入れない旨の宣言を行った。
④ 我が国の投資協定を巡る最近の状況
我が国から海外への投資が拡大していると同時に、新興国を中心に世界の市場も急速な勢いで拡大を続けており412、日本企業や日系企業は、熾烈な海外市場の獲得競争にさらされている。我が国の経済成長をより強固で安定的なものにしていくためには、貿易投資立国としての発展を目指し、世界のビジネス環境をより一層整備していく必要がある。かかる観点から、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、機会の拡大等について規定する投資協定及び投資章を含むEPA/FTA(以下、投資関連協定)は、投資支援のツールとしての重要性を一層増している。日本政府は、他の経済政策と並び、既存協定の改正を含む投資関連協定の締結を一層加速し、投資環境の整備を進めている。
2016年5月に策定された「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」(アクションプラン)では、2020年までに、100の国・地域を対象に投資関連協定を署名・発効すること、投資市場への新規参入段階から無差別待遇を要求する「自由化型」の協定を念頭に、高いレベルの質を確保すること等を指針として掲げ、積極的かつ集中的に投資関連協定の締結に取り組んできた。
2021年3月には、「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン(成果の検証と今後の方針)」を策定し、アクションプラン以降の取組を検証した。二国間投資協定のみならず、CPTPP、AJCEP、RCEPなど、多国間の投資連携協定交渉にも積極的に取り組み、締結・発効に至っている。加えて、多くの投資協定において、自由化型、我が国産業界が重視する公正衡平待遇、ISDS(投資家と国家の間の紛争解決)規定等が盛り込まれている。
さらに、今後の方針としては、アクションプランで100の国・地域という目標値が設定されたことを踏まえ、今後の投資先としての潜在力の開拓や他国の投資家と比較して劣後しないビジネス環境の整備等に向け、引き続き戦略的観点及び質の確保の観点を考慮した取組を進めることとし、特に、中南米及びアフリカを中心的な検討先とすることを明記した。加えて、投資連携協定の実効性の観点から、経済関係団体等との連携、在外公館・JETRO等を通じた、積極的な情報発信に努めることとしている。
2025年3月現在、57本の投資関連協定が署名され、うち54本が発効済みとなっている(第III-2-2-7表)。また、交渉中の協定を含めれば96の国・地域をカバーすることとなった。今後も、産業界のニーズや相手国の事情に応じ、新規協定の締結及び既存協定の改正に向けた交渉を一層積極的に進めていく必要がある。
第Ⅲ-2-2-7表 我が国の投資関連協定の発効又は署名の状況
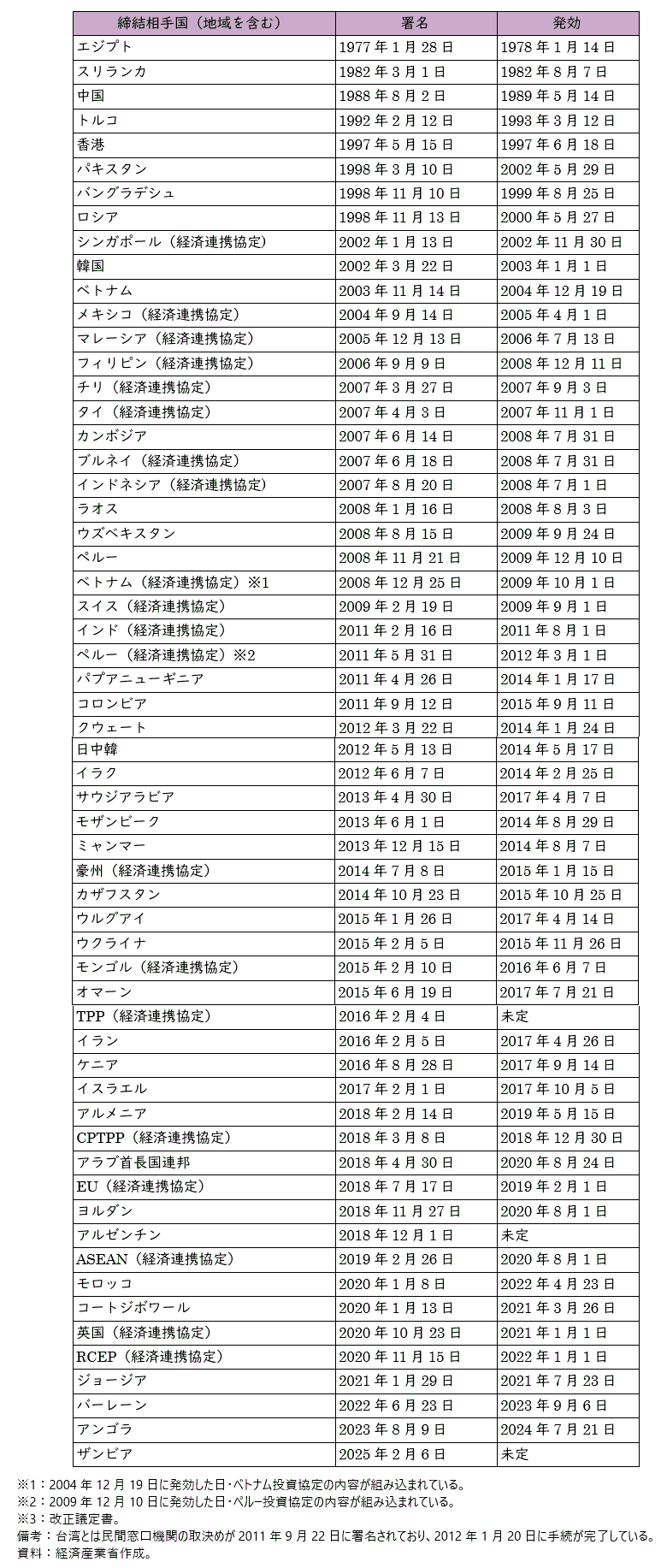
412 外務省「海外進出日系企業拠点数調査」(令和5(2023)年版)、財務省「対外・対内直接投資の推移」参照。
⑤ 今後の課題
多くの投資協定では、ISDS手続規定を設けている。これは、投資受入国が協定の規定に反する行為を行ったことにより投資家が損害を被った場合、投資家が投資受入国との紛争を、ICSID(投資紛争解決センター)413条約に基づく仲裁規則やUNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会)414仲裁規則に基づく国際仲裁に付託することを認めるものである。
近年、このISDSを投資協定に含めることを好まない国が増加している。これらの国は、ISDSに投資家寄りの制度的なバイアスが存在すると主張し、国家主権や柔軟な政策幅を確保する必要があることを根拠として挙げている。例えば、ブラジルは、ISDSは憲法に反するとして、これまでISDSを含む投資協定を締結していないほか、南アフリカ、ベネズエラは、ISDSを含む投資協定を破棄した。また、ISDSを投資協定に含めること自体は否定しないものの、インドやナイジェリア等は、ISDSに国内裁判所への訴えを要件とすることを自国の新たなモデル投資協定に規定する等、ISDSのリスク等を踏まえて協定の規定を見直す国もある。
このような状況の中、UNCITRALでは2017年からISDS改革について議論が行われる等、多国間の枠組みでの検討も進められている。このような傾向は、ISDSが投資家救済の観点から一定の成果をあげたことの裏返しでもあるが、将来におけるISDS活用の余地が狭められることにつながる懸念もあることから、国際的な動向を注視しつつ、必要な対応を検討していく必要がある。
413 世界銀行グループの1機関である常設の仲裁機関。所在地はワシントンD.C.。
414 所在地はオーストリア(ウィーン)。
6. 新たな多国間連携(IPEF、日米豪印、デジタル等)
(1) インド太平洋経済枠組み(IPEF)
米国のバイデン大統領は、2021年10月の東アジアサミットで、IPEF構想を発表した。米国とこの地域の国々に共通する課題である①貿易円滑化、②デジタル経済と技術の標準、③サプライチェーンの強靱性、④脱炭素化とクリーンエネルギー、⑤インフラストラクチャー、⑥労働基準、⑦その他の共通課題について、具体化をパートナー諸国と進めていくと表明した。
2022年5月、米国の主催により、IPEFの立上げに関する首脳級会合が東京で開催され、共同声明が公表された。同年9月に14か国(米国、日本、豪州、ニュージーランド、韓国、インド、フィジー、ASEAN7か国(ブルネイ、インドネシア、 マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム))が参加して、①貿易、②サプライチェーン、③クリーン経済及び④公正な経済の四つの柱について、正式に交渉開始が宣言された。以降、世界人口の半数を擁し、世界の活力の中核であるインド太平洋地域での、イノベーティブで、包摂的、持続可能な経済成長の実現に向け、集中的に交渉が重ねられてきた。
2023年5月にサプライチェーン協定が実質妥結に至り、同年11月に米国で開催された閣僚級会合及び首脳会合にて署名された後、2024年2月に発効した。また、同閣僚級会合では、クリーン経済協定分野及び公正な経済協定等について実質妥結に至った。
2024年6月にシンガポールで行われた閣僚級会合では、クリーン経済協定及び公正な経済協定等の署名が行われ、これらの協定は2024年10月に発効した。
(2) 日米豪印首脳会合
2024年9月、日本、米国、豪州、インドの4か国は、日米豪印首脳会合を米国にて対面で開催した。岸田総理大臣から、日米豪印の4か国が「自由で開かれたインド太平洋」という共通のビジョンへの強固なコミットメントを国際社会に示し続けていくことがますます重要である旨述べ、4か国首脳間でその旨一致した。
同会合の機会に日米豪印首脳共同声明が発出され、経済産業省関連では、重要・新興技術や気候及びクリーンエネルギー、サイバー等における4か国間の協力を更に推進することが盛り込まれた。
(3) デジタル通商ルール
近年、越境データ流通量は増加傾向にある。急速に発展するデジタル経済の機会をいかすためには、データの利活用が不可欠であり、これが社会課題の解決や企業価値向上に貢献すると期待されている。
2019年1月のダボス会議で、安倍総理大臣がDFFTを提唱し、同年6月のG20大阪サミットで、プライバシーやセキュリティ等の課題に対処することでデータの自由な流通を更に促進し、消費者及びビジネスの信頼を強化することができるとするDFFTの考え方が示された。
DFFTの推進に向けて、デジタル庁を含む関係省庁が連携しており、特に通商ルール分野の関連では、以下の取組がある。
① WTO電子商取引共同声明イニシアティブ交渉
WTO電子商取引共同声明イニシアティブに参加する91か国・地域と共に、電子商取引に関する規律について、高い水準かつ商業的に意義ある成果を目指して2019年から交渉が行われており、日本は、豪州、シンガポールとともに共同議長国を務めている。
2024年7月には、共同議長国は、交渉参加国・地域を代表して、電子商取引に関する協定に係る安定化したテキストを達成した旨の共同議長国声明を発出するとともに、テキストを公表した。
【詳細は、第III部第1章第3節5.(1)を参照。】
② 経済連携協定における電子商取引章
CPTPP(2018年12月発効)の電子商取引章で、データ流通を促進する国際約束の先駆けとして、情報の電子的手段による国境を越える移転(いわゆる、データの自由流通の原則)やコンピュータ関連設備の設置等について規定された。
以降、日米デジタル貿易協定(2020年1月発効)、日英EPA(2021年1月発効)、RCEP(2022年1月発効)でも同様の規定が盛り込まれた(なお、協定ごとに例外範囲などの違いあり)。
また、日EU・EPA(2019年2月発効)では、同協定内の規定(第8.81条)に従い、「データの自由な流通に関する規定」を同協定に含めることの必要性の再評価についての協議が行われ、2022年10月に正式交渉を開始、2023年10月に大筋合意した。2024年1月には、「データの自由な流通に関する規定」等を含めるEPA改正議定書が署名され、同年7月1日に発効した。
さらに、日インドネシアEPA(2008年7月発効)では、協定改定交渉により、電子商取引章が導入され、情報の電子的手段による国境を越える移転、コンピュータ関連設備の設置等の規定が盛り込まれることで大筋合意を確認し、2024年8月8日に署名に至った。
【個別の経済連携協定の状況については、第III部第2章第2節第5項を参照。】
③ その他国際フォーラムでの議論(G7、OECD)
(i) G7
G7貿易大臣会合(2024年7月)では、WTO電子商取引共同声明イニシアティブ交渉の適時な妥結に向けて取り組むこと、正当化できないデータローカライゼーション措置が越境データ流通に悪影響を及ぼすことを認識し、透明性を欠き、恣意的に課される正当化できないデータローカライゼーション措置に対処することに引き続きコミットすることが確認された。
【G7貿易大臣会合については、第III部第1章第1節を参照。】
(ii) OECD(経済協力開発機構)
OECDでは、デジタル経済に関する国際的な共通理解の醸成に向け、デジタル貿易に係る既存ルールや原則等を整理するOECDインベントリプロジェクトを、日本からの拠出で、2020年から2022年にかけて実施した。越境データ流通を促進する各国措置について一定の共通項を明らかにするとともに、異なる措置の相互運用性を達成するには補完的なアプローチが有効であることを示し、G7・G20の関連大臣会合やWTO電子商取引共同声明イニシアティブ交渉会合でも紹介された。2023年には産業界からも懸念の強いデータローカライゼーション措置について更なる調査を実施した。当該調査結果は、2023年G7貿易大臣声明で、正当化できないデータローカライゼーション措置に対抗すべきというG7共通のメッセージを発出する上で重要な議論の土台となった。
また、政府による民間保有の個人データへのアクセス(ガバメントアクセス)に関し、許容されるアクセスと許容されるべきでないアクセスを差別化するため、日本の提案に基づき「信頼あるガバメントアクセス原則」についての議論を開始した。2022年12月のOECD/CDEP(デジタル経済政策委員会)閣僚会合では、「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」が採択された。同宣言には、法的根拠、正当な目的、承認、データの取扱い、透明性、監督及び救済の7項目からなるガバメントアクセスに関する共通原則が盛り込まれた。
7. 人権問題への対応
グローバル化の進展によって、企業活動が人権に及ぼす負の影響が拡大する中、企業活動による人権侵害についての企業の責任に対する国際的な議論が更に活発になっている。近年、欧米を中心に人権尊重を理由とした法規制の導入が進み、企業はこれらの法規制への対応を迫られている。また、NGO等がグローバル企業のサプライチェーン上で起こった人権侵害について批判するケースも生じており、人権侵害を理由とした製品・サービスの不買運動、投資先としての評価の降格、投資候補先からの除外、投資の引揚げ、既存顧客との取引停止などの経営リスクに直面する可能性が存在している。企業が直面するこれらの経営リスクを低減し、企業価値を向上させ、強靱で包摂的なサプライチェーンを構築する観点からも、サプライチェーン上の企業等も含めた人権尊重の取組を実施・強化していくことが必要となっている。
(1) 企業に人権尊重を求める海外の動き
2011年6月、「ビジネスと人権に関する指導原則」(国連指導原則)が、国連人権理事会において全会一致で支持(endorse)された。同原則では、人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセス、という三つの柱を規定し、国家と企業とが、相互に補完し合いながらそれぞれの役割を果たしていくことが求められている。企業は、人権を尊重する責任を果たすため、①人権方針の策定、②人権デュー・ディリジェンス415、③救済(苦情処理メカニズムの設置を含む)、を実施すべきとされている。また、同原則の履行として、各国に対し国別行動計画(National Action Plan:NAP)の策定が推奨されており、2025年3月末時点で日本を含む世界の30か国以上がNAPを策定している。
また、OECD多国籍企業行動指針及び国際労働機関(ILO)多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言の改定が、それぞれ2011年、2017年に行われた際、国家の人権保護義務や企業の人権尊重責任が盛り込まれた。さらに、2023年にOECD多国籍企業行動指針がOECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針に改定され、企業によるサプライチェーンの下流へのデュー・ディリジェンスの適用範囲の明確化等、新たな規定が盛り込まれた。人権保護義務を負うことはもちろん、企業に人権尊重責任があることが国際的な原則となっており、企業はこれらの国際的文書に沿って行動することが求められている。
さらに、近年、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進んでいる。例えば、欧州では、2021年6月にドイツで「サプライチェーンにおける企業のデュー・ディリジェンスに関する法律(サプライチェーン法)」が成立し、2023年1月に発効されている。同法では、一定規模以上の企業に人権デュー・ディリジェンスの実施や、その結果に関する報告書の作成・公表等を義務付けている。
さらにEUでは、2022年2月に欧州委員会が公表した、一定規模の企業に対して人権及び環境に関するデュー・ディリジェンスを義務化する「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令」が、2024年7月に成立した。本指令に基づきEU加盟国は2026年7月までに国内法を制定することになっており、2027年7月から企業規模に応じて順次適用開始されることとなっている 416。このほか、欧州委員会が2022年9月に公表した強制労働関連産品のEU域内における上市・EU域外への輸出を禁止する規則も、2024年12月に発効しており、2027年12月から適用開始されることとなる。
米国は、外交政策における人権重視を掲げ、欧州とも連携して、新疆ウイグル自治区における人権侵害への関与を理由とした制裁を含む措置を実施している。米国は1930年関税法により、強制労働由来品等の製品の輸入を禁止しているが、2022年6月には、中国の新疆ウイグル自治区で一部なりとも生産等された製品や、米国政府がリストで示す事業者により生産された製品は、全て強制労働によるものと推定し、原則として米国への輸入を禁止する「ウイグル強制労働防止法」が施行された。同法に基づき、輸入貨物を差し止められた場合、輸入者は、輸入物品とその原材料が新疆ウイグル自治区で生産されていないこと等を示す必要があり、同法の対象である(輸入物品やその原材料が新疆ウイグル自治区で生産されたものを含む)場合には、輸入物品が一部なりとも強制労働に依拠していないこと等を、輸入者が「明確かつ説得力のある証拠」を提出し証明する必要がある。本法の施行に併せて公表された「執行戦略」 417では、法執行の優先度が高いセクターとして、アパレル、綿花・綿製品、ポリシリコンを含むシリカ系製品、トマト・その他派生製品が当初掲げられていたが、2024年7月の更新418 では、新たにポリ塩化ビニル、アルミニウム、水産物が追加されている419 。国土安全保障省税関・国境取締局(CBP)が公開した同法の執行状況についての統計ダッシュボードによると、2025年2月までに、ウイグル強制労働防止法に基づき、既に15,539件の輸入が差し止められ、そのうち8,633件の輸入が禁止され、5,558件の輸入が許可されている420。
こうした国際社会の動きも踏まえ、企業としても事業活動における人権尊重の取組を行っていく必要があり、自社内だけでなく自社のサプライチェーンやバリューチェーン全体を見据えた対応と情報開示が求められている。
415 人権デュー・ディリジェンス(DD):人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為を指す。
416 なお、欧州委員会は、2025 年 2 月 26 日に、本指令を含む持続可能性に関連する規制の簡素化を目的とするオムニバス法案を発表した。オムニバス法案では、本指令におけるデュー・ディリジェンスの義務の簡素化や適用開始時期の延期などが提案されており、今後 EU 理事会及び欧州議会において審議されることとなる。
417 US Department of Homeland Security, ‘Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China: Report to Congress’, 17 June 2022,
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-06/22_0617_fletf_uflpa-strategy.pdf![]() .
.
418 US Department of Homeland Security, ‘2024 Updates to the Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China: Report to Congress’, 9 July 2022, https://www.dhs.gov/sites/default/files/2024-07/2024%20Updates%20to%20the%20Strategy%20to%20Prevent%20the%20Importation%20of%20Goods%20Mined%2C%20Produced%2C%20or%20Manufactured%20with%20Forced%20Labor%20in%20the%20People%E2%80%99s%20Republic%20of%20China.pdf![]() .
.
419 2023年8月の執行戦略の更新においては、ナツメ他農産品、ビニル製品、アルミニウム、鉄、鉛蓄電池、リチウムイオン電池、銅、電子機器、タイヤ他自動車部品が、NGO 等による特定に起因する監視強化品目として列挙されている。US Department of Homeland Security, ‘2023 Updates to the Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China: Report to Congress’, 26 July 2023, https://www.dhs.gov/sites/default/files/2023-08/23_0728_plcy_uflpa-strategy-2023-update-508.pdf![]() .
.
420 US Customs and Border Protection, ‘Uyghur Forced Labor Prevention Act Statistics’,
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/uyghur-forced-labor-prevention-act-statistics![]() .
.
(2) 我が国の取組
我が国政府は、国連指導原則を踏まえ、2020年10月に「「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)」を策定し、日本企業に対して、規模、業種等にかかわらず、人権デュー・ディリジェンスのプロセスの導入を期待する旨を表明した。
また、経済産業省は外務省と連名で、2021年9月~10月にかけて、政府として初めて、行動計画のフォローアップの一環として、日本企業のビジネスと人権への取組状況に関する調査を実施した(「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」421 )。調査結果を見ると、回答企業のうち、人権方針を策定している企業は約7割であるほか、人権デュー・ディリジェンスを実施している企業は約5割程度にとどまっている。また、人権を尊重する経営を実践する上での課題としては、「サプライチェーン上における人権尊重の対応状況を評価する手法が確立されていない」、「サプライチェーン構造が複雑で、対象範囲の特定が難しい」、「十分な人員・予算を確保できない」との回答が多く見られ、政府に対する要望として、ガイドライン整備を期待する声が最も多く寄せられた。
このような状況も踏まえ、企業が国際スタンダードに沿った人権尊重に積極的に取り組めるよう、2022年3月、経済産業省は「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」を設置し、同検討会での議論を重ね、同年9月、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、日本政府として「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定・公表した422。
同ガイドラインは、法的拘束力を有するものではないが、国連指導原則、OECD多国籍企業行動指針及びILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言を始めとする国際スタンダードを踏まえ、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつわかりやすく解説している。企業の理解の深化を助け、その取組を促進することを目的としたものであり、 企業の規模、業種等にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業を対象としている。同ガイドラインで、企業は、国際的に認められた人権を尊重すべきとされ、その責任を果たすため、①企業トップを含む経営陣の承認を経た人権方針の策定・公表、②人権デュー・ディリジェンスの実施、③自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合における救済を行うことが求められている(第III-2-2-8図)。
第Ⅲ-2-2-8図 責任ありサプライチェーン等における人権尊重の全体像
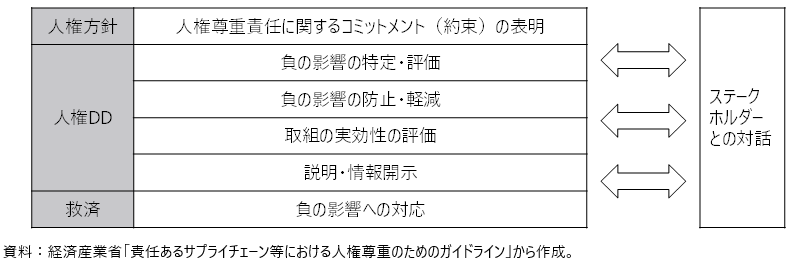
また、2023年4月には、具体的な取組方法がイメージできないなどの企業の声も踏まえて、経済産業省は、本格的に人権尊重の取組を行ったことのない企業が本ガイドラインに沿った取組を進めやすくする「サプライチェーンにおける人権尊重のための実務参照資料」を作成・公表した423 。そのほか、ILOへの拠出を通じて、2024年3月、ILOとJETROが共同で、東南アジア諸国等に活動拠点や取引先を持つ日本企業の人権尊重に係る取組をまとめた好事例集を公表した424。
さらに、ガイドラインや実務参照資料の活用を促すため、取組支援セミナー等を通じて周知徹底に努めてきた。2025年2月には、人権デュー・ディリジェンスで活用されている自己評価質問表を題材として、中小企業に求められるより具体的な人権尊重の取組に焦点を当てたセミナーを開催したほか、中小企業庁と連携して中小企業向けのセミナーを実施した。また、2022年からILOへの拠出を通じて、全国社会保険労務士連合会と協力し、中小企業の人権尊重の取組をサポートできる専門人材育成に取り組んでいる。2025年3月時点で計600名以上の社労士が研修を修了する等、中小企業に対する支援を進めてきた。そのほか、ILOへの拠出事業として、企業内人材育成プログラムの実施や、機関投資家向けのビジネスと人権に関するガイドの作成等を通じ、産業界への周知啓発を行ってきている。
日本国内だけでなく、アジア諸国でも、「ビジネスと人権」に取り組んできている。ILOへの拠出を通じて、アジアでの責任ある企業行動の推進を目的として、これまでアジア6か国 425において、日本企業の海外取引先企業などに対する人権デュー・ディリジェンスの実施支援、人権・労働環境向上のためのアドバイスの提供、国際労働基準に精通した人材育成支援などの事業を実施した。さらに、タイやインドネシアでは機械産業等技能開発への支援を通じ、責任ある企業行動の推進に努めた。また、2025年2月及び3月には、ベトナム企業と日本企業間の協力体制の構築・深化を目的に、ベトナム企業の経営層・管理職や業界団体向けに、責任ある企業行動の推進研修を実施し、サプライチェーンにおける人権デュー・ディリジェンスの実践的アプローチ等についての理解の促進に取り組んだ。
各国政策の予見可能性の向上に向け、国際協調・連携も進めている。国際場理では、2024年6月のG7プーリア・サミット及び同年7月のG7貿易大臣会合で、サプライチェーンにおける人権の確保、企業にとっての予見可能性及び確実性の向上に向けた取組の強化等について合意に至った。
日欧間では、2024年7月のEU企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令の成立を踏まえて、同年10月にウェビナーを開催した。本ウェビナーでは、欧州委員会司法総局、業界団体や有識者も交えて産業界の対応や課題についてのパネルディスカッションを実施した。
日米間では、2023年に「サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォース」を立ち上げ、2024年2月の第一回会合に続き、2024年10月及び12月に第二回会合(政府間対話及びステークホルダー対話)を開催し、両国政府や産業界の取組について情報交換を行った。
我が国政府は、企業による人権尊重の取組を促進すべく、引き続き企業に対する情報提供、周知・啓発活動を推進していくとともに、各国政府との協調を進め、公平な競争条件の下で積極的に人権尊重に取り組める環境、企業にとっての予見可能性が高まる環境の実現に向け取り組んでいくこととしている。
421 経済産業省・外務省「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査集計結果」、2021年11月、https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-jinken/suppiychain_chosa.pdf![]() 。
。
422 経済産業省「日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました」、2022年9月13日、https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html![]() 。
。
423 経済産業省「「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参考資料」を公表しました」、2023年4月4日、https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230404002/20230404002.html![]() 。
。
424 ILO「責任ある企業行動と人権デューディリジェンス:日本企業のグッドプラクティス」、2024年3月14日、https://www.ilo.org/ja/publications/responsible-business-conduct-and-human-rights-due-diligence-good-practices-JPN![]() 。
。
425 バングラデシュ、カンボジア、ベトナム、インド、ラオス、マレーシア。