第3節 我が国の通商活動を支援する取組(ツール)
経済産業省は、対外経済政策の推進体制の強化を目的として、令和6年7月に、経済協力関係課を従来の貿易経済協力局から通商政策局に移設した。これにより、通商戦略と経済協力施策を一体的に立案・実施していくための体制を整備した。
1. 貿易振興
(1) インフラ海外展開促進に向けて
① インフラ海外展開戦略
(i) 概況
拡大する世界のインフラ需要に対し、我が国の質の高いインフラ海外展開を促進することは、我が国経済成長にとって重要であるとともに、相手国の経済発展にも貢献するものである。他方、昨今は欧米企業に加え、価格競争力のある新興国企業との間で、市場競争の激化が顕著になっている。
政府では、インフラシステム輸出による経済成長の実現のため、内閣官房長官を議長とし、経済産業大臣も構成員である経協インフラ戦略会議にて、2013年に「インフラシステム輸出戦略」を策定した。それ以降、毎年改訂を重ねながら各種政策を推進してきた。2020年には、「インフラ海外展開戦略2025426」を策定し、2023年6月に追補版427を発表した。
426 経協インフラ戦略会議「インフラシステム海外展開戦略2025」、2020年12月10日、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai49/siryou2.pdf![]() 。
。
427 経協インフラ戦略会議「「インフラシステム海外展開戦略2025」の追補」、2023年6月1日、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai56/siryou1.pdf![]() 。
。
昨今では、インフラシステムの海外展開を取り巻く環境が急速に変化するとともに、国際社会は、気候変動等の地球規模課題の深刻化、自由で開かれた国際秩序への挑戦と分断リスクの深刻化、世界各地での人道危機等といった複合的危機に直面している。こうした中、カントリーリスクを始めとする投資・事業環境に関するリスクやサプライチェーン途絶といった経済安全保障上のリスクが増大している。我が国企業による持続的なインフラシステムの海外展開を推進するためには、これらの課題に対する一層の対応が求められている。
(ii) 取組・成果
こうした情勢を踏まえ、2024年12月に、2030年を見据えた、従来のインフラの概念を超えた領域における今後の海外展開の方向性を示すため、経協インフラ戦略会議にて、「インフラシステム海外展開戦略2030428」が策定された。同戦略では①相手国との共創を通じた我が国の「稼ぐ力」の向上と国際競争力強化、②経済安全保障等の新たな社会的要請への迅速な対応と国益の確保、③GX・DX等の社会変革をチャンスとして取り込む機動的対応を柱に掲げ、2030年に45兆円のインフラシステムの受注額を目指すこととしている。
428 経協インフラ戦略会議「インフラシステム海外展開戦略2030」、2024年12月24日、
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai58/siryou6.pdf![]() 。
。
② グローバルサウス戦略
(i) 概況
上記インフラシステム受注額の達成に当たっては、先進国のみならず、近年台頭が著しいグローバルサウスと呼ばれる新興国・途上国との連携強化が求められる。グローバルサウス諸国は、今後も人口増加と市場拡大が予想されることに加え、豊富な天然資源を有している。また、ウクライナ情勢や米中対立等の場面で、欧米諸国に安易に同調しない姿勢に見られるように、国際場裡における存在感も増していることから、我が国にとって不可欠なパートナーである。
他方、グローバルサウス諸国は、都市化や高齢化などの社会課題に直面する国、インフラ、公衆衛生や教育に問題を抱える国、食料や医療の不足に苦しむ脆弱国、難民の発生や気候変動の影響等の問題に苦しむ国など、様々な課題を抱えている。
国際社会が歴史の転換点を迎える中で、少子高齢化を迎え、食料・鉱物資源・エネルギー等を海外からの輸入に大きく依存する我が国にとって、グローバルサウス諸国が抱える課題に寄り添いつつ、協働を通じてその活力を取り込むことが、経済発展や経済の強靱化にとって重要である。
(ii) 取組・成果
我が国企業の「勝ち筋」が見える国・分野等を踏まえて、グローバルサウス諸国の市場における地域別・国別の戦略を策定し、我が国と相手国の相互に裨益する形で、優先度に応じて戦略的かつ集中的に事業を進めていく。
他方、グローバルサウス諸国の中でも、歴史的・文化的背景や経済状況、社会課題は様々であるため、我が国としては、必要に応じて同志国と役割分担しながら、各地域及び各国の実情に応じたテーラーメイドなアプローチを検討する必要がある。
③ グローバルサウス未来志向型共創等事業
(i) 概況
先述のとおり、グローバルサウス諸国との連携強化に向けては、我が国と相手国双方が裨益するビジネスを展開していく必要がある。グローバルサウス未来志向型共創等事業では、2024年以降、相手国のニーズが高いDX・GX分野を中心に共創案件の形成等を支援することで、相手国の産業育成や社会課題解決を目指すとともに、成長余力が高いグローバルサウス諸国の活力を生かした日本のイノベーション創出や、サプライチェーンの強靱化を含む経済安全保障の強化等を図ってきた。
(ii) 取組・成果
本事業は、グローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて、国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化することを目的とする。具体的には、インフラ等の海外展開のための大型実証事業及び小規模実証・FS事業や、我が国が相手国から「選ばれる」国となり、相手国の質の高い成長に貢献する案件形成のために、地域ごとの戦略策定に加え、インフラ等整備計画であるマスタープラン策定事業について公募を行った。2025年3月末時点で、大型実証事業(ASEAN地域)は第一次公募・第二次公募を通じて20件が採択された。小規模実証・FS事業は、第二次公募まで実施し、合計146件が採択された。マスタープラン策定事業は、第二次公募まで実施し、合計64件が採択された。
(2) 中堅・中小企業の海外展開支援
① 概況
中堅・中小企業の海外展開は、近年ますます重要なテーマとなっている。グローバル化が進む中で、国内市場の縮小や競争の激化に直面する中堅・中小企業は、新たな成長機会を求めて海外市場への進出を模索している。それに向け、高い技術力を有し、海外市場で十分に勝負できる潜在力を有する中堅・中小企業の海外展開を推進するため、貿易・投資相談など各種支援を実施している。
② 取組・成果
(i) 新規輸出1万者支援プログラム
「新規輸出1万者支援プログラム」は、経済産業省、中小企業庁、JETRO及び中小機構が一体となり、新たに輸出に挑戦する事業者を支援するためのプログラムである。
2022年12月16日に開始した本プログラムでは、登録した事業者に対して、JETROのコンシェルジュがカウンセリングを行い、事業者の海外展開の目標や準備状況から課題を整理し、中小機構、JETRO及び各支援機関の支援策を提案し、輸出の実現に向けて一気通貫の支援を実施している。
本プログラムは、2024年11月時点で全国の登録者が2万者を超え、うち2,800者超が輸出実現に至っている。登録者全体の4割超を製造業が占め、モノの輸出、特に食品関連の輸出挑戦が中心となっているが、サービス業や小売業も1割超の登録があり、海外への店舗出店やサービス輸出に取り組む事例も存在している。
輸出先国・地域別の成約件数では、米国向けの輸出が2割を占めている。本プログラムでは、直接輸出に取り組むことが難しい中小企業・小規模事業者に対しては、国内の輸出商社や越境EC等を通じた間接輸出による海外展開のアプローチを提案している。例えば、成約件数が最も多い米国に関しては、JETROがAmazon社と連携した「JAPAN STORE」を展開するなど、中小企業・小規模事業者にとって市場開拓に挑戦しやすい環境の整備を進めている。
(3) 貿易手続のデジタル化の推進
① 概況
世界貿易額は2021年以降、3年連続で20兆ドル超を記録する429など、世界経済の成長に大きく寄与している。その中で、貿易手続は未だに紙書類・手作業が残っており、貿易手続のデジタル化は長年にわたる課題となっている。WTO及びICC(国際商工会議所)の報告書によれば、2022年時点で、貿易文書のグローバルベースでのデジタル化率は1%未満であり、一般的な貿易取引において平均して36種類の書類と240部のコピーを複数の事業者間で取り交わす必要があると言われている430。
また、昨今ではコロナ禍による世界的な国際物流の混乱、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢の悪化などの影響を受けて、輸送貨物の状況確認や従来の物流ルートから代替ルートへの変更が必要となった際に、貿易データが蓄積されていないために人海戦術で個別に確認したり調査したりする対応が発生した。こうした問題への対応から、アナログな貿易手続がもたらすグローバル・サプライチェーンの脆弱性もこれまで以上に問題視されている。
このような状況下で、貿易手続のデジタル化やサプライチェーンの可視化に寄与する貿易プラットフォーム(以下、貿易PF)サービスが徐々に立ち上がりつつある一方、貿易に携わる企業の間で貿易PFの利用は未だ十分には浸透していない。現状の貿易PFを通じてデジタル化される貿易取引の割合は0.1%にも満たない状況であり431、ユーザーの拡大が喫緊の課題となっている。
429 JETRO(2024)
430 ICC (2022)
431 経済産業省「貿易プラットフォームの利活用推進に向けた検討会 中間報告書」、2024年3月、
https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/pdf/20240329_1.pdf![]() 。
。
② 取組・成果
(i) 貿易手続デジタル化に向けたアクションプランの策定
2023年11月、「貿易プラットフォームの利活用推進に向けた検討会」を立ち上げ、これまでに5回の会合を開催した。荷主企業、貿易PF提供事業者、国の3者で、貿易手続のデジタル化を目指し、貿易PFの活用に向けた各者の取組状況や抱えている課題等について継続して議論を行っている。検討会での議論を通じて、企業から挙げられた課題や国に対する要望を踏まえ、関係省庁と連携して「貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン432」を策定し、2024年6月に発表した。
以降、策定したアクションプランに基づき、未だに紙で扱われている貿易文書・手続のデジタル化や、貿易PFの導入支援・促進等に取り組んでいる。2025年2月の第5回検討会では、アクションプランの進捗報告を行うとともに、荷主企業、貿易PF提供事業者からも取組状況の共有が行われた。
432 経済産業省「貿易手続デジタル化に向けたアクションプラン」、
https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/digital_trade_platform/20240625_report.html![]() (2024年6月26日最終更新)。
(2024年6月26日最終更新)。
(ii) 貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金
貿易業務に携わる日本企業の貿易PF導入を促進するべく、企業による貿易PFの実証利用や、自社の社内システムと貿易PFの接続にかかる費用、並びに貿易PF間の連携にかかる費用の補助を行った。
(iii) 国際標準に準拠した貿易データ連携の促進
貿易分野の国際標準を定める国連CEFACT(貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター)に対して、2023年度から、日本企業が実務上使用しているデータ項目を国際標準に追加する働きかけを継続して支援し、2024年度には、インボイスや信用状など、貿易手続で取り交わされる主たる貿易文書を対象に、データ項目の国際標準への追加を要請した。
アクションプランを策定したことによって、関係省庁が連携して貿易手続のデジタル化に取り組む動きが強まり、これまでに紙で取り交わされていた貿易文書のデジタル化が着実に進みつつある。また、貿易PFの導入促進の面においても、補助金事業を通じて、貿易PFの実証利用15件、自社の社内システムと貿易PFの接続10件、貿易PF間の連携5件の支援を行った。
国際標準については、インボイス及び信用状において、日本からのデータ項目の追加要望が反映され、その他の貿易文書についても、2025年度第1四半期には追加要望が反映される見通しである。
(4) 国際仲裁の活性化
① 概況
国際仲裁とは、国際商取引をめぐる紛争について、一方当事者国の国内裁判所による「裁判」ではなく、当事者が選択に関与できる「仲裁人」と呼ばれる第三者の判断により、紛争解決を図る手続である。国際仲裁には以下のような特徴がある。
(国際仲裁の特徴)
・ 迅速な紛争解決
一審制で上訴がないので、いつ最終判断が下されるのか予測しやすい。
・ 秘密保持
原則として、手続は非公開で、企業秘密が保たれる。
・ 専門的で公平な判断
事案に即してその分野の専門性を有する第三者を仲裁人に選べる。
・ 柔軟な手続
使用言語を含め、当事者のニーズに対応した効率的な手続を当事者自身が決めることができる。
・ 仲裁判断の国際的な効力
「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)等の諸条約により、 外国における執行が容易である。
上記の特徴から、国際仲裁は、国際商取引上の紛争解決手法として、グローバルスタンダードとなっており、世界的に利用が進んでいる。他方、現在、我が国内における国際仲裁については、他の国際仲裁の振興に積極的に取り組んでいる国々と比べて利用が進んでいないとの指摘もあり、日本企業の海外進出・対日投資の呼込み等を推進するためにも、引き続き、我が国における国際仲裁の活性化を行う必要がある。
② 取組・成果
こうした状況の中、日本における国際仲裁の活性化に向けて必要な基盤整備を図るべく、政府は、2024年5月に関係府省連絡会議において「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策(令和6年指針)433」を取りまとめた。
経済産業省では、本指針を踏まえ、①法務省、日本商事仲裁協会(以下、JCAA)、経済団体等と連携し、業界団体向けの啓発・広報ウェビナーの継続・強化、②政府や関係団体等が作成するモデル契約書への仲裁条項明記に向けた働きかけ、 ③JCAAの認知度向上等、中小企業を含む我が国企業の仲裁活用の促進に向けた取組を実施している。
また、法務省、日本仲裁人協会(JAA)、JCAAと連携して、2024年11月18日~22日までの間、東京都内で、「日本国際仲裁ウィーク(Japan International Arbitration Week)」を初めて開催した。全世界から約1,300名(各セッションの参加者を合計した延べ人数)の参加登録があり、仲裁・調停を利用することによるメリットや、日本における仲裁の強みについてのパネルディスカッション、国内ユーザー向けのセッション等が行われた。
引き続き、法務省を始めとする関係府省や関係団体、経済団体、さらにはJETROや中小機構等とも連携して、日本における国際仲裁の活性化に向けた取組を推進していく。
433 内閣官房国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策(令和6年指針)」、2024年5月30日、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokusai_chusai/pdf/r06_sisin.pdf![]() 。
。
2. 通商金融
(1) 貿易保険を通じた貢献
① 概要
貿易保険は、日本企業の対外取引(輸出、投資、融資等)に関して、通常の保険によって救済することができないリスクを、国の信用力や交渉力に基づき長期間にわたり収支相償を前提にカバーする保険である。貿易保険では、「非常危険」(戦争、内乱、外貨送金停止等の相手国政府のリスク)と「信用危険」(プロジェクトの破綻等の相手企業のリスク)を引き受ける。貿易保険業務については、各国とも国の事業として実施・強化しており、我が国においては、貿易保険法に基づく特殊会社として、株式会社日本貿易保険(NEXI)が保険業務を実施している。
② 2023年度の引受状況
米中対立、ロシアによるウクライナ侵略の長期化、緊迫する中東情勢、新興国・途上国の債務問題の深刻化等の地政学リスクの高まりも受け、2023年度のNEXIの保険引受実績(フローベース)は、2017年の株式会社化以降最大額となる約8.0兆円に達した。また、2023年度末の保険責任残高(ストックベース)は約17.2兆円となり、2001年の独立行政法人化以降、最大額となった。434
434 株式会社日本貿易保険「日本貿易保険年次報告書2023」、
https://www.nexi.go.jp/corporate/booklet/pdf/annual2023-j.pdf![]() (2025年6月5日閲覧)。
(2025年6月5日閲覧)。
③ 貿易保険の機能強化
NEXIでは、「インフラシステム海外展開戦略」等の政府方針等を踏まえ、新たな保険商品の提供や機能強化を積極的に実施している。2020年12月には、カーボンニューラルやデジタル分野等における産業競争力向上、価値共創パートナーとの国際連携、社会課題解決やSDGs達成への貢献等の重点分野について、積極的な案件形成を支援するため、「LEAD(Leading Technologies & Businesses, Environment & Energy, Alliance, Development)イニシアティブ」を創設した。LEADイニシアティブの対象となる案件は既に複数組成されており、2024 年度の引受実績としては、ドイツにおいて実施する地熱発電事業に対する融資への海外事業資金貸付保険の引受があげられる。本案件は、運転中に温室効果ガスの排気量の大幅な削減を可能とする新技術を用いた事業で、欧州域内における安定的な再生可能エネルギー由来の電力・熱供給に貢献するものである。この他、2022年度のエジプトにおける陸上風力発電所の建設・運営プロジェクトや、ブラジルにおけるペレットフィードの生産プラントの建設プロジェクトも引受実績としてあげられる。こうした案件はグローバルサウス諸国との連携にも資するものであり、積極的な支援を継続する。
また、国内融資への保険提供(国内企業が、国内で建造される船舶を購入し、外航海運企業にリース・売却する事業を対象として、当該船舶を購入する国内企業が金融機関から購入資金の融資を受ける場合、NEXIがその融資のリスクをカバーすること)により、円滑な資金調達を可能とする制度改正を実施した。これにより、国内建造船の受注機会の拡大、ひいては国内造船業の国際競争力強化につながることが期待される。
④ 中堅・中小企業への支援強化
NEXIは、2005年に中小企業支援の取組として、通常商品と比較して低廉な保険料で利用可能な「中小企業輸出代金保険(現在の「中小企業・農林水産業輸出代金保険」)」を創設した。
その後、2011年には、貿易保険の普及と利用促進のため、中小企業を顧客とする全国の地方銀行・信用銀行との間で、「中堅・中小企業海外展開支援ネットワーク」を開始した。提携金融機関からの紹介により中小企業・農林水産業輸出代金保険を利用した場合、保険料が10%割引になる優遇措置を開始した(2024年10月時点で、全国の提携機関数は111機関)。また、2022年には、海外展開に取り組む中小企業への支援強化のため、中小機構、日本政策金融公庫との協力により「海外ビジネス支援パッケージ」を構築した。関係機関との連携・分担により、中堅・中小企業の課題やニーズの把握から海外ビジネスマッチング支援や金融支援まで、一体となって支援することが可能となった(2024年にはJETROも参画)。
さらにNEXIは、2024年9月に産業競争力強化法改正で新たに「中堅企業者」が定義され、また、2025年2月に「中堅企業成長ビジョン」が発表されたことを受け、2025年4月、中堅企業向けの支援強化として新たに「貿易保険中堅企業支援パッケージ(U2000)」の提供を開始した。これにより、「中小企業・農林水産業輸出代金保険」の中堅企業への適用拡大、バイヤー格付取得に係る費用の無料措置の提供を行い、中堅企業向けの支援にも積極的に取り組んでいる。
(2) 貿易保険事業のリスク対応能力強化
① 「貿易保険の在り方に関する懇談会(第3期)」の開催
地政学リスクが高まる中、グローバルに挑戦する企業にとって、貿易保険はリスク対応能力を下支えする有力な手段としてその重要性・必要性が一層高まっている。こうした中、貿易保険事業の適切かつ安定的な運営に向けた検討を行うため、2024年4~5月、経済産業省通商政策局長主催の「貿易保険の在り方に関する懇談会(第3期)」を開催した。
有識者や業界関係者との議論の結果、(1)我が国で貿易保険事業の運営を担う唯一の公的機関である NEXI において、適切なリスク管理の下で健全性を維持しつつ、将来にわたって持続可能な形で保険を引き受けることが極めて重要であり、(2)このためには今後、NEXI においてリスク管理(引受上の工夫等)及び財務基盤(保険料率の検証、余裕金運用の見直し、予算措置等)の双方の強化を図るとともに、その際に政府の果たすべき役割等について、政府が早急に検討・実施に取り組むことが期待される旨の報告書435が取りまとめられた。
435 経済産業省「貿易保険の在り方に関する懇談会(第3期)報告書」、
https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/trade_insurance/pdf/20240619_1.pdf![]() 。
。
② 取組
「貿易保険の在り方に関する懇談会(第3期)」の報告書でまとめられた検討事項のうち、「余裕金運用の見直し」については、2025年2月に所用の省令改正を実施した。NEXI が行う貿易保険事業は、その業務を安定的に運営することに対する要請が強いことから、余裕金の運用には一定の制限がかかっているが(運用先を省令で規定)、外貨資産の顕著な増加を背景に、外貨資産を保有する必要性が高まっていることから、運用先として外国政府保証債(外貨建て)を追加したものである。
3. 技術・人材協力
(1) はじめに
我が国では、技術・人材協力政策として、1950年以来、発展途上国の技術水準の向上と我が国企業の海外展開促進に資する環境整備のため、発展途上国へ我が国の技術や技能、知識を移転する技術協力や、社会・経済の開発の担い手となる人材の育成を支援する人材協力を行ってきた。その技術・人材協力政策は、世界における我が国の相対的な地位の変化や、グローバル化といった外部環境の変化等にしたがって浮かび上がる課題に対応すべく、その内実を変化させてきた。
本項では、我が国を取り巻く環境の変化とそれに伴う課題、その対応策としての技術・人材協力政策、そして高度外国人材獲得政策について見ていく。
(2) 概観
戦後日本の技術・人材協力の歴史は、1950年代に溯る。日本が高度経済成長を遂げていく中で、政府開発援助(ODA)による技術協力プロジェクトを進める一方、通商産業省(現:経済産業省)では日本企業の現地進出を後押しするため、企業による現地の人材育成を支援した。具体的な支援対象は、現地工場のライン長クラスなど工場運営に必要な現地人材を日本に招いての基礎知識の研修等の実施や、日本人専門家を現地工場に派遣する技術指導である。
こうした日本企業の海外進出が加速したのは1980年代後半である。1980年代前半に輸出を中心に大きく伸びた製造業は、プラザ合意に端を発する大幅な円高を契機に、海外における現地生産に積極的に乗り出すようになった。近年では、少子高齢化や人口減少、それによる国内市場の伸びの頭打ちが意識される一方、アジアを始めとするグローバルサウス諸国市場の伸長を背景に、海外市場に活路を見出す日本企業が増加してきた。こうした企業の海外進出に際して、現地拠点の整備や現地の法規制への対応が日本企業にとっての障壁となることがある。
また、近年では、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等を背景に、企業においてもサプライチェーン上の特定の国に過度に依存するリスクについての意識が高まっており、経済安全保障の観点からも政府による支援が求められている。
(3) 目標と現状・課題
上述の状況を踏まえると、我が国としては、海外市場の獲得を通じてその成長の活力を取り込みつつ、経済安全保障の確保を目指してサプライチェーンを強靱化させていく取組が求められる。
グローバルサウス諸国を始めとする海外市場の獲得に向けては、日本企業の海外進出や輸出を支援していく必要がある。特に、企業の海外進出については大きく、海外に拠点を設置するフェーズと、その拠点でビジネスを継続するフェーズに分けられるが、両フェーズに共通する課題として、現地におけるパートナー探しや現地事業を担う人材の不足のほか、企業にとってビジネス上の障壁となる現地の法規制が挙げられる。
輸出拡大に際して日本企業が抱える課題としては、言語や文化の壁等が要因となって輸出先市場において円滑に営業や交渉、マーケティングが出来ていないことや、市場に関する情報や現地の商慣行等に関する情報の不足等が挙げられる。
サプライチェーンの強靱化に向けては、拠点・取引先の確保やそれらの切り替えに係るコストの克服等が課題として立ちはだかるため、企業の新たな拠点の設置・取引先の開拓に向けた取組を後押しする必要がある。
(4) 我が国の取組
このように、海外市場の獲得とサプライチェーンの強靱化の実現の前には様々な困難が存在している。経済産業省は、長期的に相手国に裨益する協力関係を築きながら、現地での持続可能なビジネス環境を整備するため、技術・人材協力の観点からもそうした困難に対処しようとしている。
① 現地事業を担う人材育成の支援
海外に拠点を設置する際、そして拠点を運営していく際に企業が直面する課題である、現地における人材育成については、研修・専門家派遣・寄附講座開設事業を通じて支援を行っている。主に現地拠点を運営する人材の育成を目的に、現地の日系民間企業等の技術者や管理者に対して研修を実施するほか、現地の大学への寄附講座の開設を支援する。具体的には、まず、現地で管理監督、指導的な職務にある外国人材を日本に受入れ、日本の企業文化等の座学研修や企業での実務研修を実施する受入れ研修がある。また、日本法人の指導的立場にある者を専門家として現地に派遣し、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)による技術指導を実施する専門家派遣がある。そして、グローバルサウス諸国の大学等の在学生、若しくは日本の大学等に在籍するグローバルサウス諸国からの留学生を対象に、企業の事業活動や産業の発展の要となる技術分野に関する、寄附講座の開設支援を行っている。2024年度までに累計246,281人に対して受入れ研修を行い、5,816人の専門家を派遣し、また寄附講座436では2,928人を集めた(第III-2-3-1図)、(第III-2-3-2図)、(第III-2-3-3図)。2024年度は、新たに2,379人に研修を行い、44名を派遣、また2,174人を対象に講座を開設した。近年では、タイで半導体用金属導線の成形に使われるダイヤモンドダイスを既設の量産工場に展開すべく、本事業を活用して、現地で行われていなかった高度な特殊加工や研磨加工、検査技術についての研修を行い、現地人材を育成し、製品の生産増強・工程移管を達成した。また、ベトナムのハノイ電気機械短期大学を始めとする現地大学で、仮想空間(メタバース)上で機械設計、電気制御設計及びそれらの設計検証を行う講座の開設を支援し、受講学生から3名の採用、また今後5名の採用の計画につながっている。
第Ⅲ-2-3-1図 地域別 研修・寄附講座 指導対象者数
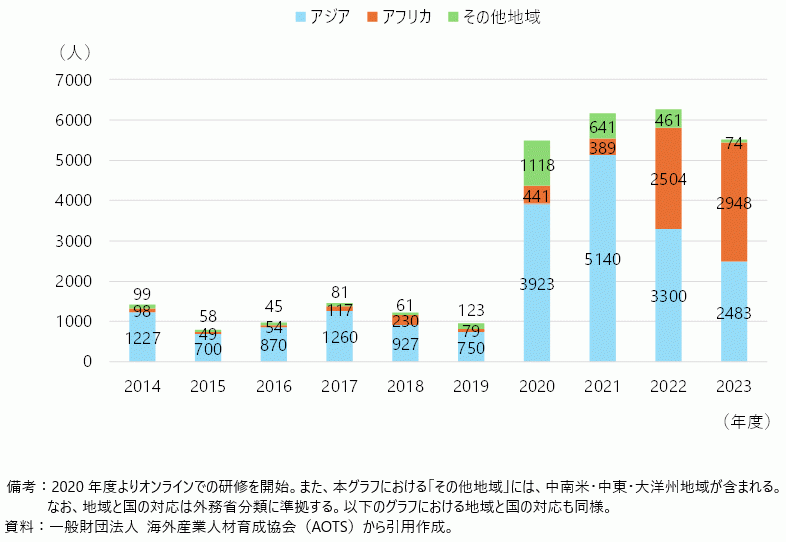
第Ⅲ-2-3-2図 地域別 専門家派遣人数
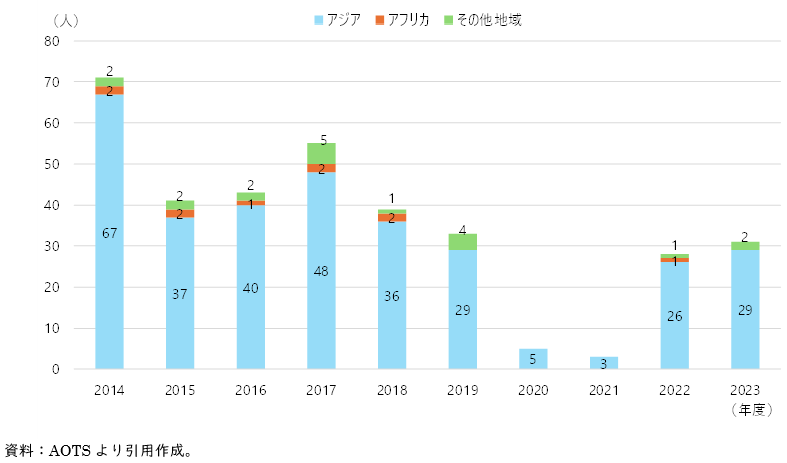
第Ⅲ-2-3-3図 地域別 研修・専門家派遣・寄附講座 件数割合
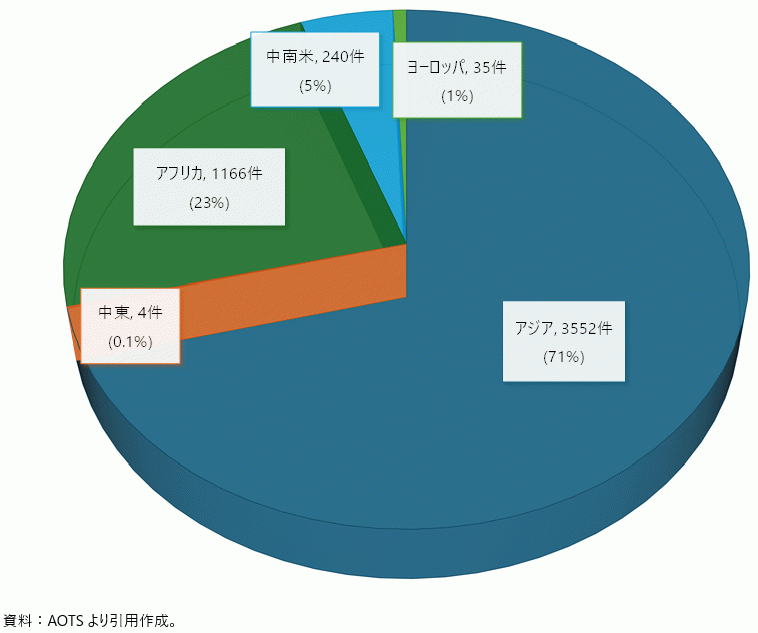
インドでは、「日本式ものづくり学校(JIM)」の設置への支援も行っている。これは、インドの若い人材に日本式ものづくりのコンセプトや技能を取得させ、将来の製造現場のリーダーを育成することを目的に、在インド日系企業が工場の既存施設等を用いて教育・実技研修を行うことを支援する事業である。これまで40校が開校され、2017年から2024年までに累計5,000人程度のインド人材の育成に貢献している。
436 現在の形を取る寄附講座は2020年度より開始。
② 障壁となる現地の法規制の改善
企業が現地でビジネスを実施していく際の障壁となり得る、規制や基準・規格の未整備に対しては、制度・事業環境整備事業を用意している。この事業では、主にグローバルサウス諸国の政府・経済界の有力者を対象に、日本の製品の技術力や法制度の考え方について、専門家が指導や啓発を行うことで、日本企業の参入障壁となっている現地の制度改正やルールメイキングにつなげることを目的としている。2024年度は、28件を採択した。例えば、マレーシアでは、我が国メーカーに優位性のある小型貫流ボイラーの普及に向け、製品に即した形での現地法令等の規制緩和を目指して現地政府関係者に対して研修を行い、参加者からは好意的な反応を得た(第III-2-3-4図)。
第Ⅲ-2-3-4図 制度・整備事業地域別及び分野別案件数(2016~23年度累計)
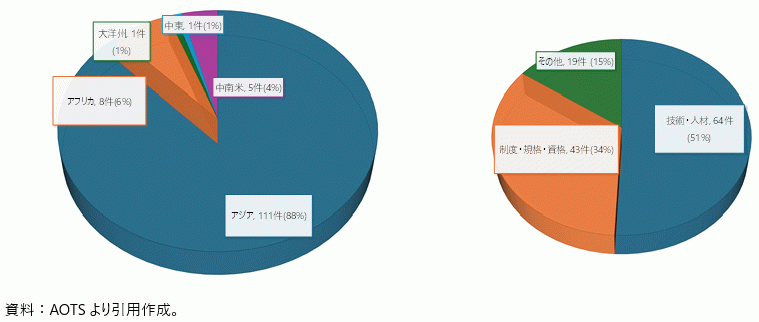
③ 国際競争力強化に向けた高度外国人材の受入・定着支援
国際競争力の強化のためには、現地事情に精通し、言語力や日本人と異なるバックグラウンドをいかして営業や交渉、マーケティング等を行える高度外国人材の活用が有効である。経済産業省では、高度外国人材の受入れ促進に向けた事業を実施している(第III-2-3-5図)。2023年度は、企業における高度外国人材の活躍環境整備の後押しや、海外展開等に取り組む体制の強化を目指し、中堅・中小企業に対してグローバルサウス諸国の大学の学生等のインターン受入れ機会を提供する国際化促進インターンシップ事業を行い、グローバルサウス諸国の学生等61名の受入れにつなげた。またグローバルサウス諸国の中でも特に、IT・AI分野を学ぶ学生と同分野の日本企業を対象に、グローバルサウスIT人材獲得支援調査事業を通じて、29社と80名の学生をマッチングさせ、インターンシップを実施した。インドやブラジル、エジプトでは、現地の大学関係者に本事業の成果をPRすること及び海外IT人材の日本での就職意欲を喚起することを目的に、成果報告会を開催し、延べ9社の登壇日本企業と、約600名の学生等を集めた。
第Ⅲ-2-3-5図 国際化促進インターンシップ 地域別インターン受入れ人数
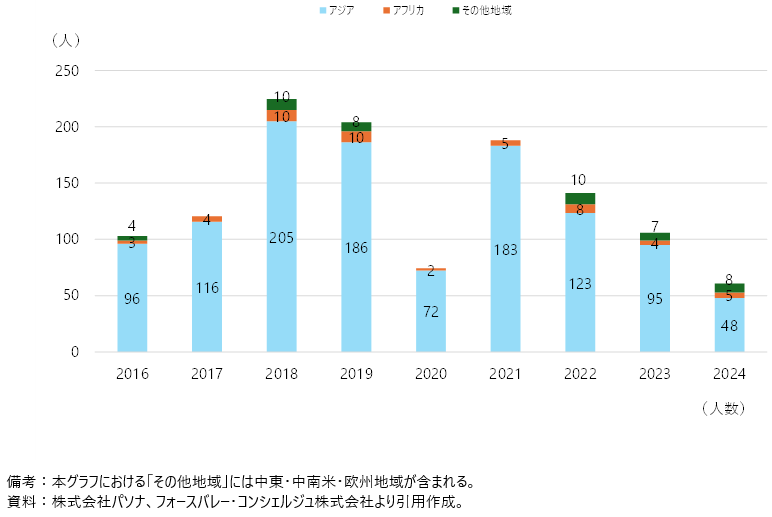
高度外国人材の雇用は、イノベーションの創出や組織の活性化を通じた企業の競争力の地盤強化につながるという期待もあり、日本企業の高度外国人採用へのニーズは高まっていくと見られている。
④ 海外市場獲得に向けたその他政策
経済産業省では、炭素中立への対応や社会課題解決の機会を捉えた現地進出・市場獲得支援や、グローバルサウス諸国に展開する際のマッチング等への支援を行っている。
アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業では、アジアにおいて、日系企業の現地工場での省エネ化によるCO2削減を実現すべく、国内工場への受入れ研修や現地工場への専門家派遣に伴う人材育成に係る費用を補助するほか、アジアにおける脱炭素化に向けた現地セミナー開催や現地企業の経営層の招聘を通して、日本の炭素中立技術の普及を支援している。
社会課題解決型国際共同開発事業では、アフリカ諸国や南西アジア等において、現地の企業・大学・NGO等のパートナーと共同で、社会課題の解決につながる製品・サービスの開発や実証等に取り組む際の経費の一部補助を行うほか、現地調査支援や、現地ネットワーク確立支援等の伴走支援を実施している。
また、UNIDOを通じて、日本企業のアフリカ進出支援を目的とした現地アドバイザーの配置や、グローバルサウス諸国の投資誘致担当官の招聘を通じた、セミナー・商談会開催によるマッチング・ネットワーキングの促進、さらにグローバルサウス諸国の持続的な産業開発に資する日本企業の優れた技術のプロモーションやビジネスマッチングを行う「サステナブル技術普及プラットフォーム(STePP)」の運営を通して、日本企業の海外への投資や技術移転を促進している。
(5) これからの技術協力政策及び高度外国人材政策
(3)で述べた課題は、一朝一夕に解決されるものではなく、また企業単独では取り組むことが難しいため、政府が引き続き関与していく必要がある。その際には、国際的な市場競争環境の変化や地政学リスクの高まり、我が国の立ち位置の相対化等の情勢の変化に、柔軟に対応していくことが求められる。
近年、「GX」「DX」「経済安全保障」など、経済合理性だけでは解決できない新たなミッションが生まれている中で、各国が自国最優先で様々な措置を導入すれば、世界の断片化が進み、国際経済秩序が漂流しかねない。このため、「持続可能性」や「信頼性」といった、同志間で共有し得る「価格以外の要素」が正当に評価され、公正な競争条件が確保されるグローバルマーケットの設計を進めていく必要がある。そこで経済産業省では、ASEANの政策立案に携わる行政官等を対象に、米国等の同志国の関係機関と連携しながら、非価格要素を考慮する重要性について研修を実施し、各国が産業政策・政府調達にその考えを取り入れることを後押しする。本研修を通じて、ASEAN各国の非市場的政策及び慣行への対応や経済安全保障上の脆弱性の克服、「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン」の確保等につなげていき、同地域の経済発展と我が国経済安全保障の確保に貢献する。
また、我が国にとって最大の貿易相手国であり、日系企業の海外拠点数が第1位である中国は、我が国にとって重要な市場であり、引き続き関係を維持していく必要がある。2024年5月の日中韓サミットの機会に実施された日中首脳会談で、両国がそれぞれ強みを持つ分野において連携し、ASEANを始めとする第三国における協力案件を具体化させていく方針で一致した。また、2025年3月の第6回日中ハイレベル経済対話でも、第三国市場での民間経済協力を引き続き推進していくことで一致した。さらに、2025年3月の日中韓経済貿易大臣会合の機会に行われた王文濤商務部長との会談でも、今後も様々な機会を活用して緊密に意思疎通を重ねていくことで一致した。このように、日中経済関係が更に前進していくことが期待されるところ、連携強化に向けて、日中第三国市場協力の現状を整理する。
また近年、欧米を中心に、法規制を早期に整備し、自国に有利な環境づくりをリードする動きが見られる一方、我が国ではこのような市場創出に向けた取組が十分に行われているとはいえない。そこで、欧米が行っている国際標準等のルール策定及びアジア諸国を始めとした個別国における法規制の整備等についての活動の実態や正攻法を調査し、今後の日本式ルールメイキングの在り方を検討する。
企業の競争力強化に向けては、高度外国人材の多様化を図りながら、その受入れを引き続き支援していく。「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン437」及び「対日直接投資加速化に向けた優先プログラム438」に基づき、東南アジアや南アジア等の高度若手人材の確保に向けた、現地大学との連携強化や在留資格制度の在り方等に関する検討を進めていく。また、我が国の企業が、特に日本語能力を有しない人材の採用やそうした人材と共に働く経験を必ずしも十分に有していないことに鑑み、その受入れ態勢整備のノウハウを蓄積させることを目的にしたマッチング・インターンシップを行う。あわせて、海外からの外国人材の直接採用を後押しするために、アジア諸国でジョブフェアを開催する。
437 対日直接投資推進会議「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」、2023年4月26日、
https://www.cao.go.jp/invest-japan/committee/action_plan.pdf![]() 。
。
438 対日直接投資推進会議「対日直接投資加速化に向けた優先プログラム」、2024年5月13日、
https://www.cao.go.jp/invest-japan/documents/pdf/yuusen_program.pdf![]() 。
。