

- 統計

- 外資系企業動向調査

- 結果の概要

- 第32回 調査結果(1997年度実績)-平成12年3月刊行-

- 研究開発の状況-平成11年7月6日公表-
外資系企業動向調査
研究開発の状況-平成11年7月6日公表-
活発であった研究開発活動
- 97年度における集計企業の研究開発費は2906億円で、前年度比12.6%の大幅増加となった。業種別では、製造業(2797億円 同11.7%増)、非製造業(109億円 同40.3%増)ともに大幅に増加した。研究開発費全体に占めるシェアをみると、製造業で全体の96.2%を占める。業種の内訳をみると、一般機械が同20.8%増の836億円となり、それまでトップシェアであった化学・医薬品(803億円 同4.9%増)を1.2ポイント上回った。上記2業種に次いで電気機械(641億円 同13.5%増)、輸送機械(321億円 同0.8%減)の順となっている(第2-(6)-1-1表)。
- 製造業について全法人企業と比較すると、集計企業における伸び率が全法人企業の伸び率を上回ったことから、国内製造企業に占める割合は前年度から0.1ポイント上昇して2.8%となった。これを業種の内訳でみると、同1.2ポイント上昇して10.6%となった一般機械をはじめ、石油(8.0%)、化学・医薬品(5.0%)などで平均を大きく上回る高い水準となっている一方、食料品(0.7%)、電気機械(1.7%)、輸送機械(1.9%)では昨年度に引き続き製造業平均を大きく下回っている(第2-(6)-1-2表)。
- 売上高研究開発費比率(注)をみると、全産業では、前年度と比べ0.5ポイント上昇の2.6%となり、業種別でみても、製造業(3.0% 同0.5ポイント上昇)、非製造業(0.6% 同0.2ポイント上昇)ともに上昇した。特に製造業においては、全法人企業の水準と比べ0.8ポイント程度低い水準となっているものの、全法人企業との差を昨年度と比べ0.4ポイント縮めており、集計企業において積極的な研究開発活動を行っていることがうかがえる。業種の内訳をみると、一般機械(7.8%)、化学・医薬品(4.6%)で、全産業平均(2.6%)を超える高い水準となっている(第2-(6)-1-3表)。
- 母国籍別にみると、アメリカ系企業及びヨーロッパ系企業ともに前年度と比べ増加となった。特にヨーロッパ系企業における増加幅は大きく、製造業においてはアメリカ系企業とほぼ同程度の水準となっている(第2-(6)-1-4表)。
- (注)
- ・ 売上高研究開発費比率=研究開発費/売上高×100
- ・ 売上高研究開発費比率は売上高及び研究開発費に百万円以上の報告のあった企業を対象。
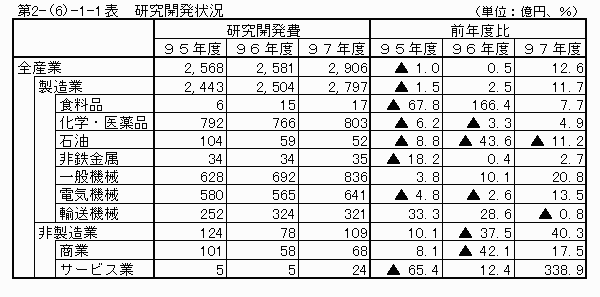
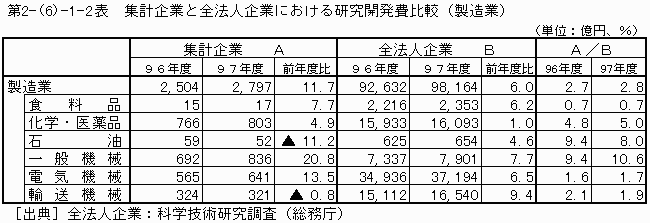

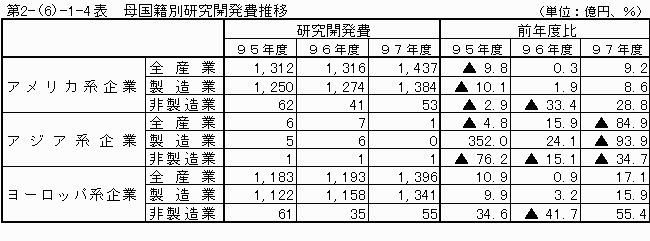
研究所の45.1%が最近の10年間に設立
- 97年度時点において集計企業が保有する研究所は170研究所であった。業種別にみると、製造業が135研究所で全体の79.4%を占めており、非製造業は35研究所(同20.6%)であった。業種の内訳では化学・医薬品が70研究所(同41.2%)と最も多く、次いで、商業(28研究所 同16.5%)、電気機械(23研究所 同13.5%)の順となっている(第2-(6)-2-1表)。
- 母国籍別にみると、アメリカ系企業で全体の56.5%を占める96研究所となっており、次いでヨーロッパ系企業(65研究所 同38.2%)、アジア系企業(4研究所 同2.4%)の順。研究開発費と同様に研究所の分布においても欧米系企業で全体の94.7%を占めている(第2-(6)-2-1表)。
- 研究所の設立年度別では、全産業では「1982年度以前」が最も多く、次いで「1995~1997年度」、「1992年度~1994年度」の順となっている。また、1989年度からの10年間に設立された研究所は全体の45.1%に達しており、製造業で同様の傾向であるが、非製造業では全体の70.6%もの研究所が1989年度以降設立されており、比較的近年に設立されたものが多いことがわかる(第2-(6)-2-1図)。また、研究員規模別にみると、30人未満で全体の72.4%を占めている(第2-(6)-2-2図)。
- 研究開発機能別にみると、全産業では「主に日本をターゲットにした製品開発」が全体の36.1%と最も多く、次いで、「日本国内での販売活動サポート」(同24.1%)、「輸入製品の日本市場向け改良・修正」(同10.2%)、「基礎的技術の研究」(同8.4%)等の順であった。業種別にみると、製造業では上位2機能について同様となっているが、非製造業では「日本国内での販売活動サポート」(同44.1%)が最も多くなっており、「輸入製品の日本市場向け改良・修正」(同23.5%)等の順となっており、業種ごとの特徴がうかがわれる(第2-(6)-2-3図)。
- 研究所の所在地別(注)では、関東地域(122研究所 研究所全体に占める割合72.6%)に最も多く設立されており、次いで、近畿地域(24研究所 同14.3%)、中部地域(11研究所 同6.5%)の順となった。これを先の研究開発機能別でみると、関東地域ではすべての機能がほぼ平均的に分布している一方、近畿地域では「製品コンセプトのデザイン」、「日本が得意とする特定分野の研究開発」が、中部地域では「輸入製品の日本市場向け改良・修正」、「主に日本市場をターゲットにした製品開発」がそれぞれ高くなっている(第2-(6)-2-4~5図)。
- (注)
- ・ 地域分割については、各通商産業局管轄と同一ブロック単位。
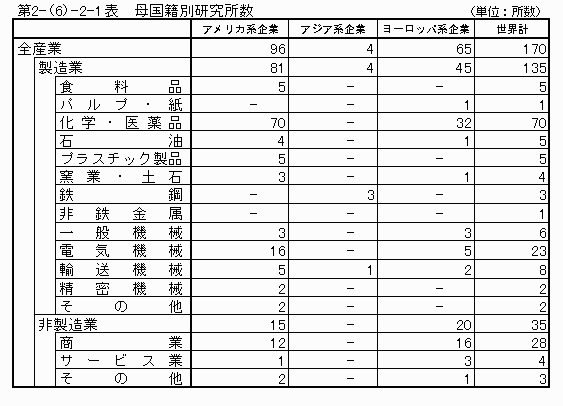
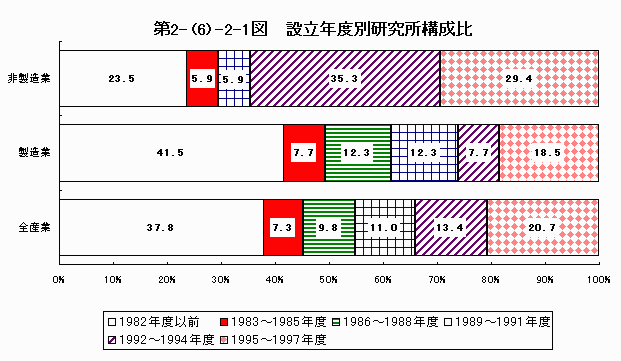
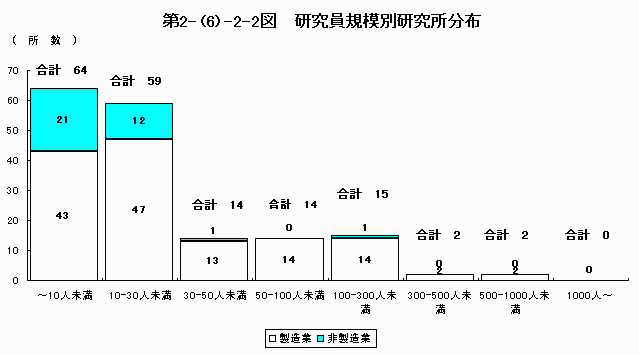
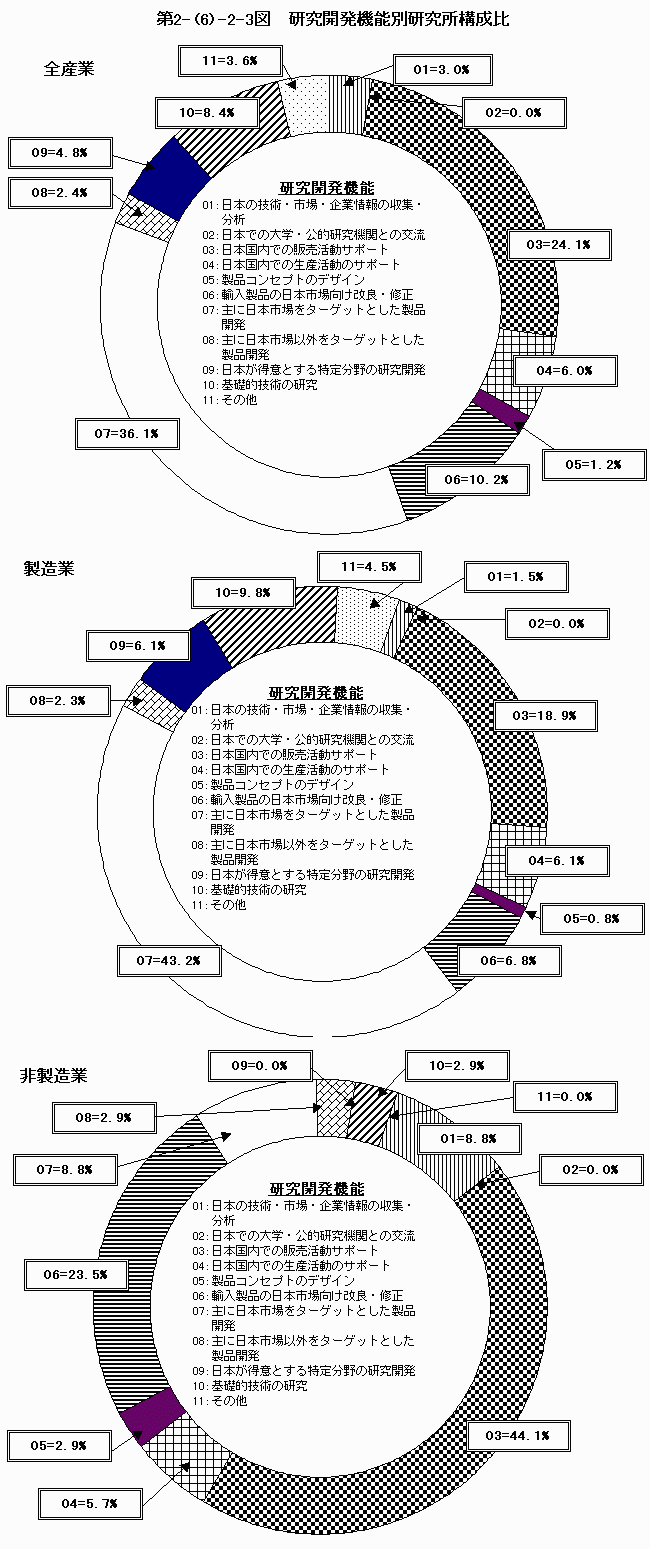
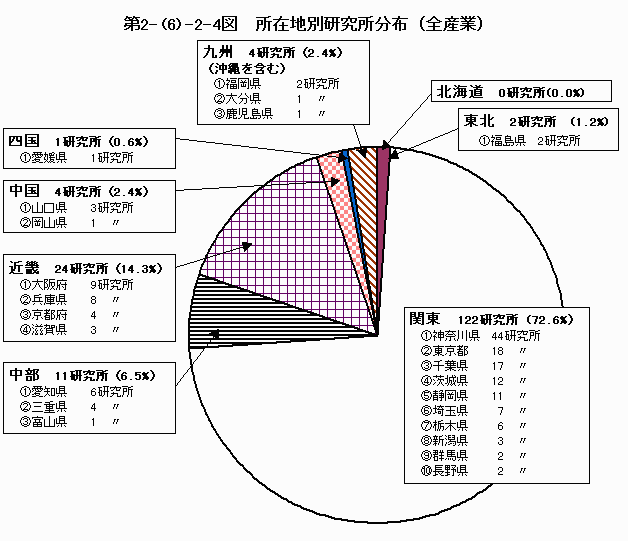
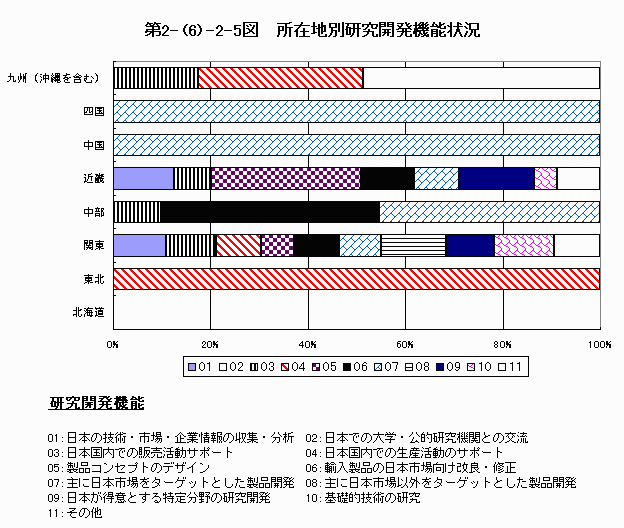
最終更新日:2007.10.1
