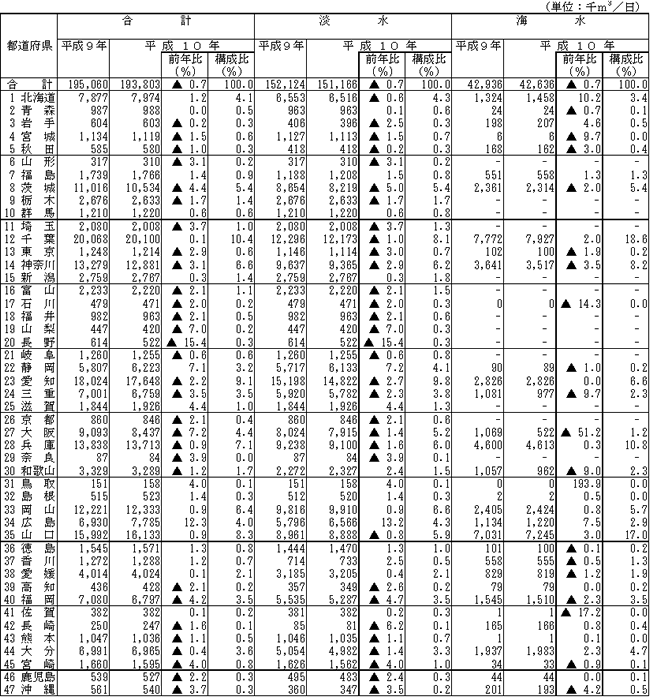- 統計

- 工業統計調査

- 調査の結果

- 統計表一覧

- 平成10年確報 用地・用水編

- 2.工業用水
工業統計調査
2.工業用水
平成10年の従業者30人以上の製造事業所における工業用水の1日当たり用水量(以下、用水量という)は、1億9380万 (前年比▲0.7%減)であった。このうち、淡水は1億5117万
(前年比▲0.7%減)であった。このうち、淡水は1億5117万 (同▲0.7%減、構成比78.0%)、海水は4264万
(同▲0.7%減、構成比78.0%)、海水は4264万 (同▲0.7%減、同22.0%)となっている(第5表)。なお、淡水の回収率(淡水計に占める回収水の割合)は、製造業計で78.0%、前年(77.9%)に比べ0.1ポイントと引き続き拡大している(第5表、第10図)。
(同▲0.7%減、同22.0%)となっている(第5表)。なお、淡水の回収率(淡水計に占める回収水の割合)は、製造業計で78.0%、前年(77.9%)に比べ0.1ポイントと引き続き拡大している(第5表、第10図)。
第5表 工業用水の主要項目の推移(従業者30人以上の事業所)
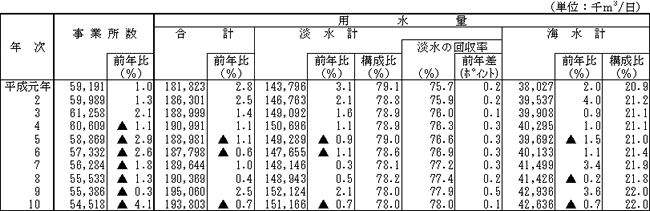
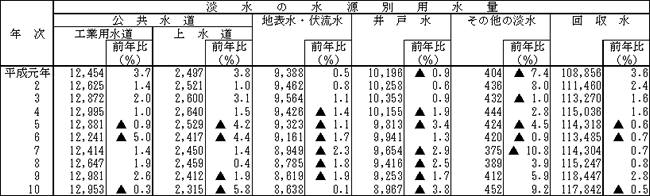
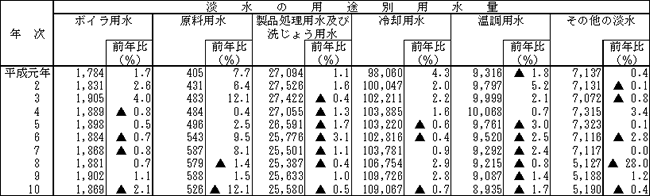
第10図 淡水の回収率の推移(従業者30人以上の事業所)
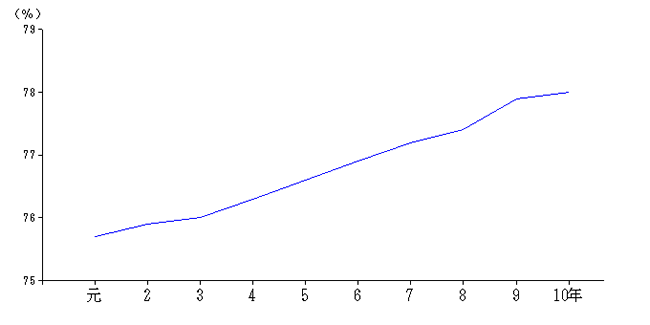
1.産業別の状況
(1) 用水量合計
- a. 工業用水の用水量は、1億9380万
 、前年比▲0.7%の減少であった(第6表)。
、前年比▲0.7%の減少であった(第6表)。
産業別にみると、化学工業(6731万 、構成比34.7%)、鉄鋼業(5354万
、構成比34.7%)、鉄鋼業(5354万 、同27.6%)の上位2産業で用水量の60%以上を占め、次いで石油製品・石炭製品製造業(1665万
、同27.6%)の上位2産業で用水量の60%以上を占め、次いで石油製品・石炭製品製造業(1665万 、同8.6%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(1556万
、同8.6%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(1556万 、同8.0%)、輸送用機械器具製造業(1075万
、同8.0%)、輸送用機械器具製造業(1075万 、同5.5%)の順となっている。この5産業で用水量の約84%を占めており、用水量が多い産業は特定の産業に集中している(第6表、第11図)。
、同5.5%)の順となっている。この5産業で用水量の約84%を占めており、用水量が多い産業は特定の産業に集中している(第6表、第11図)。
工業用水のうち淡水では、化学工業(5140万 、同34.0%)、鉄鋼業(3809万
、同34.0%)、鉄鋼業(3809万 、同25.2%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(1552万
、同25.2%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(1552万 、同10.3%)の上位3産業が用水量の約70%を占め、次いで輸送用機械器具製造業(1066万
、同10.3%)の上位3産業が用水量の約70%を占め、次いで輸送用機械器具製造業(1066万 、同7.1%)、石油製品・石炭製品製造業(920万
、同7.1%)、石油製品・石炭製品製造業(920万 、同6.1%)の順となっている。海水では、化学工業(1591万
、同6.1%)の順となっている。海水では、化学工業(1591万 、同37.3%)、鉄鋼業(1545万
、同37.3%)、鉄鋼業(1545万 、同36.2%)、石油製品・石炭製品製造業(745万
、同36.2%)、石油製品・石炭製品製造業(745万 、同17.5%)の上位3産業が用水量の90%以上を占めている。
、同17.5%)の上位3産業が用水量の90%以上を占めている。 第11図 用水量の産業別構成比(従業者30人以上の事業所)
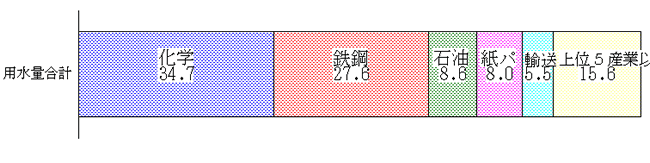
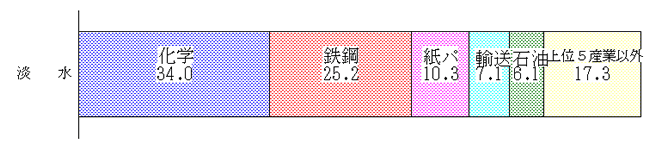
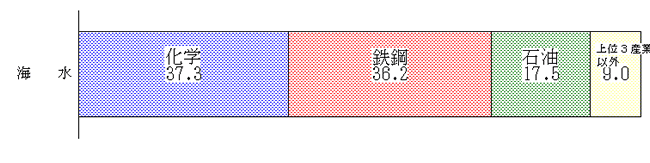
前年比でみると、飲料・たばこ・飼料製造業(前年比5.1%増)、窯業・土石製品製造業(同 3.2%増)など5産業は増加となったが、なめし革・同製品・毛皮製造業(同▲21.5%減)、家具・装備品製造業(同▲16.3%減)、木材・木製品製造業(同▲14.6%減)、その他の製造業(同▲10.0%減)など17産業は減少となっている(第6表、第12図)。
ここで、用水量の多い上位5産業についてみると、石油製品・石炭製品製造業(同2.4%増)、輸送用機械器具 製造業(同0.8%増)は増加となったが、鉄鋼業(同▲2.2%減)は減少、化学工業(同▲0.2%減)、パルプ・紙・紙加工品製造業(同▲0.1%減) は微減となっている。第12図 産業別用水量の前年比(従業者30人以上の事業所)
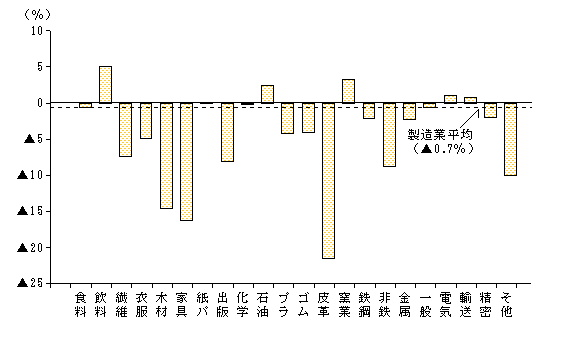
- b. 工業用水のほぼ8割を占める淡水の用水量は1億5117万
 、前年比▲0.7%の減少であった(第6表)。
、前年比▲0.7%の減少であった(第6表)。
これを産業別に、用水量の多い上位5産業についてみると、鉄鋼業は転炉・電気炉による製鋼・製鋼圧延業(単独転炉・単独電気炉を含む)、高炉による製鉄業などの減少により前年比▲2.2%の減少、化学工業は脂肪族系中間物製造業(脂肪族系溶剤を含む)などの減少により同▲0.4%の減少、パルプ・紙・紙加工品製造業は段ボール箱製造業などは増加したものの、板紙製造業などが減少したことにより同▲0.1%の微減となった。一方、石油製品・石炭製品製造業は石油精製業の増加により同4.9%の増加、輸送用機械器具製造業は、自動車製造業(二輪自動車を含む)の増加 により同0.5%の増加となっている(第6表)。
なお、1事業所当たり淡水用水量を産業別にみると、石油製品・石炭製品製造業が7万8614 と群を抜いて多く、次いで鉄鋼業(2万8725
と群を抜いて多く、次いで鉄鋼業(2万8725 )、化学工業(2万2783
)、化学工業(2万2783 )、パルプ・紙・紙加工品製造業(8628
)、パルプ・紙・紙加工品製造業(8628 )の順となっている。
)の順となっている。 第6表 産業別用水量(従業者30人以上の事業所)
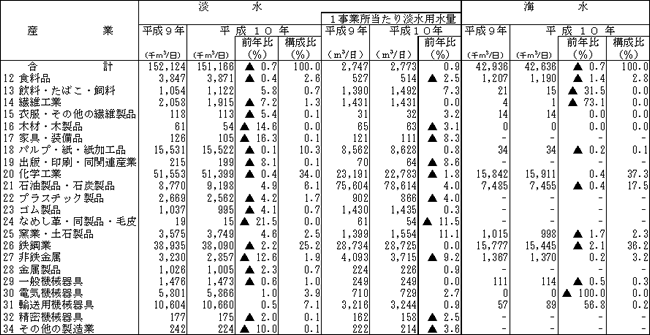
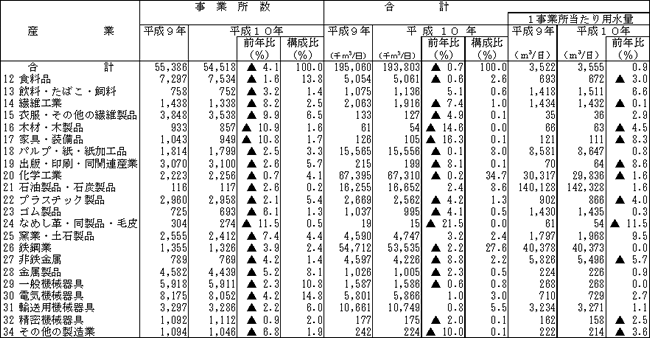
(2) 淡水の水源別用水量
淡水の水源別用水量をみると、回収水(1億1784万 、構成比78.0%)がほぼ8割を占め、次いで工業用水道(1295万
、構成比78.0%)がほぼ8割を占め、次いで工業用水道(1295万 、同8.6%)、井戸水(897万
、同8.6%)、井戸水(897万 、同5.9%)、地表水・伏流水(864万
、同5.9%)、地表水・伏流水(864万 、同5.7%)の順となっており、上水道(231万
、同5.7%)の順となっており、上水道(231万 、同1.5%)、その他の淡水(45万
、同1.5%)、その他の淡水(45万 、同0.3%)はわずかである(第7表、第13図)。
、同0.3%)はわずかである(第7表、第13図)。
前年比でみると、上水道(前年比▲5.8%減)、井戸水(同▲3.8%減)、回収水(同▲0.5%減)、工業用水道(同▲0.3%減)が減少、その他の淡水(同9.2%増)は増加、地表水・伏流水(0.1%増)は微増となっている。
各水源別にみると、
- a. 回収水の用水量は、化学工業(4284万
 、構成比36.4%)、鉄鋼業(3438万
、構成比36.4%)、鉄鋼業(3438万 、同29.2%)が群を抜いて多く、次いで輸送用機械器具製造業(983万
、同29.2%)が群を抜いて多く、次いで輸送用機械器具製造業(983万 、同8.3%)、石油製品・石炭製品製造業(830万
、同8.3%)、石油製品・石炭製品製造業(830万 、同7.0%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(710万
、同7.0%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(710万 、同6.0%)の順となっており、これら上位5産業で9割近くを占めている。
、同6.0%)の順となっており、これら上位5産業で9割近くを占めている。 - b. 工業用水道の用水量が多いのは、化学工業(442万
 、構成比34.1%)、鉄鋼業(291万
、構成比34.1%)、鉄鋼業(291万 、同22.5%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(224万
、同22.5%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(224万 、同17.3%)の順となっており、これら上位3産業で7割以上を占めている。
、同17.3%)の順となっており、これら上位3産業で7割以上を占めている。 - c. 井戸水の用水量が多いのは、化学工業(159万
 、構成比17.7%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(135万
、構成比17.7%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(135万 、同15.0%)、食料品製造業(124万
、同15.0%)、食料品製造業(124万 、同13.9%)、繊維工業(109万
、同13.9%)、繊維工業(109万 、同12.2%)などであり、これら上位4産業で6割近くを占めている。
、同12.2%)などであり、これら上位4産業で6割近くを占めている。 - d. 地表水・伏流水の用水量は、パルプ・紙・紙加工品製造業(473万
 、構成比54.7%)、化学工業(214万
、構成比54.7%)、化学工業(214万 、同24.8%)が群を抜いて多く、この2産業で約8割を占めている。
、同24.8%)が群を抜いて多く、この2産業で約8割を占めている。 - e. 上水道の用水量が多いのは、食料品製造業(45万
 、構成比19.4%)、電気機械器具製造業(38万
、構成比19.4%)、電気機械器具製造業(38万 、同16.5%)、化学工業(20万
、同16.5%)、化学工業(20万 、同8.6%)、輸送用機械器具製造業(17万
、同8.6%)、輸送用機械器具製造業(17万 、同7.3%)、一般機械器具製造業(17万
、同7.3%)、一般機械器具製造業(17万 、同7.1%)などであり、これら上位5産業で6割近くを占めている。
、同7.1%)などであり、これら上位5産業で6割近くを占めている。
第13図 淡水の水源別用水量構成比及び回収水の産業別構成比(従業者30人以上の事業所)
a.淡水の水源別用水量構成比 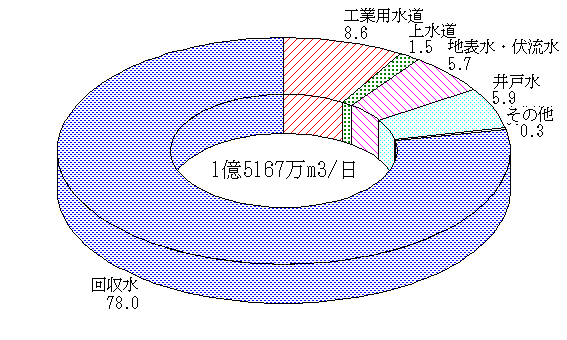 |
 |
b.回収水の産業別構成比 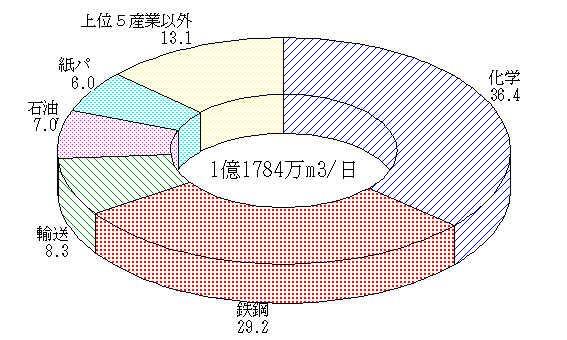 |
第7表 淡水の産業別・水源別用水量(従業者30人以上の事業所)
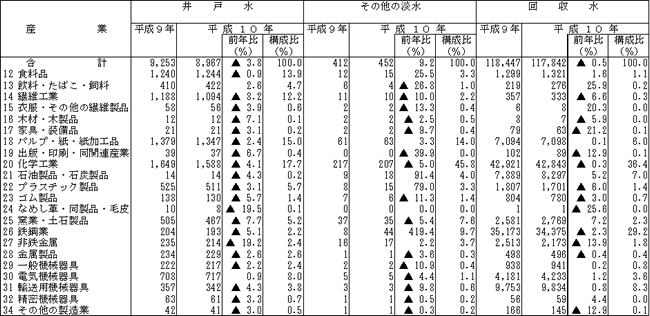
(3) 淡水の用途別用水量
淡水の用途別用水量をみると、冷却用水(1億907万 、構成比72.2%)が7割強を占め、次いで製品処理用水及び洗じょう用水(2558万
、構成比72.2%)が7割強を占め、次いで製品処理用水及び洗じょう用水(2558万 、同16.9%)、温調用水(894万
、同16.9%)、温調用水(894万 、同5.9%)、その他の淡水(519万
、同5.9%)、その他の淡水(519万 、同3.4%)の順となっており、ボイラ用水(187万
、同3.4%)の順となっており、ボイラ用水(187万 、同1.2%)、原料用水(53万
、同1.2%)、原料用水(53万 、同0.3%)はわずかである(第8表、第14図)。
、同0.3%)はわずかである(第8表、第14図)。
前年比でみると、原料用水(前年比▲12.1%減)、ボイラ用水(同▲2.1%減)、温調用水(同▲1.7%減)、冷却用水(同▲0.7%減)、製品処理用水及び洗じょう用水(同▲0.5%減)、その他の淡水(同▲0.4%減)と、すべての用途で減少となっている。
各用途別にみると、
- a. 冷却用水の用水量は、化学工業(4651万
 、構成比42.6%)、鉄鋼業(3323万
、構成比42.6%)、鉄鋼業(3323万 、同30.5%)の2産業が群を抜いて多く、この2産業で用水量の7割以上を占め、次いで石油製品・石炭製品製造業(878万
、同30.5%)の2産業が群を抜いて多く、この2産業で用水量の7割以上を占め、次いで石油製品・石炭製品製造業(878万 、同8.1%)、輸送用機械器具製造業(448万
、同8.1%)、輸送用機械器具製造業(448万 、同4.1%)の順となっている。
、同4.1%)の順となっている。 - b. 製品処理用及び洗じょう用水の用水量は、パルプ・紙・紙加工品製造業(1221万
 、構成比47.7%)が半分近くを占め、次いで輸送用機械器具製造業(363万
、構成比47.7%)が半分近くを占め、次いで輸送用機械器具製造業(363万 、同14.2%)、鉄鋼業(297万
、同14.2%)、鉄鋼業(297万 、同11.6%)、化学工業(191万
、同11.6%)、化学工業(191万 、同7.5%)、食料品製造業(125万
、同7.5%)、食料品製造業(125万 、同4.9%)の順となっている。
、同4.9%)の順となっている。 - c. 温調用水の用水量が多いのは、電気機械器具製造業(227万
 、構成比25.4%)、輸送用機械器具製造業(189万
、構成比25.4%)、輸送用機械器具製造業(189万 、同21.2%)、化学工業(137万
、同21.2%)、化学工業(137万 、同15.3%)である。
、同15.3%)である。 - d. ボイラ用水の用水量が多いのは、化学工業(62万
 、構成比33.3%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(31万
、構成比33.3%)、パルプ・紙・紙加工品製造業(31万 、同16.7%)、石油製品・石炭製品製造業(22万
、同16.7%)、石油製品・石炭製品製造業(22万 、同11.6%)、食料品製造業(18万
、同11.6%)、食料品製造業(18万 、同9.4%)である。
、同9.4%)である。 - e. 原料用水の用水量が多いのは、食料品製造業(18万
 、構成比34.7%)、化学工業(12万
、構成比34.7%)、化学工業(12万 、同23.4%)、飲料・たばこ・飼料製造業(12万
、同23.4%)、飲料・たばこ・飼料製造業(12万 、同23.3%)、窯業・土石製品製造業(9万
、同23.3%)、窯業・土石製品製造業(9万 、同18.0%)であり、この上位4産業で用水量のほとんどを占めている。
、同18.0%)であり、この上位4産業で用水量のほとんどを占めている。
第14図 淡水の用途別用水量構成比及び冷却用水の産業別構成比(従業者30人以上の事業所)
a.淡水の用途別用水量構成比 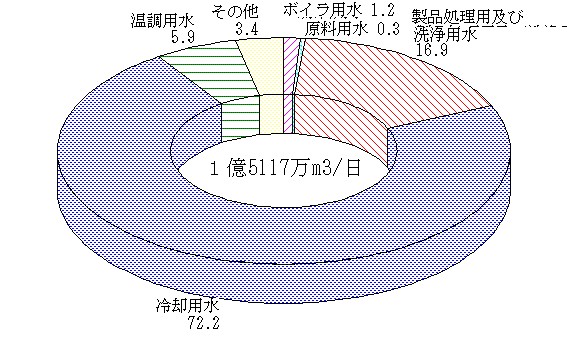 |
 |
b.冷却用水の産業別構成比 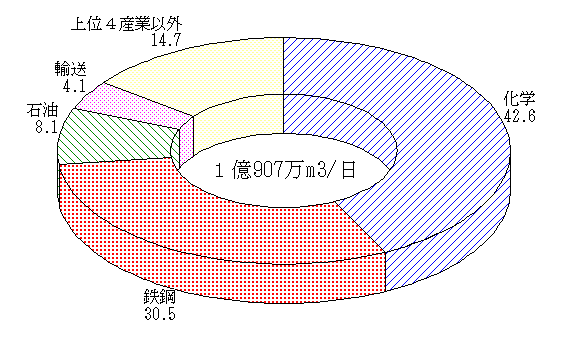 |
第8表 淡水の産業別・用途別用水量(従業者30人以上の事業所)
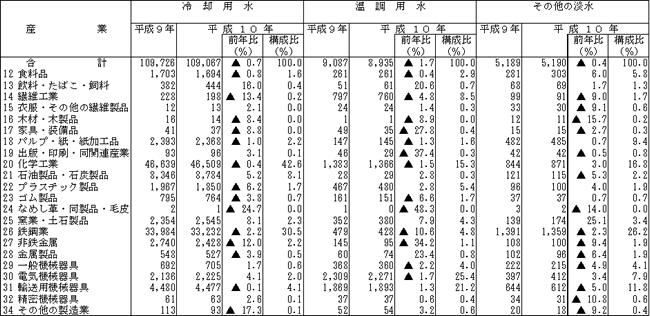
(4) 海水の用途別用水量
海水の用水量は4264万 、前年比▲0.7%の減少であった(第6表)。
、前年比▲0.7%の減少であった(第6表)。
海水の用途別用水量をみると、冷却用水(4090万 、構成比95.9%)がほとんどを占めており、原料用水(124万
、構成比95.9%)がほとんどを占めており、原料用水(124万 、同2.9%)、製品処理用水及び洗じょう用水(35万
、同2.9%)、製品処理用水及び洗じょう用水(35万 、同0.8%)、その他の海水(11万
、同0.8%)、その他の海水(11万 、同0.2%)、温調用水(4万
、同0.2%)、温調用水(4万 、同0.1%)はわずかである。
、同0.1%)はわずかである。
前年比でみると、原料用水(前年比▲5.0%減)、冷却用水(同▲0.6%減)が減少し、その他の淡水(同7.3%増)、温調用水(同6.0%増)、製品処理用水及び洗じょう用水(同2.4%増)が増加となっている。
2.従業者規模別の状況
(1) 用水量合計
従業者規模別にみると、用水量は従業者1000人以上規模(8584万 、構成比44.3%)が半分近くを占め、次いで500~999人規模(3806万
、構成比44.3%)が半分近くを占め、次いで500~999人規模(3806万 、同19.6%)、300~499人規模(2999万
、同19.6%)、300~499人規模(2999万 、同15.5%)の順となっており、従業者300人以上規模で約8割の構成比を占めている(第9表)。
、同15.5%)の順となっており、従業者300人以上規模で約8割の構成比を占めている(第9表)。
前年比でみると、500~999人規模(前年比▲3.8%減)、1000人以上規模(同▲3.6%減)、 200~299人規模(同▲3.5%減)、50~99人規模(同▲1.8%減)が減少となり、300~499人規模(同12.7%増)、30~49人規模 (同5.2%増)、100~199人規模(同2.2%増)が増加となっている。
これを淡水、海水別にみると、500~999人規模、1000人以上規模は淡水、海水とも減少、30~49人 規模、300~499人規模は淡水、海水とも増加となっている。また、50~99人規模は淡水のみが減少、100~199人規模、200~299人規模は 海水のみが減少となっている。
(2) 1事業所当たり用水量
1事業所当たり用水量をみると、従業者規模が大きくなるにつれ用水量も増加している(第9表)。
前年比でみると、500~999人規模(前年比▲1.6%減)、200~299人規模(同▲0.7%減)、 1000人以上規模(同▲0.6%減)が減少、300~499人規模(同13.8%増)、30~49人規模(同7.4%増)、100~199人規模(同 4.9%増)、50~99人規模(同1.3%増)が増加となっている。
第9表 従業者規模別用水量(従業者30人以上の事業所)

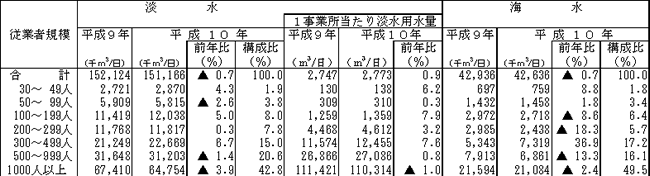
3.都道府県別の状況
都道府県別にみると、用水量が多いのは、千葉(2010万 、構成比10.4%)、愛知(1765万
、構成比10.4%)、愛知(1765万 、同9.1%)、山口(1613万
、同9.1%)、山口(1613万 、同8.3%)、兵庫(1371万
、同8.3%)、兵庫(1371万 、同7.1%)、神奈川(1288万
、同7.1%)、神奈川(1288万 、同6.6%)、岡山(1233万
、同6.6%)、岡山(1233万 、同6.4%)、茨城(1053万
、同6.4%)、茨城(1053万 、同5.4%)などの太平洋ベルト地帯である(第10表、第15図)。
、同5.4%)などの太平洋ベルト地帯である(第10表、第15図)。
第15図 都道府県別用水量の分布(従業者30人以上の事業所)
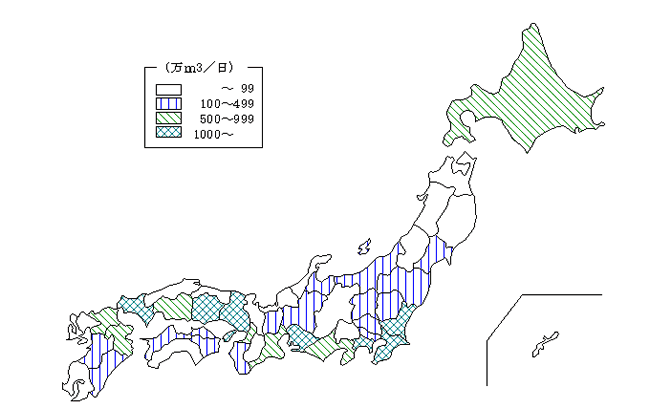
前年比でみると、広島(前年比12.3%増)、静岡(同7.1%増)、志賀(同4.4% 増)、鳥取(同4.0%増)、など16県が増加となり、青森(同0.0%)が横ばいとなったが、長野(同▲15.4%減)、大阪(同▲7.2%減)、山梨 (同▲7.0%減)、茨城(同▲4.4%減)、福岡(同▲4.2%減)、宮崎(同▲4.0%減)など30県が減少となっている(第10表、第16図)。
第16図 都道府県別用水量の前年比(従業者30人以上の事業所)
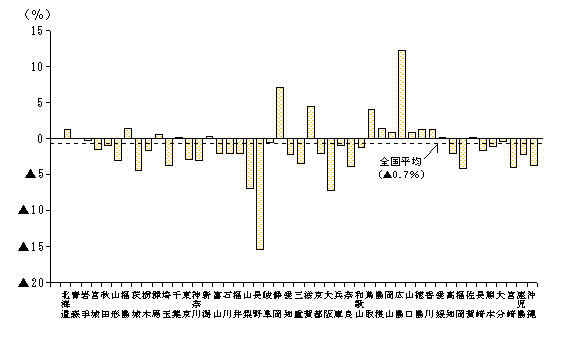
第10表 都道府県別用水量(従業者30人以上の事業所)