CONTENTS
1.諸外国における貿易救済措置の発動状況
2.各国の貿易政策の状況
①EUが中国産バイオディーゼルにかかるAD調査を開始
②米国がカナダ、中国をはじめ複数国からの錫製品の輸入に関するAD/CVD調査の結果を発表
③韓国が日本製ステンレス厚板に対するAD措置の終了を決定
④韓国が日本製ステンレス棒鋼に対するAD措置の終了を決定
⑤米国税関が、AD・CVD対象品目の輸入手続における新たな方針を発表 不備が疑われる場合に申告者に通知する
3.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ ~第Ⅶ回 公聴会への対応~
4.セミナーの御案内(日弁連セミナー)
5.相談窓口
6.FAQ
1.諸外国における貿易救済措置の発動状況
2023年12月の諸外国における貿易救済措置の発動状況をお伝えします。実施状況詳細
アンチダンピング(AD)
2023年12月は以下の調査が開始されました。
補助金相殺関税(CVD)
2023年12月は以下の調査が開始されました。
2.各国の貿易政策の状況
①EUが中国産バイオディーゼルにかかるAD調査を開始
2023年12月20日、欧州委員会が中国からEUへ輸入されるバイオディーゼルに対するAD調査の開始を発表しました1。この調査は、同年11月7日に欧州バイオディーゼル委員会より提出された申請書に基づくもので、同委員会が同申請書と共に提出した証拠から、欧州委員会は、調査対象産品の輸入によりEUの産業に実質的な悪影響がもたらされたと判断しました2。
1.https://policy.trade.ec.europa.eu/news/european-commission-examine-allegations-unfairly-traded-biodiesel-china-2023-12-20_en
2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301574
②米国がカナダ、中国をはじめ複数国からの錫製品の輸入に関するAD/CVD調査の結果を発表
米国商務省は、カナダ、中国をはじめ複数国からの錫製品の輸入に関し、AD調査を実施(中国からの輸入品についてはCVD調査も実施)していたところ、2024年1月5日、カナダ、中国、ドイツ及び韓国からの輸入品についてダンピングの事実が認められ、中国からの輸入品については補助金を受けていることも認められるとの調査結果を発表しました3。オランダ、台湾、トルコ及び英国から輸入される錫製品についてはダンピングの事実が認められないと発表しています。今回の最終決定は、韓国製錫製品の輸入に関する調査結果を除き、仮決定と同一の結果となりました。今後、米国国際貿易委員会(ITC)が、不公正な輸入品によって国内産業が実質的な損害を受けている又は実質的な損害を受けるおそれがあるかどうかを判断します。商務省とITCの両当局が肯定的な最終決定に達した場合にのみ、貿易救済措置の命令が発せられます。
商務省はオランダ、台湾、トルコ及び英国からの輸入品についてはダンピングの事実が認められないとの結論に達したため、これらの国からの輸入品に対する調査は終了し、AD関税措置は行われないこととなっています。
③韓国が日本製ステンレス厚板に対するAD措置の終了を決定
2023年12月21日、韓国貿易委員会は日本製ステンレス厚板のAD措置に関する第3次サンセット・レビューの結果、調査対象産品の輸入量の減少、同種産品の国内シェア増加、供給者の余剰生産能力の低下等を加味し、損害再発のおそれがないとして、AD措置を終了する決定を下しました4。この措置は、2011年4月に発動され、当初期間は5年間とされていました。しかし、その後、第1次サンセット・レビュー(調査期間(以下同じ)2015年12月~2016年6月)、第2次サンセット・レビュー(2019年7月~2020年3月)を経て2回延長されていたものです。なお、今回の第3次サンセット・レビューに際しては、日本政府としても公聴会での意見陳述や、AD委員会での発言5等の機会に措置の早期終了を要請していました。
4.https://www.ktc.go.kr/viewInvest.do
上記URLより、무역구제(貿易救済)>무역구제조사 진행(貿易救済調査の進行)ページ、「일본산 스테인리스스틸 후판에 대한 덤핑방지관세부과 3차 종료재심사(日本産ステンレススチール厚板のアンチダンピング関税第3次再審査)」に記載されています 5.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/ADP/M64.pdf&Open=True
④韓国が日本産ステンレス棒網に対するAD措置の終了を決定
韓国による日本産ステンレス棒鋼に対するAD措置(2004年7月課税開始)について、2024年1月22日に課税が終了しました。韓国の調査当局は、終了した理由について、AD課税により日本産のステンレス棒鋼は輸入量が減少し、その間自助努力などで国内産業の競争力が回復したと説明しています。この措置は、2004年7月課税開始されて以後、第1次(調査期間(以下同じ)2009年3月~2010年2月)、第2次(2012年10月~2013年10月)、第3次(2016年6月~2017年6月)、第4次(2020年1月~2021年1月)と4度サンセット・レビューを経て課税が延長されていました。しかし、今回国内生産者から第5次サンセット・レビューの要請がなく、2024年1月22日に課税が終了したものです。
なお、日本政府は一貫して本件措置の早期終了を要求しており、上記第3次サンセット・レビュー決定について2018年9月にWTO提訴し、2020年11月に措置の協定不整合を認定したパネル報告書が公表されています6。同パネル報告書は韓国が2021年1月に上訴(上級委機能停止後のいわゆる「空上訴」)したため採択されてはいませんが、日本政府としては、同パネル報告書の判断に沿って措置を終了するようAD委員会等7を通じて韓国に働きかけを行っていました。
6.https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201201003/20201201003.html
7.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/ADP/M64.pdf&Open=True
⑤米国税関が、AD・CVD対象品目の輸入手続における新たな方針を発表 不備が疑われる場合に申告者に通知する
2023年12月14日、米国税関・国境警備局(CBP)は、2024年1月16日から、AD及びCVDの対象品目の輸入手続において、不備が疑われる場合にその旨を申告者に通知する方針を発表しました8。具体的には、対応するAD又はCVD のケース番号に記載漏れがある場合、入力した製造者・輸出者と当該AD・CVDのケース番号にひもづく企業が一致しない場合に通知されることとなっています。この通知は情報提供のみを目的としており、通知を受けた申告者が対応することは義務付けられていませんが、手続上の負担軽減の観点から、修正対応を行うことが奨励されています。
8.https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3800350
3.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ
~第Ⅶ回 公聴会への対応~
Ⅶ.1 公聴会とは
公聴会(public hearing)とは、対面(またはオンライン)により、調査対象企業、輸出国政府、輸入国の生産者(主に申請者)などの利害関係者(AD協定6.11条)や国内ユーザー企業が一堂に会し、口頭で意見を表明したり、調査当局の担当者からの質問に答えたりする手続きのことです。 AD協定で公聴会の開催が義務づけられているわけではありません(日本のAD調査でも、公聴会は原則開催されません)。しかし、同協定6.2条では、要請があったときは、「利害関係を有するすべての者に対し相反する利害を有する者と会合する機会を与える」とされています。公聴会の開催はその代表的なものです。
AD協定6.2条は、利害関係者は「会合に出席する義務を負わない」と明示していますので、公聴会に参加しない選択も可能ですが、一般論として、調査当局の担当者の在席のもと手続が行われ、自らの意見を述べることができるほか、他の利害関係者による発言、及びそれに対する調査当局の質問等から、主要論点や調査当局の問題意識を確認することのできる貴重な機会といえます。
Ⅶ.1.1 公聴会の要請
上記の通り、AD協定6.2条では「(利害関係者からの)要請があった場合」とあり、公聴会開催も利害関係者の要請によるのが原則です。しかし、国によって実務は異なっており、要請がなくても調査当局から公聴会開催の通知が届く場合もあるようです。そのため、公聴会は要請に基づいて開催されるのか、要請が必要であれば、いつまでに要請をおこなう必要があるのか等、その国の調査手続や調査開始告示等を確認して事前に把握しておくことをお勧めします。
Ⅶ.1.2 公聴会の通知
公聴会が開催される場合、調査当局から公聴会開催に関する通知が届きます。通知は、利害関係者宛てにメールで送付される例が多いと思われます。通常、公聴会の開催日、時間、場所、参加方法(事前登録の要否等)などが記載されます。 なお、公聴会は従来対面開催・対面参加が当たり前でしたが、近年はコロナ禍への対応を契機にオンライン、ないしハイブリッドでの開催の例も見られるようになりました。オンライン参加は、現地への出張が不要になる等メリットもありますが、接続トラブル等で意見表明が妨げられるリスクもあり、その場合の対応について実務が確立しているわけではありません。
公聴会の通知の方法・送付時期についても、各調査当局や案件によりばらつきがあります。数週間前のメール通知と当局ウェブサイトでの告知を併用する周到な実務も見られる一方で、開催1週間前に突然通知が来たなどという極端な例もあります。実質的に参加が困難なほどに通知が遅い場合は、AD協定6.2条が規定するような「会合する機会を与え」たことにならないようにも思われます。しかし、過去のWTO紛争解決手続では、AD協定6.2条は通知の時期・方法について言及がないこと、公聴会をいつどのように開催するかについて調査当局の裁量をある程度尊重すべきであること、等から、同6.2条上の調査当局の義務は限定的に解釈されることが多いようです。そのため、通知の遅れや不備について、事後的にAD協定違反を指摘することは簡単ではありません。公聴会への出席を検討している場合は、調査当局に事前に開催予定・時期を確認しておく、という現実的な対応にならざるを得ないでしょう。
Ⅶ.1.3 公聴会当日の対応
公聴会の実施方法は各国の実務により様々です。公聴会の使用言語(現地公用語がほとんど)、事前登録・提出書類の有無、その他進行方法や注意事項については、調査当局からの通知等に記載がされている場合が多いので、よく確認することをお勧めします。進行方法として、AD調査の申請者(国内生産者)と調査対象企業それぞれに発言の機会が与えられる、という点は各国ほぼ共通しています。これに加え、調査当局から現場で質問がされる場合もあります。 なお、公聴会で表明した意見は、後日書面によって利害関係者が閲覧できるようにする必要があります(AD協定6.3条)。よく見られる実務は、現場では事前に用意した意見書を読み上げ、これを事後に調査当局に提出するというものです。加えて、現場での口頭発言(当局の質問への対応や、他の参加者の発言への反論)についても、後で書面にして提出することを求められる場合もあるので、準備をしておくことをお勧めします。
Ⅶ.1.4 秘密情報の扱い
意見陳述の内容には特段の制限はありません。法律上の問題点(ダンピング・マージンの計算、損害論、調査手続の瑕疵等)を提起することもできますし、AD措置の悪影響(自社ビジネスへの影響のほか、後述のユーザー企業の不都合、輸入国自身への悪影響等)を述べることもできます。しかし、これらの事情には、自社の価格情報や、取引先との関係、経営戦略等、本来対外秘であるべき情報も含まれ得ます。他方、上述の通り、公聴会は「利害関係を有するすべての者」が参加しますし、陳述内容は後に書面として他の利害関係者が入手できる状態になります。このような秘密情報についてはどのように考えるべきでしょうか。 この点、まず、文書については、「正当な理由が示される場合には、当局により秘密として取り扱われ」、「当事者の明示的な同意を得ないで開示してはならない」(AD協定6.5条)との規律があります。よって、企業がその意見書において秘密情報に触れる場合には、その部分をカギ括弧(【】)等で明示し、その部分について別途要約(例えば、「価格情報」「今後の経営戦略に触れた部分」等)を付し(AD協定6.5.1条)、秘密取扱いを求めます。調査当局は、その文書を開示する場合、当該部分を黒塗りするか、削除した上で開示する(その部分については、「価格情報」等企業が付した要約だけが開示される)ことになります。
他方、公聴会での口頭発言については、判断が難しい場合もあります。できるだけ具体的な情報を織り込んだ方が意見の説得力は増すでしょうが、競合他社を含めた不特定多数の前での発言を「黒塗り」することはできません。この点、AD協定6.2条では、公聴会開催において「秘密保持の必要性」を考慮しなければならないとされていますが、具体的な方策は規定されていません。国によっては、参加者を限定した非公開セッションの開催を要請できる例もありますが、あくまで一部です。結局のところ、個々の情報についての保秘の必要性の程度(価格情報などは基本的に言及すべきでない。)、調査当局の秘密取扱いの実務(非公開セッション要請の可否等)、等を考慮した上で対応を決定するほかないでしょう。
Ⅶ.2 政府の支援(政府意見書、公聴会への大使館職員の出席)
輸出国政府は、利害関係者でもあり(AD協定6.11条)、調査当局に対して意見を提出することができます。政府意見書の提出する時期は特段限定されていませんが、公聴会の時期とあわせて提出するのが一般的です。この場合、公聴会に現地の日本大使館職員が出席(AD協定6.2条)してあらかじめ用意された意見書を読み上げ、当該意見書を事後に提出(AD協定6.3条)する、という流れになります。政府意見書の場合は、その性質上、AD措置の個々の企業への影響よりも、WTO協定との整合性に関する法律上の問題点が主軸となることが多いです。政府意見書の内容は、事案ごとに異なるため、調査開始段階から早めに懸念点をご相談ください。事案ごとに採否は異なりますが、指摘しうる論点について、留意点を下記に記します。
Ⅶ.2.1 ダンピング・マージンの計算
実務上争いになることが多く、また企業の負担も大きい論点ですが、性質上個々の企業の価格情報に関係することが多いため、政府意見書で言及する例は実は多くはありません。下記、調査手続の論点(ファクツ・アヴェイラブルやサンプリング調査)において間接的に言及される程度です。
Ⅶ.2.2 損害・因果関係
対象輸入の量・価格や、国内経済指標(国内産品と対象輸入品との競合の程度、国内産品の生産量、売上、市場シェア等)など、一般的な情報をもとに意見陳述ができる(対象輸入による損害を安易に認定しないよう注意喚起する)ため、政府意見でしばしば言及されます。 特に、日本製品の価格帯が国内産品よりも大幅に高い、品質・機能に違いがあって直接に競合していない等の事情は、日本製品を対象とするAD調査においてよく争われる点です。対象製品をよく知る企業において、早い段階で政府に問題提起することで、政府意見への反映もスムーズになります。
Ⅶ.2.3 調査手続
調査当局の調査における対応の問題点(手続面や、調査手法)への疑義もしばしば指摘されます。 例えば、合理的な期間内に質問状に回答したにもかかわらず、合理的な理由なく回答が拒否されファクツ・アベイラブルを適用された場合、AD協定6.1.1条やAD協定6.8条に抵触する可能性があります。
また、サンプリング調査(AD協定6.10条)に関する問題も考えられます。ダンピング・マージンは個々の企業ごとに認定するのが原則ですが、輸出企業が多数いて、すべての企業を調査することが難しい場合には、一部の企業のみを選定(サンプリング)して計算することが認められています。ただ、あくまで例外的な調査手法であって、輸出企業が少数にもかかわらずサンプリング調査が実施され、個別のダンピング・マージンが計算されなかったり、あるいは、任意で情報を提出した上で個別マージン計算を要求(AD協定6.10.2条)したのに対応されなかったりする場合など、政府としてもWTO協定上の懸念があるとして意見を述べることが可能です。
Ⅶ.3ユーザー企業の参加とその重要性
調査対象製品のユーザー企業は、厳密には「利害関係者」の定義(AD協定6.11条)に含まれるかケースバイケースです(当該製品の「輸入者」(6.11条(i))に当たる可能性もあるが、末端ユーザーは含まれない。)。しかし、公聴会が開催される場合、輸入国国内における重要なステークホールダーとして、ユーザー企業の参加が許されることは実務上よく見られます。ユーザー企業の意見は、下記の2つの点で重要といえます。1点目は、損害・因果関係に関する日本企業の議論のサポートです。上述の通り、日本からの輸出品が輸入国の産品と比較して高価格・高品質であるなど、両者の競合関係に疑問がある事例はよく見られます。日本製品を輸入国内で使用するユーザー企業にもその旨主張してもらうことができれば、損害・因果関係に関する日本企業の議論に対する補強となります。前々回(Ⅴ.2.2)にも説明したとおり、日本からの対象産品を使用している需要者は、AD税が課されると今より高い価格で、商品を入手しなければならなくなります。日本製品が他国産の産品と比べ高品質であるなど需要者から見て代替不可能な場合は、この点を公聴会で主張してもらうことが有用でしょう。
2点目は、AD課税で日本産品の輸入が減ることにより、輸入国の需要を満たせなくなり、輸入国にとっての公共の利益に反する、という可能性です。「公共の利益(public interest)」に関しては、AD協定上の課税要件ではありませんが、各国国内法において注意的に規定されていることもあり、また、調査において考慮する当局も見られます。一般論として、輸入国の経済状況について意見陳述するのは輸入国内の業者が適していることから、この点をユーザー企業に指摘してもらい、間接的に日本製品へのAD課税の不当性を訴えることは有用でしょう。
公聴会に参加してくれる国内ユーザー企業の確保や、意見のすりあわせには時間を要しますので、調査の早い段階から検討することをお勧めします。
【今回のポイント】
○公聴会は、調査当局の担当者や、申請者等他の利害関係者がいる場で意見表明や反論を行うことができる機会。
○公聴会には輸出国政府も利害関係者として出席することができ、WTO協定違反の懸念があれば対面で意見表明できる。
企業として懸念点があれば、早めに相談を。
○ユーザー企業が意見表明できる場は多くはなく、公聴会はこの意味でも貴重。早い時期から協力してくれるユーザー企業を探すべき。
4.セミナーの御案内(日弁連セミナー)
経済産業省では、当省の国際通商法関連業務への理解を広げるため、日本弁護士連合会のご協力を得て、「日本をとりまく国際通商情勢と法曹の役割」と題するセミナーを開催します(2024年2月15日(木)18時~20時)。本セミナーでは、今般の通商政策(炭素国境調整措置や、通商ルールと安全保障を巡る議論等)のほか、アンチダンピング(AD)措置をはじめとする貿易救済措置への対応にも言及する予定です。オンライン開催・参加費無料にて、下記URLご参照のうえ、お気軽にご登録・ご参加いただければ幸いです。 日本弁護士連合会HP:https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240215.html
5.相談窓口
経済産業省では、皆様からのアンチダンピング調査に関する個別相談を常時承っております。アンチダンピング措置は、海外からの不要な安値輸出を是正するためWTOルールにおいて認められた制度です。公平な国際競争環境が担保された中で、日本企業の皆様が事業活動を展開できるようにするためにも、アンチダンピングを事業戦略の一つとして捉えていただき、積極的に御活用いただきたいと考えております。申請に向けた検討をどのように進めればよいのか、複数の事業者による共同申請はどのようにすればよいのかなど、相談したい事項がございましたら、まずは気兼ねなく経済産業省特殊関税等調査室まで御連絡ください。
また、2023年7月から「ADの調査対象となった場合の対応」の連載を開始しておりますが、「日本企業がアンチダンピング調査の調査対象となった場合」の御相談は、経済産業省 国際経済紛争対策室まで御連絡ください。
経済産業省 貿易経済協力局 特殊関税等調査室
TEL:03-3501-1511(内線3256)
E-mail:bzl-qqfcbk@meti.go.jp
経済産業省 通商政策局 通商機構部 国際経済紛争対策室
TEL:03-3501-1511(内線 3056)
E-mail:bzl-wto-soudan@meti.go.jp
6.FAQ
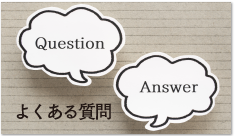
最終更新日:2025年3月26日