CONTENTS
1.諸外国における貿易救済措置の発動状況
2.各国の貿易政策の状況
①EUが貿易救済措置に関する2022年の年次報告書を公表
②EUが中国産EVに対するCVD調査を開始
3.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ~第Ⅳ回 調査開始前について~
4.相談窓口
5.FAQ
1.諸外国における貿易救済措置の発動状況
2023年9月の諸外国における貿易救済措置の発動状況をお伝えします。実施状況詳細
アンチダンピング(AD)
2023年9月は以下の調査が開始されました。
アンチダンピング(AD)
 補助金相殺関税(CVD)
補助金相殺関税(CVD)
2023年9月は以下の調査が開始されました。
2.各国の貿易政策の状況
①EUが貿易救済措置に関する2022年の年次報告書を公表
欧州委員会はEUにおける貿易救済措置の2022年版年次報告書を公表しました。1報告書の中では2022年末までに177件の貿易救済措置の発動が報告されており、そのうちアンチダンピング(AD)措置は151件、補助金相殺関税(CVD)措置は25件、セーフガード(SG)措置は1件でした。貿易救済措置が発動された177 件のうち38件は、迂回に対する調査の結果によるものでした。これらの措置を通じてEUにおける約49万4千人以上の雇用が保護されていると分析されています。
2022年に新規に開始された調査は5件で、2021年の14件と比較すると減少しています。この結果は、2022年にEU産業から寄せられた調査開始の要請数が前年度より少なかったことを反映しています。要請数減少の原因として、運輸コストの高さに起因した輸入量の減少(2021年比)や、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)後の回復による高い利益により、産業界が被った損害が少なかったことが影響しているとの推察が行われています。
EUが発動する貿易救済措置の中で最も多い地域は、中国、ロシア、インド、韓国、米国からの輸入に関するものです。EUからの輸出に対する貿易救済手段が発動される地域は、米国が38件と最多で、次いで中国とトルコがそれぞれ18件、次にブラジルが11件、カナダとインドネシアが9件と続いています。
1.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4348
②EUが中国産EVに対するCVD調査を開始
2023年10月4日、欧州委員会は「補助金に対する保護に関する2016年6月8日付欧州議会及び理事会の規則(EU)2016/1037」(基本規則)2の第10条(8)に基づいて、中国からのバッテリー式電気自動車(BEV)の輸入に対する補助金相殺関税(CVD)調査を正式に開始しました。3,4調査ではまず、①中国を原産とする調査対象製品が補助金から利益を受けているかどうか、②この補助金を受けての輸入が域内産業に経済的損害を与えているか(または与えるおそれがあるか)を判断します。①及び②の両方に該当すると判断された場合、CVD措置の発動がEU内の輸入業者、使用者、消費者に与える結果と影響を調査することになります。調査結果に基づき、補助金相殺関税を課すことがEUの利益となるか判断する予定です。
欧州委員会は、中国からの低価格なBEVの輸入台数の急増がEUの電気自動車産業に経済的脅威をもたらしているという十分な証拠を収集した上で、職権により今回の調査を開始したと発表しています。
通常、調査を開始する通知の公示から12か月(最長で13か月)以内に完了します。また、基本規則の第12条第1項に従い、調査を開始する通知の公示から9か月以内に暫定措置を課すことができることとされています。
2.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1037
3.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4752
4.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202300160
3.「ADの調査対象となった場合の対応」シリーズ
~第Ⅳ回 調査開始前について~
今回から、調査段階ごとに、調査対象企業が行うべき情報収集や反論、タイミング、留意点をご説明していきます。今回は、調査開始前の段階で出来ることについてです。 Ⅳ.1 AD調査の開始
通常、AD調査は、輸入国の民間事業者の申請によって開始されます(申請による調査開始、AD協定5.1条)。申請者は、対象輸入品と競合する製品を国内で生産する企業であることがほとんどです。事案によっては、複数社で共同申請することもあり、対象製品の業界団体が申請者になることもあります。他方、AD協定では、国内事業者からの申請がなくても、調査当局の職権によりAD調査を開始することも認めています(職権による調査開始、AD協定5.6条)。
AD調査全体の件数が比較的多い米国でも 、申請による場合の件数の方が多いですが、多くの国では、申請・職権いずれによっても調査が開始できるよう国内法を制定しています。なお、職権による場合、形式上は民間事業者の意向と無関係に開始されるわけですが、実際は国内産業界の苦境を反映した調査開始となることがほとんどです。そして、職権による場合も、申請による場合と同様の十分な証拠の確認が求められており(AD協定5.6条、5.2条準用)、調査方法に本質的な違いがあるわけではありません。
Ⅳ.2 調査内容を知ることのできるタイミング
AD調査対応は時間との勝負です。よって、AD調査が今後開始され得る旨の、又はAD調査開始決定された旨の情報等をできるだけ早く掴むことが、AD調査対応の基本です。では、具体的にどのようなタイミングが考えられるでしょうか。可能性のあるタイミングを、早い順に並べると以下のようになります。Ⅳ.2.1 日本政府のサポート
申請にせよ、職権にせよ、AD調査開始の背景には、輸入品に押された輸入国の国内産業の苦境があることがほとんどです。「国内事業者の○○社がAD申請を準備している」「輸入国の調査当局が輸入の増加を問題視している」等が現地の業界紙で報道されたり、産業界のコミュニティで事前に噂が流れたりすることがあります。もちろん、情報の真偽には気をつける必要がありますが、このような業界情報が、「対象製品は何か」「課税の場合の影響はどの程度か」「どのように対応すべきか」という初動対応を行う端緒となることがあります。Ⅳ.2.2 調査開始国による申請書受領の通知(AD協定5.5条)
当局は申請書を受領した場合、調査を開始する前に輸出国政府に通知するとされています(AD協定5.5条)。申請書それ自体は公表されないため、申請者の主張・証拠の詳細を知ることはできませんが、確実な情報源の一つです。日本政府からも通知を受け取り次第、関連企業にコンタクトを取り、調査開始の可能性について周知するようにしています。AD協定は、「調査を開始する前に」としか規定していないため、通知のタイミングは必ずしも申請書受領の直後ではないこともあり、国によっては、調査開始の直前になることもあります。
なお、この点、調査対象国・企業への通知はできるだけ早いほうが望ましいとの問題意識から、日本が締結する経済連携協定には、できるだけ早期の通知を担保する規定を置いているものがあります。例えば、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)第6章附属書6-A「手続に関する慣行」では「慣行」の一例として「調査を開始する遅くとも7日前まで」に書面により通報するという記載があります。また、「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定」第7.11条では、同様に、調査開始の7日前までの通知が努力義務とされています。
Ⅳ.2.3 調査開始の公告・通知(AD協定5.1条、12.1条)
調査開始が決定された時点で、調査当局はその事実を公告し、対象国、対象産品、調査開始日、申請書のダンピングの主張の根拠、損害の主張の根拠、意見表明の期限、等が公表されます(AD協定12.1条)。この時点で、調査対象品目や課税申請の根拠が判明し、対象となった企業のAD調査対応も本格化することになります(詳細は第Ⅴ回)。Ⅳ.3 調査開始前の対応
限られた調査期間の中で、AD調査に対して効率的に対応するためには、できるだけ早い時点から、出来る限り多くの情報を入手しておき、早目に戦略を練ることが極めて有効です。例えば、AD調査対象品目に自社製品が含まれているのか、課税の際の商業的影響はどの程度あるのか、そもそもAD調査に対応すべきなのか、AD税を課す要件に関する反論ポイントはないか(第Ⅰ回ご参照)、ユーザーから公聴会などでAD課税に反対する意見表明をしてもらえる可能性があるか(第Ⅶ回でご紹介)等、調査期間に検討すべきことは少なくありません。また、AD調査は各国の国内法に基づき行われ、現地の国内法に精通した弁護士等への依頼が必要になることもあり、こういった時間も加味すると早目の対応が大切になってきます。調査対象産品、申請者、調査対象国、調査対象企業などの情報を早目に収集し、これらの事項を事前に検討できれば、余裕をもって対応することができます。
また情報を入手した段階で、政府にご相談いただくことで、調査開始直後から効果的なタイミングで政府支援を行うことが可能となります。
次回は調査開始後の対応についてご紹介します。
【今回のポイント】
AD調査に関する詳細な情報が得られるのは、基本的には調査開始公告後ですが、入手のタイミングが早いほど調査開始後の初動が効率的・効果的なものとなり、また政府の支援も行いやすくなります。
4.相談窓口
経済産業省では、皆様からのアンチダンピング調査に関する個別相談を常時承っております。アンチダンピング措置は、海外からの不要な安値輸出を是正するためWTOルールにおいて認められた制度です。公平な国際競争環境が担保された中で、日本企業の皆様が事業活動を展開できるようにするためにも、アンチダンピングを事業戦略の一つとして捉えていただき、積極的に御活用いただきたいと考えております。申請に向けた検討をどのように進めればよいのか、複数の事業者による共同申請はどのようにすればよいのかなど、相談したい事項がございましたら、まずは気兼ねなく経済産業省特殊関税等調査室まで御連絡ください。
また、7月から「ADの調査対象となった場合の対応」の連載を開始しておりますが、「日本企業がアンチダンピング調査の調査対象となった場合」の御相談は、経済産業省 国際経済紛争対策室まで御連絡ください。
経済産業省 貿易経済協力局 特殊関税等調査室
TEL:03-3501-1511(内線3256)
E-mail:bzl-qqfcbk@meti.go.jp
経済産業省 通商政策局 通商機構部 国際経済紛争対策室
TEL:03-3501-1511(内線 3056)
E-mail:bzl-wto-soudan@meti.go.jp
5.FAQ
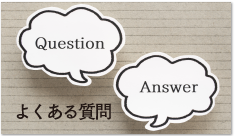
最終更新日:2025年3月26日