 |
 |
 |
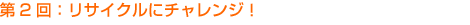 |
東京学芸大学助教授 小林 宏己(こばやし ひろみ)
|
 |
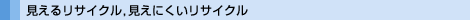 |
 |
一度使ったものをごみとして捨ててしまうのか、それとも新たにものをつくるための資源として再び利用しようとするのか。あなたはふだんどうしていますか。「リサイクル」という言葉は、「再び資源として利用する」という意味です。でも意味を知っているだけではなく、私たち一人ひとりが暮らしの中で実行することが大切なのです。
|
古新聞などの回収はリサイクルの代表的な例です。ダンボールや雑誌、牛乳パックなどを含め、古紙回収率は約70%(平成15年度)となっています。回収された古紙は製紙工場で、ほぐして繊維に戻され、異物やごみ、インキが取り除かれ、さらに漂白されて再生紙となります。現在生産される紙全体に古紙が占める割合(古紙利用率)は約60%(同年度)ですが、工場設備の整備に取り組み、古紙利用を進めています。
|
 |
古紙のほかに缶やペットボトルもリサイクルされます。アルミ缶は地金に、スチール缶は鋼材に再生されて、それぞれ新たな金属製品が作られます。ペットボトルからは卵パックや衣料のフリースなどが作られるほか、ペットボトルに戻す技術もあります。また、プラスチックの容器や包装は、公園のベンチなどになります。
このように製品の原材料として再利用するリサイクルは、再生された品物が私たちの目に見えてわかりやすいのですが、もう一つ私たちには見えにくいリサイクルもあります。それは取りにくい汚れがついていたり、複数の素材で作られていたりして、原材料としての再生が難しいものの場合です。このようなものは焼却する際に発生する熱で発電したり、固形燃料に加工したりして、エネルギー源として利用(回収)するリサイクル(サーマルリサイクル)を行っています。
|
|
 |
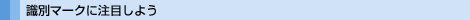 |
 |
こうしてみると、私たちの身の回りにはリサイクル可能なものがたくさんあります。でも実行するときに、気をつけなければならないルールがあります。それは、分別するということです。アルミ缶とスチール缶の区別はつきますか?それではシリアルやクラッカーなどの包装に使われている銀色の内袋はアルミ、それともプラスチックのどちらでしょう?正しく分別しなければリサイクルはできません。
|
| 迷ったときは、識別マークを探してみてください。飲料や酒類の缶、飲料・酒・しょうゆ用のペットボトル、プラスチック・紙の容器包装には識別マークをつけることが法律で定められています。正しい分別、それがリサイクルの第一歩です。 |
 |
|
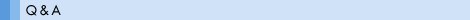 |
 |
| Q |
ペットボトルについている識別マーク 数字の1って何? |
| A |
この数字は、プラスチック廃棄物の効率的な分別を行うため、米国プラスチック産業協会が1989年に制定した原料樹脂の材質を区分するためのコード(SPIコード)です。材質別に1~7までの番号があります。
日本においても、かつて日本プラスチック工業連盟がこれらのコードの使用を推奨していましたが、容器包装リサイクル法の制定後は飲料・酒・しょうゆ用ペットボトルに三角マークの1番を、その他のプラスチック製容器包装にはプラマークを使用するよう統一されています。 |
|
 |
 |
 |
| 飲料・酒・しょうゆ用ペットボトル |
その他のプラスチック製容器包装
プラマーク |
 |
|
 |
なお、プラマークにはプラスチックの種類を表すPEやPPなどの略号を付け加えることが推奨されています。 |
 |
|
| 例:PEの場合 |
|
 |
|
 |
プラスチック材質識別マーク |
|
 |
| 米国SPIコード |
日本のプラマークの材質記号 |
 |
ペット樹脂:ポリエチレンテレフタレート |
|
PET |
 |
高密度ポリエチレン |
|
PE |
 |
塩化ビニル |
|
PVC |
 |
低密度ポリエチレン |
|
PE |
 |
ポリプロピレン |
|
PP |
 |
スチロール樹脂:ポリスチレン |
|
PS |
 |
複合材、その他 |
|
PE, M, PPなど |
|
米国プラスチック産業協会のホームページ(英文)
|
▼▼識別マークについて次のところで調べることができます▼▼ |
1.経済産業省「3R政策」のホームページ
2.(財)日本容器包装リサイクル協会のホームページ
|
 |