|
 |
| 容器包装リサイクル法において、次の事業者はリサイクル(再商品化)義務を負う特定事業者になります。 |
 |
| (1) |
特定容器利用事業者
その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む) |
| (2) |
特定容器製造等事業者
特定容器の製造などの事業を行う事業者(輸入業者を含む) |
| (3) |
特定包装利用事業者
その事業において、その販売する商品に特定包装(包装紙など)を用いる事業者(輸入業者を含む) |
|
 |
| ただし、国、地方公共団体、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人<商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む事業者については、5人>以下の事業者)のうち販売額が一定の額に満たないものはこの法律の適用を除外されます。 |
 |
| ※ |
特定容器とは、容器包装に該当すると判断されるもののうち、商品を入れるためのもの。主務省令で定められています。 |
|
 |
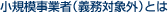
|
 |
| 業種 |
売上高 |
従業員 |
| 製造業等 |
2億4,000万円以下 |
かつ20名以下 |
| 商業、サービス業 |
7,000万円以下 |
かつ5名以下 |
|
|
 |
|
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート |
 |
| |
 |
| 特定事業者は、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人リサイクル事業者に委託してリサイクルします。 |
 |
| |
 |
|
 |
| リサイクル(再商品化)の義務を負う特定事業者が、万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。 |
 |
| |
 |
| 特定事業者は指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)へ委託料を支払うことでも義務を果たせます。 |
 |
| 「いつ、どこへ申し込む?」 |
 |
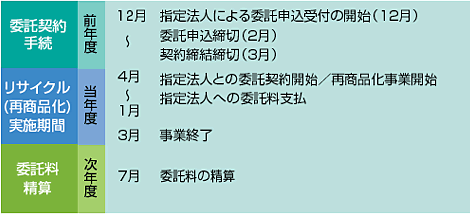 |
 |
| 委託の申込みや委託契約は、全国の「商工会議所」および「商工会」が指定法人を代行して行っています。お近くの商工会議所・商工会へお問い合わせください。 |
 |
| 「委託料はいくら?」 |
 |
| 委託料は前年度に販売した商品に利用(製造等)した特定容器・包装の量をもとに算出しますが、算出が困難な場合もあるため、次の2つの算定方法があります。 |
 |
| <自主算定> 排出見込量が算出できる場合 |
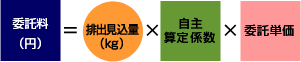 |
 |
| <簡易算定> 排出見込量が算出できない場合 |
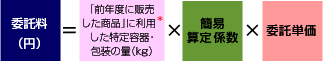 |
 |
| 排出見込量算出方法 |
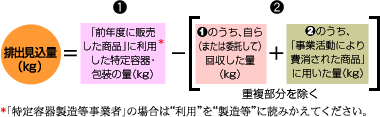 |
|
 |
|
平成24年度 算定係数表 [PDF] |
 |
詳しくは指定法人である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。
HP:https://www.jcpra.or.jp |
 |
|
 |
| 特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器の量などについて記載し、閉鎖後5年間保存することが義務づけられています。帳簿は、再商品化義務量算出のもととなると同時に、義務履行の証明ともなるものです。 |
 |
|
 |
| 容器包装に関する「識別表示」とは、資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミなどの材質を表示することをいいます。「識別マーク」とは、識別表示をするために定められた様式に基づいたマークを意味します。 |
 |
|
 |
| 次の容器には識別表示が義務化されています。 |
 |
・ |
プラスチック製容器包装(飲料・酒類・特定調味料用のPETボトルを除く) |
| ・ |
紙製容器包装(飲料用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器包装を除く) |
| ・ |
PETボトル(飲料・酒類・特定調味料用のPETボトル) |
| ・ |
飲料・酒類用スチール缶 |
| ・ |
飲料・酒類用アルミ缶 |
|
 |
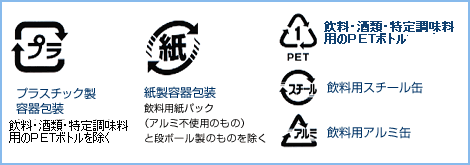 |
 |
|
 |
| 特定事業者が再商品化しなければならない再商品化義務総量は、主務大臣が定める分別収集計画量および再商品化見込み量に基づいて、定められます。 |
 |
| 5か年計画 |
 |
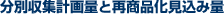 |
 |
| ▼分別収集計画量(単位:千トン) |
 |
 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
| ガラスびん(無色) |
342 |
341 |
339 |
338 |
337 |
| ガラスびん(茶色) |
294 |
293 |
292 |
291 |
290 |
| ガラスびん(その他) |
180 |
180 |
179 |
179 |
179 |
| PETボトル |
301 |
305 |
306 |
307 |
308 |
| 紙製容器包装 |
128 |
130 |
133 |
137 |
139 |
| プラスチック製容器包装 |
785 |
818 |
846 |
857 |
866 |
|
|
 |
| ▼再商品化可能量(単位:千トン) |
 |
 |
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
| ガラスびん(無色) |
160 |
160 |
160 |
160 |
170 |
| ガラスびん(茶色) |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
| ガラスびん(その他) |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
| PETボトル |
419 |
421 |
421 |
421 |
421 |
| 紙製容器包装 |
339 |
339 |
339 |
339 |
339 |
| プラスチック製容器包装 |
1,536 |
1,558 |
1,558 |
1,557 |
1,559 |
|
|
 |
| ▼再商品化義務総量(平成24年度) |
 |
特定分別
基準適合物 |
H24年度の分別収集見込総量(ア) |
H24年度の再商品化可能量(イ) |
(ア)(イ)のうちいずれか少ない量を基礎として算出した量 |
特定事業者責任比率 |
H24年度の再商品化義務総量 |
| 千トン |
千トン |
千トン |
% |
万kg |
ガラスびん
(無色) |
341 |
160 |
160 |
96 |
153,600 |
ガラスびん
(茶色) |
293 |
150 |
150 |
80 |
120,000 |
ガラスびん
(その他の色) |
180 |
160 |
160 |
92 |
147,200 |
| PETボトル |
305 |
421 |
305 |
100 |
305,000 |
| 紙製容器包装 |
130 |
339 |
38(*) |
99 |
37,620 |
プラスチック製
容器包装 |
818 |
1,558 |
818 |
99 |
809,820 |
|
|
| (*): |
分別収集計画量から、環境省が調査した市町村独自処理分(90千トン)を差し引いた量 |
 |
|
|
|
|
|
この調査は標本調査であり、調査票等を送付させていただきました事業所の方のみが対象です。
(対象事業所以外の方は、ご提出いただく必要はありません) |
 |
「容器包装リサイクル法」に基づき平成9年度から、容器を製造している事業者、容器包装を利用している事業者、輸入業者には、容器包装廃棄物の再商品化の義務が生じることとなっています。
各事業者に課せられる再商品化義務量は、国が毎年度公表する「数量」「比率」等に基づき算出されます。
この調査は、容器包装を用いた商品の販売額、容器包装の利用量等を集計、分析して、再商品化義務量を算出するときに必要となる「数量」「比率」等を国が算定するための標本調査で、毎年度実施しています。 |
| |
|
|
|
|
 |
|