

- 政策について

- 政策一覧

- 安全・安心

- 産業保安

- 高圧ガス・コンビナートの安全

- 高圧ガスに関する規制について

- 高圧ガスに関する規制について
高圧ガスに関する規制について
高圧ガスの製造に関する規制
1.第一種製造者(ガス製造能力が一日あたり100m3以上)
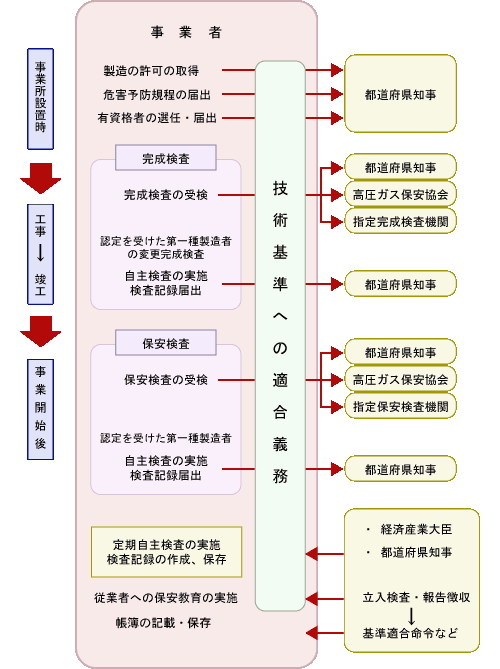
2.第二種製造者(ガス処理能力が一日あたり100m3未満など)
都道府県知事への届出、技術基準への適合義務など
3.その他製造者
技術基準への適合義務など
高圧ガス
そのときの状況により圧縮ガスと液化ガスに分けられ、それぞれ次のようなものをいう。
<状態呼称>
高圧ガスは、そのときの状態で圧縮ガスか液化ガスかに区分されるため、同一種類のガスでも、いずれに該当するかはそのときの状態によって定まる(例:圧縮酸素、液化酸素)。
このことから、高圧ガスは、上記解説中2、3(3)に該当するものを除き、物質の呼び名ではなく、状態の呼び名であるといえる。
なお、高圧ガスの各種ガスの呼称については、原則として、例えばアンモニアガスであれば、気状のものを意味する場合はアンモニアガス、液状のものを意味する場合は液化アンモニア、双方を意味する場合はアンモニアと表現することとしている。
ただし、炭酸ガス、天然ガス又は亜硫酸ガス等については、誤解を避ける意味で、液状のものを意味する場合のみ、例えば液化炭酸ガスと表現し、気状のもの及び液状のものの双方を意味する場合は、炭酸ガスという表現をとることとしている。
また、液化石油ガスについては、気状のもの及び液状のものの双方を意味するものとしている。
-
アセチレンガス以外の圧縮ガス
次のいずれかに該当するガス
(1)常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。)が1MPa以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの
(2)温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス
アセチレンガス
次のいずれかに該当するガス
(1)常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの
(2)温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
液化ガス
次のいずれかに該当するガス
(1)常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの
(2)圧力が0. 2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス
(3) (1)(2)以外の液化ガスであって、温度35 °Cにおいて圧力が0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン
<容器中の液化ガス>
容器に充てんされた液化ガスが高圧ガスかどうかを判断する場合の常用の温度の上限は、40°C(貯蔵時における許容上限値)とされている。
また、気相部にある場合のガスは圧縮ガスとせず、例外的に液化ガスとみなされる。
高圧ガスの製造
新しい物質を造り出すことではなく、一般的に高圧ガスの状態を人為的に生成することを高圧ガスの製造という。
この場合の例として典型的なものをあげると次のようなものがある。
-
気体の圧力を変化させる場合
1.高圧ガスでないガスを高圧ガスにすること
2.高圧ガスを更に圧力を上昇させること
3.高圧ガスを圧力の低い高圧ガスにすること状態を変化させる場合
4.気体を高圧ガスである液化ガスにすること
5.液化ガス(高圧ガスでないものを含む。)を気化させ高圧ガスにすること以上は「高圧ガスの製造」の基本的な操作であるが、実際の操作には次のようなものがあろう。
1.及び2.のケース
イ.圧縮機による圧縮
ロ.ポンプによる液化ガスの圧送
ハ.温度上昇による昇圧
ニ.化学変化による昇圧3.のケース
減圧弁による減圧4.のケース
凝縮器又は熱交換器による液化5.のケース
気化器による気化なお、高圧ガスの製造には、高圧ガスを容器に充てんすることを含むこととされている(法第5条第1項第1号)。
したがって、充てん容器に空の容器を接続して(圧縮機またはポンプを使用しないで)空の容器にガスを移充てんすることは製造となる。
また、製造する者に対する規制は、その規模、態様に応じて規制されており、次の三者に分けられる。・第一種製造者
・第二種製造者
・その製造者(法第13条により規制され、1日の製造量が100 m3(不活性ガス又は空気にあっては300m3)未満であって、 かつ、反復継続しないで製造する者、所定の要件に適合する緩衝装置その他により製造する者及びフルオロカーボン(不活性のものを除く。)又はアンモニアを冷媒とする冷凍機であって 冷凍能力が3トン以上5トン未満の設備又はフルオロカーボン(不活性のものに限る。)を冷媒とする冷凍機であって冷凍能力が5トン以上20トン未満の設備を使用して冷凍のための高圧ガスの製造をする者等が該当する。)
製造設備
高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のために用いられる設備をいい、次のようなものが該当する。
<一般則、液石則及びコンビ則>
ガス設備(ポンプ、圧縮機、塔槽類、熱交換器、配管、継手、附属弁類及びこれらの付属品等)、加熱炉、計測器、電力その他の動力設備、ディスペンサー、転倒台等
<冷凍則>
冷凍設備及びこれに附属する安全装置、計測器、電力設備等
製造設備は使用上の態様により、法令上次のように分類される。
移動式製造設備・・・地盤面に対して移動することができる製造設備
定置式製造設備・・・移動式製造設備以外の製造設備
第一種製造者
次のいずれかに該当するものであって、都道府県知事の許可を受けたものをいう。
1. 圧縮、液化その他の方法により1日に処理することのできるガスの容積(0℃、0Pa(ゲージ圧力)の状態に換算した容積をいう。)が100 m3(不活性ガス及び空気にあっては300m3)以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下2.において同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者を除く。)
2. 1日の処理能力が20トン(フルオロカーボン又はアンモニアを冷媒ガスとする場合は50トン)以上の設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をしようとする者
この場合、1.の設備の処理容積の算定は、設備の公称能力、設計能力等名目的な能力によるものではなく、原料事情、企業操業状況その他設備の外的条件による制約とは無関係に設備自体の実際に稼動しうる1日(24時間)の能力をいう。(実際の設備の稼働時間に関係なく24時間稼動させた場合の能力をいう。)
また、2.の「冷凍」とは、冷蔵、製氷その他の凍結、冷却、冷房又はこれらの設備を使用してする暖房加熱を意味するが、冷凍以外の高圧ガスの製造(1.の場合)に用いられる冷凍(高圧ガス貯槽の冷却等)は含まれない。
なお、第一種製造者の許可は事業所ごとであるが、法人の場合、法人全体が第一種製造者となる。
第一種製造者は、完成検査及び保安検査の受検、危害予防規程の届出、従業者に対する保安教育の実施、保安統括者等の選任、定期自主検査の実施等種々の義務付けがある。
なお、「第一種製造者」という用語は法第9条で定義されている。
第二種製造者
高圧ガスの製造をする者であって、第一種製造者以外の者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
1.高圧ガスの製造を行う者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下2.において同じ。)のため高圧ガスの製造をする者を除く。)(3.の認定指定設備を併せて使用する場合を含む。)
2.1日の処理能力が3トン(フルオロカーボン(不活性のものを除く。)又はアンモニアを冷媒とする場合は5トン、フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を冷媒とする場合は20トン)以上の設備を使用して冷凍のためガスを圧縮し、 又は液化して高圧ガスの製造をするもの(3.の認定指定設備を併せて使用する場合を含む。)
3. 認定指定設備を使用して製造を行う者
この場合(1)の「製造の事業を行う者」とは、製造を継続、かつ反復しておこなう者であって、例えば、いわゆる「流込み充てん」により充てん容器から空容器に詰替えを業とする者、1日の処理容積が100m3(不活性ガス及び空気にあっては300m3)未満の設備を使用する製造業者等が第二種製造業者に該当する。
なお、「第二種製造者」という用語は法第10条の2で定義されている。
また、製造を1回限り(反復継続して行わないもの)、かつ、1日の処理容積を100m3(不活性ガス及び空気にあっては300m3)未満の設備でする場合は、「その他の者の製造」として法第13条の規制を受ける。
お問合せ先
お問合わせはこちらのメールフォームからご連絡ください。
※できる限りフォームをご利用ください。

