

- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2018

- 白書2018(HTML版)

- 第1部 第1章 第1節 世界経済の動向
第1章 足下の世界経済及び日本の対外貿易投資の動向
第1節 世界経済の動向
1.世界GDPの動向
国際通貨基金(IMF)によれば、2017年の世界の実質GDP成長率(以下、成長率)は、世界貿易の回復が大きく寄与し2011年以来最も高い3.8%となった。先進国の成長率は2.3%(2016年:1.7%)、新興国・途上国の成長率も4.8%(2016年:4.4%)と、どちらも加速している(第Ⅰ-1-1-1図)。先進国においては、2008年の世界金融危機以降、投資が低調な状況が続き、特に2016年はその落ち込みが顕著であったが、2017年は固定資本形成及び在庫が大きく伸び、成長を加速させた。新興国及び途上国においては、個人消費の寄与度が高い。一方で、新興国・途上国も地域によって、成長の要因は様々であり、例えば中国やインドにおいては、純輸出や個人消費の伸びが成長を支えた反面、投資活動は減速している。
第Ⅰ-1-1-1図 世界のGDP成長率推移
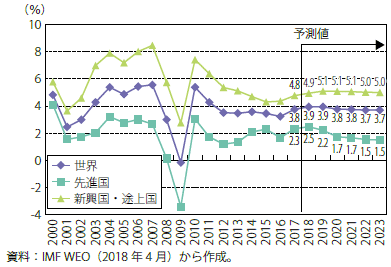
世界の成長率は今年さらに加速して3.9%となる見通しであり、中期的には3.7%程度に落ち着くと推計されている。先進国の今年の成長率は昨年よりもさらに加速して2.5%となる見通しであるが、中期的には1.5%まで減速する見込みである。日本や欧州圏の経済が引き続き好調となる見通しであることに加え、米国の拡張的な財政政策や税制改革の影響が、短期的には先進国のGDPの押し上げ要因となると考えられる。中期的な成長ペースが緩やかになる背景には、米国の税制改革が時限措置であることなどが織り込まれている。新興国・途上国の今年の成長率は4.9%の見通しであり、中期的にも5.0%と高い成長率を維持する見込みである。最近のコモディティ価格の上昇を背景に、金属や原油輸出国等の成長が緩やかに回復することに加え、中国の成長ペースが着実に鈍化しているとはいえ、引き続き新興国・途上国の平均を上回る水準で推移することが見込まれることなどが背景にある。
第Ⅰ-1-1-2表 GDP成長率(地域別)
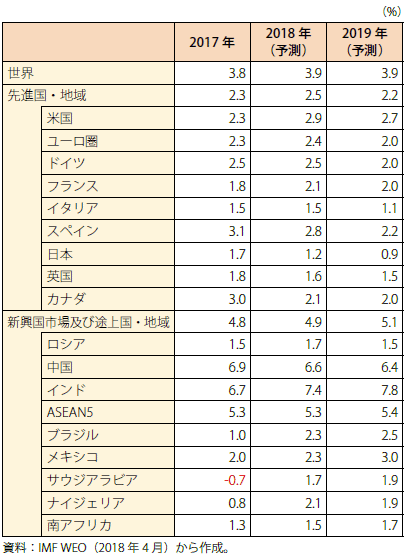
IMFは今後の世界経済のリスクについて、世界経済が想定を上回るペースで成長するサプライズが起きる可能性を指摘する一方、米国の鉄鋼・アルミニウムに対する追加関税の賦課やそれに対する中国の応酬など、世界経済の結びつきが阻害され、各国が内向き志向な政策に傾くことによる貿易・投資活動へのマイナスの影響を懸念している。
2.財貿易の動向
世界貿易機関(WTO)1によれば、歴史的には、世界の財貿易の伸びは実質GDP成長率をおよそ1.5倍上回るペースで拡大してきた。世界の財貿易の伸びを実質GDP成長率で割った比率は、1990年台には2.0を超える水準に達したが、2008年の世界金融危機後にその比率は低下し、2011年から2016年にかけて1以下の水準に低迷する「スロートレード」と言われる状況が続いてきた。2017年はこの比率が1.5まで回復し、2018年も財貿易の伸びが実質GDP成長率を上回る見通しである(第Ⅰ-1-1-3図)。
第Ⅰ-1-1-3図 世界の貿易量伸び率と実質GDPの伸び率の比較
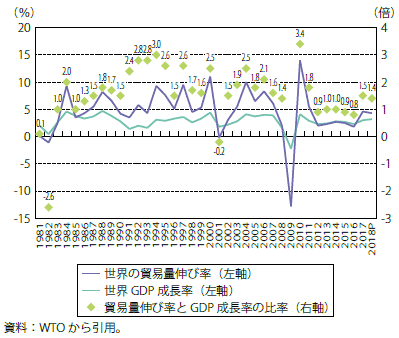
2017年の世界の財貿易量の対前年伸び率は4.7%(2016年:1.8%)となった。2017年の世界貿易の高成長の主な要因は、米国、日本、英国などの先進国における投資の拡大、コモディティ価格の上昇を通じた資源国の所得拡大や米国のシェール・オイルなどのエネルギー部門への投資の拡大などが挙げられる。地域別では、特にアジアの伸びが目覚ましく、2017年の世界全体の輸出量の伸びの51%、輸入量の伸びの60%はアジアの貿易量によって説明できる(第Ⅰ-1-1-4表)。
第Ⅰ-1-1-4表 世界の財の貿易量伸び率
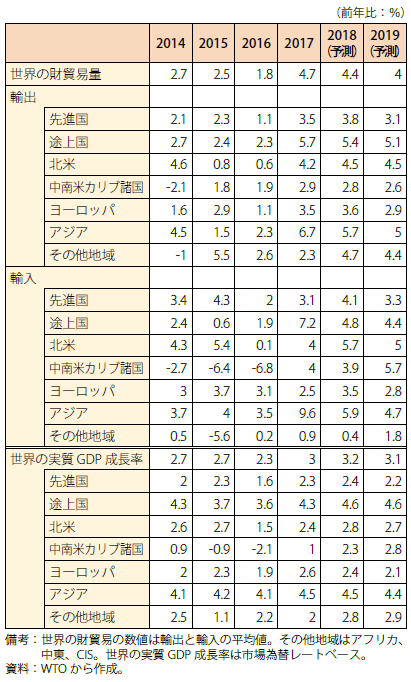
今後の貿易動向について、WTOは世界的なアンチ・トレードの傾向や各国政府による貿易制限的な措置の増加を成長の押し下げ要因として懸念している。また、一部の国において予期せぬインフレが進み、政府が金融引締めに入ることによって、景気が減速する可能性も指摘している。米国や欧州においては、既に金融政策の正常化に向けた動きが進んでおり、これらが貿易に与える影響を注視していくとしている。
1 WTO Press Release, 12 April 2018, (https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm![]() )
)
3.サービス貿易の動向
国連貿易開発会議(UNCTAD)及びWTO2によれば、2017年の世界のサービス貿易額(輸出額ベース)は、前年比7.4%増の5兆2,520億ドルであった。2015年(▲5%)、2016年(0.7%)と伸び率が低い状況が続いていたため、3年ぶりの大幅改善となった。項目別では、特に輸送サービスの伸びが好調であり、サービス貿易全体の伸び率を上回る8%を記録した。最も伸び率の低かった財関連サービスについても、5%という高水準だった。
サービス貿易が財(商品)も含めた貿易全体に占めるシェアは2011年を底に拡大し、2016年には過去最高の23.5%に到達した。2017年は財貿易の拡大がサービス貿易の伸びを上回ったため、23.1%と僅かに減少しているものの、引き続き高水準を維持している3(第Ⅰ-1-1-5図)。2012年から2016年のサービス貿易額は財貿易を上回る伸びで拡大しており(第Ⅰ-1-1-6図)、今後も通信や輸送コストの縮小、技術向上、取引形態の多様化などにより遠距離サービスの提供が容易になることによって、益々その重要性を増していくことが見込まれる。
第Ⅰ-1-1-5図 サービス貿易の貿易全体に占める割合推移
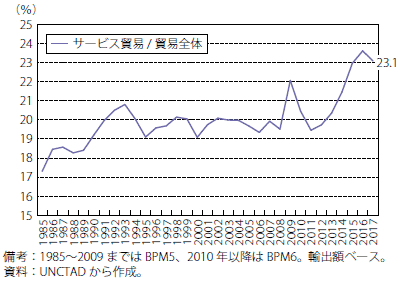
第Ⅰ-1-1-6図 財貿易とサービス貿易の前年比伸び率
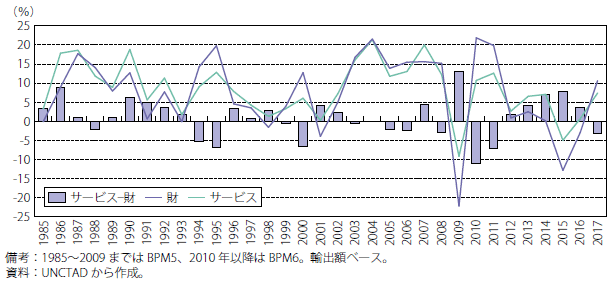
第Ⅰ-1-1-7表 地域別サービス貿易額と対前年変化率
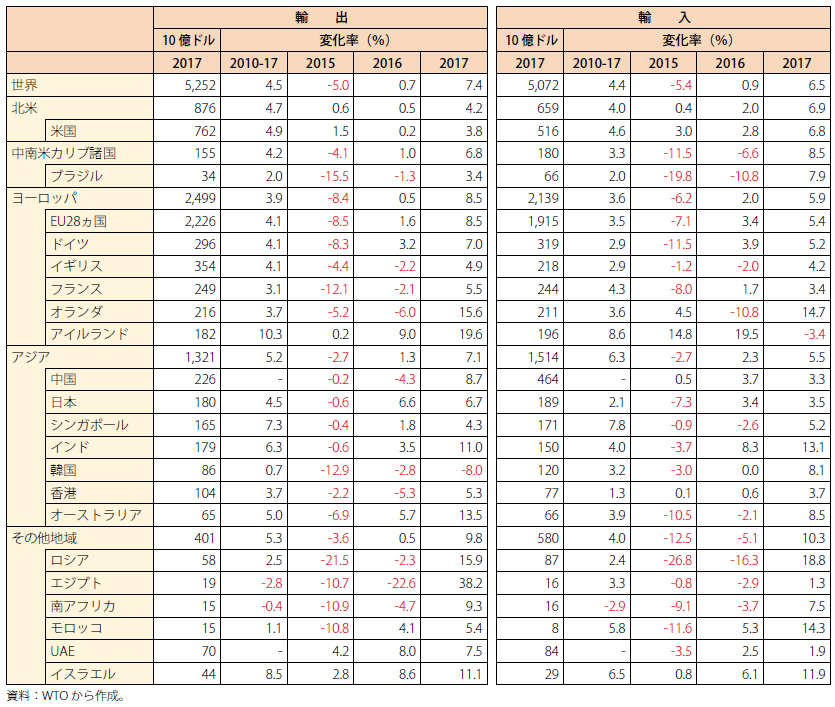
2 脚注1と同様。
3 サービス貿易額の基となる国際収支統計では、サービス貿易の四つのモード(1:越境取引、2:国外消費、3:商業拠点、4:自然人の移動)のうち、モード1の一部のみしか記録できていないため、実際のサービス貿易額は国際収支統計以上の規模があるものと推測される。
4.外国直接投資の動向
UNCTADによると、2016年の世界の対内直接投資(国際収支ベース、ネット、フロー)は前年比1.6%減の1兆7,464億ドルとなり、大幅に増加した2015年から横ばいとなった。途上国向けや一部の欧州諸国に対する投資が低調であった一方、中米や中部アフリカ、中央アジア、東南アジア、欧州の北西部においてはGDPに対して5%以上の投資があったことが指摘されている。対外投資の最大の受け手は米国であり、4,000億ドル近い金額が投資されている4。地域別の推移をみると、欧州への投資の割合が2000年と比較して大幅に減少(2000年:52.4%、2016年33.2%)しているのに対し、アジア(2000年:11.8%、2016年:27.9%)、アフリカ(2000年:0.8%、2016年:3.4%)への投資の割合は大幅に増加した。米州への投資の割合は3割で横ばいに推移している(第Ⅰ-1-1-8図)。
第Ⅰ-1-1-8図 対内直接投資額の推移(フロー)
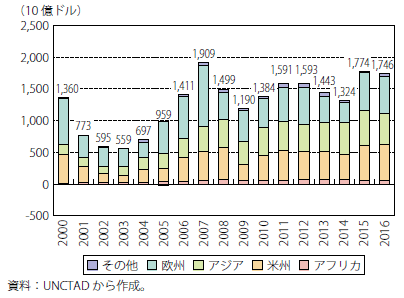
トムソン・ロイターのデータによると、2017年に公表された世界のクロスボーダーM&A総額は前年比▲2.0%の1兆4,714億ドルとなり、前年からほぼ横ばいとなった。件数ベースでもほぼ横ばいの14,431件となった(第Ⅰ-1-1-9図)。同総額は世界金融危機発生後の2009年を底にしばらく伸び悩む状況が続いていたが、2014年頃から回復傾向にある。2017年のデータを地域別に分解すると、米国企業による買収が金額ベースで前年度比5割増加しているほか、フランス(同+136%)、スイス(同+36%)などの欧州諸国、ASEAN(同+3.9%)などによる買収も増加している。次に、被買収側からみると、EUに対する買収が5割増え、オーストラリア(+133%)、東アジア(同+59%)、インド(同+87%)、メキシコ(同+37%)に対する買収金額も大幅に増加している(第Ⅰ-1-1-10表)。
第Ⅰ-1-1-9図 世界のクロスボーダーM&A件数と総額の推移
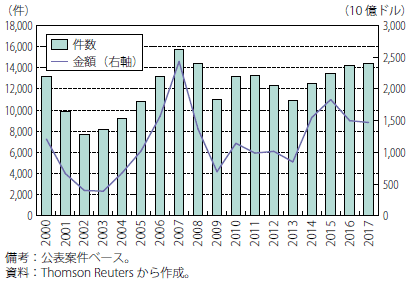
第Ⅰ-1-1-10表 世界の国・地域別クロスボーダーM&A?(2017年)
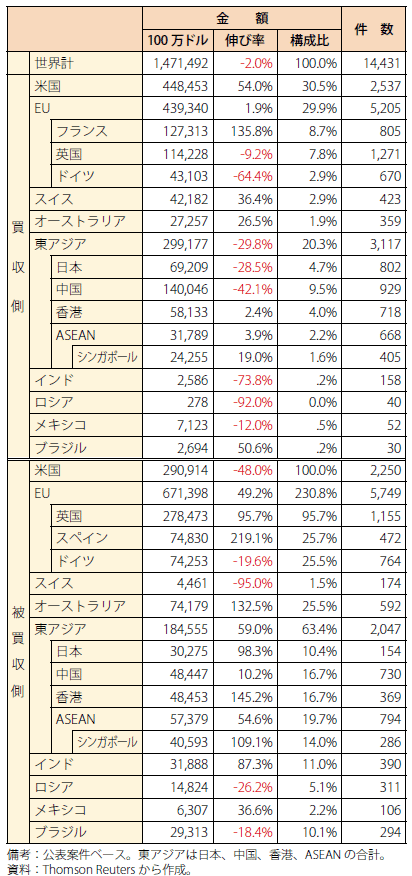
4 2016年の直接投資の最大の受け入れ国は米国(3,911億ドル)、英国(2,538億ドル)、中国(1,337億ドル)の順。
5.米欧金融政策の正常化の影響
(1)欧米における金融政策の正常化の動き
2007年夏のサブプライム住宅ローン危機に端を発する世界金融危機以降、世界各国の中央銀行は、金融システムの安定化と物価の安定を目的として、大胆な金融緩和政策を実施してきた。特に、伝統的な政策変数である短期金利が実質的に0%に限りなく近い水準となったことから、金利を操作することによる金融緩和政策の実施が不可能となり、各国の中央銀行はバランスシートの規模・構成を操作する非伝統的金融政策手段を採用するようになった(第Ⅰ-1-1-11図)。我が国においても、第二次安倍政権が経済成長を目的とした「三本の矢」の一つに掲げた「大胆な金融政策」が2013年4月から実行されている。しかし、欧米においては、こうした金融緩和政策を縮小し、徐々に正常化に向かう動きが出始めている。
第Ⅰ-1-1-11図 日米欧の中銀バランスシート推移
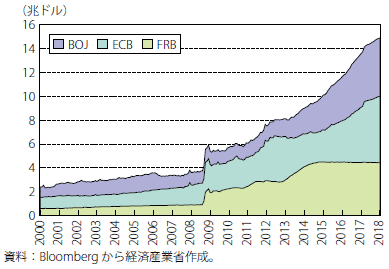
米国においては、連邦準備制度理事会(以下、FRB)が2007年9月から利下げを実施し、リーマン・ショック後の2008年12月には政策金利の誘導目標が0.0~0.25%に到達した。事実上のゼロ金利に突入したにもかかわらず、物価や労働市場の見通しが低調だったことから、2008年11月には大規模な資産購入による量的緩和政策に着手。また、その後も金融緩和政策を維持する旨のフォワードガイダンスを実施し、市場とのコミュニケーションを図った。2013年頃からは、景気の回復の状況を見定めながら、資産購入量の縮小(テーパリング)の時期を模索し、2014年1月にテーパリングを開始した。その後、2015年12月にはゼロ金利政策も解除され、2018年3月には1.50~1.75%まで利上げされている。昨年10月からはFRBは再投資額を減少させることにより保有資産を縮小させることに着手した。今後3~4年間でバランスシートの規模は4.5兆ドルから2~3兆ドルの水準5まで縮小する見込みである6。
欧州においては、世界金融危機への対応として、2009年以降、カバード・ボンドや国債の購入が行われたほか、欧州債務危機を背景とした金融市場における緊張感の高まりを緩和させるため、また経済の回復を下支えする目的で、2011年以降、数度にわたり銀行に対する長期資金供給が実施された。また、2015年3月には国債を含む本格的な資産購入が開始され、2018年現在までECB及びユーロ圏の各国中央銀行のバランスシートは拡大傾向が続いている。しかし、欧州経済が力強さを取り戻す中、資産購入については、購入額が2016年12月以降2回縮小しているほか、購入そのものの終了(実施が予定されている2018年9月以降の延長を行わない可能性)について注目が集まっている。
このように、主要先進国においては、これまで大胆な金融緩和政策が実施されてきたが、米国が先陣を切る形で金融政策の正常化に舵を切り、これに欧州が続く形となっている。我が国においては、足元の景気は緩やかに回復しているものの、物価が目標とする2%へは距離があることなどを理由に金融政策の出口対応には至っていない。
5 パウエルFRB議長は就任前の2017年11月28日、上院銀行委員会の公聴会において、バランスシートの適正規模は2.5兆~3兆ドルと述べた。
6 米国の政策金利と長期金利の関係については、コラム2「米国政策金利と長期金利の関係」を参照。
(2) 世界経済への波及効果
①世界的な債務の積み上がり
各国の金融緩和政策を背景に世界では債務が積み上がっている。世界の債務残高は2017年6月末で169兆ドルと、GDPの2倍を超える水準にまで拡大している(第Ⅰ-1-1-12図)。債務膨張のペースは各国ごとにばらつきがあるが、国際決済銀行(以下、BIS)によれば、過去の金融危機の分析の経験から、GDP成長率よりも早いペースで民間債務が拡大した国では、金融危機に直面するリスクが高いという。より具体的には、GDPに対する民間債務の比率について長期トレンドからの乖離が10%以上の場合には、その後3分の2の確率で金融危機か大幅な景気後退が起こったとされている7。例えば、日本のバブル崩壊前は23.7%、アジア通貨危機前のタイでは35.7%、リーマン・ショック前の米国では12.4%、欧州債務危機前のギリシャで24%といったように(第Ⅰ-1-1-13図)、その数値は軒並み10%を上回る水準にあった。2017年9月時点では、いくつかの国・地域がこの水準にある(第Ⅰ-1-1-14図)。
第Ⅰ-1-1-12図 世界の非金融部門への与信残高
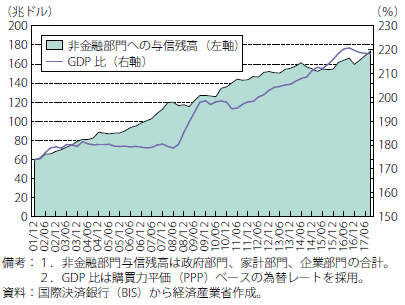
第Ⅰ-1-1-13図 過去の危機時における非金融民間部門の債務/名目GDP?(トレンドからの乖離)
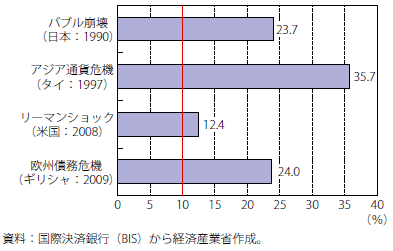
第Ⅰ-1-1-14図 国別の非金融民間部門の債務/名目GDP?(トレンドからの乖離)
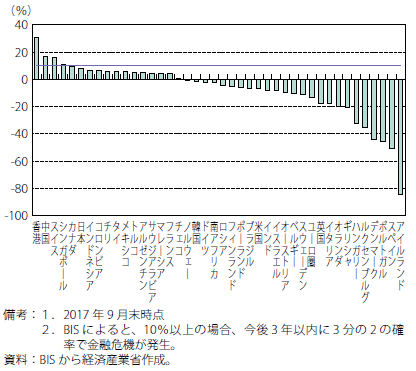
7 BIS(2018)
②新興国における資金流出入
新興国においては、米国を中心とする先進国による金融緩和政策によって、膨大な資金流入が生じた。IMFによれば、2010年からの新興国への資金流入を要因別に分解すると、米国の金融緩和政策が約2,600億ドルの資金流入(第Ⅰ-1-1-15図)8を生んだと分析している。そして、今後2年間9の米国の金融政策の正常化により、新興国へ資金流入量(第Ⅰ-1-1-16図)は年間350億ドル減少するとしている。ここでは、過去の経験を踏まえ、新興国の経済指標や金融市場の動向に目を向けながら、最近の新興国における資金流出入動向について述べたい。
第Ⅰ-1-1-15図 新興国への証券投資フローの累積寄与度(モデル推計)
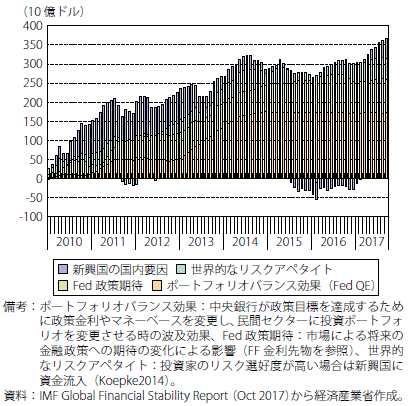
第Ⅰ-1-1-16図 新興国への証券投資フローの月次累積寄与度(2017~2019年)
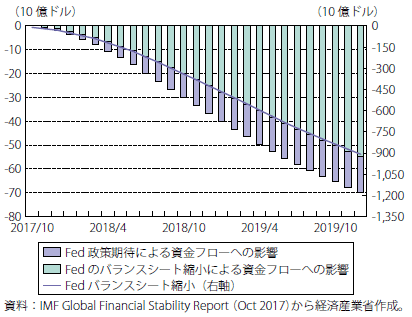
過去に米国の金融政策の変更が新興国への資金フローに大きな影響を与えた事例として、2013年のテーパー・タントラムがある。これは、当時のFRB議長であったバーナンキ氏が2013年5月22日に上下両院合同経済委員会において、FRBの資産購入額の縮小に言及したことに端を発する。これをきっかけに新興国においては、株式及び債券投資からの海外資金の急激な引上げが起こり(第Ⅰ-1-1-17図~第Ⅰ-1-1-18図)、金融市場に動揺が走った。特に、外国への借入れへの依存度が高く、経常収支が赤字の国々(ブラジル、インド、インドネシア、トルコ、南ア)においては、テーパリング発言から3か月ほどの間に急激な債券利回りの上昇(平均約2.5%)、株価の下落(平均約13.75%)、為替の下落(平均約13.5%)を経験10した。一方で、経常収支の黒字、強い財政バランス、低いインフレ率、潤沢な外貨準備といった諸条件を満たしていた国はこうした影響が少なかったとされている。
第Ⅰ-1-1-17図 新興国への株式投資フロー(2013)
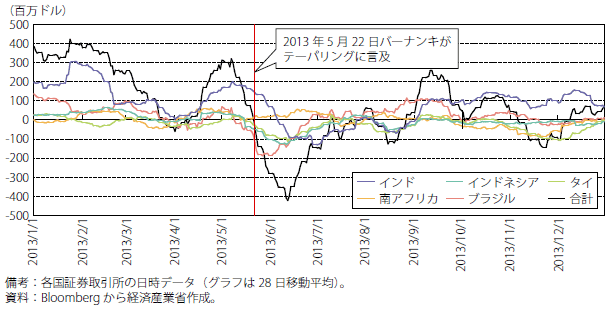
第Ⅰ-1-1-18図 新興国への債券投資フロー(2013)
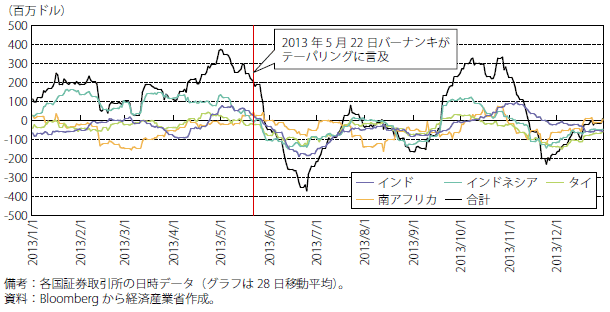
8 FRBの金融緩和政策による影響(ポートフォリオバランス効果)とFRBへの政策期待による資金流入の累積の合計値(2017年9月時点)。ポートフォリオバランス(リバランス)効果とは、中央銀行の国債買いオペレーション政策によって国債利回りを大きく低下させ、民間金融機関等を中心にそれへの投資魅力度を下げ、相対的に期待収益率の高い株式、貸出し等のリスク資産運用へのポートフォリオをシフトさせる効果を指す。(米澤、2016)
9 IMFレポート執筆時(2017年10月)より2年間。
10 MF(2014)
今回の金融政策の正常化局面について分析すると、米国が利上げ局面にある一方で、複数の新興国では、これに逆行する動きがみられ(第Ⅰ-1-1-19図)、米国と新興国の金利差は縮小している。金利差の縮小により、新興国への投資妙味が薄まることで新興国からの資金流出が加速する可能性がある。これに伴い、新興国通貨が下落し、それが輸入物価の上昇を通じて国内インフレ圧力を高め、各国中銀による急激な金融引締め策等により新興国景気を減速させることが懸念されるワーストシナリオである。しかし、今回の局面においては、市場の急激な変化は起こっていない。実際に、新興国への資金フローを確認すると、例えば、昨年10月の米国のバランスシート縮小といった金融政策の変更のタイミングでは、債券が直後から資金流出傾向にあった一方、株式は同月末にかけて資金流入傾向にあったことが示されており、テーパー・タントラム時のような資金の一斉流出といった現象は確認できなかった(第Ⅰ-1-1-20~21図)。
第Ⅰ-1-1-19図 新興国の政策金利推移
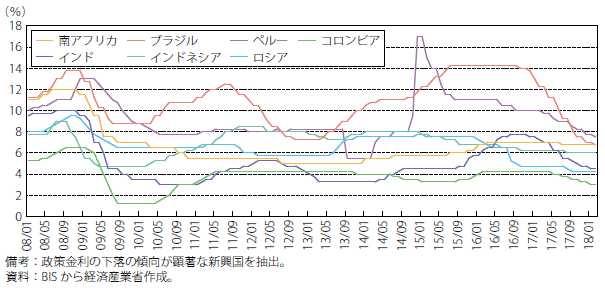
第Ⅰ-1-1-20図 新興国への株式投資フロー(2017)
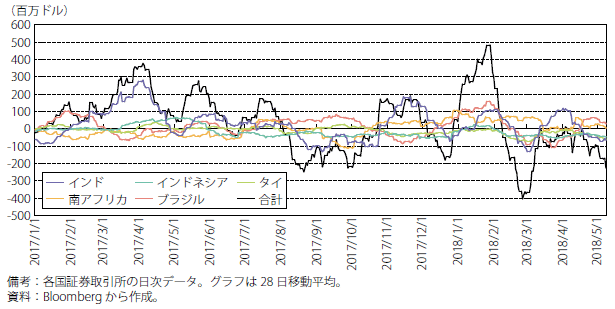
第Ⅰ-1-1-21図 新興国への債券投資フロー(2017)
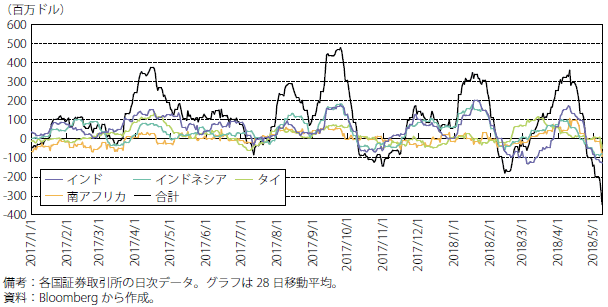
市場の反応が穏当である理由としては以下の点が考えられる。第一に、テーパー・タントラムの教訓を踏まえ、FRBはフォワードガイダンス等を通じた市場とのコミュニケーションを十分に図りながら慎重に金融政策の実施を行っている11。金融政策の予見可能性が高まったことで、金融市場の混乱は起こりにくくなっているものと思料される。第二に、新興国のファンダメンタルズ12が安定的に推移していたことである。第Ⅰ-1-1-22表は2013年と2017年の主要新興国におけるGDP成長率、経常収支、基礎的財政収支(プライマリーバランス)、政府総債務残高、外貨準備高を比較したものである。2017年の表に記載の新興国の平均GDP成長率は2013年との比較で僅かに低下しているものの、4.3%という高い伸び率を維持している。また、経常収支の対GDP比については、2013年平均の0.5%から2017年には1.9%と大幅に改善している。外貨準備高も三割近い水準を維持しており、2000年代初頭には10%台ほどだったことに鑑みれば、潤沢であると言える。また、新興国のインフレ率は2013年と比較して低い傾向にある。2013年と2017年の為替騰落率とインフレ率を比較(第Ⅰ-1-1-23図)すると、2013年には大幅な為替下落と高いインフレ率を示していた国が多数存在(インド、トルコ、南ア、ブラジル、ロシア等)していたのに対し、2017年はこうした国の数は減少し、為替の上昇と低インフレ率を示す国の数が増加していることがわかる。一方で、プライマリーバランスと政府総債務残高については、わずかに悪化の傾向がみられ、財政政策の余地が縮小し、景気を下支えすることが難しくなるとの指摘もある。しかし、FRBのパウエル議長も新興国は正常化の動きに対応することができる(manageable)と発言13しているように、今回の金融政策正常化に当たってFRB当局者は新興国経済が順調に推移していることに注目14していた。新興国経済が順調であったからこそ、米国は順調に金融政策の出口を進むことができたのではないだろうか。
第Ⅰ-1-1-22表 新興国のGDP成長率、経常収支、基礎的財政収支、政府総債務残高、外貨準備高
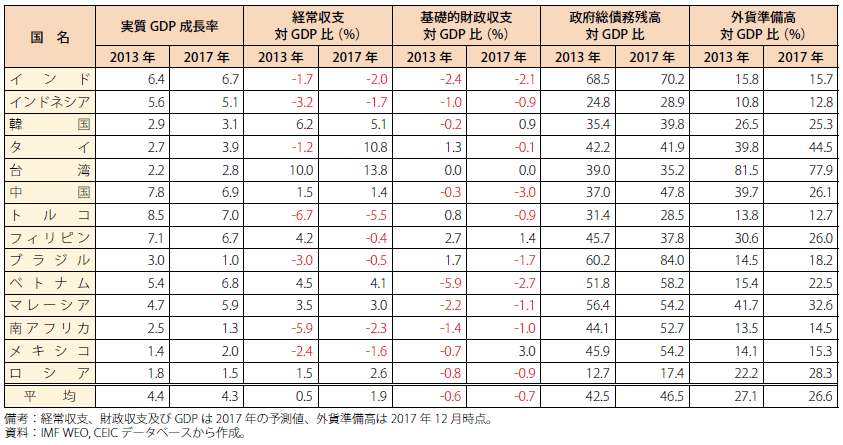
第Ⅰ-1-1-23図 インフレ率と為替騰落率の関係
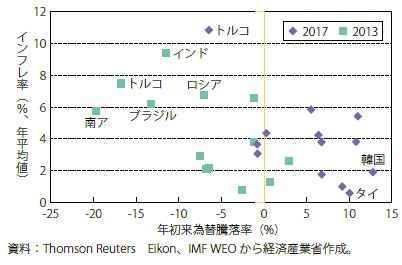
第Ⅰ-1-1-24図 GDP成長率、経常収支、資金流入額の累積規模
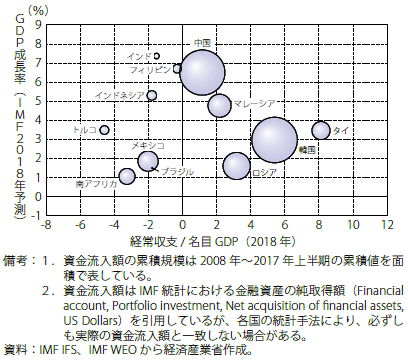
今般の金融政策の正常化は市場に大きな驚きを与えなかったが、今後の欧米金融政策は経済情勢次第で変わりうるものであり、予見可能性が高まったとはいえ、油断はできない。市場関係者の見方によれば、欧米経済が当局の予想を超えて改善した場合、従来の政策スタンスを引締め方向に見直す可能性があり、それによって急激な金利上昇を招く懸念も指摘されている。また、国際金融協会(IIF)は、米国の長期金利が4年3か月ぶりに3%台に乗せた4月後半以降は、新興国からの資金流出が顕著であったと警鐘を鳴らしている15。今後の動向に注視が必要である。
11 2014年9月に公表されていた再投資政策の見直しを柱とする出口戦略の改定時期について、2017年前半のFOMCにおいては繰り返し(1月、3月、5月会合)議論が行われ、市場とのコミュニケーションを重視しながら実施のタイミングを図ることの重要性につき言及されている(FOMC議事録より)。
12 パウエル議長は新興国のファンダメンタルズ改善が新興国への資金フローの説明要因になると講演において言及している。一方で、新興国の対外債務の水準には注視が必要とも発言。2017年10月12日、「Prospects for Emerging Market Economies in a Normalizing Global Economy」(https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20171012a.htm![]() )。
)。
13 13 上記脚注の講演(10月)における発言。
14 例えば、2017年3月3日のイエレン議長の講演においては、「特に海外に起因するリスクは幾分後退しているようにみえる(particularly as risks emanating from abroad appear to have receded somewhat)」と述べている。(https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20170303a.htm![]() )
)
15 IIFは4月16日~5月4日の期間における新興国からの資金流出は特に債券市場において顕著であり、同期間に61億ドルの投資の引上げがあったとしている。これは2013年のテーパー・タントラム時を上回るペースであり、米国金利の変動に対する感応度が増していることを示しているとした。なお、同期間における株式市場からの資金流出は31億ドルと記載されている。
