第2章 新興・途上国経済の台頭
第1節 世界経済における新興・途上国の役割の変化
1.世界の経済成長に果たす新興・途上国の役割の増加
第1部第1章で足下の世界経済の動向について見たが、本節では世界経済を先進国38と新興・途上国に分けた時に新興・途上国の役割が中長期的にどのように変化してきているか、マクロ的な観点からGDP、貿易及び直接投資の順に見てみることにしたい。
まず、第Ⅱ-2-1-1-1図は世界の名目GDPの1980年から2017年までの推移とともに、新興・途上国のシェアを取ったものである。これを見てみると、世界の名目GDPはリーマンショック等により一時的な落ち込みはあるものの順調に成長を続けてきていること、世界の名目GDPに占める新興・途上国のシェアは2000年代半ば以降上昇傾向にあり、足下では40%を超える水準に達していることが分かる。
第Ⅱ-2-1-1-1図 世界の名目GDP及び新興・途上国シェアの推移
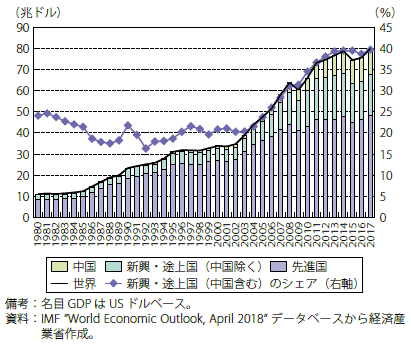
次に、世界のGDP実質成長率への各国・地域の寄与度(第Ⅱ-2-1-1-2図)を見てみると、2000年頃から世界の実質GDP成長率に占める先進国の寄与度は次第に低下してきているのに対し、中国を含めた新興・途上国による世界経済の成長への貢献度が上がってきていることが分かる。1981年以降2000年までの先進国のシェアはほぼ8割前後を占めていたが、2000年以降では、6割くらいまで低下してきている。
第Ⅱ-2-1-1-2図 世界の実質GDP成長率の推移(国・地域別寄与度)
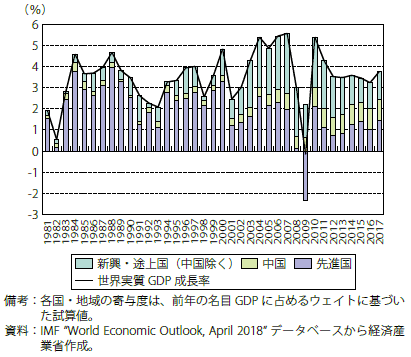
なお、新興・途上国の成長率は、2000年以降継続して先進国を上回っている一方、先進国はリーマンショック以降、以前よりも低成長を続けている(第Ⅱ-2-1-1-3図)。
第Ⅱ-2-1-1-3図 先進国及び新興・途上国の実質GDP成長率推移
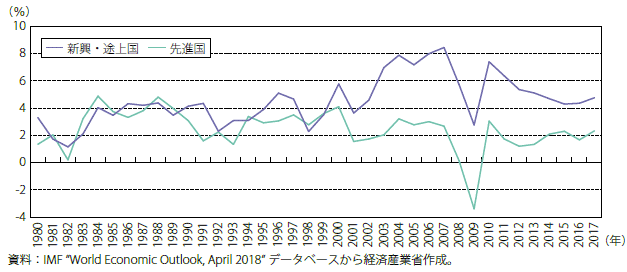
このように名目GDPに占めるシェアは依然先進国の方が上回るものの、世界の経済成長への寄与という面から見ると、特に2000年代以降新興・途上国の世界の成長に果たす役割が益々大きくなっている。
新興・途上国の経済成長要因をもう少し詳しく見るため、経済成長の需要別項目としてあげられる総資本形成(国内投資)と国内消費の関係に着目してみる。
IMFなどによると名目GDPに占める国内投資の割合は、先進国では平均2割、新興・途上国では平均3割といった水準と言われているが、国内投資額及び国内最終消費額の推移を先進国と新興・途上国の別に見ると(第Ⅱ-2-1-1-4図及び第Ⅱ-2-1-1-5図)、2000年以降新興・途上国の国内投資額が消費額を上回る勢いで拡大していること、新興・途上国の投資額は2016年で9.5兆ドルと先進国とほぼ同じ規模になっている一方、消費額は先進国の6割程度の規模にとどまることが分かる(第Ⅱ-2-1-1-6図)。また、成長率への寄与度でみると、特に2003年以降は、総資本形成の寄与が大きいことが分かる。この時期の新興・途上国の名目GDPの伸びは、後に述べる対内直接投資を含め国内投資の拡大による部分も大きいと言える。
第Ⅱ-2-1-1-4図 新興・途上国の実質GDP成長率の需要項目別寄与度分解推移
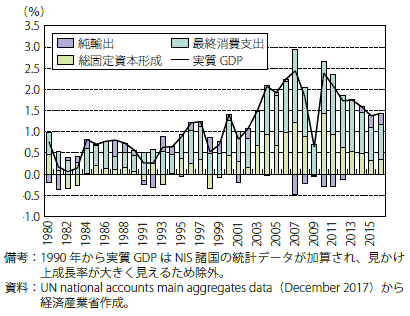
第Ⅱ-2-1-1-5図 国内投資額推移(先進国及び新興・途上国別)
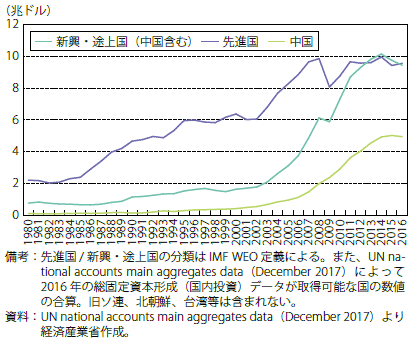
第Ⅱ-2-1-1-6図 国内最終消費額推移(先進国及び新興・途上国別)
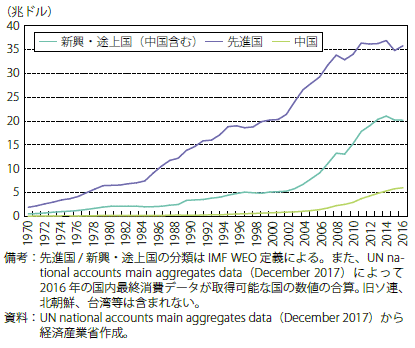
38 この節では、先進国とはIMFの定義による先進国を指す。
2.世界貿易に占める新興・途上国シェアの上昇
次に財貿易面での新興・途上国のシェアの動向について、WTOの統計データを用いて見てみたい。
まず、世界の総輸出額は、2000年以降順調に増加した後、リーマンショックの際に一度落ち込み、その後再度2014年まで増加するものの、2015年及び2016年に再度減少している(第Ⅱ-2-1-2-1図)。
第Ⅱ-2-1-2-1図 世界の財輸出額推移(国・地域別)
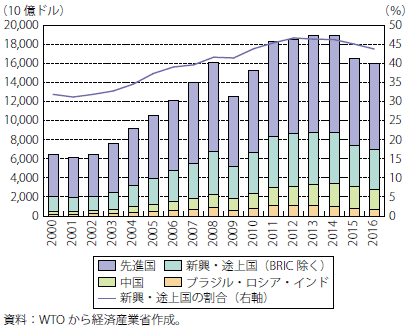
同時期における世界の総輸出額に占める新興・途上国の割合は、2000年代の約3割から少しずつ上昇し、直近では約4割に達している。特に中国の占める割合は継続的に上昇しているのが分かる。世界の名目GDPに占めるシェアの上昇に比べると輸出面でのシェアの上昇は緩やかなものとなっているが、新興・途上国の役割は着実に高まっている(第Ⅱ-2-1-2-2図)。
第Ⅱ-2-1-2-2図 世界の財輸出額における国・地域別シェアの推移
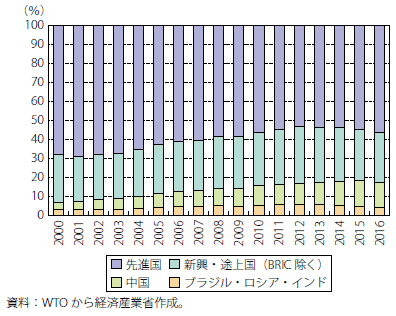
世界の総輸入額に占める新興・途上国の割合も、輸出の場合とほぼ同じ傾向を示しており、2000年代の約3割から少しずつ上昇し、直近では約4割まで達している(第Ⅱ-2-1-2-3図及び第Ⅱ-2-1-2-4図)。
第Ⅱ-2-1-2-3図 世界の財輸入額推移(国・地域別)
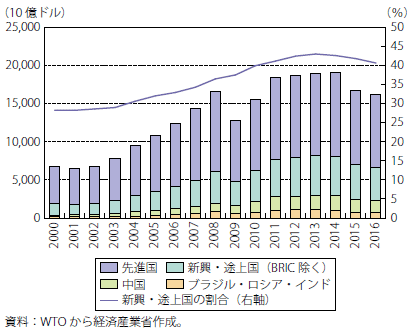
第Ⅱ-2-1-2-4図 世界の財輸入額における国・地域別シェアの推移
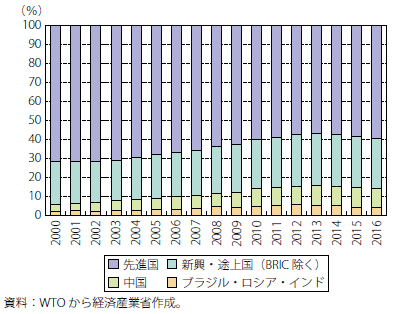
3.外国直接投資に占める新興・途上国シェアの上昇
続いて直接投資についてもUNCTADの統計データから新興・途上国のシェアの動向を見てみたい。まず、対内直接投資における新興・途上国の割合は、2000年代には1割から2割程度だったものが、2003年に上昇に転じ、2010年に初めて直接投資の受け手として新興・途上国の割合が51%と先進国を上回り、2014年に57.4%まで上昇した後、2010年では40.9%となっているなど新興・途上国の位置づけが高まっている(第Ⅱ-2-1-3-1図)。
第Ⅱ-2-1-3-1図 世界の対内直接投資額の推移(先進国及び新興・途上国別)
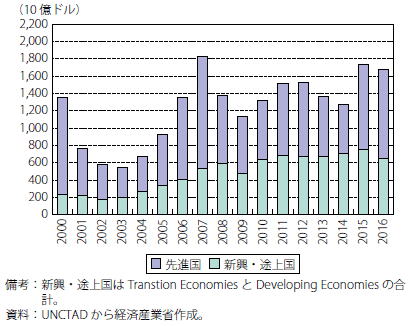
こうした変化は、輸送コストや各種調整コストの低減並びにIT技術の発展を背景に製造工程間の国際分業(グローバルバリューチェーン)が進展していること、消費市場としての新興・途上国の存在感が増してきていることなどから、先進国企業が新興・途上国に積極的に進出していることによるものと考えられる。
他方、直接投資の出し手として対外直接投資における新興・途上国の割合を見てみると、2000年代の1桁から比べれば上昇しているものの、おおよそ2~3割程度の年が多いことから、対内直接投資と比較すれば対外直接投資における新興・途上国の役割はまだ限定的であるといえる(第Ⅱ-2-1-3-2図)。
第Ⅱ-2-1-3-2図 世界の対外直接投資額の推移(先進国及び新興・途上国別)
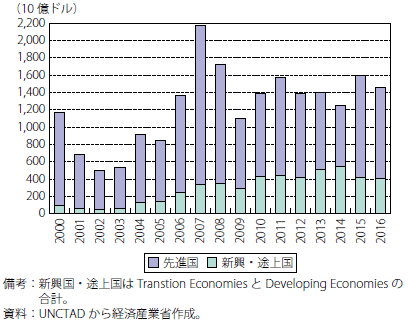
4.素材産業における新興・途上国生産能力シェアの上昇
これまで世界の経済成長、貿易及び海外直接投資の面から新興・途上国のシェアの拡大を見てきたが、ここではセミマクロの観点から、素材産業における新興・途上国の存在感の上昇についてみていく。
上記1.で、2000年代の新興・途上国は投資が成長率上昇に大きく寄与したことを指摘したが、これはこの時期に新興・途上国ではインフラ開発や企業の設備投資が多く行われたことを意味している。これらの投資には、金属、化学製品等の素材品目が多く必要とされることから、この時期にこれらの素材品目の需要が大きく上昇し、それに伴い新興・途上国での生産能力は大きく拡大したものと考えられる。また、一般に素材系産業は新興・途上国の基幹産業の1つとして位置づけられていることが多い。
そこで、素材産業の世界シェアにおける新興・途上国の位置づけを、鉄鋼及びアルミニウムを例に見ていきたい。
第Ⅱ-2-1-4-1図は、世界の鉄鋼生産能力を先進国、中国及び中国を除く新興・途上国に分けて推移を表したデータになる。先進国の鉄鋼生産能力は過去17年間、約6億トンで推移しているのに対し、新興・途上国全体の鉄鋼生産能力は右肩上がりに上昇を続け、2017年には2000年当時と比較して全世界で約2.3倍の23億トンに拡大していることが確認できる。新興・途上国の中でも中国の生産能力の拡大が著しい。また世界の2016年の鉄鋼生産量のトップ10生産国を見ても先進国4か国のシェアが18.0%なのに対し、中国(シェアが49.6%でトップ)を含め新興・途上国6か国のシェアは65.3%(2006年は50.8%)と新興・途上国のシェアが大きく、拡大傾向にあることも確認できる(第Ⅱ-2-1-4-2表)。
第Ⅱ-2-1-4-1図 世界の粗鋼生産能力の推移(先進国及び新興・途上国別)
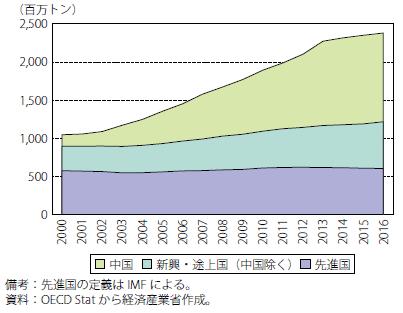
第Ⅱ-2-1-4-2表 世界の粗鋼生産量トップ10(2016年及び2006年)
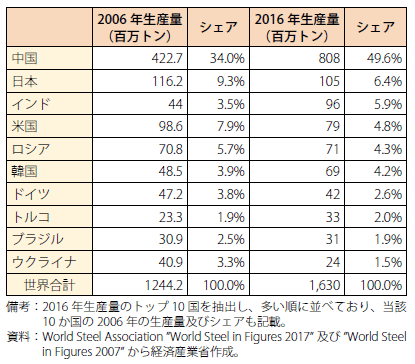
次にアルミニウムにおける新興・途上国のシェアを確認したい。第Ⅱ-2-1-4-3表は、2016年の世界のアルミ新地金39生産量トップ10のデータになる。トップ10生産国の内、先進国4か国のシェアが12.0%なのに対し、中国(シェアが55.4%でトップ)を含め新興・途上国が6か国でそれらのシェアは72.1%となっており、アルミニウムの生産においても新興・途上国のシェアが極めて高いことが確認できる。
第Ⅱ-2-1-4-3表 世界のアルミ新地金生産量トップ10(2016年)
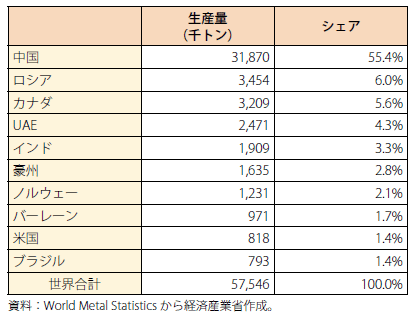
鉄鋼及びアルミニウムについて新興・途上国のシェアが拡大してきていることが確認できた。
新興・途上国が中進国や先進国へと経済発展を続けていく過程で、経済成長率は徐々に低下し、また、経済成長の内容も投資主導型から消費主導型へと移行していくことが指摘されている。一方で、市場原理に基づかない設備拡張が行われること、需要の減退により収益性を確保できず、本来であれば退出すべき企業が補助金等の政府支援措置により延命され、生産活動を継続することにより世界全体の需給環境を悪化させる恐れがあることに留意する必要がある。
39 新地金はボーキサイト鉱石から製錬された地金で、一旦使用してから再び使用される再生地金とは区別している。
