第2節 世界的な過剰生産能力問題への対応
1.過剰生産能力問題を引き起こした諸要因の分析
前節では、2000年代頃より新興・途上国経済が急速な発展を遂げる中、特に投資が活発となり、一部産業において生産能力が世界的に余剰になったことを論じた。このような過剰生産能力問題は現在G20サミット(第3部第1章第5節参照)等において主題となり、その実態や解決に向けた各国の取り組み等の情報共有と相互のレビューが実施される等、国際的に重要な課題となっている。本項では、過剰生産能力問題の事例として中国鉄鋼産業を取り上げ、産業・企業レベルでの検証により過剰生産能力問題を引き起こした諸要因を分析する。
(1)過去15年間の中国鉄鋼産業の発展経緯
中国の鉄鋼産業は中国の第1次5カ年計画の時代から重点産業として位置づけられてきた40歴史的な基幹産業である。特に中国がWTOに加盟した2001年以降、中国鉄鋼産業は急速な発展を遂げ、現在では粗鋼生産量は約8億トンにのぼり、世界の粗鋼生産量のほぼ半分を占める状況にある(第Ⅱ-2-2-1図)。
第Ⅱ-2-2-1図 中国粗鋼生産量と世界生産量に占める割合の推移
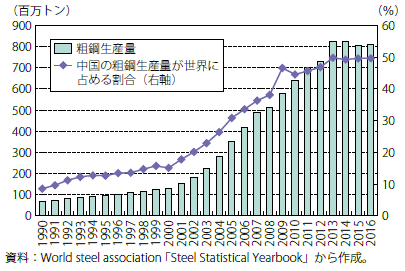
ここでは、急速な発展を遂げた中国鉄鋼産業の発展経緯について、2016年末時点で上場の鉄鋼企業33社の財務報告書等を用いて、第Ⅱ-2-2-2図に表示した4つの期間に区分して概観する。
第Ⅱ-2-2-2図 中国鉄鋼産業の発展経緯(2001-2016年)
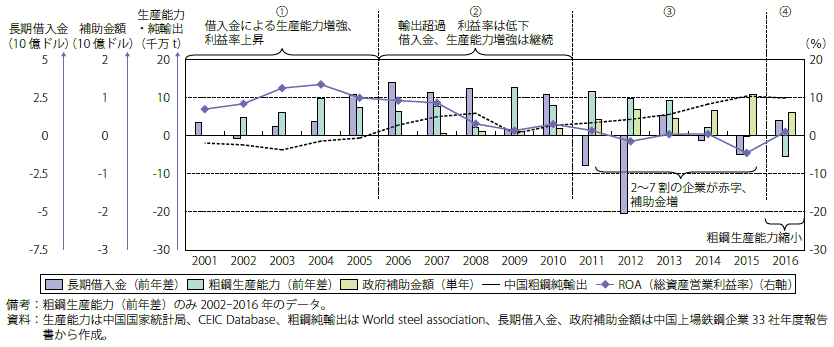
① 中国がWTO加盟を行い同国の国際市場への参入が加速した2001年以降から、鉄鋼輸入超過最後の年である2005年までの期間
② 鉄鋼輸出超過国へ転換した2006年から、「4兆元の景気対策」の最終年となる2010年までの期間
③ 「4兆元の景気対策」後の2011年から、赤字企業が増大し、政府補助金の投入額がピークに達した2015年までの期間
④ 粗鋼生産能力が減少し始める2016年以降
40 国務院(1955)「国家経済発展のための第1次5カ年計画」では、国家の中心的課題として重工業の発展を挙げており、重工業の事例の中でも鉄鋼産業が最初に言及されている。
①生産能力拡大と利益率上昇の時代
2001年から2005年の期間、中国は鉄鋼輸入超過国であった。この頃2001年に北京オリンピック(2008年)開催が決定し、2002年には上海国際博覧会(2010年)開催が決定し、また胡錦濤政権による継続的な財政政策等を背景として、国内鉄鋼需要は拡大を続けた(第Ⅱ-2-2-3図)。さらに、2001年の中国のWTO加盟は、国内鉄鋼産業にとって国際競争力向上の必要性を高めるきっかけとなった41。これらの背景から、主として大型商業銀行や政策性銀行(第Ⅱ部第3章第1節コラム4参照)が鉄鋼企業への低利融資を拡大し、鉄鋼企業は生産能力の拡大と製造ラインの高付加価値化を進めた。2001年-2005年の期間は、こうした生産能力の拡大が旺盛な国内需要を取り込むことに成功し、企業は生産量を伸ばすと共に利益率も上昇させた。2001年に7%であった総資産営業利益率は、2004年には13.5%とさらに上昇した(第Ⅱ-2-2-2図中の①)。
第Ⅱ-2-2-3図 中国見掛け消費量と世界に占める割合の推移(粗鋼ベース)
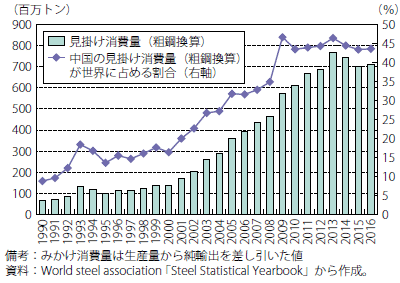
41 各企業年報の経営状況報告にWTO加盟による国際市場参入に伴う競争力向上の必要性が記載されている。
②輸出超過と利益率低下の時代
2006年、中国は鉄鋼の輸出超過国となり、以後輸出超過を継続している。輸出超過国、つまり国内需要を国内生産が上回る時代に突入する中においても、銀行は鉄鋼企業への低利融資を継続した。2001年から2006年にかけての貸出基準金利の上昇とは逆に、鉄鋼企業の長期借入金の金利(年率)は低下し、貸出基準金利の水準を下回る水準で融資が行われている(第Ⅱ-2-2-4図)。
第Ⅱ-2-2-4図 中国鉄鋼企業の長期借入金利と政策金利の推移
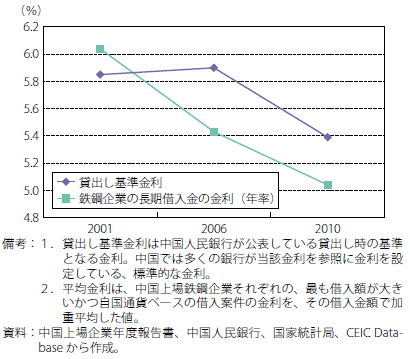
こうした、銀行による低利融資の拡大を背景として、中国鉄鋼企業の借入金と生産能力の拡大は続いた。その後、2008年の世界金融危機により世界の鉄鋼需要は低迷するも、中国政府は2009年から2010年にかけて公共投資による「4兆元の景気対策」を行い、一時的に国内鉄鋼需要が増加したこと等から、鉄鋼企業は低利の長期借入に基づく生産設備増強を続けた。一方、2008年以降鉄鋼企業の総資産営業利益率は5%を下回った(第Ⅱ-2-2-2図中の②)。
③赤字企業の増大と政府補助金拡大
「4兆元の景気対策」により中国の鉄鋼需要は上昇したものの、中国政府は投資が一部過熱化した経済に歯止めをかけるため、2010年から2011年にかけて金融引き締め策をとった(第Ⅱ-2-2-5図)。これにより、鉄鋼企業は2010年まで継続して伸ばしていた銀行からの長期借入残高を低下させた(第Ⅱ-2-2-2図中の③)。一方、2011年頃から鉄鋼の国内需要は伸び悩み、2013年には中国国内の消費量はピークアウトしている42(第Ⅱ-2-2-3図)。国内需要の伸び悩みに伴い、生産設備の稼働率は2011年以降75%を下回り(第Ⅱ-2-2-6図)、また純輸出額も増加した(第Ⅱ-2-2-2図中の③)。
第Ⅱ-2-2-5図 中国の政策金利および預金金利の推移
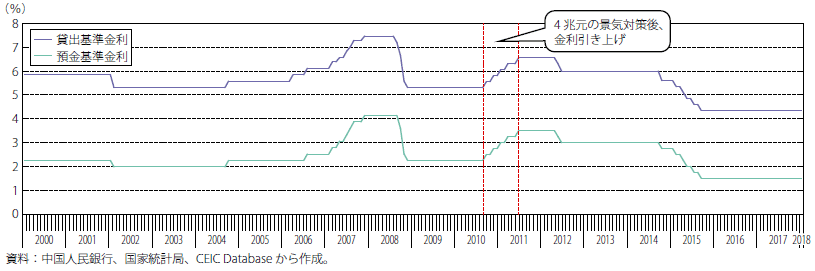
第Ⅱ-2-2-6図 中国鉄鋼産業の余剰生産能力と生産設備稼働率
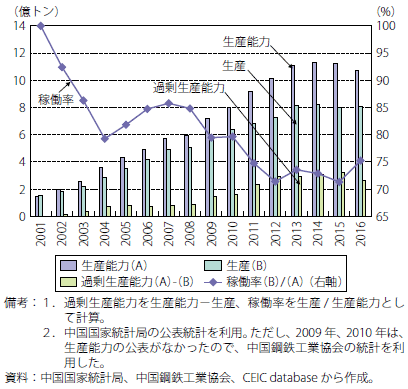
こうした鉄鋼市場の不況に伴って、2012年には鉄鋼上場企業の約半数が営業赤字となった。また、同年には政府補助額43が大きく拡大した(第Ⅱ-2-2-7図)(第Ⅱ-2-2-2図中の③)。また、2015年には鉄鋼上場33社の約7割が営業赤字を記録し、上場33社への政府補助額は10億ドルに達した(第Ⅱ-2-2-7図)。これらの補助金は環境・省エネ関連の研究開発・設備投資補助金の他、「奨励金」や「政府プロジェクト参加に際する給付金」等の補助金が多く含まれる44(第Ⅱ-2-2-8図)。2012年以降、総資産営業利益率はゼロ近傍やマイナス水準を推移することとなった(第Ⅱ-2-2-2中の図③)。このような厳しい経営状況下においても、中国鉄鋼産業の生産能力は2014年まで拡大を続けた。
第Ⅱ-2-2-7図 中国鉄鋼上場33社における営業赤字の割合
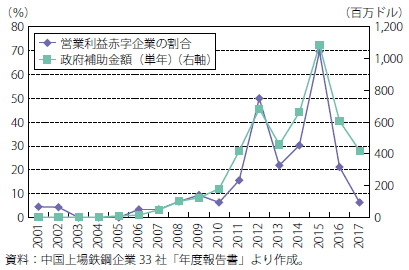
第Ⅱ-2-2-8図 中国鉄鋼上場33社における補助金用途別割合(2015年)
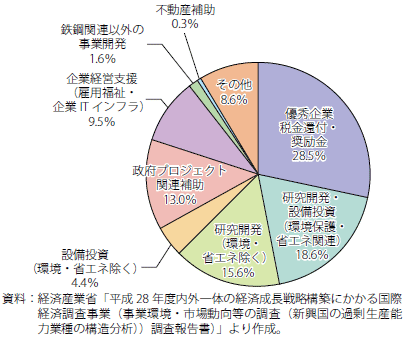
42 なお、工業信息化部の中国鉄鋼業第12次5ヶ年発展計画(2011年~2015年)では、中国の粗鋼需要量のピークは2015年以降、2020年頃にくるものと予測していたが、実際にはこれよりも早くピークアウトした。
43 政府補助額は中国鉄鋼上場企業33社「年度報告書」の損益計算書中、2001-2006年までは“補助収入”から、2007-2016年までは“営業外収益”の中の“政府補助”から取得。なお、2017年は会計基準の変更により、損益計算書中、“その他収益”および“営業外収益”の中の“政府補助”の合計値を取得。
44 こうした企業の営業赤字に伴って拡大する補助金については「翌年にも営業収益を悪化させる傾向がある」との指摘がある。渡邉(2017)p 27参照。
④過剰生産能力の削減対応
中国中央政府は2000年代から中国鉄鋼産業の過剰生産能力を問題視していた。2005年には国務院「鉄鋼産業開発政策」45において、鉄鋼産業の構造調整の必要性が唱えられ、小規模施設の廃棄等が指示されている。また2013年には「深刻な生産能力過剰問題の解消に向けた指導意見」46において設備の新規建設の禁止及び削減目標の設定が行われる等、数多に及ぶ生産能力調整政策を実施した(第Ⅱ-2-2-9図)。
第Ⅱ-2-2-9図 2005年以降の鉄鋼関連政策と関連通知年表
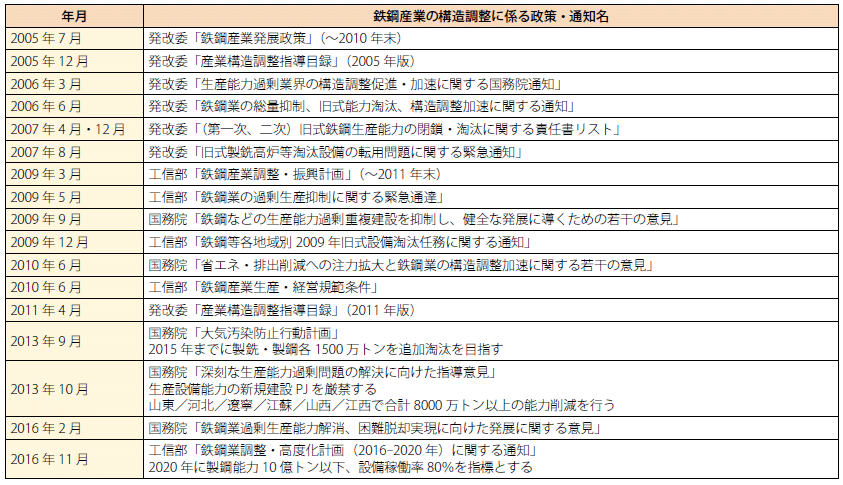
上場企業の約7割が営業利益赤字となった2015年には、12月の中央経済工作会議47において過剰生産能力解消が筆頭の重点任務に位置付けられた。これに基づき、2016年2月、中央政府は削減目標を設定48した。また、能力削減に伴う失業者問題の解決を支援する為、専用基金を創設する等の政策49を決定した。さらに、監査団を地方に派遣し、中央政府の鉄鋼過剰生産能力への対応指針に違反する地方政府幹部を処罰する等、厳格な執行管理を行った50。これらの取り組みの結果、2016年及び2017年は、生産能力削減目標を達成している(第Ⅱ-2-2-10図)。また、中国政府は鉄鋼グローバルフォーラム(第3部第1章第5節参照)において、上記の削減取り組みをフォーラムの参加国に紹介している51。
第Ⅱ-2-2-10図 中国の粗鋼生産設備削減目標と実績
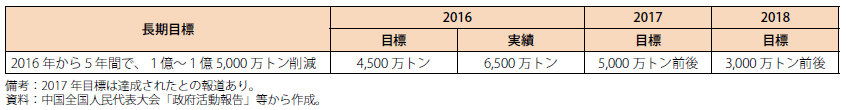
以上、中国鉄鋼産業の2001年以降の発展経緯をみると、生産能力の増加には、市況と逆行した銀行による過大かつ低利な融資が関係を有していることが示唆される。また、企業への政府補助金は、事実上企業の赤字補填および低収益性の企業の延命措置となったことが示唆される。
45 発展改革委員会(2005)「鉄鋼産業発展政策」http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbl/200507/t20050719_52618.html![]()
46 国務院(2013)「深刻な生産能力過剰問題の解消に向けた指導意見」http://www.gov.cn/jrzg/2013-10/15/content_2507507.html![]()
47 中央経済工作会議は、年に1度中共中央・国務院が行う会議であり、翌年のマクロ経済政策を決定する上で最も権威がある。中央経済工作会議には、党中央・国務院の指導者、全国人民代表大会・全国政治協商会議の指導者、各省・自治区・直轄市党委員会政府の主要責任者、中央・国家機関各部門の主要責任者、軍隊の各軍区・兵種などの主要責任者、中央直轄の関連企業の主要責任者などが出席する。(人民日報経済用語集を参照)
48 国務院(2016)「鉄鋼業過剰生産能力解消、困難脱却実現に向けた発展に関する意見」http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm![]()
49 財務部(2016)「工業企業構造調整特別奨励資金管理弁法」http://jjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefagui/201605/t20160519_1998021.html![]()
財務部(2016)「工業企業構造調整専用資金関連問題に関する通知」http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/wg2016/wg201603/201607/t20160705_2344745.html![]()
50 国務院(2016)「鉄鋼業過剰生産能力解消、困難脱却実現に向けた発展に関する意見」http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm![]()
51 BMWi & OECD (2017) “Global Forum on Steel Excess Capacity report”
(2)企業の所有形態別の動向
続いて、鉄鋼企業を「中央政府所管国有企業」、「地方政府所管国有企業」、「民営企業」の3グループに分け52、各グループにおける銀行融資残高・政府補助額・固定資産額を見ると、地方政府所管企業向けが多くを占めていることがわかる(第Ⅱ-2-2-11図)。
第Ⅱ-2-2-11図 中国鉄鋼上場企業33社の借入金残高、政府補助額、固定資産額の推移(企業分類別)
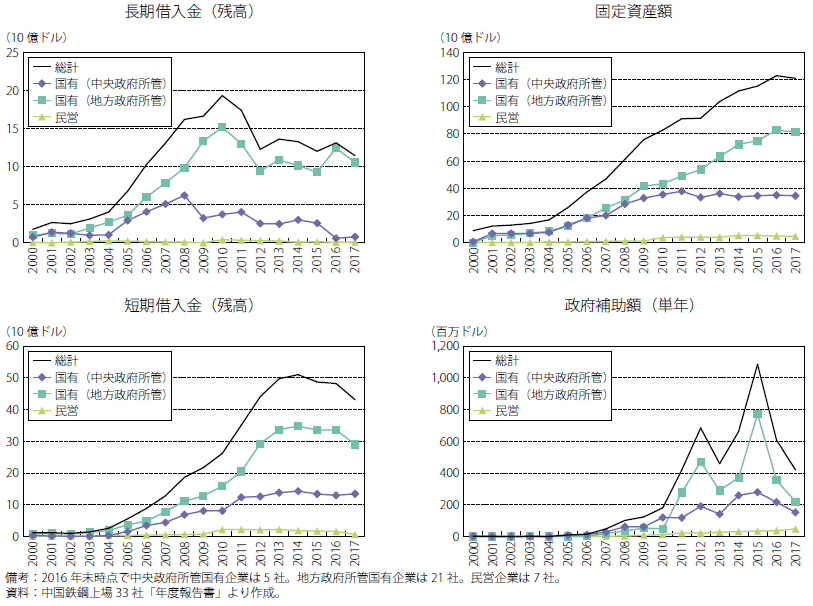
52 各企業「年度報告書」に記載の株主構成における筆頭株主から判断。
長期借入金については、対総資産の規模で比較すると、地方政府所管の国有企業が2003年以降全体の平均の数値を上回る状況が続いている(第Ⅱ-2-2-12図)。また、対固定資産額で比較した場合も、地方政府所管の国有企業が他のグループと比較して高い水準で推移している。これらから、銀行からの融資は、企業規模に比して相対的に地方政府所管の国有企業に多く行われていたことがわかる(第Ⅱ-2-2-13図)。
第Ⅱ-2-2-12図 中国鉄鋼上場企業33社の長期借入金残高対総資産の推移(企業分類別)
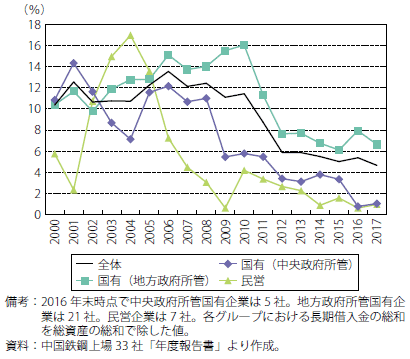
第Ⅱ-2-2-13図 中国鉄鋼上場企業33社の長期借入金残高対固定資産の推移(企業分類別)
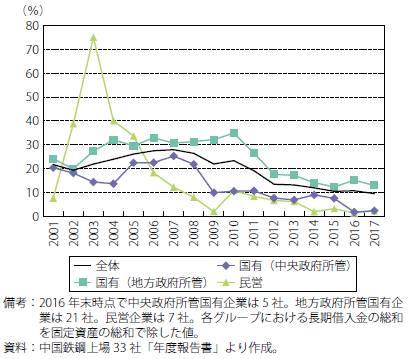
短期借入金については、2001年以降地方政府所管国有企業が対総資産額で全体の数値を上回る状況が続いており、企業の経営状況が悪化する2012年頃から2016年まで総資産の20%を占める規模である(第Ⅱ-2-2-14図)。政府補助額については、企業規模(売上高)と比較すると、各企業形態において上昇トレンドにあるが、鉄鋼業界の景気が特に悪化した2012年および2015年において、地方政府所管の国有企業の補助額が特に大きいのが目立つ(第Ⅱ-2-2-15図)。
第Ⅱ-2-2-14図 中国鉄鋼上場企業33社の短期借入金残高対総資産の推移(企業分類別)
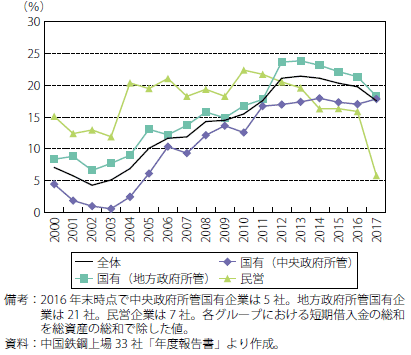
第Ⅱ-2-2-15図 中国鉄鋼上場企業33社の政府補助額対売上高の推移(企業分類別)
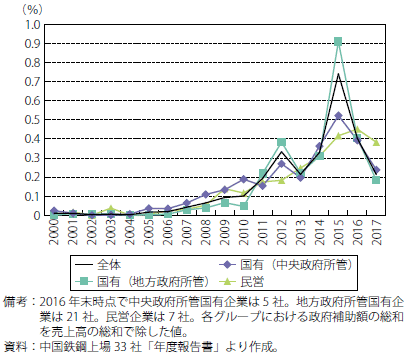
上記の動向を踏まえると、2001年WTO加盟から「4兆元の景気対策」までの鉄鋼企業への融資と生産設備投資、そして2012年以降の業績低迷に対する運転資金融資や政府補助等の支援は地方政府所管の国有企業に重点的に実施されてきたことがわかる。また、その結果は必ずしも企業の収益性や付加価値向上に寄与しておらず、特に地方政府所管国有企業は、重点的な支援を受けたにも関わらず、総資産営業利益率において他企業を下回ったままで、経営体質の改善はなされていないことがわかる(第Ⅱ-2-2-16図)。
第Ⅱ-2-2-16図 中国鉄鋼企業の総資産営業利益率(企業分類別)
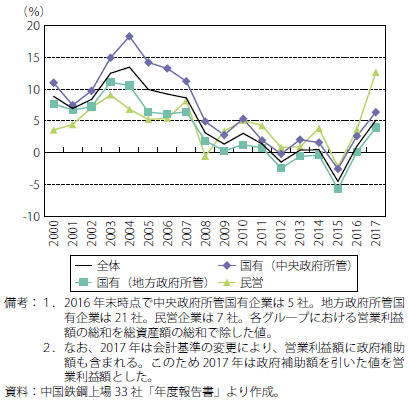
こうした鉄鋼企業への長期負債の融資元の多くは大型商業銀行や政策性銀行、株式商業性銀行の地方支店である53。これら金融機関の地方支店は、時に地元企業への融資判断が甘くなりやすい点が指摘され54ている。
また政府補助金の交付元は地方政府が大半を占めている(第Ⅱ-2-2-17図)。そうした地方政府や銀行の対応が、鉄鋼企業の過剰な生産設備増強や、過剰化した生産能力の削減への消極的な対応の要因となった可能性がある。
第Ⅱ-2-2-17図 中国上場鉄鋼企業33社への政府補助金支出元内訳(2015年)
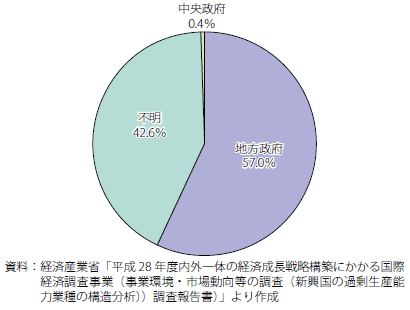
53 各企業の年度報告書中、“長期借入金(長期借款)”の詳細説明の欄に融資残高上位5行が記載されている。特に、長期借款残高が最も高かった2010年の年度報告書参照のこと。
54 (出所)「銀行の苦悩、デフォルトの嵐の中でも融資継続」(原題 ?行?苦丨????潮下被迫放?)『銀行聨合信息網』2016年10月9日。http://blog.ricoh.co.jp/RISB/china_asia/post_152.html
(3)鉄鋼輸出価格と輸出シェアへの影響
鉄鋼産業の過剰生産能力問題に伴う企業の収益性の低下は国際市況を悪化させた。鉄鋼企業の約5割が営業利益赤字となった2012年から中国国内での鉄鋼価格は製造業全体と比較して大きく下落し、輸出価格はそれ以上に下落した(第Ⅱ-2-2-18図)。2008年から2012年にかけては、中国の鉄鋼輸出価格は日米欧の平均価格と同水準か、それを上回っていただが、その後大きく下落し、世界の鉄鋼輸出価格を引き下げる一つの要因となったと考えられる。また、これに伴って2015年には世界鉄鋼輸出量に占める中国のシェアは約25%に到達することとなった(第Ⅱ-2-2-19図)。こうした動向を受け、世界的に鉄鋼に対する貿易救済措置(例えばアンチ・ダンピング等)の調査・発動件数は増加した。(第Ⅱ-2-2-20図)。
第Ⅱ-2-2-18図 中国の鉄鋼生産者物価と輸出価格の推移(前年比)
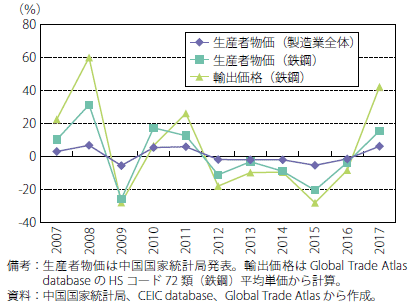
第Ⅱ-2-2-19図 中国の鉄鋼輸出価格と日米欧の鉄鋼平均輸出単価(2015年)
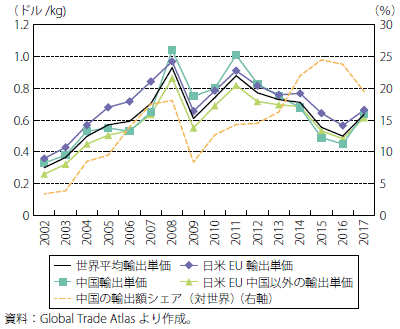
第Ⅱ-2-2-20図 鉄鋼分野の新規AD調査開始件数の推移
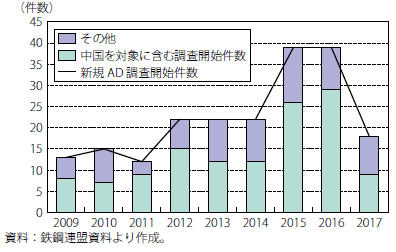
なお、直近2017年においては、世界経済が回復基調となったことや、中国の生産能力削減の取り組み等を背景に、中国鉄鋼企業の業績は回復し、鉄鋼輸出価格も上昇した。これに伴ってAD件数も減少することなった。
以上の通り、本項では中国の鉄鋼産業において引き起こった過剰生産能力問題について、過去15年間の経緯と問題の要因について事例検証を行った。中国の鉄鋼産業ではWTO加盟を契機に投資が急速に拡大し、結果として設備が余剰となった経緯がうかがえる。投資の急速な拡大は、主に地方政府所管の国有企への過大な融資・政府補助等が要因であると考えられる。
近年、鉄鋼グローバルフォーラムといった国際的枠組によって、当事国同士が互いの現状と改善策を提示し、相互レビューを実施する等、過剰生産能力問題に対する包括的な解決に向けた活動が始まっている。本項で論じた事例検証もまた、当事国同士の改善策を講じ相互レビューを実施する上で、重要な視座となると考える。
2.新たな過剰生産能力問題の可能性
これまで中国の鉄鋼産業で生じた過剰生産能力問題は、今後他産業においても生じる可能性がある55。
将来的な問題顕在化に関する検証とその対策を講じる上で、過去の事例検証に習った分析も重要な視座となる。本項では、第2部第1章で取り扱ったデジタル経済の拡大に不可欠な基盤産業となる集積回路産業を取り上げる。特に世界最大の半導体市場である中国(世界売上高シェア30%以上)(第Ⅱ-2-2-21図)の集積回路産業について、前項の鉄鋼産業と同様の手法で動向分析を行い、集積回路産業の将来的な過剰生産能力化の可能性について検証する。
第Ⅱ-2-2-21図 世界半導体市場規模と各地域・国別シェアの推移
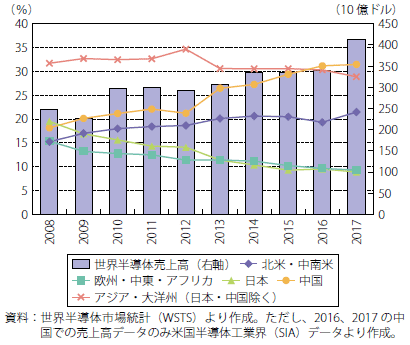
55 欧州委員会(2017)p 82 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1774![]() では、電気自動車等の新エネルギー自動車産業やロボット産業等の産業を例として挙げている。
では、電気自動車等の新エネルギー自動車産業やロボット産業等の産業を例として挙げている。
(1)過去9年間の中国集積回路関連企業の動向(第Ⅱ-2-2-22図)
第Ⅱ-2-2-22図 過去9年間の中国集積回路関連企業の動向
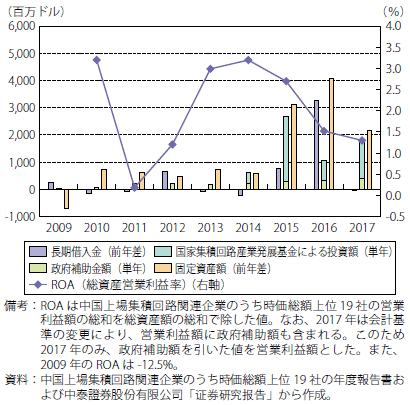
中国集積回路関連企業56は世界金融危機時に多くが営業赤字となり、総資産営業利益率はマイナスとなった。その後「4兆元の景気対策」等によって一時的に業績は改善するも、翌年には総資産利益率が0.2%となる等、不安定な経営状況にあった。
その後、中国政府は2011年の第12次5カ年計画の中で、“戦略的新興産業”の一つとしてICT産業を掲げ、またその専門政策として「ソフトウェア及び集積回路産業の発展の奨励に係る政策に関する通知」57を発出した。当該政策では、税制優遇策を中心とした財政支援策や研究開発のための投融資政策、輸出入促進政策などが掲げられた。この政策を通知した2011年は、2010年と比較して約2倍の政府補助が支出された。その後も単年毎の政府補助額は拡大を続け、第12次5カ年計画終了年の2015年には、対2010年比で約3.5倍となっている。この頃、中国国内の集積回路市場は売上高ベースで毎年20%程度拡大し、また輸入も増加が続くなどの需要の旺盛さ(第Ⅱ-2-2-23図)を背景として、集積回路関連企業は固定資産を増加させた。総資産営業利益率も向上し、2014年には3.2%まで上昇している。
第Ⅱ-2-2-23図 中国の集積回路需要
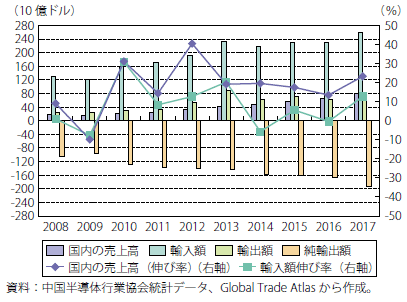
一方で、国内の需要は引き続き内製品でまかなえる状況になく、中国政府は2014年に政策支援の一層の強化のため国家集積回路発展要項58を策定した。この政策では財政支援の強化に加えて、中国輸出入銀行・国家開発銀行といった政策性銀行や商業銀行(国有銀行)等の融資を促進させ、また集積回路産業への支援に特化した国家投資基金(国家集積回路産業投資基金)の設立を決定し、また各地方における集積回路産業投資基金の設立を支援することも表明している。国家集積回路産業投資基金は2014年9月に設立され、集積回路関連企業に毎年約40億ドル規模の投資を実施している。その結果、政府補助金や企業の借入金に加えて、投資基金の投資額等、政策資源が2014年以降急速に拡大し、これに伴い、固定資産額は2015年から2017年にかけて急激に上昇している。一方で、同期間の企業の総資産営業利益率は低下を続けている。
以上で概観した中国の集積回路産業の動向は、国内の需要が旺盛な状況と将来の需要の高まりを背景とした過剰とも言える政策資源の投入による生産設備拡大という点で、輸入超過時代の中国鉄鋼産業の状況と類似しているといえる。鉄鋼産業では本来であれば市場から退出しなければならない収益性の低い鉄鋼企業の製品が国際市況を悪化させた。この結果を踏まえれば、集積回路産業においても将来的な過剰生産能力問題が懸念される。
こうした問題を背景として、半導体政府当局会合(GAMS)59においては、2017年11月に開催された会合において、産業基金等の地域支援プログラムの透明性の向上、適正化に向けたベストプラクティス及びガイドラインを合意し、具体的な実施手段として、地域支援プログラムに関する情報交換をGAMSメンバー(日本、EU、韓国、米国、台湾、中国)間で行うことを合意している。今後も当該会合等を通じて、地域支援プログラムの透明性が保たれ、結果的に集積回路産業において過剰な政策資源の投入が抑止されることが期待される。
56 本節では上場企業の中から19社を対象に分析。
57 国務院(2011)「ソフトウェア及び集積回路産業の発展の奨励に係る政策に関する通知」http://www.gov.cn/zwgk/2011-02/09/content_1800432.htm![]()
58 工業情報化部(2014)「国家集積回路発展要綱」http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757021/c3758335/content.html![]()
59 半導体の生産国の政府関係者が集まり、半導体に関する国際的に議論すべき論点について意見交換する場として、1999年に開始。以降毎年開催され、産業界の民間会合として創設されたWSC(World Semiconductor Council)の提言について議論。
(2)産業投資基金について
本節では、中国の集積回路産業において過剰な政策資源が投入され、将来的な過剰生産問題が懸念されることを論じたが、近年、特に政策資源として大きな役割を果たしているのが、国家集積回路発展基金等の産業投資基金である。
産業投資基金は政府機関、金融機関、企業、PE基金、ベンチャーキャピタル、公的年金等といった融資主体から資金を集め、政府プロジェクトへの出資や、企業の資金調達、企業合併等の産業構造最適化を支援する投資を行っている。2014年頃からその数・総額規模が急速に拡大し、現在政府の主たる政策資金源として存在感を高めている(第Ⅱ-2-2-24図)。
第Ⅱ-2-2-24図 産業投資基金の基金数・基金総額の推移
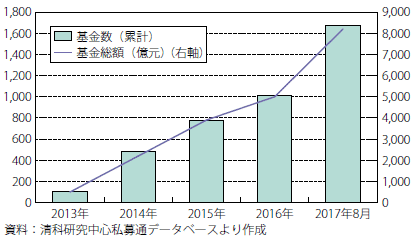
例えば、集積回路産業への支援を目的とした産業投資基金である国家集積回路産業発展投資基金の規模は1,387億元(206億ドル)とされ、中国企業への投資実績額60は政府補助金の規模を上回る(第Ⅱ-2-2-22図)。さらに地方政府においても集積回路産業への資金支援を目的とした基金が数多く設立され、その予算規模総計は2017年時点で約3,330億元(494億ドル)である61。
また、第13次5か年計画および中国製造2025において定められた戦略的新興産業(第2部第3章コラム参照)への支援を目的とした産業投資基金「先進製造産業投資基金」(予算規模200億元(29億ドル))が2016年に設立された62他、「中国製造2025発展基金」が新たに設立されるとの報道63がなされており、今後複数の産業において政策資源投入による過剰生産問題が生じることも懸念される。
60 上場企業19社に対する投資実績額。中泰證券股?有限公司「?券研究?告」http://pg.jrj.com.cn/acc/Res/CN_RES/INDUS/2018/1/2/a2dbe851-a871-4505-8907-3a4c4f79bb43.pdf![]() を参照。
を参照。
61 ??波(2018)
62 財政部(2016)「2016年7月15日報道資料」(http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201607/t20160715_2358336.htm![]() )
)
63 中国網「中国の新素材産業、2025年に生産高は10兆元へ」、2018年2月12日、(japanese.china.org.cn/business/txt/2018-02/12/content_50496646.htm![]() )
)
(3)日本の集積回路産業への産業政策と当時の企業動向について
本節では、中国における集積回路産業育成のための政策資源投資と、集積回路関連企業動向について概観した。ここでは、日本における代表的な産業振興策である超LSI技術研究開発組合が実施された1976-1979年とその前後の期間における日本の集積回路産業の動向を概観する。
超LSI技術研究開発組合は、官民共同で半導体微細加工技術の研究開発を実施し、当時最先端の大型コンピュータ用CPUやメモリの大規模集積回路(LSI)化を図ることを目的とした研究組合である。組合は富士通、日立製作所、三菱電機、日本電気、東芝、コンピュータ総合研究所(富士通、日立製作所、三菱電機の合弁)、日電東芝情報システム(日本電気、東芝の合弁)の合計7社で構成され、プロジェクトのための研究開発費総額は約730億円(うち政府負担額は約290億円)に上った。また、プロジェクトにおける研究テーマは非競争領域64に設定し、直轄の共同研究所において、複数企業の研究者達を募り研究を実施する等、実施体制についても工夫がなされた65。研究組合では、当時最先端の半導体微細加工技術の開発に成功し、これを背景として半導体の世界市場での日本のシェアは28%(1975年)から52%(1988年)に上昇した。またプロジェクト成果が活用された製品の売り上げは1983年からの5年間で2.2兆円を超える規模となった。
超LSI技術研究開発組合への政府の出資額は290億円であり、組合事業実施前後の期間(1973-1984年)において参加企業5社及び研究組合への政府補助額は多くとも売上高に対して0.3-0.5%規模66と、中国集積回路関連企業の政府補助額対売上高(2009-2017年の期間で1.3-4.1%)67を大きく下回っている。一方、超LSI技術研究開発組合実施期後の参加企業5社のROA(総資産営業利益率)は6%を超える水準を保っている。これは、足下の中国集積回路産業の動向とは対照的であるといえる。
64 財団法人武田計測先端知財団(2005)「調査報告書」
65 こうした仕組みは後ほど世界で多く実施される共同研究事業のモデルとなった。
66 参加企業5社の有価証券報告書損益計算書から推計。日本の会計基準において、政府補助金を記載する根拠法令はない。一方で、政府補助金は慣例的に営業外収益の雑収入(その他)に計上されるため、雑収入(その他)/売上高値を参照した。
67 2009-2017年平均では2.5%。また、政府補助金のみを考慮に入れているが、実際には産業投資基金からの資金受け取り等、より多くの政策資源を受け取っている。
