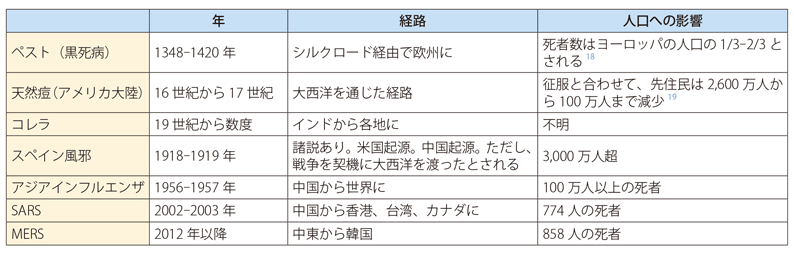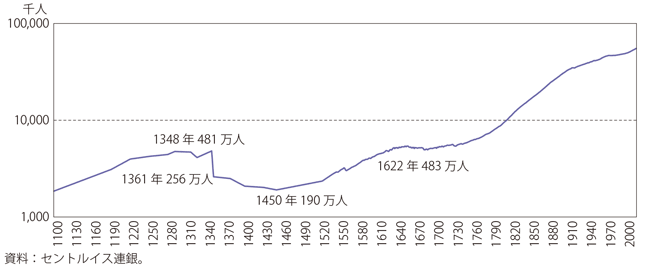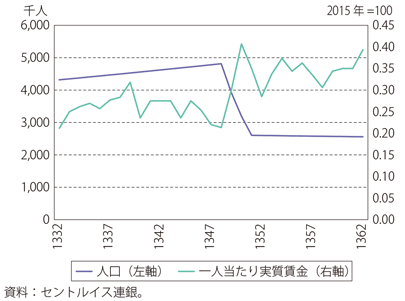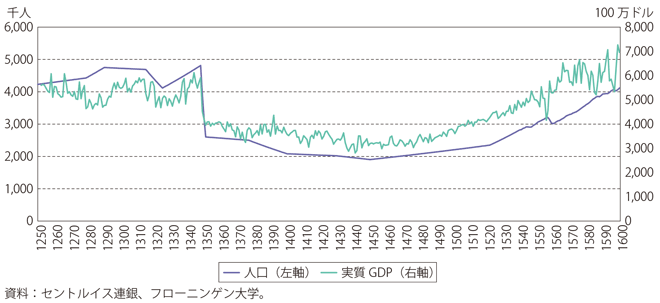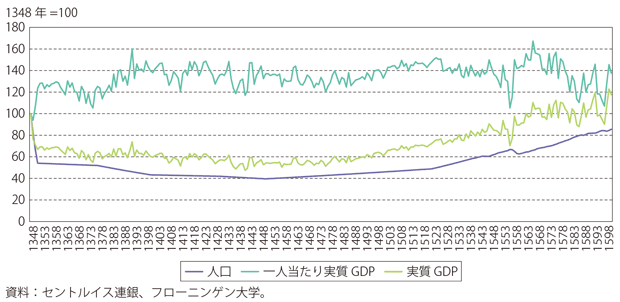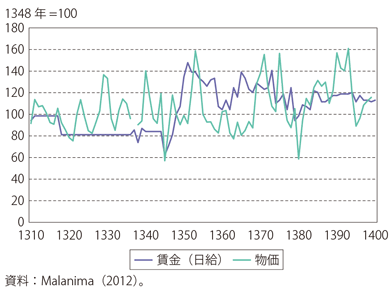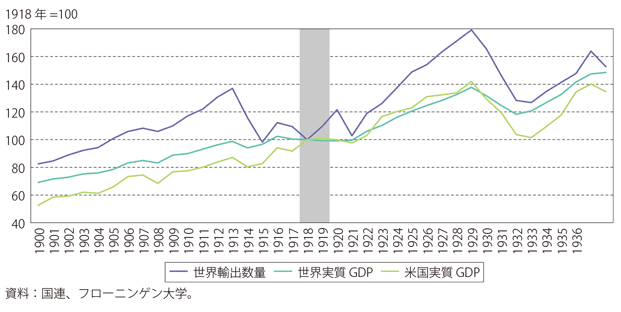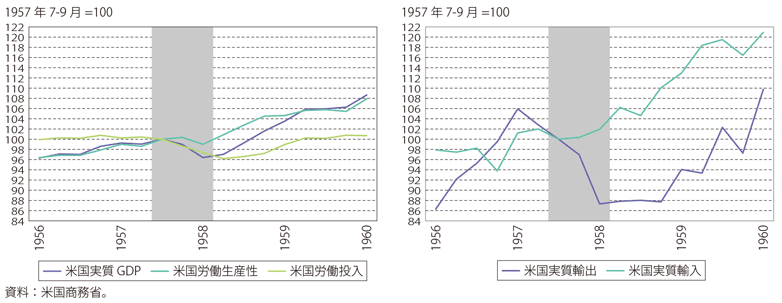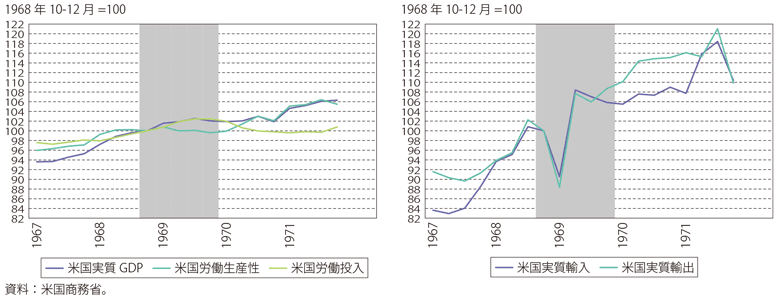- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2020

- 白書2020(HTML版)

- 第Ⅰ部 第1章 コロナショックで激変した世界経済
第1章 コロナショックで激変した世界経済
2019年に新型コロナウイルス(COVID-19)の最初の症例が中国で確認されて以降、世界経済は急速に悪化した。当初の震源地である中国から瞬く間に世界へ流行が広がり、多くの国で感染の抑制を目的とした渡航制限や外出制限等が実施されるなど、人や物の流れに変化が見られることとなった。国境を越えた人や物の交流だけではなく、国内においても人や物の交流が制限され、その結果、世界経済は急速に減速し、国際通貨基金(IMF)がグレート・ロックダウン(大封鎖)と表現するほどの経済危機が発生している。
この新型コロナウイルスの感染拡大による経済危機、つまり、コロナショックは、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの制限が本質である。新型コロナウイルスは人から人に感染が拡大するものであり、その感染拡大の抑制を目的としてフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが制限されることとなった。その結果、世界的に人・物の動きや経済活動が制限される中で、世界経済は歴史的な低迷に陥っている。
このコロナショックでは、まず、供給面でのショックが生じた。人同士のコミュニケーションが制限され、人の移動が滞ることで、その結果として、生産活動や物流が停滞し、物資の不足が生じることとなった。国際分業により国境を越えるサプライチェーンが形成される中で、人の移動の制限や物資の不足に伴ってサプライチェーンの途絶が発生した。また、感染が世界に拡大する中で、サプライチェーンの途絶は世界的な現象となり、需要の停滞と並行して世界的に生産活動が低迷している。供給面では、ロックダウン(都市封鎖)や営業自粛に伴って、不要不急のエンターテインメントサービスやレストランのイートイン営業の停止も見られている。このように、感染の抑制のために供給制約が発生している。そして、供給制約により需要が満たされず、供給ショックは需要面にも波及している。
コロナショックでは、需要面にもショックが生じている。感染拡大の抑制のための外出制限や自粛、渡航制限の導入などに伴い、人同士が接点を持つ対面サービスの需要が急減し、観光や宿泊、航空などでは前例の無い規模で需要が縮小している。物についても耐久財の需要が急減し、その需要の減少が輸出・生産の大幅な減少をもたらすことで、需要低迷と供給低迷が相互に作用する状況が生じている。
このように、コロナショックは需給の両面にショックが起こるものであり、東日本大震災のような災害や世界金融危機のような金融危機とは異なる、全く新しい種類の経済ショックである。
さらに、コロナショックは所得・雇用面にも波及している。対面接触を行うサービス業を中心として雇用に大幅な影響を及ぼしており、米国では世界金融危機時を越え、1930年代の大恐慌時以来の失業率となっている。感染の先行きの不確実性や失業の増加、所得の低迷は、消費・投資の手控えによる需要減・供給減と危機の連鎖を生んでいる。そして、新型コロナウイルスの感染は中国から欧米、新興・途上国へと深刻さを増しながら全世界に拡がっており、全世界で経済が低迷するという異次元の経済危機に発展している。
そこで、2020年版通商白書においては、現在のコロナショックという危機に注目し、過去・現在・未来のグローバリゼーションの姿を踏まえながら、人や物、資金、アイデア(技術・データ)の交流という観点から世界経済を分析し、現在進行中の危機の教訓を踏まえ、世界や日本が今後目指すべき方向性を示したい。
1.世界経済のグレート・ロックダウン
まず、コロナショックの深刻度を確認しよう。現在もコロナショックは深刻さを増しているが、世界の経済危機の状況について、これまでに見られた感染、各国・地域の経済や金融市場の動向から確認する。
(1)新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大
世界保健機関(WHO)によれば2020年5月29日時点において、新型コロナウイルスの累計感染者は世界全体で570万人を超え、死者は35万人を上回る1。国別の感染者は米国が160万人超と世界最多であり、ブラジル、ロシアが続いている。
この新型コロナウイルス感染症は、当初、中国を中心として感染が広がっていた。その中国における感染の中心であった湖北省を中国政府は封鎖し、一般市民は特別な事情がない限り家を出ることができない状況となった。その後、世界に感染が広がるに従って、欧米やアジア、その他の地域においても都市を封鎖し、人の移動の制限は広がりを見せた。
世界への感染拡大の中で、WHOのテドロス事務局長は新型コロナウイルス感染症について、「パンデミック(世界的な大流行)とみなせる」と表明した。日本においても、4月7日に安倍総理が緊急事態宣言を発出した。
1 WHO Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/![]()
(2)世界経済のグレート・ロックダウン
この新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界経済は異次元の経済危機に直面している。しかし、新型コロナウイルスの感染が当初中国を中心としたものであった2020年2月ごろまでは、感染症による世界経済への影響は大きく見込まれていなかった。
主要な国際機関による経済見通しについては、2020年2月のIMFのゲオルギエバ専務理事の会見においては、2020年の世界の経済成長率は0.1%の下方修正に留まるものとされていた。3月2日に公表された経済協力開発機構(OECD)の経済見通しにおいては、感染が中国を中心としたものに留まる状況を前提としたベースケースでは世界の経済成長率を0.5%の下方修正、世界に感染が拡大をするドミノケースでは成長率の1.5%の下方修正を行った。
その後、感染が世界の他の地域に拡大するにつれ、経済危機の深刻さが認識されていった。IMFのゲオルギエバ専務理事は3月23日の声明において、世界経済は世界金融危機と同程度かそれ以上の景気後退に陥ると警鐘を鳴らした。4月のIMFの世界経済見通しにおいては、世界経済は1930年代の大恐慌以来の景気後退に陥るとし、2020年の経済成長率の見通しは世界でマイナス3%、先進国はマイナス6.1%、新興国はマイナス1.0%と、大幅に下方修正した(第Ⅰ-1-1-1表)。これは、大恐慌以来の最悪の世界経済危機となる見込みであり、IMFはグレート・ロックダウン(大封鎖)と表現する。
第Ⅰ-1-1-1表 IMF世界経済見通し(2020年4月)
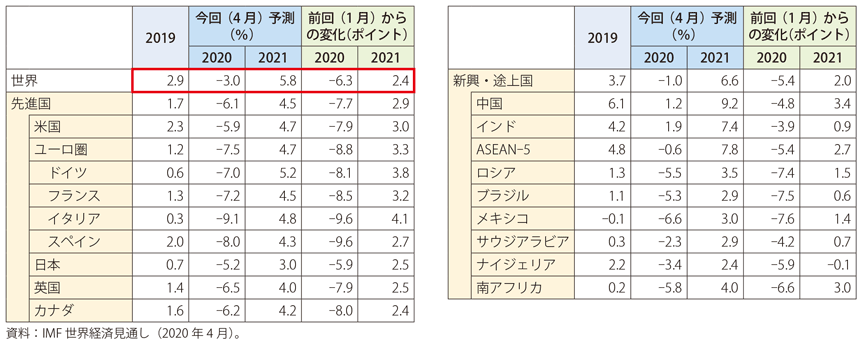
なぜ世界経済の成長見通しは徐々に下方修正を行うことになったのだろうか。第一に、感染症の拡大が時差を伴って世界に広がっていったことが挙げられる。当初は中国を中心とした感染であったが、2月の後半以降に欧米に感染が拡大し、感染の拡大と同様に経済活動の下押しも時差を有しながら世界に広がっていった。その結果、経済見通しについても、感染症の影響の深刻さは時差を伴いながら織り込まれていった。第二に、人同士の接触の制限に伴う経済ショックは、供給ショックと需要ショックの双方から影響が発生するものであり、災害や金融危機といった過去の経済ショックと異なる性質を有する。災害は主に社会資本の毀損といった供給ショックであり、金融危機は主に需要面でのショックである。このような過去のショックと異なる感染症の経済危機であるため、影響の深度を把握することが困難なものとなっている。第三に、感染の収束の時期が不透明ということが挙げられる。収束を見通すことにより最終的な経済影響を予測することが容易になるが、現時点においても感染の収束の時期は不確実である。感染が拡大を続けており、結果的に経済への影響も拡大を続けている。第四に、経済予測の性質がある。リアルタイムのデータが十分に存在しない中での予測となることで、経済予測自体は過去の経済データを平滑化したものとなりやすいという性質がある。リアルタイムのデータが限られ、前例のない経済ショックにおいては、危機の影響は過小評価される(第Ⅰ-1-1-2図)。
第Ⅰ-1-1-2図 経済見通しの下方修正
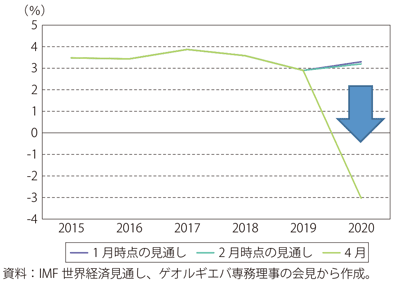
(3)世界貿易の急速な縮小
世界経済の停滞、人や物の移動の制限は貿易にも影響を及ぼしている。世界貿易機関(WTO)は4月8日に貿易見通しを公表した。その見通しでは、新型コロナウイルスの感染拡大により2020年の世界の財貿易は、2019年と比べて、楽観的なシナリオの場合では前年比で13%、悲観的なシナリオの場合では同32%減少すると予測した。つまり、世界金融危機時の貿易の減少(2009年、同12%減少)を上回る減少となる可能性が高いと指摘した2。
国・地域別では、ほとんどの国・地域において2020年の貿易量は前年比で10%を超える減少になるとし、特に北米、アジア地域からの輸出が深刻な影響を受けるとWTOは予測している。一方、アフリカ、中東、CISを含む「その他の地域」は、エネルギー資源の輸出への依存度が高く影響は限定的と指摘されている。業種別では財貿易においては電子機器、自動車等の複雑なバリューチェーンが構築されている業種が特に影響を受け、また運輸や旅行に対する制限により、サービス業はより深刻な影響を受けると指摘されている(第Ⅰ-1-1-3表)。
第Ⅰ-1-1-3表 世界貿易の見通し
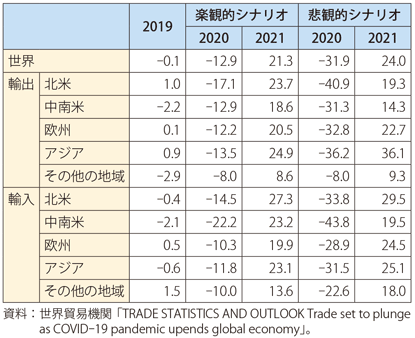
2 楽観的シナリオ:2020年後半に貿易量が回復を開始。悲観的シナリオ:貿易量の回復までより時間を要し、回復の程度も不完全という前提。
(4)世界の投資の急速な縮小
貿易と同様に投資も大幅な縮小が見込まれている。新型コロナウイルスの感染拡大により、中国などにおける需要減退やサプライチェーンの途絶が企業の投資活動を抑制することから、2020年から2021年の世界における海外直接投資が5%から15%減少するとの見通しを国連貿易開発会議(UNCTAD)は3月8日に公表した。しかし、感染が世界に拡大するにつれ、UNCTADは投資の見通しを下方修正し、2020年から2021年の世界の海外直接投資がその予測を3~4割下回るとの見通しを3月26日に公表し、6月16日に公表された世界投資報告書においても同様の見通しを示した。
(5)中国経済の急減速
次に、各地域における経済ショックの影響を確認しよう。まず、新型コロナウイルスの感染の当初の震源地であった中国においては、2020年初頭からその影響の深刻化が見られた。2020年1-2月には、小売売上高や工業生産、固定資産投資といった経済活動が前年比で10%を越える縮小となった。また、貿易についても2020年1-2月には、輸出の減少が前年比で17%、輸入の減少が前年比で4%となった。これは、中国における生産活動や物流の停滞が要因となり、輸出が輸入よりも相対的に大きな影響を受けていたことを示しており、当初は供給ショックの色彩が強かったことが示唆される。3月においても、輸出の低下幅が輸入の低下幅よりも大きい状況が継続しており、特に欧米への輸出の停滞が見られ、世界の需要の低迷が中国の輸出の低迷につながることが示されている。3月に入っても小売売上高は前年同月比15.8%減少と引続き低迷が見られたものの、生産活動の再開に伴って3月には工業生産については前年同月比1.1%減少とマイナス幅は大きく縮小しており供給サイドの回復が見られた。その中で、中国の2020年1-3月期のGDPの成長率は、前年比で6.8%のマイナス成長となり、四半期の統計の入手できる1992年以来初めてのマイナス成長となった(第Ⅰ-1-1-4図)。
第Ⅰ-1-1-4図 中国のGDP成長率(前年比)
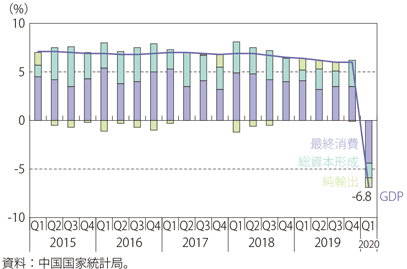
(6)欧州
中国の次に新型コロナウイルスの感染の震源地となった欧州では、2020年の2月下旬以降、イタリアから、フランス、スペイン、ドイツ、英国へと急速に感染が拡大し、感染者数の世界上位10か国のうち5か国を欧州の国が占めている(5月29日時点)。感染予防措置として、ロックダウン、外出制限や渡航禁止措置等の移動の制限のほか店舗等の閉鎖や国境の実質上の封鎖等が実施され、経済活動は停滞した。欧州域内外での人の移動の制限は、観光や小売、外食等の産業に深刻な影響を及ぼしている。欧州は観光への依存度が高い国が多いことも影響を大きなものとしている。
6月9日に公表された1-3月期のユーロ圏の実質GDP成長率は、ユーロ圏では前期比年率でマイナス13.6%、フランスではマイナス19.7%となるなど、ユーロ圏の成長率としては過去最悪のものとなった。ロックダウンが本格化した4-6月期においては、更なる悪化も予測されている(第Ⅰ-1-1-5図)。
第Ⅰ-1-1-5図 欧州のGDP成長率(前期比年率)
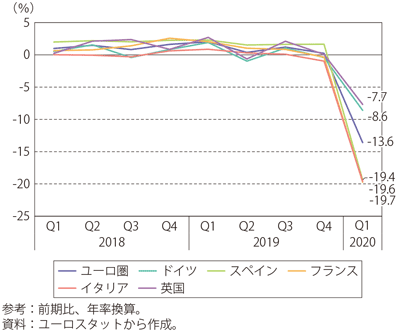
(7)米国
現在、米国では世界で最大の感染者を数えている。感染拡大を受けて、3月13日には国家緊急事態宣言が出され、3月27日には、米国内の感染者数が8万5千人を超え、中国を超えて世界最大となった。3月の後半からカリフォルニアやニューヨークといった主要都市においてロックダウンが導入された。
その中で、生産活動や消費活動は大幅に制限されており、雇用面での影響も深刻なものとなっている。新型コロナウイルスの感染拡大後に4,000万件を超える新規での失業保険が申請されており、4月の失業率は14.7%にまで上昇した。これは、失業率が10%にまで上昇した世界金融危機時を越える数値であり、失業率が25%を越えた大恐慌に次ぐ雇用情勢の悪化となっている。5月28日に公表された実質GDP成長率についても、2020年1-3月期は前期比年率でマイナス5.0%に落ち込んだ。また、4-6月期のGDPは、前期比で年率4割の低下をするという見通しも米国議会予算局からは示された(第Ⅰ-1-1-6図)。
第Ⅰ-1-1-6図 米国のGDP成長率(前期比年率)
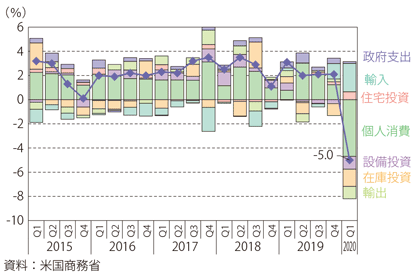
(8)アジア
アジアにおいては、いくつかの国において新型コロナウイルスの感染者が1月から確認されるなど、比較的早期から感染の広がりが見られた。その中で、国によって対応のばらつきが見られ、韓国や台湾のように感染を封じ込めた国から感染爆発によりロックダウンを行う国まで見られる。
アジアの特徴としては中国との距離が近いことが挙げられ、また、産業としてもマカオ(GDPの74%)、カンボジア(18%)、タイ(13%)のように、観光に依存する国・地域が多く、渡航制限によって影響を受けやすい国・地域が見られる。さらに、フィリピンのように海外からの送金受取への依存度が高い国(GDP比10%)も見られており、世界経済の変動や海外の情勢変化に影響を受けやすい国・地域も見られる。
2020年1-3月の実質GDP成長率(原数値・前年同期比)は、ベトナムが+3.8%と前期(2019年10-12月期)の+7.0%から大きく減速し、タイが-1.8%、シンガポールが-0.7%とマイナスに転じた(第Ⅰ-1-1-7図)。
第Ⅰ-1-1-7図 アジアのGDP成長率(前年比)

(9)中南米
中南米においては、2月26日にブラジルにおいて初の感染者が確認され、27日にはメキシコ、その後周辺国でも確認され、感染が拡大している。ブラジルもメキシコも最初の感染者はイタリアからの帰国者であった。
中南米における感染者数は3月以降急速に増加し、ブラジルは5月29日時点では世界で2番目に感染者数の多い国となっている。
ブラジルでは、3月下旬、陸路、水路、空路からの外国人の入国禁止といった制限措置が実施されたほか、経済省は5月下旬に4,177億レアル(約8兆1,242億円)の緊急経済対策を発表した3。メキシコでは、政府は3月30日、「不可抗力の衛生上の非常事態」と宣言し、保健省は3月24日、人の移動を伴う業務を差し控える要請を発出している。
メキシコの2020年第1四半期の実質GDP成長率は前期比年率で-4.9%と11年ぶりの大幅下落となり、中央銀行は、2020年の経済成長率見通しを従来の0.5~1.5%から、-4.6~-8.8%に下方修正した。また、中南米各国で製造業の工場操業停止が実施され、生産、輸出入の大幅な減少といった影響が現れている(第Ⅰ-1-1-8図)。
第Ⅰ-1-1-8図 メキシコのGDP成長率(前期比年率)
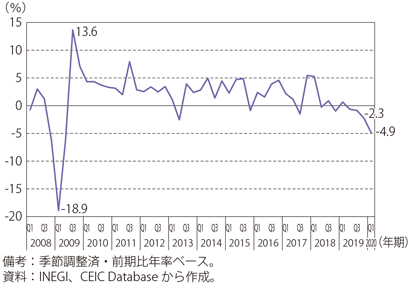
(10)資源
新型コロナウイルスの感染拡大は資源価格にも影響を与えた。WTI原油先物は2020年初めには61.18ドルであったが4月20日に-37.63ドルと史上初のマイナスの価格となった(第Ⅰ-1-1-9図)。その要因としては生産活動の停滞や外出制限等により資源への需要が減退したことや、原油の貯蔵設備が限界に近づいているという懸念から、原油現物を保有するコスト意識の高まりが警戒されたためとされている。
第Ⅰ-1-1-9図 WTI原油先物価格
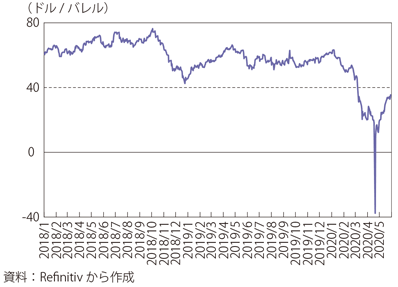
その一方で、OPECプラスが5月1日から日量970万バレル規模の減産を開始するなど資源の需給のバランス調整に向けた動きも見られている。
資源の動向については、第2章において分析を行う。
(11)金融市場
新型コロナウイルスの感染拡大は実体経済へのショックではあるが、金融市場も大きく影響を受けている。株価が大幅に下落し、2020年年初より株価が3割ほど低下する時期もあり、金融市場の混乱の中で、過去最大の株価の上げ幅、株価の下げ幅を記録することも見られた(第Ⅰ-1-1-10表)。
第Ⅰ-1-1-10表 株価の歴史的上昇・下落(日経平均、米国ダウ30種株価指数)(2020年 5月31日時点)
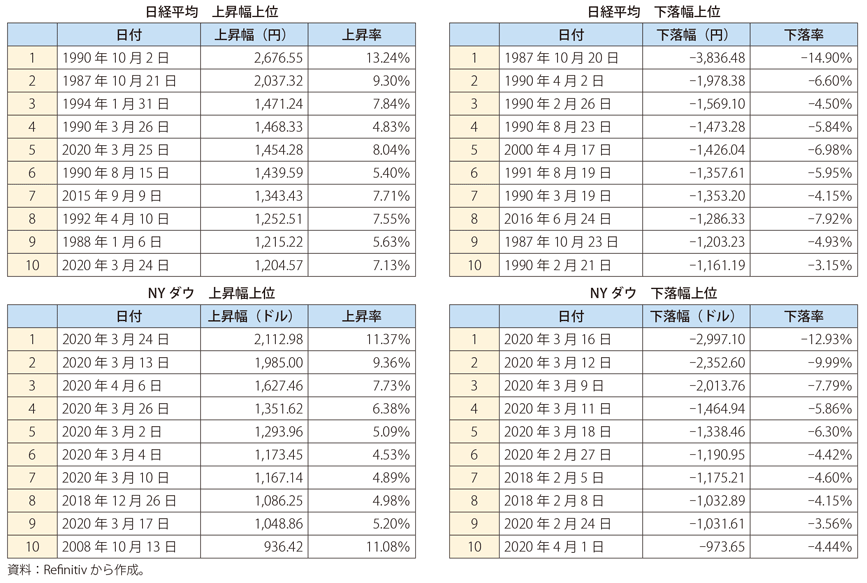
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う金融市場の動揺で見られた現象の一つに、現金、特にドルの現金への需要の高まりを挙げることができる。過去、経済危機においては、安全資産、つまり金(きん)や国債といった資産への需要が増し、価格が上昇する(国債の場合では国債金利が低下する)ことが見られた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、貯蓄の取り崩し、すなわち資産を売却することでのドルの現金化が見られ、いわゆる安全資産の価格も下落し、その一方で、ドルが上昇することとなった。その中で、ドルの需要の拡大に対応するため、米国連邦準備制度はドル供給を各国中央銀行と協調して拡大し、それにより、ドル現金の需要増加に対処した4。第Ⅰ-1-1-11図の通り、ドルに交換する際の上乗せ金利であるベーシススワップレートを見れば、ドル不足により急速にそのレートが低下する(ドル需要により上乗せ幅が高まる)ことが見られた。
第Ⅰ-1-1-11図 対ドル 通貨ベーシススワップ(1年物)
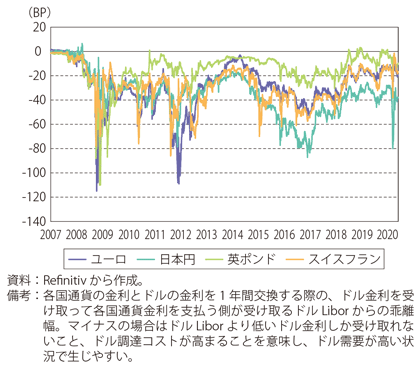
また、新興国ではクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)が上昇するなど、ソブリンリスクが意識される局面に突入している。これは資源や観光に依存する経済に大きなリスクが集中しやすい状況となっていると考えられる。格付会社のスタンダード・アンド・プアーズは3月26日にメキシコのソブリン格付けを1段階引き下げ、「BBB」とした。3月27日にはムーディーズが南アフリカのソブリン格付けを「Baa3」からジャンク級に当たる「Ba1」に引き下げた。その後も、いくつかの国において格付けの引き下げが見られた。5月22日にはアルゼンチンが国債の利払いを行わず、形式的な債務不履行状態となった。これらは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響も一因となっている。主要な金融指標を第Ⅰ-1-1-12図に示している。
第Ⅰ-1-1-12図 金融市場の指標(株価、金利)
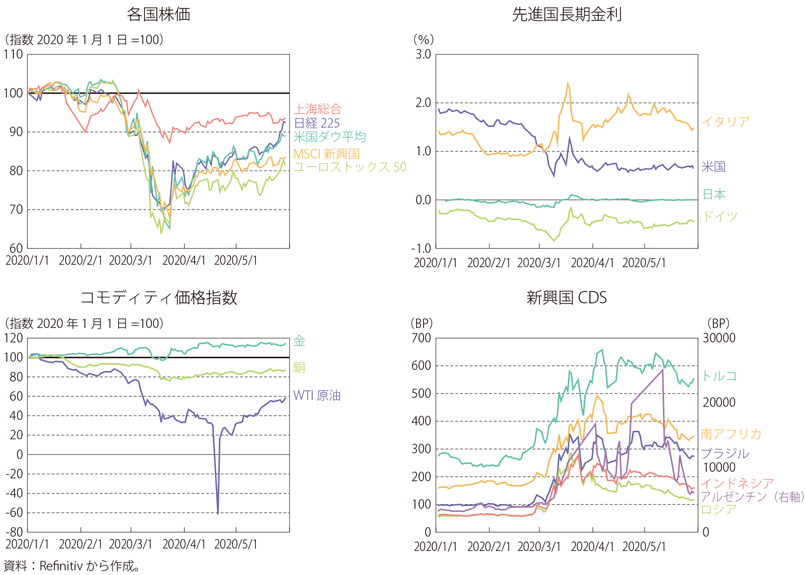
このように、世界中で経済の急速な減速が見られており、実体経済、金融市場に大きな影響が発生している。
このコロナショックの本質は、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの危機である。過去に見られた局地的な災害や金融危機といった経済危機とは異なり、人と人との対面での交流が制限されることで、供給、需要両面に甚大な影響が発生し、所得や雇用へのショックにつながり経済危機の連鎖につながることに特徴がある(第I-1-1-13図)。以下で、供給ショック、需要ショック、所得・雇用ショックの観点から、コロナショックを整理しよう。
第Ⅰ-1-1-13図 コロナショックの概念図
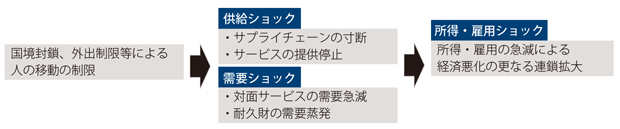
4 3月15日に、FRBは他の5カ国の中央銀行と協調して、市場へのドル資金の供給を強化した。その後、3月19日にこのスワップラインの取り決めに、新たに9行の中央銀行を加えた。3月31日には、FRBは、米国債を担保とした海外中銀・当局向けのレポ取引の実施を公表した。
2.供給ショック
コロナショックの本質は、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの制限である。感染抑制のためにフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションに制限が発生し、人や物の移動に制限が生じ、その結果、供給制約が発生している。ここでは、供給ショックからコロナショックを捉えよう。
(1)サプライチェーンの寸断
供給面については、感染症の拡大を抑止するために人や物の移動・交流を制限することで、労働者が生産活動に従事できず、また、国境を越えた移動が困難になることが見られた。不要不急の経済活動の停止を政府が要請することも見られ、生産活動にも影響が生じた。さらに、輸送面においても検問に要する時間が増加することも見られた。
その中で、世界的にサプライチェーンの途絶が生じた。国際分業により国境を越えるサプライチェーンが形成される中で、一カ国でも生産活動が停止することで、他国において物資を入手することができず、その結果として、生産の停止が他国に波及することとなった。
2020年2月の日本の貿易は、中国からの輸入が前年同期比で47.1%の減少となり、新型コロナウイルスの感染が拡大していた中国での生産の停止が、日本の輸入の大幅な縮小に寄与した。その結果、国境を越えたサプライチェーンを通じた影響の波及を受け、日本で中国からの必要な部材を入手できず、生産活動を停止せざるを得ない状況が見られた。財別で貿易状況を見ると、中国からの自動車の部分品の輸入は2020年2月に前年同月比で46.8%の減少となったが、中国からの部品供給が滞ることで日本の国内の自動車の生産にも影響を及ぼした。(第Ⅰ-1-1-14図)。
第Ⅰ-1-1-14図 日本の中国からの輸入(前年同月比)
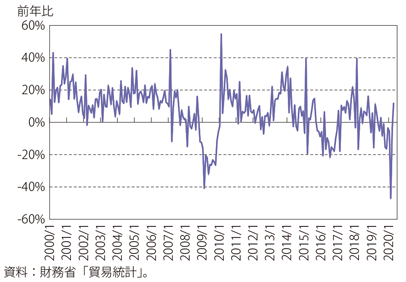
サプライチェーンが労働集約的であり、また、複雑なネットワークのもとで生産が行われている場合、人の移動の停滞や物の不足により、生産活動に支障が生じる傾向が見られる。供給と需要が相互に作用する中で、サプライチェーンの途絶という供給面の要因と感染症による需要の低迷という需要面の双方の影響を受け、3月中旬以降は、欧州や米国においても日本の現地企業が工場の稼働を停止することも見られた(第Ⅰ-1-1-15表)。欧州においては、国境を越えた物資の移動が制限される中で、EU内においてもサプライチェーンが寸断されることとなり、域内で国境を越えた生産体制が構築されている自動車産業などにおいて生産の停止が見られた。
第Ⅰ-1-1-15表 2月中旬以降の日本企業の海外生産の動向
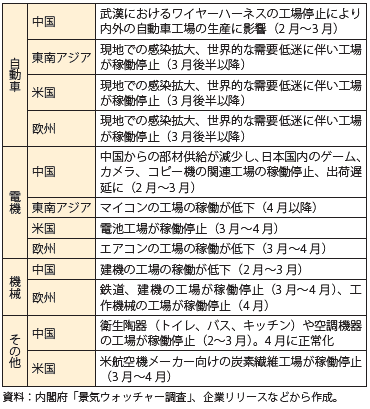
このように、国境を越える生産・販売のネットワークの構築は、平時には生産・販売を効率化するものであるが、世界的な経済ショックが発生するような危機時には、国境を越えたサプライチェーンの寸断といった形で脆弱性ともなる。
(2)物の移動制限
このサプライチェーンの途絶の要因の一つとして、物の移動制限が存在する。国境の封鎖や旅客機のフライト停止により物流の停滞が見られ、欠かせない財の入手が困難となり、その結果サプライチェーンの途絶が発生することとなった。
また、物資に関する輸出制限・輸出規制も見られており、WTOの報告書によれば、4月22日時点で80カ国・関税地域において新型コロナウイルスの感染拡大を受けた輸出制限・輸出規制が導入されている5。対象品目は国により異なるものの、検査キットや防護服、体温計、人工呼吸器などについて輸出制限が行われている。また、食料の輸出の停止も見られている(第Ⅰ-1-1-16表)。
第Ⅰ-1-1-16表 物の移動の制限の例
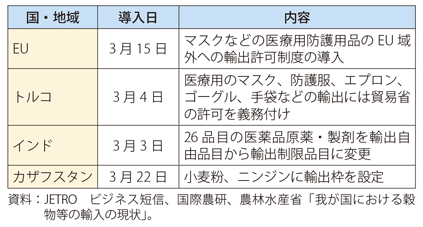
このような物資の移動の制限に対して、国際協調による対応も見られている。3月30日や5月15日に開催されたG20貿易・投資大臣会合において、物・サービスの自由な流通を確保し、経済活動を維持していくため、G20として貿易面でも連携を強化していくことが確認された。
5 WTO “EXPORT PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS, INFORMATION NOTE”. 2020年4月23日
(3)人の移動の停滞
新型コロナウイルスは人と人の接触に伴って感染が拡大をするものであった。そこで、感染拡大を抑制するために、外出制限や移動の制限、海外との往来の制限が各地で導入された(第Ⅰ-1-1-17表)。
第Ⅰ-1-1-17表 人の移動に関する各国の動き
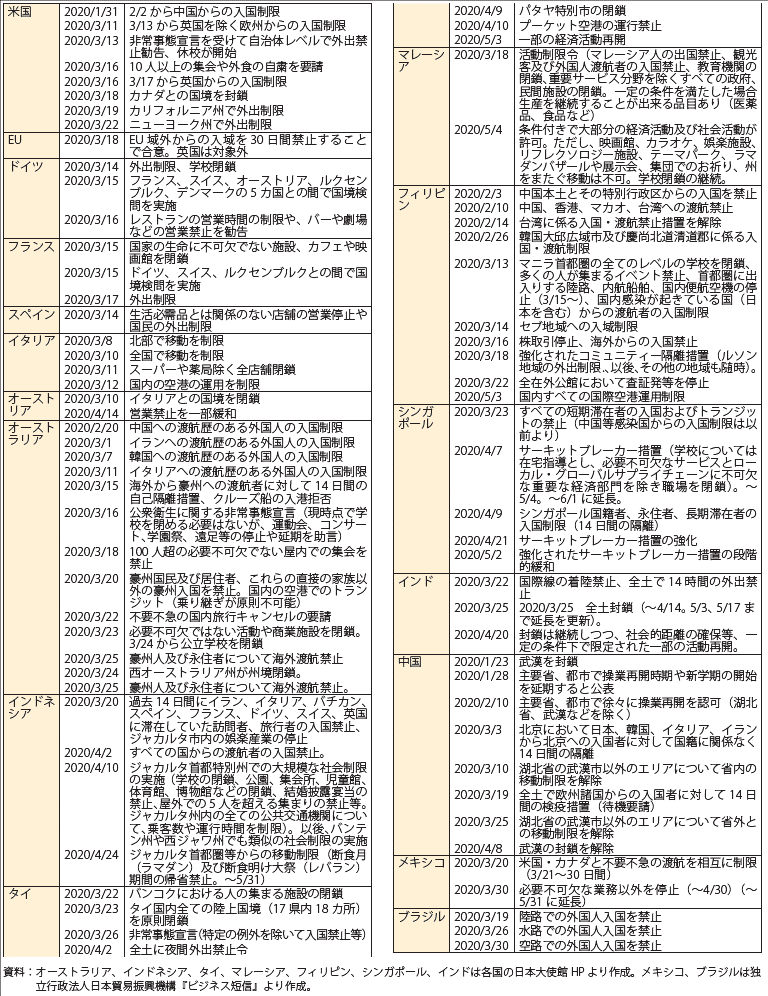
中国では春節で故郷に戻った出稼ぎ労働者が職場に戻ることができず、生産活動の再開後にも、工場の生産活動や物流に影響が見られた。また、欧州では、季節労働者の減少による労働力の減少により農作業の人手不足が懸念される事態となっている。農産物の輸出大国であるフランスでは、農業の従事者のうち8割を外国人に頼っており、EU域外からEU域内への渡航を原則として禁止するEUによる渡航制限の導入により、労働者の確保に支障が生じている。
(4)対面サービスの提供の停止
さらに、感染の拡大を予防するための経済活動の停止も見られている。都市封鎖や営業自粛に伴って不要不急のエンターテインメントサービスやレストランのイートイン営業が停止されるなど、感染の抑制のために供給制約が発生しており、需要は存在するものの需要が満たされない状況が発生している。日本においても2020年3月から、遊園地・テーマパークやフィットネスクラブ等の娯楽業の活動指数は急速に悪化した。
東日本大震災といった災害においては生産設備や社会資本の毀損による供給ショックであった。新型コロナウイルスの感染拡大では生産設備や社会資本は毀損していないものの、人と人の接触の制限に端を発して、以上のように、生産の停止、人・物の移動の制限、サービスの提供の停止が見られ、それが世界の供給を抑制している。このように過去の危機と比較して、供給ショックの特徴の違いが見られる。
第Ⅰ-1-1-18図 日本の娯楽業関連の指数の推移
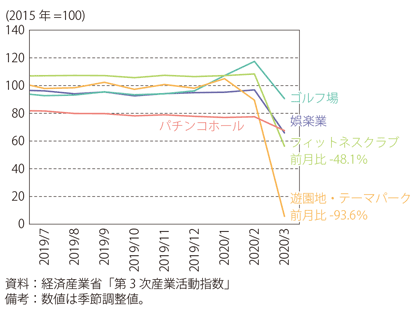
3.需要ショック
コロナショックの本質であるフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの制約は、需要面にも影響を及ぼしている。感染症の拡大に伴って需要に変化が見られており、対面での交流が必要な活動については需要の抑制が見られる。その一方で、電子商取引(EC)のように人同士の直接の交流を必要としない活動は活況を呈している。
伝統的に、サービス業は生産と消費の同時性が特徴である。製造業においては、物を輸送し、また、在庫を蓄積することにより、異なる場所と異なる時間での財の提供が行われる。その一方、サービス業においては伝統的には生産と消費が同地点で同時に発生する。このため、感染症の拡大に伴い人同士の交流が制限される中で、特にサービス業の需要に大きな影響が現れている。一方で、この同時性を克服するサービスの拡大も見られている。
3つの分類からサービスの需要動向を点検しよう。第一に、生活必需品の提供である。これは、食料や医薬品のように生活に必要な物資を提供するサービスである。同時性に伴って感染症のリスクが存在したとしても需要が変わらずに存在し、人同士の交流の制限下においてもエッセンシャルビジネスとしてサービスの提供が継続されるものである。第二に、人と同士との交流の制限が需要の縮小をもたらすものである。典型的には観光、宿泊、外食のように、人同士の交流が制限されることにより需要が減少するものである。外出制限や自粛、渡航制限の導入などに伴い、人同士が接点を持つ対面サービスの需要が急減した。第三に、第一や第二のサービスを代替する形で、対面ではなくオンライン上で交流の行われるサービスが拡大している。これは、サービスの同時性を乗り越えるものである。新型コロナウイルスの感染拡大後にはECやオンラインでの映像提供サービスなどの対面の活動を必ずしも必要としないサービスは需要の拡大が見られている。
このように、サービス業はその性質に応じて、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの制約による影響が異なって現れている。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響はサービス業にとどまるものではなく、耐久財のように財についても消費への影響が見られている。
(1)生活必需品のサービス
食料品などの生活必需品を提供するサービスは、ロックダウンや不要不急のサービスの営業停止を行った地域においても提供が継続された。
日本の4月の家計調査では、遊園地入場、パック旅行、鉄道運賃等の消費が落ち込み、ゲーム機、即席麺、電子レンジ等の消費が高まる動向が見られた(第Ⅰ-1-1-19図)。
第Ⅰ-1-1-19図 日本の消費動向(2020年4月家計調査、主な品目など)
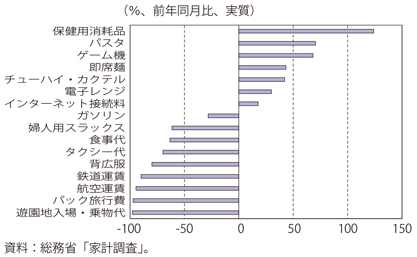
(2)人と人との交流を通じたサービス
その一方で、人と人との交流によるサービスは需要の急減が見られた。感染症の予防のために接触を避け、イベントの中止や自粛の要請も行われた。さらに海外では、ロックダウンによる外出の制限もあり、人と人の交流自体も縮小した。
GoogleはGoogleマップを基として人の移動状況を把握する、COVID-19コミュニティモビリティレポートを公表している。小売・娯楽(Retail & recreation)、食料品店や薬局(Grocery & pharmacy)、公園(Parks)、交通機関(Transit stations)、職場(Workplaces)、住宅(Residential)の分類での人の滞在を示しており、各国地域で人の移動が低下しており、3月22日にロックダウンが始まったニューヨーク州では、4月11日時点では外出を表す公共交通機関が65%減り、自宅での活動の増加を示す住宅が18%増えている(第Ⅰ-1-1-20図)。
第Ⅰ-1-1-20図 ニューヨーク州の人の移動
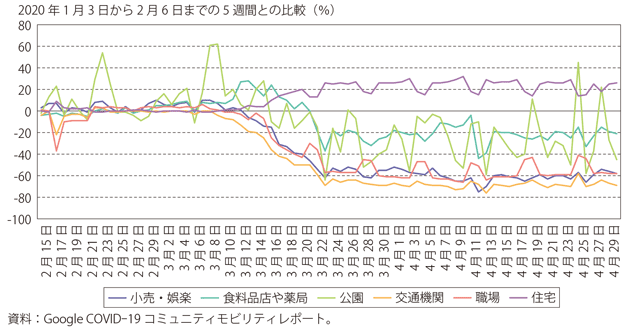
国内における外出だけではなく、各国が渡航制限や渡航中止の勧告を発出する中で、国境を越えた人の移動も停滞している。需要面でこの影響が顕著に見られているものは観光や宿泊である。2020年初頭から各地域において観光客数が大きく減少している。2020年4月の訪日外客数は前年比で99.9%減少と大幅なマイナスを記録している。
国連世界観光機関(UNWTO)は、2020年1月時点では2020年の世界の観光が3%から4%の増加となると見込んでいたものの、3月5日時点で1%から3%の減少に下方修正し、3月26日には20%から30%の減少へと大幅な下方修正を行い、さらに5月7日には58%から78%の減少と見通しを一段と下方修正した(第Ⅰ-1-1-21図)。これは、SARSの影響を受けた2003年の減少(0.4%減)、世界金融危機の影響を受けた2009年の減少(4%減)を大幅に上回る。
第Ⅰ-1-1-21図 観光客数の見通し(国連世界観光機関)
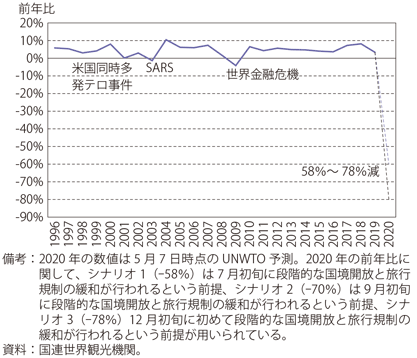
世界のインバウンド観光収入は2018年に1兆6,493億ドルとなり、世界のGDPの1.9%を占めていた。日本においてインバウンド観光収入のGDPに占める割合は2018年時点で0.9%と世界平均より低いものの、2010年の0.3%から3倍となり急速に拡大している(第Ⅰ-1-1-22図)。インバウンド観光収入がGDPに占める割合は太平洋島嶼国において21.4%、ギリシャにおいて9.9%、スペインにおいて5.7%を占める。インバウンド観光収入への依存が高い国は、観光需要が世界的に低迷をすることでより大きな影響を受けている(第Ⅰ-1-1-23図)。
第Ⅰ-1-1-22図 インバウンド観光収入のGDPに占める割合(世界、日本)
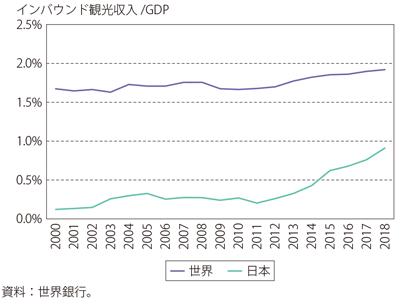
第Ⅰ-1-1-23図 インバウンド観光収入のGDPに占める割合(2010年、2018年)
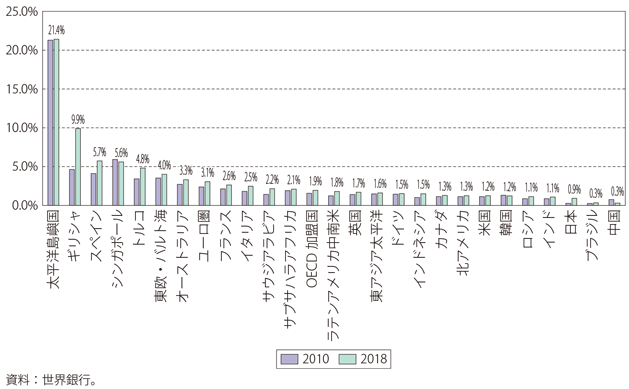
世界全体における商業フライト数は、2月に前年同月比で4.4%の減少となり、3月前半には前年同月比で7.2%減少となった6。世界のフライト数は2月末時点に比べて4月前半には6割減となった(第Ⅰ-1-1-24図)。国際航空運送協会(IATA)は、2020年の航空収入が前年比で20%の減少になる可能性があると3月5日に公表したが、その後、3月24日には2020年の航空収入が前年比で44%の減少となる可能性があると示した。
第Ⅰ-1-1-24図 世界のフライト数(国際線・国内線)
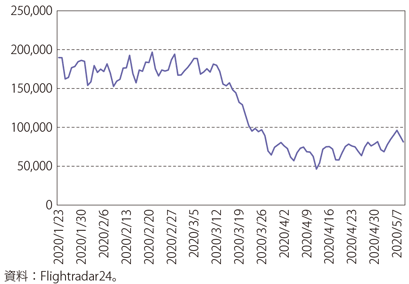
運行数の減少だけではなく、運行便においても乗客数の減少が見られている。中国においては2月に3大航空会社の運行数が前年同月比で60%の減少となったが、利用者数は前年比80%の減少と、運行数以上の大幅な減少となった7。
インバウンド観光や空運業に限らず、観光業全般のGDPに占める割合は、2017年時点で、スペインにおいて11.8%、フランスにおいて7.4%と、多くの国で観光業への依存が見られており、観光需要の縮小は経済の下押し要因となっている、(第Ⅰ-1-1-25図)。
第Ⅰ-1-1-25図 観光産業のGDPに占める割合
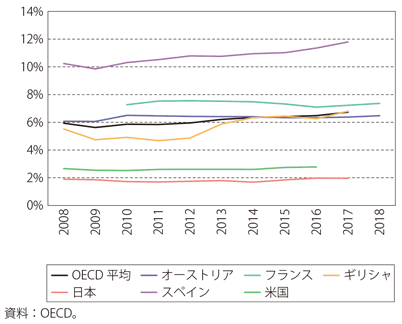
観光と同様に、外食産業も大きな影響を受けている。各国ではレストランではイートインではなく持ち帰りへの需要に代替されており、米国ではレストランの予約数が3月21日以降は前年同期比で100%の減少となった(第Ⅰ-1-1-26図)。ドイツ、英国においても3月9日以降に前年同期比で2桁の減少となり、3月後半には前年同期比で100%の減少となった。
第Ⅰ-1-1-26図 主要国のレストラン予約数
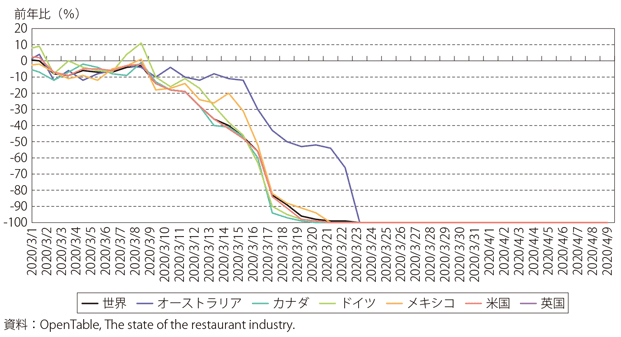
外食・宿泊産業の各国生産に占める割合は、キプロス(6.5%)、スペイン(5.8%)を筆頭に観光が盛んな国において高いものとなっている(第Ⅰ-1-1-27図)。
第Ⅰ-1-1-27図 外食・宿泊の各国生産に占める割合(2014年)
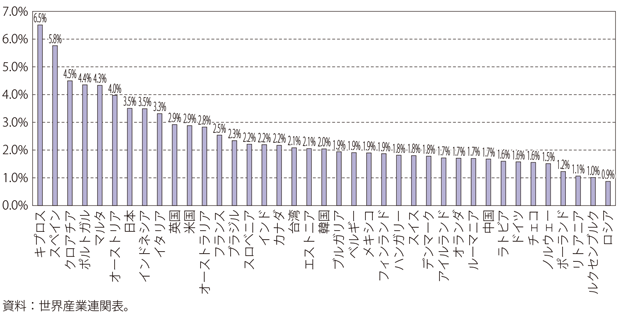
6 Commercial air traffic down 7.2% in March 2020
https://www.flightradar24.com/blog/commercial-air-traffic-now-down-7-2-in-march/![]()
7 Chinese Airlines Report Passenger Slump for February
https://www.marketscreener.com/CHINA-EASTERN-AIRLINES-CO-6496810/news/Chinese-Airlines-Report-Passenger-Slump-for-February-30186617/![]()
(3)人と人の接点を代替するサービスの拡大
新型コロナウイルスの感染の拡大は需要の変化の動向を明らかにするものでもあった。近年の経済のデジタル化は人と人の接点を代替するサービスを生み出しており、オンラインで注文をし、物の受け取りを行う場面でのみ物理的な接触が行われるサービスがある。また、全てオンライン上で完結するサービスもあり、映画館やレンタルビデオを代替するものとして、映像ストリーミングのサービスが急速に拡大をしている。このような物理的、時間的な同時性を乗り越えるサービスは、人と人との接触、つまり、感染症のリスクを低下させるものであり、新型コロナウイルスの流行に伴い、巣ごもり消費とも言われる需要が拡大している。また、オフラインの活動を代替するビデオ会議システムの利用も急増しており、3ヶ月で20倍に拡大したサービスも見られた。
このようなサービスは、社会的距離の確保というトレンドの中で、フェイス・トゥ・フェイスの活動をオンライン上で代替するものである。このようなオンライン上のサービスの拡大は、今後のオンライン、オフラインそれぞれの活動に不可逆的な変化をもたらす可能性もあることに留意が必要であり、その機会を活用することが日本にとっても重要である。これは、第Ⅱ部第1章第6節や第2章第5節・第3章第2節においても分析する。
(4)耐久財需要
このような対面のサービスの消費にとどまらず、耐久財の需要にも大きな変化が生じている。中国では自動車の販売が2月には前年同月比で79%減少、3月には43%減少となった。日本の新車販売は3月には前年同月比で9.3%減少となった。同様に、欧米、アジアにおいても、3月の自動車販売は大幅に減少した。このように世界で自動車の需要が蒸発する中で、各国で自動車の輸出・生産の大幅減少をもたらしている。また、衣料品のような半耐久財についても外出制限・自粛により需要が急速に減少している。
このような需要低迷は自動車の例に見られるように供給低迷にもつながるものであり、需要の低迷と供給の低迷が相互に作用する状況が生まれている。
4.雇用・所得ショック
このように、供給、需要双方にショックが生じる中で、雇用・所得環境も急速な悪化を示している。米国では4月の失業率が14.7%にまで上昇し、新規失業保険申請件数については、全米初の外出禁止令が出された週(3月19日、カリフォルニア州)以降の合計申請件数が4,000万件を越えている。中国においても失業率は一時6%を超える水準にまで上昇した。インドでも4月の失業率が23.5%となったというシンクタンクの推計も見られる。
雇用・所得への影響は、上記の供給・需要の影響が見られるセクターにおいて特に顕著に見られている。この雇用・所得環境の悪化により、消費や設備投資にも影響を与える懸念が生じている。先行きの不確実性や失業の増加、所得の低迷は、消費・投資の手控えによる貯蓄性向の上昇をもたらすと予測されている(第Ⅰ-1-1-28図)。
第Ⅰ-1-1-28図 欧州の家計貯蓄率の見通し
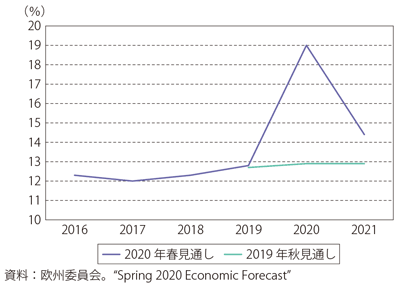
5.コロナショックのメカニズム
このように、新型コロナウイルスの感染が世界に拡大をする中で、その経済への影響は様々な国・地域や業種へと対象の広がりを見せていった。人・物資の移動の停滞、サプライチェーンの途絶から、観光や外食といった対面サービスの需要・供給両面の縮小、ロックダウンや外出自粛に伴う経済活動の停止まで、様々な社会経済活動が停滞する事態に発展していった。
過去の経済ショックと比較した経済危機の特徴として、このコロナショックの特徴は以下のように整理することができる(第Ⅰ-1-1-29表)。
第Ⅰ-1-1-29表 経済危機の類型
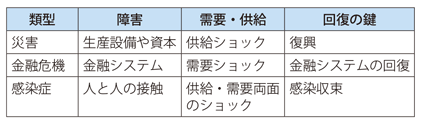
過去の経済危機として、供給ショックの例である災害を例に取ろう。地震や台風といった災害の場合には、生産設備が破壊され、道路や鉄道などの社会資本が毀損し、生産物の輸送が停止することで被災地域の活動の休止を余儀なくされる。需要は存在していても、供給制約が生じることで経済に短期的なショックが生じる。その後、災害からの復興、生産設備の復旧により、経済が回復することとなる。2011年の東日本大震災においては、社会資本・生産設備が破壊され、輸送網が寸断されることで一時的に生産活動が停滞した8。被災地域にとどまらず、サプライチェーンを通じて他地域においても経済活動が停止された。電力の供給制約も見られ、個人の消費活動も低下した。レジャー支出など必需性の低い消費を抑制し、計画停電による小売店や飲食店の営業時間短縮の影響が被災地以外にも見られた。このように、需要面でも影響は見られたが、災害は主に供給面のショックから波及するものである。
金融危機においては、金融システムが機能せず流動性が枯渇することにより企業の信用リスクが高まり、資金調達に支障が発生する。また、資産価格の再評価により、不良債権処理の必要が生じ、支出を抑えて貯蓄を蓄積するというバランスシート調整も発生する。その結果、金融危機は、民間部門の支出、つまり、家計消費や企業の設備投資の減少を伴う需要ショックとなって現れる。世界金融危機においては、耐久財の需要が特に低迷したが、これは可処分所得の低下ではなく主に心理的な落ち込みによるものであった9。このように需要が縮小する中で、企業収益が悪化し家計の所得が減少し、更に供給・需要を縮小させるという循環が生じた。
感染症による経済危機は以上の災害や金融危機による経済危機とは異なるものである。まず、物理的な社会資本や生産設備が直接損なわれたわけではない。また、金融システムも直接の影響を受けてはいない。人と人の接触に制限が生じ、その結果、物資の流通や生産が停滞するという供給面のショックが生じた。その一方で、人と人の接触が不可欠であるサービスの消費が低迷するという需要面でのショックも存在する。さらに、感染症の拡大を防ぐためにロックダウンを行うことで不要不急のサービスを停止し、社会的距離の確保のためにサービスの提供が停止された。また、外出制限や自粛に伴い様々な需要の抑制も見られている。このように、需要面・供給面の双方に発生するショックとなっている。それに伴い、米国のように急速に失業率が上昇し雇用や所得の悪化が生じ、不確実性に直面する中で消費や投資が急速に縮小し、危機の連鎖を生み、世界は異次元の経済危機に直面している。
8 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)(2011)によれば、16~25兆円の社会資本・住宅・民間企業設備への直接的被害があったとされる。
9 Olivier Blanchard, Macroeconomics (7th Edition). 2016年。
(1)供給サイドからの解釈
このコロナショックの解釈を巡っては様々な見解が示されている。生産の停滞が1970年代のオイルショックのように供給ショックとして現れる点に着目する議論がある。ハーバード大学のケネス・ロゴフ10は、感染の恐れが航空会社や世界的な観光需要に打撃を与え、予防的貯蓄を増加させるという需要ショックを認識する。その一方で、都市封鎖や感染の恐れのために働くことができず、サプライチェーンが寸断され、世界貿易が縮小することで生じる供給面のショックに、より着目する。供給サイドの景気後退がもたらす課題は、生産の急激な落ち込みと広範なボトルネックをもたらすことであり、全般的な供給不足が、最終的にインフレを押し上げる可能性があるとする。
10 Kenneth Rogoff “That 1970s Feeling.” Project Syndicate. 2020年3月2日
(2)供給から需要へ
その感染症による供給の停滞と需要不足は関係があり、感染症による景気後退の場合には供給不足が需要不足による景気後退を引き起こすことに着目するものがマサチューセッツ工科大学のイヴァン・ワーニングらである11。需要は外生的なものではなく、負の供給ショックが需要の急激な縮小を引き起こすことを示している。通常は供給と需要は独立であるが、資金制約に直面する家計が存在し、異なる企業セクターに影響が非対称に発生する場合には、その影響を受けたセクターの家計が消費を行うことができなくなる。そして、影響を受けなかったセクターまで含めて急速に経済全体の需要が縮小することとなる。さらに、企業の退出や雇用の喪失がその悪影響を拡大させることとなる。この概念を示したものが、第Ⅰ-1-1-30図である。
第Ⅰ-1-1-30図 感染症の経済ショックのメカニズム
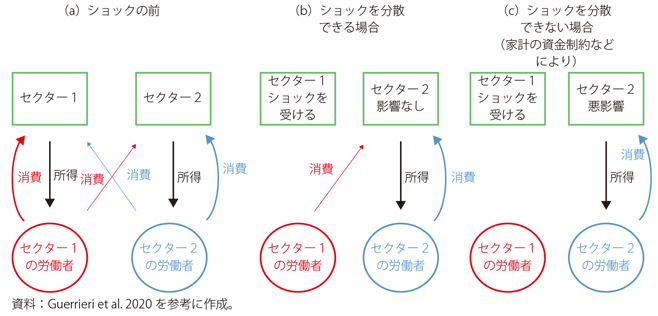
第Ⅰ-1-1-30図は、セクター1がショックを受ける場合における、セクター1と2という2つのセクターに対する効果を示すものである。ショックを分散できる場合には、セクター1とセクター2の労働者は収入をプールし、支出を継続することができる。しかし、(c)の不完全な市場では、第1セクターの労働者が第2セクターへの支出を削減するため、第2セクターも悪影響を受けることを示している。つまり、第1セクターの供給ショックが第2セクターの需要不足に波及し、それが不完全な市場によって増幅されることを示しているものである。
コロナショックにおいても実際に、サプライチェーン途絶や特定の産業への大きな供給ショックが経済全体の需要を大幅に押し下げるという状況が見られている。また、レジャー関連産業の営業自粛やレストランのイートインの停止により、消費者や企業による需要が存在をする場合でも消費を行うことができないことから、感染を抑制するための活動中止が引き起こした供給ショックの影響は大きい。ロックダウンの最中においても、対面の活動を代替するサービスは特に好調ではあるが、それが対面のサービスの需要減を完全に補うことができない場合には、供給のショックが経済全体の雇用や所得を縮小させ、経済全体に需要不足を生じさせることとなる。
11 Veronica Guerrieri, Guido Lorenzoni, Ludwig Straub, and Iván Werning. “Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages?” NBER Working Paper. 2020.
(3)外部性
もう一つの視点として、2つの外部性に注目をすることでコロナショックのメカニズムを理解できる12。新型コロナウイルスの感染の特徴として、感染者自身に対するリスクに留まらず、周囲の人へと感染を拡散させる外部性が存在している。この第一の外部性は、自身の感染を抑えるためだけの行為は社会的には過少、つまり、最適にはならないこととなる。そのため、無症状による感染拡大も見られる中で、社会的に最適な抑制策としては個人の最適な感染抑制策よりも厳しいものとなる。
第二の外部性として需要の外部性がある。上記第Ⅰ-1-1-30図の(C)に示したものであり、ある家計の所得の減少が他の家計の所得の減少につながるものである。また、需要の代替も発生している。これは、対面のサービスからオンラインでのECへの需要の移行などとして見られるものであり、対面サービスは急速な需要の縮小に直面している。さらに、自動車のような耐久消費財は過去の経済危機時には需要が先送りされることが見られたが、コロナショックにおいても同様に需要が急減している。
つまり、コロナショックのメカニズムとしては、人や物の交流の停滞から生じるサプライチェーン寸断や特定セクターの活動停止という供給面のショック、そして、外部性に起因するものや対面サービスの需要、耐久消費財の需要が急速に低迷するという需要ショックの双方に着目をする必要がある。これらの需給のショックから雇用・所得へのショックへと波及し、さらに、これが世界規模で発生したことに特徴がある。災害であれば局地的に発生し、世界金融危機は欧米を中心としたものであった。しかし、コロナショックにおいては世界全体が感染症に直面しており、全世界で経済が低迷するという異次元の経済危機となっている。これがコロナショックである。
12 楡井誠「コロナ禍の経済対策:社会的隔離・外部性・デジタル化」RIETI 2020年
6.感染症の見通し
感染症の収束には治療薬やワクチンが重要な役割を果たす。しかし、ワクチンの開発は12ヶ月以上かかるというWHOの見通しがある。過去の例としても、スペイン風邪においては、3年間以上に渡って死者が発生したとされている(第Ⅰ-1-1-31表)。
第Ⅰ-1-1-31表 スペイン風邪の死者数(百万人)
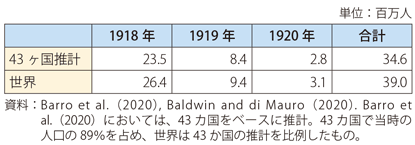
また、地域によって流行の時期や影響が異なることにも留意が必要である。ユーラシア・グループのイアン・ブレマーは国・地域に応じた感染収束と影響の見通しを発出している。
中国においては、富士山の形のように、症例数と死亡者数のピークまで爆発的な成長を遂げてから3ヶ月でピークを過ぎるものであった。
しかし、欧米のロックダウンは完全ではなかったため、富士山ではなく、津波の形となる。突然の大規模な隆起があり、その後、複数回のうねりを伴うものが長く続くものであり、経済が再開するまでには長い時間がかかる。
発展途上国では、多くの国では症例が増加し始めたばかりであり、政策、医療キャパシティ、地理・人口・天候、その他の要因に大きな格差があるため、先進工業国よりもはるかに幅広い軌道をたどることになる見込みであり、ミサイルの形として表現されている。(第Ⅰ-1-1-32図)。
第Ⅰ-1-1-32図 感染と影響の見通し(ユーラシア・グループ)
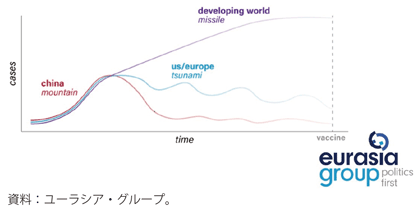
感染が長期にわたる場合には、社会変革の必要性をより高める。現在、各国において不要不急の移動は控えるという政府の勧告が発出され、企業や個人の活動・外出制限が広がる中、鉄道や航空の移動が減少している。一方、移動を伴わないテレワーク、オンライン教育、ECが普及する契機ともなっている。長期的な収束シナリオが実現する場合には、このような変化が長期的な社会変革の素地ともなりえるものであり、日本としてもこの機会を活用することが求められる。
その中で自国優先策や多国間の枠組みへの懐疑も見られており、世界での感染症の問題解決への障害ともなるものである。このような傾向は、コロナショック以前から存在しており国際協調の足かせになってきた。米国によるWHOへの拠出の停止、EUにおける輸出制限など、世界・地域単位での国際協力に遠心力が生じている。現在の状況は地政学的にも世界の秩序に変化をもたらす可能性がある。中国では2020年2月末以降に中国政府や中国企業が海外への医療支援外交を強化しており、対外支援の積極化といった動きも見られる。
7.各国の経済対策状況
(1)各国の経済対策
新型コロナウイルスの感染が拡大し、経済に深刻な影響が見られる中で、各国は経済対策を実施してきた。米国では2.2兆ドル規模のCARES法が実施に移されるなど、世界金融危機時の2008年の7,000億ドルの対策を大幅に上回る対策を実施している。ドイツにおいても、8,000億ユーロ規模の対策を実施するなど、各国で前例のない規模の経済対策が実施されている。
その経済対策の内容としては失業保険や現金給付を含む所得補償政策が見られる。英国では、休業する従業員の給与の8割を、月2,500ポンド(約32万円)を上限に、政府が補償する仕組みが3月20日に公表され、その後実施されている。香港や米国においては現金給付が実施された。
また、企業の資金繰りの支援も各国で行われており、債務保証が多くの国で見られるが、出資の実施も検討されるなど前例のない政策が行われている(第Ⅰ-1-1-33表)。
第Ⅰ-1-1-33表 各国の経済対策の一覧
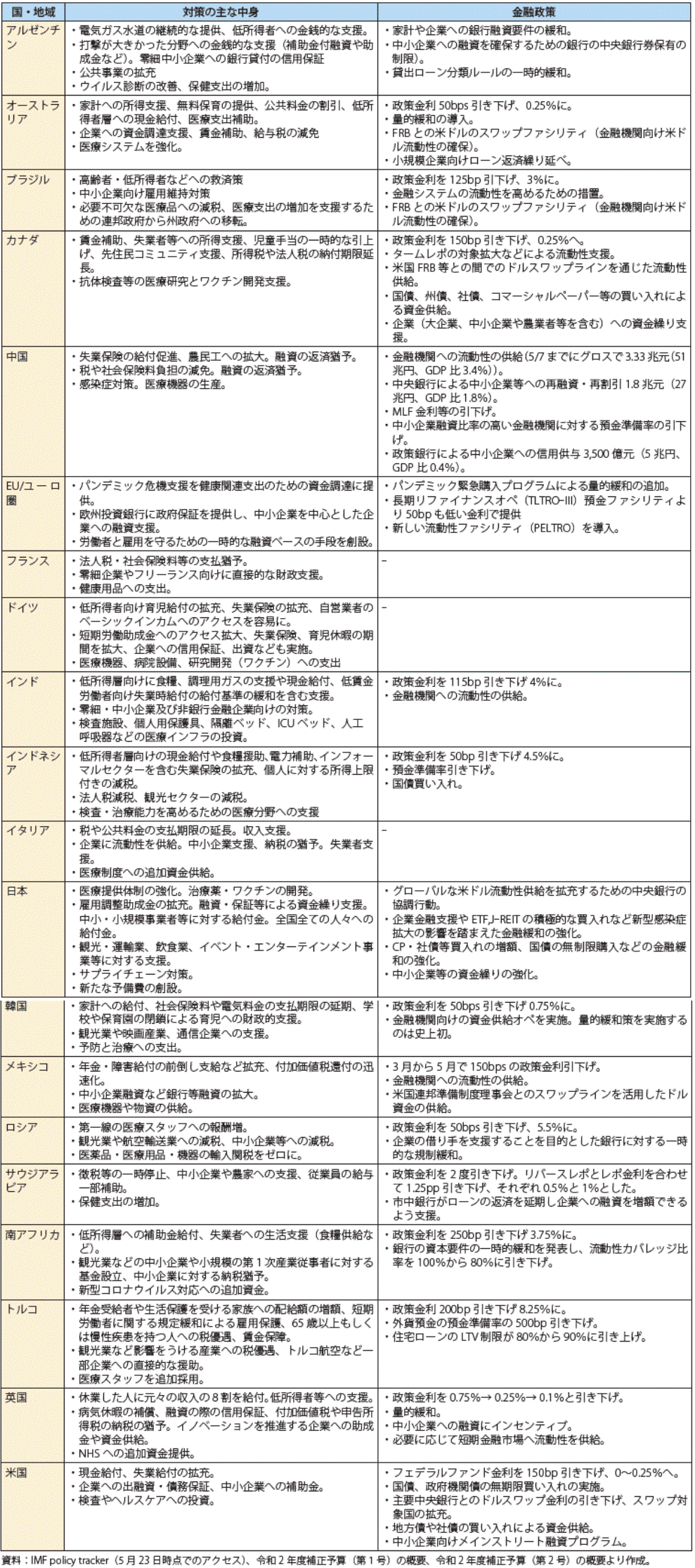
(2)国際協調の経済対策
世界金融危機時には、2008年11月に第1回20か国・地域首脳会合(G20サミット)がワシントンで開催され、世界規模での対策として、金融政策による支援、即効的な内需刺激の財政施策を必要に応じて協同して採用することで合意した。さらに、翌2009年4月にロンドンで開催されたG20サミットにおいて、2010年末までに5兆ドルの協調した財政出動で世界の成長率を4%押し上げ、雇用を創出するとともに、保護主義の拡大を許さない姿勢を示した。
新型コロナウイルスの感染拡大への対応としては、2020年3月16日にG7の首脳がテレビ会議を行い、「迅速にかつ必要な限りの、影響を最も受ける労働者、企業及び産業を支援すべく、金融、財政政策及び的を絞った措置を含めた、あらゆる手段を動員する」という声明を発出した。国際貿易及び投資を支援する点、適切な国境管理措置を含めて新型コロナウイルスの拡散を減速させるために協調して取り組む点でも合意がなされた。
また、G20の首脳によるテレビ会議が3月26日に行われた。声明では「パンデミックに伴う経済・社会的打撃を最小限に抑え、世界成長の回復や市場の安定、回復力強化のため出来ることはすべて行い、利用可能なすべての政策ツールを使う」として、世界経済に対して5兆ドル超を注入していることが確認された。