第5節 海外の技術・人材・イノベーションの取込等「内なる国際化」の促進
生産性向上・イノベーションの創発、所得水準の上昇、投資の拡大を実現する好循環を産み出すためには、外需やインバウンド需要を獲得できる企業体制の構築、すなわち「内なる国際化」を進めることが重要である。本節では、日本企業による国内及び海外のスタートアップ企業との連携、高度な知識や技能を有する外国人材(以下、「高度外国人材」という。)及び対内直接投資の取り込み状況について見ていく。
1.海外スタートアップとの連携によるイノベーションの促進
本項ではスタートアップへの投資・支援の重要性を示した上で、世界や日本のスタートアップをめぐる動向を概観していく。その上で、スタートアップによるイノベーション促進のための環境整備の方向性や海外スタートアップとの連携に向けた我が国の最近の取組事例について示していく。
(1)スタートアップ投資・支援の重要性
スタートアップは、社会的課題を成長のエンジンに転換して持続可能な経済社会を実現する存在244であり、大きく成長するスタートアップは経済成長のドライバーとなる存在である245。
スタートアップ企業への投資がイノベーションを通じて経済成長に与える影響を定量的に確認するために、OECD各国におけるベンチャーキャピタル投資額が全要素生産性(TFP)に与える影響について検証(分析の詳細については付注7を参照。)したところ、ベンチャーキャピタル投資額の増加は、TFPの増加をもたらすとの結果が得られた(第II-2-5-1図)。また、各国の状況を見ると、米国が他国を大きく引き離し、積極的なベンチャーキャピタル投資で高い経済成長を実現しているのが見て取れる。
第Ⅱ-2-5-1図 ベンチャー投資額と全要素生産性(TFP)の関係
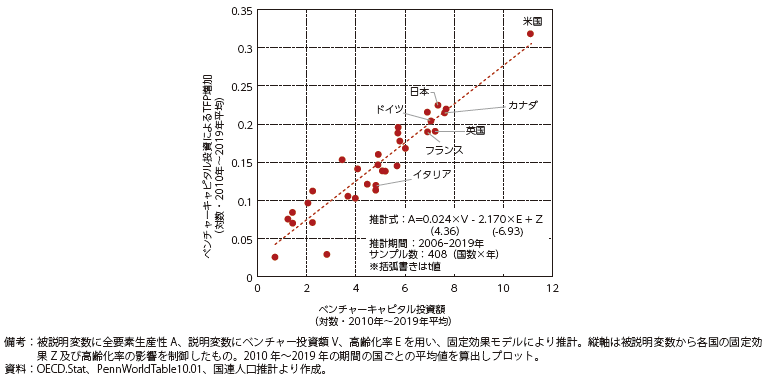
上記分析の結果が示すように、経済成長を実現する上で、スタートアップへの投資の意義は大きい。しかし、日本のベンチャーキャピタル投資は上図のとおり金額規模で見れば米国を除く主要国と遜色ないといえるが、対GDP比で見ると2021年時点で0.06%であり、G7諸国の中ではイタリアに次いで低い状況となっている(第II-2-5-2図)。
第Ⅱ-2-5-2図 G7諸国のベンチャーキャピタル投資額(対GDP比)の推移
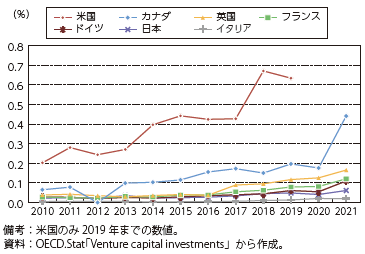
こうした状況を踏まえれば、我が国が他国に遅れを取ることのないよう、スタートアップへの投資や支援を更に促進・強化していくことが重要といえる。
244 新しい資本主義実現会議(2022)『スタートアップ育成5か年計画』。
245 経済産業省(2023)『スタートアップ育成に向けた政府の取り組み』。
(2)スタートアップをめぐる最近の動向
世界のベンチャーキャピタル投資の動向をみると、各国の金融緩和による潤沢な資金の存在等により2021年に大きく拡大したが、2022年に入ると投資の勢いは鈍化している(第II-2-5-3図)。
第Ⅱ-2-5-3図 世界のベンチャーキャピタル投資
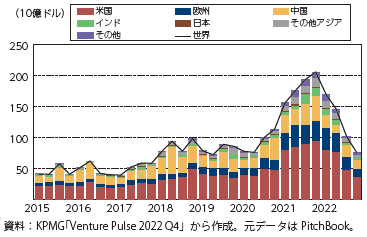
また、各案件の資金調達規模も、2021年に比べて縮小しており、10億ドルを超える調達案件が2021年は38件246であったのに対して、2022年は14件にとどまっている(第II-2-5-4表)。
第Ⅱ-2-5-4表 2022年の大規模資金調達案件(各四半期上位10企業)
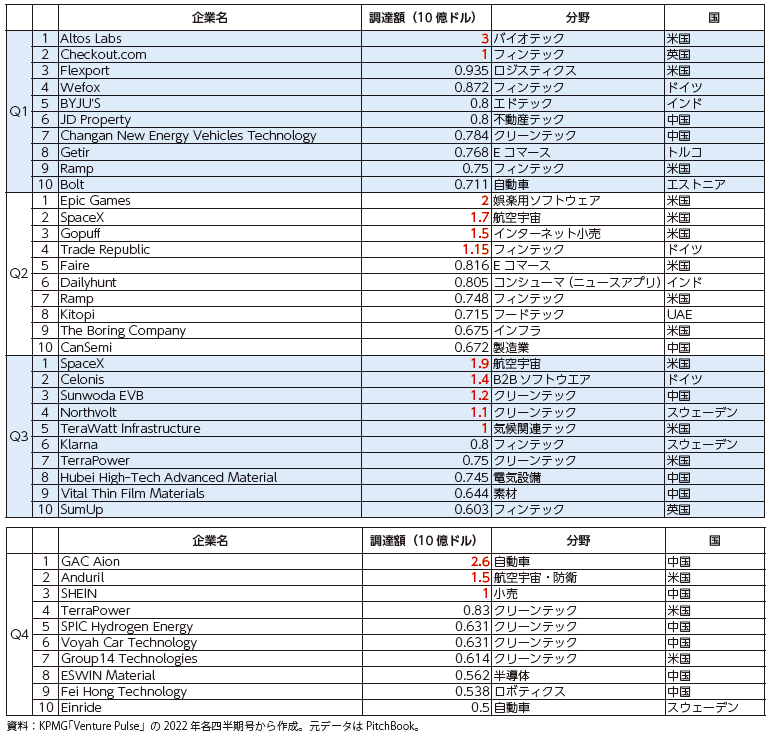
要因としては、2021年の好調に対する反動という側面に加えて、ウクライナ情勢等、地政学要因による経済混乱や、米国等各国中銀の金融引締めによる景気後退懸念等を背景に、投資家の慎重姿勢が強まっていると考えられる。
エグジットにおける新規株式公開(IPO)の調達件数、調達額をみると、2022年は前年から大きく減少している(第II-2-5-5図、第II-2-5-6図)。世界全体で、調達件数は1,333件と前年の2,436件から45%減、調達額は1,795億ドルと前年の4,599億ドルから61%減となった。特に米州は件数が76%減、調達額が95%減と他の地域に比べて大きく落ち込んでいる。米国では2022年にスタートアップのIPOの中止が相次いだと報じられている247。
第Ⅱ-2-5-5図 世界のIPO件数
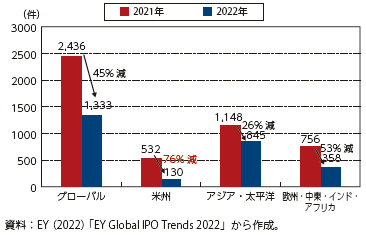
第Ⅱ-2-5-6図 世界のIPO金額
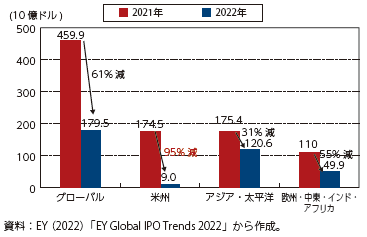
米国の主要なITプラットフォーム企業の株価をみても、2022年は業績の悪化を反映して大きく下落している(第II-2-5-7図)。
第Ⅱ-2-5-7図 2022年末までの米国テック企業の株価推移の図
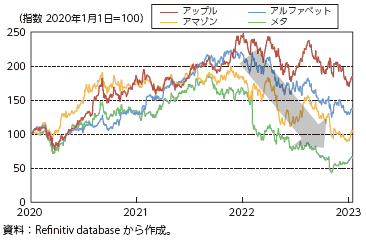
グローバルなスタートアップ向け投資が縮小した一方、日本のスタートアップ向け投資は2022年も2021年とほぼ同水準と見込まれ、堅調に推移している(第II-2-5-8図)。
第Ⅱ-2-5-8図 国内スタートアップによる調達額
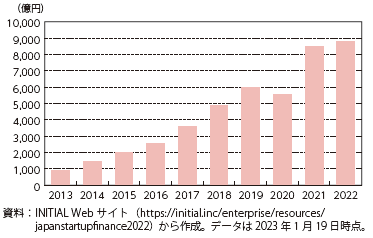
堅調な国内スタートアップ向け投資に関して、大型資金調達の事例をみると、自然エネルギー発電や、法人カード、医療関係者間のコミュニケーションアプリ等を事業内容とするスタートアップ企業が大規模な資金調達を行っている(第II-2-5-9表)。
第Ⅱ-2-5-9表 日本国内スタートアップの大型資金調達事例(2022年)
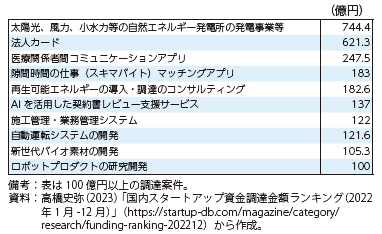
246 経済産業省(2022)『令和四年版通商白書』。
247 日本経済新聞電子版(「22 年のIPO 調達額、世界で65% 減 米国で中止相次ぐ」(2023年1月4日))。2022年のIPOの中止件数が2022年12月16日時点で173社と2000年の265社以来の水準との米金融情報会社の調査結果が報じられている。
(3)アジアを代表するスタートアップハブに向けた環境整備
日本政府は国内スタートアップ振興のため、2022年11月、新しい資本主義実現会議において、「スタートアップ育成5か年計画(以下「5か年計画」)」を取りまとめている。5か年計画ではスタートアップへの投資額を同計画の取りまとめ時点の直近である2021年の8,000億円規模から5年後の2027年度に10倍超の10兆円規模とすることや、将来におけるユニコーン100社創出、スタートアップ10万社創出により、我が国がアジア最大のスタートアップハブとして、また、世界有数のスタートアップの集積地となることを目標に掲げている。こうした目標達成に向けて、「スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築」、「スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化」、「オープンイノベーションの推進」の3本柱の取組を一体として推進していくこととしている。
経済産業省では社会課題を起点としたミッション志向のイノベーションを加速していくためのスタートアップ政策について議論を進めている。5か年計画に盛り込まれたアジア最大のスタートアップハブを構築するため、スタートアップが日本国内に閉じることなく、世界中から人材、資金を集め、グローバル市場へ製品、サービスを展開していくことが可能なグローバルなエコシステムを構築することを柱の一つとしている。また、優れた技術力等、他国にはない日本の強みを生かしたエコシステムの構築、スタートアップの創出・育成や、働き手一人ひとりが会社ベースではなく個人ベースでアントレプレナーシップを発揮する社会への転換を柱として方策の検討を行っている248。また、スタートアップの海外展開を支援することは重要であり、中小企業基盤整備機構において、スタートアップの海外展開を支援するため資金力や海外展開ノウハウを有する国内外のグローバルベンチャーキャピタルのファンドに出資していくことや、世界のイノベーション拠点に、起業等を志す若手人材を5年間で1,000人の規模で派遣することとしている。さらに、2022年度西村経済産業大臣の出張にあわせてタイ、サウジアラビア、米国、UAEでスタートアップミッションを実施し、現地財閥や政府系ファンド等とのネットワーク構築を行った。これと各種スタートアップ海外展開の支援策及び日系有望スタートアップのネットワークの構築を政策パッケージで推進している249。
また、特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような潜在力のある技術としてディープテックが注目を集めている。丸・尾原(2019)はディープテックが対象とする課題領域・分野として農業・食料、環境・エネルギー、健康、医療、海洋・宇宙を、課題解決のための技術としてAI・ビッグデータ、バイオ・マテリアル、ロボティクス、エレクトロニクス、センサ・IoT等を挙げ、課題領域と技術の掛け合わせによって、事業機会が多様に広がるとし、日本企業が培ってきた多くの技術を活かしていくことの重要性を指摘している250。
シェーデ(2022)も日本企業が製造やシステムエンジニアリングという中核的な強みを維持しつつ、オペレーションを再編し、重要な部品・素材等でディープテックのスキルや能力を構築してきたことに着目し、その強みを活かしていくべきとしている251。
ディープテック・スタートアップは特に事業化までに時間を要し、また、先端的な領域で新技術を活用するために企業価値評価が難しい側面があり、事業化までの資金調達やIPOなどエグジット面で課題がある。しかし、ディープテック・スタートアップの成長を支援するため運用期間を長期に設定するベンチャーキャピタルファンドが出てきているなど、投資側の姿勢も変化してきている252。ディープテック・スタートアップが事業化した場合のリターンの大きさが期待を集め、例えば大学発スタートアップの調達金額が増加傾向にあること等が報じられている253。経済産業省は、ディープテック・スタートアップへの投資促進のため、民間融資に対する債務保証制度を2021年に創設している。同制度では事業計画を認定されたベンチャー企業が、経済産業大臣に指定された民間金融機関から行う一定の借入れについて、中小企業基盤整備機構が債務を保証する内容となっている。また、他にも新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じた量産化・実用化・海外技術実証等に対する支援を行うとともに、ディープテック企業の無形資産の可視化に向けた指針の検討254を行っている。
248 経済産業省(2022)「スタートアップ・イノベーションの加速」産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会。
249 経済産業省「西村経済産業大臣がスタートアップの海外展開に向けた官民連携カンファレンスに出席しました」(2023年4月11日)(https://www.meti.go.jp/press/2023/04/20230411005/20230411005.html![]() )。
)。
250 丸幸弘、尾原和啓(2019)『Deep Tech ディープテック-世界の未来を切り拓く「眠れる技術」』、日経BP。
251 ウリケ・シェーデ著、渡部典子訳(2022)『再興 THE KAISHA 日本のビジネス・リインベンション』、日経BP。
252 日刊工業新聞「深層断面/ディープテック系新興に投資急増 社会問題解決へ先端技術に注目」(2022年9月7日p.28)、脱炭素に特化した「ANRI GREEN」ファンド(12年間(最長3年間の延長可能))の事例が報じられている(同社プレスリリース https://note.com/anri_vc/n/n309cf0cdfee0![]() 、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000040191.html
、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000040191.html![]() )。
)。
253 日刊工業新聞(同上)。
254 経済産業省研究開発型スタートアップの無形資産価値の可視化に係る課題検討ワーキンググループが2022年10月に検討を開始している。
(4)海外スタートアップとの連携に向けた我が国の取組
海外ではスタートアップ企業が次々に生まれ、いわゆるユニコーン企業(企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる未上場ベンチャー企業)に成長する事例も多い。巨大プラットフォーム企業となった米国GAFA255はIT技術で人々の行動様式を変えたイノベーションスタートアップの嚆矢である。中国ではBAT、TMD、BTQ256等が人口大国としてのポテンシャルや国内市場への海外プラットフォームのアクセス規制等を活かして成長した。インドのFlipkartやByju’s、One97 Communications、シンガポールのGrabやインドネシアのGo-to等の新興国企業の成長も目覚ましい。特に新興諸国ではデジタル技術による金融包摂など、日本等先進諸国が経験してきた段階的な経済発展とは異なる飛躍的な経済発展(Leapfrogging)が起こっており、新興国ならではのイノベーションの担い手としての役割を果たしているともいえよう。
若年人口が多く将来にわたって人口ボーナスを享受できると考えられる東南アジアの国々やインド等、アジア新興諸国の市場規模と、当該地域で急速に進んでいるデジタル化の動きが結びついた場合の成長のポテンシャルには大きな期待が寄せられており、ユニコーン企業数をみると、インドで70、シンガポールで14、インドネシアで7となっている(第II-2-5-10図)。
第Ⅱ-2-5-10図 国別に見たユニコーン企業数(2023年2月時点)
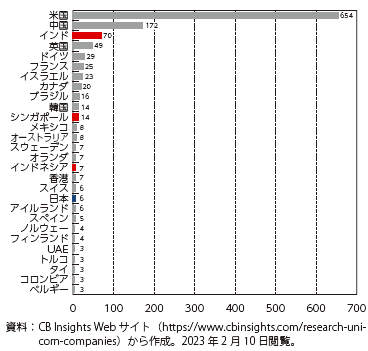
一方で、アジア新興諸国では、コロナ禍からの経済回復に加えて、いわゆる「中所得国の罠」に陥らないための「知識」や「情報」による中長期の経済の高付加価値化も重要な課題となっている。中所得国から高所得国へと所得段階を上昇させた韓国等に比べ、例えば東南アジア諸国の研究開発投資は低位にとどまるなど、アジア等新興国の経済の高付加価値化のための投資は十分とは言えない(第II-2-5-11図)。
第Ⅱ-2-5-11図 アジア諸国の研究開発支出対GDP比の推移
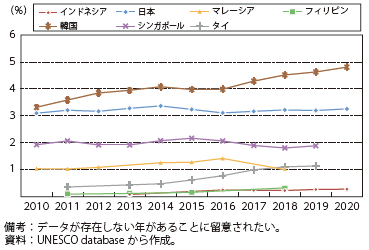
我が国企業とアジア等新興国のデジタル技術、スタートアップ等との連携は、当該諸国の成長を日本国内に取り込む観点からも、デジタル技術を通じたイノベーション促進のための投資をアジア各国内で促すという観点からも意義がある。とりわけ当該諸国の成長を日本国内に取り込むに当たっては、先進国企業が自国での製品やサービスを新興国市場にそのまま持ち込むのではなく、新興国での現地ニーズをこまやかに汲み上げて市場を獲得する、また、新興国発の製品や技術やビジネスモデルを還流する「リバースイノベーション」、外部との連携を通じて新しいアイデアを創出する「オープンイノベーション」の観点が重要となる。
我が国では、経済産業省および日本貿易振興機構(JETRO)等関係機関が連携して日本企業とアジア等新興国の企業との連携による新事業創出のため「アジアDXプロジェクト」を推進している。2022年におけるアジアDX支援事業採択案件(ASEAN)は28件であり、分野別・国別件数の状況は以下のとおりとなっている(第II-2-5-12図)。
第Ⅱ-2-5-12図 アジアDXプロジェクト採択案件(ASEAN)分野別・国別件数(2022年)
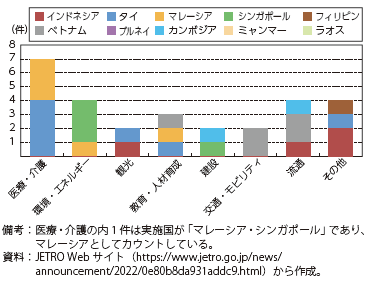
医療・介護(在宅ケア支援の実証、蚊媒介ウイルスに関する予測モデル構築等)、環境・エネルギー(カーボンニュートラルを目指したスマート保安化、海洋プラスチックごみの追跡システム実証等)といった現地社会に根差した社会課題の解決に向けた取組、流通(ECプラットフォームや物流効率化等)等、現地市場ニーズへの対応等、分野は多岐にわたっている。
経済産業省は2023年に日ASEAN友好協力50年を迎えるに当たり、「デジタル技術を活用したサプライチェーン・インフラの高度化」、「日ASEANで活躍する起業家育成・ネットワークの構築」、「社会課題解決ビジネスの共創」の3本の柱でプロジェクトを進めていく。異能人材の日本への呼び込み、人材育成プログラムへの参加促進、日ASEANの若手起業家100人のネットワーキングを進めるとともに、日本貿易保険機構(NEXI)の新しい貿易保険スキームを検討し、海外のスタートアップへの支援を強化、日本企業との協業を促進し、アジア新興国とのスタートアップとの連携によるイノベーションを促進していく。ASEAN各国との新たなイノベーション創出に向けた協力の在り方として、各国政府関係機関との共同で、日ASEAN双方のスタートアップと大企業との協業によるオープンイノベーション創出を後押しする施策を「日ASEAN共創ファストトラック・イニシアティブ」として開始している2257。上述したアジアDX促進事業についても日ASEAN友好協力50周年を機に、ASEAN地域で既に事業化したビジネスを持つスタートアップのさらなる事業拡大に対する支援を行う「ブーストアップコース」を新設する258。
255 Google(親会社はAlphabet)、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon の頭文字を取ったもの。
256 BATはBaidu、Alibaba、Tencent、TMDはToutiao、Meituan、Didi、BTQはPinduoduo、Kuaishou、Qutoutiaoの頭文字を取ったもの。
257 経済産業省「日本企業・スタートアップの海外でのオープンイノベーションを加速する「日ASEAN共創ファストトラック・ピッチ・イニシアティブ」を開始します」(2023年2月15日)(https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230215004/20230215004.html![]() )。
)。
258 経済産業省「日ASEANにおけるアジアDX促進事業のブーストアップコースを新設するとともに、通常コース第4回の公募を開始します」(2023年3月28日)(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230328005/20230328005.html![]() )。
)。
2.高度外国人材の受入れ・育成
海外から高度な知識や技術を有する人材を受入れることは、持続的な経済成長を実現する観点から非常に重要である。高度外国人材は、事業者の海外及びインバウンドにおける商機拡大、新製品やサービスに関連するイノベーションの創発、組織構成員の多様性向上を通じた組織の活性化等の効果をもたらす。高度な知識や技能を有する人材の獲得競争が世界レベルで激化していることなどを受け、我が国においても高度外国人材に対する在留資格の取得要件緩和など新たな動きが見られている。また、受入れだけではなく、外国人との共生社会の実現を図ることも極めて重要である。
本項では、高度外国人材及びその「卵」たる日本国内の外国人留学生に焦点を当て、国際機関のランキングやアンケート調査結果などを用いて、国際動向、政策動向などを概観する。
(1)我が国の高度外国人材獲得の動向と主要国の政策動向
高度外国人材の受入れに関する政策について、歴史を振り返ると、1988年6月に閣議決定された「第6次雇用対策基本計画」で「専門、技術的な能力や外国人ならではの能力に着目した人材の登用は、我が国経済社会の活性化、国際化に資するものでもあるので、受入れの範囲や基準を明確化しつつ、可能な限り受け入れる方向で対処する。」とされて以降、いわゆる高度外国人材は我が国に必要な人材として受入れに前向きな検討がなされてきた。現在も「第9次雇用対策基本計画」(1999年8月閣議決定)や「出入国在留管理基本計画」(2019年、法務省)に基づき、経済、社会等の状況の変化に応じて受入れ範囲を見直しながら、積極的な受入れが行われている。259
外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現するため、2018年より、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が定期的に開催されている。そこで決定される「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」は、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すものとなっている260。
高度外国人材261受入れを促進するため、出入国在留管理庁は2012年5月に「高度人材ポイント制」を導入、2015年4月には在留資格「高度専門職」を新設し、出入国管理上の優遇措置を講じている。
2023年4月には、高度外国人材に関連する新たな在留資格制度として、「特別高度人材制度(J-Skip)」及び「未来創造人材制度(J-Find)」が創設された。「特別高度人材制度」はトップレベルの能力がある者の受入れを促進することを目的に、学歴又は職歴と年収が一定水準以上262であれば、ポイント制によらず在留資格「高度専門職」の取得を可能とし、外国人家事使用人の雇用可能人数を1名追加可能としたり、配偶者の就労制限を緩和するなどの優遇措置を講じる。「未来創造人材制度」はポテンシャルの高い優秀な若者を早期に呼び込むことを目的に、3つの世界大学ランキング中二つ以上で100位以内に入る大学を卒業してから5年以内の外国人を対象に、日本での就職・起業準備活動を行うための在留期間を最長2年とし、家族の帯同や、その間の就労を許可するなどの優遇措置を講じる。
第Ⅱ-2-5-13図 高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移
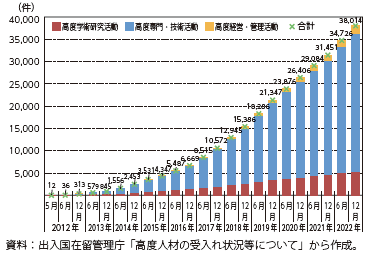
諸外国でも積極的な高度人材の受入れが行われている。例えば、英国では、2022年5月より世界トップクラスの大学卒業者に対して、現地の雇用契約無しで2~3年の居住許可が得られるHigh Potential Individual visa(通称HPIビザ)の申請受付を開始した。また、今後、成長期の企業向けに、高度な技術を持つ人を対象としたスケールアップビザの申請受付を新たに開始し、これにより更に英国に優秀な人材を呼び込み、企業の事業拡大を支援するとしている263。シンガポールでは、2023年1月より外国人高度人材向けビザOverseas Networks & Expertise Pass(通称ONE Pass)の申請が開始されたが、その対象は月額給与が30,000シンガポールドル(約286万円)以上と高所得者を狙ったものとなっている。その他、タイ、マレーシア、インドネシア等でも外国人富裕層や高度人材の獲得を狙ったビザ新設などがなされており、人材獲得競争は先進国だけでなく新興国にも広がっている。(第II-2-5-14図)
第Ⅱ-2-5-14図 2022年度新設された高度外国人材に対する諸外国の優遇制度
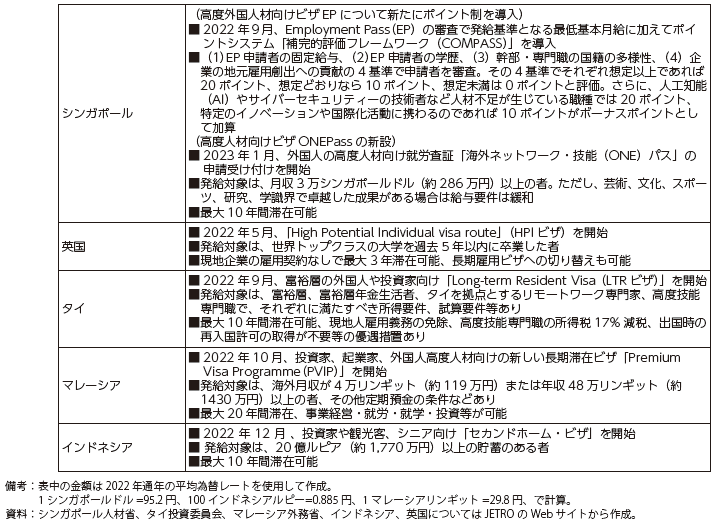
259 第9回教育未来創造会議ワーキング・グループ資料2参照。
260 2022年度からは、総合的対応策は、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」(令和4年6月関係閣僚会議決定)の策定を踏まえロードマップの施策について単年度に実施すべき施策を示すとともに、必ずしも中長期的に取り組むべき施策でないためにロードマップには記載されていないものの、共生社会の実現のために政府において取り組むべき施策も示している。
261 高度外国人材について、在留資格上の定義はないが、本稿においては、以下①~③を同時に満たす人々を高度外国人材と定義する。①在留資格「高度専門職」と「専門的・技術的分野」に該当するもののうち、原則、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「法律・会計業務」に該当するもの、②採用された場合、企業において、研究者やエンジニア等の専門職、海外進出等を担当する営業職、法務・会計等の専門職、経営に関わる役員や管理職等に従事するもの、③日本国内または海外の大学・大学院卒業同等程度の最終学歴を有しているもの。
262 三つの活動類型のうち、①高度学術研究活動、②高度専門・技術活動については、修士号以上取得又は職歴10年以上、及び、年収2千万円以上、③高度経営・管理活動については、職歴5年以上、及び、年収4千万以上。
263 JETRO「英国、大学ランキング上位校の卒業生向けビザルート導入」(https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/c429b8f7eec67b82.html![]() )を参照。
)を参照。
(2)留学生受入れ状況の各国比較
次に、高度外国人材の「卵」ともいえる留学生の受入れ状況を見ていく。
日本においては、「2020年を目途に留学生の受入れ30万人を目指す」とした「留学生30万人計画」(2008年、文部科学省)の実現が「日本再興戦略」(2013年6月閣議決定)で言及され、この目標は2019年に達成された。主要国も留学生政策に力を入れており、例えば、英国は教育関連の輸出額を年間350億ポンド(5.6兆円)に増やし、英国高等教育システムで学ぶ留学生を2030年に60万人に増やすことを目標に掲げている。また、フランスでは、2027年に50万人の留学生の受入れを目標としている264。
このような中、専門学校以上の高等教育機関の世界の留学生数は2020年で560万人と、2000年の160万人と比して約3.5倍に増加している。受入れ国別で見ると米国、英国、オーストアラリア、フランス等は安定的に上位に位置しているが、中国やカナダは2000年に比して大きく伸長している。一方で、日本のシェアは2000年の4%から変化していない(第II-2-5-15図)。
第Ⅱ-2-5-15図 世界の留学生数と各国シェア(受入れ)

主要国の専門学校以上の高等教育機関の留学生受入れ人数を見ると、日本を始め諸外国の留学生受入数は増加傾向にあり、特に米国の伸びが著しい(第II-2-5-16図)。
第Ⅱ-2-5-16図 主要国の留学生受入れ人数の推移
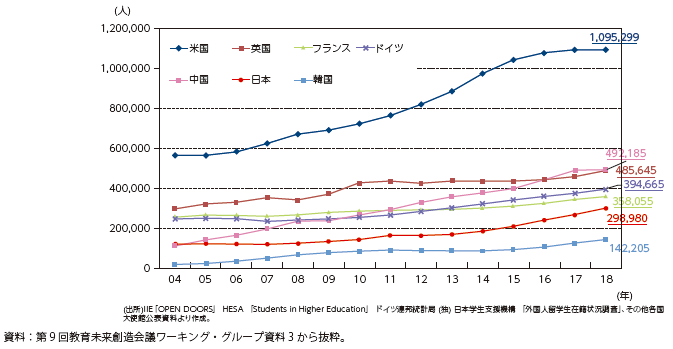
日本の大学・大学院における留学生割合は、学部段階で約3%、修士課程で約10%、博士課程で21%と、いずれもOECD平均より低くなっている(第II-2-5-17図)。
第Ⅱ-2-5-17図 在籍課程別の留学生割合
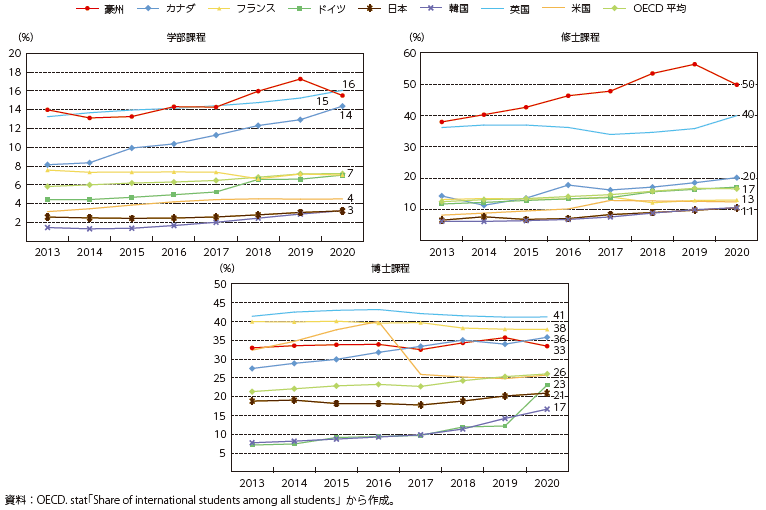
264 第9回教育未来創造会議ワーキング・グループ資料2
(3)高度外国人材にとっての日本の魅力と課題
高度外国人材や外国人留学生の受入れは増加傾向にあるが、彼らが日本に長期に滞在し活躍するためには、日本について、生活しやすく、ビジネスをする上でも魅力的だと感じてもらう必要がある。そこで、国際機関や海外の学術機関等が公表しているランキングから、世界各国・地域と比較した日本の魅力と課題について確認する。
The OECD Indicators of Talent Attractiveness(以下、「ITA」という)では、グループ別にOECD各国の魅力度を国際比較することが可能である265。ITAのフレームワークは七つの側面(機会の質、所得と税、将来の見通し、家族の環境、スキルを巡る環境、包摂性、生活の質)から成り、四つのグループ別に計23-25の変数を設定している(第II-2-5-18表)266 267。これら全ての側面が誰にとっても同程度の重要性を持っているわけではないので、この指標では利用者が各側面に相対的な重要性を加重して必要に応じたランキングが作成でき、それぞれの優先事項に最もふさわしい国がどこかが分かるようになっている。初版は2019年に三つのグループ(高学歴労働者、外国人起業家、意欲のある留学生)別で公表され、今年からスタートアップ創業者も対象に加わった。また、新型コロナウイルス感染症拡大が国際労働市場、労働シフトなどに与えた影響を考慮し、「医療システムパフォーマンス」の項目が追加されるとともに、デジタル化やデジタルインフラのレベルに関する変数が「スキルを巡る環境」の項目に、ビザ取得プロセスにおけるデジタル化レベルに関する変数がvisa and admission policyの項目に追加された。
第Ⅱ-2-5-18表 The OECD Indicators of Talent Attractivenessのフレームワーク
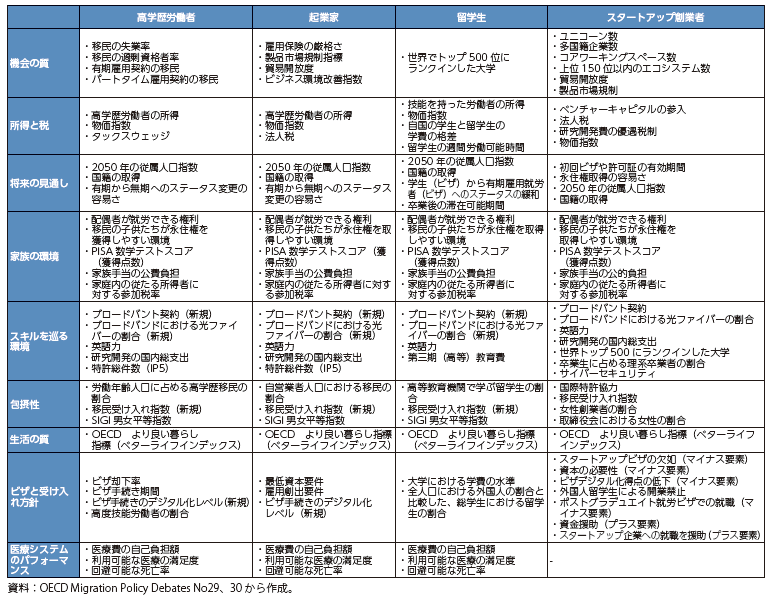
ITAでは対象のグループによってランキング上位の国が変化する。
高学歴労働者にとって魅力的な国としては、引き続きニュージーランド、スウェーデン、スイス、豪州が挙げられる。英国は、2019年と比較して大幅に順位を上げており、これは高度技能労働者枠の廃止や移民のための強い労働市場の成果によるものである。
外国人起業家にとって魅力的な国としては、スウェーデン、スイス、カナダ、ノルウェー、ニュージーランドが引き続きあげられる。これらの国々では、外国人起業家にとってビジネスを行うに当たって有利な政策がとられている。
留学生にとって魅力的な国には、米国、ドイツ、英国、ノルウェー、豪州があげられる。世界トップランクの大学が多数存在する国がランクインしている一方で、ノルウェーのような小国でランキング上位の国もあるが、これは教育分野への大規模な投資と魅力的な生活環境、有利な移住政策により、学生にとって魅力的な国となっているからである。
スタートアップ創業者にとって魅力的な国には、カナダ、米国、フランス、英国、アイルランド、ポルトガルがあげられる。カナダはすべての側面において高得点であったのに対し、米国は強力なスタートアップエコシステムは存在するものの、スタートアップ創業者向けの政策のフレームワークは特に有利とは言えない。フランスは、スタートアップビザに付随する資金調達の機会や従業員の進路等外国人スタートアップ創業者にとって最も有利な政策を打ち出している。アイルランドやポルトガルのようなヨーロッパの小国は10億円規模の企業数が少なく機会の質の側面では不利であるが、有利な税体系や生活コストの安さ、将来の見通しや包摂性の側面での高得点が順位を押し上げている。
日本については、前回調査の2019年と比較すると、高学歴労働者や外国人起業家については引き続き順位が低いが、学生については25位から7位と大きく順位を上げている。この理由として、学生から就労者へ在留資格を変更する際に要する時間の短縮や卒業後に滞在する学生のための環境改善などが挙げられる。また、近年外国人留学生のシェアが拡大し、教育関連サービスの輸出が特に力強く成長しており、外国人留学生からの収益が2014年から2019年で3倍に増えている。しかし、OECD諸国に比して、全学生に占める外国人留学生の割合はいまだ低水準である。また、日本はベンチャーキャピタルへのアクセスが良好で、スタートアップのインフラが充実しているにも関わらず、スタートアップ起業家向けのランキングは24か国中21位と極めて低い。これは、スタートアップ創業者が、在留資格を「永住者」に切り替える時に直面する障壁や家族が就労条件を限定された在留資格しか取得できないことなどが主な要因となっている。
第Ⅱ-2-5-19図 ITAグループ別魅力度ランキング(2023年)
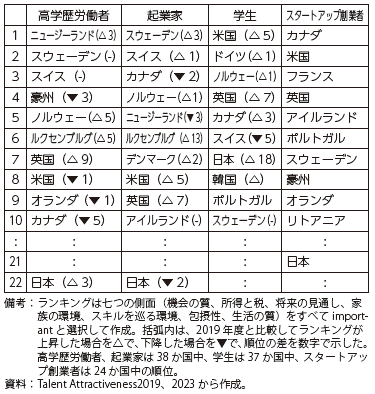
IMDのWorld Talent Ranking(2022 年12 月)は、63の国・地域を対象に、「高度人材の開拓にどれだけの資源を投資しているか(Investment & Development)」、「国内外の高度人材をどれだけ引きつけ留めておく能力があるか(Appeal)」、「人材プールにおいて利用可能な技術やコンピテンシーの質はどの程度か(Readiness)」、の3点で評価している。このランキングにおいて、日本は過去最低の41位となっており、2018年以降4年連続で順位を下げているが、順位を下げているのはInvestment & Development、Readinessであり、Appealの項目は2018年以降横ばいの27位となっている。企業において有能な人材の保持や引きつけが優先事項になっていること(4位)、ボーナスや長期インセンティブも含めたマネジメント報酬が高い(8位)、等で高い順位となっている一方で、生活コスト(59位)、外国人高度人材にとってのビジネス環境の魅力(54位)等の順位が低い。
また、INSEADのGlobal Talent Competitiveness Index(2022年11月、以下「GTCI」という)は、133の国・地域を対象に、インプット項目として「外部環境要因(Enable)」「国の魅力度(Attract)」「人材開発のための方策(Grow)」「人材を国内に維持するための方策(Retain)」、アウトプット項目として「職業上・技術的スキル(Vocational and Technical Skills)」「グローバルな知識スキル(Global Knowledge Skills)」の合計六つの項目で評価している。日本は24位と、アジア・大洋州地域ではシンガポール(2位)、豪州(9位)、ニュージーランド(18位)に次ぐ順位となっている。
GTCIを用いて、日本とシンガポールの魅力度を比較すると、シンガポールは、マイノリティや移民に対する寛容さ、女性活躍に対する機会や権利、頭脳の保持等で上位となっている一方で、日本はこれらの項目では下位となっている。一方、日本は、社会的保護や環境、個人の権利、環境性能等で上位となっており、身の安全や年金の対象範囲では世界1 位となっている(第Ⅱ-2-5-20図)。
第Ⅱ-2-5-20図 GTCIにおける日本とシンガポールの魅力度の比較
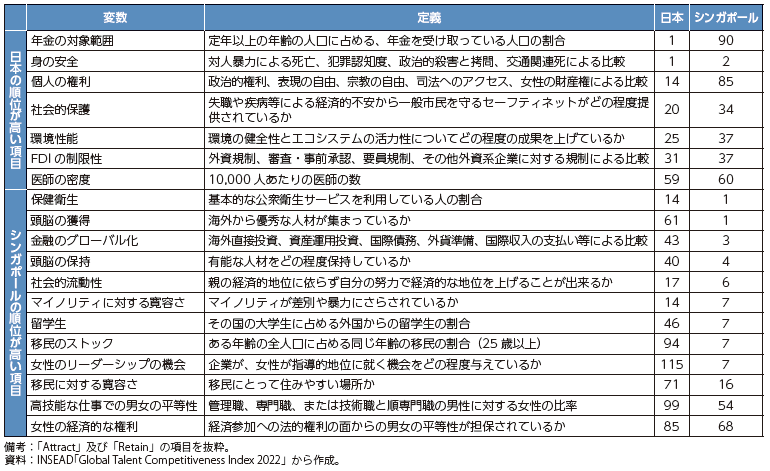
266 OECD Migration Policy Debates No29 “What is the best country for global talents in OECD?(” March 2023)
267 OECD Migration Policy Debates No30 “What are the top OECD destinations for start-up talents?(” March 2023)
(4)外国人との共生に向けて
これまで見てきたように、訪日する高度外国人材や外国人留学生の数は増加傾向にある一方で、外国人にとっての日本の魅力度は決して高いとは言えず、共生のための課題は多い。
外国人との共生社会の実現に向けて、2022年6月、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」が公表された。これは、目指すべき外国人との共生社会のビジョン(三つのビジョン)を示し、ビジョンを実現するために取り組むべき中長期的な課題として四つの重点事項を掲げ、それぞれについて今後5年間に取り組むべき方策等を示したものである(第II-2-5-21図)。
第Ⅱ-2-5-21図 外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ
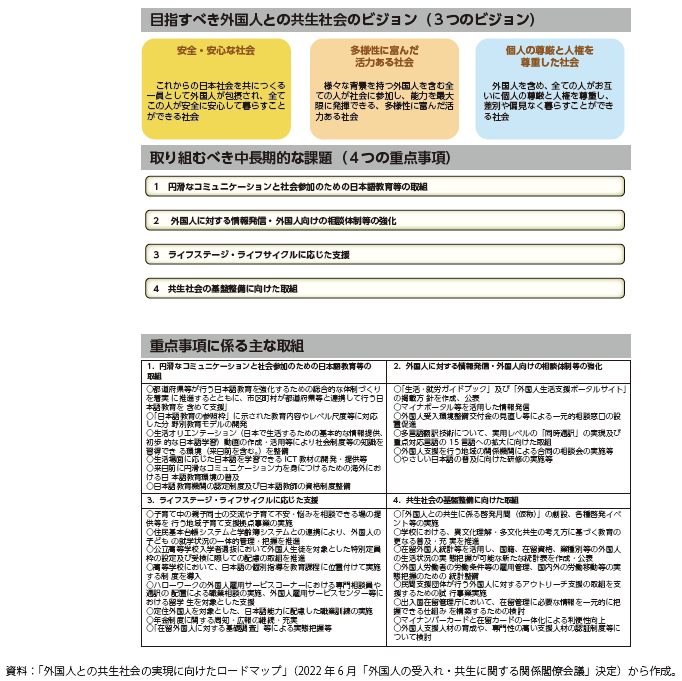
また、外国人留学生の定着については、「日本再興戦略改訂2016」(2016年6月2日閣議決定)において、「外国人留学生の日本国内での就職率を3割から5割に向上」させることを目指し、第三次教育振興基本計画において引き続き目標達成に向けて取り組んでいるところである。
現状、各年度に大学・大学院を卒業・修了した外国人留学生のうち、日本国内で就職した外国人留学生の占める割合(以下国内就職率)は約3~4割にとどまっている。特に新型コロナウイルス感染症拡大の2020年以降は、卒業・修了者数は変わらず増加傾向にあるものの、国内就職率は2年連続で3割を下回っている(第II-2-5-22図)。
第Ⅱ-2-5-22図 大学・大学院における外国人留学生の卒業・修了者数、国内就職者数及び国内就職率の推移
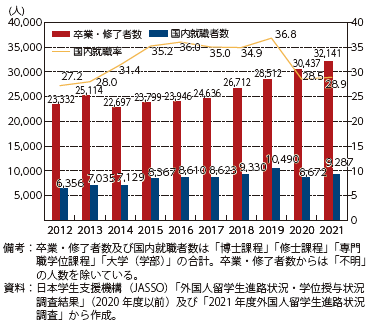
一方で、私費留学生に対するアンケート調査において、卒業後の進路希望を見ると、「日本において就職希望」が全体の約58%と最も多くなった。足下は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、日本での就職希望の割合はやや低下しているが、「出身国において就職・起業希望」や「第3国において就職・起業希望」と比較すると、我が国における就職の希望は高い水準にある(第II-2-5-23図)。
第Ⅱ-2-5-23図 卒業後の進路希望
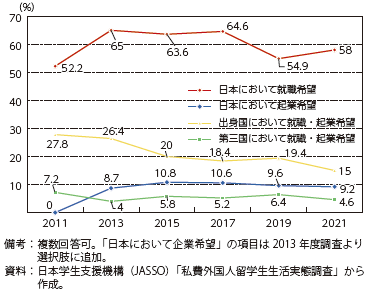
なお、外国人留学生が就職したい企業の種類として最も多いのは「日本にある日系以外の企業(外資系企業)」となっており、「日本にある日系企業」と相反して近年増加傾向にある。日本での生活には魅力を感じているが、日系企業で働く事への魅力を感じていない留学生の存在が示唆される(第II-2-5-24図)。
第Ⅱ-2-5-24図 外国人留学生が就職したい企業の種類
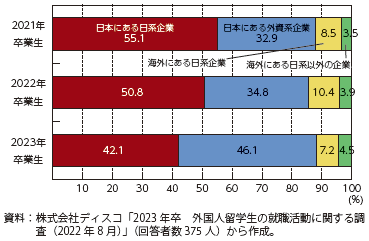
以上から、外国人留学生の日本での就職率は、その就職希望率を大きく下回っており、希望はしたものの日本での就職が叶わなかった留学生が一定数いると考えられる。さらに、日本企業のアンケート調査によれば、戦略的に高度外国人材を増やす必要性を感じている日本企業は約70%にのぼっているが、そのうち必要な人材を確保できていないと回答した企業が約80%を占めている268。また、海外に展開する日本企業向けのアンケート調査によれば、今後日本国内で重視する投資分野として、人材投資を重視するとの回答が増加している269。このような外国人留学生と企業のミスマッチの状況を鑑み、第9回教育未来創造会議ワーキング・グループ(2023年4月)において「留学生の卒業後の国内就職率6割を目指す」とされた。
留学生と企業側のミスマッチはどこで起きているのか。日本企業のアンケート調査によれば、外国の高度人材の採用に当たっては、「マッチング(スキル、職務内容、待遇等)が困難」「日本語でのビジネスコミュニケーションの困難性」「給与等報酬水準の高さ」等を課題としてあげる企業が多かった。このような課題には、留学生と企業が互いの理解を深め、柔軟に変化していくことが極めて重要である(第II-2-5-25図)。
第Ⅱ-2-5-25図 国内における高度外国人材の採用の課題
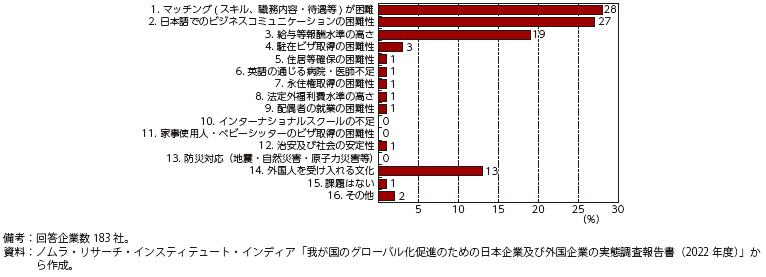
「マッチング(スキル、職務内容、待遇等)が困難」「日本語でのビジネスコミュニケーションの困難性」については、留学生の日本企業における採用慣行や働き方等に対する理解を高めることで、就職活動期のマッチングのギャップを埋めることが期待される。現在、政府、大学、企業、地方公共団体等の連携の下、留学生の国内就職につなげる施策を留学生の在学前から在学後まで様々なフェーズで実施している。具体的には、大学が自治体や産業界と連携し、外国人留学生が日本国内での就職に必要なスキル(ビジネス日本語、キャリア教育、インターンシップ等)を一体として学ぶ環境を創設する取組の支援、高度外国人材の国内就職から定着に至るまでの伴走型支援の強化、大学とハローワークの間での連携による留学早期からの一貫した就職支援の実施等を行っている(第II-2-5-26図)。
第Ⅱ-2-5-26図 留学生の定着に向けた主な施策
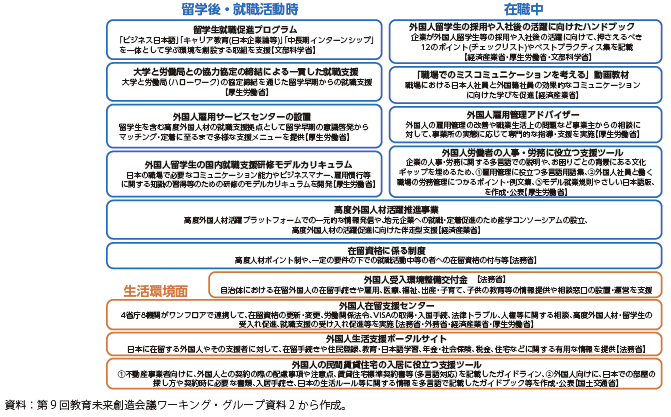
なお、外国人留学生の日本語力向上に対する努力は必要である一方で、日本企業が内定時に求める日本語力と入社後に求める日本語力に差があるという調査結果がある。日本においては就職活動が卒業の1年以上前から始まるため、企業側は採用決定から入社までの日本語力の伸びを期待して採用しているが、期待と現実のギャップが存在する可能性が示唆される(第II-2-5-27図)。
第Ⅱ-2-5-27図 外国人留学生の内定(選考)時・入社後に求める日本語コミュニケーションレベル
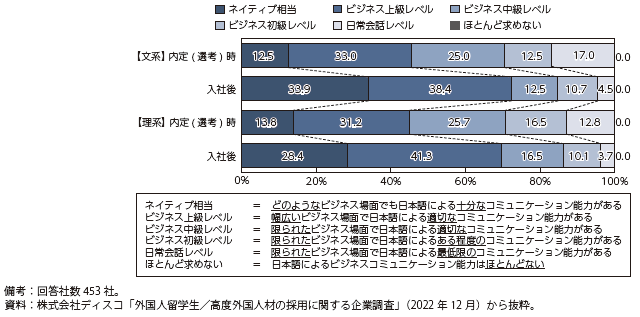
外国人留学生に対する支援と同時に、企業の受入れ体制の整備も急務である。日本独自の雇用慣行・給与体系は、高度外国人材が日本企業就職を検討する際の課題となっている可能性がある。日本企業へのアンケート調査によれば、外国人材の採用を見据えた賃金体系・待遇の整備・設定を既に行っていると回答した企業は約3割にとどまっている(第II-2-5-28図)。大半の日本企業は、外国人材の採用に向けて人事評価や待遇面での整備に着手できていない、または必要性を感じていない可能性が示唆される。こうした企業側の課題を踏まえ、2020年経済産業省において、留学生の多様性に応じた採用選考や選考後の柔軟な人材育成・処遇等に係るチェックリストやベストプラクティス集をまとめたハンドブックを策定し270、好事例を広く周知することで企業における外国人留学生の採用に係る意識改革を図ることとしている。
第Ⅱ-2-5-28図 人事評価・待遇面の整備状況
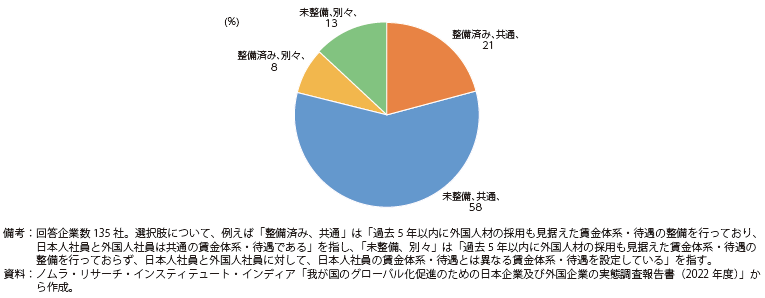
268 ノムラ・リサーチ・インスティテュート・インディア「我が国のグローバル化促進のための日本企業及び外国企業の実態調査報告書(2022年度)」。
269 ノムラ・リサーチ・インスティテュート・シンガポール「我が国企業の海外展開の実態及び課題に係るアンケート調査(2022年度)」。
270 EY 新日本有限責任監査法人「外国人留学生の国内就職促進に係る調査」(令和2年2月)。
3.対内直接投資の拡大
対日直接投資は、海外から高度な人材・技術・豊富な資金を呼び込むことでイノベーション創出や海外経済の活力の地方への取り込みにつながり、日本経済全体の成長力の強化や地域経済の活性化に貢献するものである。特に、我が国は、人口減少が進展しており、これを克服して力強い成長を実現するためには、対日直接投資を梃に、海外活力を大胆に取り込んでいかなければならない。
政府は、2013年に「2020年までに対日直接投資残高を35兆円に倍増する」という目標(KPI:Key Performance Indicator)を掲げ、その達成に向けて、対日直接投資推進会議の司令塔の下、関係省庁が連携して、投資に関心のある企業の発掘・誘致、ビジネス環境や日本で働く外国人の生活環境の改善、協業する日本企業とのマッチング機会の提供など、対日直接投資の拡大に向けた取組を進めてきた。こうした取組もあり、対日直接投資残高は、2000年代後半から横ばいで推移していたが、2014年以降増加が続き、2020年12月末時点(確報値)で39.7兆円となり、上記目標は達成された。
ただし、対内直接投資の拡大は経済規模の拡大に比例するものであり、必ずしも対内直接投資促進策によってもたらされたものではない可能性もある。そこで2013年以降の対日直接投資促進施策によって対日直接投資残高が加速的に増加したか否かをHoshi(2018)271の手法に倣い、検証を試みた(分析の詳細については付注8を参照)結果が第II-2-5-29図である。これによれば、対日直接投資促進施策が実行段階に移った2014年以降の対内直接投資残高は、対日直接投資促進施策が実行段階に移る以前の2013年以前の対内直接投資残高対名目GDP比のトレンドに基づき推計した対内直接投資残高を有意に上回っており、2013年以降の取組により対日直接投資が促進された可能性が高いといえる。
一方で、対日直接投資残高の対GDP比の水準そのものは、2020年12月末時点で7.4%であり、OECD加盟国平均の56.4%(2019年)と比較し、国際的にみて著しく低い水準にとどまっている現状に鑑みれば、持続可能な成長の実現には、グローバルな投資や人材・技術の呼び込みは引き続き重要であり、そのための環境整備を続けていくことが求められる。このため、政府は、令和3年6月に、「対日直接投資残高を2030年に80兆円と倍増、GDP比12%とすることを目指す」という新たなKPIを設定し、その達成に向けた対日直接投資促進のための中長期戦略(「対日直接投資促進戦略」)を定めて取組を推進してきた。こうした取組により、対内直接投資残高は、2021年末に40.5兆円、2022年末に46.2兆円となった。さらに、令和5年4月の対日直接投資推進会議において、「国際環境の変化を踏まえた戦略分野への投資促進・グローバル・サプライチェーンの再構築」、「アジア最大のスタートアップハブ形成に向けた戦略、高度外国人材等の呼び込み」、「国際的な頭脳循環の拠点化に向けた制度整備、海外から人材と投資を惹きつけるビジネス・生活環境の整備等」、「オールジャパンでの誘致・フォローアップ体制の抜本強化」、「G7等を契機とした世界への発信強化」の五つを柱とする「海外からの人材・資金を呼び込みためのアクションプラン」を取りまとめるとともに、「2030年80兆円の対内直接投資目標の更なる高みを目指し、早期に100兆円を目指す」とされ、対日直接投資の更なる拡大を図ることとしている。
対日直接投資の更なる拡大を促すためには、我が国の強みを生かすとともに、課題を克服し、「内なる国際化」を進めていくことが重要である。第II-2-5-30図は、外国企業が事業拠点として最も魅力的と考える国・地域を示したものだが、外国企業は研究開発拠点としての日本に対して高い評価を行っているといえる。また、第II-2-5-31図は、先進国間での比較を示したものだが、日本は、インフラ、市場規模、社会の安定性、消費者の所得水準等が「強み」である一方、英語、事業活動コスト、税率等に課題があることが分かる。政府としては、これらの課題への対応を含め、「内なる国際化」を推進していくことが重要である。
第Ⅱ-2-5-29図 対内直接投資残高の推移
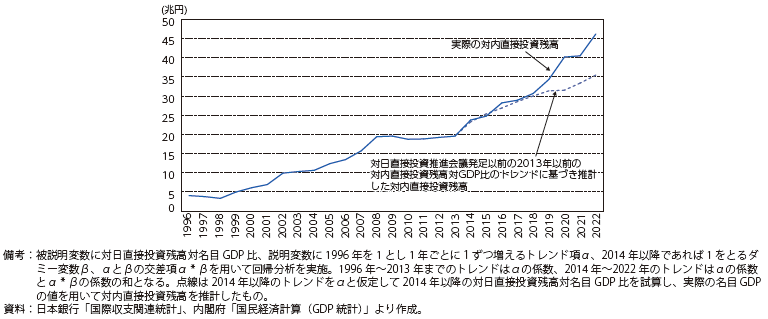
第Ⅱ-2-5-30図 外国企業が事業拠点として最も魅力的と考える国・地域
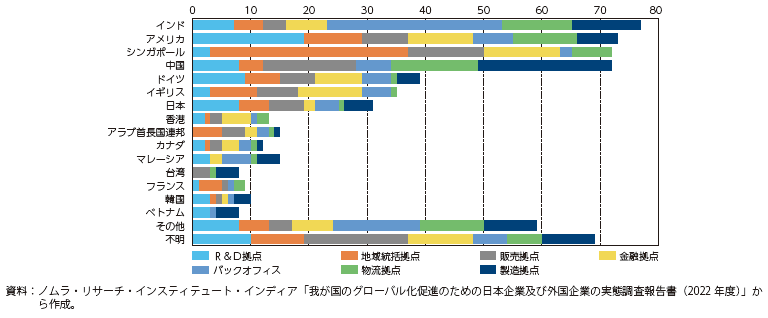
第Ⅱ-2-5-31図 先進国と比較した日本のビジネス環境の「強み」と「弱み」
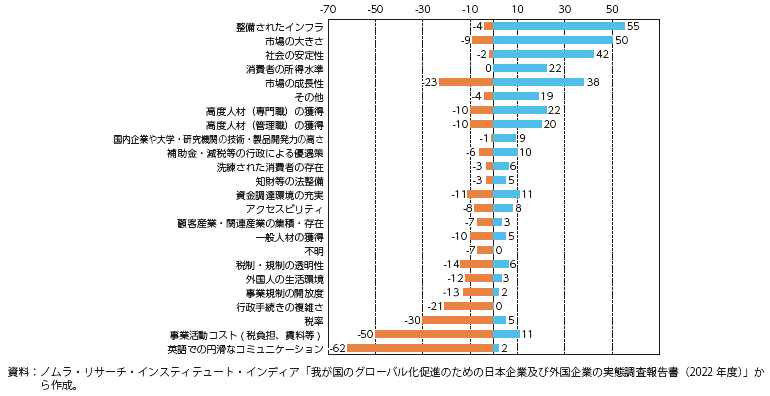
271 HOSHI Takeo(2018) “Has Abenomics Succeeded in Raising Japan’s Inward Foreign Direct Investment?”, Asian Economic Policy Review(2018) 13, 149–168