

- 統計

- 外資系企業動向調査

- 結果の概要

- 第32回 調査結果(1997年度実績)?平成12年3月刊行?

- 要旨

- 外資系企業の活動状況(要旨)(平成11年7月6日公表)
外資系企業動向調査
外資系企業の活動状況(要旨)(平成11年7月6日公表)
(1)売上高の状況
- 97年度の集計企業の売上高は19兆9059億円で、前年度比9.5%の増加となった。業種別では製造業(12兆9407億円 前年度比10.7%増)、非製造業(6兆9653億円 同7.5%増)ともに増加となり、特に非製造業は4年連続の増加であった。また、全法人企業売上高(1467兆4千億円 同1.3%増)に占める割合は前年度から0.1ポイント上昇して1.4%の水準となり、外資生産比率も同0.2ポイント上昇の3.1%となった。
- 1企業当たり売上高は132億円で前年度比3.0%の増加となった。特に製造業(258億円)が93年度以降5年連続で増加しており、全法人企業の1.3倍と依然高い水準を維持している。
- しかしながら、98年度予測では、製造業(前年度比7.0%減)、非製造業(同12.8%減)ともに大幅な減少を見込んでおり、全産業では同9.4%の減少となる見込み。
- 母国籍別でみると、全体の94.0%を占める欧米系企業(アメリカ系企業:前年度比8.8%増、ヨーロッパ系企業:同16.1%増)でそれぞれ増加となったのとは対照的に、アジア系企業では同27.2%の大幅減少となった。
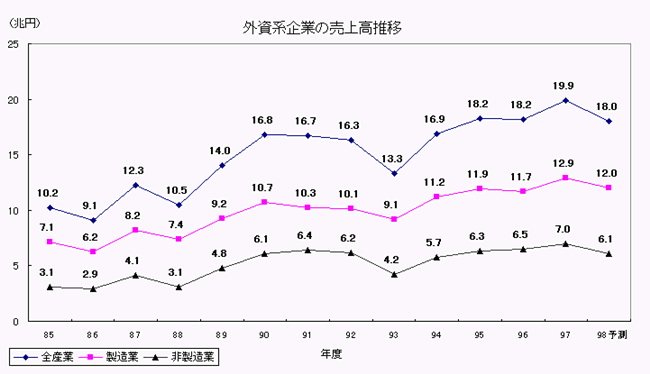
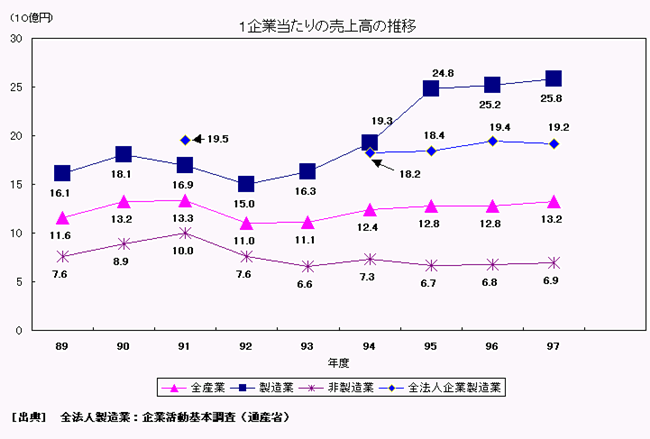
(2)輸出入の状況
- 97年度の集計企業の輸入額は前年度比17.8%増の5兆448億円で、我が国輸入総額の14.2%(前年度比3.4ポイント上昇)。一方、輸出額は2兆4903億円(同7.2%増)で、我が国輸出総額の5.1%(同0.1ポイント上昇)となった。
- 集計企業全体の輸出入バランスは、依然2兆5545億円の輸入超過(石油に係る1兆16億円を除いても全体で1兆5529億円の輸入超過)であった。また、石油を除く製造業では94年度以降続いていた輸出超過が4年ぶりに755億円の輸入超過となった。
- 母国籍別にみると、昨年度とあまり変化はみられず、欧米系企業の対欧米貿易が大幅な輸入超過である一方、アジア系企業の対アジア貿易は3年連続して輸出超過となっている。
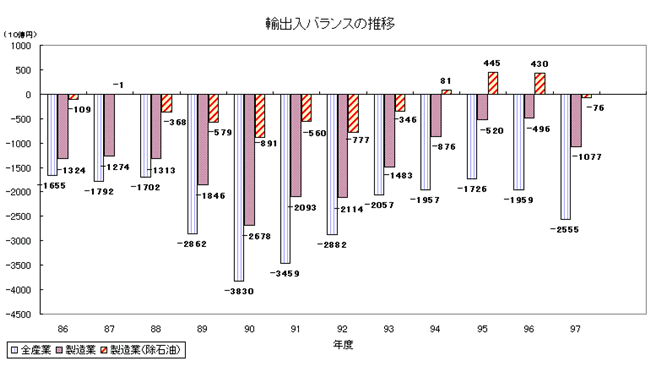
(3)財務状況
(3)-1収益状況
- 97年度の集計企業の経常利益額は、非製造業における大幅な減益(2081億円 前年度比21.8%減)の影響から、全産業では同2.3%減少の8542億円と2年連続で減益となった。1企業当たりでみると、製造業(12億79百万円 同2.4%減)、非製造業(2億7百万円 同25.5%減)ともに減益となり、全産業(5億65百万円)では同8.1%の減少と2年連続の減益。
- 売上高経常利益率をみると、全産業では依然全法人企業(1.3%)を3.0ポイント上回る4.3%となったものの、前年度と比べ0.5ポイントの低下となり、製造業(5.0%同0.2ポイント低下)、非製造業(3.0% 同1.1ポイント低下)ともに低下した。
- 母国籍別にみると、ヨーロッパ系企業(2382億円)、アジア系企業(29億円)で増益となったものの、アメリカ系企業(5994億円)では非製造業の減益が大きく4年ぶりの減益となった。また、売上高経常利益率でも堅調に推移したヨーロッパ系企業、アジア系企業とは対照的に、アメリカ系企業では前年度比0.9ポイントの低下となり、特に非製造業では3年ぶりにヨーロッパ系企業を下回った
- 参入時期別では、参入年数を経るごとに売上高経常利益率水準が高くなる傾向となっており、また、参入時期ごとに赤字企業の割合をみると、参入直後の立ち上がり期にある企業では45.3%と高い割合になっているものの、参入後年数が経つにつれて割合が低下している。
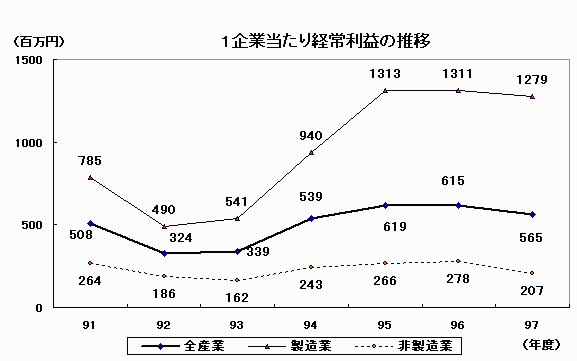
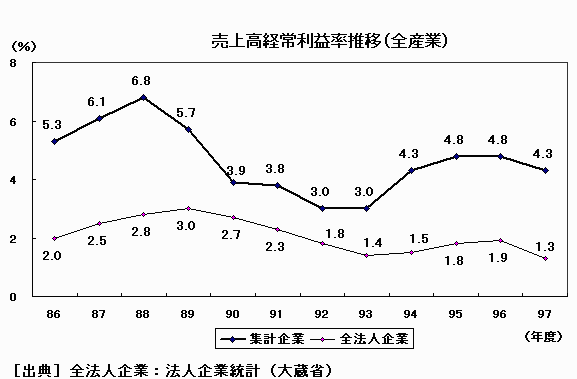
(3)-2費用と利益処分の状況
- 集計企業の製造業における各費用項目の売上高比率を日系海外現地法人と比較すると、減価償却費を除くすべての費用で日系現地法人を集計企業が上回っており、依然として我が国における費用水準が高いことがわかる。
- 一方、集計企業の配当性向は全産業で71.3%と前年度比13.4ポイントの上昇となった。なかでも非製造業で同39.0ポイントの大幅上昇となっており、4年ぶりに全法人企業の水準を上回った。また、配当率は19.1%と前年度を2.6ポイント上回り、依然全法人企業(5.6%)を大きく上回る水準
- 集計企業の自己資本利益率(ROE)は10.3%と前年度比1.5ポイント低下したものの、依然全法人企業(3.2%)を大きく上回る水準を維持している。母国籍別にみると、欧米系企業では、全法人企業の約3倍強となる10%程度の高い水準となった。
- また、外国側出資者への支払状況をみると、支払総額は5968億円と前年度比16.1%の増加となり、86年度以降最高額となった昨年の水準を大きく更新した。
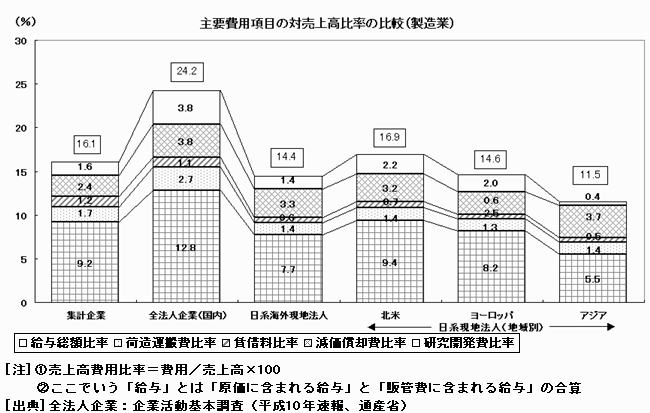
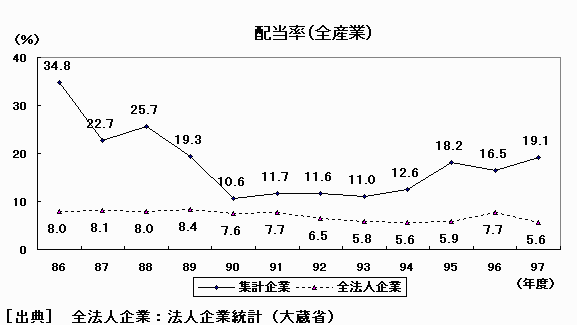
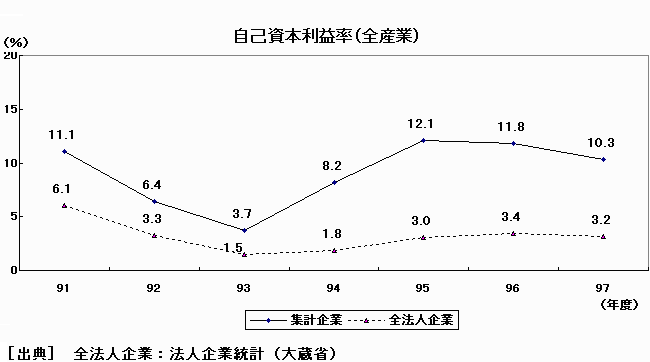
(4)資金調達状況
- 集計企業の借入金総額は3兆1787億円(前年度比1.9%増)であった。内訳をみると、短期借入金(1兆7811億円)が長期借入金(1兆3975億円)を上回っている。
- 借入金依存度をみると、全産業は24.2%で、前年度と比べ2.1ポイントの低下となっており、借入金による資金調達の割合は低下している。これを全法人企業と比較すると、集計企業は全法人企業よりも18.8ポイント低い。
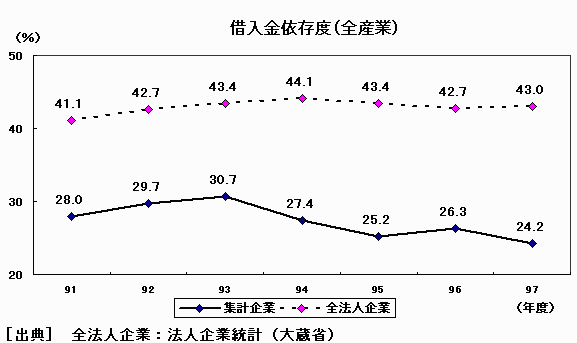
(5)投資関連の状況
- 97年度の集計企業の設備投資額は7044億円で、非製造業(1339億円 前年度比50.6%増)が大幅増加したことから、全産業で同8.3%の増加となった。非製造業における増加額(450億円)は、設備投資額全体における増加額(537億円)の約8割を占める。
- このうち、集計企業が我が国で行った再投資をみると、全産業で前年度比10.6%増の6955億円となった。これは、商業における再投資(1168億円 同52.6%増)の増加を中心とした非製造業の増加が大きく寄与しており、再投資全体に占める割合も同4.6ポイント上昇させている。
- 一方、研究開発の状況を売上高研究開発費比率でみると、前年度と比べ0.5ポイント上昇の2.6%となった。このうち、製造業の売上高研究開発費比率(3.0%)を全法人企業(3.8%)と比べると、水準的には0.8ポイント低い水準となっているものの、その差は前年度と比べ0.4ポイント縮小(1.2ポイント→0.8ポイント)しており、集計企業の積極的な研究開発活動の一端がうかがえる。
- また、97年度時点で集計企業が保有する研究所の分布をみると、全産業で170研究所が設立されており、このうち、製造業が化学・医薬品、電気機械を中心として135研究所(シェア79.4%)、非製造業が商業を中心に35研究所(同20.6%)を保有している。これを研究所の設立年度別でみると、1989年度からの10年間に設立されたものが全体の45.1%を占めており、特に非製造業では全体の70.6%に達していることからも、比較的近年に設立されたものが多いことがわかる。これらの研究所が有する機能としては「主に日本をターゲットにした製品開発」(シェア36.1%)、「日本国内での販売活動サポート」(同24.1%)等が主であった。
(6)雇用の状況
- 97年度の集計企業の従業者数は24万2994人で前年度に比べ5.5%の増加。全法人企業における従業者数(4096万6千人 同0.5%増)の伸び率を上回ったものの、全法人企業に占める割合は前年度と変わらず0.6%であった。しかしながら、1企業当たりでみると、非製造業(70人)で同2.3%増加したものの、製造業(334人)では比較的規模の大きい石油(660人 同5.9%減)、輸送機械(604人 同3.5%減)等で軒並み減少となったことから同3.2%減少しており、全産業(159人)では同0.9%減と2年連続減少。
- また、従業者のうち、外国側派遣者を役職別比率でみると、管理職(2.5%→2.5%)、一般職(0.6%→0.7%)ではいずれもほぼ横ばいとなっている一方、常勤役員では前年度と比べて2.1ポイント上昇(14.6%→16.7%)している点が特徴的であった。また、母国籍別では、いずれの地域でも常勤役員における比率が最も高くなっているが、欧米系企業では常勤役員の比率に変化がないのに対し、アジア系企業では大きく上昇している。
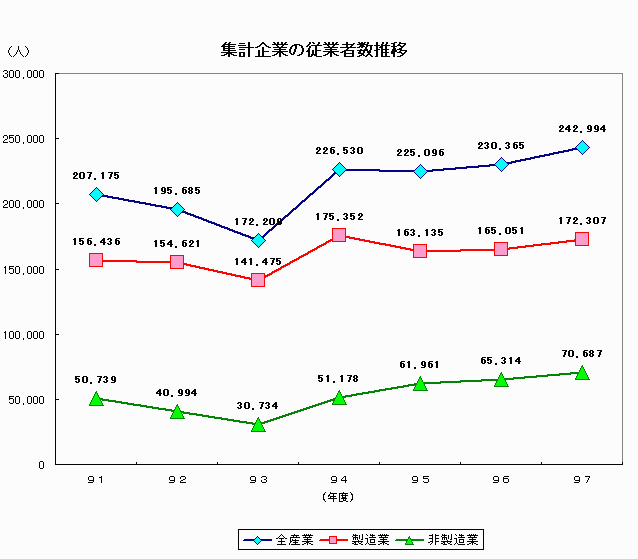
最終更新日:2007.10.1
