- 経済産業省ホーム
- 統計
- 海外事業活動基本調査
- 結果の概要
- 第28回海外事業活動基本調査結果概要-平成9(1997)年度実績-
- 撤退状況-平成11年5月18日公表-
撤退状況-平成11年5月18日公表-
海外事業活動基本調査
撤退企業数の推移
増加に転じた本社企業ベースでの撤退数
97年度における本社企業ベースでの撤退企業数(現地法人のすべてを撤退させた企業)は、45社(前年度比 9社増)と3年ぶりに増加に転じた。一方、現地法人ベースでの撤退企業数は、249社(同37社増)と2年連続の増加となっている。内訳については、製造業が109社(同22社増)、非製造業140社(同15社増)であった(第1-(4)-1-1図、第1-(4)-1-2図)。
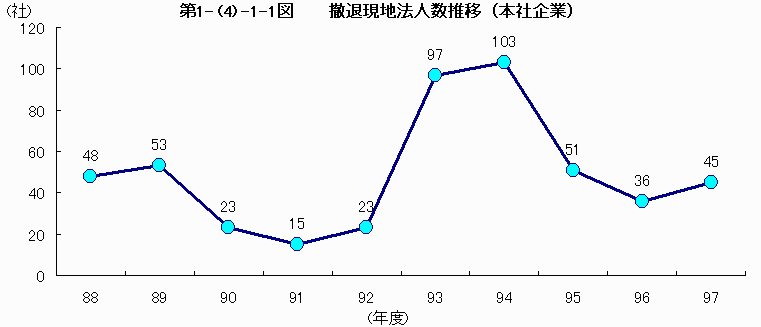
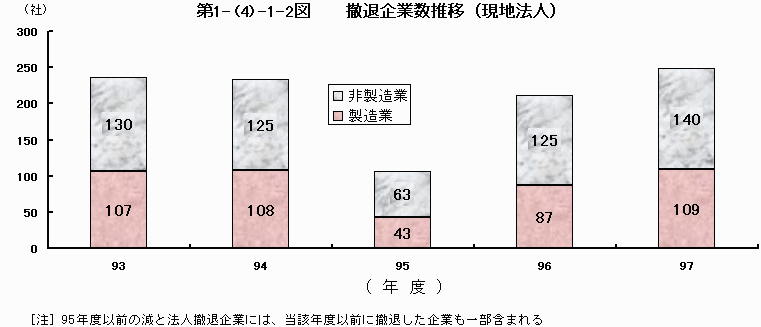
撤退企業における中堅・中小企業比率をみると、本社企業ベースで75.6%、現地法人ベースで20.9%と、それぞれ新規進出企業に占める中堅・中小企業の割合を上回っている(第1-(4)-1-1表)。
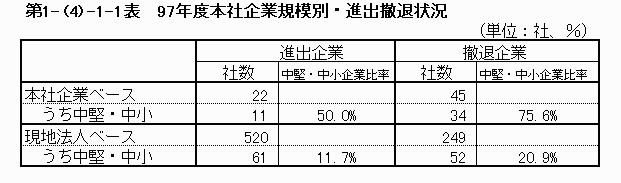
地域別の撤退企業数を前年度と比較すると、北米(前年度比23社増)、アジア(同10社増)、ヨーロッパ(同 3社増)ともに増加した。アジア地域の内訳については、NIEs4(同 6社増)、中国(同 4社増)において増加となった一方で、ASEAN4(同 1社減)では減少となっている(第1-(4)-1-3図)。
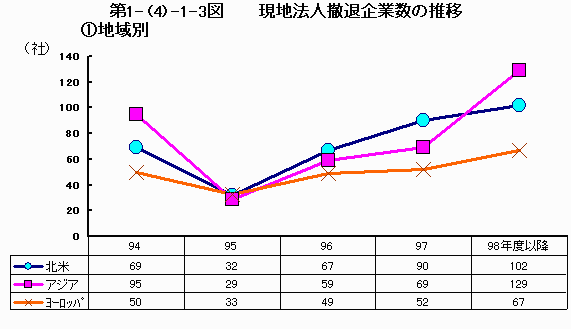
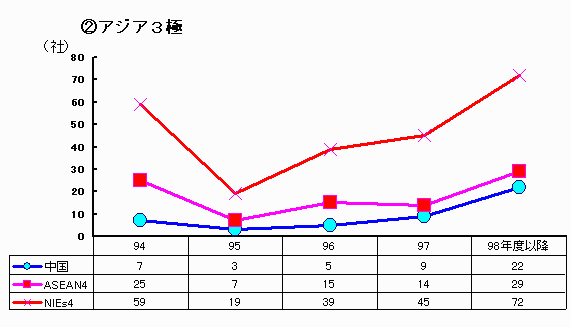
98年度以降に撤退を予定している現地法人数は352社となっているが、これは97年度撤退企業総数の約1.4倍の規模に相当する。地域別でみるとアジアが129社(シェア36.6%)と最多となっている。一方、97年度末現在における休眠中の現地法人数は312社であり、地域別では撤退予定企業数と同様、アジアが115社(同36.9%)と最多になっている(第1-(4)-1-2表、第1-(4)-1-3表)。
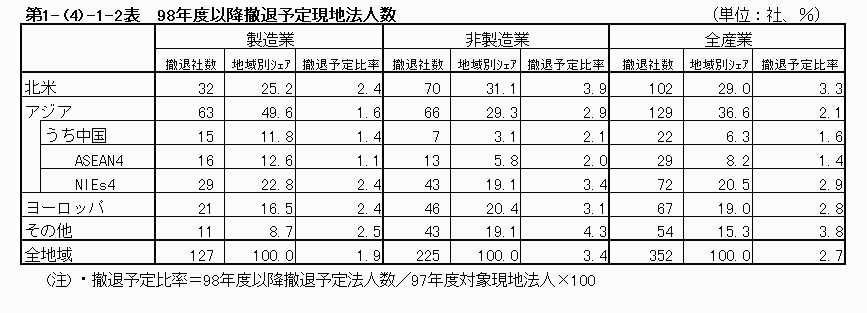
97年度における撤退状況
製造業ではアジア、非製造業では北米が最多
97年の地域別の撤退状況は以下のとおりである。
地域別では、北米が90社(撤退比率(注)2.9%)と最多となり、以下、アジア69社(同1.1%)、ヨーロッパ52社(同2.2%)となっている。アジアの内訳については、NIEs4が45社と全体の約65%を占めている。業種別では、製造業でアジアが43社(うちNIEs4が29社)、非製造業で北米が52社とそれぞれ最多となっている(第1-(4)-2-1表)。
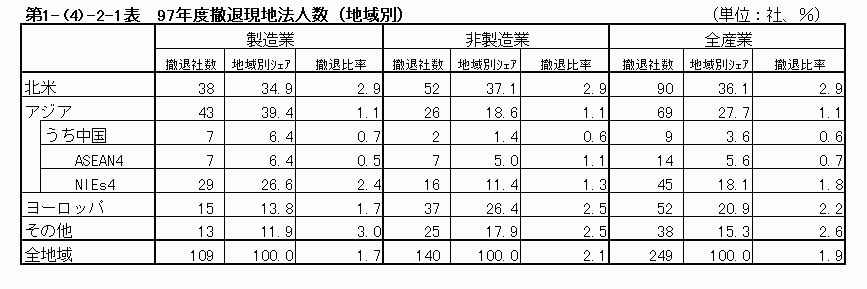
アジア地域(除く中国)について国別の状況をみると、台湾13社、韓国及びシンガポール各11社、香港10社の順となっているが、撤退比率でみた場合では、韓国が3.4%と最も高くなっている(第1-(4)-2-2表)。
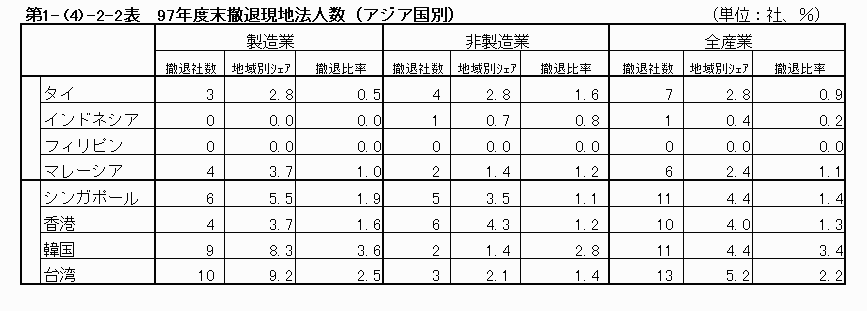
業種別にみると、
製造業では、電気機械が29社と最も多く、以下、輸送機械が15社、化学及び繊維各14社と続く(第1-(4)-2-1図)。
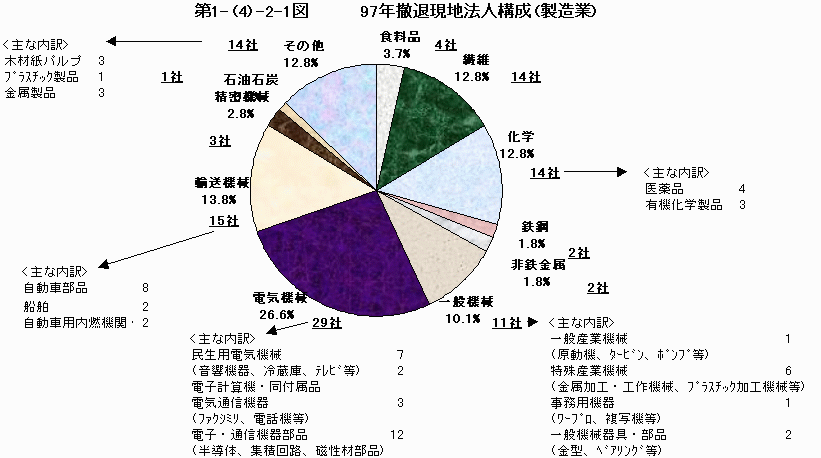
非製造業では、商業52社、サービス業43社、金融保険業15社、運輸業10社等となっている(第1-(4)-2-2図)。
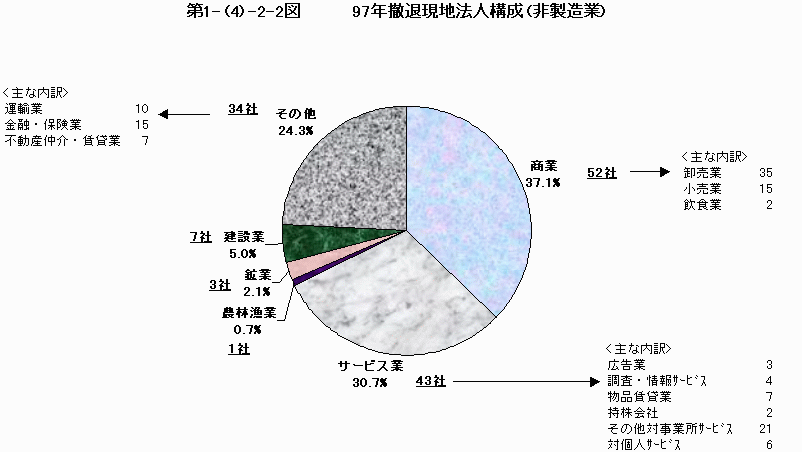
撤退後、他の拠点へ移転又は統合された現地法人数は、50社(撤退企業総数に占める割合20.1%)となっており、地域別の内訳についてみると、北米28社、ヨーロッパ12社、アジア 5社等となっている(第1-(4)-2-3図)。
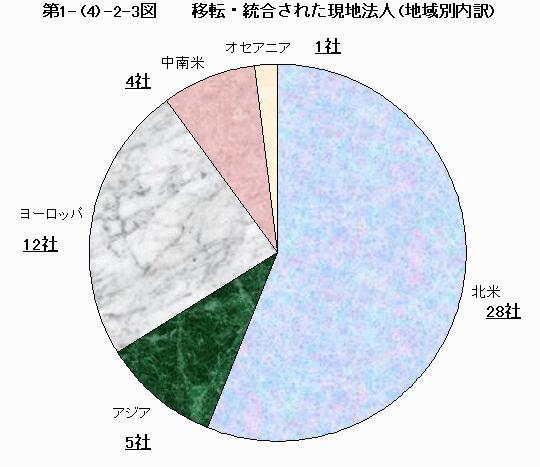
(注)・撤退比率=97年度撤退現地法人数/97年度対象現地法人数×100
撤退・休眠理由
地域によってばらつきのみられる撤退・休眠理由
現地法人の撤退・休眠理由について、「需要の見誤り」・「競争激化」による販売不振、収益悪化を挙げる企業が約4割と最も多く、“販売面における問題”が撤退・休眠の主要な理由となっている。以下、「短期的事業目的の終了」、「為替変動」、「パートナーとの対立」等の項目が続く(第1-(4)-3-1図)。
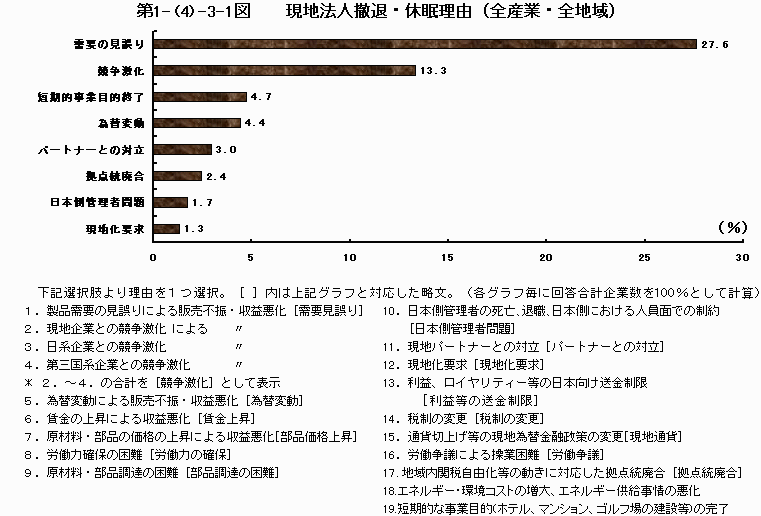
上記の“販売面における問題点”以外の理由について地域毎の特徴をまとめると以下のとおりである。
北米では「短期的事業目的終了」、ヨーロッパでは「拠点統廃合」といった事業計画上の項目が上位となっている。
中国では、「パートナーとの対立」、「日本側管理者問題」といった“現地法人運営面に関する問題”が多く、以下、「労働力確保」、「為替変動」、「短期事業目的の終了」等の項目が続く。
ASEAN4及びNIEs4においては両地域の経済情勢を反映して「為替変動」の回答率が高く、特に、ASEAN4では15.4%と他地域と比較して極めて高い数値となっている(第1-(4)-3-2図)。
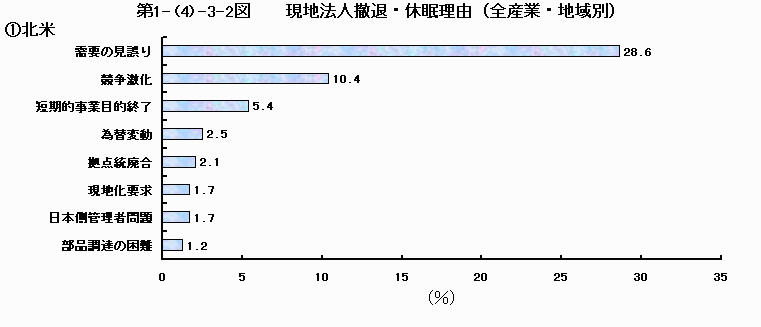
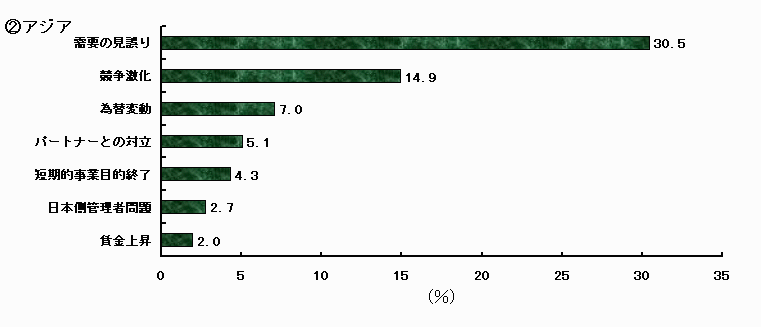
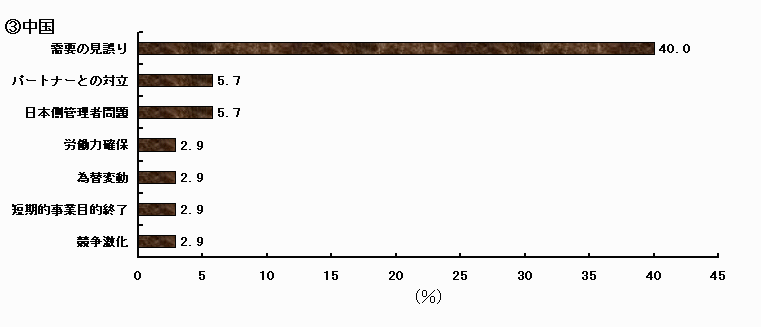
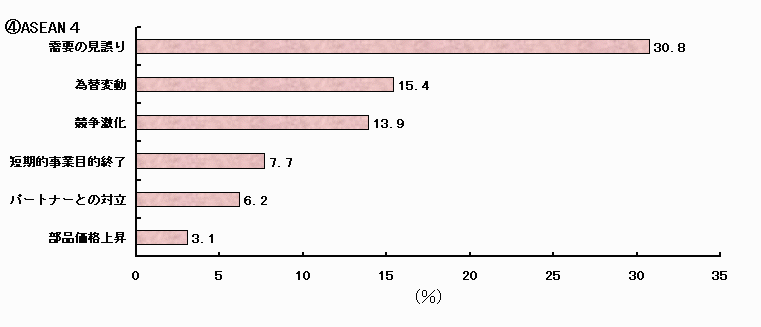
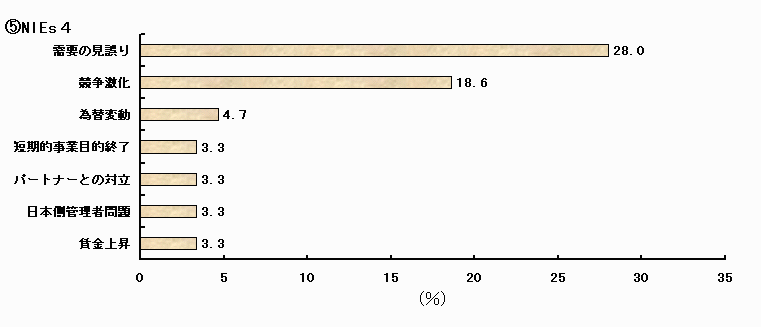
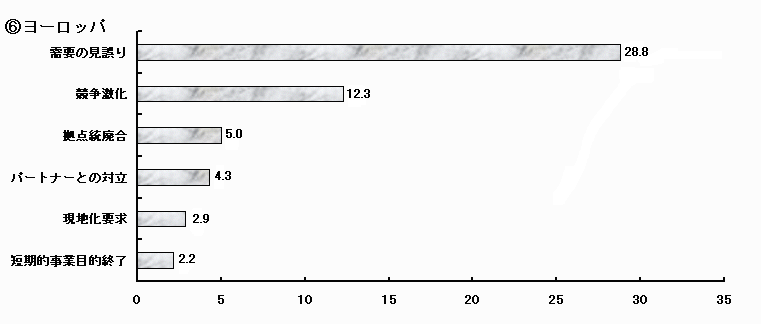
最終更新日:2007.10.1