国際産業連関表
集計結果又は推計結果
利用上の注意
2005年日米国際産業連関表
- 2005年日米国際産業連関表(以下、「日米表」という)は、日米両国における各産業の生産活動が、国内及び国外のどのような産業または最終需要との関連で行われているかを明らかにするため、2005年において日米両国内及び両国間で行われたすべての財・サービスの取引を一覧表にまとめたものである(第1図参照)。
第1図 日米表の構造
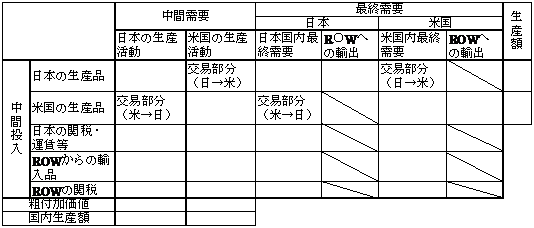
- この表をタテ方向にみると、日米の各産業が生産活動を行うにあたり、日米及びその他世界のどの商品をどれだけ使ったか、また、その生産活動によって、どのような付加価値をどれだけ生み出したか(費用構成)がわかる(注1)。
- また、この表をヨコ方向にみると、日米の各産業で生産された商品が、日米及びその他世界のどのような需要向けに、いくら販売されたか(販路構成)がわかる。
- 中間需要と中間投入に囲まれた領域の中の、日米及び米日の交易部分は、日米各産業の生産活動における相互依存関係を表している。ただし、関税及び海上運賃・保険料等は別掲されている。
(注1) このように、自国の生産品と他国の生産品を別々に記述した産業連関表を「非競争輸入型」(または「アイサード型」)の産業連関表という。
- 各財の価格評価は、日米それぞれの生産者価格で評価されている。すなわち、日本財の日本国内における取引及び米国における日本財の投入は、日本の生産者価格で、米国財の米国国内における取引及び日本における米国財の投入は米国の生産者価格で評価されている。商業部門及び運輸部門に計上されている日米間の取引は、日米それぞれの相手国向け輸出に係わる国内の商業マージン及び運賃を一括計上したものである。ROWとの取引は、輸出が表側の国(輸出国)の生産者価格なので、輸入は表頭の国(輸入国)のCIF価格(通関輸入ベース)で評価されている。
- 表の金額表示はドルである。日米表は、IMFの2005年の対ドル平均為替レート110.22円/ドルで換算している(1995年日米表は94.06円で、2000年日米表は107.77円でそれぞれ換算している)。
なお、国際間の産業連関分析を行う場合、購買力平価あるいは各商品別国際統一価格等による共通の価格評価を行うことが望ましいとされているが、方法論等については現在も研究段階であり、2000年日米表と同様、年平均レートで換算している。 - 2005年日米表の基本分類表は行列とも174部門で、2000年日米表よりも1部門減少した。
さらに、基本分類のほかに、「54部門表」及び「27部門表」の統合分類表も作成している。 - 2005年日米表では、もっとも詳細な174部門において、対角要素の自部門間取引に関し、自部門取引をゼロにし、生産額も同額だけ減額している。したがって、日本政府が正式に公表している産業連関表の生産額とは異なっている。
- 付帯表として、日米それぞれ輸出入マトリクス(20カ国・地域別輸出入額表)を作成した。輸出は生産者価格、輸入はCIF価格で評価している。
(注2) 生産者価格とは、いわゆる生産者の出荷価格(蔵出し価格)であり、運賃及びマージン等のマージンは含まれない。
用語の解説
- 自部門投入の処理:
- 産業連関表の生産額は、個々の商品毎の生産額を単純に積み上げたものであり、ある商品の原材料・部品として使用される場合、全体としての生産額は重複されて計上される。このような生産額の重複の違いは、日米両国の産業連関表を比較する際、無視できない取引として、同一部門の(行)と(列)の交点(「自部門投入」という)にのみ表れることに着目し、最も詳細な日米共通部門分類の段階で、国内製品の国内取引部分について「自部門投入」を強制的にゼロに置き換えることによって日米間の整合を図っている。
- 購買力平価:
- 各国の通貨の対内購買力の比率のこと(PPP:Purchasing power parity)。一般に通貨の対内購買力は物価指数の逆算としてとらえられる。「購買力平価指数」は、通常、国際間の通貨の購買力を比較する指数として用いられ、理論的には均衡為替 れートに対応すると考えられている。
- CIF価格:
- CIFとは、Cost Insurance and Freightの略で、産業連関表で輸入品の価格を評価するとき、国際貨物運賃及び保険料を含んだ「着港渡し」の価格である。輸出品の価格の評価は、FOB(Free on board)価格であり、積出港で買い手に渡す「本船渡し」の価格である。
その他
-
最終更新日:2013.5.20
