

- 統計

- 商業統計

- 統計表一覧

- 平成9年商業統計 業態別統計編(小売業)<概況>

- <トピックス1> 開設年別にみた業態別商店の状況
商業統計
<トピックス1> 開設年別にみた業態別商店の状況
- 多様化するニーズに対応し、業態も変化 -
- (1) 開設年別にみた商店数
-
業態別にその開設年をみると(第1図)、百貨店では昭和50年代に開設された商店が多いものの、20年代、30年代以外での開設割合も10%を超えている。なかでも19年以前の商店が18.1%と高いのは、老舗とよばれる昔ながらの百貨店が多いためである。また、各年代で一定の開設数がみられたのはその他のスーパー、専門店、中心店といずれも商店数の多い業態である。なお、中心店は19年以前に開設した商店の割合が最も多く、その中で食料品中心店の開設が5割を超えている。一方、総合スーパーは昭和40年代以降の開設が94.9%と、40年以降急激に開設がみられた新しい業態であり、平成4年以降の約6年間で26.1%の商店が開設となっている。専門スーパーは総合スーパー同様40年以降の開設が89.7%と高く、50年以降では2割を超える開設、平成4年以降にいたっては33.1%の開設となっている。総合スーパーや専門スーパーが平成4年以降大幅に増加した背景には、大規模小売店舗法の改正、バブル崩壊後の土地価格の低下などの影響に加え、ワンストップショッピングなどに代表されるように一か所でいろいろな商品が購入できる、また、ショッピングを兼ねたレジャーが楽しめる大型ショッピングセンターなどの開設がみられたことなどによる。コンビニエンス・ストア(以下、コンビニという)は平成4年以降の開設店が35.5%と最も多いが、昭和60年以降では6割近くの商店が開設しており、近年最も進展している業態である。なお、コンビニは、新業態でありながら昭和19年以前の開設店が9.8%、20年代、30年代、40年代においてもいずれも5?6%の開設がみられるが、これは、米、酒を扱っていた従来の小売店が、近年の消費者の利便性に合わせ、終日営業を中心とする長時間営業、弁当類や生活雑貨から書籍に至るさまざまの商品の品揃えなどを取り込んだコンビニスタイルに業態替えしたものと考えられる。
第1図 業態別の年代別開設状況
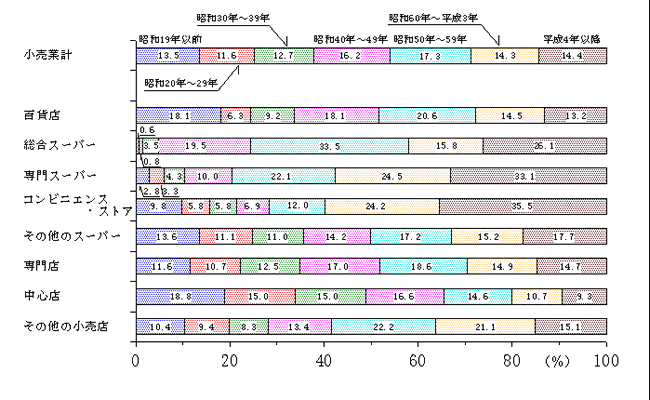
ここで、平成4年以降の開設状況をみると(第2図、第1表)、20万5千店の新設店のうち、その6割が専門店、次いで2割近くが中心店となっている。これを、年次別にみると、平成6年には営業時間や大型小売店舗法の改正などの規制緩和から百貨店、総合スーパー、専門スーパー、コンビニの新規開店が急増しており、7年以降は専門店、中心店も含め新規出店の割合が高まっている。
注:平成9年は6月1日調査第2図 平成4年以降開設店の業態別割合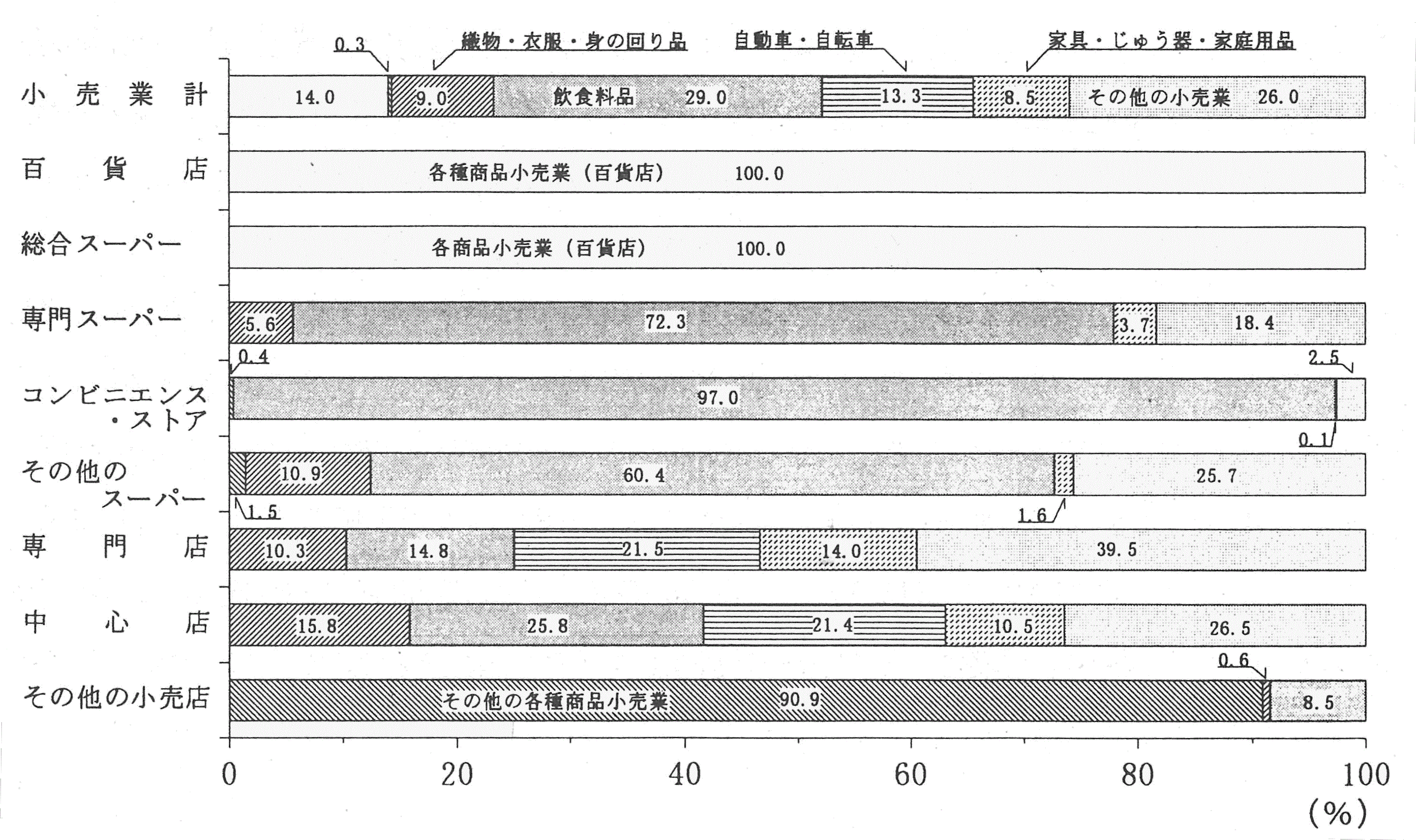 注:平成9年は6月1日調査第1表 平成4年以降の商店の開設状況
注:平成9年は6月1日調査第1表 平成4年以降の商店の開設状況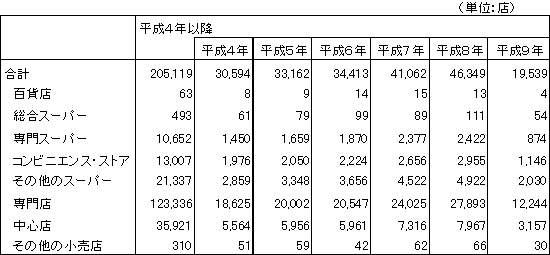
- (2) 平成4年以降のコンビニエンス・ストア及び専門スーパーの地域展開
-
平成4年以降開設商店の割合が高い専門スーパーとコンビニの開設年別・地域別の商店の展開状況をみてみる。
- 専門スーパー
専門スーパーの平成4年以降の開設商店をみると、東京、愛知、大阪、兵庫、北海道、福岡での開設が多い(第3図)。
平成4?5年には、愛知(188店)、北海道(170店)、埼玉(165店)、福岡、大阪、兵庫の6県において120店を超える開設となっている。平成6?7年においても、平成4?5年に120店以上の開設があった6県は引き続き120店以上の開設、加えて茨城、千葉、神奈川、長野、静岡でも120店以上の開設となり、11県で120店以上の開設がみられた。なかでも、愛知(295店)、埼玉(275店)、大阪(204店)、東京(200店)での開設は200店を超えた。平成8?9年では、調査時点が平成9年6月1日のため他の時点に比べ期間が短いものの、8県において120店以上の開設みられた。このように専門スーパーでは、東京、大阪、愛知、兵庫、福岡、北海道、埼玉などベッドタウン化が進んでいる大都市圏及び近隣県ではいずれの期間においても120店以上の開設が続いている。注:平成9年は6月1日調査第3図 専門スーパーの都道府県別開設年別の商店数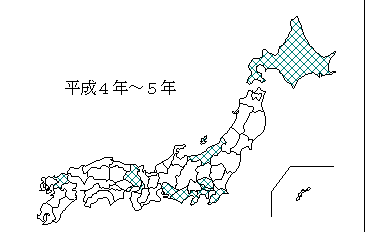
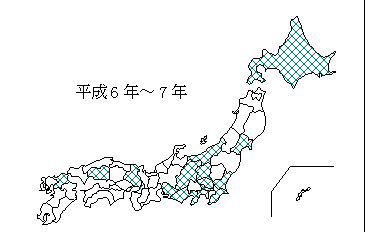
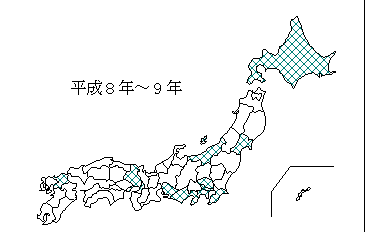
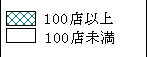
- コンビニエンス・ストア
コンビニの平成4年以降の開設商店をみると、人口の集中する大都市圏での開設が引き続き多いが、そのほかの地域へも開設の進んでいる状況がみられる(第4図)。
平成4?5年には、首都圏である関東から中部にかけての地域での開設が多く、四国、九州南部、山陰等での開設は30店未満と少ないものであった。平成6?7年は、大都市圏での開設が引き続き多く、九州ではすべての県で30店以上の開設となったが、四国、山陰での開設は30店未満となっている。平成8?9年には、山陰でも30店以上の開設と地方への展開が進展している。注:平成9年は6月1日調査第4図 コンビニエンス・ストアの都道府県別開設年別の商店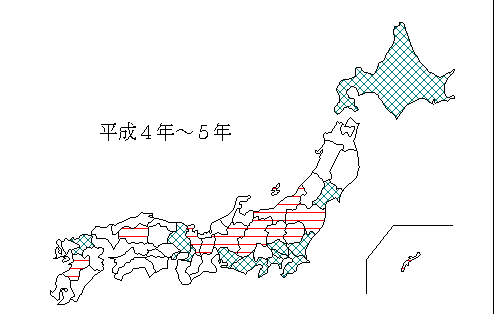
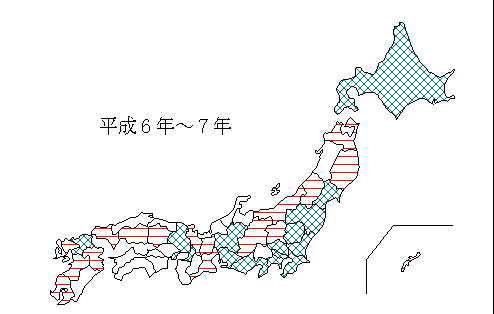
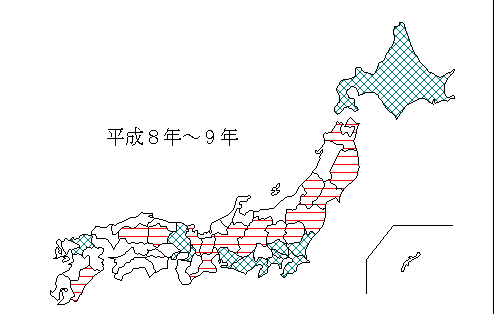
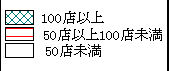
- 専門スーパー
- (3) 開設年別にみた年間販売額
-
年間販売額を開設年別にみると(第5図、第2表)、昭和50年?59年に開設された商店が最も多く、全体の21.5%を占めている。業態別にみると、百貨店は昭和19年以前に開設された商店、総合スーパー、専門スーパー、専門店、中心店は昭和50年?59年、コンビニ、その他のスーパーは平成4年以降開設された商店の年間販売額が多い。なお、ほとんどの業態が昭和50年以降の開設店ではそれぞれの年代で年間販売額の割合が2桁台と高いが、そのなかでコンビニは平成4年以降の開設店の年間販売額は35.6%とさらに高い割合となっている。
第5図 年間販売額の開設年別割合
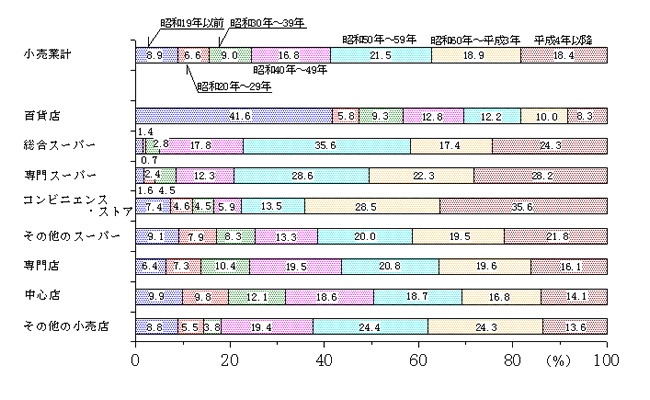 第2表 業態の開設年別年間販売額の状況
第2表 業態の開設年別年間販売額の状況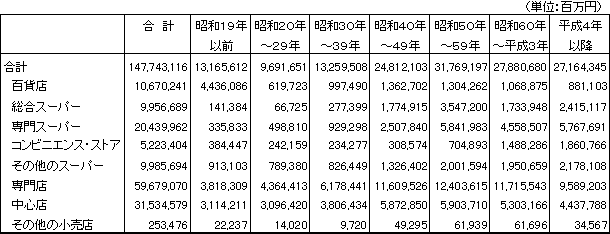
- (4) 1商店当たりの年間販売額
-
- 高いのは百貨店、伸びているのはスーパー -
開設年別に1商店当たりの年間販売額をみると(第3表)、百貨店では昭和19年以前の開設商店が516億円で最も高く、最も低いのは昭和50年?59年に開設した商店(1商店当たり年間販売額は133億円)であった。総合スーパーでは昭和19年以前の開設店(同118億円)が最も高く、最も低いのは昭和30年?39年(同41億円)となっており、百貨店、総合スーパーの大規模商店はいずれも、古くから開設している商店の1商店当たり年間販売額が高い。専門スーパーは1商店当たり年間販売額が最も高いのは昭和50年?59年(同8億円)の開設商店、また、コンビニ、その他のスーパー、専門店、中心店は昭和60年からバブル期である平成3年開設商店が最も高くなっており、これらの業態は近年になるほど、消費者ニーズにマッチした長時間営業や品揃えから、1商店当たり年間販売額は高いものとなっている(なお、平成4年以降の開設店の1商店当たり年間販売額が比較的低いのは、8年、9年に開設した商店の年間販売額が1年に満たないことなどが影響している)。第3表 業態別開設年別1商店当たり年間販売額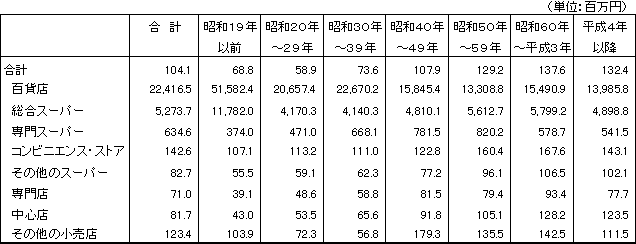
- (5) 開設年別商店の駐車場保有割合
-
- 駐車場は開設年が近年に近いほど保有 -
開設年別に駐車場の保有割合を小売業全体でみると、昭和50年以前の開設店では駐車場の保有割合は半分以下であった。これは、従来の商店が交通の便利な駅前や商業集積地区を中心に立地がみられ、駐車場の必要性はさほどなかったためと思われる。昭和50年以降の開設店をみると、開設が新しいほど駐車場の保有割合は高まり、新しく開設する商店にとって、駐車場の保有が立地条件の要素の一つといえる。
業態別にみると(第4表)、百貨店を除くほとんどの業態で開設が新しいほど保有割合が高く、なかでも総合スーパーは平成4年以降に開設された商店は100%、専門スーパーは97.1%の商店が駐車場を保有しており、保有割合の低い専門店でも57.4%と6割近くの商店が保有している。このように、駐車場の保有割合が高まっているのは、モータリゼーションを背景に、消費者が最寄りの商店から遠くの商店へと購買範囲が拡大したこと、週末のまとめ買い、ワンストップショッピングに代表されるように一か所でいろいろなものが買えること、レジャーを兼ねて買い物のできる大規模なショッピングセンターなどが郊外に多く立地されていることなど、車を交通手段とする消費エリアが拡大していることによるものといえる。一方、百貨店は、平成3年までの開設店の駐車場保有割合はほぼ9割であったが、平成4年以降の開設店ではほぼ6割強と大幅に低下しているが、これは、最近は交通の便利な駅前や市街地に開設される百貨店が多かったと考えられる。このように、多様化する消費者ニーズの中、利便性や規制緩和などを背景に平成4年以降大幅に開設のみられるコンビニ、専門スーパー、総合スーパー、また、店舗の大型化、近年開設店のほとんどが駐車場を保有する割合が高まるなど、小売業は消費者のさまざまなニーズに対応しつつ大きく業態変化を遂げてきた。第4表 業態別の開設年別商店の駐車場保有割合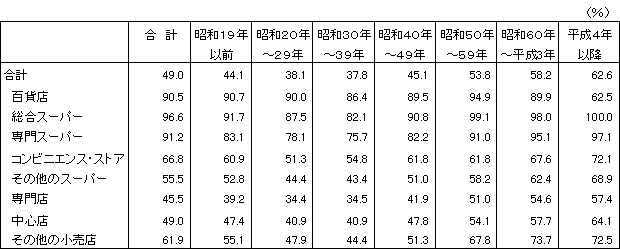
最終更新日:2007.10.1
