PRTRに関するQ&A(PRTR排出等算出マニュアル)
よくある質問
| 対象事業者関係 | 対象物質関係 |
| 政令改正関係 | 電子届出関係
|
PRTRに関するQ&Aの質問リスト
事業者等からよくある質問をまとめてあります。該当する事例や似ている事例がありましたら、参考にしてください。
- 1.届出に関するもの
- 2.対象業種・事業所の範囲に関するもの
- 3.常時使用する従業員の数に関するもの
- 4.対象物質に関するもの
- 5.取扱量の把握に関するもの
- 6.排出量・移動量の算出に関するもの
- 7.特別要件施設に関するもの
1.届出に関するもの
- 1-1 届出全般に関するもの
- 問1-1-1 提出するもの
- 問1-1-2 輸入に係る手続きの必要性
- 問1-1-3 代理者による届出
- 問1-1-4 法人の外部の者の代理人としての届出
- 問1-1-5 本社の住所が登記簿上の所在地と異なる場合
- 問1-1-6 「前回の届出における名称」の記入
- 問1-1-7 同一都道府県内に複数の事業所がある場合の磁気ディスクによる届出
- 問1-1-8 主たる業種以外の業種における秘密情報の請求
- 問1-1-9 届出要件を満たさなくなった時
- 問1-1-10 届出担当者等を変更する場合の手続き
- 1-2 事業者・事業所の移転・合併・廃業等に関するもの
- 問1-2-1 事業所が移転した場合
- 問1-2-2 複数の事業者が合併した場合
- 問1-2-3 事業所が独立した場合
- 問1-2-4 把握対象年度の翌年度に事業を開始した場合
- 問1-2-5 年度途中に会社が倒産、工場が閉鎖、事業所名称が変更した場合
- 1-3 事業者間の委託関係等に関するもの
- 問1-3-1 工程の一部を別の事業者に委託している場合
- 問1-3-2 同一敷地内に子会社がある場合
- 問1-3-3 貸している土地で事業活動を行っている場合
- 問1-3-4 隣接する異なる事業者の事業所で管理を共同で行っている場合
- 問1-3-5 薫蒸庫を貸している場合
2.対象業種・事業所の範囲に関するもの
- 2-1 対象業種・事業所の範囲全般に関するもの
- 問2-1-1 業種コードの記入方法
- 問2-1-2 日本標準産業分類の改正に伴う業種コードの記入
- 問2-1-3 事業所の範囲の判断
- 問2-1-4 対象業種以外の事業のみを行っている場合
- 問2-1-5 非対象業種
- 問2-1-6 対象業種以外の事業も行っている事業所の場合
- 問2-1-7 複数の業種を兼業している場合
- 問2-1-8 民間事業所内や自衛隊駐屯地等に併設された診療施設
- 問2-1-9 大学病院の場合
- 問2-1-10 企業が経営する病院の場合
- 2-2 行政機関の事業所に関するもの
- 問2-2-1 国や地方公共団体等の公務の根拠
- 問2-2-2 国や地方公共団体等の届出者、従業員数
- 問2-2-3 国や地方公共団体等の届出のあて先となる事業所管大臣
- 2-3 上記以外の業種に関するもの
- 問2-3-1 その他製造業に該当する業種
- 問2-3-2 自動車部品等を販売している事業者がフロン類の抜き取りをしている場合
- 問2-3-3 建設工事中の発電所
3.常時使用する従業員の数に関するもの
4.対象物質に関するもの
- 4-1 金属等の化合物に関するもの
- 問4-1-1 金属化合物の届出対象となる個別物質の範囲
- 問4-1-2 有機スズ化合物の範囲
- 問4-1-3 「水溶性」と限定している化合物の個別物質の範囲
- 問4-1-4 「亜鉛の水溶性化合物」における個別物質の範囲
- 問4-1-5 1つのPRTR対象物質に複数の物質が該当する場合
- 問4-1-6 金属等の化合物の年間取扱量、排出量等の考え方
- 問4-1-7 六価クロム化合物が中和沈澱処理により三価クロム化合物になる場合
- 問4-1-8 ふっ化水素酸の一部がふっ化水素の気体となって排出される場合
- 4-2 金属等以外の対象物質に関するもの
- 問4-2-1 水加ヒドラジンを取り扱う場合
- 問4-2-2 ヒドラジン誘導体を取り扱う場合
- 問4-2-3 ダイオキシン類に含まれるコプラナーPCBの考え方
- 問4-2-4 事業活動に伴い付随的に生成、または排出される物質の範囲
- 問4-2-5 別名がある物質の届出
- 4-3 その他
- 問4-3-1 今後の対象物質の変更の可能性
5.取扱量の把握に関するもの
- 5-1 製造量の把握に関するもの
- 問5-1-1 同一物質を含む原材料を多数使用している場合
- 問5-1-2 ナフサに含まれる対象物質を抽出している場合
- 問5-1-3 火力発電所で石炭中に微量に含まれている対象物質が排出されている場合、クラフトパルプ漂白時にクロロホルムが生成する場合
- 問5-1-4 金属板をエッチングする場合
- 問5-1-5 密閉された製品を他社から仕入れ、そのままの状態で他へ転売する場合
- 5-2 対象物質の含有率に関するもの
- 問5-2-1 用いる対象物質の含有率
- 問5-2-2 1質量%未満の対象物質を合算すると1質量%を超える場合
- 問5-2-3 対象物質を溶媒等で希釈している場合
- 問5-2-4 対象物質が濃縮される場合
- 問5-2-5 取り扱う製品中の対象物質の含有率が1質量%未満の場合
- 問5-2-6 消費者用製品を製造する場合の取扱量の把握
- 問5-2-7 石油系燃料等に含まれる対象物質
- 5-3 取扱量を把握する原材料、資材等の要件に関するもの
- 問5-3-1 取扱量を把握する必要のない原材料、資材等
- 問5-3-2 一般消費者用の製品
- 問5-3-3 ハンドソープ中に第一種指定化学物質が含まれる場合
- 問5-3-4 廃棄物を受けいれている場合
- 問5-3-5 ブラウン管や蛍光灯を取り扱う場合
- 問5-3-6 白熱灯や蛍光灯を取り扱う場合
- 問5-3-7 電子回路基板のような半製品を購入している場合
- 問5-3-8 ステンレス鋼の製品を取り扱う場合
- 問5-3-9 難燃剤を含む生地を取り扱う場合
- 問5-3-10 古くなった機器をメーカーに引き取ってもらっている場合
- 問5-3-11 ダイオキシン類を含む焼却灰をレンガの原料としている場合
- 問5-3-12 PCBを含むコンデンサーを倉庫内に保管している場合
- 問5-3-13 溶接芯線、溶接母剤を使用している場合
- 問5-3-14 対象物質を含むステンレス板を溶接により接合等している場合
- 問5-3-15 はんだを使用している場合
- 問5-3-16 ガラスを使用している場合
- 問5-3-17 ペレット製造の際に添加剤を練りこむ場合
- 問5-3-18 ペレットを原料に電線の被覆材等を成型加工している場合
- 問5-3-19 対象物質を含む切削工具を使用している場合
- 問5-3-20 金属やプラスチック等を研磨・切削している場合
- 問5-3-21 スラグ中に鉛を含む場合
- 問5-3-22 混合物における年間取扱量の考え方
- 5-4 その他取扱量の把握に関するもの
- 問5-4-1 届出の対象となる年度以前に受けいれた在庫品を使用した場合
- 問5-4-2 事業所内で発生する成型くずを再利用している場合
- 問5-4-3 職員等の健康管理を目的としたレントゲン室で現像液を取り扱う場合
- 問5-4-4 自動車整備業でフロンの抜き取り作業を行う場合
- 問5-4-5 芝生にまく農薬、食堂において洗剤、工場の壁を塗る塗料、社用車のガソリンを使用している場合
6.排出量・移動量の算出に関するもの
- 6-1 排出量・移動量の届け出の分類に関するもの
- 問6-1-1 同一法人の他の事業所に廃棄物を搬出している場合
- 問6-1-2 廃油をリサイクル業者に搬出している場合
- 問6-1-3 事業者Aが発生した金属くずを別の事業者Bへ引き渡し、事業者Bはそれを中間処理した金属を事業者Cに販売している場合
- 問6-1-4 金属くず等を有料で引き取ってもらう場合
- 問6-1-5 発生した廃液を同じ事業者の別の事業所に運び、その事業所で処理を行い公共用水域へ排出している場合
- 問6-1-6 農業用水路に排出している場合
- 問6-1-7 溶接の際、大気中に排出される金属ヒュームの場合
- 問6-1-8 燃焼施設から排出される金属化合物等の場合
- 6-2 実測を用いた算出方法に関するもの
- 問6-2-1 廃棄物中の対象物質含有率の実測値がない場合
- 問6-2-2 焼却灰等の溶出試験結果の適用可能性
- 問6-2-3 排ガス・排水処理施設の除去率、実測濃度がない場合
- 問6-2-4 測定データが検出下限以上、定量下限未満、あるいは検出下限未満の場合
- 問6-2-5 ダイオキシン類の測定データが検出下限以上、定量下限未満、あるいは検出下限未満の場合
- 6-3 種々の工程における排出量等の算出に関するもの
- 問6-3-1 指定化学物質を凝集剤として使用している場合
- 問6-3-2 めっき等の工程における製品や半製品としての搬出量の把握
- 問6-3-3 ニッケルを電極、ニッケル化合物をめっき液として使用するめっき工程
- 問6-3-4 活性炭により吸着回収した対象物質を再利用している場合
- 問6-3-5 パイプラインのつなぎ目やフランジから漏洩している場合
- 問6-3-6 有機溶剤焼却装置に助燃剤としてトルエンを使用している場合
- 問6-3-7 洗剤製造時の乾燥工程
- 問6-3-8 試薬等を容器に充填する場合
- 問6-3-9 研究所における排出量等の算出
- 問6-3-10 機械修理業における排出量等の算出
- 問6-3-11 事業所外での事業活動がある場合
- 6-4 自動車・給油施設等からの排出量の把握に関するもの
- 問6-4-1 事業所で自動車を保有している場合
- 問6-4-2 船舶を保有している場合
- 問6-4-3 事業所内に、業としてガソリンを給油する施設がある場合
- 問6-4-4 構内専用の車両(フォークリフト等)を保有している場合
- 問6-4-5 ガソリンスタンドの場合
- 問6-4-6 対象物質を輸送している場合
- 問6-4-7 重油の取り扱い
- 6-5 その他
- 問6-5-1 大気と水域への排出量を比較する場合
- 問6-5-2 外資系の企業で排出量等を年次単位で把握している場合
- 問6-5-3 届出書別紙中に記載する河川等の名称
- 問6-5-4 年間取扱量の記載の必要性
- 問6-5-5 環境中への排出がほとんどない場合
7.特別要件施設に関するもの
- 問7-1 一般・産業廃棄物処理施設、下水道終末処理施設を設置している事業が届け出る物質
- 問7-2 他法令に基づく測定項目以外の排出量等
- 問7-3 他法令で測定義務があるにもかかわらず測定していない場合
- 問7-4 放流水のない一般廃棄物最終処分場、排水が出ない構造の一般廃棄物焼却施設の場合
- 問7-5 溶解性マンガン等の他法令の測定項目とPRTR 対象物質の範囲が異なる場合
- 問7-6 EPNの測定結果
- 問7-7 焼却灰中の水銀
- 問7-8 対象業種に属する事業所の接続がないことが明らかな下水道の場合
- 問7-9 測定結果が定量下限値以下の場合
- 問7-10 市町村の設置した一般廃棄物処理施設
- 問7-11 一部事務組合等が民間企業に委託している場合の従業員の数
- 問7-12 一般廃棄物焼却施設・最終処分場で下水道放流している場合
- 問7-13 ごみ処分業とし尿処理業のそれぞれの焼却施設を設置している場合
- 問7-14 粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等再生利用施設、運搬中継施設等が独立した事業所である場合
PRTR排出量等算出マニュアルに関するQ&Aの回答編
1.届出に関するもの
1-1 届出全般に関するもの
問1-1-1 (提出するもの)
何を提出すればよいのですか。
答 「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」(各事業所の概要を記載するもの及びその別紙として対象物質ごとの排出量、移動量を記載するもの)を主務省令で定められた様式に従って、提出してください。
なお、作業シートについては、提出する必要はありません。
問1-1-2 (輸入に係る手続きの必要性)
対象物質を輸入する場合、化管法の手続きは必要でしょうか。
答 化管法は、日本国内で対象物質を取り扱う場合のPRTR届出やSDS提供等を規定しています。このため、輸入に関しては化管法の手続きはありません。 ただし、対象物質を輸入し他の事業者に販売する場合はSDSの提供義務とラベル表示の努力義務が発生します。
問1-1-3 (代理者による届出)
届出は法人の代表者名で行うこととされていますが、代理者が届出を行うことはできないのでしょうか。
答 工場長や事業所長など当該事業所の化学物質管理に責任を有する者に届出を委任し、代理者を記入できるよう運用しております。(PRTR届出の手引き参照)
問1-1-4 (法人の外部の者の代理人としての届出)
法人の外部の者を届出の代理人とすることは認められますか。
答 代理人として選定できるのは、あくまで「工場長や事業所長など当該事業所の化学物質管理に責任を有する者」であり、届出対象となる事業者の組織に所属しない者(別法人の代表者など)を法人の代理人として届け出ることは認めていません。
問1-1-5 (本社の住所が登記簿上の所在地と異なる場合)
届出者の住所(本社所在地)の取扱いについて登記簿上の所在地には届出者の事業所はまったく存在せず、本社機能は別の場所にある事業者の場合、事業者の住所としては登記上のものを記載すべきでしょうか。それとも、実際の本社所在地を記載すべきでしょうか。
答 実際の本社所在地と登記上の住所が異なる場合は、本法においては、登記上の住所を記載してください。
問1-1-6 (「前回の届出における名称」の記入)
届出書本紙の「前回の届出における名称」の欄は何を記入するのでしょうか。
答 御指摘の欄は、事業者又は事業所の名称が、前回の届出時における名称から変更された場合(会社又は事業所の名称変更、合併等の場合)のみ記入してください。(PRTR届出の手引き参照)
事業者が合併した場合は、合併前の事業者名をすべて記入してください。
事業所を合併もしくは買収した場合は、合併もしくは買収前の事業所名をすべて記入してください。
問1-1-7 (同一都道府県内に複数の事業所がある場合の磁気ディスクによる届出)
一事業者が、その同一都道府県内に複数の事業所を有し、磁気ディスクによる届出を行おうとする場合、複数の事業所に係る届出を一枚の「磁気ディスク本体」及び「磁気ディスク提出票」にまとめて提出してもよいでしょうか。
答 この場合、ある事業者の同一の都道府県内に所在する事業所については、一枚の磁気ディスク及び磁気ディスク提出票でまとめて提出して差し支えありません。ただし、磁気ディスクのラベルには、届出に係る情報を記録した事業所の名称をすべて記載してください。また、各事業所の届出が判別できるよう、別個のファイル名で保存してください。(例:具体的な事業所名又は事業所1、事業所2...など。) なお、同一県内でも、千葉県と千葉市等、提出自治体の窓口が異なる場合は磁気ディスクを分けて届出する必要があります。
問1-1-8 (主たる業種以外の業種における秘密情報の請求)
事業者が主たる業種以外の業種で行う事業において、秘密情報の請求を行う必要が生じた場合、当該請求はいずれの事業所管大臣に行うのでしょうか。
答 主たる事業を所管する大臣ではなく、秘密情報に係る事業を所管する大臣あてに請求(まずは事前相談)を行ってください。(PRTR届出の手引き参照)
問1-1-9 (届出要件を満たさなくなった時)
従来届出を行ってきましたが、届出要件を満たさなくなった場合届出が必要でしょうか。
答 届出要件を満たさなくなった場合、届出は不要です。
問1-1-10 (届出担当者等を変更する場合の手続き)
人事異動に伴い、電子届出システムに登録した届出担当者が変わることになりました。この場合、どのような手続きを行えば良いでしょうか。
答 登録した届出者、代理人、届出担当者等に変更が生じた場合には、変更のあった時点で速やかに、電子届出システム上で「電子情報処理組織変更届出」を自治体に提出してください。本変更届出が自治体に受理されれば、変更が有効となり、次回届出等に反映されます。
1-2 事業者・事業所の移転・合併・廃業等に関するもの
問1-2-1 (事業所が移転した場合)
届出年度の前年度途中に事業所が移転し、事業所名を変更した場合、届出上の事業所の名称及び所在地は、どのように記載するのでしょうか。
答 移転前と移転後の2つの事業所として扱ってください。従って、移転前の事業所と移転後の事業所それぞれについて届出を行ってください。
問1-2-2 (複数の事業者が合併した場合)
年度途中で対象事業者を含む複数の会社が合併した場合、どの主体がいかなる届出を行わなければならないのでしょうか。例えば、平成15年10月1日付けで、事業者AとB(いずれも第一種指定化学物質等取扱事業者)が合併して事業者Cとなり、事業者Aの事業所a1の名称が事業所c1に、事業者Bの事業所b1の名称が事業所c2に改められたとすると、具体的な届出はどうなりますか。
答 把握対象年度に対象物質の把握義務を負っていた事業者の権利義務を承継する主体が次年度に届出を行ってください。 上記の例においては、事業者A及び事業者Bが負っている届出の義務は、事業者Cに承継されており、届出を行うのは事業者Cです。 その際、事業者Cが提出すべき届出書は以下の2通となります。
(1)平成15年4月1日~平成16年3月31日までの排出量等を記入した届出書(事業者名:A、事業所名:a1)(実際には、平成15年4月1日~平成15年9月30日の「事業所a1」としての排出量等及び平成15年10月1日~平成16年3月31日の「事業所c1」としての排出量等を合算)
(2)平成15年4月1日~平成16年3月31日までの排出量等を記入した届出書(事業者名:B、事業所名:b1)(実際には、平成15年4月1日~平成15年9月30日の「事業所b1」としての排出量等及び平成15年10月1日~平成16年3月31日の「事業所c2」としての排出量等を合算)
いずれも、「届出者」の欄には、事業者Cの名称を記載してください。
問1-2-3 (事業所が独立した場合)
A社で対象物質を取り扱っていた工場が4月1日に独立し、別会社Bになりました。4月1日以降、A社では対象物質を取り扱っていませんが、その場合、前年度分(A社の工場時代分)の排出・移動量に係るPRTR届出は、A社と独立したB社のどちらが行うことになるのでしょうか。
答 把握対象年度に対象物質の把握義務を負っていた事業者の権利義務を承継する主体が次年度に届出を行うことになります。このため、A社のPRTR届出義務を継承したB社がPRTR届出を行うことになります。なお、B社がA社の工場時代のPRTR届出を行う際には、事業所名はA社の工場名を記載してください。
問1-2-4 (把握対象年度の翌年度に事業を開始した場合)
把握対象年度(例えば、平成14年度)には事業を行っていなかったのですが、その翌年度(平成15年度)に事業を開始した場合、その年度(平成15年度)に届出の必要はありますか。
答 把握対象年度に取扱量等の要件を満たさないこととなるので、届出の必要はありません。
問1-2-5 (年度途中に会社が倒産、工場が閉鎖、事業所名称が変更した場合)
(1)年度途中で会社が倒産したような場合、次の年度に届出は行わなければならないのでしょうか。
(2)年度途中で工場(事業所)を閉鎖した場合、次年度に当該事業所に関する届出は行わなければならないのでしょうか。
(3)年度途中で事業所の名称を変更した場合、変更前後のいずれの名称を次年度の届出書に記載すべきでしょうか。
(4)PRTRの届出後に、届出者である代表者が変更になりました。その時点で直ちに変更届出を出す必要はあるのでしょうか。 また、PRTR の届出期間内(4月~6月末)であった場合、変更届出を出す必要はあるのでしょうか。
答
(1)対象事業者であった事業者(A社)の権利義務が他の会社(B社)に承継されている場合は、後者(B社)が前者(A社)の分の届出を行う必要があります。一方、事業者の廃業や法人の解散等により、対象事業者であった事業者(A社)の権利義務を承継する主体がない場合は、届出の必要はありません。
(2)年度途中で廃止された事業所については、原則として、把握対象年度の期首(4月1日)から廃止までの期間における対象物質の排出量等を届け出ていただくことになります。なお、年度途中で廃止された事業所(廃止事業所)を有していた事業者が存続している場合は、当該事業者が廃止事業所の所在していた都道府県知事を経由して、当該廃止事業所における廃止までの期間の排出量等の届出を廃止の翌年度に行ってください(事業者が変更している場合は、①を参照)。
(3)年度途中で名称変更があった場合の事業所については、原則として、把握対象年度の期首(4月1日)現在における事業所名を 記載してください。(ただし、年度中に新たに設置された事業所については、設置時の名称を記載してください。)
(4)届出者である代表者の情報は、書面及び磁気ディスクによる届出の場合は提出日、または電子による届出の場合は送信日における代表者の情報の記入をお願いしております。届出後に代表者が代わった場合、PRTRの届出期間内である4月~6月であったとしても、代表者の変更手続きは必要ありません。
1-3 事業者間の委託関係等に関するもの
問1-3-1 (工程の一部を別の事業者に委託している場合)
A事業者が、その事業所内で行っている製造工程等の一部の工程について別のB事業者に委託している場合、委託した一部の工程の分の届出はどちらが行うのでしょうか。
答 事業を委託する場合でも、その委託の内容や形態は非常に多岐にわたっており、一概にどちらとはいえません。このため、以下のように整理しております。
委託先のB事業者の担当している工程での事業活動をA事業者が管理している(B事業者の化学物質の取扱いについての責任者がA事業者に存在する)場合は、委託している工程を含めてA事業者が全体の排出量等を届け出てください。この場合、その工程で働いているB事業者の従業員はA事業者の従業員とみなされます。
逆に、B事業者の事業活動をB事業者が自ら管理している(B事業者の化学物質の取扱いについての責任者がB事業者自身に存在する)場合は、委託された一部の工程からの排出量等についてはB事業者が、その他のA事業者の持つ工程(A事業者が排出量等を把握)とは別に届出を行ってください。なお、作業委託・業務委託は、通常契約書に基づくものであり、契約書に従うまたは契約内容を契約書で明確にすることが望ましいです。更に、作業委託の場合は作業細則を明記する必要があります。
問1-3-2 (同一敷地内に子会社がある場合)
同一敷地内にA社とB社のそれぞれの工場がありB社がA社の子会社の場合、A社が一括して届出を行うことは出来ないのでしょうか。
答 事業者が異なる(法人格が異なる)場合、同一敷地内にある事業所であっても、届出は原則としてA社とB社がそれぞれ別個に行ってください。問1-3-1も参照してください。
問1-3-3 (貸している土地で事業活動を行っている場合)
A事業者が貸している土地でB事業者が事業活動を行っている場合、そこから排出される対象物質の量についての届出はどちらが行うのでしょうか。
答 土地の所有者から一概にどちらかを判断することはできません。このため、問1-3-1と同様に、B事業者の事業活動を管理している(B事業者の化学物質の取扱いについての責任者が所属している)のがどちらの事業者になるかによって判断してください。
問1-3-4 (隣接する異なる事業者の事業所で管理を共同で行っている場合)
事業者が異なる事業所(事業場・工場)が2つ隣接しており、環境面の管理を共同で行っている場合、1つの事業者が一括して排出量・移動量を届け出ることは可能ですか。
答 法律においては、事業者に届出義務が課せられるため、それぞれの事業者に管理者が存在する場合はそれぞれの事業者が別々に届け出てください。問1-3-1も参照してください。
問1-3-5 (薫蒸庫を貸している場合)
薫蒸庫を所有する事業者が、薫蒸業者との契約に基づき、薫蒸庫を貸しています。当該事業者は薫蒸業者から利用料を定期的に徴収していますが、薫蒸に用いる化学薬品の内容はまったく知りません。このような場合、排出量等の届出を行うのは、施設の持ち主ですか、それとも、実際に薫蒸業を行っている薫蒸業者ですか。
答 当該事業者が倉庫業を営んでおり、その了解のもとに、倉庫内で薫蒸業者が薫蒸作業を行っている場合は、通常、当該倉庫施設を管理すべき主体は当該倉庫業者であり、当該倉庫事業者が届出の対象事業者となると考えられます。なお、薫蒸業者は自らの事業所以外で化学物質を排出していることになりますので、対象事業者にはなりません。
2.対象業種・事業所の範囲に関するもの
2-1 対象業種・事業所の範囲全般に関するもの
問2-1-1 (業種コードの記入方法)
6業種コードは、必ず4桁で記載しなければならないのですか。
答 届出書の業種コード欄には、PRTR届出の手引きに記載されているもの(4桁)のみを記載してください。例えば、同要領の中で下2桁が「00」となっているものは、日本標準産業分類のより詳細な業種分類やコード番号を記入しないでください。また、第III部4-1-1の最左欄に記載されている記号も記入しないでください。
例:×「プラスチック管製造業2212※」→○「プラスチック製品製造業 2200」
×「食料品製造業3a」→○「食料品製造業 1200」
※:日本標準産業分類(平成5年改訂版)の分類番号。
問2-1-2 (日本標準産業分類の改正に伴う業種コードの記入)
日本標準産業分類は適宜改訂されますが、業種コードは改定されたあとの最新のものを記入するのでしょうか、それとも改定前の( 従来どおりの)ものを記入するのでしょうか。
答 PRTRの届出に際しては、PRTR届出の手引きに記載されている業種コードを記入してください。日本標準産業分類の分類番号は記入しないでください。問2-1-1も参照してください。
問2-1-3 (事業所の範囲の判断)
本法における「事業所」の範囲は、どう判断したらよいのですか。
答 法第5条における「事業所」とは、政令で定める業種に属する事業活動が行われている一単位の場所をいい、原則として、単一の運営主体のもとで、同一の又は隣接する敷地内において継続的に事業活動を行っているものをいいます。ただし、同一の又は隣接する敷地内になくても、道路や河川等を隔てて近接しており、かつ、化学物質管理が一体として行われている場合は、一事業所として取り扱って差し支えありません。また、当該場所における人的管理部門の存否は問いません。(以下の例1~例5も参照してください。)
[例1]異なる製品を生産する複数の工場a~cがある場合においても、単一の運営主体のもと、同一の又は隣接する敷地内で事業活動が行われていれば、全体を一括して一事業所としてください。
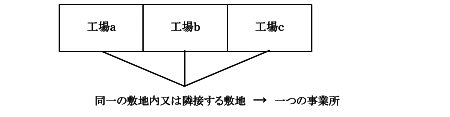
[例2]同一会社のA工場とB工場が離れた場所にある場合、原則として別個の事業所としてください。また、大学が複数のキャンパスに分かれている場合や、同一名称の自衛隊駐屯地、基地等が場所的に離れて位置する場合も、それぞれを別個の一事業所としてください。
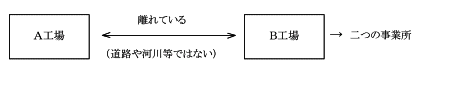
[例3]例2にかかわらず、同一会社の工場Aと工場bが道路や河川等を隔てて設置されているが、近接しており、化学物質管理が一体として 行われている場合には、工場Aと工場bを一括して一事業所として取り扱って差し支えありません。
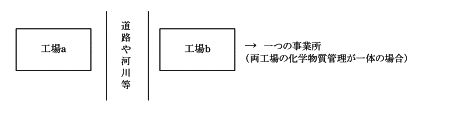
[例4]同一の又は隣接する敷地内にA社の工場とB社の工場がある場合には、運営主体が異なるため、別個の事業所としてください。 (A事業者とB事業者に製造等の委託関係がある場合は、問12を参照してください。)
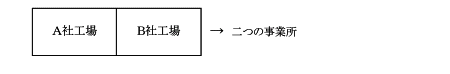
[例5]常駐する者がいない場所でも、「事業所」となり得ます。(把握、届出は「事業者」が行ってください。)
問2-1-4 (対象業種以外の事業のみを行っている事業所の場合)
対象業種ではない事業のみを営む事業所は、届出が必要ですか。
答 第一種指定化学物質等取扱事業者が、ある事業所において同時に二以上の業種に属する事業を行っており、かつ、それらの業種の一つが政令で定める業種(以下「対象業種」という。)である場合には、当該事業所は法第5条に規定する把握・届出を行う必要があります。しかし、第一種指定化学物質等取扱事業者が、ある事業所においては対象業種に属する事業をまったく行っていない場合には、当該事業所は法第5条にいう「事業所」に該当せず、把握・届出の必要はありません。
問2-1-5 (非対象業種)
対象業種ではない業種はどういったものがありますか。
答 商社、レンタカー事業者、倉庫業のみを行っている事業者はPRTR届出の対象ではありません。上記は、よくあるお問い合わせから一部を記載していますのでこれ以外にも非該当の業種はあります。まずは対象業種をご確認ください。
問2-1-6 (対象業種以外の事業も行っている事業所の場合)
対象業種以外の業種に属する事業も同時に行っているような事業所の場合、その事業所における対象物質の取扱量を考えるときには、その事業所が業として取り扱っているものすべて(対象業種以外も含めて)を取扱量に含めて算出するという考え方でよいでしょうか。
答 そのとおりです。
なお、届出書に記載する「事業所において行われている事業が属する業種」の欄は、対象業種のみを列記することとなりますので、PRTR届出の手引きを御参照ください。
問2-1-7 (複数の業種を兼業している場合)
複数の業種を兼業している事業所が届出する場合、届出上の業種名はどのようにするのでしょうか。
答 対象業種に該当する全業種を記載してください。その際、主たる業種(製品や半製品等の出荷額・売上額が最も多い業務に関係する業種)1つを届出様式の一番上の欄に記載してください。
問2-1-8 (民間事業所内や自衛隊駐屯地等に併設された診療施設)
民間事業所内や自衛隊駐屯地等に併設された診療施設について、PRTRの届出は必要でしょうか。
答 当該施設が医療法上の「診療所」、「病院」に該当する場合であっても、当該施設における化学物質の取扱いが民間事業者の福利厚生施設での化学物質の取扱いに相当するものである限り、当該施設における化学物質の取扱いは化管法上の「業として」行われるものではないと考えられることから、医療業としてのPRTRの届出は必要なく、また、事業所における年間取扱量に算入する必要はありません。
他方、診療施設での化学物質の取扱いが民間事業者の福利厚生施設での化学物質の取扱いに該当しない場合において、従前から届出事業者が届出対象事業者であるときは、年間取扱量及び届出値に算入する必要があります。また、当該事業者がそれ以前は届出対象事業者でなかった場合において、当該事業者全体における常用雇用者数が21人以上、事業所における年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)に該当するときは、医療業として事業所全体の排出量・移動量を合算して届出を行う必要があります。
なお、「診療施設における化学物質の取扱いが民間事業者の福利厚生施設での化学物質の取扱いに該当する場合」とは、診療施設が事業所内に設置され、当該事業所に勤務する職員を対象として行う医療行為等において化学物質を取り扱う場合を想定します。具体的には、事業所内・省内の診療所、駐屯地に併設されている医務室等が考えられます。他方、診療施設の建物が事業所とは別の敷地に別途設けられている場合は、常用雇用者数及び取扱量の要件に該当すれば、PRTRの届出の対象となります。
問2-1-9 (大学病院の場合)
大学病院はいずれの事業所管大臣に届け出なければなりませんか。
答 大学病院は、「高等教育機関の付属施設」として文部科学大臣あてに届け出てください。
問2-1-10 (企業が経営する病院の場合)
企業が病院を経営する場合、届出は必要ですか。
答 医療業として届出の対象となります。
2-2 行政機関の事業所に関するもの
問2-2-1 (国や地方公共団体等の公務の根拠)
国や地方公共団体等の公務は、法施行令第3条に規定されていませんが、届出の根拠はどこにあるのでしょうか。
答 法施行令第3条には、明示的に「公務」が規定されていませんが、国や地方公共団体等の行う業務については、実際に行われる業務の外形に着目して業種の分類を行い、結果として分類された業種が法施行令第3条に列記されているものであれば、届出の対象と整理しています。
問2-2-2 (国や地方公共団体等の届出者、従業員数)
国や地方公共団体等の公務については、届出者や従業員数をどう判断したらよいですか。
答 次のとおりとしてください。
| 事業者 | 代表者 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 国※1 | 各省大臣 | 全職員数(省庁単位) |
| 防衛省 | 防衛大臣(※) (※代理人として駐屯地等の管理責任者) |
全職員数(駐屯地等単位) |
| 独立行政法人等 | 独立行政法人等の長 | 全職員数(法人単位) |
| 国立大学 | 国立大学の長 | 全職員数(大学単位) |
| 国立病院(診療所を含む) | 国立病院の長 | 全職員数(病院単位) |
| 公立病院(診療所を含む) | 公立病院の長 | 全職員数(病院単位) |
| 都道府県 | 都道府県知事 | 全職員数(都道府県単位) |
| 市町村 | 市町村長 | 全職員数(市町村単位) |
| 地方公営企業※2 | 管理者※3 | 全職員数(公営企業単位) |
| 一部事務組合 | 管理者 | 全職員数(組合単位) |
| 公立大学 | 公立大学の長 | 全職員数(大学単位) |
| 公立病院(診療所を含む) | 公立病院の長 | 全職員数(病院単位) |
| (参考)民間企業 | 代表取締役 | 全従業員数(事業者単位) |
※1 防衛省を除く。
※2 地方公共団体の経営する企業のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受けるもの。
※3 地方公営企業法第7条ただし書の規定により管理者を置かない場合は、地方公共団体の長とする。
※4 地方公共団体に併設される直営の病院(診療所も含む)の従業員数は都道府県もしくは市町村単位とする。
問2-2-3 (国や地方公共団体等の届出のあて先となる事業所管大臣)
国や地方公共団体等については、届出のあて先となる事業所管大臣をどう判断したらよいですか。
答 国の機関や独立行政法人等については、その行う事業がいずれの業種に属するにかかわらず、当該機関又は法人等を所管する大臣に対して行うこととし、地方公共団体(地方公営企業等を含む)については、その行う事業を所管している大臣に対して行うものとします。
[例1]駐屯地で防衛庁の職員が行う自動車等への給油は「燃料小売業」に相当するものであるが、対象物質の排出量等は、都道府県を経由して、燃料小売業を所管する経済産業大臣ではなく、防衛大臣に対して行う。
[例2]市町村や地方公営企業の下水道事業を行う事業所に係る排出量等は、都道府県を経由して、下水道業を所管する大臣(国土交通大臣)に対して行う。
2-3 上記以外の業種に関するもの
問2-3-1 (その他製造業に該当する業種)
「その他の製造業」(業種コード3400)には、いかなるものが含まれますか。
答 貴金属製品製造業、楽器製造業、玩具・運動用具製造業などが含まれます。詳細は、PRTR排出量等算出マニュアルの「4-1-1 対象業種の区分」 を参照してください。届出にあたっては、PRTRの届出の業種コード3400を記入してください。なお、「その他の製造業」に含まれる業種は限定されておりますので、十分に確認したうえで記載して下さい。
問2-3-2 (自動車部品等を販売している事業者がフロン類の抜き取りをしている場合)
専ら自動車部品やカーアクセサリーの販売を行っている事業者が、部品の修理サービスを行い、それに伴ってカーエアコン等からフロン類の抜き取りなどを行っている場合、対象業種に該当しますか。(なお、自動車整備業の登録はしていません。)
答 この場合、当該事業者が行う事業は、修理サービスを含め「自動車部分品・付属品小売業」であり、対象業種には該当しません。
問2-3-3 (建設工事中の発電所)
建設工事中の発電所で使用した塗料中の対象物質について、届出が必要でしょうか。
答 建設工事中の発電所は未だ「電気業」を営んでいるとは考えられないので、同一の事業所内で他の対象業種に属する事業を行っていなければ、届出は不要です。
3.常時使用する従業員の数に関するもの
問3-1 (常時使用する従業員の数が21名未満の場合)
現在、常時使用する従業員の数が20人以下ですが、届出の必要がありますか。
答 排出量・移動量を把握する年度の4月1日の時点または、前年度の2月及び3月中に使用している従業員の数で判断してください。常時使用する従業員の数がこの時点で届出の対象となる規模未満の事業者の場合は、対象外です。
→「常時使用する従業員の数の確認」は、PRTR排出量等算出マニュアル第II部1-2を参照してください。
問3-2 (21人以上と21人未満の事業所が混在している場合)
複数の事業所を持っていますが、従業員数21人以上と21人未満の事業所が混在しています。届出対象となるのは21人以上の事業所だけでしょうか。
答 従業員数による届出対象かどうかの判断は、事業者(会社全体)を対象としたもので個々の事業所の従業員数には関係ありません。個々の事業所が取扱量などの届出要件を満たしていれば、事業所単位で届出が必要です。
問3-3 (別会社に委託している場合の従業員の数)
A事業者は、対象物質を1トン/年以上取り扱う化学工業のメーカーですが、正社員は管理部門の10人だけです。他の現場作業員等は、すべて別会社に委託しています。この場合、A事業者の常時使用する従業員の数には、下請けの別会社の従業員数を含めるのですか。
答 A事業者との委託・請負により、A事業者が管理している事業所で働いている者は、A事業者の常時使用する従業員の数に含めます。PRTR排出量等算出マニュアル第II部1-2及び問1-3-1も参照してください。
4.対象物質に関するもの
4-1金属等の化合物に関するもの
問4-1-1 (金属化合物の届出対象となる個別物質の範囲)
金属化合物の場合、個別物質名がリストアップされていませんが、届出の対象となる物質の範囲はどこまでですか。
答 PRTR排出量等算出マニュアル第III部4-2-8に例示されている化学物質を含め、政令に定められた名称に該当する化学物質が全て対象となります。
問4-1-2 (有機スズ化合物の範囲)
有機酸とスズとの塩である2-エチルヘキサン酸スズは、化管法の有機スズ化合物(管理番号239)及び有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。)(管理番号664)に該当するのでしょうか。
答 化管法の有機スズ化合物は、少なくとも一つの有機炭素が直接スズに結合している構造の物質を対象としています。
2-エチルヘキサン酸スズは構造の中に有機炭素を含んでいますが、直接スズに結合している有機炭素がないので、化管法の有機スズ化合物には該当しません。
問4-1-3 (「水溶性」と限定している化合物の個別物質の範囲)
金属化合物で「水溶性」と限定されているものがありますが、こうした限定のない金属化合物(例えばマンガン化合物)の場合は、水溶性ではない物質であっても届け出る必要があるのでしょうか。
また、「水溶性」と限定した金属化合物と限定しなかった金属化合物がありますが、これらはどんな基準によって区別されたのでしょうか。
答 化学物質の毒性の程度は、水溶解性によって異なる場合があるため、必要に応じ、「水溶性」という限定を化学物質につけています。ちなみに、マンガン化合物のように「水溶性」という限定のない金属化合物の場合は、該当する全ての個別物質が対象になりますので、「非水溶性」の物質も含めてマンガンに換算したうえで、合計して排出量等を届け出てください。なお、「水溶性」とは、常温で中性の水に対し1質量%(10g/l)以上溶解することをいいます。
問4-1-4 (「亜鉛の水溶性化合物」における個別物質の範囲)
例えば、「亜鉛の水溶性化合物」(管理番号1)の場合、金属単体である「亜鉛」は含まれますか。
答 この場合、金属単体である「亜鉛」は含まれず、「亜鉛の水溶性化合物」のみが対象となります。なお、「カドミウム及びその化合物」(管理番号75)のように、金属単体が明記されている場合は、金属単体である「カドミウム」も含まれます。
問4-1-5 (1つのPRTR対象物質に複数の物質が該当する場合)
亜鉛の水溶性化合物(管理番号1)に該当する物質AとBを取り扱っています。対象物質はその物質毎に取扱量を把握することになりますが、亜鉛の水溶性化合物の取扱量は、どのように考えれば良いのでしょうか。
答 亜鉛の水溶性化合物のように、1つの対象物質に複数の物質が該当する場合は、その対象物質に該当する取り扱い物質全体の合計数量となります。このため、亜鉛の水溶性化合物に該当する物質AとBを取り扱っている場合は、物質AとBの取扱量の合計が亜鉛の水溶性化合物の取扱量となります。ただし、元素への換算が必要な物質については、換算量の合計が取扱量となります。亜鉛の水溶性化合物であれば、亜鉛の合計量が取扱量になります。
問4-1-6 (金属等の化合物の年間取扱量、排出量等の考え方)
金属等の化合物の年間取扱量、排出量等は、化合物としての量を用いるのですか。
答 亜鉛の水溶性化合物や鉛及びその化合物のような金属化合物、「無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)」(管理番号144)、「ふっ化水素及びその水溶性塩」(管理番号374)、「ほう素及びその化合物」(管理番号405))については、それぞれの物質に含まれる金属元素、シアン、ふっ素あるいはほう素の量を用いてください。
→SDSには金属元素等の量に換算した含有率が記載されています。また個別に換算を行う際の換算係数は第III部4-2-8を参照してください。
| 管理番号 | 第1種指定化学物質 | 換算する金属元素等 |
|---|---|---|
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 亜鉛 |
| 31 | アンチモン及びその化合物 | アンチモン |
| 44 | インジウム及びその化合物 | インジウム |
| 75 | カドミウム及びその化合物 | カドミウム |
| 82 | 銀及びその水溶性化合物 | 銀 |
| 87 | クロム及び三価クロム化合物 | クロム |
| 88 | 六価クロム化合物 | クロム |
| 132 | コバルト及びその化合物 | コバルト |
| 144 | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | シアン |
| 237 | 水銀及びその化合物 | 水銀 |
| 242 | セレン及びその化合物 | セレン |
| 272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 銅 |
| 305 | 鉛化合物 | 鉛 |
| 309 | ニッケル化合物 | ニッケル |
| 321 | バナジウム化合物 | バナジウム |
| 332 | 砒素及びその無機化合物 | 砒素 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | ふっ素 |
| 394 | ベリリウム及びその化合物 | ベリリウム |
| 405 | ほう素化合物 | ほう素 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | マンガン |
| 453 | モリブデン及びその化合物 | モリブデン |
| 664 | 有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。) | スズ |
| 665 | セリウム及びその化合物 | セリウム |
| 666 | タリウム及びその化合物 | タリウム |
| 679 | テルル及びその化合物 | テルル |
| 697 | 鉛及びその化合物 | 鉛 |
問4-1-7 (六価クロム化合物が中和沈澱処理により三価クロム化合物になる場合)
原材料として使用している六価クロムを含む排水を中和沈殿処理を行った後、放流しており、処理後に三価クロムを含む汚泥が発生して廃棄処分にしています。このような場合、六価クロム、三価クロムの取扱量はどのように考えればよいですか。
答 六価クロムについては、原材料(含有率が0.1質量%以上のもの)として使用している量を取扱量としてください。その年間取扱量が0.5トン/年以上の場合には、年間取扱量の要件を満たします。
三価クロムについては、製品や半製品、汚泥として生成している量が取扱量となります。その生成量が1トン/年以上の場合には、年間取扱量の要件を満たすことになります。なお、PRTR排出量等算出マニュアルにおいては、これを年間製造量として計算するようになっています。
このような場合の排出量、移動量の算出例を第III部1-8に示しますので、参考にしてください。
問4-1-8 (ふ っ化水素酸の一部がふっ化水素の気体となって排出される場合)
事業所内で金属表面処理にふっ化水素酸(ふっ化水素水溶液)を使用しており、一部がふっ化水素の気体となって大気へ排出されています。政令では ふっ化水素及びその水溶性塩が対象物質となっていますが、この場合、排出量はどのように届け出れば良いのでしょうか。
答 生成した気体状のふっ化水素をふっ素換算した上で、大気への排出に加えて届け出てください、また、ふっ化水素酸(ふっ化水素水溶液)のまま排出・移動される場合も、ふっ素換算した上で届け出てください。なお、消石灰等でCaF2に処理したものは「水溶性」に該当しませんので、排出・移動量からは差し引いてください。
4-2 金属等以外の対象物質に関するもの
問4-2-1 (水加ヒドラジンを取り扱う場合)
ヒドラジンは第一種指定化学物質に指定されていますが、「水加ヒドラジン」は対象物質ですか。
答 水加ヒドラジンは、ヒドラジン(管理番号333)に任意の割合で水が混和したものと考えられ、法の運用上、「ヒドラジン」には「水加ヒドラジン」が含まれるものとして整理しています。水加ヒドラジンを製造又は使用している場合は、ヒドラジンに換算して取扱量や排出量等を算出してください。
問4-2-2 (ヒドラジン誘導体を取り扱う場合)
蒸気を取り出す目的で使用しているボイラーに塩酸ヒドラジン、炭酸ヒドラジン等のヒドラジン誘導体を脱酸素剤(錆防止目的)として使用しています。これらヒドラジン誘導体はボイラー内で容易に分解しヒドラジンとして作用しており、そのうちいくらかは大気中、排水中に排出されています。この場合の届出についてはどのようにしたらよいのですか。
答 塩酸ヒドラジン、炭酸ヒドラジン等は、ヒドラジン誘導体であってヒドラジンではないため対象物質ではありませんが、使用過程でヒドラジンとなっている(ヒドラジンを能動的に生成している)ことから、ヒドラジンの年間生成量を年間取扱量として届出の必要性を判断してください。
問4-2-3 (ダイオキシン類に含まれるコプラナーPCBの考え方)
「ダイオキシン類」について届け出る場合、その中に含まれるコプラナーPCBの扱いはどうすればよいでしょうか。
答 法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」(管理番号243)の排出量(ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」とします)の特定施設を有する事業所にあっては排出量及び移動量)を把握する義務がある事業者は、その事業所内の施設でダイオキシン法等の他法令に基づき測定した、排出ガス・排出水中のダイオキシン類の排出濃度の実測値等を用いて、ダイオキシン類の排出量を算出し、届け出る必要があります。
この場合の「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン類対策特別措置法にいうダイオキシン類と同義であり、コプラナーPCBを含むものです。したがって、コプラナーPCBをTEQ換算した量もダイオキシン類に合算して届け出てください。法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」及び「PCB」(管理番号406)の排出量を把握する義務がある事業者(ダイオキシン法施行令別表第2第13号に掲げる下水道終末処理施設を有する事業者及び一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物最終処分場を有する事業者(ごみ処分業又は産業廃棄物処分業を営む事業者に限る。))は、コプラナーPCBについて、「ダイオキシン類」とは別に、PCBの排出量も届け出る必要があります。「PCB」はコプラナーPCBも含めたPCBの異性体すべての混合物です。したがって、 異性体すべての混合物である「PCB」として把握した量をそのまま届け出てください。この「PCB」中のコプラナーPCBはTEQ換算する必要はありません。
なお、法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」について把握する義務があるが、「PCB」については把握する義務がない事業者は、その事業所内の施設で実測した「ダイオキシン類」中にコプラナーPCBが含まれていたとしても、当該コプラナーPCBを「PCB」として届け出る必要はありません。
問4-2-4 (事業活動に伴い付随的に生成、または排出される物質の範囲)
事業活動に伴って付随的に生成、または排出する物質はどこまで届け出るのですか。
答 製品を製造する反応工程で対象物質が副生成され、その副生成物が年間1トン(特定第一種指定化学物質の場合は年間0.5トン)以上である場合は副生成物も届出対象となります。問5-1-3 を参照してください。
また、特別要件に該当する施設を有する場合は、その施設から排出される排ガス・排水等の中に含まれている他法令に基づく測定対象物質について排出量、移動量を届け出てください。
問4-2-5 (別名がある物質の届出)
別紙への物質の記載については別名のあるものは別名を記載することとなっていますが、別名が複数存在するものについてはどのように記載すればよいでしょうか。また、シマジンの場合、「シマジン又はCAT」となっており、この場合「シマジン」、「CAT」、「シマジン又はCAT」のどちらで記載すべきでしょうか。
答 いずれの別名を記載しても差し支えありません。
4-3 その他
問4-3-1 (今後の対象物質の変更の可能性)
今後、対象物質に関する変更はあるのですか。
答 2021(令和3)年の法施行令改正により、第一種指定化学物質462物質から515物質に変更されました。また、特定第一種指定化学物質についても指定要件が、「人に対する発がん性に加えて、生殖毒性、変異原性があると評価された物質で特に注意を要するもの」に「一定以上の生態毒性を有する物質で難分解性かつ高蓄積性を有するもの」が追加され、15物質から23物質に変更されました。(改正後の対象物質の排出・移動量の把握は2023(令和5)年度から、届出は2024(令和6)年度から実施されます。)
今後も、科学的知見の充実状況及び排出量データの把握の状況等に応じて追加、削除等の見直しを行っていく予定です。
5.取扱量の把握に関するもの
5-1 製造量の把握に関するもの
問5-1-1 (同一物質を含む原材料を多数使用している場合)
同じ第一種指定化学物質が含有されている製品(原材料)を多数使用しています。第一種指定化学物質を1質量% 以上含有している製品(原材料)は、取扱量に合算しますが、1質量%未満の製品についても合算する必要がありますか。
答 取扱量を算出する時には含有率1質量%未満(ただし、特定第一種指定化学物質については0.1質量%未満)の製品(原材料)については合算する必要はありません。
問5-1-2 (ナフサに含まれる対象物質を抽出している場合)
石油化学メーカーで、原料ナフサを受け入れ、ナフサ中に1%未満含まれる 対象物質を抽出して、製品や半製品として出荷しています。この場合、 対象物質の年間取扱量による判定はどうするのですか。
答 この場合は、対象物質を「製造」していることになります。したがって、対象物質の年間製造量が1トン/年(特定第一種指定化学物質は0.5トン/年)以上であるかどうかで、届出が必要かどうかを判定してください。
問5-1-3 (火力発電所で石炭中に微量に含まれている対象物質が排出されている場合、クラフトパルプ漂白時にクロロホルムが生成する場合)
火力発電所において、石炭中に微量(含有率が1%未満)含まれている第一種指定化学物質(水銀等の重金属)が排出されている場合、「製造量」に含めて取扱量に算入すべきでしょうか。同様に、クラフトパルプ漂白時に付随して生成するクロロホルムについてはどうでしょうか。
答 火力発電等において、原料である石炭中に含有される水銀がボイラーから排出される場合は、既に石炭中に含有されていた水銀が物理的に石炭から分離され、副生成物としてボイラーから放出されるのみで、水銀が新たに作り出されたわけではないので、「製造量」として取扱量に算入する必要はありません。
一方、クラフトパルプ漂白時に付随して生成されるクロロホルムは、反応プロセスで新たに作り出されたものと考えられますので、「製造量」として取扱量に算入する必要があります。
問5-1-4 (金属板をエッチングする場合)
金属(例えば、銅版)のエッチングの場合の取扱量は、表面の溶けた部分の量でしょうか、それとも母材も含めた全体の量でしょうか。
答 この場合は、銅と硝酸との反応(エッチング)により「銅水溶性塩」(管理番号272)に該当する硝酸銅が新たに製造されたと考えられるため、銅換算した硝酸銅、すなわち、溶出した銅の重量を取扱量としてください。
問5-1-5 (密閉された製品を他社から仕入れ、そのままの状態で他へ転売する場合)
密閉された状態の製品(他社に生産委託した製品を含む)を他社から仕入れ、 そのまま仕入れた状態で他へ転売する場合、PRTRの届出は必要でしょうか。
答 この場合、密閉された状態の製品を他社から仕入れ、そのまま仕入れた状態で他へ転売する行為は、対象化学物質の取扱いには該当しないため、PRTRの届出は必要ありません。
なお、サンプリング検査のため容器を開封した場合や別の容器に小分けするため容器を開封した場合は、開封した容器中の製品に含まれる指定化学物質ごとに取扱量( 使用量) を把握し、第一種指定化学物質では1トン以上、特定第一種指定化学物質では0.5トン以上であれば、届出が必要です。
5-2 対象物質の含有率に関するもの
問5-2-1 (用いる対象物質の含有率)
対象物質の含有率は、どのような値を用いればよいのでしょうか。
答 原材料、資材等(製品)に関するSDS(安全データシ-ト)でご確認ください。SDS省令(平成12年通商産業省令第401号)第4条第3項において、 SDSには対象物質の含有率を有効数字2桁で記載することが規定されていますので、その値を用いてください。
問5-2-2 (1質量%未満の対象物質を合算すると1質量%を超える場合)
キシレン(管理番号80)が0.7質量%、トルエン(管理番号300)が0.5質量%含まれている製品を取り扱っています。両物質とも含有率は1%未満ですが合算すると1質量%を超える場合、取扱量の把握及び排出量・移動量の届出が必要でしょうか。
答 届出が必要か否かは、対象物質毎の含有率(第一種指定化学物質の場合は1質量%以上、特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)で判断することになります。このため、キシレンとトルエンの含有率がそれぞれ1質量%未満であれば、届出は必要ありません。
問5-2-3 (対象物質を溶媒等で希釈している場合)
対象物質が製品(原材料、資材等)に他の化学物質との混合物として含まれている場合や溶媒等で希釈されている場合、どう取り扱えばよいのでしょうか。
答 対象物質を1質量%(特定第一種指定化学物質については0.1質量%)以上含む製品(原材料、資材等)の年間取扱量と対象物質の含有率の積から対象物質の年間取扱量を算出してください。
問5-2-4 (対象物質が濃縮される場合)
原料中には第一種指定化学物質が1%未満のもので、意図的に濃縮しているわけではないのですが、最終的に製品もしくは中間工程品で1%以上に濃縮する場合は取扱量としてカウントする必要がありますでしょうか。
答 化管法施行令第5条にて、「法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。」と規定されており、第一種指定化学物質の割合が1%以上であるものを取り扱うことは取扱要件に合致しますので、取扱量への算入が必要となります。
問5-2-5 (取り扱う製品中の対象物質の含有率が1質量%未満の場合)
取り扱う製品(原材料、資材等)中の対象物質(特定第一種指定化学物質に該当しないもの)の含有率は1質量%未満ですが、年間の取扱量の合計は裾切り値 (1t/年)以上という場合、届出の必要はありますか。
答 取り扱う製品(原材料、資材等)中の対象物質含有率が1質量%未満であれば届出の必要はありません。
問5-2-6 (消費者用製品を製造する場合の取扱量の把握)
一般消費者用の製品に含まれる対象物質については、PRTR届出の対象外となっています。このため、一般消費者用の製品を製造する場合も、原料となる対象物質の取扱量の把握は不要でしょうか。
答 一般消費者用の製品を製造するために対象物質を取り扱う場合は、その対象物質の取扱量を把握し、排出量と移動量の届出をすることが必要です。
問5-2-7 (石油系燃料等に含まれる対象物質)
第III部4-2-4に記載されたもの以外の石油系燃料等に含まれる対象物質(例:金属化合物)は、届出の対象となりますか。
答 当該表に記載されたもの以外であっても、対象物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれている場合は、届出対象となる場合があります。
5-3 取扱量を把握する原材料、資材等の要件に関するもの
問5-3-1 (取扱量を把握する必要のない原材料、資材等)
取扱量を把握する必要のない原材料、資材等には、どんなものがありますか。
答 取扱量を把握する必要のない原材料、資材等としては、以下のものがあります。
・ 対象物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)のもの【=含有率が少ないもの】
・ 固形物(取扱いの過程で溶融したり、粉状や粒状にならないもの)【=金属板、管など】
・ 密封された状態で使用されるもの【=乾電池など】
・ 一般消費者用のもの【=家庭用洗剤、殺虫剤など】
・ 再生資源【=金属くず、空き缶など】
第I部のp.I-25、第II部のp.II-21も参照してください。
問5-3-2 (一般消費者用の製品)
一般消費者用の製品とは、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。
答 「主として一般消費者の生活の用に供される製品」(法施行令第5条)とは、もっぱら家庭生活に使用されるものとして、容器などに包装された状態で流通し、かつ、一般消費者向けの表示がされているものを言い、例えば、小売店やスーパーなどで販売される洗剤や家庭用殺虫剤などを指します。
問5-3-3 (ハンドソープ中に第一種指定化学物質が含まれる場合)
令和3年の第一種指定化学物質増加に伴い、ハンドソープ、手指消毒剤等の製品の多くに第一種指定化学物質が含まれることとなります。これら製品について、次の場合は届出対象になるのでしょうか。
(1)業務上の目的(例: 食品工場における手洗い)で使用されるハンドソープ、手指消毒剤等の医薬品、医薬部外品、化粧品は、届出対象になるのでしょうか。
(2)対象になる場合、以下の行為は排出または移動に該当し、届出対象になるのでしょうか。
(2-1)第一種指定化学物質を1wt%以上含むハンドソープで手指を洗浄し、使用したハンドソープをその場で排水に流した場合
(2-2)第一種指定化学物質を1wt%以上含む手指消毒剤等を手指に塗布し、その場は洗浄しないが次回の手洗い時等に排水に流される場合
答 (1) 事業者での使用「食品工場における手洗い」は事業活動と密接で不可分なもので「主として一般消費者の生活の用に供される製品」とは見なされません。 第一種指定化学物質が1重量%以上含まれるハンドソープ、手指消毒剤等の製品の当該用途での取扱はPRTR 制度の対象となり、年間取扱量に算入していただくことになります。
(2) (2-1)(2-2)ともに指定化学物質は排水に流されますので、(年間取扱量が1トン以上であれば) 排水が河川に流れ出る場合は「公共用水域への排出量」、排水が下水道に流れ終末処理施設で処理されるのであれば「下水道への移動量」として届出して頂くことになります。
問5-3-4 (廃棄物を受けいれている場合)
廃棄物処理業において、受け入れた廃棄物に含まれている対象物質について、排出量・移動量を届け出る必要がありますか。
答 受け入れた廃棄物は、排出量等を把握する製品(原材料、資材等)の要件にあてはまりませんので、その取扱いの過程で揮発するなどして排出される量を把握する必要はありません。ただし、受け入れた廃棄物から有用な物質を回収するような場合は、「製造」に当たり、対象物質の製造量が年間1t以上(特定第1種指定化学物質にあっては年間0.5t以上)であれば、排出量・移動量の届出が必要になります。
→「法律に基づく製品の要件」については、PRTR排出量等算出マニュアル第II部1-4-2を参照してください。
なお、廃棄物の処理に使用した対象物質及び廃棄物処理施設から排出される対象物質で他法令により測定の対象となっているものについては、廃棄物処理業者における届出の対象となります。特に、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を有する事業者はダイオキシン類が、大気汚染防止法の水銀排出施設を有する事業者は水銀及びその化合物が届出の対象となりますので、注意してください。
問5-3-5 (ブラウン管や蛍光灯を取り扱う場合)
ブラウン管や蛍光灯の取扱いはどうするのですか。
答 法律に基づく製品の要件に該当するかどうかで判断します。これらの製品を購入してそのまま使用しているのであれば、排出量、移動量の届出の対象とはなりません。ただし、ブラウン管等を製造している場合は、製造過程で使用した対象物質の排出量、移動量の届出が必要となる場合があります。
問5-3-6 (白熱灯や蛍光灯を取り扱う場合)
白熱灯や蛍光灯等の照明器具は法施行令第5条の要件を満たす製品でしょうか。
答 当該照明器具がもっぱら消費者に販売されるものであれば、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。当該照明器具が事業者用のものであれば、第一種指定化学物質が蛍光灯の真空管の中にしか封入されておらず、外部に出てこないのであれば、「第一種指定化学物質が密閉された状態で取り扱われる製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。第一種指定化学物質がガラス部分や外部の金属部分に含有されているのであれば「固体以外の状態にならず、取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解しない製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。
問5-3-7 (電子回路基板のような半製品を購入している場合)
例えば、電子回路基板を購入して電気製品を製造する場合のように、ある段階まで製造された「半製品」を購入し、それを組み立てて、完成品を製造している場合、半製品に含まれる対象物質は届出の対象となりますか。
答 当該「半製品」が、法律に基づく製品(原材料、資材等)の要件(法施行令第5条)に該当するかどうかで判断してください。
問5-3-8 (ステンレス鋼の製品を取り扱う場合)
ステンレス鋼(スタッドボルト、ナット等)の金属を製品または製品の構成部品として顧客に提供しています。このステンレス鋼の中に、クロム、ニッケル、マンガンが含まれていますが、届出が必要でしょうか。
答 法第2条第1項で規定されているとおり化学物質には元素も含まれ、ステンレス鋼中の金属元素であるクロム、ニッケル、マンガンは、それぞれ「クロム及び三価クロム化合物(管理番号87)」、「ニッケル(管理番号308)」、「マンガン及びその化合物(管理番号412)」として対象物質となります。このため、これらの金属からステンレス鋼を製造する事業者や、ステンレス鋼のインゴットなどから溶融工程を経てボルト、ナット等の製品を製造する事業者は、対象物質であるクロム、ニッケル、マンガンを使用したこととなり、事業者が常時使用する従業員の数が21人以上の場合には、各々の対象物質の年間取扱量が1トン/年以上の事業所について排出量・移動量の届出が必要となります。
一方、ステンレス鋼のボルト、ナット等を単に部品として使う場合は、固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならないため、法施行令第5条の製品の要件には該当しないと考えられます。したがって、これらの部品を購入して製造品の構成部品として取り扱う事業者においては、通常、届出の必要はありません。
なお、SDSについては、ボルト、ナット等が取引先の事業者において部品として使用され、溶融等の加工が行われなければ製品の要件に該当しないため、その提供は義務ではありません。また、インゴットは通常取引先の事業者により溶融等の加工が行われるものであり製品の要件に該当するため、SDSの提供が必要となります。
問5-3-9 (難燃剤を含む生地を取り扱う場合)
例えば、難燃剤としてアンチモン及びその化合物(管理番号31)を塗布した 生地を購入して、自動車用のシートを製造している場合、届出の必要性はどのように判断すればよいでしょうか。
答 当該生地が製品の要件(法施行令第5条)に該当するかどうかで判断してください。
問5-3-10 (古くなった機器をメーカーに引き取ってもらっている場合)
事業所において、古くなった機器をメーカーにそのまま引き取ってもらっています。この場合、含まれている化学物質の成分まで調べて届け出る必要があるでしょうか。
答 機械類は固有の形状を有するため製品の要件に該当せず、対象物質の年間取扱量に含める必要はありません。
問5-3-11 (ダイオキシン類を含む焼却灰をレンガの原料としている場合)
下水処理場で汚泥の焼却灰が発生しています。その9割は同一事業所内で焼成レンガの原料として使用し、残りの1割は別の事業所へ運び、そこでセメント原料として使用されています。焼却灰に含まれるダイオキシン類は実測していますが、その数量を下水処理場からの排出量や移動量として届け出る必要があるでしょうか。
答 事業所内で生成した焼却灰にダイオキシン類が含まれていても、それを同一事業所内で原料として使う場合には、環境への排出あるいは廃棄物に含まれての移動には該当しないため、その量を排出量や移動量に含める必要はありません。その焼却灰を別の事業所が原料として使う場合であっても、廃棄物として引き渡している場合は、下水処理場としては「廃棄物」として搬出していることになりますので、搬出された焼却灰に含まれているダイオキシン類の量を、「当該事業所の外への移動」に含めてください。
問5-3-12 (PCBを含むコンデンサーを倉庫内に保管している場合)
PCBを含む廃コンデンサーを倉庫内に保管していますが、これは取扱いの対象となりますか。
答 PCBを含む廃コンデンサーを倉庫内(事業所内)に保管している場合、コンデンサーを倉庫内(事業所内)で一度も開封せず、かつ密閉された状態で入っていたPCBは、一般的に密閉された状態で使用される製品と考えられることから、法施行令第5条の要件を満たさないため、これを廃棄物として移動する場合は、その取扱量を把握する必要はありません。
問5-3-13 (溶接芯線、溶接母剤を使用している場合)
事業所内で溶接芯線、溶接母剤を用いて溶接を行っていますが、排出量、移動量を届け出る必要がありますか。なお、常時使用する従業員の数は21人です。
答 溶接工程で使用する溶接芯線、溶接母剤は取扱いの過程で溶融していますので、対象物質を1質量% (特定第一種指定化学物質については0.1質量%)以上含有し、その年間取扱量が1トン/年(特定第一種指定化学物質については0.5トン/年)以上である場合には、排出量、移動量を届け出る必要があります。なお、問5-3-14も参照してください。
問5-3-14 (対象物質を含むステンレス板を溶接により接合等している場合)
クロムやニッケルを含有するステンレス板の溶接により接合等を行っている場合、それぞれの物質の取扱量は、板全体の含有量を算入するのでしょうか、それとも溶接部分のみでよいのでしょうか。
答 溶接されるステンレス板は、事業者による取扱いの過程で「固体以外の状態」 になると考えられるため、第一種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上)の質量で含有する場合は、法施行令第5条の要件を満たす製品に該当します。対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので、ステンレス板全体の中に含まれるクロムの量を「クロム及び3価クロム化合物」(クロム換算)の取扱量として、ニッケルの量を「ニッケル」(ニッケル換算)の取扱量として算入してください。
問5-3-15 (はんだを使用している場合)
はんだの取扱いはどうするのですか。
答 はんだ付け作業に使用するはんだであって、はんだ中に対象物質を1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含有している場合、取扱いの過程で液状となることから、法施行令第5条の要件を満たす製品に該当します。年間取扱量を算出して届出の必要があるか判断してください。
問5-3-16 (ガラスを使用している場合)
対象物質のリストに「ガラス」の記載がないが、どのように取り扱えばよいのですか。また、ガラスの中に金属化合物などの対象物質が含まれている場合にはどのように取り扱うのですか。
答 「ガラス」は化学物質の名称ではありませんので、「ガラス」そのものが排出・移動量の届出が必要な対象物質とはなりませんが、原材料として使用したガラス中に対象物質が1質量%(特定第一種指定化学物質は0.1質量%)以上含まれており、取扱工程で溶融等を行う場合等は、当該対象物質について排出量・移動量の届出が必要となります。ただし、購入したガラスをそのまま製品に組み込んでいるような場合には、届出の対象とはなりません。
問5-3-17 (ペレット製造の際に添加剤を練りこむ場合)
ペレットを製造する際に、対象物質を含む添加剤を練りこむ場合は、排出量・移動量の届出の対象となるのですか。
答 添加剤に含まれる対象物質の含有率、年間取扱量から届出の必要性を判断してください。
なお、ペレット化する際に、その添加剤に含まれる対象物質が反応せずに、ペレット中に存在している場合は、他の事業者に譲渡、提供する際にSDSの添付が必要かどうかを判断する必要があります。
問5-3-18 (ペレットを原料に電線の被覆材等を成型加工している場合)
樹脂ペレットを原料としたプラスチックを成型加工する電線の被覆材などに含まれている対象物質や圧延加工・鍛造加工を行う金属は、取扱量に含める必要がありますか。
答 樹脂ペレットを原料としたプラスチックを成型加工するものは、押出加工等の過程で団塊状のものが加熱されて溶融・結合し、明らかに異なる形状を有するに至っていることから、「固体以外の状態」になると考えられます。したがって、原料の樹脂ペレット中に含有される第一種指定化学物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれているのであれば、取扱量に含める必要があります。
なお、圧延加工や鍛造加工が行われる金属は、加熱によって明らかに金属が溶解していれば「固体以外の状態」となりますが、単なる加圧によって当初の金属を屈曲・変形させるだけであれば、「固体以外の状態」になったとはいえないと考えられます。
問5-3-19 (対象物質を含む切削工具を使用している場合)
対象物質を含有する切削工具は、それを使用することにより摩耗していきますが、「粉状、粒状になる」ものとして、取扱量とする必要があるのでしょうか。
答 法施行令第5条の「粉状又は粒状にならない」製品とは、「製品が粉状又は粒状になることによって、その含有している対象物質の環境中への有意な量の排出が想定されないもの」を指します。切削工具等の部品は、それらが使用される過程で摩耗するが故に一定期間経過後に交換されることがあらかじめ想定されているものであり、含有されている物質が有意な量で環境中に排出されると考えられますので、「粉状又は粒状になる」ものとして工具に含有されている第一種指定化学物質の量全体を取扱量に含める必要があります。
問5-3-20 (金属やプラスチック等を研磨・切削している場合)
事業者の取扱いの過程で、金属やプラスチック等を研磨・切削することに伴い、粉状のものや粒状のものが発生する場合、何を取扱量としてカウントすればよいでしょうか。
答 事業者の取扱いの過程で研磨又は切削されることが想定される固体状の製品は、研磨等の過程で対象物質が「粉状又は粒状」となり、環境中へ有意な量の排出が想定されるので、当該製品中に第一種指定化学物質が1質量%以上含有されている場合は、法施行令第5条の要件を満たす製品に該当します。(なお、切断やくり抜きのように、環境への排出量がごく微量しか想定されない場合は、法施行令第5条の要件を満たす製品には該当しません。)
対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので研磨・切削される金属・プラスチック等の母材に含まれている対象物質の全体を取扱量に含めてください。
問5-3-21 (スラグ中に鉛を含む場合)
鉄鋼業で鉄スクラップを使用して製品を製造していますが、スラグ中に鉛が含まれていることが分かりました。届出は必要でしょうか。
答 鉄スクラップは再生資源ですが、その鉄スクラップから製造した製品中や製造工程で発生する廃棄物等の中に対象物質が含まれていることが明らかな場合はこれらに含まれる対象物質の年間取扱量を把握し、1トン( 特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン) 以上であれば届出が必要です。
対象物質が「鉛及びその化合物」であれば( 特定第一種指定化学物質に該当するため) 鉛換算で0.5トン以上で届出が必要となります。
なお、鉄スクラップについては使用量としての年間取扱量を把握する必要はありません。
問5-3-22 (混合物における年間取扱量の考え方)
成分Aが50%、成分Bが30%、成分Cが20%含まれた混合物Dを取り扱っています。対象物質は成分Cのみですが、対象物質の取扱量は混合物全体の量になるのでしょうか。
答 混合物の場合、対象物質の取扱量は対象物質に該当する成分のみの量となります。このため、成分Cのみの取扱量を混合物Dにおける対象物質の取扱量としてください。
5-4 その他取扱量の把握に関するもの
問5-4-1 (届出の対象となる年度以前に受けいれた在庫品を使用した場合)
届出の対象となる年度以前に受け入れた在庫品を使用したため、届出対象物質の当該年度の排出量が対象年度内に実際に受け入れた量よりも多くなりました。このように以前からあった在庫を使用した場合も、対象年度の取扱量に含める必要があるのでしょうか。
答 対象年度以前の在庫を使用した場合は、その量を対象年度の取扱量に含めてください。
問5-4-2 (事業所内で発生する成型くずを再利用している場合)
事業所で発生する対象物質を含む成形くずを同一事業所において、同一年度内に原料として再利用している場合は、再利用された成形くずに含まれる対象物質の量を年間取扱量に含める必要がありますか。
答 この場合、再利用された量が二重にカウントされることになるので、年間取扱量に含めないでください。既に年間取扱量の中に含まれています。
問5-4-3 (職員等の健康管理を目的としたレントゲン室で現像液を取り扱う場合)
飛行機の整備(機械整備業)を行う事業所において、乗員の健康管理及び職員の健康管理を目的とするレントゲン室があり、そこで対象物質を含む現像液を使用しています。年間取扱量に算入する必要はありますか。
答 乗員や職員の健康管理の目的で使用するレントゲンの現像液の使用は、「業として」使用されるものではないと考えられるため、取扱量に含める必要はありません。
問5-4-4 (自動車整備業でフロンの抜き取り作業を行う場合)
自動車整備業において、フロンの抜き取り作業を行う場合の取扱量はどうカウントすればよいですか。また、抜き取ったフロンを別の装置に再充填する場合の取扱量のカウントの仕方はどうすればよいですか。
答 自動車整備業で取り扱われるフロン(CFC等)については、購入量と全回収量(実際に抜き取った量)の和を取扱量と整理しています。また、抜き取ったフロンを再充填する場合は、ダブルカウントを排除するため、再充填した量を取扱量に算入しないでください。
問5-4-5 (芝生にまく農薬、食堂において洗剤、工場の壁を塗る塗料、社用車のガソリンを使用している場合 排出量・移動量の算出に関するもの - 1 排出量・移動量の届け出の分類に関するもの)
製造業を行っており、事業所内で取り扱っている対象物質として、原材料などで用いるもののほか、例えば、芝生にまく農薬や事業所内の食堂で使用される洗剤に含まれているものがありますが、これらは取扱量に含めて考える必要がありますか。
また、工場の壁を塗る塗料や社用車のガソリンについてはどうでしょうか。
答 当該事業者が業として(本来目的とする事業と密接不可分な行為として)取り扱う対象物質については、取扱量に含めて考える必要がありますが、それ以外で事業活動に伴い取り扱うこととなる場合は含めません。
そのため、ご質問の農薬や洗剤についてはいずれも取扱量に含める必要はありません。
また、工場の壁を塗る塗料についても、建造物に対する維持管理として一般的に行われることであることから、取扱量に含める必要はありません。一方、製造装置自体に対して腐食防止等の観点から塗装を行っている場合については取扱量に含める必要があります。
さらに、事業所内で使用される車両については、社用車のような公道も走行する車両については取扱量に含める必要はありません。一方、構内専用の車両(フォークリフトなど)については取扱量に含める必要があります。
なお、問6-4-4も参照してください。
6.排出量・移動量の算出に関するもの
6-1 排出量・移動量の届け出の分類に関するもの
問6-1-1 (同一法人の他の事業所に廃棄物を搬出している場合)
ある対象事業者(事業所A)が同一敷地内にない同一法人の他の事業所Bに廃棄物を搬出している場合、排出量・移動量はどのように届け出るのですか。
答 事業所Aから事業所Bに搬出されている廃棄物に含まれる対象物質の量は事業所Aからの「当該事業所の外への移動」に含めてください。
問6-1-2 (廃油をリサイクル業者に搬出している場合)
使用済みのトリクロロエチレンを含む液体をリサイクル業者に搬出していますが、これは、「当該事業所の外への移動」として届け出る必要がありますか。
答 1) 廃棄物として引き渡している場合
廃棄物として引き渡している場合には「当該事業所の外への移動」移動量に含めて届け出る必要があります。
2 ) 廃棄物以外のものとして引き渡している場合
廃棄物以外のものとしてリサイクル業者へ引き渡している使用済みの液体に含まれる対象物質(ご質問のケースではトリクロロエチレン)の量は、移動量として把握する必要はありません。
ただし、使用した対象物質の量は取扱量には含めて計算してください。取扱量が1t(特定第一種指定化学物質については0.5t)以上の物質については排出量・移動量を届け出る必要が生じます。ご質問のケースのトリクロロエチレンは特定第一種指定化学物質なので、取扱量0.5t以上で届出が必要となります。
届出の必要が生じる場合に、事業所外に移動するもののうち、下水道に移動するものを除く全てが廃棄物以外のものであれば、移動量のうち「当該事業所の外への移動」は「0kg」として届け出てください。また、移動の分類が複数ある場合は、その種類ごとに算出し、集計した結果を届け出てください。
問6-1-3 (事業者Aが製造工程等で発生した金属くずを別の事業者Bへ引き渡し、事業者Bは中間処理を行い、製造した金属を事業者Cに販売している場合)
事業者Aでは発生した金属くずを、廃棄物として処理費用とともに金属製品製造業に属する事業者Bへ渡しており、事業者Bは、その金属くずから製品として金属を製造し、更に別の事業者Cに販売しています。この場合、どの事業者が何を届け出れば良いのでしょうか。また、事業者Bが受け入れている廃棄物に含まれる対象物質の量には、年間取扱量の裾切りが適用されるのでしょうか。(事業者A、B及びCはいずれも常時使用する従業員の数が21人以上。)
答 金属くずに含まれる物質が届出対象物質であって、当該物質の年間取扱量が1t 以上( 特定第一種指定化学物質に該当する場合は0.5t以上) の場合は、事業者A は、事業者B に廃棄物として引き渡している金属くずに含まれる対象物質の量を「当該事業所の外への移動」に含めて届け出てください。
事業者B は、受け入れた金属くずが廃棄物に該当するため、金属くずに含まれる対象物質の量を使用量としての年間取扱量に含める必要はありません。しかし、事業者B が届出対象物質を含む金属を製造する場合、当該対象物質の製造量を年間取扱量に含める必要があります。また、当該年間取扱量が1t以上( 特定第一種指定化学物質に該当する場合は0.5t以上) の場合、当該対象物質の排出量、移動量の届出が必要となります。
事業者C は、金属製品を購入していますので、通常の対象物質の取扱いの場合と同じ考え方にしたがって、使用の有無を確認したうえで、年間取扱量を算出し、排出量、移動量の届出対象となるかどうか判断してください。
問6-1-4 (金属くず等を有料で引き取ってもらう場合)
金属くず等を輸送料を含めて費用を支払った上で引き取ってもらう場合、金属くず等は再生資源であり移動量の届出は不要と考えるべきか、廃棄物であり移動量の届出は必要と考えるべきでしょうか。
答 金属くず等を排出した事業者(排出事業者)が、金属くず等を廃棄物として他の事業者へ引き渡している場合、
「当該事業所の外への移動量」として移動量の届出が必要です。
問6-1-3も参照してください。
問6-1-5 (発生した廃液を同じ事業者の別の事業所に運び、その事業所で処理を行水域へ排出している場合)
A事業者には、すべて届出の対象であるa、b、cの3つの事業所があり、bとcの事業所で生じた廃液はすべてa事業所に運び、a事業所で処理を行ってから公共用水域へ排出しています。この場合のそれぞれの事業所からの廃液について、排出量・移動量はどのように算出したらよいでしょうか。
答 b及びc事業所の廃液がパイプライン等によって直接にa事業所の廃水処理施設に搬送され、そこから公共用水域に排出されている場合は、b及びc事業所からの「排出量」として届け出てください。この場合、b及びc事業所の廃液分についてa事業所から排出量の届出は不要です。
一方、パイプライン等により直接に搬送されていない場合、通常、ここでの廃液は本法上の「廃棄物」に該当すると考えられますので、b及びc事業所からの「移動量」として届け出てください。また、a事業所において廃棄物処理施設を設置している場合は、b及びc事業所の廃液に関するものも含めて法施行規則第4条に基づき排出量についての届出が必要になります。
問6-1-6 (農業用水路に排出している場合)
農業用水路に排出している場合、排出先は「公共用水域」で良いのでしょうか。
答 「公共用水域」とは「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう」と定義されており、農業用水路は「かんがい用水路」に該当するため、そこへの排出は「公共用水域への排出」として届け出る必要があります。
問6-1-7 (溶接の際、大気中に排出される金属ヒュームの場合)
溶接を行う際、金属ヒュームが大気中に排出されますが、厳密に言えば、いったんは大気に排出されたものが、温度低下に伴って、事業所内の壁や床、土壌等に染み込むと考えられますが、この場合でも全量が大気への排出であると考えてよいでしょうか。
答 排出区分(大気、水域、土壌)毎に排出量を把握することが基本ですが、このような場合には、その厳密な把握は不可能なため、すべて大気への排出とみなして差し支えありません。
問6-1-8 (燃焼施設から排出される金属化合物等の場合)
燃焼施設から排出される金属化合物等は、大気への排出、土壌への排出のどちらで届け出ればよいのですか。
答 燃焼施設の煙突から排出される金属化合物等は、大気への排出として届け出てください。土壌への排出は、漏洩や地下浸透等により直接、対象物質が土壌へ排出されるものを対象としています。
6-2 実測を用いた算出方法に関するもの
問6-2-1 (廃棄物中の対象物質含有率の実測値がない場合)
廃棄物の移動量を算出する場合、対象物質の含有率が必要ですが、実測値等のデータがない場合、どうすればよいのですか。
答 廃棄物中の対象物質の含有率については、類似施設での文献値、廃棄物発生工程毎の経験値等を参考にして求めても構いません。
問6-2-2 (焼却灰等の溶出試験結果の適用可能性)
廃棄物焼却炉から発生した焼却灰等に含まれるクロム等の重金属類等の移動量を把握するために、溶出試験の結果を用いてもよいのでしょうか。
答 溶出試験は、あるpHに設定した(埋立処分するものにあっては5.8以上6.3以下)試料液に焼却灰等から溶出する重金属類等の量を測定しているものですので、実際に焼却灰等に含まれている重金属類等の量とは異なるため、算出に用いることは適切ではありません。
問6-2-3 (排ガス・排水処理施設の除去率、実測濃度がない場合)
排水処理施設や排ガス処理施設での対象物質の除去率や排出濃度の実測データがない場合はどうすればよいのですか。
答 取扱工程からの潜在排出量を物質収支、又は経験値等から推算し、これとPRTR排出量等算出マニュアル第III部4-3-8の除去率を用いるなどして算定してください。なお、除去された分は廃棄物に含まれる量となる場合もありますので留意してください。
問6-2-4 (測定データが検出下限以上、定量下限未満、あるいは検出下限未満の場合)
排水中の対象物質の測定データから、公共用水域への排出量を算出したいが、測定データが検出下限以上、定量下限未満あるいは検出下限未満の場合の扱いはどうすればよいのでしょうか。
答 測定データが検出下限以上、定量下限未満の場合は、定量下限値の2分の1とみなし、検出下限未満の場合は、0(ゼロ)とみなして、排出量を算出してください。PRTR排出量等算出マニュアル第II部2-2-6の留意事項(1)を参照してください。
問6-2-5 (ダイオキシン類の測定データが検出下限以上、定量下限未満、あるいは検満の場合)
排出ガス及び排出水中のダイオキシン類の量について、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則では、異性体の測定量ごとに、その測定量が定量下限以上のものはそのままの値をTEQ換算し、定量下限未満のものは0としてTEQ換算し、それらを合計することになっています。一方、PRTR排出量等算出マニュアル第II部2-2-6及び問6-2-4では、「測定値が検出下限未満(N.D.)の場合は0とみなし、検出下限以上、定量下限未満の場合には、定量下限値の1/2とみなすこと」とされています。ダイオキシン類についてPRTRの届出を行うに当たっては、どちらの考え方によるのが適当でしょうか。
答 法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」(管理番号243)の排出量(ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を有する事業所にあっては排出量及び移動量)を把握する義務がある事業者は、その事業所内の施設でダイオキシン類対策特別措置法等の他法令に基づき測定した、排出ガス・排出水中のダイオキシン類の排出濃度の実測値等を用いて、ダイオキシン類の排出量を算出し、届け出る必要があります。
したがって、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に従った方法で化学物質排出把握管理促進法に係る排出量を算定してください。マニュアルの第Ⅱ部2-2-6及び問2-6-2-4 は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等については適用せず、PRTR の届出のために新たにダイオキシン類の量を計算しなおす必要はありません。
6-3 種々の工程における排出量等の算出に関するもの
問6-3-1 (指定化学物質を凝集剤として使用している場合)
指定化学物質を凝集剤として使用している場合は、排出量等をどのように算出するのでしょうか。
答 凝集剤として投入した指定化学物質が排水中で全て沈殿物となり、排水中に指定化学物質が存在しない場合には、公共用水域への排出量は「0」として届出してください。
また、沈殿物の中に指定化学物質は含まれない(反応により全て対象物質以外の物質に変化した)場合には、移動量は「0」として届出してください。一方、過剰な指定化学物質が排水中あるいは沈殿物中に含まれている場合には、その指定化学物質の量を公共用水域への排出量あるいは移動量として届出してください。
問6-3-2 (めっき等の工程における製品や半製品としての搬出量の把握)
めっき等の工程において、個々の製品や半製品に付着する対象物質の量(製品や半製品としての搬出量)を把握するのが困難である場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
答 製品1トンあたりの対象物質の平均付着量などを利用するなどして製品や半製品としての搬出量を算出してください。
問6-3-3 (ニッケルを電極、ニッケル化合物をめっき液として使用するめっき工程)
ニッケル(金属ニッケル)を電極として、ニッケル化合物(硫酸ニッケル等)であるめっき液を使用するめっき工程では、年間取扱量をどのように算出するのでしょうか。
答 「ニッケル」については、電極(陽極)の使用電極の減耗分に相当するニッケルの量を年間取扱量に算入してください。「ニッケル化合物」については、ニッケル電極(陽極)から溶解した量を「製造量」として、めっき液の入れ替えや追加的な注入によって電解浴槽に投入されたニッケル化合物の量を「使用量」として、それぞれニッケル換算して年間取扱量を算入してください。
この考え方に沿っためっき工程における排出量の算出例を第III部1-8に示しますので、参考にしてください。
問6-3-4 (活性炭により吸着回収した対象物質を再利用している場合)
排ガス・排水処理として、活性炭吸着回収装置を使用しており、活性炭に吸着した対象物質を同一事業所内で回収・再利用しているが、この場合はどのように排出量、移動量を算出すればよいのですか。
答 回収・再利用している場合は、排ガス・排水処理がある場合に算出する「排ガス・排水処理からの廃棄物に含まれる量」を算出しないで、物質収支をとって排出量を算出してください(これにより、回収・再利用している分を「廃棄物に含まれる量」に加算することや、排出量から二重に差し引くことがなくなります)。
問6-3-5 (パイプラインのつなぎ目やフランジから漏洩している場合)
対象物質が、製造プラントのパイプラインのつなぎ目やフランジから大気中へ漏洩する分は、どのようにして排出量を把握するのですか。
答 パイプラインのつなぎ目やフランジ等から排出される量を測定するなどして個別に把握するのは難しいと考えられます。年間取扱量から製品や半製品としての搬出量等、廃棄物に含まれる量、水域への排出量などを差し引く物質収支による方法で、製造プラント全体での大気への排出量を算出し、それに含まれるものとするなどして把握してください。PRTR排出量等算出マニュアル第III部1-2を参照してください。
問6-3-6(有機溶剤焼却装置に助燃剤としてトルエンを使用している場合)
有機溶剤焼却装置にトルエンを助燃剤として使用していますが、全て炭酸ガスと水になると考えて良いでしょうか。
答 焼却装置や焼却条件により除去率が異なり、トルエンが全て分解しているとは限りません。装置の取扱説明書や文献、同様の事例から除去率が分かる場合はその数値を用いて算出してください。その除去率が把握できない場合は、除去率を99.5(「4-3-8 代表的な排ガス、及び排水処理装置の除去率と分解率」、「排ガス処理装置の除去率と分解率(%)」表の「代表値」)%とみなして算出してください。
問6-3-7 (洗剤製造時の乾燥工程)
洗剤製造時の乾燥工程での揮発成分(対象物質)の排出量、移動量はどのように算出すればよいのでしょうか
答 製造した洗剤中の余分な揮発成分等を乾燥により、除去していると考えられますので、この前段の製造工程で製造された洗剤に含まれる揮発成分がすべて大気へ排出されるものとして、大気への排出量を算出してください。
問6-3-8 (試薬等を容器に充填する場合)
試薬等の製品や半製品をビンや缶などの容器に充填する際の排出量、移動量はどのように算出し、届け出ればよいのでしょうか。
答 容器に充填する際に気化するものについては、「大気への排出」として、またこぼれたものなどを水で洗い流し、公共用水域へ放流している場合は「公共用水域への排出」として算出し、届け出てください。水で洗い流したものを下水道へ放流している場合は「下水道への移動」として算出し、届け出てください。また、こぼれたものを集めて廃棄物処理業者等に引き渡している場合などは「当該事業所の外への移動」として算出し、届け出てください。
問6-3-9 (研究所における排出量等の算出)
研究所における対象物質の排出量、移動量はどのように算出すればよいのでしょうか。
答 研究所では、一般に反応工程、溶剤使用工程など様々な工程が組み合わさったものと考えられますので、「PRTR排出量等算出マニュアル第III部1.」の工程のうち該当するものを参考にするか、第II部を参考にするなどして、対象物質の排出量、移動量を算出してください。
問6-3-10 (機械修理業における排出量等の算出)
機械修理業においては、塗装や接着等の作業時に対象物質が排出、移動されますが、修理箇所や損傷の程度により数多くの作業方法があるため、個々に排出量、移動量を算出するのが困難です。どのようにして排出量、移動量を算出すればよいでしょうか。
答 個々の作業における排出量、移動量を算出するのが困難であれば、事業所全体での排出量、移動量を物質収支とその他の方法とを組み合わせるなどして算出してください。なお、「第III部 1.」の工程のうち該当するものを参考してください。
問6-3-11( 事業所外での事業活動がある場合)
事業所外の事業活動(客先での据付工事など)に伴う対象物質の排出量、移動量は届出の対象となりますか。
答 事業所外の事業活動に伴う排出量、移動量は届け出る必要はありません。
6-4 自動車・給油施設等からの排出量の把握に関するもの
問6-4-1 ( 事業所で自動車を保有している場合)
事業所で自動車を保有しており、燃料中に対象物質が1質量%以上含まれていますが、自動車からの排出についても届け出る必要がありますか。
答 自動車から排出される対象物質については、国において排出量の推計を行うことになっており、届出の必要はありません。
問6-4-2 ( 船舶を保有している場合)
船舶を保有していますが、船舶から排出される対象物質についても届け出る必要がありますか。
答 船舶から排出される対象物質も自動車同様に、国において排出量の推計を行うことになっており、届出の必要はありません。
問6-4-3 ( 事業所内に、業としてガソリンを給油する施設がある場合)
事業所内に、業としてガソリンを給油する施設がありますが、そこからの排出について届け出る必要がありますか。
答 事業者が業種、常時使用する従業員の数の要件を満たしている場合、ガソリンには対象物質であるベンゼン、トルエン、キシレン等が含有されていますので、届出の必要性を判定してください。
問6-4-4 ( 構内専用の車両(フォークリフト等)を保有している場合)
構内専用の車両(フォークリフトなど)については、排出量をどのように算出したらよいですか。
答 ガソリンエンジンで稼働する車両(フォークリフト、空港補助機械、物流機械、オフロード車両)については、例えば、以下の排出係数、事業所内での年間使用時間(業務日誌等で確認)のデータ等を用いて、フォークリフト等の燃料として用いられるガソリン以外の用途(塗料等)も含めて事業所全体における年間取扱量が1t以上となるキシレン、トルエン、エチルベンゼン、トリメチルベンゼン、ベンゼン、ヘキ
サンまたは年間取扱量が0.5t以上となるベンゼンについて、その排出量を算出してください。
なお、軽油(ディーゼルエンジン)やLPGを燃料として稼働する車両については、燃料中の第一種指定化学物質の含有率が1%に満たないことから、排出量の把握の必要はありません。
| 対象となる第一種指定化学物質の名称 | エンジン定格出力1kW(または1PS)、使用時間1時間あたりの物質別排出量 | |||
|---|---|---|---|---|
| (単位:mg/kW・h) | (単位:mg/PS・h)※1 | |||
| 未対応 | 排出ガス対応 ※2 | 未対応 | 排出ガス対応 ※2 | |
| エチルベンゼン(管理番号:53) | 6.9 | 3.8 | 5.1 | 2.8 |
| キシレン(管理番号:80) | 36.3 | 19.6 | 26.7 | 14.4 |
| 1,2,4-トリメチルベンゼン | 5.5 | 3.0 | 4.1 | 2.2 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン | 7.9 | 4.3 | 5.8 | 3.1 |
| トルエン(管理番号:300) | 68.3 | 36.9 | 50.2 | 27.2 |
| ノルマルヘキサン(管理番号:392) | 32.0 | 17.3 | 23.5 | 12.7 |
| ベンゼン(管理番号:400) | 56.6 | 30.6 | 41.6 | 22.5 |
※1 PS とは馬力のことで、1PS(馬力)=0.7355kW です。
※2 排出ガス対応とは、酸化触媒、EGR、三元触媒などの排出ガス低減装置を装備することをいいます。例えば、 定格出力50kW(68.0PS)のエンジンで稼働する未対応のフォークリフト10台を年間1,000時間稼働した場合のベンゼンの排出量は、 以下のように算出します。
50(kW)×1,000(h)×56.6(mg/kW ・h)×10(台)=28,300,000mg =28,300g=28kg
[ 68.0(PS)×1,000(h)×41.6(mg/PS ・h)] ×10(台) ]
(資料出所)
平成20年度届出外排出量の推計方法の詳細 14.特殊自動車(建設機・農業機械・産業機械)に係る排出量(平成22年2月)
問6-4-5 ( ガソリンスタンドの場合)
ガソリンスタンドは、政令で定める業種の燃料小売業に該当しますが、どのような物質について、どのように排出量を算出したら良いのでしょうか。
答 ガソリン中に含まれているベンゼン、トルエン、キシレン等が届出の対象となります(PRTR排出量等算出マニュアル第III部4-2-4参照)。貯蔵タンクからの算出については第III部1-1にベンゼンの例が示されていますので参考にしてください。( 対象となる全物質についてはpⅢ-546の排出係数を参照してください。) NITEのウェブサイトで提供しているPRTR 届出作成支援システムの燃料小売業用排出量算出機能により算出することも可能です。
( URL: http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/notify.html )
また、灯油やA 重油を取り扱っている場合は、灯油中のキシレン等やA重油中のメチルナフタレンが届出対象物質になります。
問6-4-6 ( 対象物質を輸送している場合)
対象物質を輸送している際の排出量を届け出る必要があるのですか。
答 事業所外での活動における排出、移動は対象となりませんので、輸送している際の排出量、移動量を届け出る必要はありません。
問6-4-7 (重油の取り扱い)
弊社では、製品を加熱乾燥させる燃料として重油を使用しています。製品の加熱乾燥のために使用する燃料についても、対象物質の把握が必要なのでしょうか。
答 業のために使用される燃料については、その燃料中に含まれる対象物質の取扱量を把握する必要があります。SDS等を用いて当該重油に含まれる対象物質の含有率を確認し、対象物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれている等の届出要件を満たす場合には、PRTR届出を行う必要があります。
6-5 その他
問6-5-1 ( 大気と水域への排出量を比較する場合)
対象物質の大気と水域への排出量の比較をする場合、実測データがないとき、取扱状況及びヘンリー定数等から、どちらにより多く排出されるか判断することとなっていますが、どのように判断すればよいのですか。
答 大気と水域のどちらが多いかがまったくわからない場合は、PRTR排出量等算出マニュアル第III部4-3-9を参考に判断してください。 なお、対象物質のヘンリー定数は第III部4-2-9を参照してください。
問6-5-2 ( 外資系の企業で排出量等を年次単位で把握している場合)
A事業者は外資系の企業であり、排出量等の把握を年次単位で行っていますが、年次実績で排出量等を届け出てよいでしょうか。
答 法では、年度単位で届け出ることになっていますので、年度単位で届け出てください。
問6-5-3 ( 届出書別紙中に記載する河川等の名称)
届出書別紙中に記載すべき排出先の河川等の名称は、いかなるものを記載したらよいでしょうか。
また、事業所からの排水が2つ以上の河川等に排出されている場合には、排出先の河川等の名称はどうすればよいのでしょうか。
答 経済産業省及び環境省のホームページにおいて、都道府県ごとに記載すべき名称を整理したもの(「PRTR届出の公共用水域(河川、湖沼、海域等)の名称について」)が掲載してありますので、それを参照してください。
また、事業所からの排水が2つ以上の河川等に排出されている場合には、排出される対象物質の排出量の多い方の河川等を記入してください。
問6-5-4 ( 年間取扱量の記載の必要性)
届出様式には「年間取扱量」を記載する欄がありませんが、排出量の算出にあたって把握した年間取扱量を届け出る必要はないのでしょうか。
答 届出の必要はありません。ただし、取扱量を把握していないと自社が対象事業者か否かが判明しませんので、取扱量を把握することは重要です。
問6-5-5 ( 環境中への排出がほとんどない場合)
年間取扱量が5トンを超えていますが、環境中への排出はほとんどなく届出様式に記載する数値は「0.0」となりました。この場合も届出が必要ですか。
答 対象事業者としての要件を満たすものが排出量又は移動量を算出した結果、「0.0」である場合は、「0.0」と届出書に記載して届出を行うことが必要です。
7.特別要件施設に関するもの
問7-1 ( 一般・産業廃棄物処理施設、下水道終末処理施設を設置している事業出る物質)
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置している廃棄物処理業者や下水道終末処理施設を設置している下水道業者が届け出るべき物質は、具体的には何ですか。
答 下水道事業者については「下水道法に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」(法施行規則第4条第1号ニ)、廃棄物処理業者については「水質汚濁防止法第14条第1項等に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第1項に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」(法施行規則第4条第1号ホ)、また下水道事業者、廃棄物処理業者ともに「大気汚染防止法第18条第35項に基づく測定の対象( 以下、「大防法の測定対象」) となっている第一種指定化学物質( 法施行規則第4条第1号ニ、ホ) 」であり、具体的には以下に掲げる30物質( 水質検査の対象。水銀及びその化合物は大防法の測定対象でもある。) とダイオキシン類です(ただし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令に規定する廃棄物の最終処分場の場合のみ)。
なお、「フェノール類」が水質検査の対象となっていますが、これには第一種指定化学物質である「フェノール」、「クレゾール」及び「ピロカテコール」を含む多様な物質が含まれており、それぞれの分別が困難であること等にかんがみ、いずれについても届出は不要と解します。
都道府県の判断により以下に示す30 物質及びダイオキシン類以外のPRTR の対象物質で水質検査や排ガス検査の対象に加えられている物質については、届出の必要はありません。ただし、自ら第一種指定化学物質を使用しており、その年間取扱量が1トン( 特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン)を超える場合は、当該第一種指定化学物質についての届出が必要となります(問7-2、問7-8参照)。
| 1 亜鉛の水溶性化合物 | 237 水銀及びその化合物 |
| 48 O-エチル=O-4-ニトロフェニル=ホスホノチオアート(別名EPN) | 242 セレン及びその化合物 |
| 75 カドミウム及びその化合物 | 262 テトラクロロエチレン |
| 87 クロム及び三価クロム化合物 | 268 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム) |
| 88 六価クロム化合物 | 272 銅水溶性塩(錯塩を除く。) |
| 113 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジン又はCAT) | 279 1,1,1-トリクロロエタン |
| 144 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | 280 1,1,2-トリクロロエタン |
| 147 N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) | 281 トリクロロエチレン |
| 149 四塩化炭素 | 332 砒素及びその無機化合物 |
| 150 1,4-ジオキサン | 374 ふっ化水素及びその水溶性塩 |
| 157 1,2-ジクロロエタン | 400 ベンゼン |
| 158 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) | 405 ほう素化合物 |
| 159 シス-1,2-ジクロロエチレン | 406 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) |
| 179 1,3-ジクロロプロペン(別名D-D) | 412 マンガン及びその化合物 |
| 186 ジクロロメタン(別名塩化メチレン) | 632 「1,2-ジクロロエチレン」のうち、シス体 |
| 697 鉛及びその化合物 |
※1 物質名の前の番号は管理番号
※2 2015(平成27)年の大気汚染防止法等の改正により、「水銀及びその化合物」が大防法の測定対象に追加されました。当該施設については2022( 令和4)年度から把握を行い、2023(令和5)年度の届出より、排出量の届出を行う必要があります。
問7-2 ( 他法令に基づく測定項目以外の排出量等)
いわゆる特別要件施設に関して、他法令に基づく測定項目(水質検査による測定が義務付けられているもの)となっている対象物質以外に、汚泥中の化学分析等を自主的に行っております。こうして把握した対象物質の排出量等を届け出る義務はありますか。(又は、届け出てもよいでしょうか。)
答 排出量等の把握が求められているもの以外については、届出の必要はありません。(届出を行わないでください。)
ただし、業として対象物質を使用しており、その年間取扱量が1トン( 特定第1種指定化学物質の場合は0.5トン)を超える場合は、その物質について届出が必要です。
例えば、下水処理場で指定化学物質を凝集剤として使用した場合、年間1トン以上の取扱いがあると届出対象になります。
問7-3 ( 他法令で測定義務があるにもかかわらず測定していない場合)
他法令で測定義務があるにもかかわらず、実際には測定していない第一種指定化学物質がある場合、PRTRの届出をしなくてもよいのでしょうか。
答 下水道法等に基づく測定が求められている第一種指定化学物質については、仮に実際には測定を行っていなかったとしても、法に基づく届出を行う必要がありますので、法施行規則第2条の定めるいずれかの方法に基づき、排出量を把握した上で、届出を行ってください。
問7-4 ( 放流水のない一般廃棄物最終処分場、排水が出ない構造の一般廃棄物の場合)
放流水のない一般廃棄物最終処分場や排水が出ない構造の一般廃棄物焼却施設が設置されている事業場においては、法定測定項目について、排出量を「0.0」として届出を行う必要があるのでしょうか。
答 放流水のない一般廃棄物最終処分場や排水が事業所の外へ排出されない構造の一般廃棄物焼却施設については、法施行規則第4条第1号ホに列記した法令に基づく測定を求められていない場合、法に基づく排出量の把握の義務はなく、「0.0」と記載した届出書を届け出てもらう必要はありません。
問7-5 ( 溶解性マンガン等の他法令の測定項目とPRTR 対象物質の範囲が異なる)
例えば、マンガン及びその化合物(管理番号412)等については、下水道法や水質汚濁防止法等の法定測定項目としては「溶解性」のものに限定されており、第一種指定化学物質の範囲と法定測定項目の記載にズレがあります(注)。このような場合は、「溶解性マンガン」についての測定結果をそのまま用いて、「マンガン及びその化合物」の排出量を算出してもよろしいですか。
答 差し支えありません。(なお、「下水道における化学物質排出量の把握と化学物質管理計画の策定等に関するガイドライン(案)」(国土交通省年・地域整備局下水道部、平成17年8月)の中でサンプリング調査等を行い、一定の排出係数が設定されています。)
(注)なお、以下についても同様です。
・「亜鉛の水溶性化合物」(←法定測定項目は「亜鉛含有量」)
・「クロム及び三価クロム化合物」(←「クロム含有量」)
・「無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)」(←「シアン化合物」)
・「水銀及びその化合物」(←「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」)
・「銅水溶性塩(錯塩を除く)」(←「銅含有量」)
・「鉛化合物」(←「鉛及びその化合物」)
・「砒素及びその無機化合物」(←「砒素及びその化合物」)
・「ふっ化水素及びその水溶性塩」(←「ふっ素化合物」)
・「ほう素化合物」(←「ほう素及びその化合物」)
問7-6 ( EPNの測定結果)
EPNについては、法ではEPN単体が届出の対象である第一種指定化学物質とされているが、下水道法や水質汚濁防止法等の法定測定項目ではパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNの総量で「有機燐化合物」として測定しています。外部委託で測定を実施している場合、有機燐化合物として環境計量証明が出されており、EPN単体としては証明されていないのが通常ですが、このような場合、測定業者にEPN単体の測定結果を問い合わせて排出量を算定しなければならないのですか。
答 「有機燐化合物」としての測定値を用いて、「EPN」(管理番号48)の排出量を算出しても、差し支えありません。(PRTRの届出を行うべき物質は、「有機燐化合物」ではなく、「EPN」です。)
問7-7 ( 焼却灰中の水銀)
特別要件施設で発生する焼却灰中の水銀は移動量として届出する必要があるのでしょうか。
答 特別要件施設である一般廃棄物処理施設より発生する焼却灰中の水銀の移動量届出は不要です。なお、取扱量が水銀換算で年1トン以上あれば特別要件施設に関係なく届出が必要となります。
問7-8 ( 対象業種に属する事業所の接続がないことが明らかな下水道の場合)
下水道業者について、国土交通省下水道部から発出された事務連絡(平成13年7月6日付け)に、「下水道業のうち、自ら第一種指定化学物質の製造、使用その他の取扱いがなく、かつ、下水道法第11条の2に基づく届出等の状況から、法施行令第3条の業種に属する事業場の接続がないことが明らかで、第一種指定化学物質の流入が見込まれない下水道に係る下水道事業を営む者については、法第2条第5項に基づく『事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者』には該当せず、第一種指定化学物質等取扱事業者には該当しません。」との記述がありますが、具体的には如何なる対象が除外されるのでしょうか。
答 下水道法第11条の2の規定に基づく下水道使用者による届出の状況から、下水道管理者において、 以下のいずれにも該当することが確認できた下水道終末処理施設については、法施行規則第4条第1号ニに基づく届出は不要として運用しています。
(1)法施行令第3条の業種に属する事業所の接続がないこと(届け出られた下水道使用者のリストから判断するものとし、 いかなる事業を営んでいるか不明な事業者が含まれている場合は、対象事業を行っているものとみなしてください。)
(2)第一種指定化学物質の流入が見込まれないこと(過去に行われた放流水の水質測定において第一種指定化学物質が検出されなかった場合を意味します。)
ただし、下水道業を営む事業者が、下水汚泥焼却施設を有する場合は水銀及びその化合物の届出、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設となっている下水道終末処理施設を有する場合はダイオキシン類の届出、また自ら第一種指定化学物質を使用しており、その年間取扱量が1トン(特定第一種指定化学物質については0.5トン)を超える場合は当該第一種指定化学物質の届出が必要となります。なお、同様の考え方から、もっぱら生活排水等の処理を行う農業集落排水施設及び合併処理浄化槽についても、届出は不要としているところです。
問7-9 ( 測定結果が定量下限値以下の場合)
他の機関に分析を依頼して、「定量下限値○○mg以下」との証明が出ている場合は、「定量下限値の1/2」の値を用いて計算するべきでしょうか、それとも、ダイオキシン類と同様に「0」として計算してよいでしょうか。
答 pII-84の記載を参照してください。
1) ダイオキシン類の場合:
ダイオキシン類対策特別措置法と同一の方法、すなわち異性体の測定量ごとに、その測定量が定量下限以上のものはそのままの値をTEQ 換算し、定量下限未満のものは「0」としてTEQ 換算し、それらを合計するという方法で算出して構いません。
2)ダイオキシン類以外の対象物質の場合:
測定値が検出下限未満(N.D.)の場合は、0(ゼロ) とみなし、検出下限以上、定量下限未満の場合には、定量下限値の1/2 とみなして算出してください。検出下限、定量下限が不明の場合には測定を担当した分析業者等に問い合わせてください。
問7-10 ( 市町村の設置した一般廃棄物処理施設)
市町村の設置した一般廃棄物処理施設は、法施行令第4条第1号ホの「一般廃棄物処理施設」に該当しますか。
答 市町村の設置した一般廃棄物処理施設も、法施行令第4条第1号ホの「一般廃棄物処理施設」に該当します。法施行令第4条第1号ホが引用する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」とします)第8条第1項に規定する「一般廃棄物処理施設」とは、「廃掃法第8条第1項に定義されている一般廃棄物処理施設」を指し、「廃掃法第8条第1項に基づき許可を受けなければならない一般廃棄物処理施設」を意味するものではありません。したがって、市町村の設置する一般廃棄物処理施設については、廃掃法第8条第1項に基づく許可を必要とされておりませんが(廃掃法第9条の3参照)、同項に規定する「一般廃棄物処理場」の定義には合致すると考えられます。
問7-11 ( 一部事務組合等が民間企業に委託している場合の従業員の数)
ごみ処分業を行っている一部事務組合等が、民間企業に収集・運搬業務を委託している場合、民間企業の従業員数は、一部事務組合等の常用雇用者数に算入するのでしょうか。
答 委託業務に関する管理の責任を一部事務組合等が負っているのであれば、当該委託業務に従事する者も当該一部事務組合等の常用雇用者数に算入してください。なお、委託関係については、問1-3-1を参照してください。
問7-12 ( 一般廃棄物焼却施設・最終処分場で下水道放流している場合)
一般廃棄物焼却施設及び一般廃棄物最終処分場における物質について、下水道放流の場合は届出不要との記載がありますが、法施行規則もそのような規定ぶりになっていると理解してよろしいでしょうか。
答 マニュアルに記載のとおり、一般廃棄物処理施設(一般廃棄物焼却施設及び最終処分場)から下水道放流される第一種指定化学物質の量については、仮に他法令に基づく測定を行うこととなっているとしても、法に基づく届出の必要はありません。
法施行規則第4条第1号ホに列記されているとおり、一般廃棄物処理施設において把握する必要があるのは「排出量」のみであり、「移動量」については、把握の対象となっていません。下水道放流は「移動量」という整理ですので、下水道放流の把握の必要はありません。
ただし、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(一定要件を満たす一般廃棄物焼却炉など)を設置している場合は、法施行規則第4条第1号トに基づき、ダイオキシン類については、下水道への移動量及び事業所の外への移動量についても把握が必要です。(法施行規則第4 条第1 号トには、「排出量及び移動量」と規定されています。)
問7-13 ( ごみ処分業とし尿処理業のそれぞれの焼却施設を設置している場合)
同じ事業所内に「ごみ処分業」に係る焼却施設と「し尿処理業」に係る焼却施設を設置している場合、両方の施設からの「ダイオキシン類」などに関する排出量を合計したものを、事業所からの排出量として届け出るのでしょうか。
答 法施行規則第4条第1号ホにおいては、ごみ処分業を営む者が有する事業所について、所要の排出量を把握することとされており、「ごみ処分業に係る排出量」といった限定された規定の仕方にはなっていません。したがって、例えば、ごみ処分業を営む事業所内に設置されている「し尿処理業」に係る焼却施設については、水質汚濁防止法に基づく測定が求められていれば、その測定対象となっている排出量とごみ処分業に係る焼却施設からの排出分を合算して把握・届出することとなります。
また、ごみ処分業を営んでいる者がダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を有している事業所についてはダイオキシン類の排出量について、また大気汚染防止法の水銀排出施設に該当する廃棄物処理施設を有する事業所については水銀及びその化合物の排出量について、ごみ処分業に係る焼却施設からの排出分のみならず、その他の事業(し尿処理業)に係る排出量も合算して把握することとなります。
問7-14 ( 粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等再生利用施設、運搬中継施設等が独立した事業所である場合)
一般廃棄物処理施設を設置する事業者(市町村、一部事務組合)の届出について、一般廃棄物処理施設(廃掃法第8条第1項)のうち、粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等再生利用施設、運搬中継施設等が独立した事業所である場合も当該施設が特別要件に該当する施設であり届出対象事業所となりますが、特に他法令に基づく測定対象物質がないため、どのように届け出るのでしょうか。また、特別要件施設を設置する事業所ではなく、届出対象業種を営む事業者の一事業所と考えた場合、当該事業所で取り扱う 廃棄物は使用量の把握から除かれることから、対象物質をどのように把握し、どのように届け出るべきでしょうか。
答 廃掃法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設が設置されている事業所(ごみ処分業を営む者が有するもの)であっても、法施行規則第4条第1号ホに列記されている法令(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める省令、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法)のいずれに基づく水質検査も求められていないものについては、法施行規則第4条第1号ホに基づく排出量の把握の義務はありません。
最終処分場、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設、水質汚濁防止法又は大気汚染防止法の対象となる施設(焼却施設)のいずれも有していない粗大ごみ処理施設、再生利用施設、運搬中継施設については、仮にこれらが一般廃棄物処理施設に該当するとしても、上記の法令に基づく水質検査を行うこととはされておらず、したがって、法施行規則第4条第1号ホに基づく把握の義務はありません。
なお、法施行規則第4条第1号イ又はロに該当する場合(第一種指定化学物質を1トン以上取り扱っている場合など)は別途把握が必要です。(それらもなければ、当該事業所については届出の必要はありません。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問合せメールフォーム
お手数おかけしますが、お問い合わせいただく場合には、上記のメールフォームにてご連絡いただきますようお願いいたします。

