 |
 |
 |
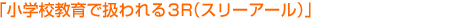 |
 |
| 東京学芸大学助教授 小林 宏己(こばやし ひろみ) |
 |
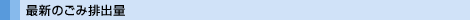 |
 |
| 東京ドームで約140杯分(5210万t)、これが2001年度に全国の家庭や事業所から出されたごみの量です。廃棄物は、廃棄物処理法によって一般廃棄物と産業廃棄物に分けられますが、私たちがごみと呼んでいるものは家庭や事業所から出される一般廃棄物のことです。1人1日当たりのごみの排出量に換算すると1124gで、前年度に比べて8g僅かに減っていますが、ここ10年間はほぼ5千万tのレベルで横ばい状態が続いています。 |
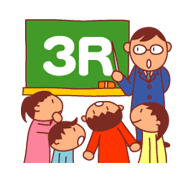 |
|
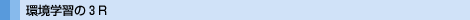 |
 |
人々が豊かで快適な暮らしを願うこととごみの排出量などを減らして水や大気や国土の環境を守ること、これら2つのことをどのようにしてバランスよく両立させていくことができるか。学校教育の場でもこうした問題を扱いながら、子ども時代から関心・意欲を育て、国民一人ひとりの「生活スタイルの改善」とその実現に向けた歩みに取り組んでいます。授業としては小学校第3学年および第4学年での社会科で、「廃棄物の処理について、見学したり調査したりして調べ、これらの対策や事業は地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを考えるように」扱われています。さらに第5学年では「国土の環境と人々の生活や産業とのかかわり」をふまえながら、私たち一人ひとりの暮らしの見直しを問いかけています。平成14年度より実施された「総合的な学習の時間」を活用し、社会科での学習を発展させて、地域の人々と連携してごみの分別・回収活動を進めたり、地域のフリーマーケットなどに参加したりする子どもたちの姿も見られるようになりました。
3R's(読み=read、書き=write、計算=arithmetic)といえば教育の基礎・基本を象徴する言葉ですが、環境学習にも3Rがあります。Recycle(再び資源として利用する)、Reuse(繰り返し使う)Reduce(ごみそのものを減らす)の3つの取り組みのことです。学校教育はもとより家庭や地域でも、子どもたちと大人が共に考えあい協力して取り組んでいくべき大切な課題です。 |
 |
 |
 |
子どもの発達段階、認識度の成長に合わせて
「リサイクル」→「リユース」→「リデュース」
の順番で理解を促すことがポイントです。 |
|
 |
|
 |
|
 |
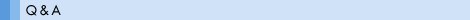 |
 |
| Q |
3Rについてもっと知りたいときはどうするの? |
| A |
経済産業省の「キッズページ」で、3Rについてやさしく説明しています。また、財団法人クリーン・ジャパン・センターのホームページには、「小学生用」・「中学生用」にわけた環境リサイクル学習のサイトがあります。
ホームページのほかにも、パンフレットの中で3Rについて説明しています。パンフレットの種類については、ホームページをご覧ください。 |
|
| ▼▼次のところで調べることができます。▼▼ |
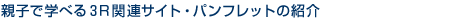 |
1. 経済産業省のホームページ
2. (財)クリーン・ジャパン・センターの環境リサイクル学習ホームページ
|
 |
| 問い合わせ 3r-info@meti.go.jp |