 |
 |
 |
 |
東京学芸大学助教授 小林 宏己(こばやし ひろみ)
|
 |
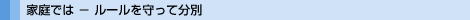 |
 |
私たちの家庭からは、いったいどれくらいのごみが出されているのでしょうか。その量は平均すると一人一日当たり1kg程ですが、種類の多さに驚きます。新聞・雑誌・ティッシュペーパーの箱・ダンボールなどの紙類、カバーや袋などのビニール類、缶やびん、ペットボトル、トレイ・容器などのプラスチック類、台所から出される生ごみ、油類、さらに乾電池や布類まで。その他にも、壊れた傘やガラス製品や不要になった家具や家庭電気製品等々、あげれば切りがありません。
|
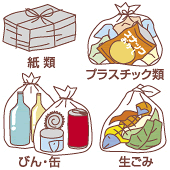 |
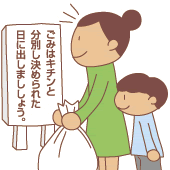 |
これらのごみは、分別して出すというのが大切です。正しい分別、それがリサイクルの第一歩でしたね。そして、私たちがごみを出すときに守らなければならないルールがもう一つあります。それは決められた日時と場所に出す、ということです。それぞれの地域では「ごみの集積所」を示す看板があり、ごみを分別する種類や収集日が記されています。ごみの収集と処理は主に市区町村の仕事ですが、地域に暮らす住民の一人ひとりがルールを守って分別し、決まった日時と場所に出すという協力がなければなりません。
|
| その他にも、街の中にはごみを分別して出す場所がいろいろあります。スーパーやコンビニの店先、飲物の自動販売機の横など、役所などの公共機関でもリサイクルなどを呼びかける様々な取り組みをしていますから注目してみてください。 |
|
 |
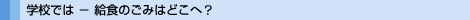 |
 |
私たちの学校からもごみは出ます。紙類はもちろん、文具関係のプラスチックやビニール類、机・椅子を含めた事務機器類など、家庭とは違った種類のごみが多いようです。しかし、もっとも気になるものは給食の残飯です。これらの残飯はどうしているのでしょうか。
実は多くの学校、そして市区町村では、こうした残飯類を堆肥化する事業が進められています。残飯類を生ごみ処理機(コンポスト)に入れ、細菌の力をかりて堆肥化し、学校の花壇や菜園に利用したりするのです。また役所の方が残飯類を集めて、契約している農地で堆肥化し、農作物を栽培して再び学校給食の材料に生かすという循環も作り出されています。こうした取り組みにより、食べ物の大切さやごみ問題などが意識され、残飯になる量とともにごみ処理の経費も減るという効果が生まれています。ごみは捨てずに生かすもの、という考え方がいろいろな場面で実行されているのです。
|
|
 |
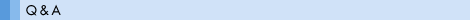 |
 |
| Q |
どれくらいのごみが資源に生まれ変わっているの? |
| A |
市町村が収集したごみのうちリサイクルされた量と自治会などがリサイクルのために回収したごみの量を合計すると平成13年度は825万トンで、全国の家庭から出るごみの約15%を占めています。平成10年度から比べると、全国の家庭から出るごみの排出量が4年間で100万トン増加しているのに対し、リサイクルされたごみは約200万トン増えていますので、みなさんが分別してごみを出している効果が表れはじめたことがわかります。 |
|
 |
| 総資源化量とリサイクル率の推移 |
 |
| |
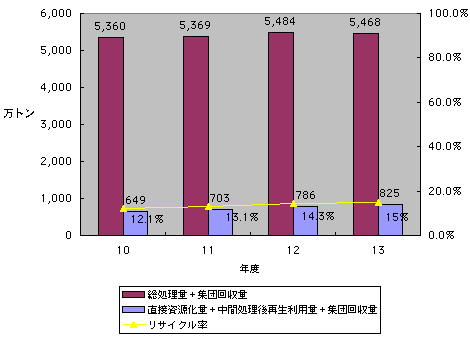 |
 |
| リサイクル率= |
| 直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量 |
 |
| ごみの総処理量+集団回収量 |
|
|
 |
| 出典:環境省資料に加筆 |
 |
▼▼統計資料は次のところで調べることができます▼▼ |
1.経済産業省「3R政策」のホームページ
|
 |