 |
 |
 |
 |
| 容器包装の識別表示Q&A |
 |
|
 |
 |
 |
識別表示については、容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(概ね利用事業者)のいずれにも表示義務がかかります。また、輸入販売事業者も表示義務者となります。包装については、製造事業者に表示義務はありません。
なお、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義務の対象と識別表示義務の対象者は基本的に同じです。 |
 |
 |
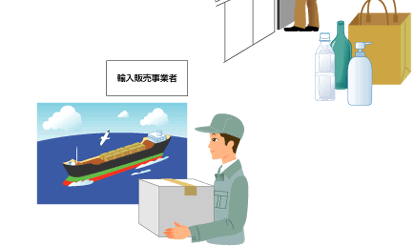 |
 |
 |
 |
 |
容器包装の再商品化義務がない小規模事業者も表示義務があるのですか? |
 |
 |
 |
 |
再商品化の義務とは異なり、識別表示については、小規模事業者にも表示義務があります。
なお、小規模事業者とは、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす事業者を指します。
| 小規模事業者とは |
| 業種 |
売上高 |
従業員 |
| 製造業等 |
2億4,000万円以下 |
かつ20名以下 |
| 商業、サービス業 |
7,000万円以下 |
かつ5名以下 |
|
|
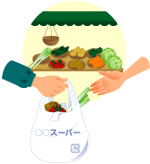 |
|
|
 |
 |
 |
 |
紙マークやプラマークを印刷する際の製造事業者と製造を発注する事業者の費用負担はどのように分配すればよいのですか? |
 |
 |
 |
 |
法律では規定されていないので、通常の商慣習などを踏まえ、事業者間で決めてください。 |
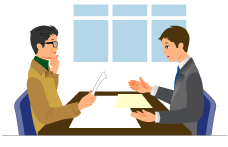 |
 |
 |
 |
 |
市販品を商品の容器包装へ転用した場合の表示義務対象者は誰になるのですか? |
 |
 |
 |
 |
市販品を商品の容器包装へ転用した事業者が表示義務対象者となります。
ただし、市販品の容器包装にラベルを貼る等の行為が行われず、そのまま使われる場合は無地の容器包装に該当するため、表示の義務は生じません(Q.19参照)。 |
 |
(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)
<消費者向けの商品(市販品)を転用した容器包装への対応> |
 |
本来、消費者向けの商品(紙コップ、紙皿等の市販品)を、容リ法の対象となる容器包装に転用した場合、表示の義務対象者は、市販品の製造事業者ではなく転用者である。したがって、こうした転用者が、新たに印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルを施さないでそのまま転用した場合には、無地の容器包装に該当するため、表示を省略できるものとする。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
容器包装リサイクル法の再商品化義務の対象でない容器包装に自主的に識別マークを表示することに問題はありますか? |
 |
 |
 |
 |
問題があります。
識別マークは容器包装リサイクル法における製造・利用事業者等に再商品化を義務付けている容器包装を分別排出するためのマークです。
|
|
|
 |
|