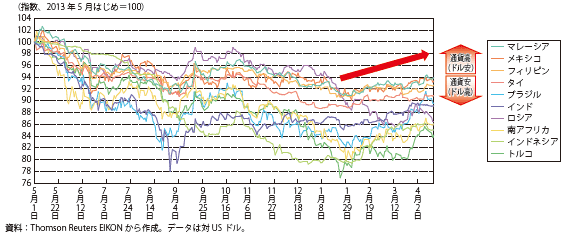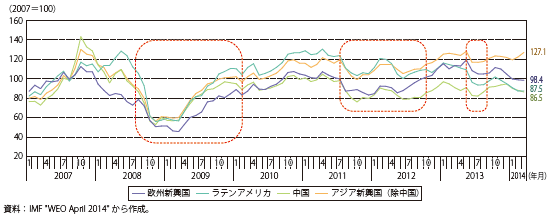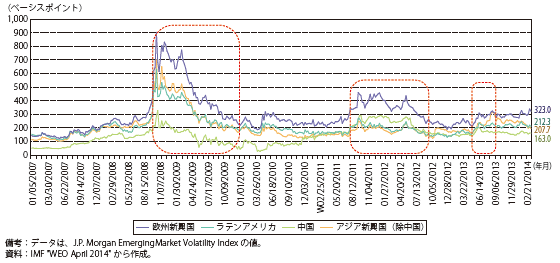- 政策について

- 白書・報告書

- 通商白書

- 通商白書2014

- 白書2014(HTML版)

- 第1部 第1章 第2節 米国の量的金融緩和縮小とその影響
第2節 米国の量的金融緩和縮小とその影響
世界経済危機に際して米連邦準備制度理事会(FRB)が2008年以降に講じた金融緩和策10は、金融市場の動揺を緩和するとともに経済の下支えに大きな役割を果たした。一方、緩和マネーが膨らんだことによる副作用についても指摘されていた。こうした中、2013年5月に、FRBのバーナンキ議長が量的金融緩和第3弾(2012年9月開始)の縮小可能性について示唆したことをきっかけに、通貨ドルの窮迫懸念が生じ、新興国を中心に金融市場は大きく動揺した。
ここでは、2013年5月下旬から2014年1月にかけて、米国が量的金融緩和の縮小に向かうプロセスにおける新興国の資本流出及び通貨下落の状況を中心に見ていく。
10 政策金利の実質的なゼロ水準への引下げ(いわゆる「異例な低金利」政策)、「異例な低金利」政策の将来的な解除に関するガイダンスの提示(いわゆる時間軸政策)、大規模な資産購入(いわゆる第1~3弾量的緩和策(QE1~3))を指す。
1.新興国の資本フローへの影響
世界経済危機に際して、主要国は、量的金融緩和や低金利政策等の金融政策及び財政政策を通じて大規模な景気刺激策を講じた11。
世界経済危機の震源地となった米国においても、FRBが、2008年11月から2013年12月までの間に3段階にわたり、3兆5,050億ドル(約335兆円)にのぼる大規模な量的緩和策を講じた(第Ⅰ-1-2-1表)。
11 通商白書2010版。IMF “WEO April 2010”によれば、各国が講じた景気刺激策は、全体で約20兆ドル、世界GDPのおよそ30%にのぼった。
第Ⅰ-1-2-1表 米国FRBによる量的金融緩和の実施及び第3弾縮小の状況
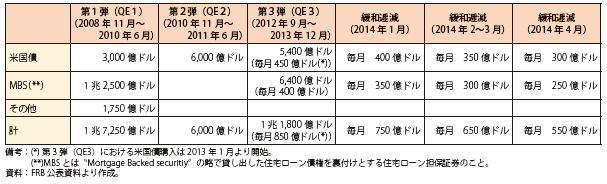
米国をはじめとする主要国の潤沢な資金供給から生じた余剰資金は、投資先を求めて、高い成長力及び高金利を有する新興国へと流入した。こうした活発な緩和マネーの流入は、世界経済危機後の新興国における高い経済成長を支えてきたが、その一方で、いくつかの新興国において、経常赤字が大幅に拡大又は経常黒字が大幅に縮小した(第Ⅰ-1-2-2図)。
第Ⅰ-1-2-2図 主要新興国におけるリーマン・ショック後の経常収支の黒字縮小又は赤字拡大状況
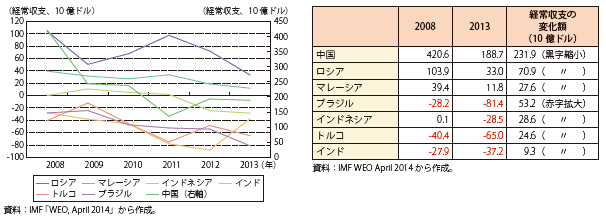
2013年5月22日、米FRBのバーナンキ議長の発言をきっかけに、量的金融緩和の縮小観測が高まると、市場では通貨ドルの窮迫懸念が生じた。新興国では、膨らむ経常赤字を対外資金によってファイナンスしてきたことから、ドル窮迫懸念により対外債務の返済能力が改めて不安視された。加えて、米国の長期金利の上昇が見込まれる中、新興国との間の金利差縮小によって投資の魅力が低下すること、中国において金融市場の引締めによる資金窮迫懸念が高まり、景気の先行き不安が高まったこと等もあり、投資家のリスク回避姿勢が強まった。こうした背景から、2013年5月下旬から6月末にかけて新興国は大幅な資本流出に見舞われた(第Ⅰ-1-2-3図)。
第Ⅰ-1-2-3図 新興国ファンドへの資本フロー(ネット)
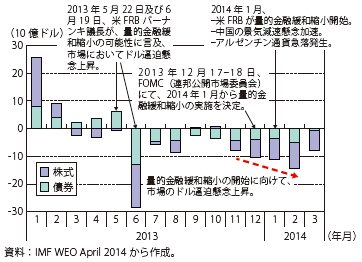
なお、2013年に入って以降、新興国経済への懸念などから、既に新興国への資本は細ってきており、こうした流れが米国の量的金融緩和の縮小観測によって加速されたとみられる。
2.新興国の通貨への影響
2013年5月22日及び6月19日、米FRBのバーナンキ議長が量的金融緩和の縮小の可能性に言及したことを受けて、同年5月下旬から 6月下旬にかけて、ほぼ全ての新興国で一斉に通貨が下落した(第Ⅰ-1-2-4図)。この際、FRBが、「量的金融緩和を縮小しても、ゼロ金利政策は継続する」、「量的金融緩和の終了と金融引締め(利上げ)は異なる」との趣旨のメッセージを発したこともあり、市場は徐々に落ち着きを取り戻した。同年8月中旬頃には、米国経済指標に改善が見られたことなどを背景に、再び量的金融緩和の縮小が意識され、新興国通貨は下落した。その後、同年9月18日、市場の予想に反して、FOMC(連邦公開市場委員会)が量的金融緩和の維持を発表すると、新興国通貨は上昇した後、やや下落した。同年10月1日には、米国において、暫定予算案及び債務上限引上げのための法案について与野党が合意に至らず、政府機関が閉鎖されたことから、量的金融緩和の早期縮小の可能性が低くなったとの見方が高まり、新興国通貨は上昇した。
第Ⅰ-1-2-4図 新興国の為替の推移(対ドル)
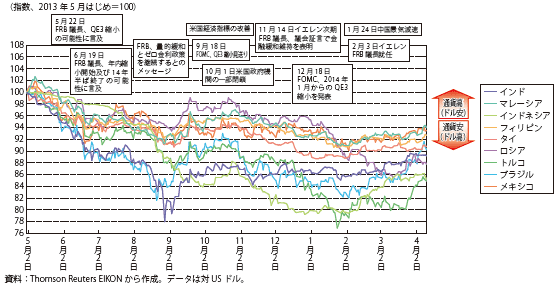
5月下旬から6月下旬にかけては、ほぼ全ての新興国で一斉に通貨が下落したが、その後は、経常収支、成長率、外貨準備、インフレ率等の状況に応じて投資家による選別の動きが表れ、国によってその強弱に差が生じた(第Ⅰ-1-2-5図~第Ⅰ-1-2-10図)。特に下落率が大きいのは、インド、インドネシア、トルコ、ブラジルである(第Ⅰ-1-2-11図)。
第Ⅰ-1-2-5図 主要新興国の実質GDP成長率
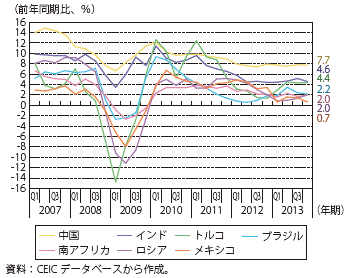
第Ⅰ-1-2-6図 ASEAN主要国の実質GDP成長率
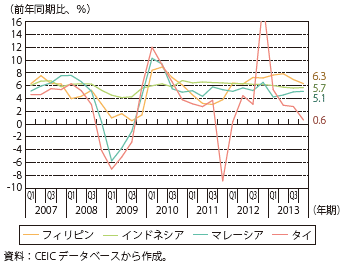
第Ⅰ-1-2-7図 主要新興国の外貨準備高
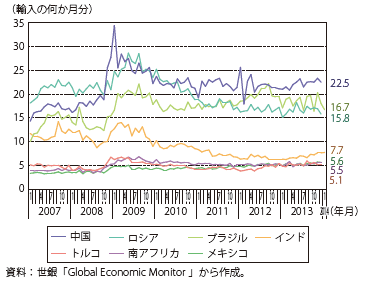
第Ⅰ-1-2-8図 ASEAN主要国の外貨準備高
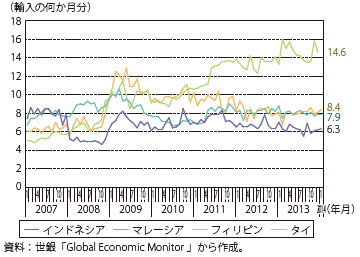
第Ⅰ-1-2-9図 主要新興国の消費者物価指数
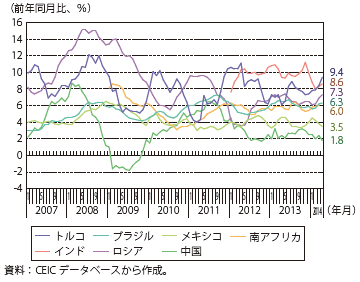
第Ⅰ-1-2-10図 ASEAN主要国の消費者物価指数
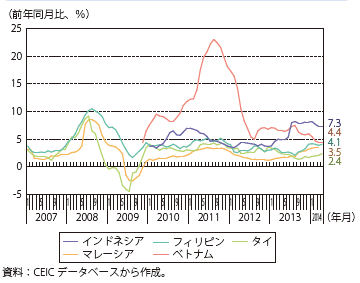
第Ⅰ-1-2-11図 通貨のぜい弱な新興国における為替推移(対ドル)
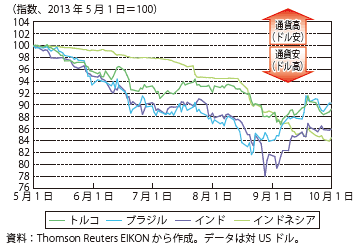
第Ⅰ-1-2-12図は、第Ⅰ-1-2-11図の期間における新興国通貨の下落幅と、経常収支の対GDP比との相関を示している。対外債務の返済能力への懸念が意識されやすい経常赤字国ほど通貨の下落幅が大きくなっている。
第Ⅰ-1-2-12図 新興国の経常収支対GDP比と為替変化率
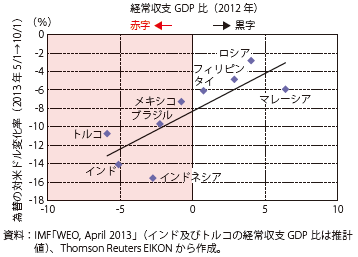
多額の経常赤字を抱える国には注意が必要であるが、その一方で、各国とも外貨準備を積み増すなど、過去の危機時と比べてリスクへの耐性を強めてきている。第Ⅰ-1-2-13図は、主要新興国として、インド、ASEAN主要国、ブラジル、メキシコ、トルコの8か国についての、対外債務残高、外貨準備高、短期対外債務残高の関係を見たものである12。外貨準備高の適正水準については、様々な見解があるが、ここでは対外ファイナンスが困難になった場合の当該年に支払期限が来る債務に対する外貨準備保有高での支払能力として、1をベンチマークとする見解を参考に両指標をみることとする。8か国の外貨準備高を見ると、いずれの国においても増加している。また、8か国における外貨準備高の短期対外債務残高比を2012年時点でみると、ブラジルが11.5倍、フィリピンが9.9倍と高く、いずれの国もベンチマークの1.0倍を超える水準を保っている。
12 統計の制約上、データは2012年までとなっている。
第Ⅰ-1-2-13図 主な新興国の対外債務残高、外貨準備高、短期対外債務残高の推移
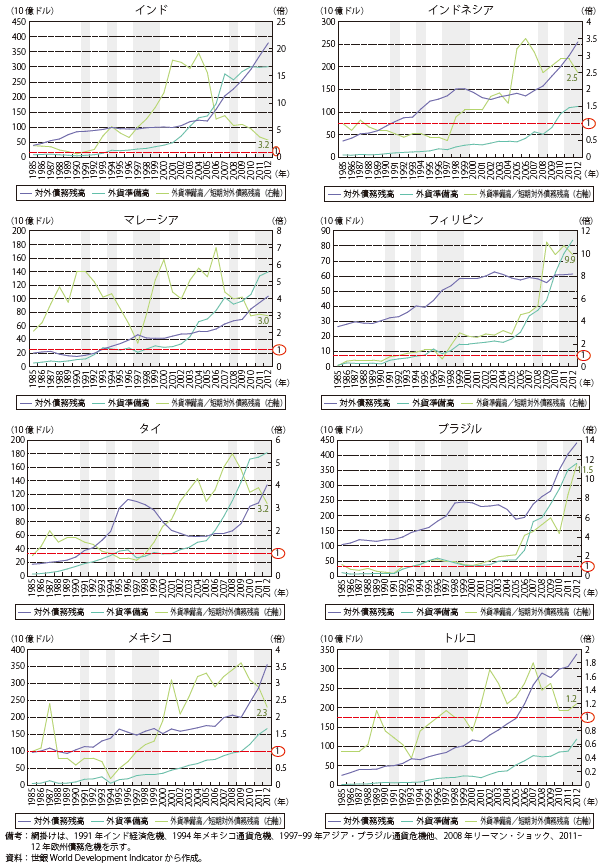
- Excel形式のファイル(インド)はこちら

- Excel形式のファイル(インドネシア)はこちら

- Excel形式のファイル(マレーシア)はこちら

- Excel形式のファイル(フィリピン)はこちら

- Excel形式のファイル(タイ)はこちら

- Excel形式のファイル(ブラジル)はこちら

- Excel形式のファイル(メキシコ)はこちら

- Excel形式のファイル(トルコ)はこちら

また、新興国は通貨防衛のため、政策金利の引上げ、投資優遇政策等の対策を講じた。第Ⅰ-1-2-14表は、通貨が大きく下落したインド、インドネシア、トルコ、ブラジルについて、新興国の金融市場が大きく動揺した2013年5月末から9月末までに講じられた政策対応をまとめたものである。さらに、第Ⅰ-1-2-15図では、インド及びインドネシアにおける株価及び為替の推移を通じて、2013年8月から9月にかけて両国で講じられた対策とその効果を見ている。政策金利の引上げに伴う景気減速の影響などに注意が必要であるが、これらの対策により、通貨の下支えに一定程度成功した。
第Ⅰ-1-2-14表 新興国における通貨下支えのための政策対応
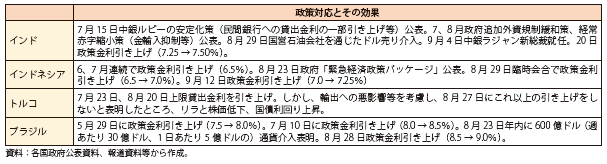
第Ⅰ-1-2-15図 新興国の政策対応による通貨下支えの効果
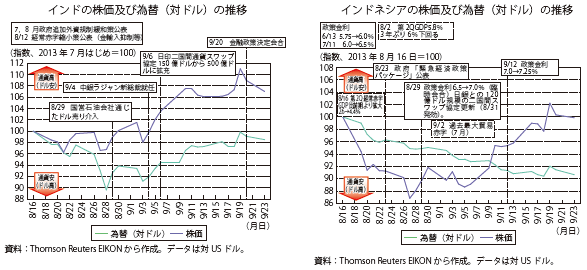
2014年1月から、FRBによる量的金融緩和の縮小が開始された。今後の状況により、経常収支の赤字国を始め一部の新興国において短期的な動揺が生じる可能性はあるが、過去の危機時と比較してリスク耐性を強めてきていること、迅速な政策対応が図られていること、FRBのイエレン議長が、量的金融緩和の縮小はゆっくり進め、金利引上げは当分先であると発言していること、米国の景気回復によるプラスの影響などから、過去の経済危機において見られたような大きな混乱が生じる可能性は低いと見られている。