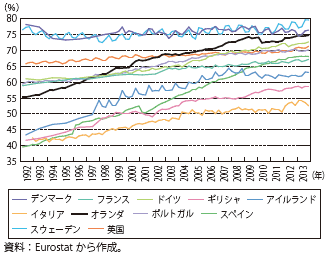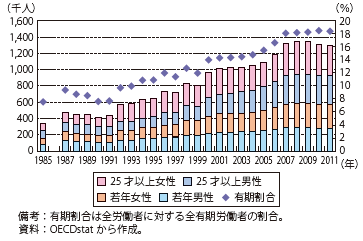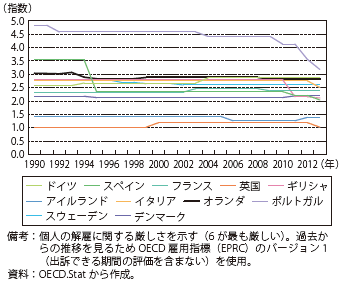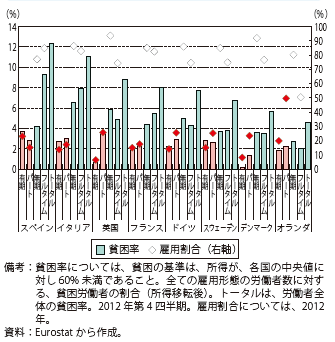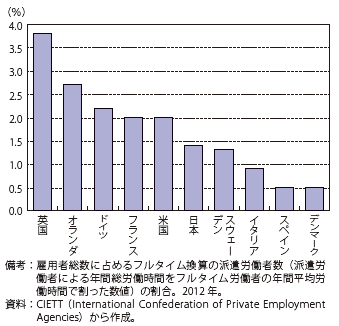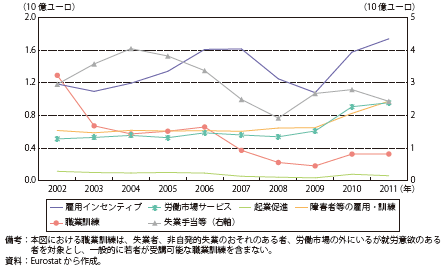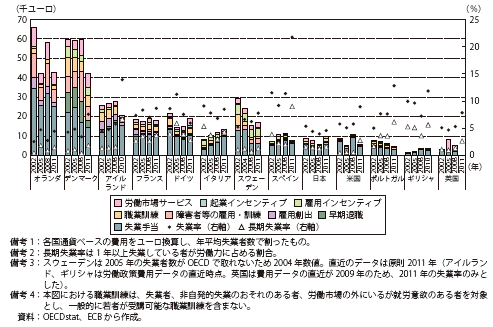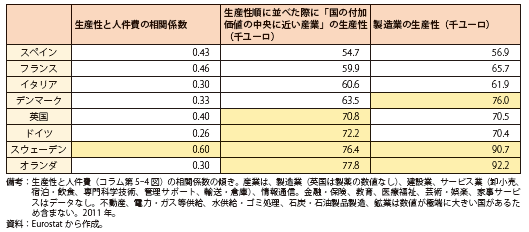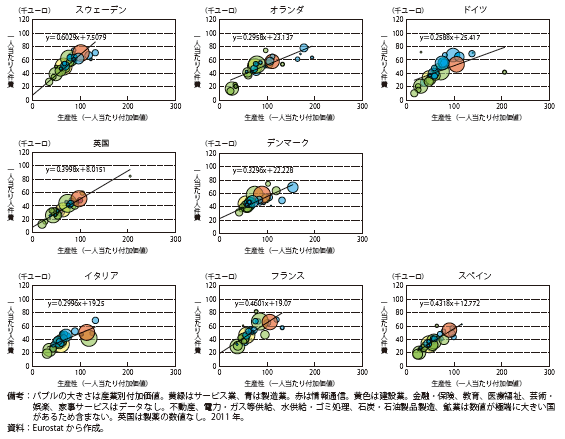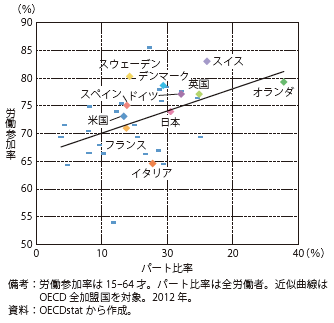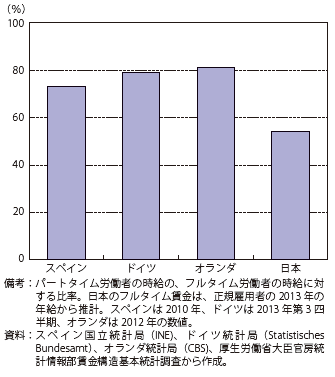第1節 欧州における労働市場改革
1.欧州の経済状況
ユーロ圏の実質GDP成長率は、2013年第2四半期に7四半期ぶりにプラス成長となった。鉱工業生産も緩やかに回復してきている。また、国債利回りは2012年秋に低下した後落ち着いており、域内向け証券投資が増大するなど、金融市場も安定してきている。
経済が緩やかに回復の兆しを見せている一方、引き続き経済を下押しするリスク要因も見られる。
消費者物価上昇率は依然として低水準で推移しており、銀行セクターに対する財務健全化要請や需要の弱さなどを背景として、民間企業向け銀行融資も依然として低迷している。
また、失業率は、2012年秋以降、ユーロ圏全体で12%前後、若年失業率は23%を超えて推移しており1、一部の国では改善傾向も見られるものの、引き続き高い水準となっている。
他方、設備投資及び個人消費が伸び悩む中、輸出が拡大し、国外からの直接投資も一部の国で増加しているが、こうした輸出の拡大や直接投資の増加は、労働市場改革の効果の表れであるとも指摘されている。
欧州債務危機により経済が低迷する中、欧州各国は財政健全化と競争力向上に向けて様々な構造改革を実施しているが、その中でも労働市場改革が注目されている。
規制の緩和と就業支援の強化などを組み合わせつつ進められている労働市場改革は、その内容やバランスにおいてそれぞれ特徴が見られる。以下では、欧州各国における労働市場改革を見ていく。
2.近年の欧州における労働政策の方向性
1990年代以降、欧州各国では、グローバル競争を背景に、コストを低減させる必要性から非正規雇用が増大した。こうした中、非正規雇用労働者の雇用条件の改善を図るため、1997年と1999年に、パートタイム労働、有期雇用労働に関する欧州枠組み指令が出され、多くの国では、非正規雇用契約について、労働者の賃金や休暇に関して一定の待遇確保を図りつつ、規制緩和が実施された2。
欧州は、南欧を中心に労働市場の硬直性の問題が指摘されている。すなわち、非正規雇用については上記のとおり柔軟化が図られている一方で、正規雇用労働者については、賃金、労働時間、解雇といった調整を行うことが難しく、業況が悪化した際に企業の利益圧縮の負担が重くなるだけでなく、新たな雇用が手控えられるといった影響を生じる。このため、南欧諸国の近年の労働市場改革においては、産業ごとの最低賃金協約制度の拘束力低下や賃金調整の手続の緩和、あるいは解雇規制の緩和など、労働市場の柔軟化が図られている。
同時に非正規雇用労働者については、その割合が高いことが欧州債務危機において失業率を悪化させた要因の一つであるとの認識から、正規雇用労働者との格差を是正するため、待遇のさらなる改善が図られている。具体的には、有期雇用契約の長期化回避3、一定期間経過後の無期雇用への転換などである。また、低賃金労働者の割合が高いドイツでは、低賃金労働者の生活水準の引上げを図るため、2014年4月に、全国一律の最低賃金を導入することが合意されている。
他方、デンマークとオランダは、1990年代半ば以降、「フレキシキュリティ(Flexicurity)」と呼ばれる労働政策を採用している。フレキシキュリティとは、①労働時間や労働市場における柔軟性(Flexibility)を高める一方、②手厚い社会保障(Security)により失業期間における所得を保障し、③積極的労働市場政策によって就業可能性を向上させることによって、雇用の安定を図るものである。2000年代に入り、フレキシキュリティは他国にも拡大し、中でも柱の一つである積極的労働市場政策については、ドイツ、スペインをはじめとして多くの国で導入されるようになってきている4。
第Ⅱ-1-1-1表 近年の欧州における主な労働政策
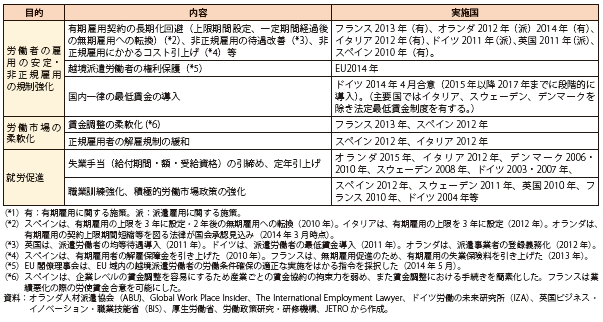
2 例えばイタリアは1997年に派遣労働を合法化するとともに、許可制、利用理由制限、均等待遇原則を規定。2003年に利用可能範囲を拡大(濱口(2012))。
ドイツは2001年、一定の目的を有する有期契約であれば期間を問わない、2年までの期間であれば目的を問わないとすると同時に、均等待遇原則を定めた(田端(2012))。
3 一人の労働者が有期労働契約を繰り返して締結し、同じ職場で同様の仕事に従事し続けることを避ける目的。EUでは、無期雇用が一般的であり、有期雇用は例外的である、という考え方が基本。
4 鈴木(2009)。
3.労働市場と労働政策に関する各国比較
各国における労働政策は様々であるが、労働政策の影響が労働市場と国民の所得格差にどのように表れているかを確認するため、長期失業率5と所得移転前のジニ係数6を比較すると、北欧及びオランダでは、長期失業率、格差とも相対的に低く、南欧では、長期失業率、格差とも相対的に高い傾向が見られる。ドイツは、欧州の中で高い水準にあった長期失業率が近年低下し、2012年時点では北欧及びオランダに近い水準となっている。なお、英国と米国は、長期失業率がそれほど高くない一方、格差が大きくなっている(OECD加盟国の分布の近似線から横軸(ジニ係数)方向へのかい離が大きい)(第Ⅱ-1-1-2図)。日本は、長期失業率が低く、格差は北欧及びオランダ、英国及び米国との間、近年は北欧及びオランダに近いところに位置している。
第Ⅱ-1-1-2図 長期失業率と格差(所得移転前)
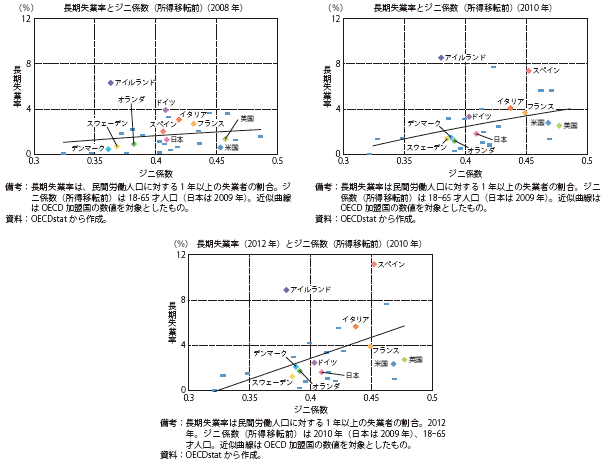
- Excel形式のファイル(長期失業率とジニ係数(所得移転前)(2008年))はこちら

- Excel形式のファイル(長期失業率とジニ係数(所得移転前)(2010年))はこちら

- Excel形式のファイル(長期失業率(2012 年)とジニ係数(所得移転前)(2010年))はこちら

5 1年以上の失業者(OECDstat)。
6 公的年金や失業給付といった公的所得移転及び課税前の、18-65才に関する数値(OECDstat)。
(1)北欧及びオランダ
各国の労働政策に関する指標について見ると、北欧及びオランダでは、職業訓練や失業者への就労支援などに用いられる積極的労働市場政策費用が他国と比べて大きい。非正規雇用に関しては、契約規制は中程度、均等待遇は比較的高い水準に位置する。解雇規制の厳しさに関しては、スウェーデン及びオランダがOECD平均をやや上回る一方、デンマークは欧州平均を下回っている(第Ⅱ-1-1-3図)。
第Ⅱ-1-1-3図 北欧及びオランダの労働政策指標
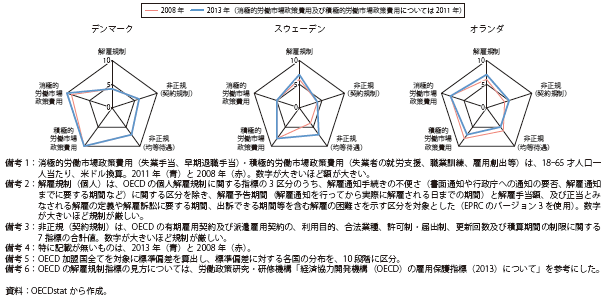
(2)ドイツ
ドイツでは、積極的労働市場政策費用は上記3か国より少ないがOECD平均を上回っている。非正規雇用に関する規制は中程度、解雇規制の厳しさについてはOECD平均を上回っている(第Ⅱ-1-1-4図)。
第Ⅱ-1-1-4図 ドイツの労働政策指標
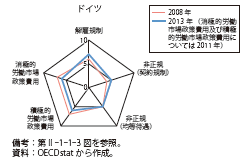
(3)南欧
南欧では、非正規雇用関連規制、解雇規制とも厳しく、積極的労働市場政策費用については、欧州平均を下回っている(第Ⅱ-1-1-5図)。
第Ⅱ-1-1-5図 南欧の労働政策指標
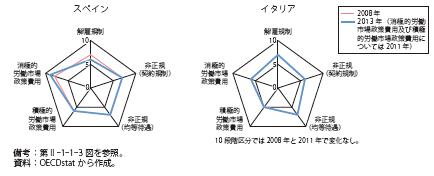
(4)英国及び米国
英国及び米国では、積極的労働市場政策費用、消極的労働市場政策費用とも小さく、解雇規制や非正規雇用に関する市場規制が弱い(第Ⅱ-1-1-6図)。
第Ⅱ-1-1-6図 英国及び米国の労働政策指標
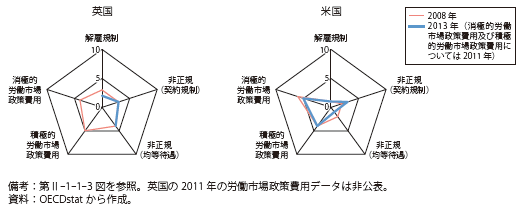
4.デンマークの労働政策
(1)長期失業率の抑制
デンマーク経済は、主要な輸出先であるEU域内需要の低迷を背景に、2010年以降伸び悩んでいる。失業率は2009年に大幅に悪化し、2012年には7.8%となった。しかし、他国と比べると失業率の水準は低く抑制され(第Ⅱ-1-1-7図)、特に長期失業率は、最大で2012年第1四半期の2.2%と、低い水準を維持している7(第Ⅱ-1-1-8図)。
第Ⅱ-1-1-7図 失業率の推移
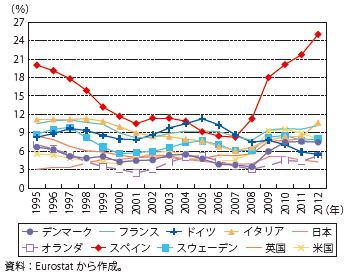
第Ⅱ-1-1-8図 長期失業率の推移
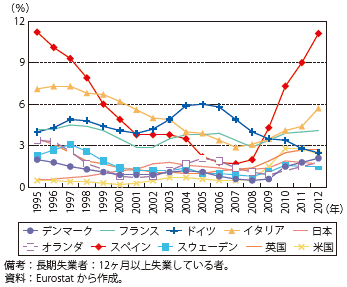
7 2013年第4四半期までの数値。
(2)柔軟な労働市場と労働者の待遇確保
このように、デンマークでは長期失業率が低い水準で維持されているが、同国では、1994年の労働市場改革以降、柔軟な労働市場、手厚い失業保険制度、積極的な労働市場政策を柱とする「フレキシキュリティ」と呼ばれる労働政策が実施されている。
まず、フレキシキュリティの柱の一つである労働市場の柔軟性について見ていく。
解雇規制については、経済的な理由に基づく解雇が認められているほか、解雇手当は欧州の多くの国に比べ低い。解雇予告期間は比較的長く規定されている一方、手続を踏めば企業は労働者を解雇することができる8。同一組織での勤続期間を見ると、デンマークでは相対的に短くなっている(第Ⅱ-1-1-9図)。
第Ⅱ-1-1-3図 (再掲) デンマークの労働政策指標
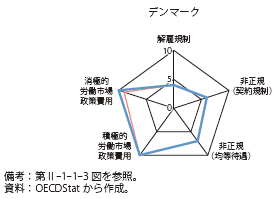
第Ⅱ-1-1-9図 各国労働者の勤続期間別割合
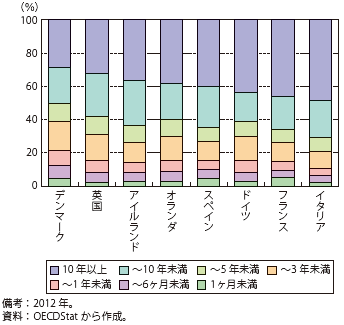
こうした解雇に関する柔軟性は企業にとっての負担軽減となるが、労働者が一方的に軽視されているわけではない。古く1900年代初頭に遡る労使合意において、労組は賃金や労働条件について交渉する権利を獲得し、現在でも、労使交渉が広く労働者の待遇確保に貢献している。労使交渉により決定される最低賃金の平均賃金に対する割合9は国際的に高い水準であり(第Ⅱ-1-1-11図)、平均賃金も高い水準となっている(第Ⅱ-1-1-10図)。また、有期雇用契約や派遣雇用契約も労働協約の対象となっており、非正規雇用労働者についても、原則として、正規雇用労働者と同じ待遇が確保されている。
第Ⅱ-1-1-10図 年間平均賃金
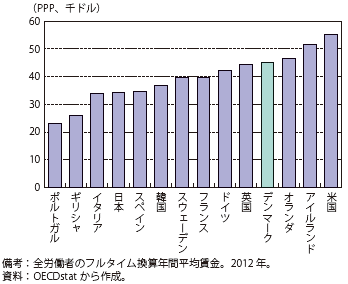
第Ⅱ-1-1-11図 各国の最低賃金比率
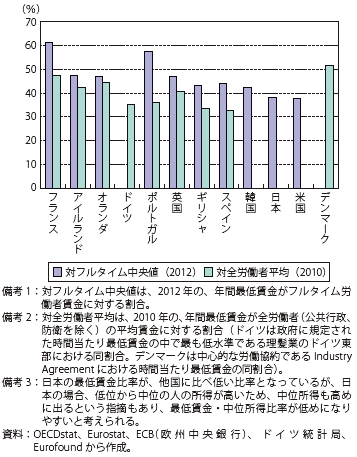
その結果、貧困率及び所得格差を示すジニ係数は、所得移転後のみならず、所得移転前においても、主要国の中で最も低い国々の一つとなっている(第Ⅱ-1-1-12図)。
第Ⅱ-1-1-12図 貧困率とジニ係数(所得移転前後)
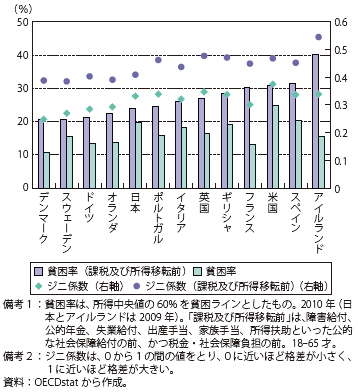
8 デンマークは、OECDの解雇規制に関する指標によれば、不当解雇の定義は緩いが、解雇予告期間は最大6ヶ月と長く(JETRO(2009))、また解雇通知手続は、ドイツとオランダより規制が弱いものの、多くの欧州諸国よりも厳しいものとなっている。
9 中心的な労働協約であるIndustry Agreementにおける最低賃金は、全労働者平均賃金の52%と高い(EurofoundとEurostatから試算。2010年。)。
(3)積極的労働市場政策
デンマークにおいては、1990年代から2000年代を通じて、失業者に対する就労インセンティブの付与が強化されている。その柱は、「アクティベーション」と呼ばれる就労のための活動プログラムである。アクティベーションとは、失業給付受給の条件として失業者が参加を義務づけられる、就労に向けた活動で、就労支援(カウンセリング、職探し、就職活動計画作成等)、職業訓練、及び企業における職業訓練や賃金助成付きの労働が含まれる10,11。
手厚い失業手当が支給される場合、失業者の就労意欲がそがれてしまう可能性があるが、このアクティベーションを背景に、失業率が悪化した2012年にも、失業者のうち36%が3か月未満で再就職している(第Ⅱ-1-1-13図)。
第Ⅱ-1-1-13図 各国失業者の失業期間別割合
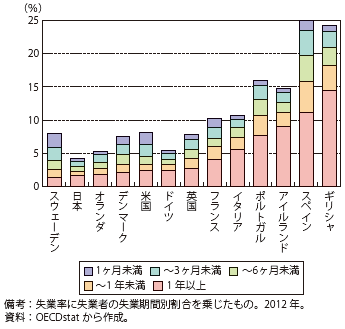
一方、失業期間を短縮し失業者の早期就労を促すために、失業手当を受給する失業者に課される条件は年々強化されている。2006年以降、失業者は毎週ジョブセンターのホームページに登録することが義務づけられた。また、アクティベーションを受ける義務と権利が発生する時期が短縮されている。さらに、2007年以降、運営の効率化を図るため、失業手当の受給者の再就職支援を行う国の職業安定所と、生活保護手当の受給者の再就職支援を行う市の施設が一体化されてジョブセンターとなり、市がジョブセンターを運営するとともに、失業手当を負担することとなった12。市が負担した失業手当は、その後条件付で国から還付される仕組み13となっており、市は、失業者の早期就業を実現するための支援に重点を置くこととなった14。
なお、一般的な職業訓練に対しては、労働市場が求める人材を創出するため、産業界が資金の一部を拠出するとともに、プログラムの作成や企業内訓練の実施などに深く関与している。
10 The National Labour Market Authority (Denmark) (2010).
11 19才未満は失業から2週間後に、30才未満の者については失業から13週間後に、30才以上の者については失業後9か月でアクティベーションを受ける義務と権利が発生する。
12 JETRO(2011)。
13 還付額は失業手当給付期間が長くなるほど削減される。また失業者との面談やアクティベーションが規定された日程で実施されない場合には還付がなされない。
14 早期の就労を失業者に強く求めることについては、失業期間の短縮という一定の効果は得られている一方、失業者が早く仕事に就くことが優先され、職業を選択する自由が制限される可能性も懸念されている(OECD(2012))。
(4)失業手当
デンマークでは、手厚い失業保険制度がフレキシキュリティの柱の一つとされており、失業手当の補償率は最大で従前賃金の90%15と高い(第Ⅱ-1-1-14表)。上限額が設定されているため、実際に補償率90%が適用されるのは賃金水準が低いグループのみであるが、フルタイム労働者に対する平均補償率を算出したOECDの指標によると、2009年まではOECD加盟国の中で最も高い水準であった(第Ⅱ-1-1-15図)。
第Ⅱ-1-1-14表 主要国の失業手当補償率(対従前賃金)

第Ⅱ-1-1-15図 失業手当の補償率(社会扶助等除く)
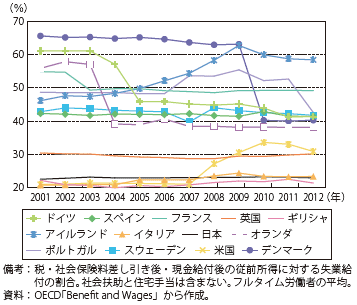
受給期間についても1990年代初頭までは無期限とされ、こうしたことが失業者の就労意欲を減退させているとの問題意識から、1990年代後半から数回にわたり給付期間が短縮され、2006年には受給資格が厳格化された。
失業者一人当たりの失業手当政策費用は、2006年以降急激に低下(第Ⅱ-1-1-17図)しており、同国のフレキシキュリティ政策は、失業給付よりも積極的労働市場政策により重点がシフトしていると言える。ただし、失業時の給付に社会扶助や住宅手当を含めた場合の補償率はオランダとともに65%を超え、OECD主要国の中で高い水準となっている(第Ⅱ-1-1-16図)。
第Ⅱ-1-1-16図 失業手当の補償率(社会扶助等含む)
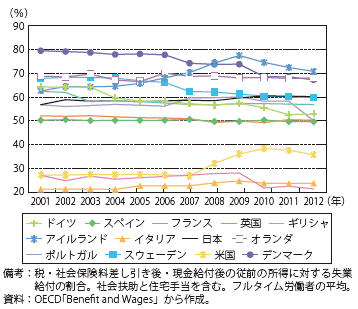
第Ⅱ-1-1-17図 デンマークの労働市場政策費用(失業者一人当たり)
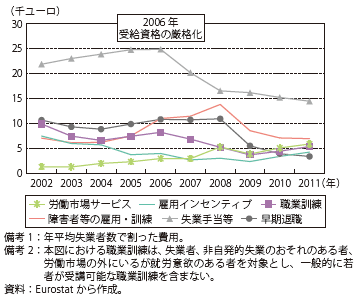
第Ⅱ-1-1-18図 デンマークの労働市場政策費用の推移
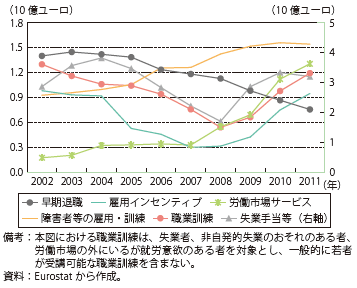
15 従前賃金の90%、ただし週当たり3940クローネ(2012年時点、約5万4千円)を超えないこととされている(デンマーク外務省「Work In Denmark」ウェブサイト、
(https://www.workindenmark.dk/en/Find_information/Information_for_job_seekers/Working_in_Denmark/Unemployment_insurance/Unemployment_benefits![]() ))。
))。
5.ドイツの労働政策
(1)1998年以降の労働市場改革
ドイツでは、1990年代まで手厚い失業給付と硬直的な労働制度が支配的であったが、経済の低迷による高失業率を背景に、「福祉から就労へ」の理念の下、2002年から2005年にかけて労働市場改革が実施された。
内容は、失業手当の減額や受給資格の厳格化を通じた失業者の就労促進、就労支援をはじめとする積極的労働市場政策、雇用契約の柔軟化と非正規雇用労働者の待遇改善までを含む包括的なものであった。
一連の労働市場改革の後に生じた世界経済危機とそれに続く欧州債務危機において、ドイツは他国と異なりGDPの縮小にも関わらず雇用を維持することができたことから「ドイツの奇跡」とも言われた。以下では、2000年代前半の労働市場改革と近年の労働政策について見ていく。
(2)失業給付の引締めと長期失業者を対象とする失業給付Ⅱの創設
ドイツの失業手当は従来手厚く、2004年末までは、最高32か月間受給でき、32か月経過後は従前所得の53%に相当する失業扶助を無期限に受給することができるというものであった27。このように手厚い失業手当が失業者の就労意欲を阻害しているとの認識の下、2005年から失業手当の受給期間は最大12か月に短縮され、12か月経過後は従前所得とは切り離された失業給付Ⅱが支給されることとなった。
失業給付Ⅱは、通常の失業者を対象とする失業手当制度(失業給付Ⅰ)とは別に新たに設けられ、従来の失業扶助受給者に加え社会扶助受給者のうち就労可能な者も対象としており、手当の支給とともに就労を要請する仕組みとなった。
一般的な失業手当の受給期間短縮と、長期失業者に対する就労要請によって、失業率の低下と社会保障費の削減が図られた28。
第Ⅱ-1-1-19表 主要国の失業手当最長給付期間
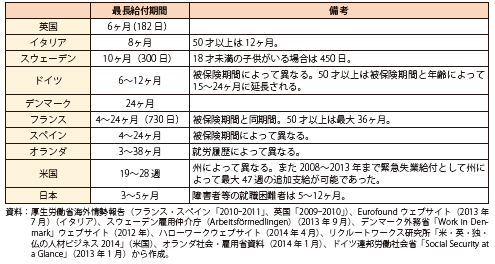
27 労働政策研究・研修機構(2006)。
28 労働政策研究・研修機構(2006)。
(3)就労支援の強化と雇用創出
先に見た失業給付の引締めは、失業者の就労インセンティブを高めることが目的であったが、失業者の早期の就労を実現するため、2002年から2003年にかけて成立した労働市場近代化法(ハルツ第Ⅰ法~第Ⅳ法)によって、失業者に対する就労支援が大幅に拡充された。
主な施策としては、連邦機関が担ってきた失業扶助と、自治体が担ってきた社会扶助を統合し、長期失業者に対する手当(失業給付Ⅱ)と就労支援の効率化が図られた29。失業者に対しては就労を要請する姿勢が明確化され、失業給付Ⅱを受給するためには、失業者は地域の雇用エージェンシーに登録し、就業する努力を行うことが必要となり、紹介された仕事を断った場合や職を探す努力を怠っている場合には失業給付Ⅱは停止する30とされた。また、各地の雇用エージェンシーには、失業者を労働者として派遣する人材サービスエージェンシー(PSA)が設置されることとなった31。
さらに、低技能者や長期失業者を労働市場に統合することを目的として、使用者に対する助成や、月収が400ユーロ以下の場合に被雇用者の税・社会保険料の支払が免除されるミニ・ジョブ32のほか、公共分野における助成付きの雇用(1ユーロ・ジョブ)などの施策が実施された(第Ⅱ-1-1-22図)。
第Ⅱ-1-1-22図 労働市場プログラム参加者に占める長期失業者割合(ドイツ)
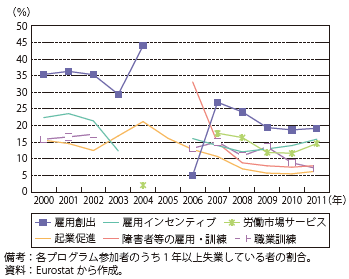
失業者を対象とする職業訓練は、その効率化が図られ33、2000年から2005年にかけて参加率が減少したが、他の労働市場プログラムと比較すると、失業者の参加率は最も高い水準を維持し、費用配分も高い(第Ⅱ-1-1-20図、第Ⅱ-1-1-21図)。
第Ⅱ-1-1-20図 ドイツの労働市場政策費用推移
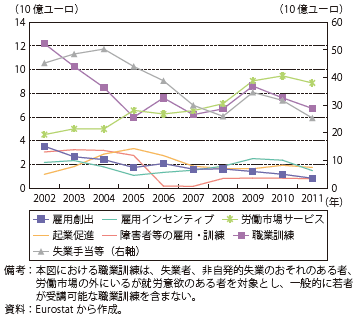
第Ⅱ-1-1-21図 求職者の積極的労働市場プログラム参加率(ドイツ)
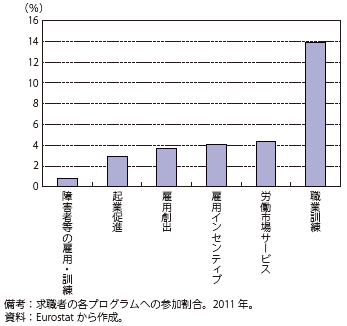
第Ⅱ-1-1-23図 欧州の有期・派遣雇用契約規制
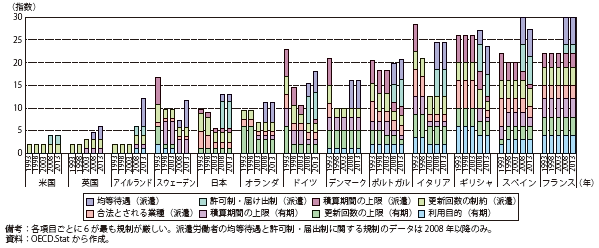
29 武田(2012)。
30 労働政策研究・研修機構(2007)。
31 2005年6月以降はPSA設置は任意となった。
32 ミニ・ジョブでは、使用者は疾病保険、年金保険、税金分として一律賃金の30.88%を負担する。月収の上限は2013年に450ユーロに引き上げられた。なお、月収800ユーロ以下(2013年以降、850ユーロ以下)で、被雇用者の税・社会保険料の支払が軽減される「ミディジョブ」も導入された。2013年1月から、ミニ・ジョブ従事者にも法定年金の加入が義務づけられることとなった(労働政策研究・研修機構「2013年1月記事」、
(http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_1/german_02.htm![]() )、ドイツ労働社会省ウェブサイト「2014年4月2日記事」、
)、ドイツ労働社会省ウェブサイト「2014年4月2日記事」、
(http://www.bmas.de/EN/Our-Topics/Social-Security/450-euro-mini-jobs-marginal-employment.html![]() ))。
))。
33 雇用エージェンシーの裁量に基づいて職業訓練クーポンを発行する制度により、受講者は就労可能性の高い者に集中することとなった。
(4)雇用契約の規制緩和と待遇改善
有期雇用契約については、2000年に、客観的な理由のない有期契約が可能となった。同時に、契約期間の上限は2年と定められ、これを超えると無期雇用に移行するとされた。
派遣雇用契約については、2002年に派遣期間の上限が撤廃された。なお、賃金や休暇等に関する均等待遇原則については2002年に導入されたものの、労働協約によりこの原則を逸脱することが認められていたことから、多くの場合、低水準の賃金が適用され、2010年時点では68%の派遣労働者が「低賃金」34労働であった35。
解雇規制については、2003年の労働市場改革法により解雇制限法の適用除外対象が拡大され、2004年以降新規採用された労働者については、10人以下の事業所の場合、特別な理由を示すことなく解雇することができるようになった36ものの、他国と比較すると厳しい水準にとどまっている(コラム第4-4図(前掲))。
34 フルタイム労働者賃金中央値の3分の2を下回る賃金水準の労働者。
35 Spermann(2013).
36 労働政策研究・研修機構(2006)。
(5)賃金の抑制
ドイツの賃金上昇率は他国に比べ低水準で推移している(第Ⅱ-1-1-24図)。
第Ⅱ-1-1-24図 主要国の年間平均賃金の推移
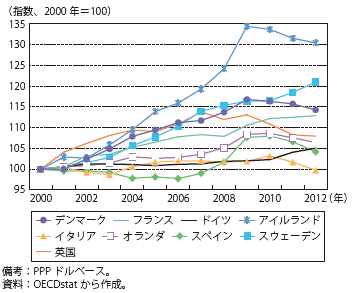
賃金が抑制された背景としては、ミニ・ジョブをはじめとする非典型雇用の増加により労働コストが押し下げられたこと、1990年代以降、労働協約の拘束力が次第に低下したこと37、1990年代後半以降に普及した労働時間貯蓄口座制度38により、柔軟な労働時間の調整が可能になったこと等が指摘されている39。
なお、賃金の変動を見ると、スウェーデンと英国では、景気縮小時には付加価値の低下幅以上に減少し、景気拡大時には付加価値の増加幅以上に上昇している。ドイツとデンマークでは、スウェーデンや英国ほどではないものの、景気縮小時には付加価値の低下幅以上に賃金が減少している。他方、南欧諸国では、景気縮小時にも賃金の減少幅が小さい(第Ⅱ-1-1-25図)。また、スペインとイタリアでは、GDPがマイナス成長となる期間が多いにも関わらず、時間あたり賃金の伸び率がマイナスとなる期間が少ない(第Ⅱ-1-1-26図)。
第Ⅱ-1-1-25図 時間あたり賃金伸び率とGDPの伸び率の差の推移
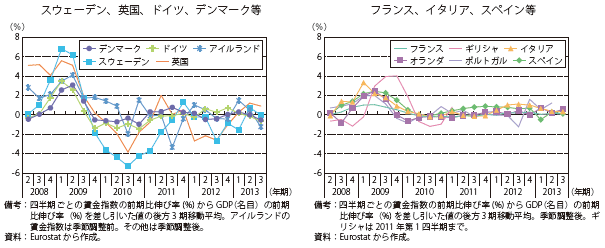
第Ⅱ-1-1-26図 時間あたり賃金とGDPのマイナス成長期間数
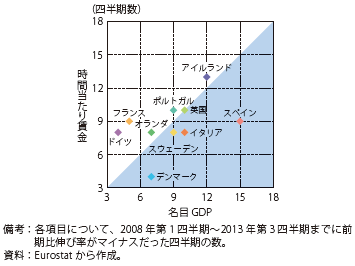
スペインとイタリアで顕著に見られるこうした賃金の下方硬直性は、景気縮小時には企業の業績を更に圧迫する要素となって経済の回復を阻害する可能性があるが、その背景となる賃金調整の仕組みは、次に述べるように国によって異なっている。
業績などに応じて賃金を柔軟に変更することを可能にする仕組みとしては、ドイツとスウェーデンでは、労働協約において、多くの場合労働協約を逸脱できる条件が規定されており、業績不振に陥った企業は労働協約を逸脱して賃金を削減することができる40。
また、英国とアイルランドでは、南欧と異なり、集団賃金協約が適用される労働者の比率が低いことが賃金の柔軟な調整を容易にしていると考えられる。
また、労組の代表が意思決定に関与する権利が、南欧では弱いのに対し、スウェーデン、デンマーク及びドイツでは強い(第Ⅱ-1-1-27図)。
第Ⅱ-1-1-27図 労使交渉への労働者の関与
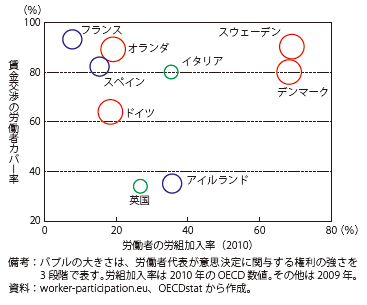
ドイツでは、労働者の利益を代表する仕組みとして、労働組合の他に、5人以上の事業所において設置される「事業所委員会」がある。事業所委員会は、多くの大規模事業所に存在し、現場の労働者全員を代表する。使用者から情報提供を受け協議し、また主に労働に関する事項について使用者と共同決定する権利を有しており、労使の緊密なコミュニケーションと紛争の解決に寄与しており41、企業収益を圧縮しない賃金調整に結びついた可能性が考えられる。
37 産業別労働協約から離脱して企業別労働協約を締結する企業が増加し、また産業別労働協約自体において「開放条項」を設けて企業ごとの個別的な決定の余地を認めることが多くなった(齋藤(2012))。
38 銀行口座のように労働者が実労働時間を記録して積み立て、所定労働時間との差を金銭ではなく労働時間によって清算する仕組み。
39 杉浦、吉田(2014)。
40 スウェーデンでは、事業再生に際し、労働協約を逸脱して賃金を引き下げた事例(2012年)が報告されている(Eurofound (2012))。ドイツでも協約逸脱による賃金削減が報告されている(労働政策研究・研修機構(2013))。
41 ベルント・ヴァース(2013)。
(6)労働市場への影響
2002年からの労働市場改革において、失業給付Ⅱの創設や就労支援の強化、企業の社会保険料率の引下げ42、中高年の雇用促進策43の拡充などが実施される中、長期失業率は、2007年以降大きく低下し、欧州債務危機の際も上昇せず、現在では北欧やオランダに近い水準まで低下している(第Ⅱ-1-1-28図、第Ⅱ-1-1-8図(前掲))。
第Ⅱ-1-1-28図 ドイツの失業率の推移
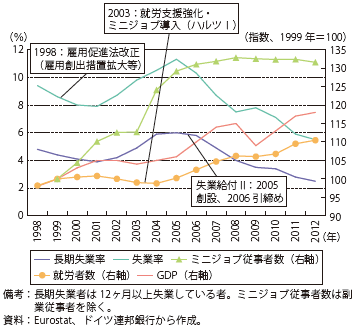
また欧州債務危機においては、操業短縮手当制度44や労働時間貯蓄口座制度により、労働者を解雇する代わりに労働時間を短縮することを通じて、雇用が維持された面もある(第Ⅱ-1-1-29図、第Ⅱ-1-1-30図)。
第Ⅱ-1-1-29図 ドイツの失業率と操業短縮手当制度適用者の割合
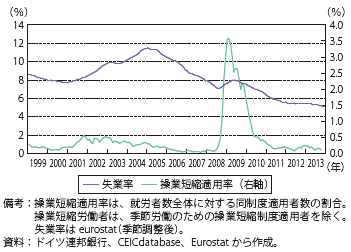
第Ⅱ-1-1-30図 一人当たり年間労働時間の推移
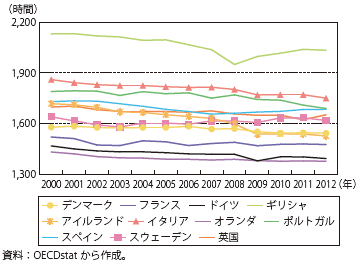
一方で、一連の規制緩和を受けて非典型労働者45は増加し(第Ⅱ-1-1-31図)、2000年から2012年の労働者数の伸びは、正規雇用が2%にとどまるのに対し、非典型雇用は31%となっている。特に失業給付Ⅱが導入された2005年には、パートタイム労働者、有期労働者、僅少労働者とも急激に増加している。
第Ⅱ-1-1-31図 ドイツの非典型労働者数の推移
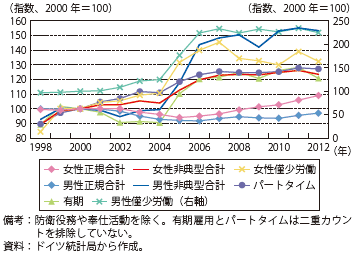
ただし、ミニ・ジョブの増加が雇用の創出につながったかどうかについては議論46がある。また、ミニ・ジョブ従事者47の1割強が就労しながら失業給付Ⅱを受給している(第Ⅱ-1-1-32図)など生活水準が低く、それ以外の雇用形態に移る割合が低いことも指摘されている。
第Ⅱ-1-1-32図 ドイツの失業給付Ⅱ受給者の内訳
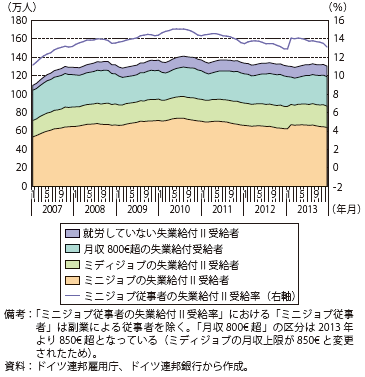
なお、派遣労働については、2012年1月に最低賃金が導入されたほか、派遣労働の濫用を防止する規定が導入48され、また、EU派遣労働指令を受けて派遣労働は一時的なものとする旨の規定が導入49されるなど、規制が強化されている。
2012年の非典型雇用労働者は前年に比べ減少しており、その背景として、こうした派遣労働に関する規制の強化も指摘されている。
42 2005年の20.725%から2007年には20%に低下。2013年には19.275%となっている(単身・子供なし・平均所得世帯の総収入に対する割合)(OECDstat)。社会保険料と労働関連の課税分の企業負担の労働1時間当たり費用の伸び(2000年から2008年まで)は、欧州主要国の中で最も低く抑制されている(Eurostat)。
43 中高年の失業者雇用を促進するための使用者に対する賃金助成。
44 経済的要因又は不可抗力の出来事に起因して、事業主が従業員を解雇することなく一時的に操業短縮を行ったことにより、賃金の支払いが減少した場合に、賃金の補塡のための費用を事業主に支給する制度。
45 ドイツ統計局統計の「非典型雇用」。有期労働者、僅少労働従事者、非正規パートタイム労働者を含む。
46 従来登録されていなかった「ヤミ雇用」が顕在化・合法化されミニ・ジョブとして振り替えられた、また社会保険義務のある正規の雇用関係が、低コストのミニ・ジョブに置き換えられただけであるとの指摘もある(労働政策研究・研修機構(2007))。
47 副業での僅少労働を除く。
48 正規雇用労働者を一旦解雇して、低賃金の派遣労働者として雇用するという「回転ドア」と呼ばれる事例が見られていたが、新たな規定により、均等待遇原則を逸脱する取決めは、同一(又はコンツェルン関係にある)派遣先への派遣について、従前の派遣契約終了後6か月の間は適用されないこととなった(齋藤(2012))。
49 2011年労働者派遣法改正。2013年には、この規定に基づき、派遣労働者の利用が一時的でないと認められる場合に、派遣先企業の事業所委員会は当該派遣労働者の受入れについて拒否権を行使することができる、との判断が連邦労働裁判所によって下された(労働政策研究・研修機構「国別労働トピック」、2013年8月、(http://web.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_8/germany_01.htm![]() ))。
))。
(7)最近の最低賃金制度に関する動き
僅少労働者を中心とした低所得労働者の待遇を改善するため、2014年4月に、ドイツ政府は、2015年以降2017年までに段階的に全国的な最低賃金を導入することを内容とする最低賃金法について閣議決定した。
ドイツにおける最低賃金制度の導入により、賃金格差の縮小が期待される(第Ⅱ-1-1-33図)一方、最低賃金比率の水準が過度に高い場合には、企業の生産性上昇に見合わない賃金上昇を引き起こす可能性もある。
第Ⅱ-1-1-33図 最低賃金比率と賃金格差
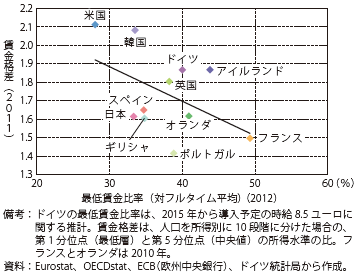
また、非正規雇用労働者や一部の業種、また地域によっては、1時間当たり8.5ユーロの最低賃金導入によって、賃金の引上げが生じることとなる。産業別の労働協約を見ると、サービス分野においては、2013年の協約賃金が1時間当たり8.5ユーロを下回る割合が19%、工業分野においては、サービス業に比べ大幅に低く、3%となっている(第Ⅱ-1-1-34図)。ただし、労働協約のカバー率は同国の労働者の50%にとどまっており、労働協約対象外の企業における低賃金割合の方が高い可能性があることに留意する必要がある。
第Ⅱ-1-1-34図 ドイツの協定賃金(1時間当たり賃金水準別)
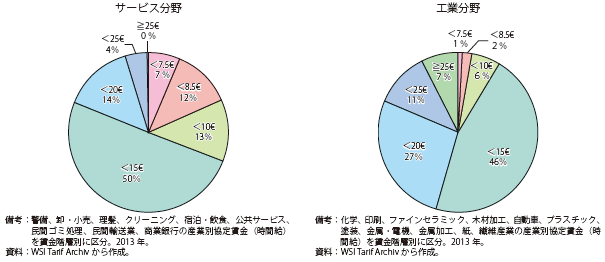
第Ⅱ-1-1-35図 低賃金労働者比率(2010年)
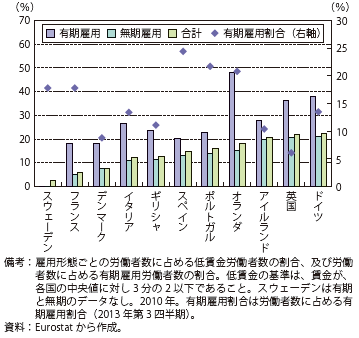
第Ⅱ-1-1-36図 ドイツの雇用・産業別月収比較
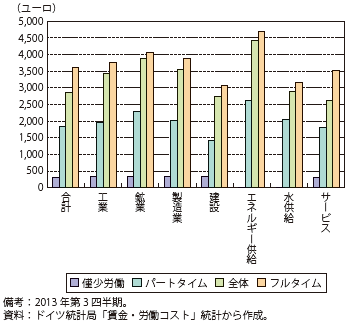
6.スペインの労働市場改革
(1)雇用状況
スペインでは、欧州債務危機を背景に雇用環境が大幅に悪化した。2013年には失業率が26%を超え、若年失業率は最大で56%を超えた。
世界経済危機以降、GDPの縮小を経験した多くの国と比較しても、スペインはGDPの縮小の程度に比べ長期失業率の増加幅が突出している(第Ⅱ-1-1-37図、第Ⅱ-1-1-38図)。
第Ⅱ-1-1-37図 GDP(変化率)と長期失業率の変化
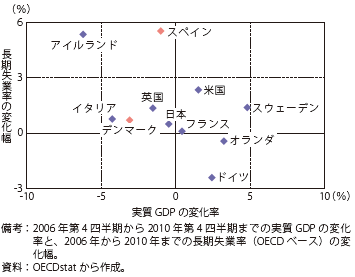
第Ⅱ-1-1-38図 GDP(マイナス期間数)と長期失業率の変化
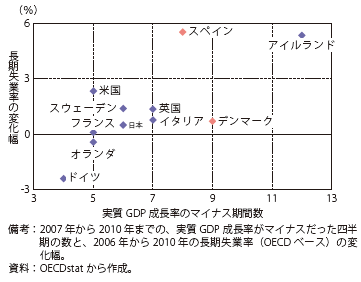
年齢別に見ると、雇用状況の悪化は若年層において顕著である。若年層は、2009年以降労働参加率が低下しているにも関わらず、失業率は他の年齢層と比べ大幅に悪化した(第Ⅱ-1-1-39図、第Ⅱ-1-1-40図)。一方、25~64才については、女性の非労働力人口が減少(家計収入の減少を補うために働きに出る女性が増加)し、労働力人口を押し上げたにも関わらず、失業率の上昇は若年層に比べれば抑制されている(第Ⅱ-1-1-41図、第Ⅱ-1-1-42図)。
第Ⅱ-1-1-39図 スペインの失業率推移(年齢別)
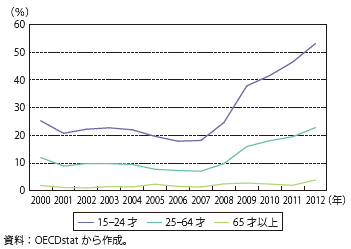
第Ⅱ-1-1-40図 スペインの労働参加率推移(年齢別)
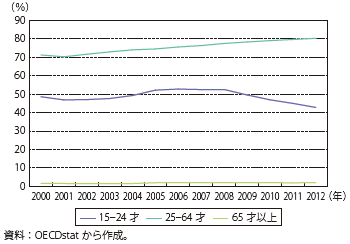
第Ⅱ-1-1-41図 スペインの若年労働状況
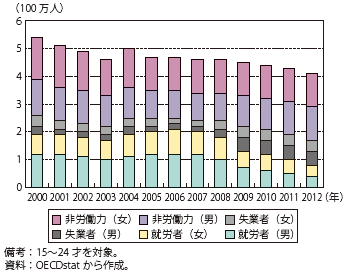
第Ⅱ-1-1-42図 スペインの25才以上の労働状況
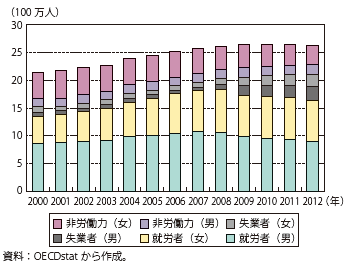
雇用契約別では、有期雇用労働者の雇用の悪化が顕著である。失業に移行した割合は、2012年には有期雇用労働者の30%に上ったが、無期雇用労働者については5%にとどまっている(第Ⅱ-1-1-43図)。また、25才以上の無期雇用労働者数が緩やかな減少にとどまる一方で、有期雇用労働者は年齢を問わず大幅に減少した(ただし2010年から2011年にかけては、25才以上の有期雇用労働者のみ増加している)(第Ⅱ-1-1-44図)。
第Ⅱ-1-1-43図 失業に移行した者の前年の雇用形態別割合(スペイン)
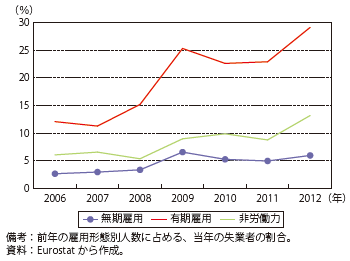
第Ⅱ-1-1-44図 労働者の雇用形態・年齢別減少率(スペイン)
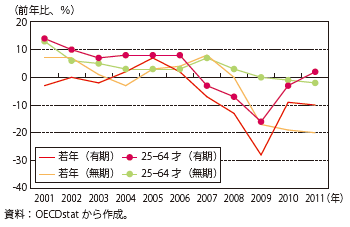
(2)正規・非正規の格差是正及び解雇規制の緩和
スペインの失業率を大きく悪化させた要因としてまず挙げられるのは、正規雇用労働者に対する手厚い保護である。
従来、同国では、高い解雇補償金によって、正規雇用労働者の解雇は理由を問わず高いコストを必要とした。さらに解雇を正当化する定義が不明確であり、解雇の多くがより多額の解雇補償金を必要とする不当解雇として扱われ50、企業にとって正規雇用労働者の解雇は非常にハードルが高いものであった。
一方、有期雇用労働者に関する解雇補償金は正規雇用労働者よりも低く51、賃金水準は低い(第Ⅱ-1-1-45図)。企業は正規雇用労働者を採用することによるコスト増を回避するため、新規雇用の際には主に有期雇用契約を採用した52。その結果、2000年代前半の有期雇用割合は、若年労働者を中心に他国に比べ10%以上高い水準で推移した(第Ⅱ-1-1-46図)。
第Ⅱ-1-1-45図 スペインの平均賃金(雇用形態別)
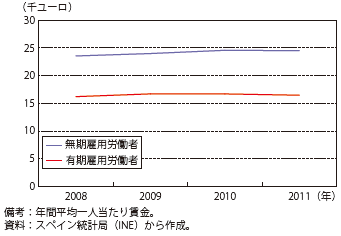
第Ⅱ-1-1-46図 有期雇用比率
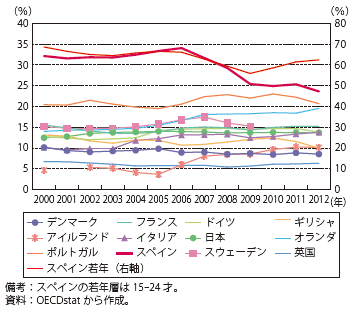
欧州債務危機によって経済活動が縮小する中、労働力の調整は、有期雇用労働者の解雇又は契約終了が中心となり、有期雇用労働者の失業が急増することとなった。
スペイン政府は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇における格差が、有期雇用契約の増加を通じ失業増大の要因となったとの認識に基づき、2011年以降の労働市場改革において、有期雇用契約締結による企業にとっての利点の軽減を図った53。
また、経済的理由による解雇を正当化するための定義について「3四半期連続の減収」等明確化し54、さらに無期雇用労働者の解雇が不当と判定された場合の補償金支払額を削減55することで、正規雇用労働者の解雇費用の軽減を図った。
50 厚生労働省(2011a)。
51 厚生労働省(2011a)。
52 村田(2011)。
53 有期雇用契約の解雇補償金を段階的に引上げ(2011年より)、契約期間の上限を2年に設定した上で上限を超えた場合には無期契約を締結したものとみなすこととなった(2012年)。(Clauwaert, Schömann (2013))。
54 JETRO(2012a)。
55 勤続1年あたり給与45日分から33日分へ、最大42か月分から最大24か月分へ削減した(Clauwaert, Schömann (2013))。
(3)賃金調整の柔軟化
スペインにおける失業率悪化の要因としては、賃金の硬直性が挙げられる(図Ⅱ-1-1-25(前掲)、図Ⅱ-1-1-26(前掲))。
同国では、産業別の労働協約により賃金調整が規制され、企業は、業績が悪くても賃金を下げることができなかった。
雇用悪化の背景に賃金調整の硬直性があるとの認識に基づき、2011年以降、労働協約の改革が行われた。
企業は、2四半期以上の減収があった場合には、地域や産業別の労働協約から逸脱して企業レベルで賃金や労働時間等について調整することが可能となった56。2013年12月時点で逸脱を行った労働協約の対象となった被雇用者は全体の1.2%にとどまるが、そのうち64%(労働協約数ベースで90%)が賃金に関する逸脱であった57。
また、企業内協約は地域・産業別の集団労働協約を遵守することが義務づけられていたが、改革によって、従来の位置関係が逆転し、企業内協約が集団労働協約よりも優先することになり、企業は集団労働協約の内容に拘束されることなく、独自に賃金や労働時間、企業内の人事異動等を含む労働条件について労働協約を締結することができるようになった58。
労働者カバー率は産業別の集団労働協約の比重が大きく、企業レベルの割合は10%に満たないが(第Ⅱ-1-1-47図)、新たな枠組みの下、企業レベルの労働協約が拡大し賃金調整の柔軟化が進むことが期待されている。なお労働協約による労働者カバー率は、従来70%を超えて推移していたが、2012年に低下した(第Ⅱ-1-1-48図)。
第Ⅱ-1-1-47図 スペインの労働協約のタイプ別割合
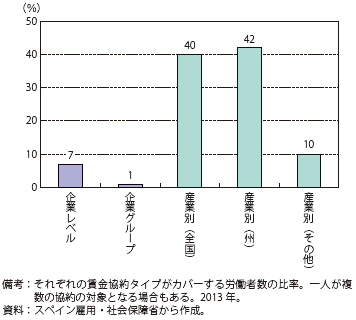
第Ⅱ-1-1-48図 スペインの労働協約カバー率推移
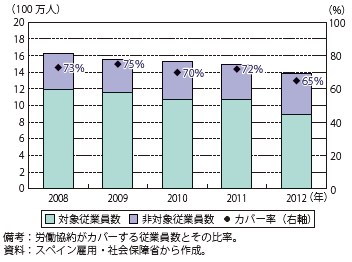
56 JETRO(2012a)、Clauwaert, Schömann(2013)。
57 スペイン雇用・社会保障省統計より。
58 Clauwaert, Schömann (2013).
(4)労働時間規制の緩和
スペインでは労働時間についても労働協約の拘束力が強く、企業は柔軟に労働時間を調整することが困難であった。そのため、企業は労働力の調整を有期雇用労働者の契約終了に頼ることとなり、これが欧州債務危機における失業者の大幅な増大の一因となった。雇用が悪化した2009年以降に、一人当たりの年間労働時間が増加していることからも、労働時間の短縮よりも有期雇用労働者の解雇又は契約終了が選択される傾向があったことがうかがえる(第Ⅱ-1-1-30図(前掲))。
そのような中、2012年には労働時間の柔軟化が図られ、企業は、年間労働時間のうち5%までを原則自由に変更することができるようになった。また、一時的な労働時間の短縮や一時帰休といった雇用調整については、従来必要とされていた自治州当局による承認が不要となり、労使合意のみで行えるようになった59,60。
オランダでは、1990年代に一人当たり労働時間の短縮によって雇用が増加している(第Ⅱ-1-1-49図)。スペインにおいても、規制緩和によって雇用が増加する可能性はあるが、パートタイム労働比率が高いことが必ずしも雇用の改善につながるわけではない(第Ⅱ-1-1-50図)。
第Ⅱ-1-1-49図 一人当たり労働時間と就労者数の推移(オランダ)
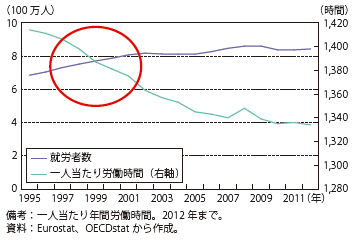
第Ⅱ-1-1-50図 OECD加盟国の長期失業率とパート比率
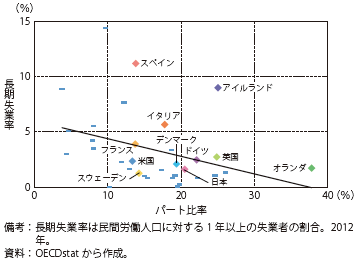
スペインをはじめとして南欧諸国では、世界経済危機以降、有期雇用労働者とフルタイム労働者が減少した一方で、パートタイム労働者は増加している(第Ⅱ-1-1-51図、第Ⅱ-1-1-52図)。中でも、非自主的なパートタイム労働者が大幅に増加している61ことから、フルタイム労働がパートタイム労働に置き換えられた可能性がある。
第Ⅱ-1-1-51図 スペインの労働者数推移(雇用形態別)
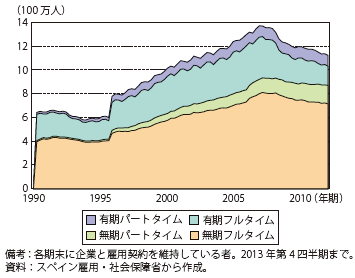
第Ⅱ-1-1-52図 2008-2012年の雇用形態別割合の増減
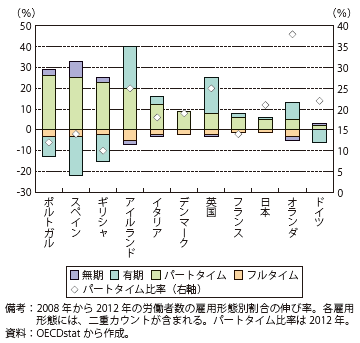
59 JETRO(2012a、2012b)。
60 また、パートタイム労働者には、従来残業が認められていなかったが、同契約利用における柔軟性の向上による雇用の促進のため、政府は、2012年から2013年にかけて、パートタイム労働者の残業を可能にし、2013年には残業時間の上限を引き上げるとともに残業の事前予告期間を短縮することで、柔軟な労働時間の配分を可能にした(JETRO(2014))。
61 Eurostat。
(5)積極的労働市場政策・若年雇用の強化
積極的労働市場政策費用について見ると、スペインの水準は欧州の中では中程度であり、また、雇用促進のための費用は、緊縮財政を背景に2011年以降落ち込んでいたが、若年失業者の増大を背景に、様々な労働政策を打ち出している。
その内容は、若者や長期失業者の雇用に際し事業主の社会保険料を減免する等の雇用インセンティブ、公的雇用サービス機関の効率化と強化(地方と中央の連携構築、地方機関への予算配分の基準となる指標(効率性など)の構築、ジョブマッチングデータベースの構築、職業訓練制度の拡充(情報通信技術、外国語など市場の要請に応える人材育成、ドイツと同様の若者向け職業訓練制度(デュアルシステム)の導入、職業体験機会の拡充等)、失業給付等受給者に対する就職活動やエンプロイアビリティ向上に向けた活動の義務化、失業者の起業支援(減税、失業給付の継続等))と幅広い68。
また、若年雇用に重点が置かれており、2012年の若年雇用対策としての費用69は286百万ユーロであったが、2013年3月に発表された「若者の雇用と起業のための戦略」では、2016年までに年間平均871百万ユーロの支出が予定されている。また若年雇用対策を含む雇用促進のための予算は2014年に増加しており、国の予算総額が前年に比べ3%増にとどまるのに対し、25%の増加となっている70(第Ⅱ-1-1-53図)。
第Ⅱ-1-1-53図 スペインの予算額推移
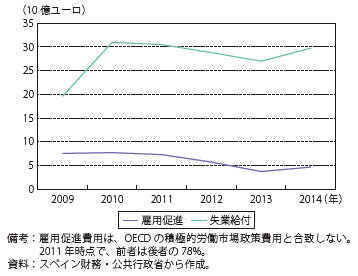
第Ⅱ-1-1-5図 (再掲) スペインの労働政策指標

68 スペイン政府(2013)、スペイン雇用・社会保障省(MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL)(2013)。
69 ESF(欧州社会基金)からの支出。
70 スペイン財務・行政省統計。
(6)労働市場改革の効果
以上に述べた労働市場改革の効果は、スペインの輸出拠点としての評価などに表れている。2011年以降、輸出単価の伸びは多くの国に比べて抑制され、輸出数量は、多くの国において大幅な低下が見られる中で小幅な低下にとどまった(第Ⅱ-1-1-54図、第Ⅱ-1-1-55図)。欧州委員会の製造業企業に対するアンケート調査によれば、競争力が改善していると回答する割合が、スペインでは2011年以降大幅に増加している71(第Ⅱ-1-1-56図)。
第Ⅱ-1-1-54図 欧州主要国の輸出単価指数の推移
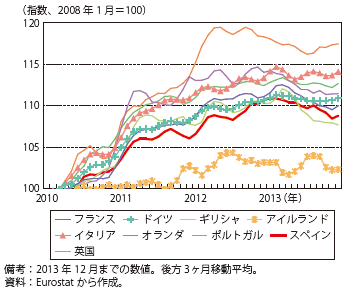
第Ⅱ-1-1-55図 欧州主要国の輸出数量指数の推移
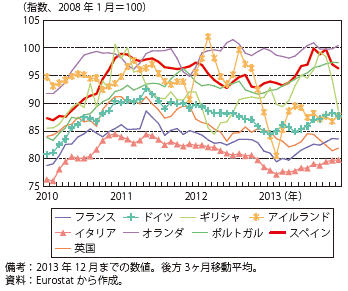
第Ⅱ-1-1-56図 EU域外における企業競争力(欧州委員会景況感調査)
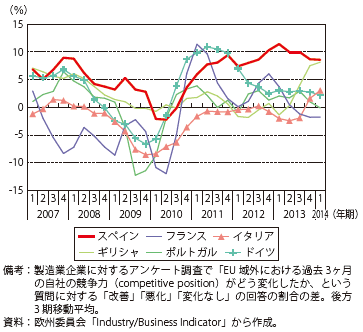
また、対内直接投資が増加している(第Ⅱ-1-1-57図)。世界経済の回復等も背景にある一方、スペインの賃金や解雇に関する規制が緩和されるなど労働市場改革の進展を理由とした投資事例も見られる。
第Ⅱ-1-1-57図 スペイン向け海外直接投資残高
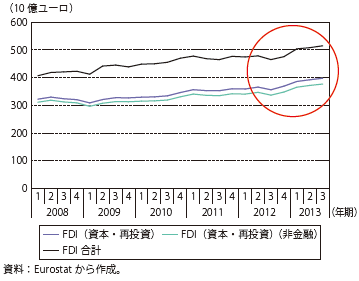
労働者数は、建設業と工業で減少が続いており、全体でもまだ増加に至っていない(第Ⅱ-1-1-58図)ものの、労働市場の柔軟性が高まることで、今後企業活動が拡大し、中長期的に雇用が回復することが期待される。
第Ⅱ-1-1-58図 スペインの労働者数推移(産業別)
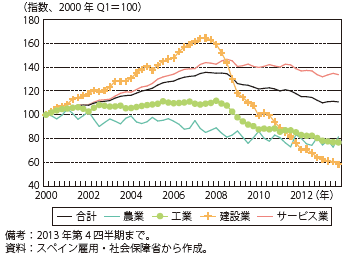
71 欧州委員会Industry/Business Indicatorより。