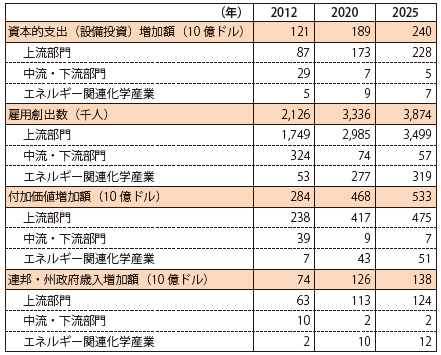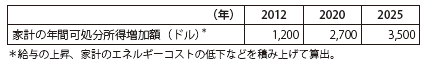第2節 米国における製造業・国内回帰の動きとシェール革命の影響
1.世界経済危機以降の米国経済
米国はサブプライム住宅ローン問題等から2007年12月に景気後退入りし、翌2008年9月には投資銀行のリーマン・ブラザーズが破綻する等、深刻な経済危機に陥った。危機さなかの2009年1月に就任したオバマ大統領は、ブッシュ前政権下の2008年10月に成立した「不良資産救済プログラム」(TARP:Troubled Assets Relief Program)に基づき、公的資金注入による自動車業界の救済等、政権発足直後から積極的な危機対策に取り組んだ。また、2009年2月に「米国再生・再投資法」(American Recovery and Reinvestment Act of 2009、以下「ARRA」と表す)を成立させ、過去最大規模の景気対策に着手した。ARRAにおいては、勤労世帯税額控除、失業保険給付期間延長等に加え、長期的な視点から経済成長や雇用創出を促進するための投資を行うこととされた72。
このように迅速かつ大規模な金融・経済対策が功(こう)を奏したこともあり73、米国では2009年6月に18か月にわたった景気後退期を脱出した74。
第Ⅱ-1-2-1図は、米国が景気後退期入りした2007年第4四半期を100として実質GDPの推移を先進国・地域、新興国別に見たものである。先進国の中では、米国はドイツと並んで、いち早く実質GDPを危機前の水準まで回復させていることが分かる75。他方、新興国を見ると、インドやインドネシアでは、世界経済危機時における景気後退は余り見られず、その他の国では同時期に景気の減速が見られるものの、その後の回復ペースは米国を大きく上回っている。
第Ⅱ-1-2-1図 米国の景気後退期の実質GDPの推移(左:先進国・地域、右:新興国)
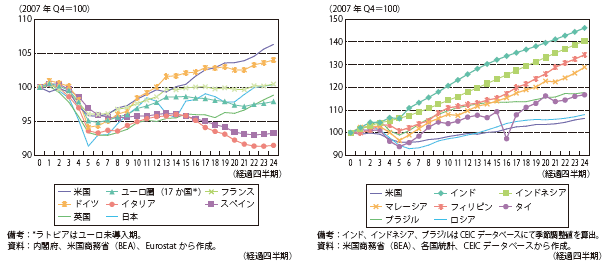
米国では2011年第2四半期に実質GDPが景気後退前の水準まで回復した。過去の景気後退時と比べると、実質GDP、雇用者数ともに落ち込み幅が大きく、景気後退前の水準に回復するまでの期間も長くなっている76。非農業部門雇用者数はいまだ景気後退前の水準に回復するに至っていない77(第Ⅱ-1-2-2図)。
第Ⅱ-1-2-2図 景気後退期からの回復推移の比較(左:実質GDP、右:雇用者数)
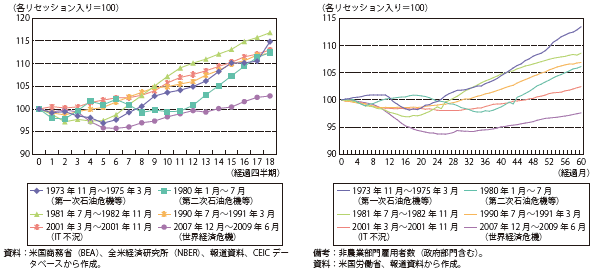
実質GDPを需要項目別に見ると、個人消費、輸出入は景気後退前の水準を回復し、その後も伸びている。他方、住宅投資は2010年第3四半期に底を打ち、その後回復傾向にあるものの、依然として景気後退前の水準を大きく下回っており、他項目と比較してもその回復の弱さが目立っている。設備投資は2013年第4四半期にようやく景気後退前の水準まで回復した(第Ⅱ-1-2-3図)。
第Ⅱ-1-2-3図 需要項目別実質GDPの推移
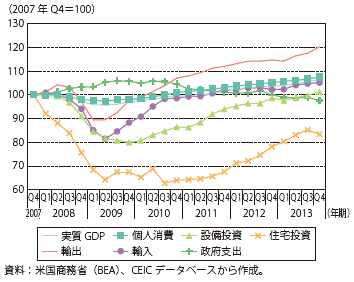
実質GDPを産業別に見ると、シェールガス・オイルによる効果等を背景として、鉱業の伸びがめざましい一方、建設業では回復に遅れが見られる。卸売業も、景気後退前の水準にいまだ回復していない(第Ⅱ-1-2-4図)。
第Ⅱ-1-2-4図 産業別実質GDPの推移
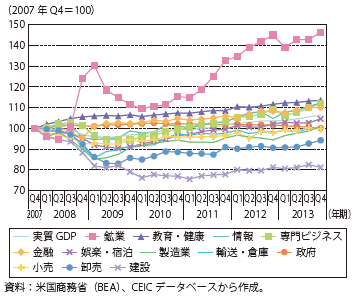
次に雇用者数について産業別に見ると、シェールガス・オイルによる効果等を背景として、石油・ガス掘削業では景気後退期に落ち込むこともなく、雇用者数を大きく伸ばし続けている。また、教育・健康も底堅く推移している。他方、建設業、製造業等では、雇用者数が大きく減っており、2014年4月時点でも景気後退前の水準を大きく下回っている(第Ⅱ-1-2-5図)。
第Ⅱ-1-2-5図 産業別雇用者数の推移
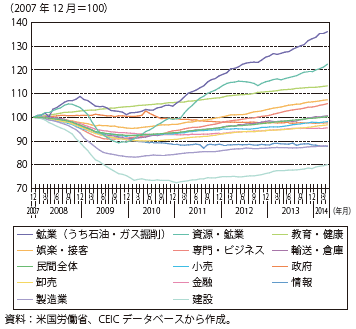
オバマ政権は危機を克服していく過程において、質の高い雇用の創出を通じて中間層を強化することを最優先課題として位置づけ、その中で製造業重視の姿勢を強く打ち出している。
以下ではまず、米国における製造業の最近の動向について見ていく。
72 インフラ・科学、クリーンエネルギー、医療、教育分野等。詳細は通商白書2009第1章第2節1.バランスシート調整に直面する米国経済?米国の経済・金融問題への対応参照。
73 大統領経済報告(2014)においてARRAは、雇用や生産に大きなプラスの効果をもたらしたと指摘されている。ARRA単独の効果として、2009年末から2011年半ばまでにGDP水準を2から2.5%押し上げ、更にARRAとその後の景気安定財政策の効果を合わせると、2009年から2012年で、2008年第4四半期のGDPの9.5%に相当する押し上げ累積効果があったと推計している。また、短期的なマクロ経済効果のみならず、クリーンエネルギー、教育、健康管理、インフラ分野への投資を行うことでARRA終了後も長期にわたり経済成長をもたらすと分析している。
74 2010年9月、米経済研究所(NBER)の発表による。
75 大統領経済報告(2014)でも、2007年、2008年に金融危機を経験した12か国のうち、生産年齢人口一人当たりの生産量が危機前の水準を回復したのは米国とドイツのみと報告されている。
76 大統領経済報告(2014)によると、米国の実質GDP潜在成長率は1953年第2四半期から2007年第4四半期までは平均3.3%であったが、2013年第3四半期から2024年第4四半期の潜在成長率見通しは2.3%とその水準が以前より下がっていることが指摘されている。
77 非農業部門雇用者数(政府部門含む)は足下の2014年4月時点で1億3,825万人と景気後退入りした2007年12月の1億3,835万人をいまだに下回っている。ただし、民間部門のみ見ると、1億1,638万人と2007年12月の1億1,597万人を上回っている。
2.米国製造業を巡る動向
(1)製造業重視
オバマ大統領は、就任当初より、イノベーションの推進と力強い中間層の実現による良質な雇用創出の鍵として、製造業を重視してきた。
製造業が昨今見直されている理由として、①製造業の賃金水準は他産業の同程度の職と比較して高水準であり、特に十分に教育を受けていない層に対して質の高い雇用を提供し、力強い中間層を維持する観点から重要であること78、②製造業の生産活動は他の経済主体にプラスの波及効果を及ぼすため、喪失することで経済的・社会的な利益を失う恐れがあること79、③米国では民間部門の研究開発の7割は製造業で行われており、製造業の衰退によりイノベーションを喚起する土壌が失われ、イノベーションの衰退につながるおそれがあること等が挙げられる(第Ⅱ-1-2-6図)。
第Ⅱ-1-2-6図 製造業が占める研究開発費の割合(民間部門、2011年)
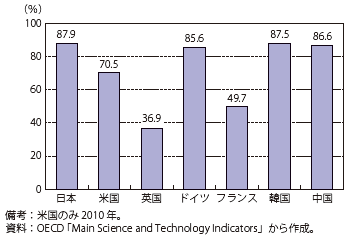
世界全体の名目付加価値に占める国別シェアを見ると、サービス業については、米国は、2000年代に低下してきているが、依然として最大のシェアを維持している。他方、製造業については、2010年に中国に抜かれている(第Ⅱ-1-2-7図)。
第Ⅱ-1-2-7図 世界全体に占める名目付加価値の各国シェアの推移(左:サービス業、右:製造業)
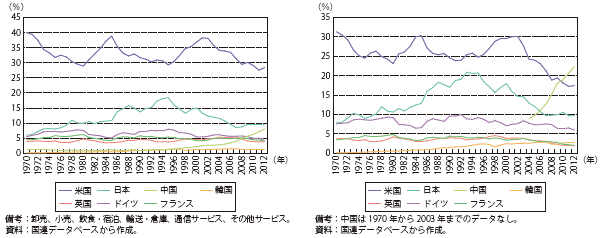
このような情勢の下、製造業重視の姿勢が明確に現れた2012年の一般教書演説では、「製造業を米国内に戻すには今が大きなチャンスである」と述べられており、翌2013年の一般教書演説にも、米国を製造業と雇用をひきつける磁石にするための税制改正等、国内事業環境整備に取り組む必要性を述べ、引き続き製造業の重要性を訴えている80。
オバマ政権は,製造業復権の視点として、①海外に展開している米国企業の製造拠点の国内回帰(リショアリング)の奨励、②3Dプリンターの活用等による高い付加価値をもった先端製造業(Advanced Manufacturing)の育成の二つの方向性を掲げている。以下では、製造拠点の国内回帰(リショアリング)について見ていく。
78 大統領経済報告(2013)において、教育水準、年齢、性別、人種等の諸条件を調整すると、製造業の雇用者報酬は他産業より14%高いとされている。
79 政府機関のAdvanced Manufacturing National Program Officeによると、製造活動は他のどの主要経済活動よりも波及効果が大きく、製造業へ1ドル投入すると、その他経済活動にて追加的に1.35ドルを生み出すとしている。http://www.manufacturing.gov/mfg_in_context.html![]()
80 具体策は2013年2月ホワイトハウスFact Sheet参照。15の製造業イノベーション拠点の全国ネットワーク構築(1回限り10億ドル)、製造業法人税率を25%へ引き下げ、研究開発税額控除の拡大・恒久化、製造業の地域誘致支援1億1,300万ドル等の予算規模と提案が盛り込まれている。
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/13/fact-sheet-president-s-plan-make-america-magnet-jobs-investing-manufactu![]()
(2)製造拠点の国内回帰(リショアリング)
2011年8月にボストンコンサルティンググループ(BCG)により“Made in America, Again -Why Manufacturing Will Return to the U.S.”が発表された。この中で、米国と中国の生産コストの差が縮小することにより、現在中国にアウトソーシングされている北米市場向け製品の生産拠点の米国回帰が予測されるとの分析がなされ、5年以内には実質的に生産コストの差が10%から15%程度になる81との結果を示し、注目を集めた82。
以下では、リショアリングを促す要因として指摘されている事業環境の変化のうち、賃金コスト、輸送コスト、エネルギーコスト、その他のコストについて見るとともに、リショアリングの動きを受けて、米国経済における製造業の位置付けに実際に変化の兆しが現れているかどうか、マクロ的な視点から見ていく。
81 同じくBCGにより2013年8月に発表されたレポートによると、2015年の生産コストの差は米国を100とすると中国は95と、更に差が縮まるとの分析がなされている。
82 一方、リショアリングへの懐疑的見方も存在する。Goldman Sachsの主席エコノミストJan Hatzius(2013)は、米国の製造業拠点が戻ってくるとする「製造業ルネッサンス」は循環的なもので、構造的なものではないと指摘している。また、IMF(2014)も、世界経済危機以降の米国製造業の回復は著しいと認めてはいるが、成長の主エンジンになるとは見ておらず、「製造業ルネッサンス」は認められないとしている。
①事業環境の変化
a.賃金コスト
米国の国内市場向け製品の主要アウトソーシング先である中国における製造業の年平均賃金(ドルベース)は、米国約37,690ドルに対して約6,600ドルと、足下の水準にはいまだ6倍近くの差がある。しかし中国の平均賃金は1999年から2012年の間、年平均約16%のペースで上昇しており、タイやメキシコと比べて高い水準となっている(第Ⅱ-1-2-8図)。製造業も含む全産業の賃金水準を省別に見ると、事業環境が整備され、外資による投資も活発に行われている地域の賃金は高水準となっており、中国で生産活動を行う際の賃金コストの相対的な優位性が低下してきている(第Ⅱ-1-2-9図)。
第Ⅱ-1-2-8図 中国製造業の年平均賃金と伸び率(対前年比)の推移
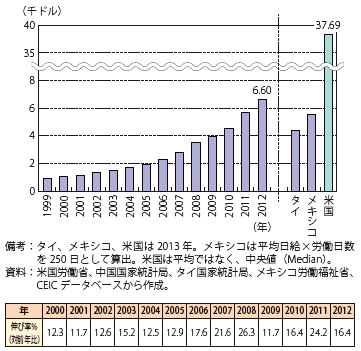
第Ⅱ-1-2-9図 中国の省別の年平均賃金推移(全産業、2012年)
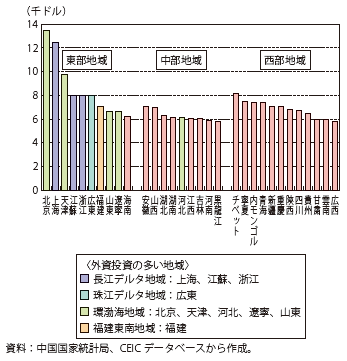
これに対して、米国では、時間当たりの雇用者報酬の伸びが先進国の中でも抑えられている。2000年には米国は賃金水準が最も高い位置に属していたが、2012年には中間程度の水準となっている(第Ⅱ-1-2-10図)。
第Ⅱ-1-2-10図 製造業における雇用者報酬の各国比較(ドル換算ベース)
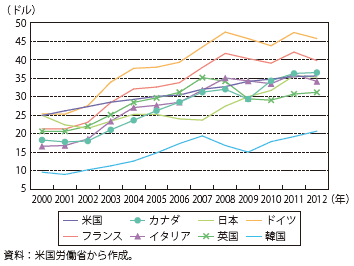
米国の雇用者報酬を地域別に見ると、ミシガン州(中西部)、オハイオ州(中西部)、テキサス州(南部)等で、低い水準となっており、特にこれらの地域でリショアリングの動きが見られている(第Ⅱ-1-2-11図)。
第Ⅱ-1-2-11図 米国の地域別時間当たりの雇用者報酬(2013年12月)
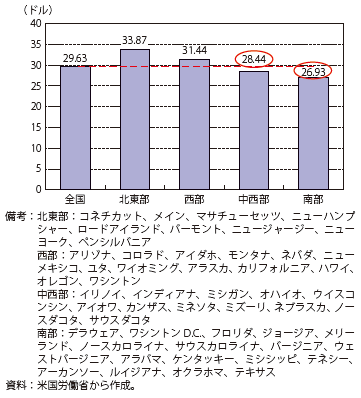
米国企業が為替の影響も含めて、どこにどのように事業展開を行うのが最も効率的かという立地戦略を考えるに当たり、この労働コストを取り巻く環境変化が、コスト面における米国の事業環境の優位性を高めつつある。
米国商務省(経済統計局)によると83、労働コスト(雇用者報酬)に労働生産性の視点を加えた単位労働コスト(一人当たり雇用者報酬/労働生産性、現地通貨ベース)は、米国では2000年から2011年の間に17%低下している一方、中国では同期間に85%上昇している(第Ⅱ-1-2-12図)。中国では、一人当たり雇用者報酬の伸びが労働生産性の伸びを上回り、生み出す付加価値当たりの労働コストが急速に増加している。さらに、第Ⅱ-1-2-12図は現地通貨ベースであり、為替の影響は考慮していないが、2010年半ば以降、対ドルレートでの人民元の値上がり(人民元高)を勘案すると、ドルベース換算では中国の単位労働コストは更に大きく上昇していることが想定される。
第Ⅱ-1-2-12図 製造業における単位労働コストの各国比較(現地通貨ベース、2000年=100)
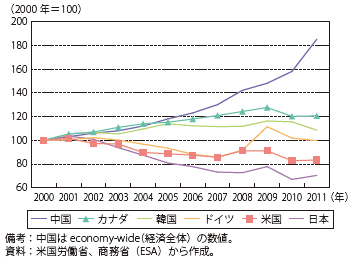
同期間の単位労働コストの水準は依然として米国の方が高いものの、その差は急速に縮まってきている(第Ⅱ-1-2-13図)。
第Ⅱ-1-2-13図 製造業における単位労働コストの水準(ドル換算ベース)
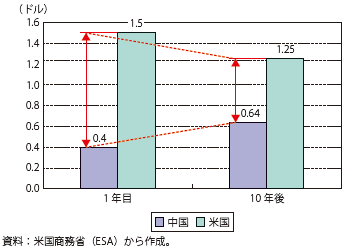
83 Langdon (2013) “Assess Costs Everywhere: Today’s Cheap Labor May Be More Costly Tomorrow”
http://www.esa.doc.gov/print/Blog/2013/04/22/assess-costs-everywhere-today%E2%80%99s-cheap-labor-may-be-more-costly-tomorrow![]()
b.輸送コスト
米国でリショアリングが検討され始めた2009年から2010年頃は、世界経済危機の影響で落ち込んだ北米向けのコンテナ輸送運賃が徐々に上昇し始めた時期と重なることもあり、中国で生産した製品の米国までの輸送コスト負担の増加が見られた(第Ⅱ-1-2-14図)。
第Ⅱ-1-2-14図 中国発コンテナ船の運賃指数の推移
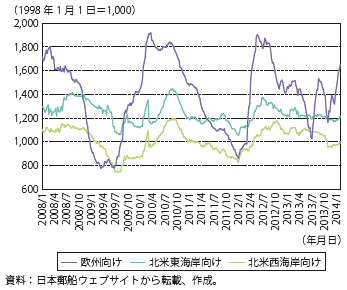
また、世界経済危機以降、高止まりしている原油価格も輸送コスト負担の増加を招く懸念要因となっている(第Ⅱ-1-2-15図)。
第Ⅱ-1-2-15図 WTI原油先物価格の推移
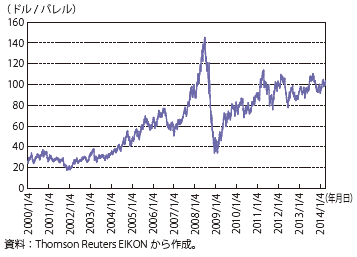
c.エネルギーコスト
米国ではシェールガス・オイルの採掘技術の進歩により生産コストが低下し、これまで採算上困難であったシェールガス・オイルの生産が商業ベースで可能となり、2000年代半ば以降開発が加速化した(「3.シェールガス・オイルの影響」参照)。生産量の拡大により米国の天然ガス価格は大きく低下し、国内における産業向けエネルギーコストが低下することとなった。
国際エネルギー機関(IEA)84は、米国の天然ガス取引価格は、EUの輸入価格の3分の1、日本の5分の1であり、また産業用電気料金も日本とEUは米国の2倍以上、中国も2倍程度高いと指摘している。こうしたエネルギー価格の地域差は今後縮小する見込みであるが、2035年においてもなお米国はエネルギーコスト面の優位性があると見込まれている(第Ⅱ-1-2-16図、第Ⅱ-1-2-17図)。
第Ⅱ-1-2-16図 2012年産業向けエネルギー価格(税込)
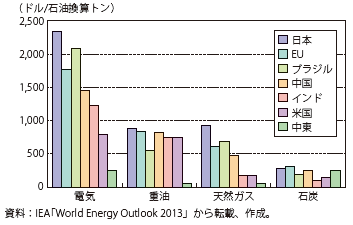
第Ⅱ-1-2-17図 産業向けエネルギー価格の対米国比
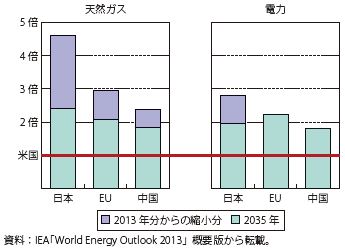
エネルギー価格の低下は、化学等のエネルギー集約型産業の国際競争力にとって有利である。IEAによれば、2035年にかけて、中国、インド等がエネルギー集約型製品の世界市場における輸出シェアを伸ばすと見込まれるが、EUや日本がシェアを低下させる一方、米国はシェアを維持すると見られている(第Ⅱ-1-2-18図)。
第Ⅱ-1-2-18図 エネルギー集約型製品の世界輸出市場シェアの推移
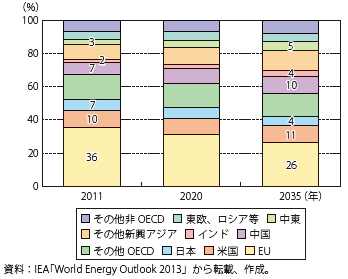
このようにシェールガス・オイルの生産増によるエネルギーや原材料コストの低下を通じて、化学、金属産業、セメント等、エネルギー集約型産業が米国内で価格競争力を拡大させる可能性がある。
84 IEA (2013)。
d.その他のコスト
オフショアリングによりコスト削減を目指す企業が増える中、当初期待したほどの効果が出ない場合があるが、その主な理由の一つは、米国外でのオペレーションに伴い現在及び将来に発生する「隠れたコスト」の存在の看過にあると指摘されている。「隠れたコスト」には直接的なコストと間接的なコスト、また、即座に生じるコストと時間の経過とともに明らかになるコストがある。さらに時間の経過ともに変化し、想定外のコストを誘発することもある。具体的には、第Ⅱ-1-2-19表のような事例が指摘されている85。
第Ⅱ-1-2-19表 「隠れたコスト」の例

また、製造拠点とR&D拠点とを切り離してオフショアリングを行う場合、コスト削減の観点のみならず、製造プロセスがイノベーションに及ぼす影響の重要度も考慮する必要があるとの見方が示された。その際、「自立度」と「成熟度」86の二要素から作成するマトリックスに着目し、製造プロセスとイノベーションが不可欠に結びついた場合には、製造部門のオフショアリングによりイノベーションが衰退するリスクが極めて大きく、製造部門を国内に維持することが必要としている87(第Ⅱ-1-2-20表)。
第Ⅱ-1-2-20表 自立度と成熟度のマトリックス
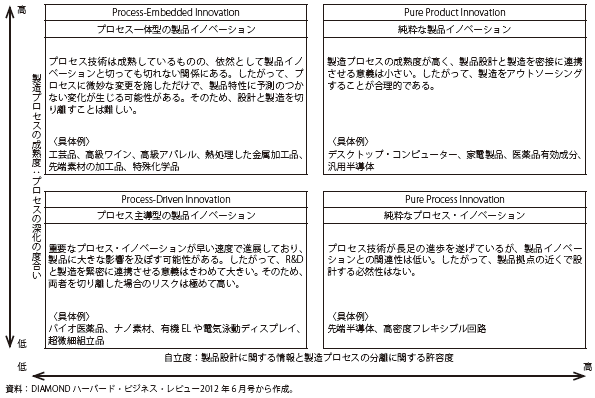
さらに、アウトソーシングを行うと、サプライヤー、技術を持った熟練労働者、オペレーションの経験があるマネージャー等製造活動に欠かせない「産業コモンズ(製造活動に必要な共有財産)」も同時に失われるため、一度海外にアウトソーシングした製造活動を国内に戻すリショアリングは、一筋縄ではいかないと指摘している。
このように「隠れたコスト」の存在や、製造プロセスとイノベーションの相互作用の重要性への認識が高まってきたことも、リショアリングの背景にあると見られる。
85 Porter & Rivkin(2012)。その中で、アーンスト・アンド・ヤングが2010年に行った調査「What lies beneath? –The hidden costs of entering rapid-growth markets」でも、こうした隠れたコストの存在が指摘されていることが紹介されている。
(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/CFO_Study_Master_series_What_lies_beneath/$FILE/CFO_Study_Master_series_What_lies_beneath.pdf![]() )
)
86 「自立度」とは、製品の研究開発・設計に関連する情報が製造プロセスと離れていても問題ないかどうかとの観点であり、他方「成熟度」とは製造のプロセス技術に改善の余地があるかどうかとの観点である。
87 Pisano & Shih(2012)。製造プロセスが製品イノベーションに及ぼす可能性を軽視し、単なるコスト・センターとして積極的に製造部門がアウトソーシングしたことで、米企業のイノベーション能力が損なわれ、将来的に有望視されている環境技術やエネルギー、バイオテック、航空宇宙、ハイテク医療機器等の分野において、現在、米国の優位性が脅かされていると指摘している。
e.事業環境の変化を受けた企業行動
ボストンコンサルティンググループ(BCG)が2013年8月、米国に拠点を有する売上高10億ドル以上の製造業企業の幹部を対象に実施した調査88によると、「中国からの製造拠点の移転を計画、または実際に検討している」との回答は54%と、前回調査89(2012年2月)時の37%を上回った。また、現在、米国へ生産をシフトしている最中、または2年以内に米国へ生産をシフトするとの回答は21%と、前回調査時の約2倍となった。
将来の生産拠点の立地決定において重視するのは、①労働コスト(43%)、②顧客への近接(35%)、③製品の品質(34%)が多く、回答者の80%以上が少なくともこのうち1つを鍵となる要素として重視している。その他としては、熟練労働者の存在、輸送コスト、整ったビジネス環境等が挙げられている(第Ⅱ-1-2-21図)。
第Ⅱ-1-2-21図 米国製造業企業幹部のリショアリングに対する見方
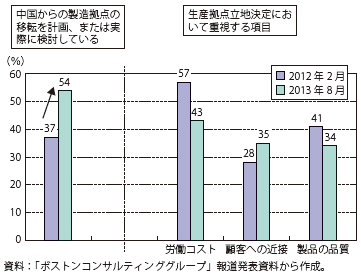
具体的なリショアリングの事例を見ると、主な理由として、中国における労働コストの上昇や米国におけるシェールガス・オイル生産のような事業環境の変化のみならず、米国の高い技術力を持つ豊富な労働力や、世界の主要市場である米国消費者への近接等を目的としたものも見られる(第Ⅱ-1-2-22表)。
第Ⅱ-1-2-22表 米国企業によるリショアリング、国内投資事例
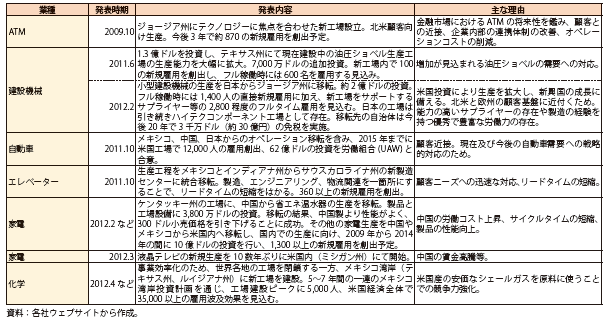
また、シェールガス・オイル増産や米国の将来性を目的にした米国以外の国の企業による米国への拠点新設・増強の事例も見られる(第Ⅱ-1-2-23表)。
第Ⅱ-1-2-23表 米国以外の企業による米国投資事例
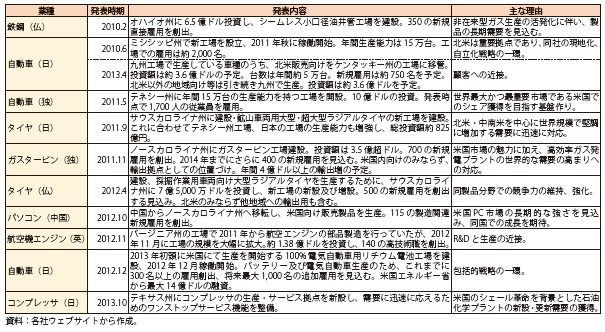
88 BCG Press Release(2013年9月24)
http://www.bcg.com/media/pressreleasedetails.aspx?id=tcm:12-144944![]() 。
。
89 BCG Press Release(2012年4月20日)
http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-104216![]() 。
。
②米国経済における製造業の位置付け
a.GDPと雇用者数
名目GDPに占める産業別シェアの推移を見ると、製造業は、1990年代以降漸減傾向にあったが、2009年を境に下げ止まりが見られる(第Ⅱ-1-2-24図)。
第Ⅱ-1-2-24図 名目GDPに占める産業別シェアの推移
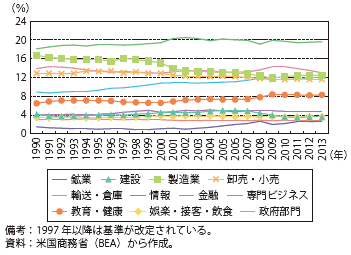
他方、雇用者数のシェアを見ると、製造業は1990年代以降減少傾向にあったが、2009年以降、ほぼ横ばいになっている(第Ⅱ-1-2-25図)。
第Ⅱ-1-2-25図 雇用者数に占める産業別シェアの推移
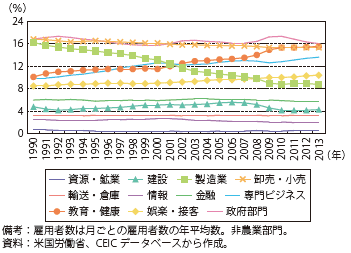
製造業の名目GDPに占める業種別シェアを見ると、化学製品や石油・石炭製品等で上昇している(第Ⅱ-1-2-26図)。
第Ⅱ-1-2-26図 製造業の名目GDPに占める業種別シェアの推移
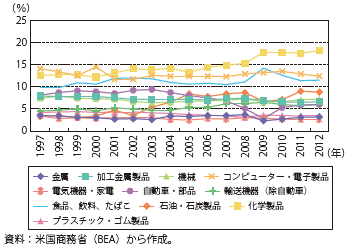
このようにシェールガス・オイルのプラスの影響が期待される化学産業等における事業活動の活発化に伴い、関連分野への投資の増加も見込まれるが、労働コストを抑え、オートメーション化が進むことで、雇用が限定される傾向が見られること等から、リショアリングによる雇用創出効果はそれほど大きくならない可能性もある90。
90 西川(2013)によると、名目GDPに占める製造業のシェアの下げ止まりは構造的な変化の兆しとも言えるが、この背景には製造業デフレーターの下落傾向(製造業デフレ)の終息がある。製造業デフレの終息の背景には、労働分配率の低下(雇用者報酬の抑制)と単位労働コストの下落率縮小(労働生産性の上昇率の低下)があり、雇用・所得の改善という好循環につながりにくく、米国全体の持続的な成長力の観点からも懸念材料であると指摘している。
b.鉱工業生産指数
鉱工業生産指数の推移を見ると、鉱業はシェールガス・オイルの影響で大きく上昇している。製造業は世界経済危機により大きく落ち込んだ後、上昇を続けているが、2014年3月時点で、世界経済危機前の2007年の水準まで回復していない。
業種別にみると、コンピューター・電子製品、自動車・部品等で上昇が目立つ一方、シェールガス・オイルのプラスの影響が期待される化学では、前述の名目GDPシェアとは異なり、まだ回復基調は見られない(第Ⅱ-1-2-27図)。
第Ⅱ-1-2-27図 鉱工業生産指数の推移(左:主要業種、右:主要製造業)
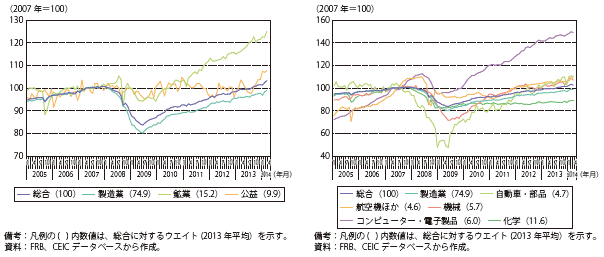
c.対内外直接投資
対内・対外直接投資のネット額の推移を見ると、全産業では、対外直接投資が対内直接投資を上回る資本流出超の構造となっている。他方、製造業では2013年は18.7億ドルの流出超になったものの、2005年以降、対内直接投資が対外直接投資を上回る資本流入超の状況が続いていた(第Ⅱ-1-2-28図)。
第Ⅱ-1-2-28図 対内・対外直接投資のネット額の推移
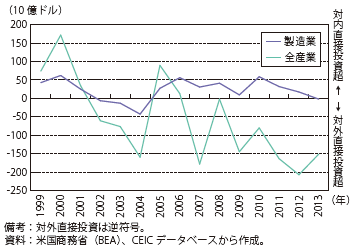
業種別に見ると、シェールガス・オイルのプラスの影響が期待される化学で増加傾向となっている(第Ⅱ-1-2-29図)。
第Ⅱ-1-2-29図 対内・対外直接投資額(主要製造業)の推移
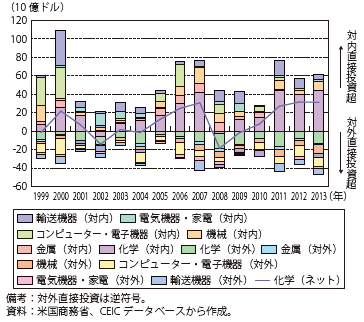
また、中国向け対外直接投資額を見ると、リショアリングが検討され始めた2009年以降も米国から中国製造業への直接投資は増加傾向にある(第Ⅱ-1-2-30図)。
第Ⅱ-1-2-30図 米国の中国向け対外直接投資額(製造業)
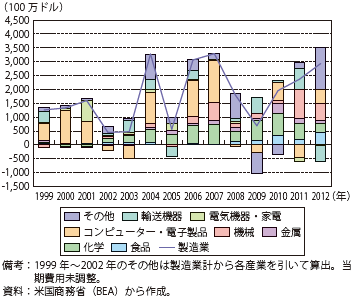
d.貿易収支
貿易収支の動向を見ると、赤字額が足下で縮小傾向にある。月別の貿易赤字が近年のピークであった2012年1月と足下の2014年2月を比較すると、輸出は6.1%増の一方、輸入は0.6%増となっている(第Ⅱ-1-2-31図)。そのうち、工業用原材料の貿易赤字額が近年低下傾向にある(第Ⅱ-1-2-32図)。
第Ⅱ-1-2-31図 米国の貿易収支の推移
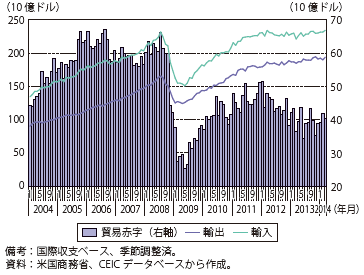
第Ⅱ-1-2-32図 米国の財貿易赤字の推移
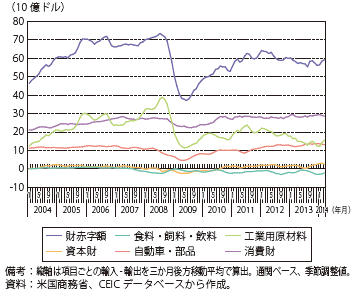
工業用原材料のうち、2000年1月から2014年2月までの輸出額の伸びが大きい上位4財は、燃料油、天然ガス、石油製品、LNG(液化天然ガス)である一方、これらの財の輸入額は縮小傾向にあり、シェールガス・オイルの生産増による影響が見られ始めている(第Ⅱ-1-2-33図)。
第Ⅱ-1-2-33図 主要工業用原材料の貿易推移(左:輸出、右:輸入)
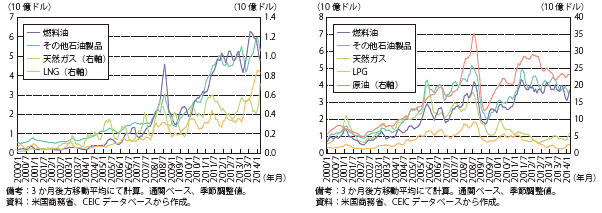
e.労働コスト
米国の時間当たり実質賃金の推移を見ると、製造業(全雇用者)では、全民間産業(全雇用者)よりも高い水準にあるが、世界経済危機後は差が縮まりつつある。
一方、製造業(生産現場雇用者)の賃金水準は大きく低下傾向にあり、2006年に全民間産業(非管理職)と水準が逆転した後、その差が開く傾向にある(第Ⅱ-1-2-34図)。
第Ⅱ-1-2-34図 米国の時間当たり実質賃金の推移(左:全雇用者、右:生産現場雇用者・非管理職)
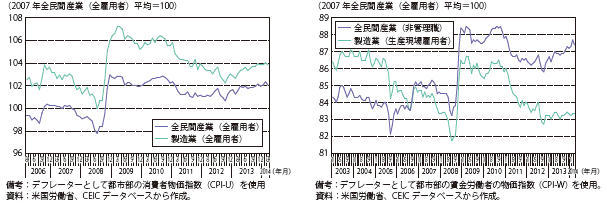
こうした背景には、労働権法(RTW法)の導入91によるバーゲニング・パワーの低下や二段階賃金方式(Tier Wage System)の導入92もあると見られ、現場雇用者の賃上げよりも雇用確保が優先されている状況がうかがえる。
一度海外にアウトソースした仕事を米国内に戻すリショアリングでは、米国内の雇用者に対して、従来より低い賃金水準の設定や年金、医療費等を削減する例が見られる。
例えば、ある航空機メーカーは、次世代機の製造を米国内で行うと表明した。これにより数万人の雇用創出が見込まれる一方、従業員の年金契約を確定給付型から確定拠出型に変更し、企業側の負担を削減することで労働組合と合意した。また、米国内への生産移転を行った建設機械メーカーは、給与水準の高い熟練労働者の昇給凍結、確定給付型年金制度の廃止、医療費の従業員負担率の引上げを含む新たな賃金契約を労働組合と合意した。
このように賃金水準や企業負担を抑えることで、利益の確保を図る企業戦略が「雇用か賃金か」の選択を迫るような例も見られる。
また、単位労働コストについては、「①事業環境の変化」で前述したように、中国との格差が縮まっており、米国における労働コストを取り巻く環境が改善していると見られている。
そこで、製造業における単位労働コストを一人当たり雇用者報酬と労働生産性で要因分解したところ、2007年までは、一人当たり雇用者報酬の伸びを上回る労働生産性の伸びにより、単位労働コストは下落が続いていたが、近年、一人当たり雇用者報酬の伸びの抑制にもかかわらず、労働生産性の伸びが停滞していることにより、単位労働コストに上昇傾向が見られる(第Ⅱ-1-2-35図)。
第Ⅱ-1-2-35図 製造業における単位労働コストの変化率(対前年比)の要因分解
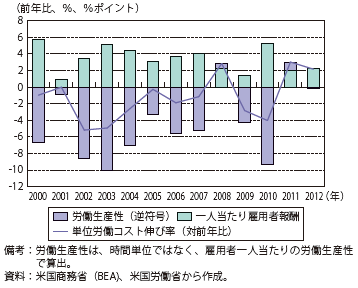
91 Right To Work Law(RTW法)は、雇用条件として労働組合への加入を義務付けることを禁ずるとともに、全従業員からの強制的な組合費徴収を違法と定めた法律。労働組合に加入しない権利を労働者に認めるものであるが、米国労働省データによると、労働組合非加入者の賃金水準は加入者に比べて2割程度低い。
92 今後新たに雇用する従業員に対する時給水準を従前の従業員よりも低く設定する方式。
f.米国経済のマクロ的視点から見た製造業の現状
これまで見てきたように、米国においては、中国における賃金上昇を受けた単位労働コストの差の縮小、シェールガス・オイルの産出等の事業環境の好転、顧客との近接による顧客ニーズへの迅速な対応の必要性等を背景として、過去にアウトソーシングしてきた製造拠点のうち、主に米国顧客向けの生産を米国内に戻すリショアリングが注目されている。
他方、製造業を取り巻くマクロ的な経済指標を見ると、名目GDPに占める製造業の割合に下げ止まりが見られること、対内直接投資の対象としてシェールガス・オイルの効果が期待できる化学産業等への投資が活発なこと、貿易収支赤字が縮小傾向にあること等、シェールガス・オイルの生産増による影響が一部見られ始めているが、鉱工業生産においては顕著な回復基調は見られていない等、その影響は限定的なものにとどまっており、製造業の復権と言えるほどの構造的な変化は現時点では見られていない。
さらに雇用情勢についても、大きな改善・回復は現時点では見られず、足下で労働生産性の伸びの停滞による単位労働コストの上昇も見られる等、質の高い雇用の創出は引き続き課題となっている。
3.シェールガス・オイルの影響
(1)シェールガス・オイル生産と貿易収支
米国では、シェールと呼ばれる頁岩(けつがん)層から天然ガスや原油を採掘する技術が進歩したことで、これまで採算がとれなかったシェールガスやシェールオイル等の非在来型資源の採掘が本格化している。
天然ガスについては、在来型ガスの生産が減少する一方、非在来型であるシェールガス等の生産が拡大し、2006年以降生産の増加が顕著になっており、2040年まで右肩上がりの増産が見込まれている。米国エネルギー情報局(EIA)によると、全生産に占めるシェールガスの割合は2012年時点で約40.4%だが、2040年には50%超まで大きく拡大する見通しである(第Ⅱ-1-2-36図)。
第Ⅱ-1-2-36図 米国の天然ガス生産量の推移と見通し
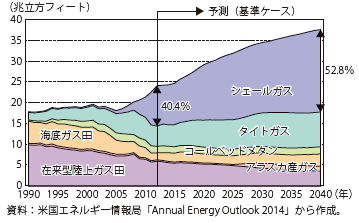
一方、生産が減少傾向にあった原油についても、シェールオイルを含むタイトオイルの増産により、2009年以降生産の拡大が見られるが、天然ガスとは異なり2019年の日量960万バレルの生産をピークにその後減少し、2040年時点では日量750万バレルの生産予測となっている。非在来型であるタイトオイルの生産は2021年に日量480万バレルでピークに達する見通しである(第Ⅱ-1-2-37図)。このようにシェール開発による天然ガス生産への影響は、原油生産に比べて非常に大きい。
第Ⅱ-1-2-37図 米国の原油生産量の推移と見通し
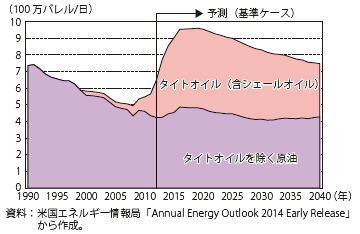
シェール開発による影響が大きい天然ガスについては、2018年を境に純輸出国になる見通しである。一方、石油等液体燃料については2040年時点でも輸入依存度は32.2%と、引き続き純輸入国であるものの、2005年の60.3%と比べると、輸入依存度は大きく低下すると見込まれている93(第Ⅱ-1-2-38図)。
第Ⅱ-1-2-38図 米国のエネルギーの国内供給量と消費量の推移と見通し(左:天然ガス、右:石油等液体燃料)
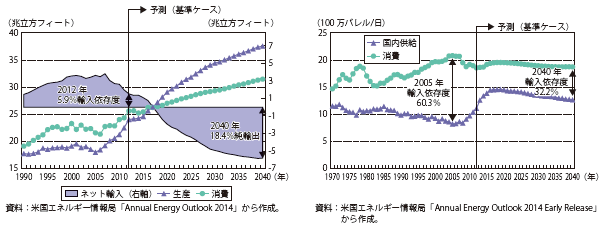
93 国際エネルギー機関(IEA)の見通し(2013年11月)においても、米国は2015年にもサウジアラビアとロシアを抜いて世界最大の産油国になり、2030年代前半まで(2035年には再度サウジアラビアが世界最大の産油国の見込み)その状況を維持しつつ原油の輸入依存度を減らすと予測されている。
(2)地域経済への影響
シェールガス・オイルの生産本格化に伴い、米国内ではエネルギーコストが相対的に低く抑えられており、リショアリングの一因として考えられている。また、このような大幅な生産の拡大を受け、シェールガス・オイルを巡る米国内の経済情勢にも変化が見られる。以下では、シェールガス・オイルの生産拡大の産出地域への影響について見ていく。
米国最大のバッケン鉱区を抱えるノースダコタ州、イーグルフォード、パーミアンベイシン等多くの鉱区が存在するテキサス州、マーセラス鉱区が広がるウェストバージニア州、ナイオブララ鉱区がある中西部等、シェールガス・オイルが採掘される州、地域においては、全米平均よりも高いGDP成長率や低い失業率を示しているところがある。
シェールガス・オイルの鉱区が広がる代表的な州の実質GDPの推移を見ると、1999年時点では各州とも全米の実質GDP成長率を下回っていたが、シェールガス・オイル産出が本格化した2000年代半ば以降、全米の成長率を上回る伸びを示している(第Ⅱ-1-2-39図)。
第Ⅱ-1-2-39図 シェールガス・オイル産出州の実質GDP成長率の推移図
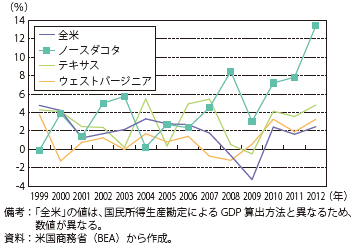
実質GDP成長率への産業別寄与度を見ると、州ごとに特徴はあるものの、全米との比較において、鉱業のみならず、建設業、卸売・小売業等でも高い寄与が見られ、シェールガス・オイル採掘に伴う経済への波及効果が幅広い分野に及んでいることが示される。特に2012年に10%を超える実質GDP成長率となったノースダコタ州では、卸売・小売業(2.3%ポイント)、輸送・倉庫(1.8%ポイント)、建設(1.3%ポイント)等幅広い分野で成長への寄与が見られる(第Ⅱ-1-2-40図)。
第Ⅱ-1-2-40図 産業別実質GDP成長率への寄与度
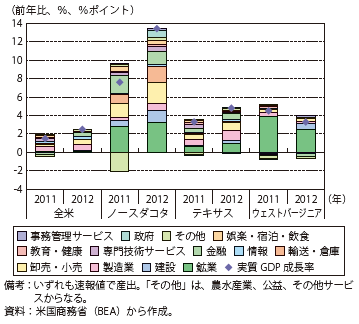
失業率の推移を見ると、全国の失業率よりも低い水準を続けているノースダコタ州のみならず、テキサス州、ウェストバージニア州においても、シェールガス・オイルの開発が活況を帯びてきた2000年代半ば以降、常に全米の水準を下回って推移している(第Ⅱ-1-2-41図)。
第Ⅱ-1-2-41図 シェールガス・オイル産出州の失業率の推移
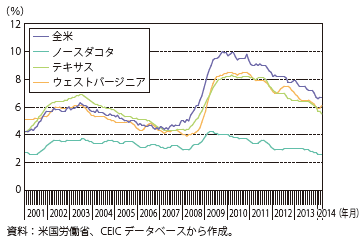
このように、産出地域の経済には、シェールガス・オイルの生産拡大によるプラスの影響が見られる。
4.米国の海外事業展開の動向
「2.米国製造業を巡る動向」で見たように、内外の事業環境の変化等を背景として、製造業のリショアリングの動きが見られるが、こうした動きは米国内需向けの生産拠点に関するものが中心であることもあり、米国経済全般の動向から見ると、現段階においては限定的なものとなっている。ここでは、世界経済危機以降プレゼンスを拡大してきた新興国を始めとする海外市場への事業展開について見ていく98。
98 米国の海外事業展開については、知的財産管理会社を低税率国に置き、そこに知的財産の使用料を各国から集中させる等、データからは事業活動の実態を正確に把握することが難しい事例も報告されているが、ここでは米国商務省(BEA)が発表しているデータに基づいて検証する。
(1)対外直接投資の動向
①対外直接投資額(フロー及び残高)
対外直接投資額のフロー(国際収支ベース)の推移を見ると、2007年に過去最高の4,140億ドルに達した。世界経済危機等の影響を受け、2008年から2010年まで3年連続で減少しているが、2010年でも3,010億ドルとなっており、日本の対外直接投資の過去最高額が2013年の13.2兆円(約1,320億ドル)であることと比べて、はるかに高い水準となっている。その後、2011年には過去最高の2007年に次ぐ4,090億ドルとなり、世界経済危機前の水準をおおむね回復している99。対象地域については、地域別では毎年欧州が5割前後、OECD加盟地域で7割超100を占めており、投資先として先進地域が大きなシェアを占めている。
対外直接投資残高の推移を見ると、右肩上がりに堅調に推移している。地域別の残高構成の推移を見ると、欧州向けのシェアが最も大きく、地域別のシェアに大きな変化は見られない(第Ⅱ-1-2-42図、第Ⅱ-1-2-43図)。
第Ⅱ-1-2-42図 米国の地域別対外直接投資額(左:フロー、右:残高)
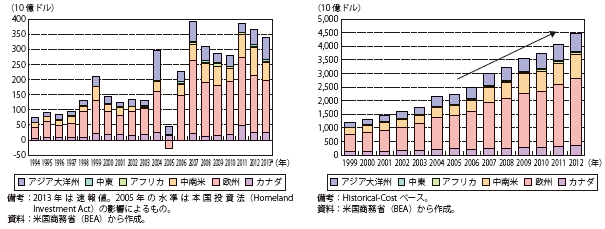
第Ⅱ-1-2-43図 米国と日本の直接投資残高の地域別シェア(1999年、2012年)
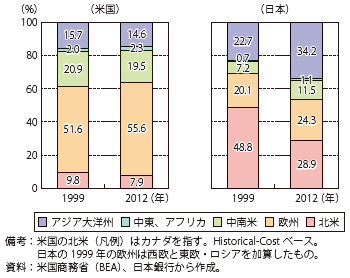
99 未分類を含むため、第Ⅱ-1-2-42図の各年のフロー額の合計とは異なる。
100 対外直接投資フロー額におけるOECD加盟国(米国除く)が占めるシェアは2009年71.5%、2010年80.9%、2011年76.3%、2012年71.7%となっている。
②対外直接投資収益率
対外直接投資収益率を見ると、全世界では10%前後で推移している。国・地域別に見ると、近年、中東での収益率が高くなっている。また、欧州、カナダでの収益率が平均を下回る一方、アジア大洋州、アフリカ、中南米での収益率が平均を上回っている。
アジア大洋州を更に詳しく見ると、日本や豪州では地域全体の収益率を下回り、ASEAN4、中国等では、地域全体の水準を上回っている。インドでは、1999年の収益率は0.3%と地域全体の収益率10.3%を大幅に下回っていたが、2004年以降、地域全体の収益率を上回る傾向が見られる(第Ⅱ-1-2-44図)。
第Ⅱ-1-2-44図 米国の対外直接投資収益率(左:対世界、右:対アジア大洋州)
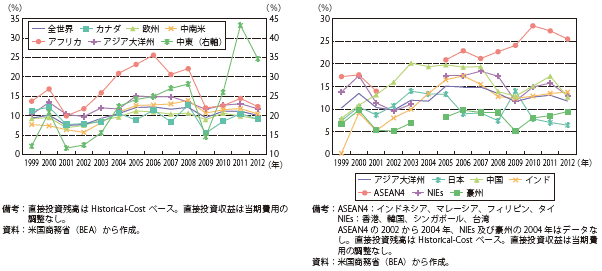
(2)米多国籍企業の動向
以上、米国の対外直接投資について全体の動向を確認してきたが、以下では、米多国籍企業の海外事業展開の動向を主要指標を通して見ていく。
2011年時点で米国企業が議決権の10%以上を所有する在外子会社の総資産は22.9兆ドル(対親会社の75%)、売上げ7.0兆ドル(同65.3%)、雇用者数1,368万人(同59.8%)である。このうち議決権の過半数を所有する在外子会社(MOFA:Majority Owned Foreign Affiliates)の総資産は20.7兆ドル、売上げ6.0兆ドル、雇用者数1,179万人と、それぞれ在外子会社全体の9割前後を占めている。以下、米国企業が議決権の過半数を所有する在外子会社を「在外子会社」とする。
①売上高
在外子会社の売上高を地域別に見ると、約5割が欧州であるが、近年、その割合は減少傾向にある一方、アジア大洋州の割合が増加傾向にある(第Ⅱ-1-2-45図)。
第Ⅱ-1-2-45図 在外子会社の地域別売上高の推移(上:額、下:シェア)
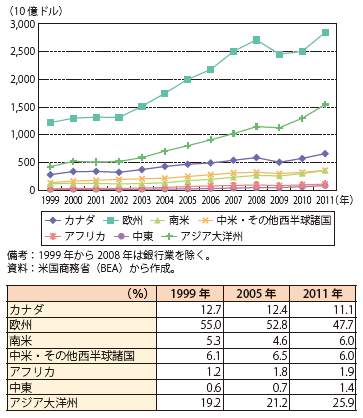
次に、各地域の在外子会社による財の販売先を見てみると、欧州の在外子会社では、米国向けは少なく、9割以上が現地向けと第三国向けとなっている。南米の在外子会社の販売先は約7割が現地向けで、米国向けは極めて少ない一方、メキシコ等中米・その他西半球諸国では、3割弱が米国向けとなっている。アジア大洋州については、日本、中国、インドでは現地向けが多い一方、マレーシアやフィリピンでは米国向けが、インドネシアでは第三国向けが多い等、その国の消費市場の規模や地域の特性に応じた事業展開が行われている(第Ⅱ-1-2-46表)。
第Ⅱ-1-2-46表 在外子会社による財(サービス除く)の販売先の地域別シェア(2011年)
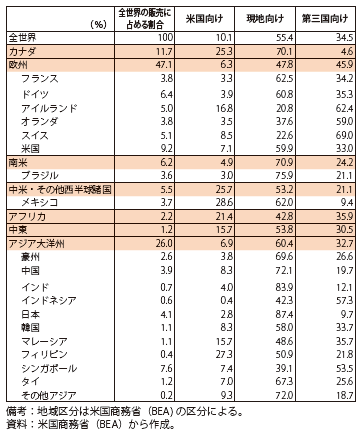
②純利益
米多国籍企業の親会社と在外子会社の純利益の推移を見ると、親会社は2001年、2008年の景気後退期に純利益を大きく落としたが、在外子会社はその間も底堅く純利益を伸ばし、2007年以降、在外子会社の純利益が親会社を上回っている(第Ⅱ-1-2-47図)。
第Ⅱ-1-2-47図 米多国籍企業の純利益の推移
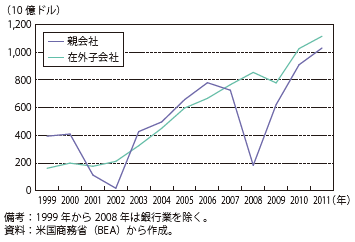
地域別に見ると、欧州における純利益が多く、全体の約6割を占めている。また中東やアフリカにおける純利益の水準は低いものの、その割合は着実に増加傾向にある(第Ⅱ-1-2-48図)。
第Ⅱ-1-2-48図 在外子会社における地域別純利益の推移(上:額、下:シェア)
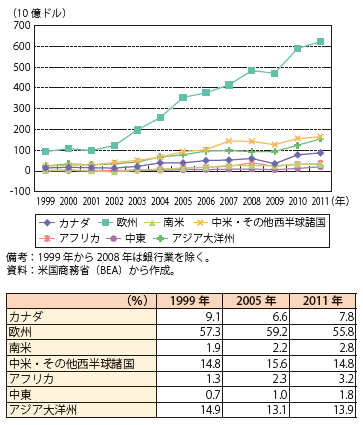
①の売上高と合わせて見ると、中米・その他西半球諸国においては、売上高のシェアと比べると純利益のシェアが高く、売上高が純利益に結びつきやすい構造となっていると考えられる一方、アジア大洋州地域においては、売上高のシェアは比較的高いにもかかわらず、純利益のシェアが抑えられている。
産業別に見ると、2001年以降、銀行以外の企業の管理業(Management of nonbank companies and enterprises)101における純利益が製造業を上回って推移しており、2011年時点で、同部門が純利益全体の約5割に及んでいる(第Ⅱ-1-2-49図)。
第Ⅱ-1-2-49図 在外子会社における産業別純利益の推移(上:額、下:シェア)
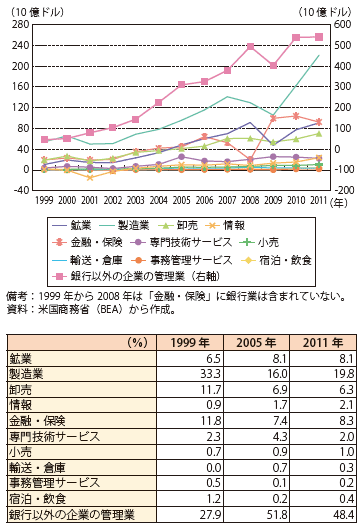
101 銀行持株会社以外の持株会社や地域統括会社等を指しており、この管理下に様々な業種の企業が属す形態。
③雇用者数
親会社と在外子会社における雇用者数の推移を見ると、1999年から2004年の間とリーマン・ショックが発生した2008年において、全体の雇用者数に減少が見られるものの、世界経済危機を経て2009年以降は緩やかではあるが増加傾向にある。
そのうち在外子会社の雇用者数102が全体に占める割合は上昇傾向にあり、2011年では全体の34%を占めている(第Ⅱ-1-2-50図)。
第Ⅱ-1-2-50図 多国籍企業内における親会社と在外子会社における雇用者数の推移
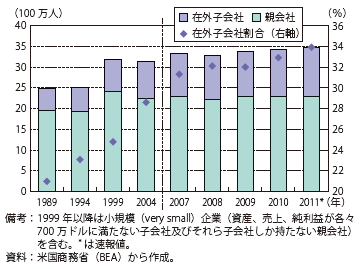
102 在外子会社の雇用者数には、親会社から派遣されている人のみならず現地採用者も含む。
地域別に見ると、1999年時点では中南米と同水準であったアジア大洋州の雇用者数が目立って増加しており、近年欧州に並ぶ勢いを見せている(第Ⅱ-1-2-51図)。さらにアジア大洋州を国別に見ると、2003年以降の中国、2008年以降のインドにおける伸びが著しい(第Ⅱ-1-2-52図)。
第Ⅱ-1-2-51図 在外子会社における地域別雇用者数の推移
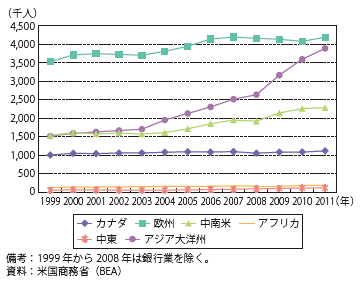
第Ⅱ-1-2-52図 アジア大洋州地域の在外子会社における雇用者数の推移
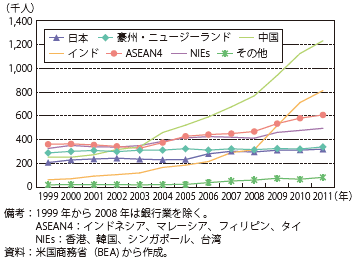
中国では製造業の雇用者の増加が大きい一方、インドでは専門技術サービス業(建築、エンジニアリング、コンピューターシステム設計、経営管理、科学技術コンサルティング、広告業等)の雇用者の伸びが目立つ(第Ⅱ-1-2-53図)。
第Ⅱ-1-2-53図 中国、インドの在外子会社における雇用者数の推移
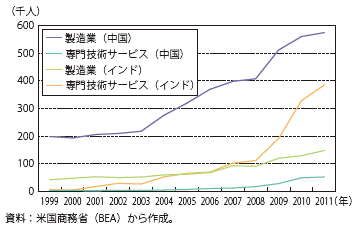
インドの在外子会社について、米国商務省(2012)によると、多国籍企業の業務を支える在外子会社のオペレーションは、対象サービスを低コストで提供することが可能な場所に立地することが最適であり、専門技術サービス業雇用者数は、運営コストが安く、英語が通じる等の利点を持つインドにおいて世界最多となっている。これら在外子会社を利用することで、米多国籍企業は業務の効率化を実現するとともに、海外の技術や人材を活用して競争力を強化・維持しており、米国における2007年から2009年の景気後退時には特に有益であった、と評価している。
1999年から2011年の間、在外子会社全体における専門技術サービス業の雇用者数は年平均8.5%の増加であるのに対して、インドにおける専門技術サービス業の雇用者数は年平均40%増加しており、インドにおける雇用者数の増加の要因となっている。
産業別に見ると、製造業では436万人(2000年)から476万人(2011年)へ、小売業では41万人(2000年)から122万人(2011年)へと増加している。産業別シェアを見ると、製造業が大きなシェアを占めている状況は変わらないものの、その割合は低下しつつあり、代わって小売業、専門技術サービス業、事務管理サービス業等でシェアが高まっている(第Ⅱ-1-2-54図)。
第Ⅱ-1-2-54図 在外子会社における産業別雇用者の推移(上:雇用者数、下:シェア)
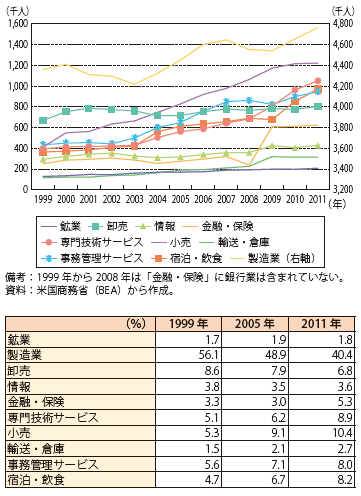
④付加価値(総生産)
在外子会社が現地で生み出している名目付加価値額を産業別に見ると、増加幅や世界経済危機時の落ち込み等に差はあるものの、多くの業種でおおむね増加傾向にある(第Ⅱ-1-2-55図)。
第Ⅱ-1-2-55図 在外子会社における産業別名目付加価値の推移(上:額、下:シェア)
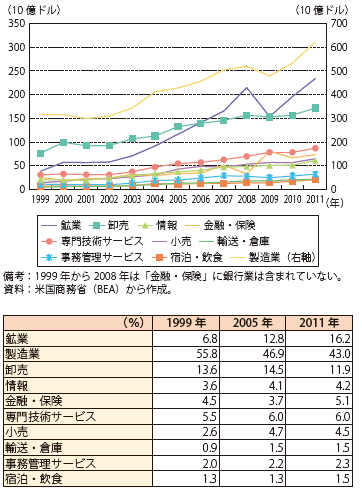
最大付加価値を生み出している製造業の全体に占めるシェアは1999年の55.8%から、2011年の43.0%まで低下しており、代わって鉱業がシェアを大きく伸ばしている。また、米国の名目GDPにおいて最大シェアを占める金融・保険業は、在外子会社の付加価値シェアでは低くなっている(前掲第Ⅱ-1-2-24図)。
製造業の内訳を見ると、化学産業、コンピューター・電子製品、石油・石炭製品、輸送機器等で付加価値を多く生み出している(第Ⅱ-1-2-56図)。
第Ⅱ-1-2-56図 在外子会社における製造業名目付加価値の内訳の推移(上:額、下:シェア)
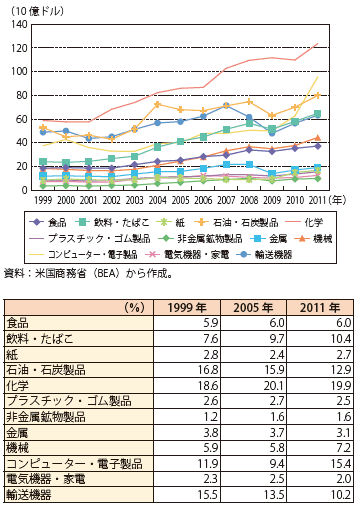
⑤資本的支出(設備投資)
多国籍企業の中で在外子会社における資本的支出(設備投資)の割合は長期的に見ると上昇してきている(第Ⅱ-1-2-57図)。
第Ⅱ-1-2-57図 多国籍企業内における親会社と在外子会社における資本的支出(設備投資)の推移
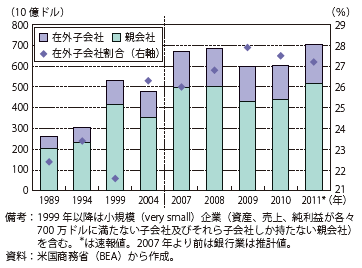
特にアジア大洋州地域においては、2005年まではカナダとほぼ同水準であったが、それ以降、カナダを大きく引き離し、欧州に迫る勢いで増加している。地域別シェアを見ると、欧州の割合が大きく低下する一方、アジア大洋州、中東の割合が上昇している(第Ⅱ-1-2-58図)。
第Ⅱ-1-2-58図 在外子会社における資本的支出(設備投資)の推移(上:額、下:シェア)
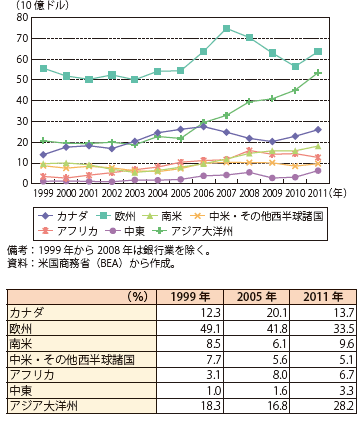
アジア大洋州を国別に見ると、豪州、中国の伸びが目立つが、その対象業種の中心は豪州では資源投資(鉱業)、中国では製造業や卸売・小売業となっており、各国の特性をいかした配分となっている(第Ⅱ-1-2-59図、第Ⅱ-1-2-60表)。
第Ⅱ-1-2-59図 アジア大洋州地域における資本的支出(設備投資)の推移
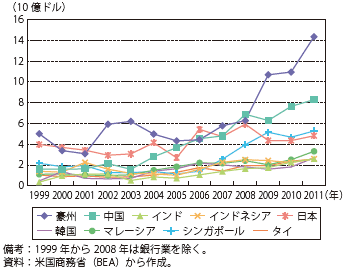
第Ⅱ-1-2-60表 アジア大洋州地域主要国における資本的支出(設備投資)(2011年)
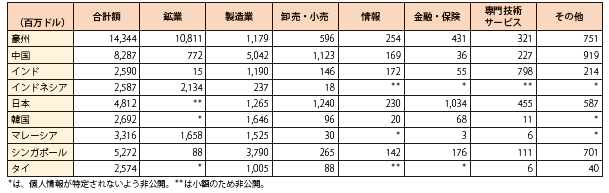
⑥研究開発費
米多国籍企業の親会社と在外子会社における研究開発費の推移を見ると、在外子会社の研究開発費が全体に占める割合が上昇している(第Ⅱ-1-2-61図)。
第Ⅱ-1-2-61図 多国籍企業内における親会社と在外子会社における研究開発費の推移
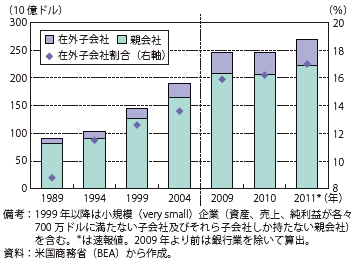
現地での研究開発を通じて、イノベーションの強化や生産性向上を図るとともに、顧客ニーズを吸い上げ、それを製品改良に短期間で反映していく取組を進めていると考えられる。
地域別に見ると、欧州向けが多いが、全体に占めるシェアは低下傾向にあり、代わって中南米、中東、アジア大洋州のシェアが拡大している(第Ⅱ-1-2-62図)。アジア大洋州では、1999年時点で約5割を占めていた日本のシェアが約半分に縮小し、中国、インドのシェア上昇が目立つ。特にインドにおける研究開発費の伸びはめざましく、2011年にはほぼ日本と並ぶ水準となっている(第Ⅱ-1-2-63図)。前述したようにインドでは、専門技術サービス業でのパフォーマンスが秀でており、研究開発投資でも2011年合計で20.8億ドルのうち、10.3億ドルが同産業においてなされている。
第Ⅱ-1-2-62図 在外子会社における地域別研究開発費の推移(上:額、下:シェア)
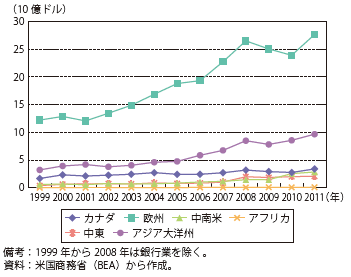
第Ⅱ-1-2-63図 アジア大洋州地域における研究開発費の推移(上:額、下:シェア)
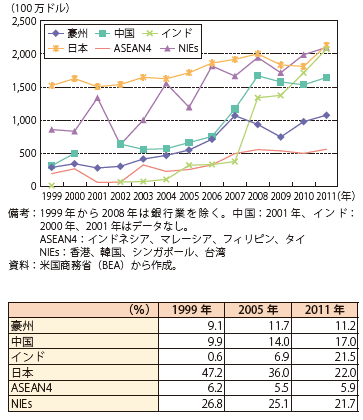
⑦米国企業の海外事業展開の現状
米国では、リショアリングの動向が注目されているが、一方、米国企業は、リショアリングが注目を浴び始めて以降も、積極的に海外において事業展開を行っている。
近年では、多国籍企業において、在外子会社の純利益が親会社を上回っており、海外収益の重要性が増している。資本的支出(設備投資)や研究開発費等の経営資源の在外子会社への投入を強化する動きも見られる。中国における製造業、インドにおける専門技術サービスへの集中投資等、その国の持つ特性に応じた戦略的な事業展開を行い、在外子会社をうまく活用することで業務の効率化や競争力の維持・強化を図っている。