第4節 次なる成長ステージへの転換を図るASEAN
ASEAN4(タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン)は、1997年のアジア通貨危機による大きなマイナス成長を経験した後、世界経済の中では比較的堅調な経済成長を維持している116。2013年、タイ117を除く3か国は、民間消費や投資が下支えして前年比4.7-7.2%と比較的高い成長率を記録した(第Ⅱ-1-4-1図~第Ⅱ-1-4-3図)。
第Ⅱ-1-4-1図 ASEAN4の実質GDP成長率の推移
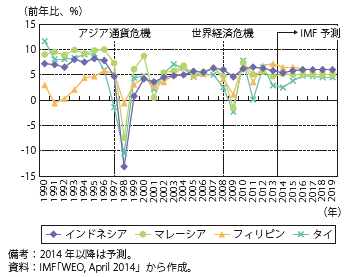
第Ⅱ-1-4-2図 ASEAN4の実質GDP成長率及び需要項目別寄与度の推移(左:年ベース、右:四半期ベース)
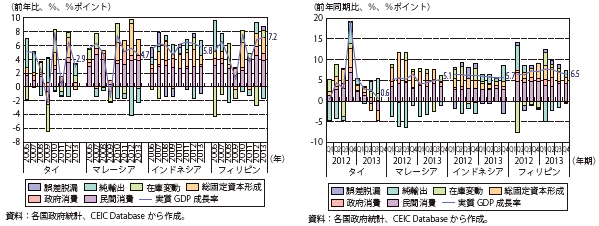
第Ⅱ-1-4-3図 ASEAN4の実質GDP成長率及び需要項目の推移(前年同期比)
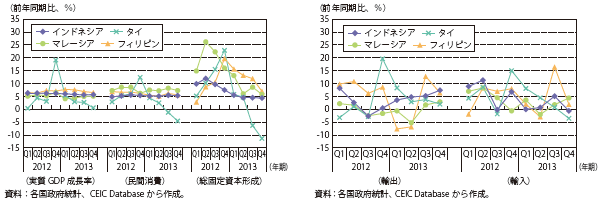
116 アジア通貨危機については第2章第1節「新興国等の経済ファンダメンタルズ」、世界経済の動向については第Ⅰ部第1章第1節「世界金融危機後の変化」を参照。
117 タイでは2012年の成長を押し上げた洪水復興需要の剝落、2012年末までの初回自動車購入支援策の終了、2013年10-12月期の反政府デモの激化などにより内需が低迷し、2013年の実質GDP成長率は前年比2.9%であった。
各国の経済構造の特徴を見ると、需要項目別では、タイ及びマレーシアは輸出のシェアが他の項目に比較して高く、インドネシア及びフィリピンは民間消費のシェアが同様に高い(第Ⅱ-1-4-4図)。また、産業別では、タイの製造業のシェアが足下にかけて上昇している一方、他の3か国の製造業のシェアは低下している。インドネシアは製造業を除く第二次産業(鉱業など)、マレーシア及びフィリピンは第三次産業(サービス業)のシェアが上昇している(第Ⅱ-1-4-5図)。各国の経常収支の推移を見ると、フィリピンは労働者送金(第二次所得収支に計上)やサービス貿易の黒字を下支えとして経常黒字が拡大している一方、他の3か国は主に財貿易黒字の縮小に伴い、経常黒字が縮小又は経常赤字が拡大している(第Ⅱ-1-4-6図)。
第Ⅱ-1-4-4図 ASEAN4の名目GDPの需要項目別構成比の推移(1995-2012年)
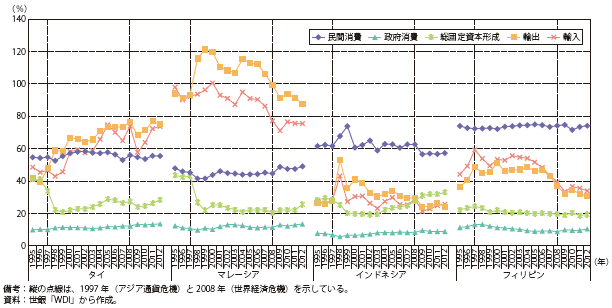
第Ⅱ-1-4-5図 ASEAN4の名目GDPの産業別構成比の推移(1980-2012年)
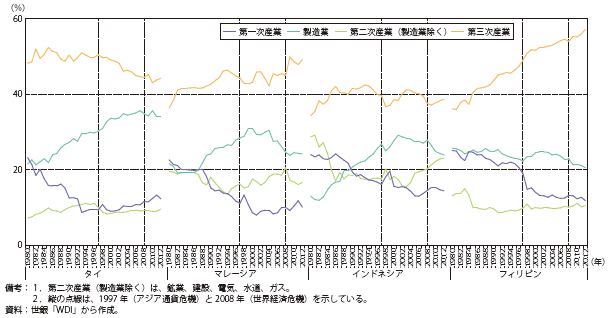
第Ⅱ-1-4-6図 ASEAN4の経常収支の推移
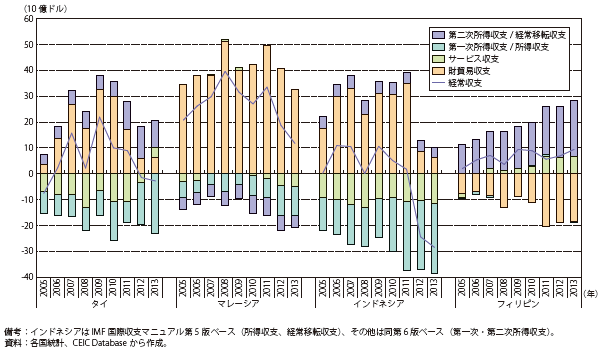
このようにそれぞれの経済構造の特徴や経済状況が異なる中、各国政府は持続的な経済成長に向けて、有望な産業を見据えた構造改革への取組を表明している。それらの内容について、国別に見ていく。
1.タイ
タイは、アジア通貨危機の経験から、海外との資本取引を規制する一方で、外資の積極的誘致や輸出の促進による成長を実現してきた。タクシン政権(2001-2006)は内需と外需の両方の成長を取り入れる「Dual Track政策」を掲げ、2002年に発足させた国家競争力強化委員会において、タイが既に一定の産業基盤を有しており、差別化を通じて世界市場で競争できる潜在性がある戦略産業として、自動車、ファッション、食品、観光、ソフトウェアの5つを指定した。加えて自由貿易協定(FTA)と外資誘致を組み合わせて戦略産業のクラスター化の促進を図った。その後、AFTA(ASEAN自由貿易協定)やASEAN+1のFTAによって域内の関税撤廃が進んだこともあり、タイでは特に部品産業を含めた自動車産業の集積が加速し、ピックアップトラックの世界的な生産拠点となった118。タイは2013年の5トン以下貨物自動車119の輸出額が世界第一位となっている120(第Ⅱ-1-4-7図、第Ⅱ-1-4-8表)。
第Ⅱ-1-4-7図 タイの自動車生産台数の推移
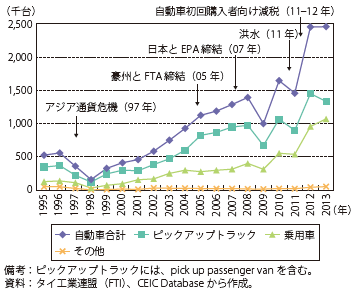
第Ⅱ-1-4-8表 5トン以下貨物自動車の主要輸出国
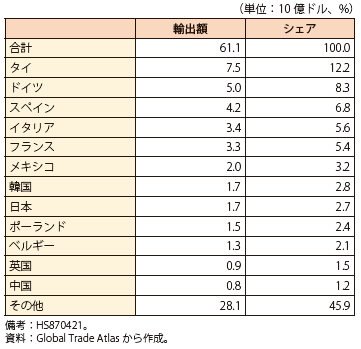
118 経済産業省(2004)、大泉(2013)。
119 HSコード870421(1トンピックアップトラックを含む)。
120 タイの自動車政策については、第2章第4節「メキシコ、タイ、インドの自動車政策」を参照。
政府は、タイを電気・電子産業の東南アジアにおける生産・輸出拠点とする考えを打ち出し、同分野における投資優遇策を相次いで発表した。タイ投資委員会(BOI)は、2004年にハードディスクドライブ(HDD)産業に対する投資優遇策を導入したほか、2006年には設備投資が長期にわたる電気・電子産業に対して最長13年間法人税を免税するなど、他の産業に比べて手厚い恩典を与えた121。
このような政策を背景として、アジア通貨危機以降減少傾向にあった対内直接投資額は、2003年より増加に転じた(第Ⅱ-1-4-9図)122。また、同時期、電子機器、農水産加工品、自動車を中心に製造業の輸出も増加したことにより(第Ⅱ-1-4-10図)、名目GDPに対する輸出シェアは上昇傾向となった(前掲第Ⅱ-1-4-4図)。2006、2007年には、クーデターなど政局の混乱により内需が低迷した一方で、輸出が成長を下支えした(前掲第Ⅱ-1-4-2図)。
第Ⅱ-1-4-9図 タイの対内直接投資額の推移(業種別)
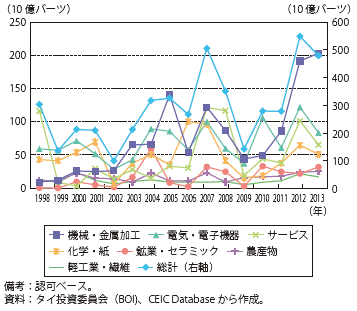
第Ⅱ-1-4-10図 タイの輸出額の推移(左:総額、右:主要製造業別)
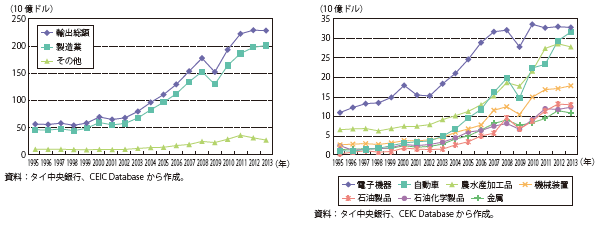
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は2011年10月に発表した「第11次経済社会開発計画(The Eleventh National Economic and Social Development Plan (2012-2016))」で、タイはこれまで外国からの投資や輸出、安い労働力に依存した経済構造のために競争力の向上が制約されてきたと分析し、競争力強化のための高付加価値産業を奨励する方針を示した。こうした方針に基づき、タイ投資委員会(BOI)は2013年1月、投資奨励10分野(①基礎インフラ・物流業、②基礎的産業、③医療機器・科学的装置、④代替エネルギー・環境サービス、⑤産業のサポートサービス(研究開発など)、⑥先端コア技術、⑦食品・農産品加工、⑧ホスピタリティ・福祉(観光、スポーツ振興)、⑨自動車・輸送機器、⑩電気・電子)を発表した123。また、2012年から2013年にかけて最低賃金が大幅に引き上げられた。タイ労働省は2012年10月、「最低賃金は国民経済の全体的な拡大を阻害するものでも、業務や民間投資に影響するものでも、失業率上昇や解雇につながるものでもない。反対に労働者の収入を増やし、生産性向上により生活の質、購買力、仕事意欲を上昇させるのに貢献するものである」との調査結果を示している124。2014年2月のタイの製造業平均賃金は、2011年1月時点より約45%上昇している(第Ⅱ-1-4-11図)。
第Ⅱ-1-4-11図 タイの製造業平均賃金の推移
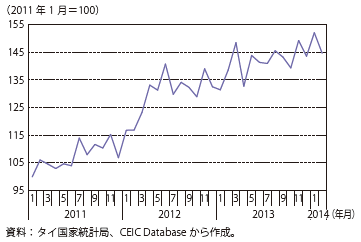
2013年には2013~2020年にわたる総額4兆バーツ(2012年名目GDPの約40%に相当。2兆バーツの借入れを含む125)のインフラ開発計画が発表されるなど、これまで様々な政策が打ち出されてきたが、今後の政治情勢による影響などに留意する必要がある。
121 JETRO(2006,2007)。世界のHDD生産台数におけるタイのシェアは第一位の43%(2010年)(経済産業省(2012))。
122 対内直接投資の業種分類のうち、自動車は「機械・金属加工」に含まれる。
123 http://www.boi.go.th/upload/content/2013-01-16%20seminar%20news_FINAL_84913.pdf![]()
この新投資奨励策は当初2013年央の導入を予定していたが、2015年1月1日まで延期することになっている。
http://www.boi.go.th/upload/content/2013-05-22%20press%20release%20-%20new%20strategy%20time%20frame%20ENG_80177.pdf![]()
124 http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/pdf/Wage_2013_Eng.pdf![]()
125 2014年3月、タイ憲法裁判所により、インフラ開発計画のための2兆バーツの借入れ法案が違憲とされた。
2.マレーシア
マレーシアでは、1980年代末からの対内直接投資の増加(第Ⅱ-1-4-12図)に伴い、1990年代には電気・電子部門などの輸出産業が発展し(第Ⅱ-1-4-13図)、成長をけん引した。この期間、実質GDP成長率は9%台とASEAN4の中でも高い水準で推移した126。アジア通貨危機を経て、2000年代に入ってからは、実質GDP成長率は世界経済危機の時期を除いておおむね5%前後で推移している(前掲第Ⅱ-1-4-1図)。この期間の名目GDPの産業別構成比を見ると、製造業のシェアは低下傾向にあり、その中でもかつて成長をけん引した電気・電子産業のシェアが低下傾向にある(第Ⅱ-1-4-14図)。この背景としては、2000年以降、安価な人件費を強みとする中国、タイ、ベトナムなどに家電メーカーの生産拠点がシフトしたことなどが挙げられる127。輸出総額に占める電気・電子産業のシェアも低下傾向にあり128、その一方で鉱物性燃料など資源の輸出シェアが上昇傾向にある(前掲第Ⅱ-1-4-13図)。他方で、卸売・小売業や金融業などを中心にGDPの約50%を占めるサービス産業のシェアは、長期的に上昇傾向にある(第Ⅱ-1-4-15表、前掲第Ⅱ-1-4-5図)。このような状況について、2013年6月発表の世銀「マレーシア経済モニター」では、マレーシアの最近の経済動向や短期見通しは、コモディティ部門に負うところが大きく、他方で製造業やサービス部門の貿易において競争力を失うリスクも生じていると指摘されている。そして、このようなリスクを軽減するには、生産性を高めるような構造改革の実行を早めて非コモディティ部門においても生産性を高める必要があると指摘されている129。
第Ⅱ-1-4-12図 マレーシアの製造業対内直接投資額の推移(業種別)
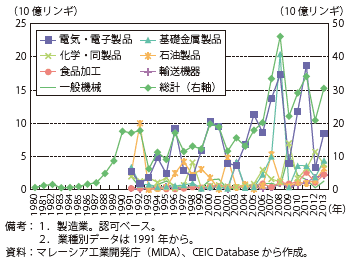
第Ⅱ-1-4-13図 マレーシアの輸出額の推移
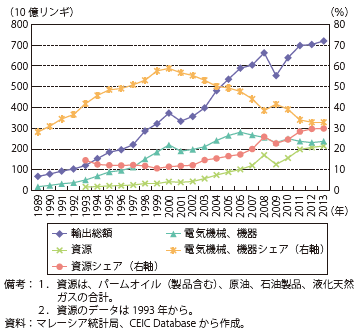
第Ⅱ-1-4-14図 マレーシアの名目GDPに占める製造業のシェア及び製造業名目GDPに占める電気・電子産業のシェアの推移
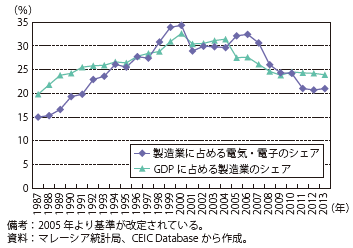
第Ⅱ-1-4-15表 マレーシアの名目GDPの産業別構成比(2013年)
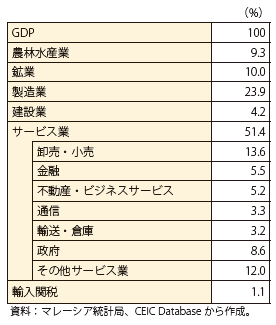
126 小野沢(2009)は、製造業の業種別の付加価値額構成比のうち、90年代には裾野産業(機械、金属加工、基礎金属)の構成比が上昇したことを示し、電気・電子部門などの輸出産業が裾野産業にも波及効果をもたらし始めたと指摘している。
127 国際協力銀行(2014)。
128 電気・電子産業の中では、集積回路や太陽光発電など省エネルギー関連機器のシェアが伸びている。電気・電子産業の輸出額に占める熱電子管、チューブ、太陽電池などのシェアは2002年の36.6%から2013年には47.0%に上昇している。
129 World Bank(2013)。
マレーシアの経済政策は、1991年2月にマハティール首相が発表した「2020年ビジョン」がベースとなっており、2020年までにマレーシアが先進国入りをするとの目標が示されている。2009年4月に成立したナジブ政権は、2010年3月に「新経済モデル(NEM)」130と呼ぶ経済政策の新指針を発表した(第二部131を同年12月に発表)132。政府はこの中で、同国の成長率が鈍化し、アジア通貨危機以降、他国よりも成長率が低く、投資が回復しない背景として、マレーシアでのビジネスが困難であることから投資先としての魅力を失いつつあること、未熟練労働者が多いこと、生産性の伸びが非常に遅いこと、技術革新が不十分であること、経済格差が広がっていること、などを指摘し、2020年先進国入りに向けて、8つの戦略的改革イニシアティブを提示した。また、2010年6月には「第10次マレーシア計画」133、同年10月には「経済変革プログラム(ETP)」134を相次ぎ発表し、産業の高付加価値化を進める方針を示している(第Ⅱ-1-4-16表)。政府は2011年から2015年の間に毎年6%程度の経済成長率を持続させる目標を立てており、サービス部門が経済をけん引すると見込んでいる(同表)。政府は経済の国際化が進む中、サービスの自由化により対内直接投資の増加や競争力の強化などによる成長が期待できるとして、2009年4月にコンピューター・関連サービス、保健・社会サービス、観光、輸送など8業種27分野の自由化を決定し、更に2012年以降の18分野の自由化を決定している135。
第Ⅱ-1-4-16表 マレーシアの経済政策の概要(2010年発表)
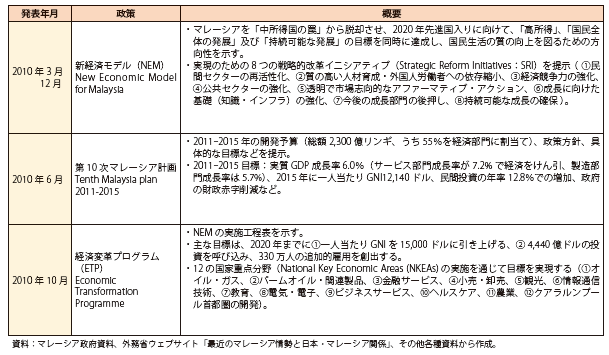
マレーシアはASEAN4の中でも財政赤字のGDP比が大きく(第Ⅱ-1-4-17図)、財政健全化が急務となっている。政府は2013年9月にはガソリン、ディーゼル油の補助金を削減し、同年10月には砂糖の補助金の廃止を表明した。2014年1月には商工業用電力料金を引き上げた。2015年4月には消費税(物品・サービス税:GST)の導入を予定するなど、政府は構造改革への取組を進めている。
第Ⅱ-1-4-17図 ASEAN4の財政収支(GDP比)の推移
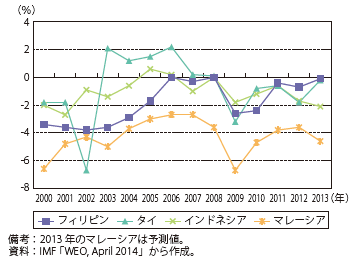
130 http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/NEM_Report_I.pdf![]()
131 https://www.pmo.gov.my/dokumenattached/NEM_Concluding_Part.pdf![]()
132 「2020年ビジョン」以降、「国民開発政策」(NDP、1991-2000年)と「国民ビジョン政策」(NVP、2001-2010年)の二つの長期経済政策が発表されていた。
133 http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/RMK/RMK10_Eds.pdf![]()
134 http://etp.pemandu.gov.my/About_ETP-@-Overview_of_ETP.aspx![]()
3.インドネシア
名目GDPの産業別構成比の推移を見ると、スハルト政権時代(1968-1998年)の工業化政策により、2000年代初めにかけて製造業のシェアが拡大し(1980年13%→2001年29%)、2002年以降は縮小傾向にある(2002年29%→2012年24%)。他方、中国など新興国の資源需要拡大に伴い、製造業を除いた第二次産業(鉱業など)のシェアが拡大傾向にあり、製造業のシェアとほぼ同じ水準となっている(同16%→同23%)136(前掲第Ⅱ-1-4-5図)。
輸出財の構成についても同様の傾向を示している137。1980年代から2000年代初めにかけて縮小傾向にあった素材のシェアが、その後拡大している(第Ⅱ-1-4-18図)。これを産業別で見ると、石油・石炭及び関連の鉱業の輸出額が2004年頃から急増している(第Ⅱ-1-4-19図)。このため、資源の需要動向や価格の影響を受けやすい構造となってきている。中国・インドなどの資源需要減速とそれに伴う資源価格の下落の影響を受けて、2012年のインドネシアの輸出額は前年比減少した。その一方で、国内の旺盛な需要により輸入額は増加し、結果として、2012年の財貿易収支(通関ベース)は赤字に転じた。2012年は経常収支も赤字に転じており138、2013年5月から始まった米国の量的金融緩和の縮小観測に伴う通貨ルピアの下落の背景ともなった139。2013年通年で見ると、輸出額の減少及び輸入額の増加により貿易赤字は前年から拡大した。同様に、経常赤字も前年から拡大した(貿易収支の推移は第Ⅱ-1-4-20図、経常収支の推移は前掲第Ⅱ-1-4-6図)。ただし、四半期ベースで見ると、足下にかけて経常赤字は縮小傾向にある140。
第Ⅱ-1-4-18図 インドネシアの生産工程別財輸出額及びシェアの推移(左:輸出額、右:シェア)
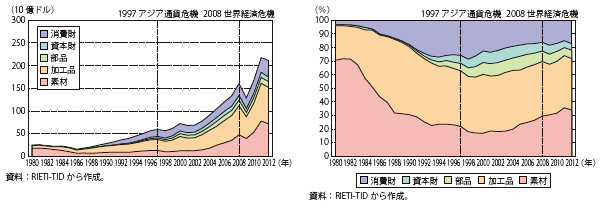
第Ⅱ-1-4-19図 インドネシアの素材の輸出額の推移(産業別)
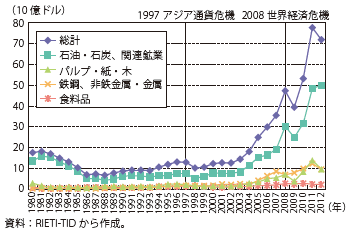
第Ⅱ-1-4-20図 インドネシアの貿易額の推移(財別)
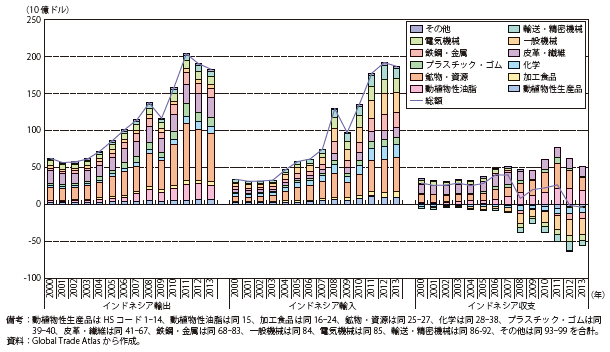
136 佐藤(2011)は、スハルト体制が、政府主導で強力に推進した工業化政策、いわば「上からの工業化」を推し進めるに当たって、軽工業、資源加工業から重工業までをフルセットで国内に構築することを目指したのに対して、現在の民主主義体制の下では、一つの明確な成長主導産業を設定しているわけではなく、投資主体がそれぞれの特性に応じた利益追求行動を始め、全体として相互に補完的な投資行動をとった(言い換えれば成長のエンジンが複数の産業に分散し、結果としてフルセット志向の産業発展パターンが現れている)ことを指摘している。
137 使用したRIETI-TIDでは、貿易財を生産工程別に、素材、中間財(加工品、部品)、最終財(資本財、消費財)の3つのカテゴリー(5つのサブカテゴリー)に分類している(付注1、2参照)。
138 2012年、通関ベースでの財貿易収支は赤字に転じ、2013年には更に赤字が拡大した(2011年261億ドル→2012年▲17億ドル→2013年▲41億ドル)。経常収支を構成する国際収支ベースでの財貿易収支も黒字が縮小した(2011年348億ドル→2012年86億ドル→2013年61億ドル)。
139 第Ⅰ部第1章第2節「米国の量的金融緩和の縮小とその影響」を参照。
140 経常赤字は、2013年4-6月期(101億ドル)をピークに、7-9月期(86億ドル)、10-12月期(43億ドル)、2014年1-3月期(42億ドル)と縮小傾向にある。
インドネシアは再び産業と輸出の構造改革期に入っている。2011年5月、政府は「インドネシア経済開発加速・マスタープラン2011~2025年」(MP3EI)を発表した。具体的には、全国各島をインフラ網で連結し、各地の特性に合わせて選ばれた22の優先業種を振興する計画である。この中で政府は「2025年までに世界の十大経済国になり、2050年には世界の六大経済国になることを目指す」と表明している141。
また、政府は2013年6月、財政を圧迫する要因とされていた燃料補助金の削減を決定した。同年8月、12月には経済政策パッケージをまとめており、内需を抑えるとともに、輸出を促進することとしている(第Ⅱ-1-4-21表)。そして政府は新鉱業法(2009年公布・施行)及び同法の運用に関する各種政令及び大臣令により、2014年1月よりニッケルなどの鉱物資源につき国内高付加価値化義務を課し、未加工鉱石の輸出を禁止した。銅精鉱については、輸出禁止の実施が2017年1月に延期され、当面輸出税及び輸出許可制が導入された。インドネシアは、そのほかにも一定の鉱物資源につき国内供給優先義務を課している142。
第Ⅱ-1-4-21表 インドネシアの政策パッケージ
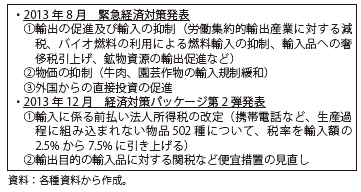
インドネシアの対内直接投資額を見ると、2010年以降、大きく増加している。特に鉱業や輸送機械など第二次産業の伸びが大きい(第Ⅱ-1-4-22図)。2013年の対内直接投資額(実行ベース)は286億ドル(前年比16.5%増)であり、そのうち我が国からの直接投資額は47億ドル(前年比91.8%増)と、国別では1位の16.5%を占める(第Ⅱ-1-4-23図)。
第Ⅱ-1-4-22図 インドネシアの対内直接投資額の推移(主要産業別)
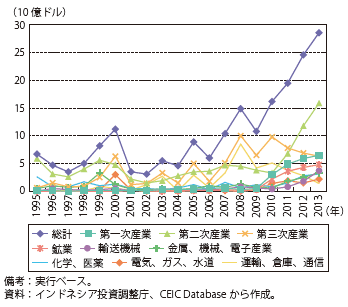
第Ⅱ-1-4-23図 インドネシアの対内直接投資額の推移(主要国・地域別)
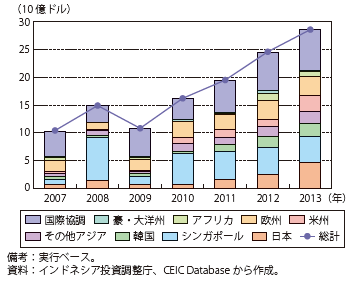
2013年11月に公表された国際協力銀行の報告書143によると、我が国製造業企業の中期的な有望国として、インドネシアが初めて1位となった。一方、同報告書では、インドネシアの課題として、「労働コストの上昇」「インフラの未整備」「不透明な法制の運用」などが挙げられている。また同年12月に公表されたJETROの調査144でも、インドネシアに進出している日系企業(製造業・非製造業)の投資環境面でのリスクとして、同様に「人件費の高騰」「インフラの未整備」「法制度の未整備・不透明な運用」が挙げられるなど、インドネシアにおける投資環境整備の必要性が示されている。
インドネシアでは2014年4月に総選挙を実施しており、7月には大統領選が予定されている(新大統領の就任は10月)。選挙の結果に伴い、今後構造改革がどのように進展するか、注目される。
141 インドネシア外務省(http://www.kemlu.go.id/rome/Documents/MP3EI_PDF.pdf![]() )、佐藤(2011、2014)。優先業種は、農林水産業7業種、鉱業5業種、製造業5業種、観光、海運、IT・通信、2つの戦略地域開発戦略。
)、佐藤(2011、2014)。優先業種は、農林水産業7業種、鉱業5業種、製造業5業種、観光、海運、IT・通信、2つの戦略地域開発戦略。
142 なお、本措置について、我が国は、二国間協議やWTOの委員会において継続的に是正を求めてきており、今後とも是正を求める取組を継続する方針である(経済産業省「2014年版不公正貿易報告書」)。
143 国際協力銀行(2013a)。
144 JETRO(2013)。
4.フィリピン
2013年の実質GDP成長率は前年比7.2%と、ASEAN4の中で最も高い。需要項目別では民間消費、産業別ではサービス産業が主導する経済構造となっている。
まず、需要項目別では、民間消費が名目GDPの7割を超える一方で、総固定資本形成は2割弱となっている(前掲第Ⅱ-1-4-4図)。民間消費は海外労働者からの送金にも支えられている。フィリピンでは出生率が高い145が、国内雇用が少なく、ASEAN4の中で最も成長率が高い一方で失業率が最も高くなっている146。海外で働くフィリピン人の数は、2012年にフローでは約180万人(第Ⅱ-1-4-24図)、ストックでは約450万人いると推定されている147。本国への労働者送金額は、インド及び中国に次ぐ世界第3位であり、GDP比では9.8%(2012年)と、他国と比較しても高水準にある(第Ⅱ-1-4-25図)。このため、フィリピンは労働者送金を支えに経常黒字を継続している(前掲第Ⅱ-1-4-6図)。
第Ⅱ-1-4-24図 フィリピンの海外労働者及び失業率の推移
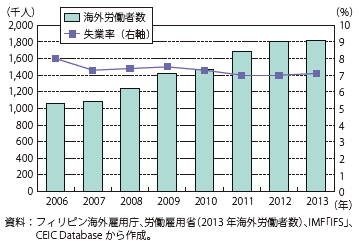
第Ⅱ-1-4-25図 海外労働者送金額の推移(2013年予測上位10か国)
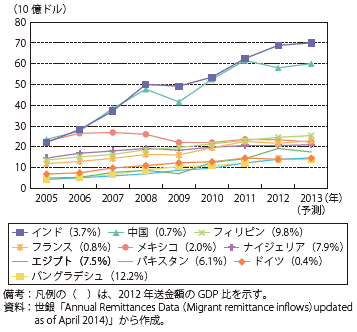
145 世銀(WDI)によると、2011年の1,000人当たり出生率は、フィリピンが24.8人、インドネシアが19.6人、マレーシアが17.6人、タイが10.7人。また、同年の合計特殊出生率は、フィリピンが3.1人、インドネシアが2.4人、マレーシアが2.0人、タイが1.4人。
146 IMFデータ(WEO April 2014)によると、2013年の失業率は、フィリピンが7.1%、インドネシアが6.3%、マレーシアが3.1%、タイが0.7%。
147 海外移住者(定住者)も含めると、在外フィリピン人は900万人超(全人口の約1割)に達していると推定されている(鈴木(2013))。
次に産業別では、製造業のシェアが約2割で低下傾向にあるのに対して、第三次産業は6割弱あり、そのシェアは上昇傾向にある(前掲第Ⅱ-1-4-5図)。
サービス産業の中でも、アウトソーシング産業(BPO: Business Process Outsourcing)の成長が著しい。フィリピンのITアウトソーシング産業148の売上高を見ると、コンタクトセンター(コールセンターなど)149の他、ソフトウェア開発やトランスクリプション(医療事務など)といった領域へと広がりを見せている。これによって2011年には約68万人の雇用が創出された(第Ⅱ-1-4-26図)。ITアウトソーシング産業は主に欧米から対内直接投資を受け入れている(第Ⅱ-1-4-27図)。売上高の9割以上は輸出によるものであり150(第Ⅱ-1-4-28図左)、その多くは米国向けである(2011年輸出額のうち、76%が米国向け)(同図右)。BPO産業は、観光、電子産業、海外労働者送金と並んでフィリピンの4大外貨収入源の一つとされており151、政府は開発計画(2011-2016)の中で、BPO産業を優先産業に位置付けている152。
第Ⅱ-1-4-26図 フィリピンのITアウトソーシング産業の売上高(左)と雇用者数(右)の推移
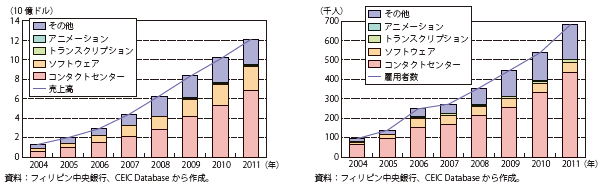
第Ⅱ-1-4-27図 フィリピンのITアウトソーシング産業への対内直接投資額の推移(投資国別)
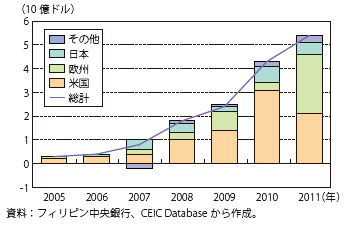
第Ⅱ-1-4-28図 フィリピンのITアウトソーシング産業の輸出額の推移(左)と2011年輸出先国シェア(右)

148 フィリピン中銀の報告「Measuring the Contribution to the Philippine Economy of Information Technology-Business Process Outsourcing (IT-BPO) services」
(http://www.bsp.gov.ph/downloads/publications/2012/BS2012.pdf![]() )によると、フィリピンのITアウトソーシング産業の総売上高対GDP比は2004年の1.4%から2011年には同5.4%に伸びており、国全体の雇用者に占める同産業の雇用者の割合は2004年の0.3%から2011年には1.8%に伸びている。
)によると、フィリピンのITアウトソーシング産業の総売上高対GDP比は2004年の1.4%から2011年には同5.4%に伸びており、国全体の雇用者に占める同産業の雇用者の割合は2004年の0.3%から2011年には1.8%に伸びている。
149 フィリピンを拠点とし、様々なオフショアサービスを世界中の顧客に向けて主に英語で提供するノウハウの蓄積が進み、成熟度が高くなった結果、コールセンター部門の売上高はインドを抜いて世界第一位となっている(国際協力銀行(2013b))。
150 2011年売上高121億ドルのうち、輸出によるものが112億ドル。
151 鈴木(2013)
152 フィリピン国家経済開発庁(NEDA)「Philippine Development Plan 2011-2016」
(http://www.neda.gov.ph/?p=1128![]() )。
)。
