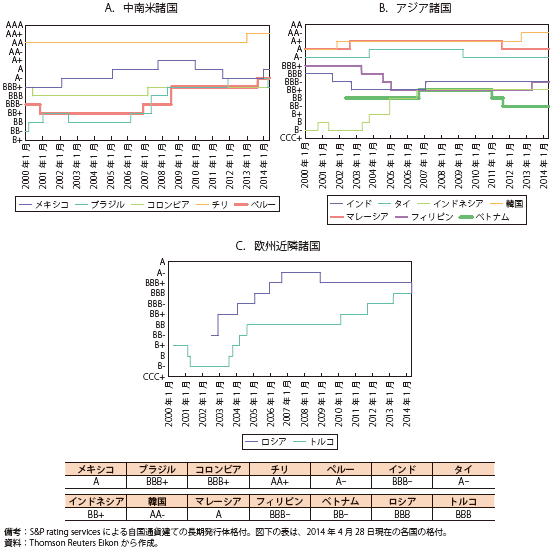第1節 新興国等の経済ファンダメンタルズ
新興国においてビジネスを展開する際には、当該国に内在する政治、経済、社会的リスクやぜい弱性と共に、今後の成長基盤を検討することが必要である。このような認識の下、本項では過去の通貨・金融危機の原因、経過(危機の波及・伝播)及び各国の政策対応について簡単に振り返ることから始める。次に、過去の通貨・金融危機によって大きな被害を受けた新興国を中心として、経済のファンダメンタルズに関わる多様な統計・データを用いて、各新興国のリスク耐性と成長基盤をスコアリングし、各国間で相対評価する。最後に、韓国を事例として、危機からの脱却に向けて断行された各種の構造改革について、その内容と成果を定性的に評価する。
1.過去の経済危機と政策対応
本項では、過去の通貨・金融危機としてメキシコ通貨危機、アジア通貨危機及びリーマン・ショックに端を発する世界経済危機の3つを取り上げる。第Ⅱ-2-1-1図は、国際通貨研究所が算出・公表しているGlobal Market Volatility Index(以下、世界市場ボラティリティ指数という)の推移を描いている153。この指数は、株式、債券及び為替の各市場の変動性(ボラティリティ)を算出したものであり、世界の金融・資本市場のリスクストレス度を表している。このグラフからも、過去の危機時あるいは直後に各指数が大幅に上昇し、市場の不安定性が大きく高まっていることが分かる。
第Ⅱ-2-1-1図 世界市場ボラティリティ指数の推移(1994年1月28日~2014年3月14日)
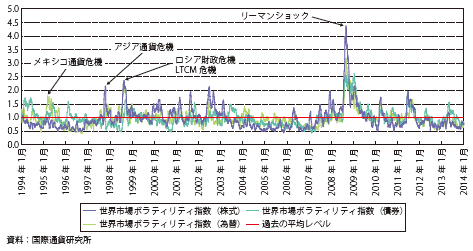
153 世界市場ボラティリティ指数の見方や作成方法等については、国際通貨研究所が公表している次の資料を参照。http://www.iima.or.jp/Docs/ppp/index/kaisetsu.pdf![]()
(1)メキシコ通貨危機
通貨危機発生前の1982年8月に、メキシコは債務危機を経験している。1970年代半ばに大規模な石油の埋蔵が発見されたメキシコは、国際金融市場における信用力が高まった結果、対外借入れが容易となり対外債務が増加していった。メキシコは油田の発見及び石油価格の高騰(第二次オイルショック)に乗って、対外借入れによってファイナンスされた公共事業を中心とした開発投資が実行され、高い経済成長率を達成していた。しかし、石油価格が下落すると、米国における金利上昇、資本流出によるメキシコ・ペソの下落等によって対外債務の返済負担が増加し、対外債務返済の不履行(デフォルト)を宣言するに至った。
第Ⅱ-2-1-2図はこの時期のメキシコのデット・サービス・レシオ154とネット・トランスファー比率155の推移を示している。債務危機発生の前年である1981年におけるデット・サービス・レシオは51.6%であり、輸出額の半分以上が対外債務の返済に充てられる計算となる。また、同年のネット・トランスファー比率は15.7%であり、新規融資額のうち自由に使えるのは約15%しかなく、新規融資額の約85%が元利返済に充てられる計算となる。このことからも、いかに当時のメキシコの対外債務の返済負担が重かったかが分かる。
第Ⅱ-2-1-2図 メキシコのデット・サービス・レシオとネット・トランスファー比率の推移
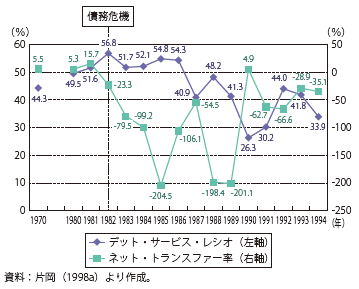
154 デット・サービス・レシオは債務返済額を輸出額で割った値で、対外債務の返済可能性を示す指標の一つ。値が高いほど債務返済の負担が重いことを表す。
155 ネット・トランスファー比率は新規融資額と元利返済額との差を新規融資額で割った値で、元利返済の負担を示す指標の一つ。値が小さいほど元利返済の負担が重いことを表す。
第Ⅱ-2-1-3図はメキシコの対外債務のGNI(国民総所得)に対する比率の推移を示している。1982年時点でメキシコの対外債務はGNIの50%を超える水準(53.4%)まで上昇しており、石油価格の下落とメキシコ大地震が発生した1986年に82.9%のピークに達した。
第Ⅱ-2-1-3図 メキシコの対外債務残高の対GNI比の推移
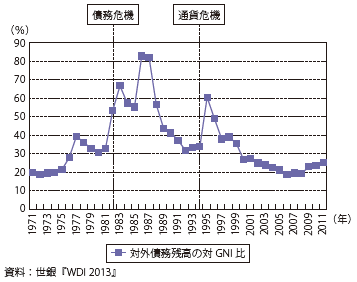
既述のように、1970年代に大規模な石油の埋蔵が発見されたメキシコは、国際金融市場における信用力が高まった結果、対外借入れが容易となり対外債務が増加していった。第Ⅱ-2-1-4図はメキシコのプライマリー・バランス及び財政収支の対GDP比の推移を示したものであるが、1982~87年にかけて、プライマリー・バランスの対GDP比が1982年を除いて黒字であるのに対して、財政収支の対GDP比はプライマリー・バランスの対GDP比から大きくかい離して大幅な赤字となっており、金利返済負担の重さを物語っている。
第Ⅱ-2-1-4図 メキシコのプライマリー・バランス及び財政収支の対GDP比の推移
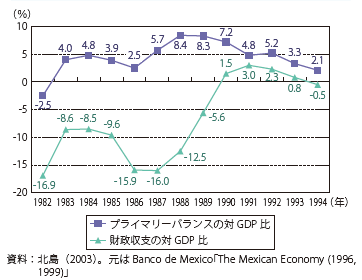
債務危機の経験以来、メキシコはIMFの勧告を受け入れ、輸入代替工業化政策からの脱却を図り改革・開放路線へと歩み始め、1986年にはGATT(現WTO)へ加盟した。1988年に発足したサリナス政権は国営企業の民営化・売却、金融制度の自由化、インフラ整備等、国内経済の自由化を推進し、1994年1月1日にNAFTA(北米自由貿易協定)が発効する礎を築いた。
債務危機が収束に向かう中、1994年12月に発生することとなるメキシコ通貨危機以前の数年間、メキシコには大量の資本が流入していた。特に、1990~1993年にかけて、直接投資におけるインフロー(ネット)がほぼ一定で安定している一方、証券及びその他投資におけるインフローが大きく増加している(第Ⅱ-2-1-5図パネルA参照)。これは対GDP比で約5%に相当する。1993年の資本流入額は約300億ドルに上り、これは中南米諸国全体への資本流入額の約半分を占めていた。
第Ⅱ-2-1-5図 メキシコの直接投資と証券及びその他投資のインフローの推移(ネット)

これを反映して、メキシコの資本収支の対GDP比率は、1993年には6.6%に達した。他方、経常収支の対GDP比率は、同年▲4.8%となっており、経常収支の赤字を上回る資本が流入していたことが分かる(第Ⅱ-2-1-6図パネルA)。これを受けて、メキシコの外貨準備は増加していた(第Ⅱ-2-1-6図パネルB 156)。伊藤(2007)で指摘されているように、当時、外貨準備が増加している経済は健全であることを示していると考えられていた。しかし、急激な資本流出が生じた際に、固定為替を維持するために為替介入によって対抗しようとすると、いずれ外貨準備は枯渇し、固定為替を維持することができなくなる。
第Ⅱ-2-1-6図 メキシコの経常収支と資本収支の対GDP比と総準備(金除く)の推移
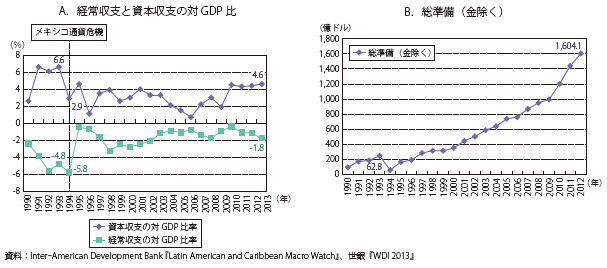
メキシコ通貨危機は、1994年12月20日、メキシコ政府が通貨ペソの大幅な切下げをアナウンスしたことに端を発する金融危機である。メキシコを震源とした金融不安は、ブラジル、アルゼンチンといった中南米諸国、香港、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシアといったアジア諸国、欧州の一部の国にもその影響が波及し、この現象は「テキーラ効果」と言われた。また、メキシコ通貨危機は、1980年代の資本移動の自由化により資本が瞬時にかつ大量に流出入するようになったことによって生じた危機であり、従来の経常収支赤字を問題とする危機とは異なり、「21世紀型の資本勘定型の危機」と言われた157。
通貨切下げのアナウンス後、投資家は一斉に資本を引き揚げ始めた。メキシコ政府は為替介入により通貨価値の維持を図ろうとしたが、外貨準備が十分ではなく、同年12月22日には変動為替相場制への移行を余儀なくされ、これによりメキシコ・ペソは大幅に減価した(第Ⅱ-2-1-7図)。最終的には、1995年1月31日、米国、IMF及びG10諸国を中心とした、総額500億米ドルのメキシコに対する支援パッケージが策定され、メキシコ通貨危機は収束に向かった158。
第Ⅱ-2-1-7図 メキシコ・ペソの実質実効為替レート(ナローベース)の推移
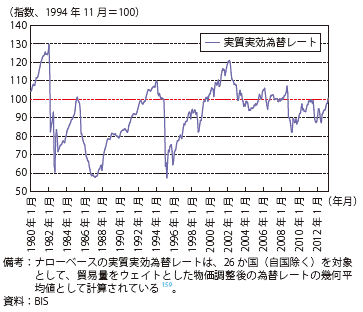
通貨危機を教訓として、メキシコは国内の構造改革を進め、経済のファンダメンタルズを改善させてきている。前掲第Ⅱ-2-1-6図のパネルA及びパネルBに見られるように、経常収支は赤字ではあるものの、その対GDP比は2013年時点で▲1.8%と小幅にとどまっている(パネルA)。また、総準備の額も2012年時点で、財・サービスの輸入額の5か月分に相当する約1,600億ドルまで積み上げている(パネルB)。
また、前掲第Ⅱ-2-1-5図のパネルA及びパネルBに見られるように、対内直接投資は2010年頃から証券及びその他投資による資本流入が増加していたが、2013年には直接投資による資金流入の方が大きくなっている。
対外債務構造にも変化が見られる。第Ⅱ-2-1-8図は、メキシコの債務構造(公的債務/GDP、対外債務/公的債務、短期対外債務/対外債務)を債務危機時、通貨危機時及び世界経済危機の3つの年代別に分けて示している。通貨危機時には、対外債務/公的債務が1980年代の債務危機時よりも高い値となっており、政府のファイナンスにおいて対外的な依存度が高まっていたことが分かる。メキシコ通貨危機時と世界経済危機時を比較すると、対外債務/公的債務及び短期対外債務/対外債務の比率が低下してきている。このことから、通貨危機以来、メキシコ政府は対外借入れの割合を縮小させ、国内で資金調達を行うようになってきていることが分かる。また、対外債務における短期の借入れの比率も低下しており(短期資金への依存度が低下している)、より期間の長い借入れを行うようになってきている。
第Ⅱ-2-1-8図 メキシコの債務構造の年代別比較
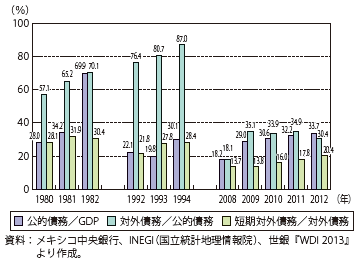
156 図では総準備(金除く)の推移が示されている。
157 伊藤(2007)、伊藤・織井(2006)。当時、IMFの専務理事であったカムドシュがメキシコ通貨危機を「21世紀型の危機」と名付けた。
158 伊藤(1997)。
159 詳細はBank for International Settlementsのホームページを参照。http://www.bis.org/statistics/eer/![]()
(2)アジア通貨危機
アジア通貨危機は、1997年7月、タイの通貨バーツが急落したことに端を発し、金融不安がアジア各国(インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、香港等)、さらにはロシアや中南米、東欧諸国にも伝播した金融危機である(第Ⅱ-2-1-9図参照)160。1990年代の前半には、多くのアジア諸国は「東アジアの奇跡」と呼ばれる高成長を遂げていたが、1990年代後半には、アジア通貨危機による経済危機を経験することとなった。以下では、アジア通貨危機により深刻な金融危機を経験した国について、それらの国々が抱えていたリスク・ぜい弱性の共通要因と個別要因に着目して、危機の発生、伝播及び収束過程を振り返る。
第Ⅱ-2-1-9図 伝染効果:アジア通貨危機の影響の伝播状況
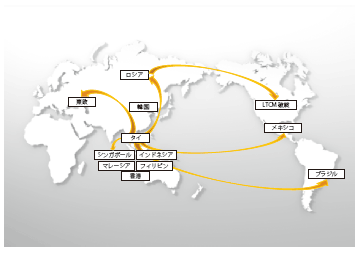
アジア通貨危機の影響を受けた国は為替レートの大幅な下落に直面した。第Ⅱ-2-1-10図は、アジア通貨危機の影響が大きかったインドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン及びタイ(以下、アジア5か国と言う)の実質実効為替レートの推移を示している。全ての国で実質実効為替レートは大きく下落しているが、特にインドネシアにおける下落は突出しており、1998年7月には、1997年6月の水準から約8割も下落している。韓国を除く4か国の実質実効為替レートは現在に至るまで、アジア通貨危機時に下落した水準と同程度の水準で推移している。韓国の実質実効為替レートは、アジア通貨危機後緩やかに上昇を続けたが、2008年9月のリーマン・ショックによる世界経済危機によって再び大きく下落した。
第Ⅱ-2-1-10図 アジア5か国の実質実効為替レート(ブロードベース)の推移
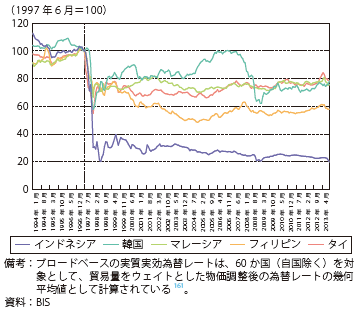
160 内閣府経済社会総合研究所(2002)でも述べられているように、危機の伝染に関する因果関係は必ずしも明らかではないが、一般的には、タイ・バーツの急落が危機の発端であると考えられている。
161 詳細はBank for International Settlementsのホームページを参照。http://www.bis.org/statistics/eer/![]()
第Ⅱ-2-1-11図は、Ito and Hashimoto(2002)による、アジア通貨危機時のアジア諸国において為替レート変動がどこからどこに伝播したかという因果関係の特定を分析した結果を表している。図において、矢印が太い方が統計的により信頼できることを表している。この結果によると、タイ・バーツの下落はアジア通貨危機のきっかけとはなったが、危機の最中においては他の国の為替レートに有意な影響を与えておらず、むしろ為替レートの変動を引き起こしていたのは、インドネシア・ルピア(他の全ての通貨に影響を及ぼしている)あるいは韓国ウォン(台湾ドル以外の他の全ての通貨に影響を及ぼしている)であることが分かる162。
第Ⅱ-2-1-11図 アジア諸国における為替レート変動の伝播の因果関係
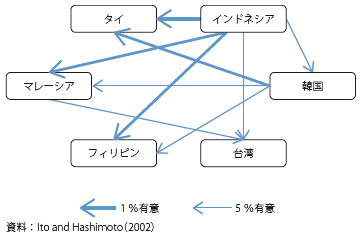
162 伊藤・橋本(2005)も参照。
アジア通貨危機においても、メキシコ通貨危機時のメキシコと同様に、危機発生前に大量の資本がアジア諸国に流入していた。第Ⅱ-2-1-12図は、アジア5か国の投資収支の推移を示している。アジア通貨危機が発生する前、5か国全ての国で資本が流入超であったことが分かる。インドネシア、韓国、フィリピンでは証券投資の割合が高く、マレーシアでは直接投資が、タイではその他投資の割合が高い。各国ごとに内訳は異なるものの、アジア通貨危機もメキシコ通貨危機と同様に、直接投資に比して証券及びその他投資の割合が高いという類似性を持っていた。アジア通貨危機が発生した1997年以後、インドネシア、マレーシア及びタイでは、その後数年に渡って資本が流出するという状況が続いた。韓国は1998年に僅かに流出超に転じたが、すぐに持ち直した。フィリピンでは、資本の流出入という観点からは、アジア通貨危機の影響は軽微であった。
第Ⅱ-2-1-12図 アジア5か国の投資収支の推移
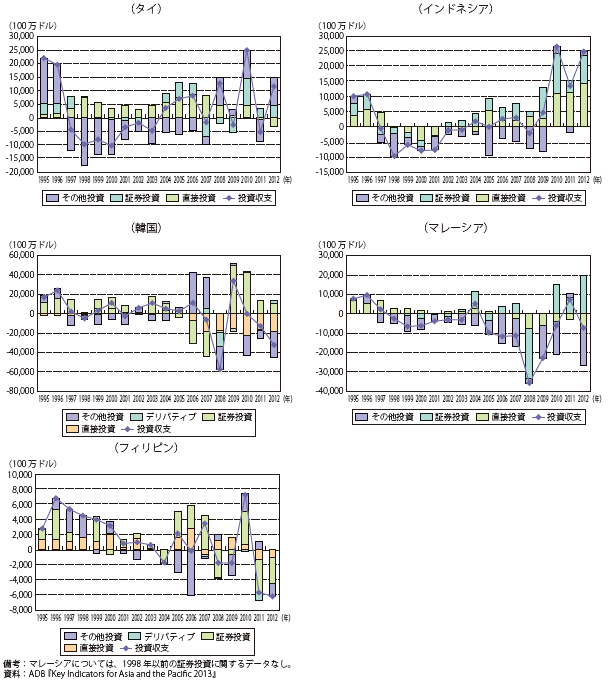
- Excel形式のファイル(タイ)はこちら

- Excel形式のファイル(インドネシア)はこちら

- Excel形式のファイル(韓国)はこちら

- Excel形式のファイル(マレーシア)はこちら

- Excel形式のファイル(フィリピン)はこちら

第Ⅱ-2-1-13図は、アジア5か国の経常収支の対GDP比の推移を示したものである。1993年の韓国を除いて、アジア通貨危機まで全ての国が経常収支赤字となっており、特に、タイやマレーシアでは経常収支の対GDP比が▲8%を超える年もある。
第Ⅱ-2-1-13図 アジア5か国の経常収支の対GDP比の推移
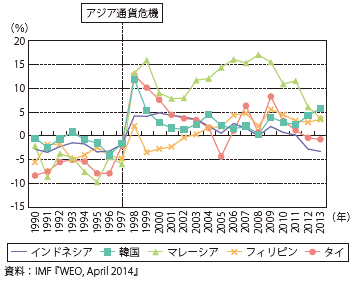
続いて、第Ⅱ-2-1-14図は、アジア5か国の対外債務残高に関連する指標の推移を示している。パネルAは総対外債務残高の対GNI比、パネルBは短期対外債務が総対外債務残高に占める割合、パネルCは外貨準備高の短期債務残高に対する割合を示している。まず、パネルAを見ると、アジア通貨危機発生時の1997年において最も高い総対外債務残高の比率を示しているのはタイの74.6%であり、インドネシアが65.1%、フィリピンが58.3%と続く。これらの値は、前段で見たメキシコの債務危機が生じた際の値を上回っている。一方、パネルBを見ると、1997年の時点で最も短期債務残高の割合が高いのは、パネルAと同じくタイの34.5%であるが、次いでマレーシア(31.6%)と韓国(30.4%)となっている。最後に、パネルCを見ると、1997年の時点で、マレーシアを除いて全ての国で100%を割り込んでいる。特に、韓国は30%程度の水準しかなく、パネルBと併せて見ると、韓国における短期債務への依存度が高かったことが分かる163。
第Ⅱ-2-1-14図 アジア5か国の対外債務残高関連指標の推移
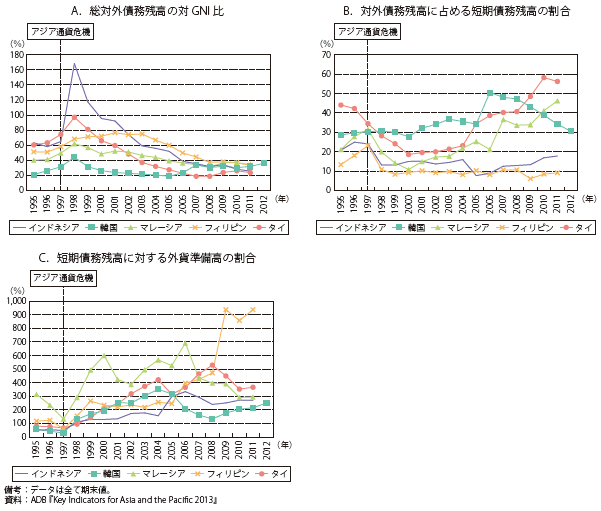
- Excel形式のファイル(A.総対外債務残高の対GNI比)はこちら

- Excel形式のファイル(B.対外債務残高に占める短期債務残高の割合)はこちら

- Excel形式のファイル(C.短期債務残高に対する外貨準備高の割合)はこちら

前掲の第Ⅱ-2-1-2図と同様に、アジア通貨危機時におけるアジア5か国のデット・サービス・レシオの推移を示したのが第Ⅱ-2-1-15図である。メキシコの債務危機時ほどではないが、インドネシアでは1997年時点で30.3%に達している。
第Ⅱ-2-1-15図 アジア5か国のデット・サービス・レシオの推移

アジア通貨危機に見舞われた国々には、各国に共通した複数の要因と各国ごとの個別の要因が存在する。まず、第Ⅱ-2-1-16表は、特に影響が大きかったタイ、インドネシア及び韓国について、アジア通貨危機の概要とIMFプログラムの内容を一覧にしてまとめたものである。
第Ⅱ-2-1-16表 アジア通貨危機の概要とIMFプログラムの比較
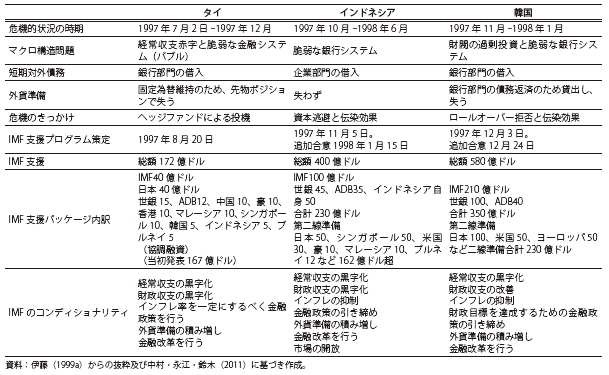
続いて、第Ⅱ-2-1-17表には、アジア通貨危機に見舞われたこれらの国に共通していた要因及び各国の個別要因がまとめられている。共通要因としては、①ドル・ペッグによる通貨の過大評価、②ぜい弱な銀行・非銀行の監督及び③過大な短期資本の流入が挙げられる。個別要因としては、タイ、韓国では外貨準備の管理の失敗、韓国、インドネシアでは弱いコーポレート・ガバナンスが挙げられる164。
第Ⅱ-2-1-17表 アジア通貨危機発生の各国の共通要因と個別要因
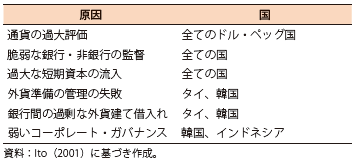
第Ⅱ-2-1-18表は、Summers 165(2000)おいて分析された、アジア通貨危機発生国における各国のぜい弱性をスコアリングした結果を示している166。固定為替制度あるいは外貨準備に関しては、全ての国が「非常に深刻」(あるいはそれ以上)とされている。経常収支赤字については、タイが「非常に深刻」、インドネシアは「深刻」、韓国は「深刻ではない」と、三者三様となっている。財政赤字については、メキシコ通貨危機の場合とは異なり、アジア通貨危機ではそれほど問題ではなかった。一方、銀行・金融機関のぜい弱性については、全ての国が「非常に深刻」な状態であった。政府の短期債務については、タイ以外の国では深刻ではなかったが、対外短期債務総額及びガバナンス問題については、全ての国で「深刻」あるいは「非常に深刻」とされている。
第Ⅱ-2-1-18表 アジア通貨危機における各国のぜい弱性の要因
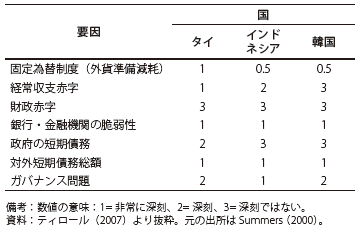
163 本段の論旨から外れてしまうが、パネルAに見られるように、2005年以来韓国の総対外債務残高の比率が上昇してきている。しかし、パネルBに見られるように、短期債務残高の割合は減少してきており、対外債務が長期の債務でファイナンスされるようになってきていることが分かる。
164 Ito(2001)を参照。
165 元ハーバード大学学長。米国財務長官、国家経済会議委員長も歴任。
166 オリジナルであるSummers (2000)の論文では、メキシコ通貨危機時におけるメキシコ、アジア通貨危機後に危機的状況に陥ることとなるロシアとブラジルについても分析対象に含められている。
各国事情
(タイ)
タイにおける危機は、事前にある程度予測されていた。IMFは、タイ経済が抱えるリスクへの懸念から、タイに対してより柔軟な為替制度(変動幅の拡大、変動相場制への移行)を求めていた167。タイでは、経常収支の対GDP比が▲8%を超える中、輸出が急減速したことにより、通貨の切下げ観測が台頭した。1997年5月12~14日には、ヘッジファンドによる大規模なバーツ売りが行われ、タイ政府は通貨防衛のため為替介入(先物市場でのドル売り・バーツ買い)及び資本規制を導入したものの、同年7月2日に変動相場制(管理為替フロート制)へ移行した。
その後、タイ政府はIMFに支援を求め、同年8月13日にIMFプログラムに大筋で合意した。しかし、タイ中央銀行の先物市場でのドル売りポジションが公表されると、IMFプログラムの合意内容では対処しきれないと市場に受け止められた。このため、IMFプログラムの発表後もバーツの下落は止まらず、為替レートを基準としてみる限り、IMFプログラムは有効に機能しなかった。
1997年12月にタイ政府が国内金融機関の再編を発表すると、タイ・バーツは、危機発生から対米ドルで約50%減価したところで下げ止まり、その後若干増価した後、1998年4月頃から安定して推移するようになった。為替の大幅な下落と深刻な景気後退によって、タイの経常収支は大きく改善し、その結果外貨準備が大きく積み上がっていった。そして、1999年8月、タイはIMFからの支援を停止することを決定した168。
タイにおける通貨危機発生の原因としては、マクロ・ファンダメンタルズのぜい弱性とその悪化、すなわち、経常収支赤字の持続可能性に疑問が持たれ、実体経済における輸出の伸び率及びGDP成長率の鈍化が背景にあったと考えられる169。
167 伊藤(2007)。
168 Sussangkarn and Vichyanond (2007)。
169 伊藤(1999b)。
(インドネシア)
アジア通貨危機が発生した当初、通貨ルピアは下落していたものの、それほど大きな影響を受けていたわけではなかった。しかし、インドネシア政府は予防的な措置として1997年10月、IMFへ支援を要請し、同年11月5日にIMFプログラムが理事会に承認された。このことが結果的に国内の政治問題とも絡み合って、インドネシア・ルピアの暴落を招くこととなる。
IMFプログラムにより短期的にインドネシア・ルピアの下落は止まったものの、長期的な効果はなかった。1998年1月15日には、IMFと追加的な合意がなされ、IMFは構造改革をインドネシアに対する信頼の回復の中心に据えた。しかし、このIMFのコンディショナリティには実効性に乏しいものまで含まれていた。その後、当時のスハルト大統領がIMFとの合意を実行する意思がないことを示唆すると、再びルピアは下落することとなり、結果的に、アジア通貨危機時において最も大きな通貨の下落に見舞われたのはインドネシア・ルピアであった170。
通貨危機が進行する中、インフレーションの高進や国内での暴動等によって、1998年5月、スハルト大統領は退陣することとなった。1999年6月、インドネシアでは初めてとなる民主的な選挙が行われ、同年10月にワヒド政権が発足した。その後、2001年7月にメガワティ大統領が就任し政情不安が収まると、インドネシア・ルピアの下落もようやく下げ止まることとなった。
170 より包括的な文献としてはHill and Shiraishi (2007)を参照。
(韓国)
タイで通貨危機が起こった後でも、韓国で通貨危機が起こるとはほとんど考えられていなかったが171、韓国の短期対外債務が外貨準備に比して巨額に上ることが認識されたことで金融危機に発展した。韓国の銀行は、日米欧の銀行から短期の借入れを行っていたが、上記事実が認識されると、日米欧の銀行は韓国の銀行の借換え(ロールオーバー)の要請を一斉に拒否するようになった。1997年11月下旬には韓国ウォンが急落することとなり、韓国政府はIMFへ支援を要請、同年12月4日、IMFプログラムが理事会に承認された。
韓国においても、韓国ウォンはIMFプログラム合意後も下落を続け、タイと同様に、為替レートを基準とするとIMFプログラムの実効性はほとんどないに等しかった。同年12月24日、IMFとG7諸国による緊急措置(日米欧の銀行に対する韓国向け貸出しの強制借換え(ロールオーバー))が行われることとなり、これによってようやくウォンの下落に歯止めがかかった。
韓国における通貨危機は、投資家のパニックによって引き起こされた流動性の危機であったという側面も見られる172。
アジア通貨危機後、これらアジアの国々は、危機を教訓としてファンダメンタルズの改善・強化に向けて様々な政策を採った。まず、為替に関して、アジアの多くの国は変動為替相場制へと移行した。よく知られているように、①固定為替相場制、②自由な資本移動、③独立した金融政策の3つを同時に実現することは不可能であり、これは国際金融のトリレンマ又はImpossible trinityと呼ばれている。
アジア通貨危機前のアジア各国で採用されていた政策は、この国際金融のトリレンマへの挑戦であったと見なすこともできる173。アジア通貨危機後、韓国、フィリピン、タイ、インドネシアは変動為替相場制へと移行した。これら各国は、自由な資本移動と独立した金融政策を継続する代わりに、固定為替相場を放棄した。つまり、第Ⅱ-2-1-17表で挙げたアジア通貨危機の共通要因の一つであった通貨の過大評価をもたらしたドル・ペッグを放棄したことになる。他方、1998年9月、マレーシアは資本の流出に対する規制を行った(第Ⅱ-2-1-19表参照)。
第Ⅱ-2-1-19表 国際金融のトリレンマに対する各国の対応
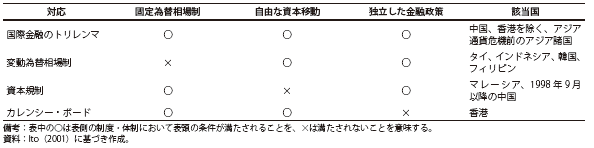
前掲第Ⅱ-2-1-17表でアジア通貨危機の共通要因の二つ目に挙げた金融システムのぜい弱性(ぜい弱な銀行・非銀行の監督)については、アジア通貨危機以降、アジア5か国で銀行の不良債権比率(商業銀行の融資残高に占める不良債権額)は低下傾向を示している。特に、タイやインドネシアでは、1998年時点で不良債権比率が40%を超えていたものが、2011年には2~3%弱まで激減した(第Ⅱ-2-1-20図)。
第Ⅱ-2-1-20図 不良債権の商業融資残高に対する比率の推移
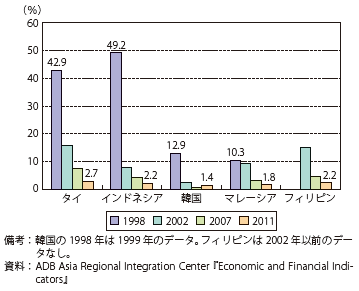
また、銀行の経営基盤の健全性を示すリスク調整後自己資本比率(自己資本/総資産)は多くのアジア諸国で上昇傾向を示している。インドネシアのみ低下傾向を示しているが、それでも他のアジア諸国と比較して相対的に高い水準を維持している(第Ⅱ-2-1-21図参照)。
第Ⅱ-2-1-21図 リスク調整後自己資本比率の推移
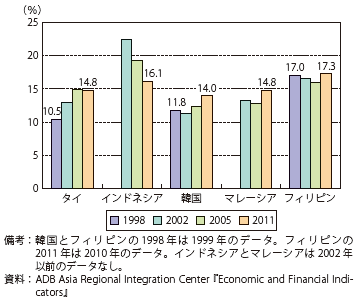
171 伊藤(2007)。
172 伊藤(1999b)、伊藤(2007)。
173 伊藤(1999b)。
(3)世界経済危機
世界経済危機は、2007年夏以降、前年からの米国の住宅価格下落(第Ⅱ-2-1-22図参照)によるサブプライム・ローンの焦げ付きによって仏大手銀行BNPパリバ傘下のファンドが凍結されたことに端を発し、2008年3月の米大手投資銀行ベア・スターンズの破綻・救済、同年7月のファニーメイ、フレディマックといったGSE(政府支援企業)の国有化、そして同年9月の米大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻、AIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)のFRBによる救済へと至る、世界的に金融市場が混乱した金融危機である174。
第Ⅱ-2-1-22図 S&Pケース・シラー住宅価格指数(20都市)の推移
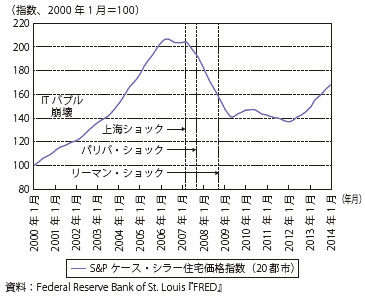
世界経済危機が発生した発端は米国のサブプライム・ローンの焦げ付きであったが、その影響は世界の金融市場に波及した。第Ⅱ-2-1-23図は、IMFの試算による、様々な資産クラスにおける市場のボラティリティ(変動性)の推移を示しており、緑色→橙色→赤色の順に、市場のボラティリティが高まっていることを表している。サブプライム・ローン問題が明るみに出ると、まずボラティリティはABS(資産担保証券)モーゲージで高まった。その後、2007年7~8月にかけてサブプライム・ローン問題の深刻さが認識されるとCMBS(商業用不動産担保証券)、金融機関、先進国市場とボラティリティが急激に高まり始め、米大手投資銀行ベア・スターンズが破綻した2008年3月頃からは、プライムのRMBS(住宅ローン担保証券)や企業信用に関わる市場のボラティリティが大きく高まり始めた。そして、2008年9月に米大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻すると、米国発の危機は新興国にまで飛び火し、新興国市場のボラティリティも上昇した。
第Ⅱ-2-1-23図 ボラティリティ・ヒートマップ
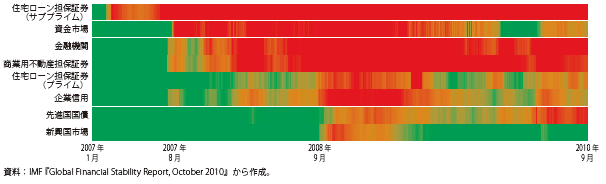
世界経済危機は、先進国である米国の住宅バブルの崩壊を根源としており175、その影響の規模と範囲からも上記2つの通貨危機とは異なる性格を有しているが、背後に金融システムの混乱があったということは共通している。
新興国自身の金融機関における証券化商品等の保有は限定的であったにも関わらず、欧米発の金融危機が新興国に飛び火したのは、欧米の金融機関が先進国と新興国における共通の貸手になっていたためである。そのため、欧米の金融機関におけるバランスシート圧縮の動きやリスク回避的な投資行動を通じて、新興国にも危機が伝播することとなった176。アジアを中心とした新興国は、過去の通貨危機の経験を教訓に、経常収支の黒字化(前掲第Ⅱ-2-1-13図参照)や「自己保険」としての外貨準備の積み増し(第Ⅱ-2-1-24図参照)等によって対外経済に関わるファンダメンタルズを改善していた177。しかしながら、2008年9月のリーマン・ショック以降、相対的に信用力の低い新興国は急激な資本流出に見舞われ、韓国やインドネシアのような海外からの資金調達に対する依存度が高まっていた国々では、通貨の大幅な減価や株価の急落、外貨準備の減少に直面した178。
第Ⅱ-2-1-24図 外貨準備高(期末値)の推移
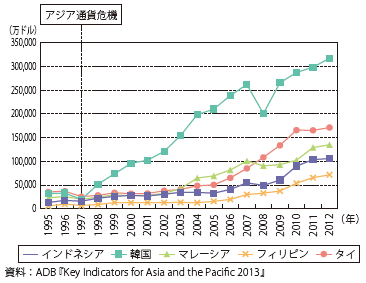
IMFのレポートによる第Ⅱ-2-1-25図は、新興国の対外的及び対内的ぜい弱性を散布図で表している。第Ⅱ-2-1-25図の縦軸には、経常収支の対GDP比、横軸には実質融資成長率のGDP成長率超過幅179がとられている(共に2010-12年の平均値)。図の第4象限に位置する国ほど対内・対外ともにぜい弱性が高いことを表しており、ブラジル、コロンビア、トルコといった国々が相対的に高いぜい弱性を抱えていることが分かる。
第Ⅱ-2-1-25図 新興国の対外及び対内ぜい弱性
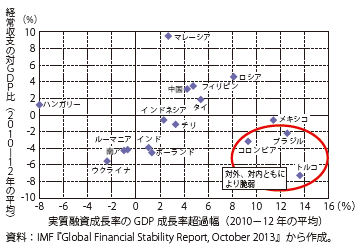
第Ⅱ-2-1-26図は、新興国におけるインフレ率、経常収支の対GDP比及びCDSスプレッドと対ドル為替レート変化率との関係を図示したものであるが、例えばパネルAによると、インフレ率が高い国ほど為替レートの減価率が大きい傾向があることが分かる。同様に、パネルBは、経常収支の対GDP比の赤字幅が大きいほど為替レート減価率も大きいという関係が緩やかながらも成立していることを示している。最後にパネルCはCDSスプレッドの拡大幅が大きい国ほど為替レートが大きく減価する傾向があることが見てとれる。
第Ⅱ-2-1-26図 新興国における最近の金融ストレス
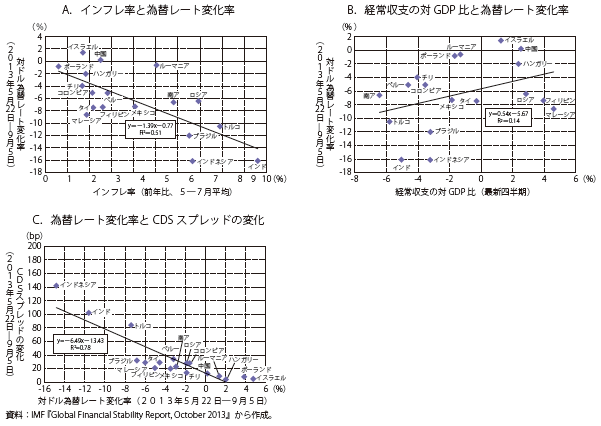
- Excel形式のファイル(A.インフレ率と為替レート変化率)はこちら

- Excel形式のファイル(B.経常収支の対GDP比と為替レート変化率)はこちら

- Excel形式のファイル(C.為替レート変化率とCDSスプレッドの変化)はこちら

多くの新興国では、過去の通貨・金融危機を教訓に、国内経済のファンダメンタルズの強化や対外的なショックに対する備えを進めてきているが、その進捗状況やそれぞれの国における政策の方向性・優先順位などには相違が見られ、そうしたことも背景となって、現在のリスク耐性や成長基盤の特徴となって表れてきている。
174 竹森(2007)は、アジア通貨危機からサブプライム問題へと続く金融危機の流れを整理している。
175 伊藤(2009)。
176 内閣府(2009b)。
177 伊藤(2007)。一見して分かるように、韓国の外貨準備高の増加が著しい。しかし、第Ⅱ-2-1-14図のパネルCで見たように、短期対外債務に対する比率で見ると、アジア諸国の中では相対的に低水準にとどまっている。
178 みずほ総合研究所(2009)。
179 GDP成長率を大きく上回る融資が続けば、経済の成長に見合う以上に信用が膨張しており、いわゆる資産バブル発生についての一つの尺度になると考えられる。
2.新興国等の経済ファンダメンタルズ
(1)リスク耐性分析
本段では、前項における過去の通貨・金融危機の経験を踏まえ、新興国を中心に各国が抱える内在的なリスク・ぜい弱性を指標化し、各国間の相対的なリスク耐性についてスコアリングすることを試みる180。以下ではまず、本節での分析と同様に、各国におけるリスク・ぜい弱性と金融危機との関連を分析した先行研究を幾つか概観する。
伊藤(2009)は、世界経済危機のアジア諸国への影響を分析している。伊藤(2009)によると、世界経済危機は、主に貿易を通じてアジア諸国へ影響を及ぼしたが、金融を通じた影響は一部の国(インドネシアや韓国)を除いて大きくなかったとされる。通貨の大きな下落を経験した国も一部にとどまり、世界経済危機のアジアへの伝播は軽微であった。また、通貨の下落と成長率の落ち込みの間には、ほとんど相関がなかったことが報告されている。この要因としては、アジア通貨危機以来、アジア諸国は金融セクターの健全化や外貨準備の蓄積によって対外的なショックからの耐性を高めており、金融面からの影響を最小限にとどめることができたとしている。
Goldstein and Xie(2009a)では、経済・金融データの中から66のぜい弱性指標を定義し(第Ⅱ-2-1-27表参照。赤枠で囲った指標は本稿における分析でも使用する指標若しくは内容が近いもの)、世界経済危機(2007-09年)時におけるアジア各国のぜい弱性について分析し181、様々なチャネルを通じたショックに対してぜい弱な国をランキングしている(第Ⅱ-2-1-28表参照)。また、その結果に基づき、総合的なぜい弱性ランキング指標(数値が低下するほどぜい弱性が高い)とGDP成長率の低下との間に正の相関関係があるとしている(第Ⅱ-2-1-29図参照)。Goldstein and Xie(2009a)の分析は、本稿における分析と最も関連が深いものと考えられる。
第Ⅱ-2-1-27表 ぜい弱性指標のリスト
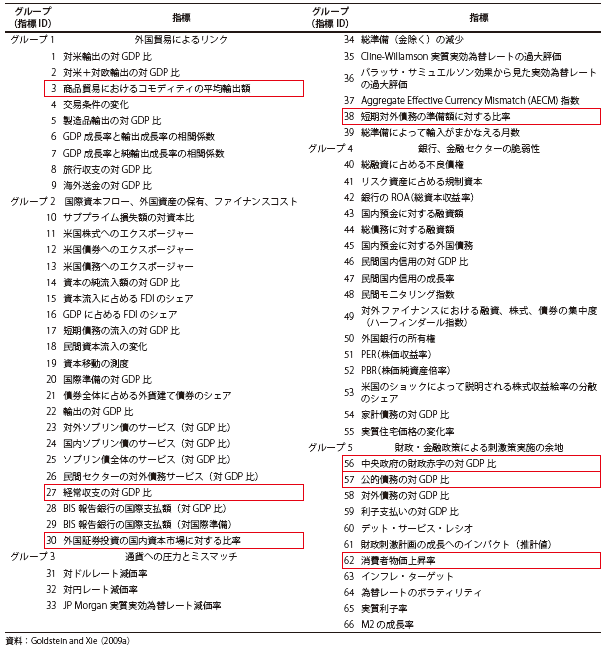
第Ⅱ-2-1-28表 各チャネルを通じたショックに対するぜい弱性ランキング
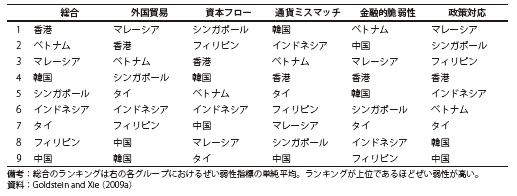
第Ⅱ-2-1-29図 GDP成長率の減速とぜい弱性指数との相関

180 ファンダメンタルズのスコアリング及び相対評価の方法については、付注6で述べられている。
181 Goldstein and Xie (2009b)も参照。
Board of Governors of the Federal Reserve System(2014)は、①経常収支の対GDP比率、②政府債務の対GDP比率、③過去3年間の平均インフレ率、④民間への銀行信用の対GDP比率の過去5年間の変化、⑤対外債務残高の輸出(年換算)に占める割合及び⑥外貨準備の対GDP比率の6つの指標から、ぜい弱性指標(vulnerability index)を構築し、新興国経済の足下におけるぜい弱性指標と為替レートの変化率の関係を分析している。当レポートは、ぜい弱性指標が高い(ぜい弱性が高い)ほど為替レートの減価率が大きいことを示しており、ファンダメンタルズの改善のために、幾つかの新興国では財政・金融政策及び構造改革の推進が必要とされると述べている。
それでは、以下で新興国を中心に各国に内在するリスク・ぜい弱性を評価した結果を見ていくこととする。指標の選択に当たっては、前項で見たように、過去の通貨・金融危機においてリスク・ぜい弱性の先行指標として考えられた代表的なファンダメンタルズ指標及び経済・金融指標を中心に選択した。リスク耐性指標として選択した指標の一覧は第Ⅱ-2-1-30表にまとめられている。本分析では、これまでの既存研究では余り採り上げられてこなかった「(輸出先の)国・地域の偏り」、「資源・一次産品依存」といった貿易構造におけるリスク・ぜい弱性、政府や経済・社会制度の質に関する「ガバナンス」といった指標も取り入れることとした。なお、以下では、スコアリングの上昇/低下を基準として、当該指標の改善/悪化ということがある。
第Ⅱ-2-1-30表 リスク耐性指標のリスト
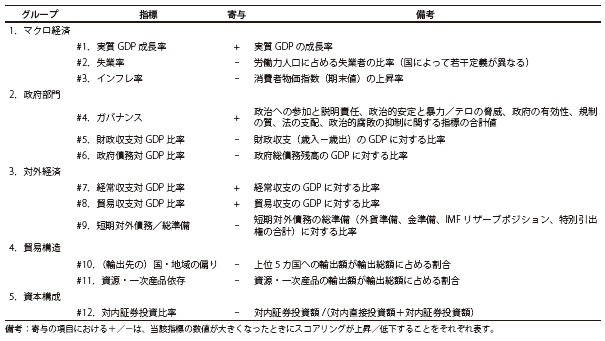
第Ⅱ-2-1-31図は、付注6で説明されている手続きに従って各国のリスク耐性指標をスコアリングし、結果をレーダーチャートによって表示したものである。
第Ⅱ-2-1-31図 リスク耐性指標のレーダーチャート
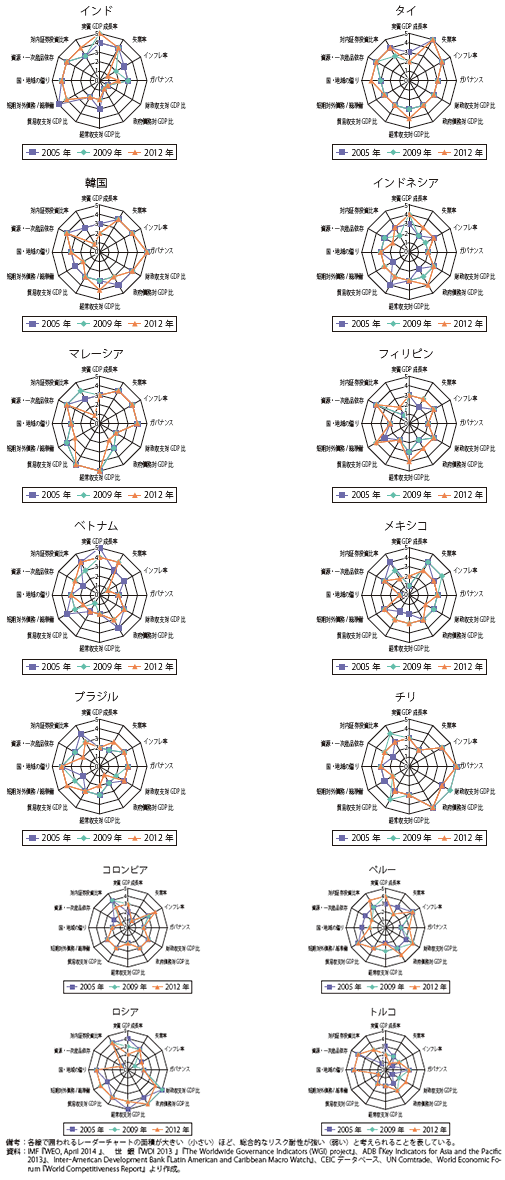
第Ⅱ-2-1-32表は、第Ⅱ-2-1-30表における5つのグループ182及び全体の合計6グループについて、各国のスコアの単純平均値を1~1.99、2~2.99、3~3.99、4~5に区分して示している。
第Ⅱ-2-1-32表 各グループにおけるリスク耐性指標の評価(スコアの単純平均値(2012年))
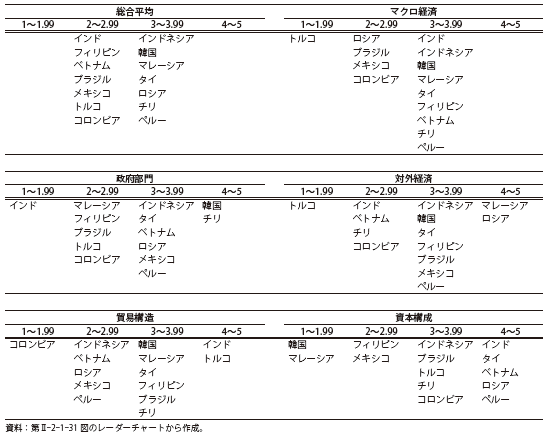
まず総合平均(各評価項目の単純平均値)の場合、全ての国が2~2.99若しくは3~3.99の間に位置しており、それぞれちょうど7か国ずつ分類される。2~2.99に位置する国は、インド、フィリピン、ベトナム、ブラジル、メキシコ、トルコ、コロンビアとなり、これらの国は、各指標を総合(平均)的に見ると、平均的なパフォーマンスを下回っていることとなり、外生的なショックに対して相対的にぜい弱であると考えられる。一方、3~3.99に位置する国は、インドネシア、韓国、マレーシア、タイ、ロシア、チリ、ペルーとなり、各指標を総合(平均)的に見ると、これらの国は外生的なショックに対して相対的に耐性が強いと考えられる。
各グループ別に見ると、それぞれのグループで最もスコアが低い部類に属するのは、マクロ経済と対外経済ではトルコ、政府部門ではインド、貿易構造ではコロンビア、資本構成では韓国及びマレーシアとなる。反対に、最もスコアが高い部類に属するのは、マクロ経済では4以上のスコアの国はなく、3~3.99の間に9か国が集中しており、アジア諸国は全てこの区分に該当し、中南米諸国からはチリとペルーが該当する。政府部門では韓国とチリ、対外経済ではマレーシアとロシア、貿易構造ではインドとトルコ、資本構成ではインド、タイ、ベトナム、ロシア及びペルーが相対的に高いスコアを示している。
以下では、各国の個別のファンダメンタルズの時系列的な変化について、特徴的な点を述べることとする。アジア諸国(特に、ASEAN諸国)及び中南米諸国(特に、ブラジルとメキシコ)については、後節でより詳細に議論する。
182 各グループはそれぞれ、マクロ経済(実質GDP成長率、失業率、インフレ率)、政府部門(ガバナンス、財政収支対GDP比、政府債務対GDP比)、対外経済(経常収支対GDP比、貿易収支対GDP比、短期対外債務/総準備)、貿易構造(国・地域の偏り、資源・一次産品依存)、資本構成(対内証券投資比率)と定義している。
対外経済指標
まず、メキシコ通貨危機及びアジア通貨危機の際に重視された指標の一つである経常収支赤字(対GDP比)を取り上げる。アジア通貨危機に見舞われたアジア5か国(タイ、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン)では、第Ⅱ-2-1-33表に見られるようにおおむね経常収支対GDP比が改善傾向、あるいは相対的に良好なパフォーマンスを示している。タイ、韓国及びフィリピンは、2005年の3から2012年には4にスコアが上昇している。また、マレーシアは、一貫して最高評価の5となっている。これらの国々では、アジア通貨危機後、景気の悪化による輸入の減少、為替レートの減価による輸出の拡大等も相まって、急速に経常収支が改善した。メキシコにおいても、2005年から2009年にかけてスコアが2から3に改善し、2012年も3の評価を維持している。一方、インド、ベトナムといったアジア諸国、ブラジル、コロンビア、ペルーといった中南米諸国、欧州近隣諸国ではトルコといった国々では、2005年から2012年にかけて、経常収支対GDP比が悪化、あるいは相対的に悪いパフォーマンスが継続している。
第Ⅱ-2-1-33表 経常収支対GDP比のスコアの推移
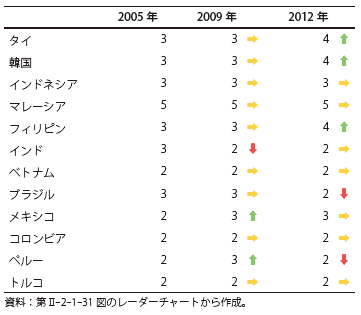
同じく過去の通貨危機の際に短期対外債務の深刻さを測る指標として注目された短期対外債務/総準備のスコアの推移を見ると(第Ⅱ-2-1-34表)、アジア諸国では韓国、マレーシア、ベトナム、中南米諸国ではチリが2005年時よりも相対的なパフォーマンスが悪化している183。また、トルコは一貫してスコアが1となっており、比較国中最も低いパフォーマンスが続いている。一方、ブラジルは2005年の2から1ポイントずつスコアを上げてきており、2012年では相対的に健全であると評価される4となっている。インドネシア及びフィリピンも、2005年と比較して、2012年時点でスコアを1ポイント上昇させている。
第Ⅱ-2-1-34表 短期対債務/総準備のスコアの推移
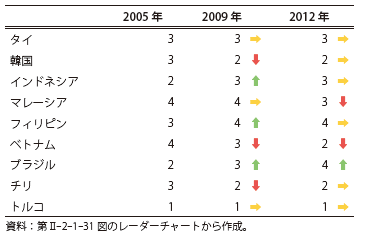
183 石川(2009)、森川(2011)も参照。
政府部門指標
続いて、財政収支対GDP比のスコアを比較してみると(第Ⅱ-2-1-35表)、多くのアジア諸国は、2005年以降、一定のスコアを維持している。2012年時点でマレーシア、ベトナム及びインドのスコアが2以下となっている。マレーシアは財政再建に向けた取り組みを始めているものの、2005年以降、スコアが2を継続している。ベトナムは2009年から2012年にかけてスコアが3から2へ低下している。最も評価が低いのはインドであり、手厚い農業支援等による補助金の増加等によって慢性的な財政赤字体質となっていることもあり184、2005年以降、一貫してスコアが1となっている。一方、ブラジル、トルコでは改善の傾向が見られる。
第Ⅱ-2-1-35表 財政収支対GDP比のスコアの推移
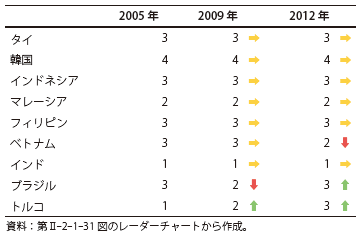
政府債務対GDP比の比較では(第Ⅱ-2-1-36表)、2012年時点で、インド、ブラジルが最低評価の1となっている。マレーシアは先に見たように財政収支対GDP比が改善していないことを反映して、2009年から2012年にかけて3から2にスコアが低下している。また、韓国では、2005年から2009年にかけてスコアが4から3へと低下している。一方、インドネシアは比較年ごとにスコアを上げてきているほか、フィリピンも2012年に2から3へとスコアを上げている。
第Ⅱ-2-1-36表 政府債務対GDP比のスコアの推移
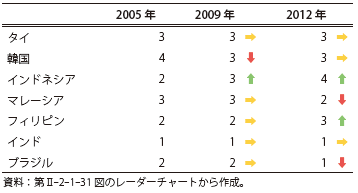
184 内閣府(2012)。
マクロ経済指標
続いて、失業率とインフレ率について概観する。まず、失業率の推移を見ると(第Ⅱ-2-1-37表)、チリ、コロンビア、ペルー及びトルコの4か国のスコアが2以下となっており、中南米諸国に相対的に失業率が高い国が多く見られる。2012年時点で、相対的に最もパフォーマンスの悪い国はコロンビアとトルコであり、2005年以降、両国とも慢性的に10%前後の失業率が継続している。
第Ⅱ-2-1-37表 失業率のスコアの推移
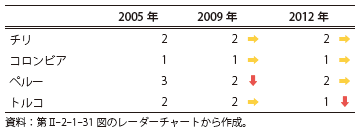
次に、インフレ率の推移を比較してみると、インフレ率はここで取り上げた多くの国で安定的に推移しているが、第Ⅱ-2-1-38表に見られるように、2012年時点で、インド、ベトナム、ロシア及びトルコの4か国においてスコアが2以下となっている。特に、ベトナムは2005年から2009年にかけて2ポイント下落している。近年、インドやベトナムでは、利上げや物価抑制策によってインフレ率の安定化を図っているが、相対的に高いインフレ率が継続している。逆にインフレ率が改善傾向を示しているのがロシアとトルコである。ロシアは、2009年までは2桁のインフレ率を記録する年が多かったが、近年、インフレは鎮静化に向かっている。また、ブラジルも、1980年代後半から1990年代前半までは年率2,500%(消費者物価、期末値)に迫るハイパー・インフレーションを経験したが、1990年代半ば以降、インフレ率は比較的穏やかに推移している。
第Ⅱ-2-1-38表 インフレ率のスコアの推移
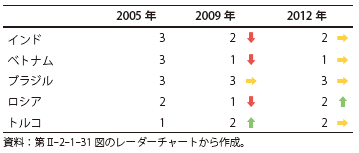
貿易構造指標
続いて、輸出の資源・一次産品への依存度を見ると(第Ⅱ-2-1-39表)、2012年時点でスコアが2以下なのは、インドネシア、ブラジル、コロンビア、ペルー、ロシアの5か国であり、中南米諸国に多く見られる。インドネシア、ブラジル、コロンビア、ペルーはいずれも、2005年と比較してスコアが悪化しており、資源・一次産品への依存度が相対的に高まっている。最もスコアが低いのはロシアで、2005年から通時的にスコアが1となっており、石油に代表される一次産品輸出に依存する貿易構造となっている。
第Ⅱ-2-1-39表 資源・一次産品依存のスコアの推移

国・地域(輸出先)の偏りは、フィリピン、メキシコ、コロンビア、ペルーが2012年時点で2以下のスコアを記録しており、輸出の資源・一次産品への依存と同様に、中南米諸国が多い(第Ⅱ-2-1-40表)。アジア諸国の中では唯一フィリピンが2以下を記録しているが、この背景には、フィリピンが他のアジア諸国と比べて日本及び米国への輸出が相対的に高くなっていることがある。国・地域(輸出先)の偏りが最も顕著なのはメキシコであり、NAFTAの締結による米国との結び付きが非常に強く、2012年時点で輸出額の8割弱が米国向けとなっている。
第Ⅱ-2-1-40表 (輸出先の)国・地域の偏りのスコアの推移
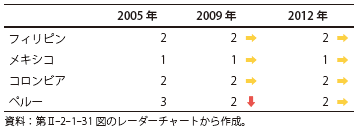
資本構成指標
最後に、対内証券投資比率のスコアの推移を見ると(第Ⅱ-2-1-41表)、2005年と比較して、2012年にはアジア諸国では韓国とマレーシア、中南米諸国ではメキシコにおいてスコアが2ポイント以上低下している。過去の通貨・金融危機発生時にも急速な資本逃避が生じたように、足の速い証券投資への依存度が高い場合、資本逃避が生じたときの影響が大きくなり、国際金融市場が混乱するような事態に陥った際にリスクを内包する経済構造であると考えられる185。一方、トルコは2005年時のスコアは1であったが、同期間においてスコアが2ポイント以上上昇し、対内証券投資への依存度を低下させている。
第Ⅱ-2-1-41表 証券投資比率のスコアの推移
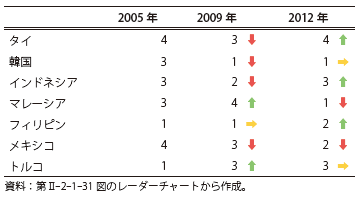
第Ⅱ-2-1-42図は、以上で構築された各国のリスク耐性指標と国債の信用格付との間の相関係数を示している186。国債の信用格付と最も相関が高いのはガバナンス指標で0.88という大きな正の値(ガバナンスがぜい弱なほど国債格付が低い)となっている。政府部門及び対外経済とは正の相関を示しているが関係は緩やかである(0.26~0.28)。一方、資本構成とは緩やかながら負の相関(対内証券投資比率が高いほど国債格付が高い)を示している。これは、証券投資比率が相対的に高い国は短期的に資本が多く流入してきている一種のブーム状態にあると考えれば、そのような国の格付が高くなりやすい傾向にあることを意味している。
第Ⅱ-2-1-42図 リスク耐性指標(2012年)と国債の信用格付との相関
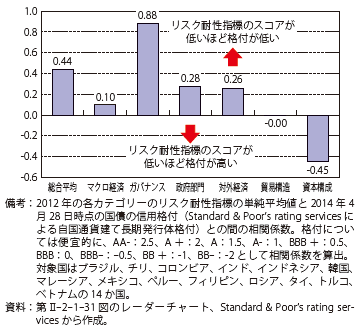
185 石川(2009)、森川(2011)も参照。
186 ここでは、政府部門の中の指標からガバナンスのみを取り出している。
(2)成長基盤分析
前段では、各国が抱える内在的なリスク・ぜい弱性を指標化し評価・分析を行った。次に本段では、各国の成長基盤に焦点を当て前段と同様のスコアリングによる評価・分析を試みる。各国の将来の成長基盤指標として選択した指標の一覧は第Ⅱ-2-1-43表にまとめられている。指標の選択に当たっては、既存研究を参考にしつつ、多角的な観点から中・長期的な経済の成長・開発と相関が高いと考えられる指標を選択した。
第Ⅱ-2-1-43表 成長基盤指標のリスト
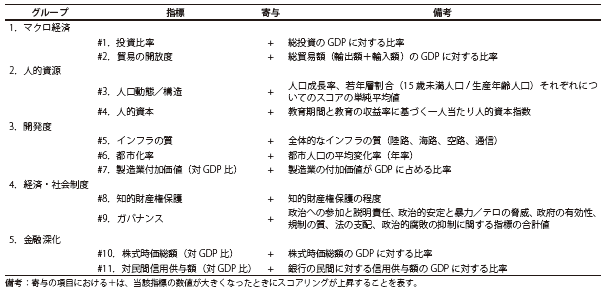
第Ⅱ-2-1-44図は、リスク耐性指標のスコアリングと同様に、各国の成長基盤指標についてスコアリングした結果をレーダーチャートによって表示している。
第Ⅱ-2-1-44図 成長基盤指標のレーダーチャート
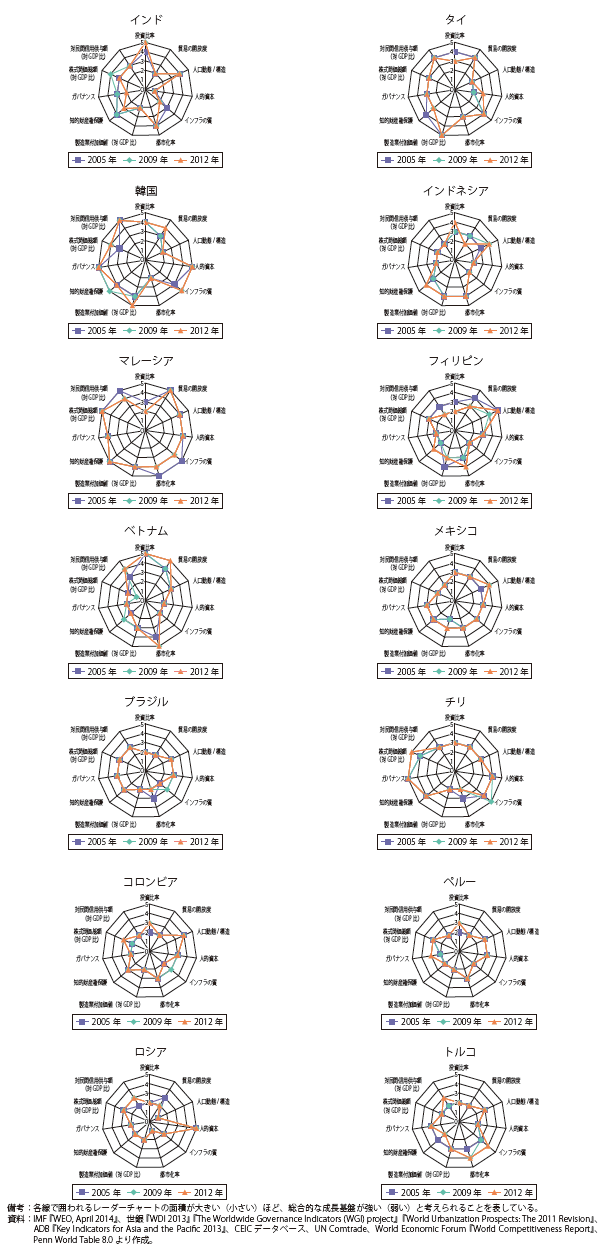
第Ⅱ-2-1-45表は、第Ⅱ-2-1-43表における成長基盤指標を5つのグループ187と指標全体の合計6グループについて、各国のスコアの単純平均値を1~1.99、2~2.99、3~3.99、4~5に区分して示している。
第Ⅱ-2-1-45表 各グループにおける成長基盤指標の評価(スコアの単純平均値(2012年)
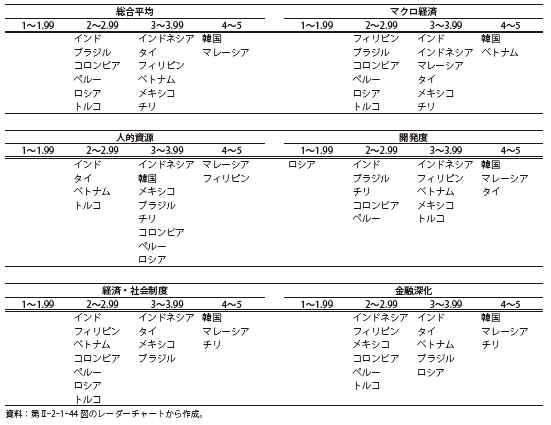
総合平均(各評価項目の単純平均値)の場合、ほとんどの国が2~2.99及び3~3.99の間に位置しているが、韓国とマレーシアは4以上のスコアとなっている。2~2.99の間には、インド、ブラジル、コロンビア、ペルー、ロシア及びトルコの6か国が該当する。中南米諸国及び欧州近隣諸国が多くなっている。一方、3~3.99の間には、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、メキシコ及びチリの6か国が該当し、これらの国々は相対的に成長基盤が強いと評価される。アジアの国々の多くがこの区分に該当し、中南米諸国からはメキシコとチリが該当する。
各グループ別に見ると、それぞれのグループで最もスコアが低い部類に属するのは、マクロ経済ではフィリピン、ブラジル、コロンビア、ペルー、ロシア及びトルコ、人的資源ではインド、タイ、ベトナム及びトルコ、開発度ではロシア、経済・社会制度ではインド、フィリピン、ベトナム、コロンビア、ペルー、ロシア及びトルコ、金融深化ではインドネシア、フィリピン、メキシコ、コロンビア、ペルー及びトルコとなる。反対に、最もスコアが高い部類に属するのは、マクロ経済では韓国とベトナム、人的資源ではマレーシアとフィリピン、開発度では韓国、マレーシア及びタイ、経済・社会制度及び金融深化では韓国、マレーシア及びチリとなる。
第Ⅱ-2-1-46図は、各国の成長基盤指標の各グループと一人当たり実質GDP(PPP換算)との間の相関を、2005年、2009年及び2012年それぞれについて見たものである。期間を通じて、一人当たり実質GDP水準と正の相関を示しているのは人的資源、経済・社会制度及び金融深化であり、マクロ経済及び開発度とはほとんど相関が見られない。人的資源や経済・社会制度の中には経済成長の源泉となる人口成長率や人的資本の蓄積、法の支配の強さ等が含まれており、経済成長に関する研究分野で重要視されている変数との相関が緩やか~中程度観察される。金融深化との相関は年を追うごとに上昇してきており、経済の成長・発展にとって市場あるいは銀行を通じた金融環境の発達といった要因の重要性がより高まってきていることを示唆する188。総合平均との相関は全期間において約0.2~0.3で一定となっている。
第Ⅱ-2-1-46図 新興国の成長基盤指標と一人当たり実質GDP (PPP換算)との相関
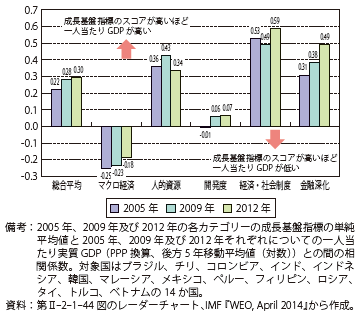
近年、経済成長理論の分野では、一国の経済成長・開発に対して政治・経済的制度が果たす役割を強調する研究が注目を集めている189。そこで以下では、より詳細にガバナンス指標に焦点を当て、各国の経済成長・開発との関係を見ていく。
第Ⅱ-2-1-47表は、上の分析でも用いた世界銀行が算出・公表している各国・地域における6つのガバナンス指標の内訳(「政治への参加と説明責任」、「政治的安定と暴力/テロの脅威」、「政府の有効性」、「規制の質」、「法の支配」、「政治的腐敗の抑制」)とその定義を一覧にして示している。
第Ⅱ-2-1-47表 各ガバナンス指標の定義
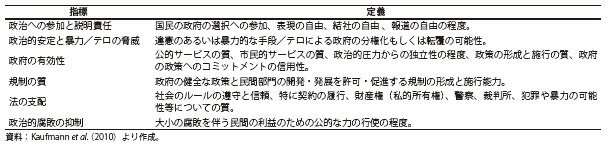
第Ⅱ-2-1-48図は、各ガバナンス指標について一人当たり実質GDP(PPP換算)との相関関係を図示している190。政治への参加と説明責任(パネルA)及び政治的安定と暴力/テロの脅威(パネルB)については一人当たり実質GDPと有意な関係が見いだされなかったが、その他の4指標(パネルCからパネルF)については一人当たり実質GDPと有意な正の関係が見いだされた。一人当たり実質GDPと最も相関が高いガバナンス指標は規制の質(0.732)、続いて政府の有効性(0.654)となり、政府の統治能力が経済の成長にとって重要な要因として機能していることがうかがわれる191。
第Ⅱ-2-1-48図 ガバナンス指標と一人当たり実質GDP(PPP換算)との間の相関関係
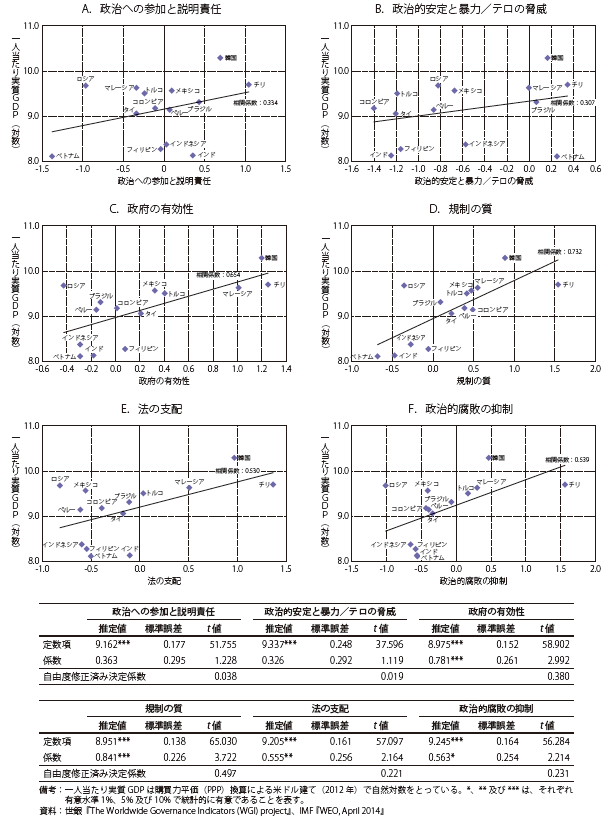
- Excel形式のファイル(A.政治への参加と説明責任)はこちら

- Excel形式のファイル(B.政治的安定と暴力/テロの脅威)はこちら

- Excel形式のファイル(C.政府の有効性)はこちら

- Excel形式のファイル(D.規制の質)はこちら

- Excel形式のファイル(E.法の支配)はこちら

- Excel形式のファイル(F.政治的腐敗の抑制)はこちら

187 各グループはそれぞれ、マクロ経済(投資比率、貿易の開放度)、人的資源(人口動態/構造、人的資本)、開発度(インフラの質、都市化率、製造業付加価値(対GDP比))、経済・社会制度(知的財産権保護、ガバナンス)、金融深化(株式時価総額(対GDP比)、対民間信用供与額(対GDP比))と定義している。
188 金融深化(銀行及び市場を通じた金融の発達)が経済成長を促進することについては、Beck and Levine(2004)、岡部・光安(2005)でもより広範なサンプルを用いた回帰分析のもとで示されている。
189 例えば、福味(2006)、Acemoglu et al. (2003)、Acemoglu et al. (2005)、Rigobon and Rodrik (2005)、Rodrik et al. (2004)を参照。また、「中所得国の罠」の観点から、制度と経済成長の関係を分析したものとして山澤(2013)がある。
190 ガバナンス指標の概要、算出方法等については、Kaufmann et al. (2010)で解説されている。
191 もちろん、一人当たり実質GDPが高くなるほど政治的安定が促されるという逆の因果関係も考えられる。また、本文における結果は、現在分析対象としている14か国に限定した場合の結果であり、サンプルに含まれる国の変更等によって結果が変わりうることに留意。
(3)リスク耐性と成長基盤の双方から見る経済ファンダメンタルズ
リスク耐性指標を横軸に、成長基盤指標を縦軸にとって、2005年、2009年及び2012年それぞれについて散布図を描いたのが第Ⅱ-2-1-49図のパネルAからパネルCである。リスク耐性指標及び成長基盤指標それぞれの平均である3を中心とした散布図を見ると、右上の領域は相対的にリスク耐性が強く成長基盤も強い国、左上の領域は相対的にリスク耐性は弱いが成長基盤は強い国、左下の領域は相対的にリスク耐性が弱く成長基盤も弱い国、右下の領域は相対的にリスク耐性は強いが成長基盤は弱い国となる。
第Ⅱ-2-1-49図 リスク耐性指標と成長基盤指標の散布図
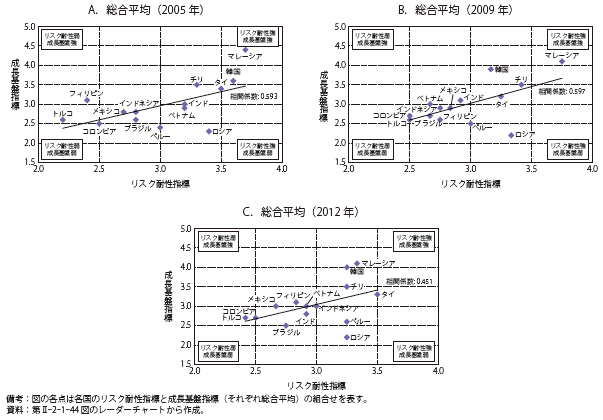
リスク耐性指標と成長基盤指標の間の相関係数は、2005年時点(パネルA)では0.593、2009年時点(パネルB)では0.597、2012年時点(パネルC)ではやや相関が低下し0.451となっている。したがって、リスク耐性が強い国の方が成長基盤も強く、リスク耐性が弱い国の方が成長基盤も弱いという基本的な傾向が観察される。また、2005年時点(パネルA)では各新興国を表す点が比較的散らばって位置しているが、年を追うごとに各点が中心付近に寄ってきていることが確認できる。
より詳細に各国の動向を追跡するために、第Ⅱ-2-1-50図は前掲第Ⅱ-2-1-49図のパネルAからパネルCを一つの図に重ね合わせ、各国について時系列の推移を線で結んでプロットしたものである。この図によると、幾つかの国の位置が時間を通じて大きく動いていることが分かる。
第Ⅱ-2-1-50図 リスク耐性指標と成長基盤指標の散布図(2005~12年)
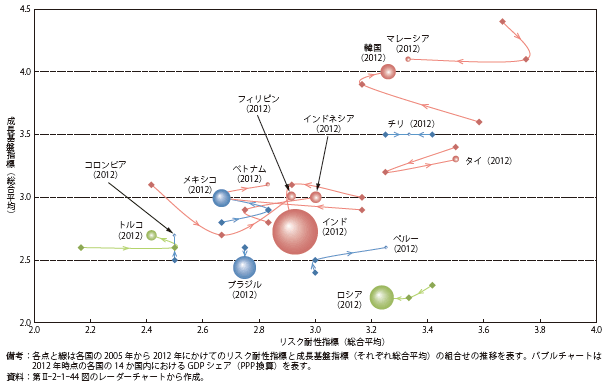
まず悪化傾向を示している国であるが、リスク耐性指標については、2005年時点からマレーシア、韓国、ベトナム、インドが比較的大きいスコアの低下を示している。成長基盤指標については、マレーシアとインドで2005年時点から比較的大きくスコアが低下している。マレーシアは両指標ともに悪化しているが、依然として最も右上の領域に位置している。
一方、改善傾向を示している国もある。リスク耐性指標については、2005年時点と比較してインドネシア、フィリピン、ペルー、トルコで比較的大きくスコアが改善している。成長基盤指標については、唯一韓国が比較的大きなスコアの改善を示しており、2005年時点より改善している国としては、ベトナム、メキシコ、ペルー、トルコが挙げられる。トルコは両指標ともに改善しているが、依然として最も左下の領域に位置している。
全体的に見ると、アジア諸国の多くは中心付近から右上の領域に多く分布しており、反対に、中南米諸国は中心付近から左下に比較的多く分布しており、唯一「南米の優等生」と言われる192チリのみが右上の領域に位置している。また、当初相対的に右上に位置していた国は左~左下へ、相対的に左下に位置していた国は右~右上へ移動している。つまり、2005~12年の期間、元々相対的にリスク耐性が強かった国のリスク耐性は低下し、相対的にリスク耐性が弱かった国のリスク耐性は改善しているという傾向も読み取れる。
加えて、近年、ぜい弱性が指摘されている国々193は、図の中心付近から左下に位置しており、リスク耐性が相対的に弱いだけでなく成長基盤も相対的に弱くなっている。
192 例えば、西川(2014)。
193 特にインド、インドネシア、ブラジル、トルコ及び南アフリカ(本分析には含まれていない)の5か国。