第2節 アジア通貨危機後の韓国における構造改革
以下では、経済の構造改革によってファンダメンタルズ及び成長基盤の強化を進めた事例としてアジア通貨危機後に韓国で行われた改革について見ていく。
1.マクロ経済状況の改善
アジア通貨危機発生後、マクロ経済的には、韓国は、タイやインドネシアなどアジア通貨危機に見舞われた他の国々と比較して、経済の落ち込みから早期に回復した。1998年代半ば、韓国はIMFによって課せられた緊縮的なコンディショナリティ(第Ⅱ-2-2-1表参照)から拡張的な財政・金融政策にスタンスを転換し、これによるマクロ経済政策及び構造改革プログラムが回復に大きく寄与した。また、1998年は落ち込んだものの、為替の減価によって輸出が早期に回復したことも追い風となった。第Ⅱ-2-2-2図は、財・サービスの輸出(2005年価格基準の実質)の伸び率の推移を表しているが、この時期の韓国の輸出は、同じアジア通貨危機に見舞われたタイや同時期の日本よりも高い伸びを示している。
第Ⅱ-2-2-1表 IMFのコンディショナリティ
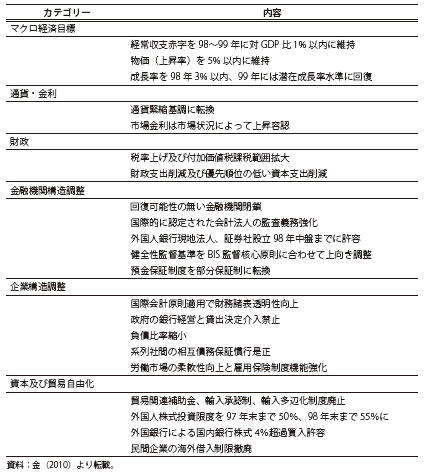
第Ⅱ-2-2-2図 韓国の財・サービスの輸出伸び率の推移(タイ、日本との比較)
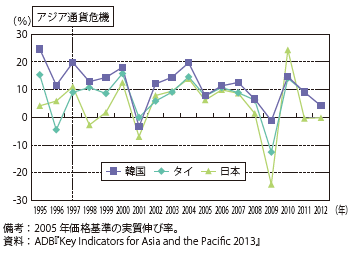
第Ⅱ-2-2-3図は韓国における失業率の推移を示している。アジア通貨危機前年の1996年には2.0%であったが、アジア通貨危機発生直後の1998年には7.0%まで悪化しており、わずか2年で5.0%ポイントも上昇している。しかし、翌年の1999年には低下に転じ、2000年には急速に改善し4%まで低下している。その後2002年に更に低下した後はほぼ横ばいで推移しており、アジア通貨危機前の水準よりは高いものの、2012年時点では3.2%となっている。
第Ⅱ-2-2-3図 韓国の失業率の推移
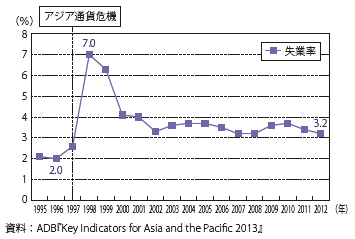
2.構造改革の推進
アジア通貨危機発生直後、韓国政府は、不良債権、過剰供給能力、財閥のオーバー・レバレッジの問題に取り組み、これが金融機関や企業が抱える様々な問題の解決に寄与した194。アジア通貨危機の最中に発足した金大中政権は、IMFによるコンディショナリティと平行して、国内経済の四大改革を推し進めた。四大改革とは、金融部門、企業(財閥)部門、労働市場及び公共部門における4つの改革のことである。以下では、金融、企業(財閥)、労働市場における改革について見ていく。
(金融部門)
金融部門においては、巨額の不良債権を抱えた銀行を中心とした金融システム全体について、経営基盤の健全化と業界再編のための改革が行われた。その特徴としては、①大規模な再編による集約化、②外資の出資比率の上昇、③米国型のコーポレート・ガバナンスの採用が挙げられる195。
アジア通貨危機発生後から2001年末までに、韓国政府は、銀行が抱える不良債権の処理及び自己資本の拡充による体力の回復のために、GDP比で30%に上る155.3兆ウォンの公的資金を投入した。このような巨額の財政出動を行うことができた背景としては、アジア通貨危機前から健全財政を維持していたことが挙げられる(第Ⅱ-2-2-4図参照)。金融監督院は、公的資金投入に当たって、BISの基準である8%以上という条件を満たしているかどうかを検査し、この条件を満たさない銀行は他の銀行に合併されることとなった。この公的資金の投入によって、前掲第Ⅱ-2-1-20図で見たように、銀行の不良債権比率(不良債権の商業融資残高に対する比率)は大きく減少した。また、不良債権処理については、アジア通貨危機後に政府資金のファイナンスのために設立された資産管理公社(KAMCO:Korea Asset Management Corporation)による買取りが順次進められた。このようにアジア通貨危機後の韓国における金融部門の健全化には、政府主導による迅速な整理・統廃合が大きく寄与し、銀行業界の集約化が進んだ。
第Ⅱ-2-2-4図 韓国の財政収支対GDP比の推移
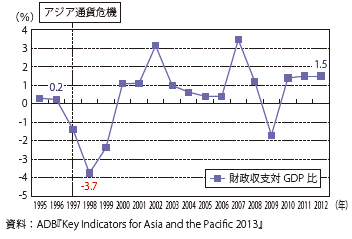
また、アジア通貨危機後、欧米金融機関の韓国市場への進出が拡大したことによって、金融機関における外資の出資比率が高まることとなった。さらに、米国型のコーポレート・ガバナンスを採り入れたことによって、大規模な企業や金融機関では、社外取締役を中心とする諸委員会の設置が義務付けられることとなった196。
195 高(2008)。
196 高(2008)。
(企業(財閥)部門)
韓国では「ビッグ・ディール」と言われる財閥企業に対する構造改革が断行された。金大中大統領は財閥がアジア通貨危機の発生の主因であるとみなし、財閥企業に対して、①過剰債務の解消(財務リストラ)②過剰多角化の解消(事業リストラ)による選択と集中(いわゆる「ビッグ・ディール」)及び③コーポレート・ガバナンスの強化を求めた197。
①の過剰債務の解消について、アジア通貨危機発生直後の1998年の第4四半期には、30大財閥の負債比率は約519%に達していた198(第Ⅱ-2-2-5図参照)。金大中政権は30大財閥に対して、1999年末までに負債比率を200%以下に低下させることを求めた。また、財閥企業は、銀行から融資を受ける際に系列企業間で債務保証を行っていたが、金大中政権は2000年3月までにすべての系列企業間での債務保証を解消することを求めた199(第Ⅱ-2-2-5図参照)。
第Ⅱ-2-2-5図 韓国の30大財閥の主要経営指標
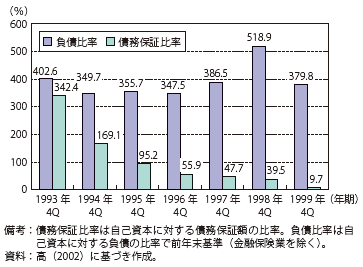
197 高(2002)、高(2008)。
198 一般に、負債比率は50%以上になると経営の健全性が損なわれると言われる。
199 高(2002)。
②の過剰多角化の解消による選択と集中について、金大中政権は政府主導の政策によって、多角化した財閥企業の事業に対して選択と集中による大規模な事業集約(いわゆる「ビッグ・ディール」)を断行した。最終的に、半導体、鉄道車両、精油、発電設備、船舶用エンジン、航空機、石油化学、自動車、電子部門の9業種で事業集約が進められ、鉄道車両、精油、発電設備、船舶用エンジン、航空機では1999年までに事業集約が完了した200。この選択と集中による集約化によって、それれの市場は1~2社に集約された。この結果、1社当たりの市場規模を日本と比較すると、乗用車1.5倍、鉄鋼1.5倍、携帯電話2.2倍となっている(携帯電話は2009年見込み。その他は2008年実績)201。このように、「ビッグ・ディール」によって財閥企業の経営・財務状況が改善し、これが競争力の基盤の一つとなっている202。
業界再編は財閥企業以外でも進んだ。特に繊維・アパレル、金融、建設といった業種で非効率な企業の市場とう汰が進み、繊維・アパレルと金融では上場企業数が約3割、建設部門では約2割減少した203。
③のコーポレート・ガバナンスの強化について、金大中政権は、IMFからの勧告によって、敵対的買収を容認することとなった204。その結果、アジア通貨危機以降、韓国の30大財閥の株式の内部所有比率は、創業者一族が保有する割合が低下した一方、系列企業における保有割合が上昇することとなった(第Ⅱ-2-2-6図参照)。また、企業経営の透明性の向上を図るため、少数株主権行使要件の緩和や社外取締役制度の導入・拡大など、各種のコーポレート・ガバナンスに関わる改革を行った205。
第Ⅱ-2-2-6図 韓国の30大財閥の株式の内部所有比率
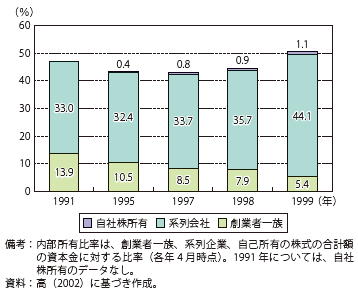
200 高(2002)。
201 佐野(2011)及び経済産業省(2010)。
202 「ビッグ・ディール」により、独占市場や寡占市場が現れることとなり、自由な市場での競争が制限され、割高な国内価格や下請への不当行為など独占によるゆがみも指摘されている(佐野(2011))。
203 佐久間(2002)。
204 高(2002)。
205 高(2008)によれば、主要な財閥を中心としてコーポレート・ガバナンスに関わる法令違反が相次いでおり、コーポレート・ガバナンスに関する改革には依然課題が残っている。
(労働市場)
韓国はもともと、非常用雇用については柔軟な労働市場を持っていたが、常用雇用者についても、1998年2月、政府、企業、労働組合の三者協調路線の下、真にやむを得ない経営存続上の理由がある場合には常用雇用者の解雇も認めるという内容の合意が行われ、労働市場の柔軟性が以前より高まることとなった。上で述べた「ビッグ・ディール」等の事業集約化は失業の増加という副作用をもたらしたが、非常用雇用の増加が一部吸収したと考えられる。また、政府は失業者の再就職のための政策として再就職訓練プログラムを実施し、雇用対策に費やされた財政負担はGDP比で7%に上った206。
第Ⅱ-2-2-7図は、韓国における産業別従業者数の推移を1997年、2002年、2005年及び2009年の4時点について示している。アジア通貨危機が発生した1997年から構造改革が行われた2002年にかけては、農林水産業、建設のほか、繊維をはじめとする多くの製造業種で従業者が減少している。代わりに大きく雇用を伸ばしているのは、レンタル・対事業所サービス、教育、医療・社会福祉、その他対個人サービスといったサービス業であり、これらの産業が構造改革によって増加した失業者を吸収したと考えられる。また、2002年以降は、電気・精密機器、輸送用機器、卑金属、ゴム・プラスチックといった製造業種では従業者数が増加しており、製造業においても一定程度雇用が維持されている。
第Ⅱ-2-2-7図 韓国の産業別従業者数の推移
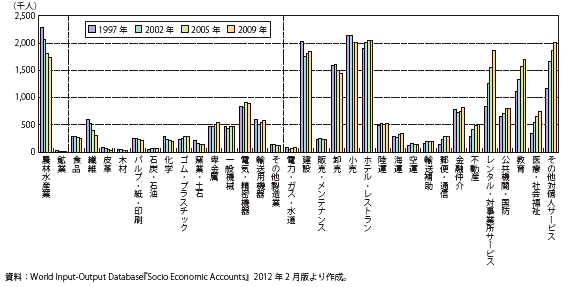
206 佐久間(2002)。
(対外開放戦略)
以上のように、アジア通貨危機以降、韓国は金融、企業(財閥)、労働市場といった国内経済の主要なセクターにおいて、各種の構造改革を断行してきた。これらは国内経済に関わるものであるが、韓国のアジア通貨危機以降における政策で注目に値するのが、積極的な対外開放戦略である。韓国は国内市場が比較的小さいこともあり、アジア通貨危機以降、対外開放路線を推し進めると同時に、積極的にFTAの締結を推進してきた。第Ⅱ-2-2-8表は、韓国のFTA締結の状況をまとめたものである。
第Ⅱ-2-2-8表 韓国のFTAの締結状況
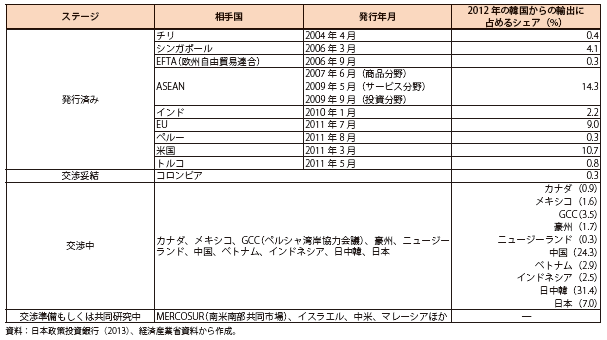
(規制緩和の推進)
アジア通貨危機以降、金大中政権は、市場参入障壁の撤廃や外資参入規制の緩和といった規制緩和策も積極的に実施した。第Ⅱ-2-2-9図は、韓国についてのFDI制限指標207を産業別に示している。2013年における韓国のFDI制限指標を1997年時のデータと比較すると、ほぼ全ての産業でFDI制限指標が大きく低下しており、韓国の対外開放戦略が抜本的な規制緩和を伴う政策であったことが分かる。全産業を総合したFDI制限総合指数(第Ⅱ-2-2-9図中右端の棒グラフ)は、1997年の0.54から2013年の0.14へと0.39ポイント低下している。これは、他の先進国、新興国と比較してもかなり大きな低下である208。
第Ⅱ-2-2-9図 韓国の産業別のFDI制限指標(1997年と2013年の比較)
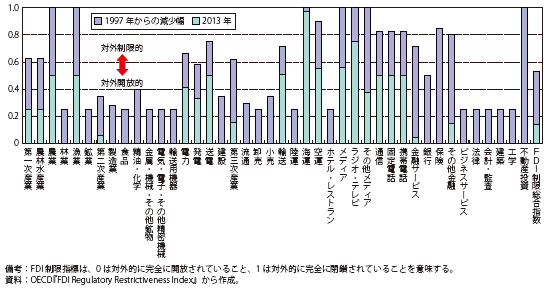
207 OECDが算出・公表している対内直接投資に対する各種の制限や規制の強さを指数化した指標。数字が0に近いほど、より対外的に開放されていることを表す。FDI制限指標の算出方法等については、Golub(2003)、Kalinova, Palerm, and Thomsen(2010)、Koyama and Golub(2006)に解説がある。
208 例えば、同期間における減少幅は、日本0.03ポイント、米国0.00ポイント、メキシコ0.09ポイント、ブラジル0.02ポイント、インドネシア0.17ポイント、マレーシア0.30ポイントとなっている。OECD(2011)も参照。
1998年には、外国人による株式取得に対する限度額が撤廃されたほか、外国人投資促進法の施行によって、外国人の投資に対する規制は大きく緩和された。その他、中小企業の活性化や技術・人材開発の促進のための特別税制も導入された(第Ⅱ-2-2-10表参照)。
第Ⅱ-2-2-10表 特別税制の導入施策(1999年5月)
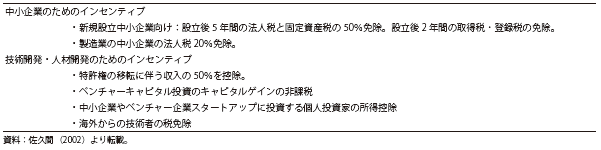
こうした各種の規制緩和やインセンティブ政策はベンチャー企業などの設立を促進し、新興企業が多く上場するKOSDAQ市場における上場企業数が急増した(第Ⅱ-2-2-11図参照)。2001年時点で、KOSDAQ市場の上場企業数がKOSPI市場における上場企業数を上回っており、この動向は2013年時点でも変わっていない。KOSPI市場に対するKOSDAQ市場の時価総額の比率は、2004年の13.2%をピークにその後低下し、2005年以降は10%前後で安定している。
第Ⅱ-2-2-11図 韓国株式市場の上場企業数と時価総額比率
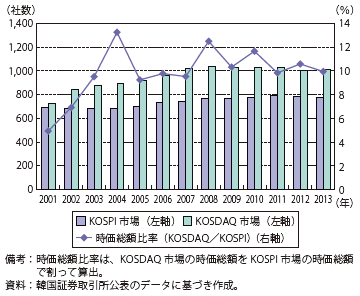
積極的な対外開放政策はグローバル競争を促し、外資出資比率も高まっている209。第Ⅱ-2-2-12図は、韓国全上場企業の株式時価総額に占める保有主体別の割合の推移を表している。1998~2007年までの10年間、その他に含まれる政府・公共機関や個人による株式保有が減少傾向にある一方、海外の株式保有比率が上昇傾向にある。2008年のリーマン・ショック以降、その他に含まれる政府・公共機関の保有比率が再び拡大しているが、海外保有も30%代半ばを維持しており、個人や機関投資家の保有比率が低下している。
第Ⅱ-2-2-12図 韓国上場企業の株式の保有主体別割合(時価総額基準)
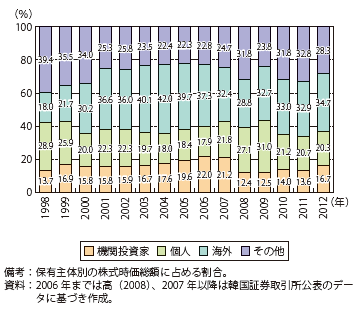
209 高(2008)。
こうした外資の参入による圧力は、経営者が経営の効率化や株主への説明責任を果たそうとするインセンティブを高めることにより、企業の競争力の強化に資するものであると考えられる。
2008年9月のリーマン・ショック後の世界経済危機以降も、韓国政府は様々な政策対応によって企業の競争力強化を図っている。例えば、法人税の減税や電子申告化による納税の負荷の軽減といった事業環境の整備、破産法の改正による事業再生・継続の促進、最低資本金の撤廃等による起業の促進など、主に中小企業を対象とした規制緩和策を実行した210。第Ⅱ-2-2-13図及び第Ⅱ-2-2-14図は、韓国におけるベンチャー企業とInno-biz企業211の推移と企業の開廃業の推移を示しているが、これらの政策による効果もあり、韓国において新興企業の設立や新規企業の創業が非常に活発であることが分かる。開廃業率については、単純に水準を比較できないものの、日本よりも3倍程度高くなっており、経済の新陳代謝が活発であることがうかがわれる212。
第Ⅱ-2-2-13図 韓国におけるベンチャー企業とInno-biz企業の推移
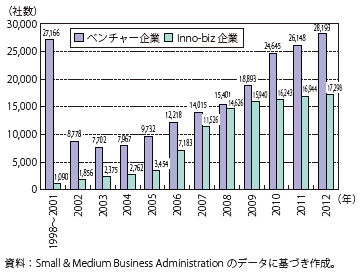
第Ⅱ-2-2-14図 韓国における企業の開廃業率の推移(日本との比較)
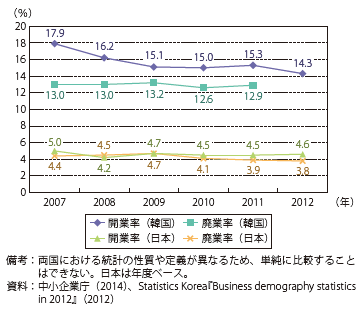
210 Doing Business(2012)。
211 Inno-biz企業とは、ベンチャー企業よりも更に革新的な技術を持つ企業のことをいう。
212 中小企業庁(2014)によると、2010年時点における米国の開業率と廃業率はそれぞれ9.3%と10.3%、2012年時点における英国の開業率と廃業率はそれぞれ11.4%と10.7%となっている。
