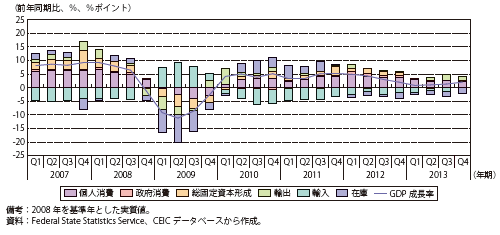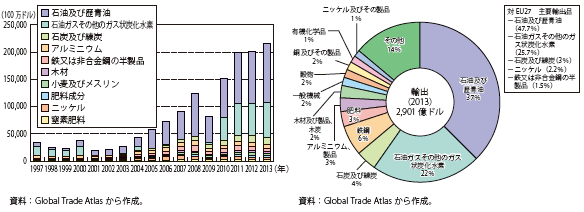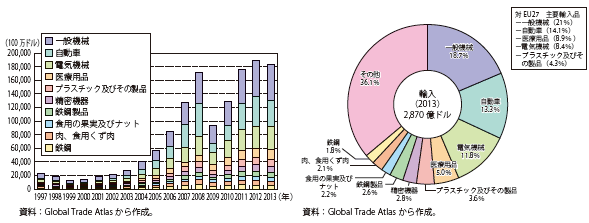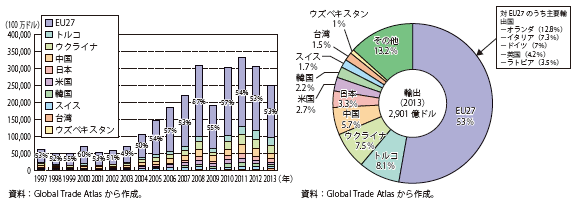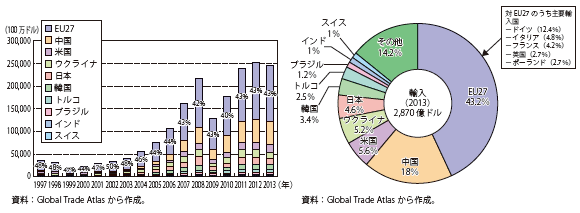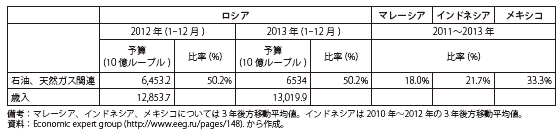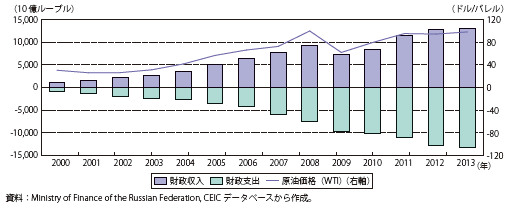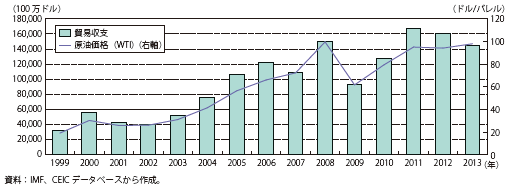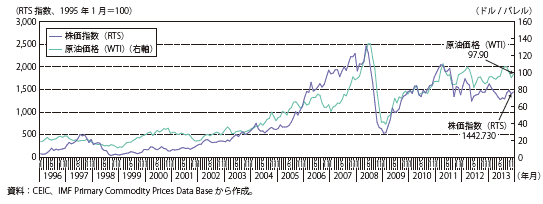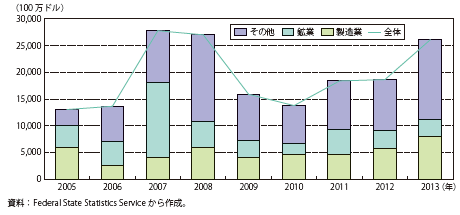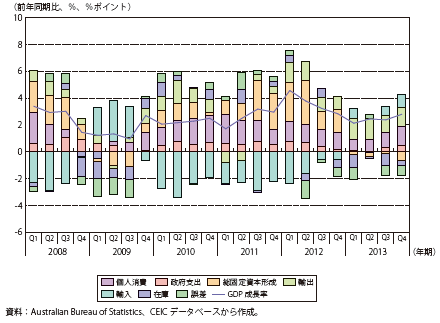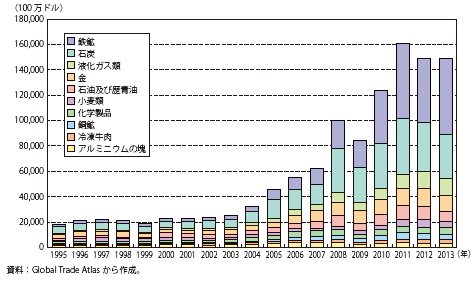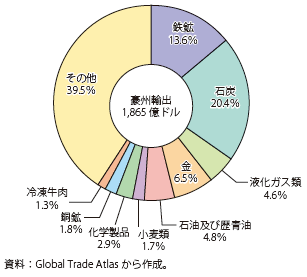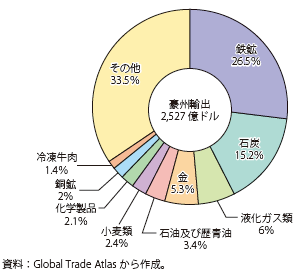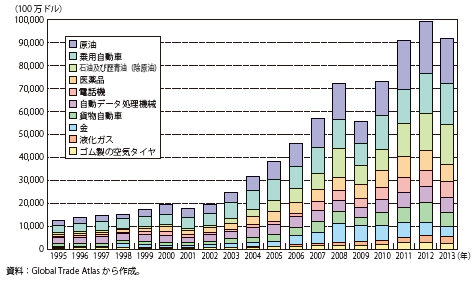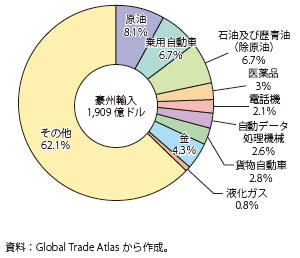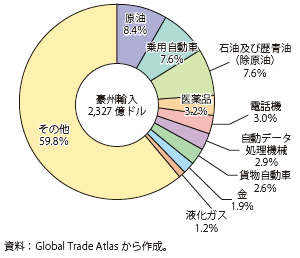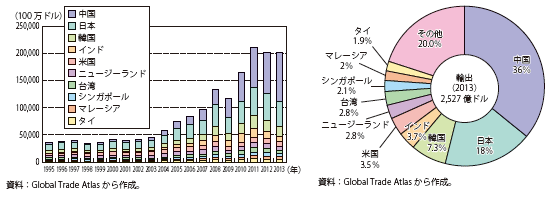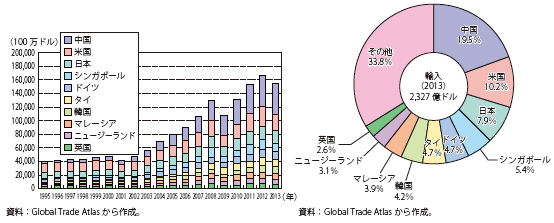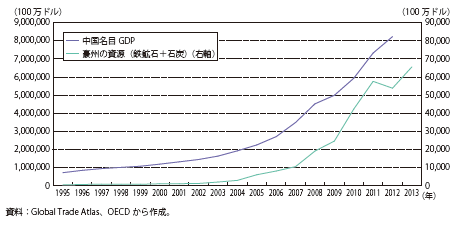第3節 メキシコとブラジルの成長戦略
ブラジルとメキシコは、1970年代まで高成長を続けたが、その後ハイパーインフレーションや債務危機、通貨危機などを経験し、経済は大きく減速することとなった。これらの危機に直面する中で、両国が選択した政策の方向性は極めて対照的である。両国の輸出上位10品目の推移を見ると、1970年代から1980年代までは両国とも一次産品が中心であったが、1990年代以降は大きく異なっている(第Ⅱ-2-3-1表)。すなわち、ブラジルにおいては、資源、農産物など一次産品とその加工品を中心とした輸出構造が継続しており、最近ではその傾向が更に強まってきている。これに対して、メキシコにおいては、工業製品中心の財を輸出する構造に大きく変貌している。また、ブラジルのGDPはメキシコよりも大きいが、輸出額はメキシコの方が大きく、輸出額の対GDP比はブラジルの約1割に対してメキシコでは約3割となっている(第Ⅱ-2-3-2図)。
第Ⅱ-2-3-1表 ブラジル及びメキシコの輸出構造
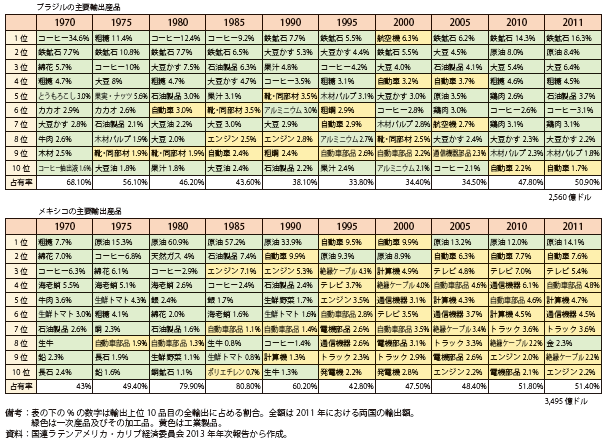
第Ⅱ-2-3-2図 ブラジル及びメキシコの輸出額、対GDP比の推移
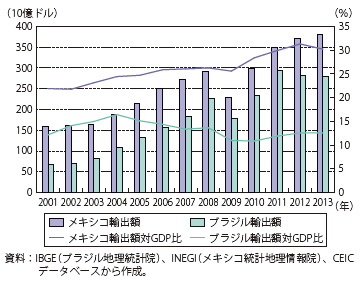
以下では、経済危機を経験した両国がそれぞれどのように乗り越え、その結果どのような経済構造を有するに至ったのかについて見ていく。
1.リスクへの耐性
経済構造のぜい弱性が危機を招く要因となった過去の教訓を踏まえ、ブラジル、メキシコとも、経済ファンダメンタルズの強化に取り組み、危機に際しての政策対応能力を高めてきた。この結果、近年は、外部金融環境の急激な変化などにより動揺が生じる可能性はあるものの、第Ⅱ-2-3-3表に示すように過去の経済危機時と比較してリスクへの耐性が強化されている。例えば、ブラジルのインフレ率は、現時点においても相対的に高い水準にあるが、ハイパーインフレーション時と比べてはるかに安定している。また、メキシコの経常収支も改善している。
第Ⅱ-2-3-3表 ブラジル及びメキシコの過去の危機時の経済指標との比較
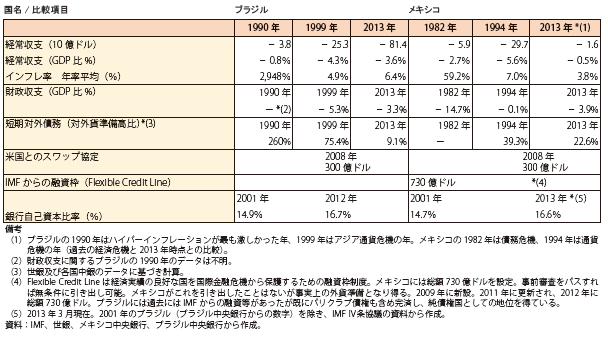
2.成長戦略
(1)対外経済政
メキシコは、1982年の債務危機を契機として、それまでの国内産業の保護・育成を目的とした輸入代替政策から自由貿易政策へと転換した。まず、1985年に輸入ライセンス制の元にあった品目のうち8割を数量制限に移行させた。1986年にGATT(現WTO)に加盟し、加盟議定書等にしたがって、輸入数量制限品目を1985年初頭83%あったのを86年には約27%までに削減した。また、国際競争によってインフレーションを安定化させるとの観点から最高関税率を20%まで引下げを行うなどの貿易の自由化を進めていった214。他方、ブラジルはGATT(現WTO)に1948年に加盟しているが、メルコスール(1991年署名、1995年発効)とともに域内関税と域外関税を設定してきた。なお、世銀による適用関税率(単純平均ベース)を見ると2003年までは両国ともおおむね15%台の平均関税率で推移してきたが、2010年時点でメキシコが2.8%、ブラジルが7.2%になっている(第Ⅱ-2-3-4図)。一方、メキシコは1994年のNAFTAへの加盟を始め、中南米諸国、欧州諸国、日本など21の国と地域で17のFTAを締結するなど世界各国・地域との自由貿易網を積極的に構築し、各国との経済連携を強化していった。他方、ブラジルにおいては、国内産業の保護・育成が長く続き、経済連携の動きも基本的には南米諸国を中心としたものになっている(第Ⅱ-2-3-5表)。
第Ⅱ-2-3-4図 関税率の推移
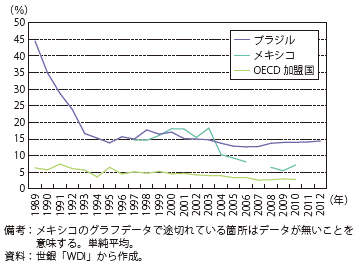
214 P. Aspe (1993) Economic Transformation the Mexican Way, The MIT Press, L.Agama, and C.A. McDaniel (2002) “The NAFTA Preference and U.S. -Mexico Trade” U.S. International Trade Commission
第Ⅱ-2-3-5表 メキシコとブラジルのFTA締結状況
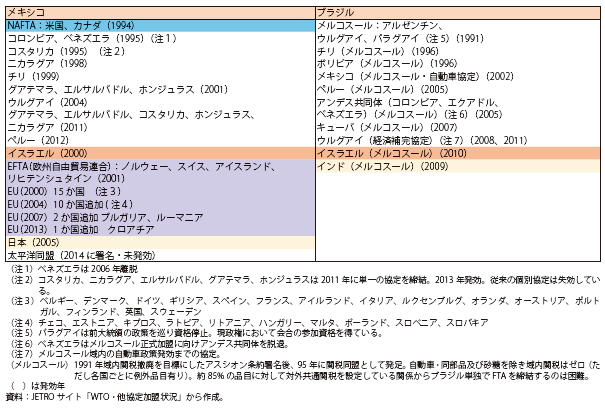
また、メキシコは、外資参入規制の緩和、民営化などの改革も進めた結果、対内直接投資も増加し、資源の輸出国から工業製品の製造・輸出拠点へと成長した(第Ⅱ-2-3-6図)。ブラジルへの直接投資も近年増加している(第Ⅱ-2-3-7図)。メキシコでは製造業に対する直接投資が特に伸びているのに対して、ブラジルではサービス業、鉱業、農業に対する直接投資が多くなっている。
第Ⅱ-2-3-6図 メキシコへの対内直接投資(左)とメキシコへの日本からの直接投資(右)
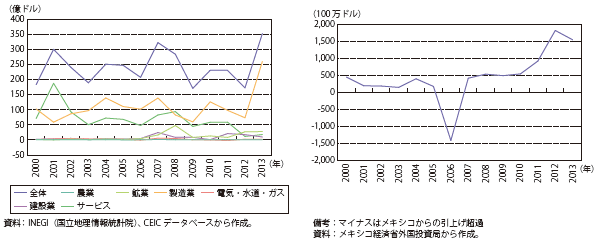
第Ⅱ-2-3-7図 ブラジルへの対内直接投資(左)とブラジルへの日本からの直接投資(右)

ブラジルの製造業については、国際的な競争力を有する企業も存在するが、近年の資源需要の増加、資源価格の上昇などを背景として、輸出に占める一次産品の割合が上昇し、輸出に占める工業製品の割合は低下している。工業製品の輸出割合が低下した背景として、コモディティブームに伴う割高なレアルや215、インフレ圧力への懸念から高水準で推移している政策金利・国内貸出金利が製造業の生産・輸出を下押ししていることも考えられる(第Ⅱ-2-3-8図)216。
第Ⅱ-2-3-8図 ブラジルの国内貸出金利の推移(左)、政策金利とインフレ率の推移(右)
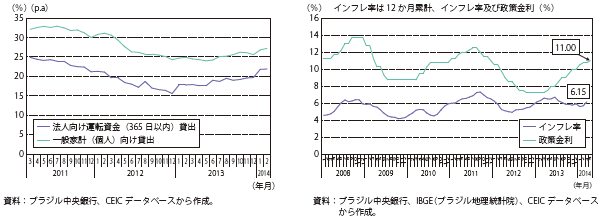
215 近田亮平編(2013)『躍動するブラジル―新しい変容と挑戦』、P72-75アジア経済研究所 実質実効為替レート(第Ⅱ-2-3-9図)を見るとメキシコの方が高い傾向にあるが、冒頭第Ⅱ-2-3-1表で示した主要輸出産品の推移で分かるようにメキシコが90年代には工業製品を主力輸出産品にしていたのに対して、ブラジルが一次産品への依存が高い輸出構造であり、通貨高になると貿易をあまり必要としないサービスに依存する経済構造になり結果として消費にけん引される内需主導型経済になったと考えられる。
216 「第Ⅱ-2-3-10図メキシコの政策金利とインフレ率の推移」比較参照。
第Ⅲ-2-3-9図 ブラジルレアルとメキシコペソの実質実効為替レート
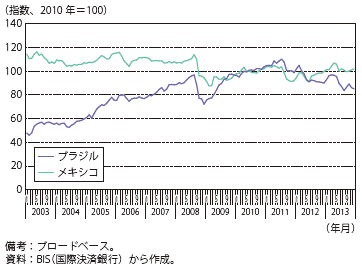
第Ⅲ-2-3-10図 メキシコの政策金利とインフレ率の推移
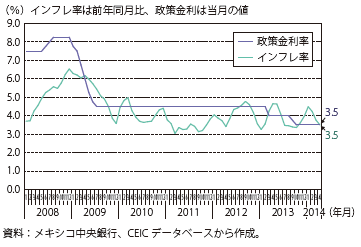
(2)国内市場育成
メキシコ政府が行った調査によると、メキシコに所在する事業所の約96%が従業員数10人以下の事業所となっている。製造業で見ると、10人以下の事業所が約93%、10人以下の事業所の売上額は約4.3%となっており、小規模事業所が多くなっている(第Ⅱ-2-3-11図)217。
第Ⅱ-2-3-11図 メキシコの全産業の事業規模と製造業の事業規模

217 我が国の場合、従業員数10人未満の事業所は約78%を占め、製造業で見ると約69%(総務省・経済産業省「平成24年経済センサス―活動調査産業横断的集計」統計表データ)。
メキシコは、低賃金などコスト面での優位性から製造・輸出拠点へと成長する一方、所得格差の問題が指摘されている。メキシコ政府の家計調査による10段階の所得階層で見ると、上位20%(Ⅸ及びⅩ)で所得総額の5割を占めている(第Ⅱ-2-3-12表)。これは非正規雇用者(特にインフォーマルセクター218の労働者)が多く存在していることが考えられる。
第Ⅱ-2-3-12表 メキシコの家計調査
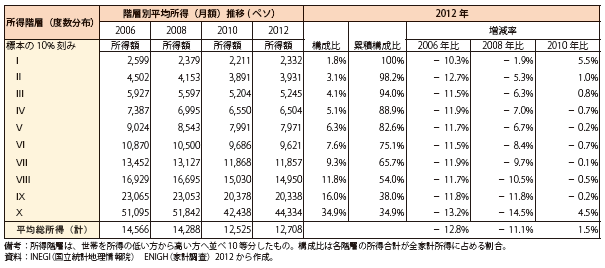
218 メキシコ当局の定義では「法人格を持たない家内工業的な性格を有するすべての活動主体」を指す。
なお、所得階層意識について、AMAI(メキシコ市場・世論調査機関協会)によれば、自分は「中間層(中流の上、下)である」とする層が約53%となっている(第Ⅱ-2-3-13図)。
第Ⅱ-2-3-13図 所得階層意識
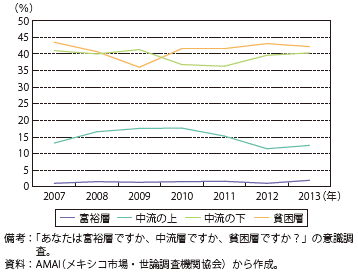
他方、ブラジルは、コモディティブームに伴う雇用(特に正規雇用)の確保、最低賃金の引上げ、低所得者層に対する「ボルサ・ファミリア」という貧困対策(子供に健康診断を受けさせ、就学させる義務を果たせば現金給付を受けることができる制度219)などにより、「C層」と分類される中間層に相当する人口が著しく増加し、人口の半数を超えるようになった。こうした中間層は、消費者信用の増加にも支えられて消費のけん引役となり、ブラジル経済は世界が注目する一大市場へと成長した(第Ⅱ-2-3-14図、第Ⅱ-2-3-15図、第Ⅱ-2-3-16図)。
第Ⅱ-2-3-14図 ブラジルの最低賃金(左図)と正規雇用者数の推移(右図)
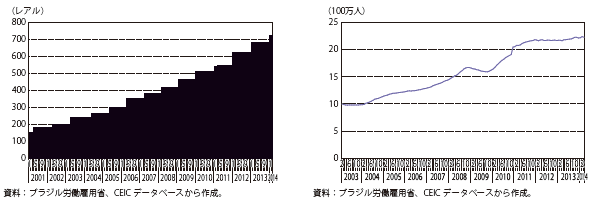
第Ⅱ-2-3-15図 ボルサ・ファミリア(普及家族数・GDP比支出規模)
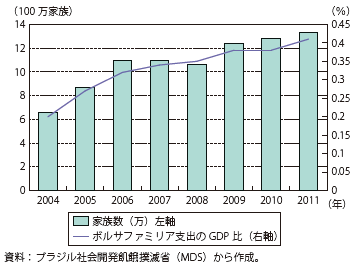
第Ⅱ-2-3-16図 ブラジルの所得階層別人口割合の推移
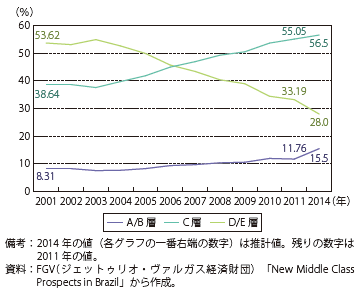
219 GDPに対する支出規模に比して人々を貧困から救済したとの評価がある(F.V. Soares(2011))。ボルサ・ファミリアは2013年にILOの関連非営利国際機関であるISSA(国際社会保障協会)からAward for Outstanding Achievementを受賞。
(3)貿易構造
メキシコは、世界各国・地域とFTAを締結しているが、巨大消費市場の米国に隣接している優位性からも、米国経済との結びつきが強く、メキシコの輸出の79%を米国が占めている。また、近年は中南米諸国への玄関口としても注目されている(第Ⅱ-2-3-17図)。
第Ⅱ-2-3-17図 メキシコの輸出相手国
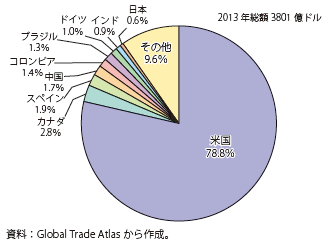
米国の主要輸入相手国・地域を見ると、米国にとって最大の輸入相手国は中国で19%、メキシコは12%となっている(第Ⅱ-2-3-18図)。
第Ⅱ-2-3-18図 2013年時点の米国の主要輸入国・地域
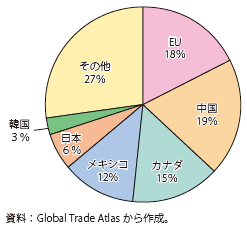
メキシコと中国の米国への輸出上位10品目を見ると、5品目で競合しており、そのうち3品目は上位1位から3位までを占めている(第Ⅱ-2-3-19表)。近年、メキシコは、米国経済から影響を受けやすい構造を緩和すべく、輸出先の多角化を模索している(第Ⅱ-2-3-20図)。
第Ⅱ-2-3-19表 米国の中国とメキシコからの輸入品
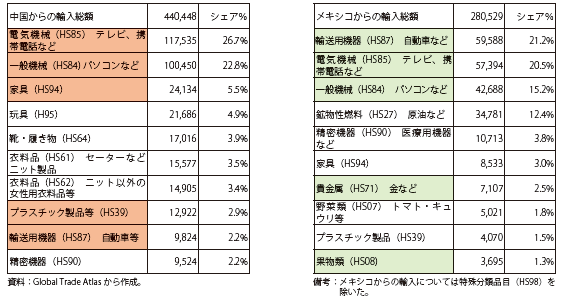
第Ⅱ-2-3-20図 メキシコの輸出における米国依存度
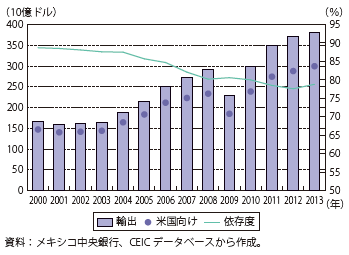
これに対して、ブラジルでは、中国など新興国における一次産品需要が飛躍的に増大したため、特に中国向けの輸出が増加し、2009年には中国が最大の輸出相手国となり、主要輸出品目も鉄鉱石、大豆、原油といった一次産品が占めるようになった(第Ⅱ-2-3-21図)220。
第Ⅱ-2-3-21図 ブラジルの輸出品の推移と輸出先の動向
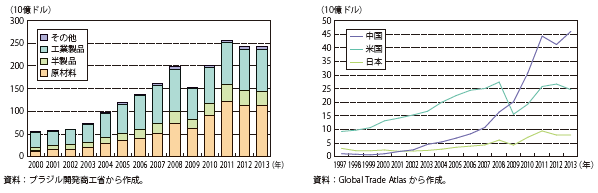
特に2008年から2010年に中国向け輸出が急速に伸び、それに伴いブラジルのGDP成長率も急回復した。減税策221などの効果もあったと見られるが、中国からの旺盛な需要がブラジル経済をけん引したものと考えられる。ブラジルの輸出依存度はGDPに対して高くはないが、中国経済や国際商品価格の動向から影響を受けやすい構造となっている(第Ⅱ-2-3-22図、第Ⅱ-2-3-23図)。
第Ⅱ-2-3-22図 ブラジルの輸出相手国(2013年)と推移
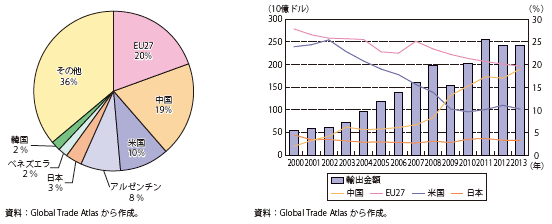
第Ⅱ-2-3-23図 ブラジルの鉄鉱石、大豆、原油の輸出先(2013年)
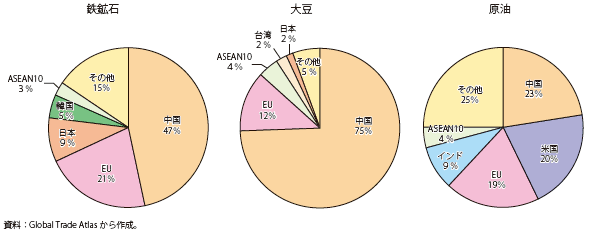
220 欧州の国をEUとしてみるとEUが1位だが中国とは僅差。
221 自動車に対する工業製品税(IPI)減税。
(4)今後の課題
メキシコ、ブラジルとも、経済危機などを契機として改革を進めることとなった。メキシコは、1982年の債務危機、1994年の通貨危機などを経て、自由化・民営化といった構造改革を進めるとともに、米国と隣接する優位性を最大限いかしつつ、対外開放政策を積極的に進めることにより、製造・輸出拠点として成長を遂げた。これに対して、ブラジルは、対内直接投資を積極的に受け入れる一方、国内産業の育成と中間層の拡大を通じて国内市場を成長させ、さらに近年では資源輸出によって貿易黒字を維持しつつ発展してきた。それぞれ独自の成長戦略を展開してきているが、課題も多い。
メキシコについては、所得格差の問題やエネルギー分野などにおける構造改革が課題である。この点、ペニャ・ニエト大統領の構造改革への取組に期待が高まっており、これまでの取組に対して市場からも一定の評価を得ている(第Ⅱ-2-3-24表)。
第Ⅱ-2-3-24表 メキシコとブラジルの外貨建国債格付
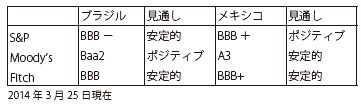
一方、一般に中南米諸国の貯蓄率は、アジア新興国と比べて低いとされるが、特にブラジルは中南米諸国の中でも貯蓄率が低い。貯蓄率を高めて投資を促進し、「ブラジルコスト」のひとつであるインフラの整備を進め、インフレを抑制していくことが必要である(第Ⅱ-2-3-25表)。
第Ⅱ-2-3-25表 国内総貯蓄率(アジア新興国との比較)
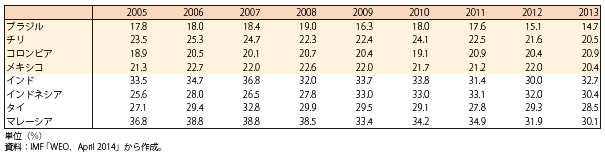
ブラジルは、国内市場の成長に伴い輸入が増加し、経常収支の赤字が続いていることで、外部金融環境の変化の影響を受けやすくなっている。また、米国格付機関によりブラジル国債の外貨建て長期債の格付が引き下げられたが、財政規律を維持することができるかどうかも注目される(第Ⅱ-2-3-26図)。
第Ⅱ-2-3-26図 ブラジルのプライマリーバランス対GDP比の推移と目標値
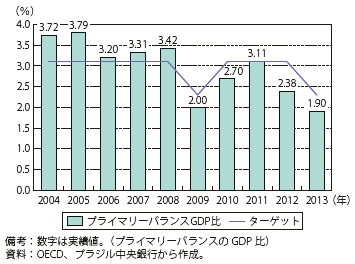
また、ブラジルでは、近年、家計の負債比率は上昇している一方、民間銀行の貸出残高が伸び悩んでいる(第Ⅱ-2-3-27図)。中間層の負債は、主要中南米諸国(アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー、メキシコ)の平均値を超えており、民間による資本形成が進んでいないとも指摘されている222。ブラジルでは、近年、中間層が出現し、その旺盛な消費意欲によって、例えば自動車の国内販売台数がドイツを抜いて世界4位となるなど、国内市場が大きく成長してきた。ブラジルは、こうした大きな国内市場を有していること、多様な資源に恵まれている点で、メキシコと比較し限定的な対外開放路線を歩むことが可能であった面もあると考えられるが、対外経済関係も含め、国内消費がけん引する内需主導型経済の持続可能性をどのように確保していくのか注目される。
第Ⅱ-2-3-27図 ブラジルの家計の債務負担(左図)及びブラジルの銀行貸出し残高のGDP比推移(右図)
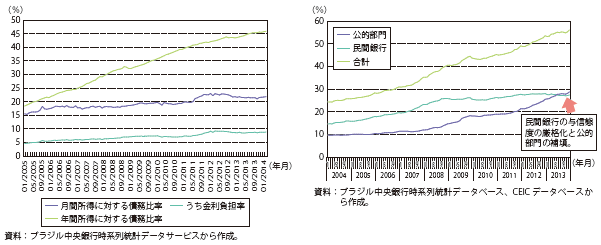
222 Ferreia, Francisco H G., Julian Messina, Jamale Rigolini, Luis-Felipe Lōpez-Calva, Maria Ana Lugo and Renos Vakis (2013) “Economic Mobility and The Rise of The Latin American Middle Class” World Bank