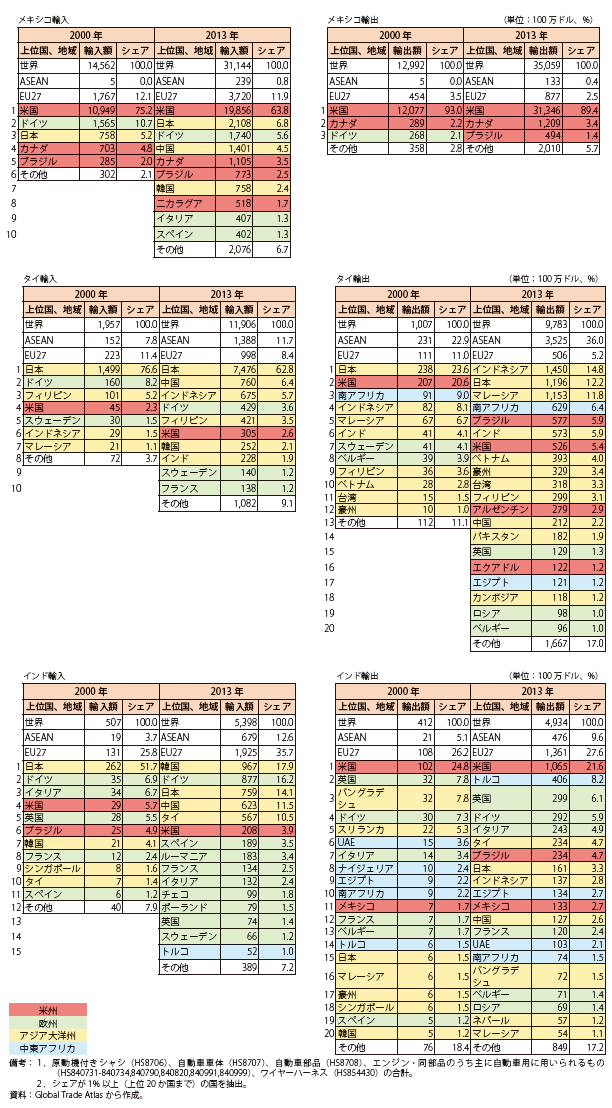第4節 メキシコ、タイ、インドの自動車政策
世界の自動車販売台数の推移を見ると、先進国の販売台数減少の影響を受けて2008年、2009年に落ち込んだものの、2010年には再び増加に転じた。その後は堅調に推移し、2013年には8千万台を超えた。新興国の販売台数は2008年、2009年も増加を続け、2011年以降は先進国を上回って推移している(第Ⅱ-2-4-1図)225。2013年の自動車販売台数を国別に見ると、新興国では中国(世界第1位)、ブラジル(同4位)、インド(同5位)が上位にきている(第Ⅱ-2-4-2表)。株式会社フォーインの予測によると、インドは、2019年には米国、中国に次いで世界第3位となる見通しである。また、ASEANも2024年には世界第4位となる見通しである(第Ⅱ-2-4-3表)。今後も販売市場としての新興国の重要性が増すと見られる。
第Ⅱ-2-4-1図 先進国・新興国の自動車販売台数の推移
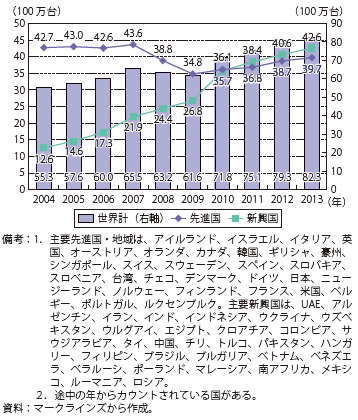
225 第Ⅰ-1-1-14図再掲。
第Ⅱ-2-4-2表 世界の自動車販売台数(2005年、2013年)
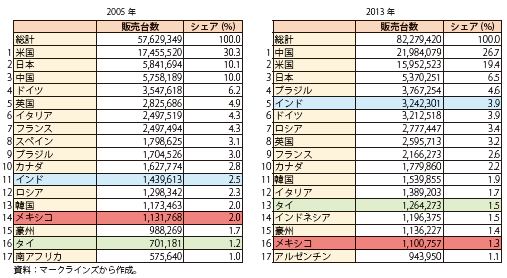
第Ⅱ-2-4-3表 世界の自動車販売台数予測(2019年、2024年)
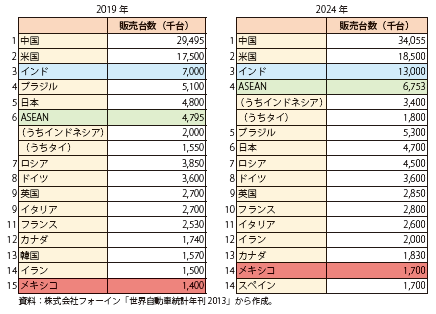
2012年の世界の自動車生産台数を見ると、上位10か国のうち新興国が半分を占めており、2005年と比べて新興国の伸びが目立っている。中国は世界第3位から同1位へ、インドは同12位から同6位へ、ブラジルは同9位から同7位へ、メキシコは同11位から同8位へ、タイは同14位から同10位へ、それぞれ上昇している(第Ⅱ-2-4-4表)。
第Ⅱ-2-4-4表 世界の自動車生産台数(2005年、2012年)
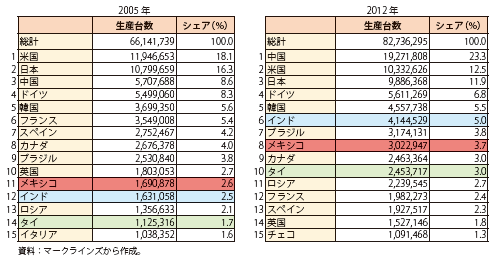
メキシコは他の新興国に比較して自国内での販売台数が頭打ちにある中、輸出を軸に生産台数を伸ばしており、2013年の自動車関連品目の輸出額では世界第4位と、新興国の中では最も上位にある(第Ⅱ-2-4-5表)。
第Ⅱ-2-4-5表 主要国・地域の自動車関連品の輸出額の推移

メキシコ、タイ、インドにおける2013年の生産台数、国内販売台数、輸出台数を見ると、3か国の中で最も生産台数の多いインドでは、国内市場規模の拡大に伴い販売台数を大きく伸ばしてきた226一方、他の2か国に比べて輸出台数は少ない。インドに次いで生産台数の多いメキシコでは、国内販売台数は2009年には78万台と低迷し、2013年には2007年以来の110万台を突破したが、他の2か国と比較して販売台数が少ない。他方、輸出台数は国内販売台数の2倍以上で、3か国の中で最も多い。タイでは、他の2か国に比べて国内販売台数と輸出台数の差が小さくなっている(第Ⅱ-2-4-6図。各国データの推移は、後の第Ⅱ-2-4-8図~第Ⅱ-2-4-10図に示す)。
第Ⅱ-2-4-6図 メキシコ、タイ、インドの自動車生産台数、国内販売台数及び輸出台数(2013年)
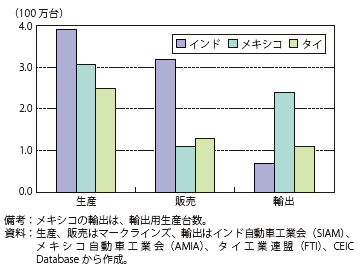
226 インドとタイの2013年の国内販売台数は2012年を下回った。インドでは景気低迷が長引く中、燃料費の高騰や金利の高止まりを背景に買い控えが続いている。タイでは自動車初回購入者向け減税の実施により2012年の販売台数が急増しており、2013年にその反動が見られた。
これらは、メキシコは海外市場への輸出、インドは国内市場、タイは輸出と国内市場の両方を中心とした構造であることを示している。
また、メキシコ、タイ、インドにおける国内販売台数のメーカー別シェアを見ると、メキシコ、タイでは外資系がほぼ100%となっている一方、インドでは現地系が約36%のシェアを占めている(第Ⅱ-2-4-7図)。
第Ⅱ-2-4-7図 メキシコ、タイ、インドの完成車メーカー別国内販売シェア(日系企業、その他外資系企業、現地系企業別。2013年)
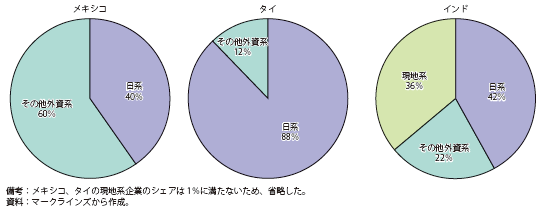
各国がこのように異なる構造を持つに至った背景として、それぞれの自動車産業政策の特徴を見ていく。
1.対外経済政策と成長
メキシコでは、1960年代以降、輸入代替政策(完成車や部品に対する国産化規制、部品メーカーに対する外資出資比率規制等)など国内保護政策がとられていたが、1982年の債務危機を契機として、IMF勧告を受け入れ、改革・対外開放路線へと歩み始めた。1986年にはGATT(現WTO)に加盟し、関税引下げや輸入規制緩和を行い、また、外資参入規制の緩和、国営企業の民営化、金融の自由化などの改革も進められた。巨大市場である米国に隣接している優位性も活かして製造・輸出拠点化を進め、1994年のNAFTA加盟でこうした動きがさらに加速した。こうした中、日本、米国、欧州諸国などの外資系企業が相次いで進出し、完成車メーカーに加え、部品メーカーの参入も進んだ。その後も、中南米諸国、欧州諸国、日本など世界各国・地域との自由貿易網を積極的に構築し、各国との経済連携の強化を図っている(第Ⅱ-2-4-11表)。
第Ⅱ-2-4-11表 メキシコ、タイ、インドのFTA/EPA締結国と発効年
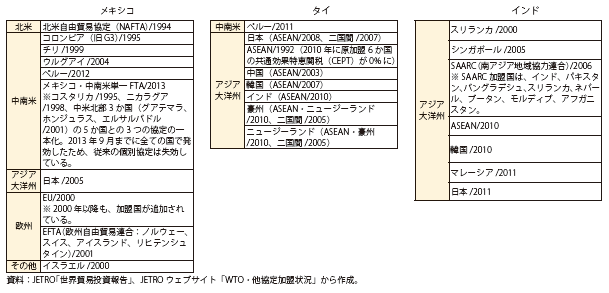
タイでも、1960年代以降、輸入代替政策(完成車や部品に対する国産化規制、外資参入規制、生産モデル数制限、輸入禁止・高率関税賦課等)など国内保護政策がとられていたが、1990年代に入ると、国内需要の拡大と需要増に対応するための技術水準の向上や量産体制の整備の必要性などから、部品産業に対する外資による直接投資を奨励するなど一部自由化の動きが進んだ。1997年のアジア通貨危機を契機として、国内市場が低迷する中、輸出強化に取り組むようになり、2000年代に入ると、AFTAなど貿易自由化の流れの下、部品に対する国産化規制を撤廃するなど、自由化の流れがさらに加速した227。ASEANの中で輸出強化の取組にいち早く着手したタイは、「東洋のデトロイト」構想を掲げ、外資誘致や各国とのFTA締結などを積極的に推進し、東南アジアにおける一大生産・輸出拠点へと成長を遂げた。タイはピックアップトラックの世界的な生産拠点となっているが228、近年は小型乗用車にも力を入れており、ピックアップトラックに続く戦略としてエコカー分野における強化を図っている。
インドでは古くからインド現地企業が設立され、1947年の独立以降、国産化規制、外資参入規制、輸入規制など国内保護政策が徹底された。当時既にインドに進出していた外資系企業は、こうした厳しい国産化規制などに対応することができず撤退を余儀なくされ、インド現地企業による寡占構造が長く続くこととなった。1980年代に入ると、鈴木自動車工業株式会社(現スズキ株式会社)とインド政府との国営企業マルチ・ウドヨグ社229の四輪車合弁契約の調印に見られるように、外資系企業に対する規制が一部緩和されるようになった。1990年代には、日本、欧米諸国、韓国などの外資系企業がインドに相次いで進出したが、外資系企業に対して、インド政府とのMOU(覚書)に基づき、国産化義務、輸出入均衡義務などが引き続き課されていた。2000年代に入り、こうした規制がWTO違反とされ230、インドは、従来の政策を修正し、対外自由化を加速させることとなった。2002年に打ち出した新自動車政策においては、外資系企業による出資に関する最低投資金額規制の撤廃、100%外資の参入可、国産化率達成義務の撤廃などが行われるとともに、小型車・二輪車・自動車部品をインド自動車産業の基幹分野と位置づけ、輸出や研究開発を促進する方針が示された231。2006年には「自動車ミッションプラン2006-2016(Automotive Mission Plan 2006-2016)」232を策定し、2016年までの中長期的な数値目標を設定した。この中で、自動車生産台数の世界順位を2016年までに7位にするとしていたが、2009年に達成されるなど、インドの自動車産業は急拡大している。2013年には「国家電動モビリティ促進策2020(National Electric Mobility Mission Plan 2020)」233を策定し、電気自動車などの生産・開発拠点を目指すこととしている。
このように、対外自由化の時期、内容や程度には3か国の間で相違があり、それが現在の異なる構造を持つに至った背景ともなっているが、3か国とも国際的な貿易・投資自由化の流れの中で、規制緩和、FTA締結などを進めることにより、輸出を拡大してきた。また、地理的条件や国内市場の規模などそれぞれの特徴をいかしつつ、外資による投資を受け入れ、戦略的な生産・輸出・販売網のプラットフォームの構築を図ることで発展を遂げている。
第Ⅱ-2-4-8図 メキシコの自動車生産、販売、輸出用生産台数の推移
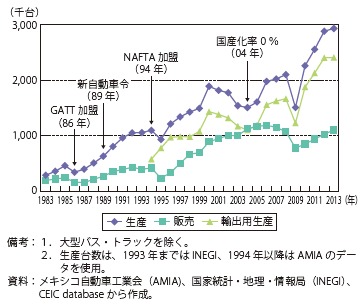
第Ⅱ-2-4-9図 タイの自動車生産、販売、輸出台数の推移
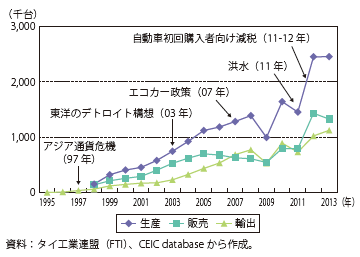
第Ⅱ-2-4-10図 インドの自動車生産、販売、輸出台数の推移
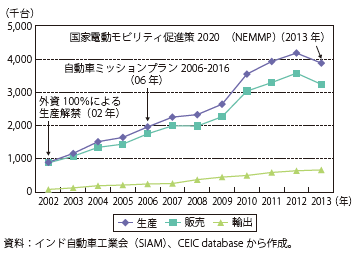
227 タイなどASEANの自動車産業は、域内の自動車部品の補完支援によって進展してきた。1988年からのBBC(ブランド別自動車部品相互補完流通計画)やその発展形態である1996年からのAICO(アセアン産業協力計画。個別企業のASEAN域内での相互輸出プロジェクトについて、関係国政府が認可して、5%以下の特恵関税を供与するスキーム)による関税恩典、AFTAによる関税引下げなどを利用して主要な部品を補完することにより、各自動車メーカーはASEAN大での自動車生産を進めてきた(清水(2010))。
228 タイの5トン以下貨物自動車(HS870421)の輸出額(2013年)は75億ドルと、世界第1位である。
229 2006年12月にインド政府が全保有株式の売却を決定し、その後完全民営化された。2007年には社名がマルチ・スズキ・インディア社に変更された。
230 本ケースは2013年不公正貿易報告書第Ⅱ部第8章で紹介されている。
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/pdf/2013_02_08.pdf![]()
231 中小企業基盤整備機構(2006)
2.輸出先の多角化
メキシコではいち早く輸出強化戦略をとり、NAFTAを軸としつつ、世界各国・地域との自由貿易網を構築することで輸出市場の獲得に努めてきた。タイ、インドにおいても、輸出強化に向けた取組が進められている。ここでは、メキシコ、タイ、インドの完成車の輸出先や部品貿易の動向にどのような変化があるのか見ていく。
メキシコ、タイ、インドの完成車の輸出先別シェアを見ると、メキシコは、世界各国・地域と幅広くFTAを締結しているが、米国のシェアが、2000年の88.8%から2013年の75.8%へと低下しているものの、引き続き突出して高くなっている。他方、近年はブラジルをはじめ南米諸国のシェアが高まってきている。
タイは、2000年には欧州のシェアが39.7%と高かったが、2013年には3.5%と大きく低下している。代わってアジア大洋州及び中東アフリカのシェアが高まっているが、2000年にもシェアが高かった豪州234を除き、輸出先は多様化されている。
インドも、2000年には欧州のシェアが46.9%と高かったが、2013年には21.8%と低下している。代わって中南米及び中東アフリカのシェアが高まっているが、最大の輸出先も変わるなど多様化されている(第Ⅱ-2-4-12表)。
第Ⅱ-2-4-12表 メキシコ、タイ、インドの完成車輸出額及びシェア(主要国別、2000年、2013年)
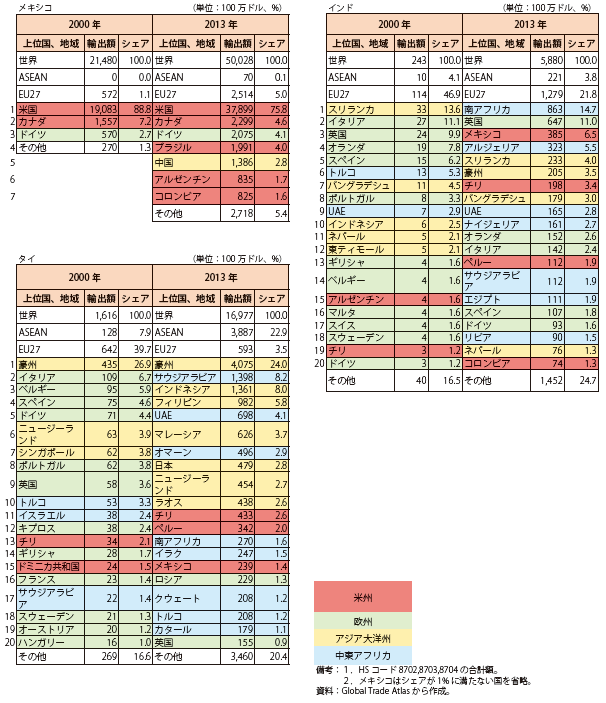
234 タイから豪州への完成車輸出額は、タイ-豪州FTAが発効した2005年に11.7億ドル(前年比69%増)と、対世界輸出(51.5億ドル、同35%増)の伸びを大きく上回った。
次に、メキシコ、タイ、インドの自動車部品貿易を見ていく(第Ⅱ-2-4-13図)。
第Ⅱ-2-4-13図 メキシコ、タイ、インドの自動車部品貿易額の推移
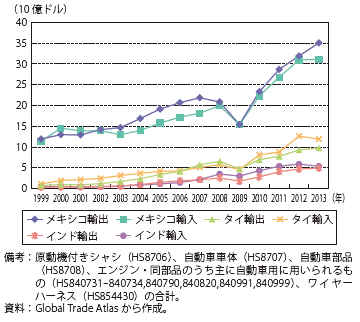
メキシコの輸出先は、2000年、2013年とも米国のシェアが90%前後と突出して高いが、やや低下している。輸入先についても米国のシェアが高くなっているが、輸出に比べると2013年63.8%と低く、2000年からの低下幅も大きくなっている。他方、日本、中国、韓国のシェアがやや高まっている。
タイの輸出先は、アジア大洋州、特にASEAN諸国のシェアが高まる一方、日本、米国のシェアが大きく低下している。輸入先については、日本のシェアが突出して高くなっているが、2000年の76.6%から2013年の62.8%へと低下している。代わって中国、インドネシアのシェアが高まっている。
インドの輸出先は、米国、欧州のシェアが高く、2000年、2013年で大きなシェアの変化は見られない。他方、トルコを除いて中東アフリカのシェアが低下している。輸入先については、欧州、ASEAN諸国のシェアが高まっている。国別に見ると、日本のシェアが大きく低下する一方、韓国、ドイツ、中国、タイのシェアが高まっている(第Ⅱ-2-4-14表)。
第Ⅱ-2-4-14表 メキシコ、タイ、インドの自動車部品貿易の主要相手国、地域(2000年、2013年)