第1節 東アジアにおける貿易投資動向
1.世界貿易における東アジア
東アジアと世界主要地域との貿易フローを俯瞰(ふかん)すると、東アジアは、国際的な生産分業が発達し、東アジア域内の貿易では中間財の比率が高く、欧米向けには最終財の比率が高い(第Ⅱ-3-1-1図)。これは東アジアの中で、日本・韓国から中間財が中国・ASEANに輸出されるとともに、ASEAN域内、中国・ASEAN間においても相互に中間財が輸出され、組み立てられた最終財が中国・ASEANから欧米へ輸出されることを示唆している。このような基本的な構造は、2000年、2012年ともに見られ、金額ベースで拡大している。特に、中国の貿易額が大きく増加し、その存在感が高まっている。
第Ⅱ-3-1-1図 東アジアと世界の主要地域との貿易フロー
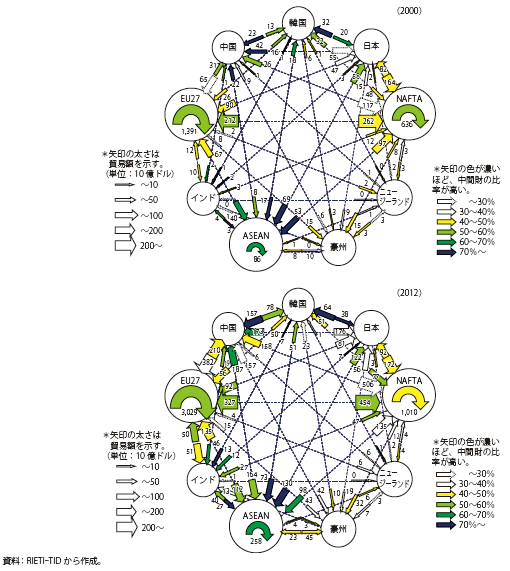
このような東アジアの貿易構造を次項以下で更に詳しく見ていく235。
235 ここでは生産分業を念頭に、貿易を生産工程別の財(素材、中間財、最終財)に分けて分析を行う。その基礎データとしては、このような財別に整理されている独立行政法人経済産業研究所RIETI-TID2012を利用する。中間財・最終財のイメージやRIETI-TID2012については 、それぞれ付注1、付注2を参照。
2.東アジアの貿易構造の特徴
東アジアの貿易構造を分析するに当たって、まず、域内貿易と域外貿易の比重の置き方、域内の経済的結びつきを分析し、次に域内貿易、域外貿易の特徴を考察する。その上で長期的な変化の動向、リーマン・ショック後の直近の変化を見ていく。なお、その過程でNAFTA、EUなど他の主要経済圏との比較も試みる。
(1)域内貿易比率
東アジアと他の主要経済圏の域内貿易比率を比較し、東アジアの特徴を見ていく(第Ⅱ-3-1-2図)236。
236 ここでは、東アジアは便宜的にRIETI-TID2012の地域区分に従った。具体的には、東アジアは、日本、中国、香港、韓国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ブルネイ、カンボジア、ベトナム。NAFTAは米国、カナダ、メキシコ。EUは27か国ベースでとっている。なお、ASEANはブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8か国。ただし、データの制約で、一部の国・年については統計が入手できない場合もある。特に記載がない限り、RIETI-TIDのデータによる集計の場合は以降も同じ。
第Ⅱ-3-1-2図 主要経済圏の域内貿易比率の推移
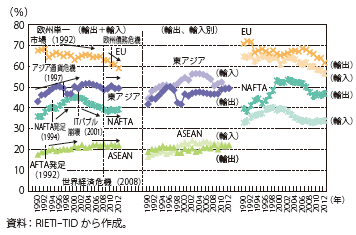
まず、EUの域内貿易比率(輸出+輸入ベース)が相対的に高くなっている。これは、EU加盟国にとって貿易パートナーとして域内諸国の比重が大きく、経済的結びつきも強いことを意味する。ただし、長期的な動向を見ると、欧州単一市場が発足した1992年時点で既にEUの域内貿易比率は高かったものの、次第に低下してきている。これに対して、東アジアは、地域全体をカバーする制度的枠組みを持たないものの、1990年代から域内貿易比率が上昇し、域内の経済的結びつきが強まってきている(1990年代末の一時的な低下はアジア通貨危機の影響が考えられる)。なお、東アジアの一部であるASEANについては、1992年のAFTA発足後、緩やかに域内貿易比率が上昇している。NAFTAは、1994年のNAFTA発足以来、域内貿易比率が上昇し経済的結びつきが強まったが、2000年代初頭から緩やかに低下、リーマン・ショック以降は横ばいで推移している。
輸出・輸入それぞれにおける域内比率を見ると、東アジアにおいては、輸入が輸出よりも高い水準で推移している。これは後で詳しく見るが、輸入においては域内の部品貿易が急速に拡大して域内比率を高めたのに対して、輸出においては域内への部品貿易とともに域外への消費財輸出も同時に拡大していったことが影響していると考えられる。なお、EU、NAFTAにおいては輸出の域内比率の方が輸入よりも高い水準で推移しており、特に1990年代のNAFTAの輸出における域内比率の上昇が顕著である(2000年代初頭以降に横ばいとなっているのは米国ITバブルの崩壊の影響などが考えられる)。
輸出における域内比率を財別に見ると、EUは総じて各財とも域内比率が高く、その推移も同じような動きとなっている(第Ⅱ-3-1-3図)。これに対して、東アジアの場合は財別に大きな相違が見られる。具体的には、素材、部品、加工品の域内比率が高く、特に部品は大きく上昇している。他方、消費財、資本財については域内比率が低く、特に消費財の域内比率の低下が顕著である。これは1990年代から2000年代にかけて、東アジアで機械工業を中心とする国際的な生産分業が進展していったことを示唆している。ただし、リーマン・ショック後、東アジアの消費財の域内比率上昇の動きも見られる。
第Ⅱ-3-1-3図 主要経済圏の輸出における財別域内比率の推移
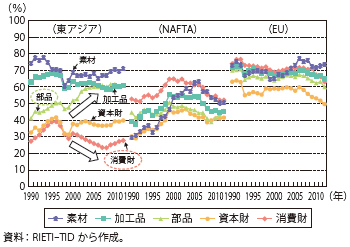
(2)域内貿易の特徴
次に域内貿易の特徴を見ていく。財別に金額、シェアの推移を見ると、東アジアは、消費財に比べて、部品の貿易額の急増が目立ち、EUで部品よりも消費財が大きくなっているのとは対照的である(第Ⅱ-3-1-4図)。その結果、シェアの変化を見ると、東アジアの部品のシェアが上昇する一方、消費財のシェアが低下している(第Ⅱ-3-1-5図)。東アジアの直近の財別シェアを主要経済圏で比較すると、部品のシェアが極めて高く(2012年:東アジア29.1%。NAFTA 18.0%、EU 15.8%)、反対に消費財のシェアが極めて低くなっている(東アジア11.5%、NAFTA 21.6%、EU 28.5%)。
第Ⅱ-3-1-4図 主要経済圏の域内貿易の推移(財別金額)
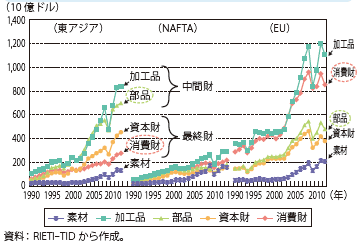
第Ⅱ-3-1-5図 主要経済圏の域内貿易の推移(財別構成比)
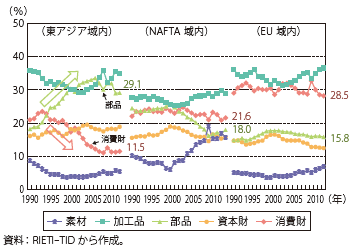
(3)東アジアの域外貿易
東アジアの輸出について域内と域外の主要輸出先を見ると、域内向け輸出は中間財が多いのに対して、域外(NAFTA、EU)向け輸出は最終財が多い。これは域内で組み立てられた最終財が域外に輸出されていることが示唆される(第Ⅱ-3-1-6図)。
第Ⅱ-3-1-6図 東アジアの地域別・財別輸出額の推移東アジアの地域別・財別輸出額の推移
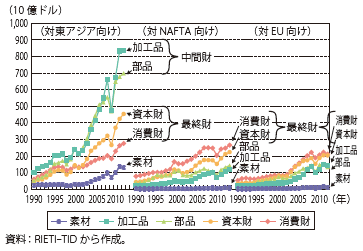
3.東アジアの貿易構造の変化
(1)東アジアの輸出先の変化
これまで見てきた東アジアの貿易構造は、消費財等の需要の多くを欧米市場を中心とする域外が占めていたため、域外の需要動向による影響を受けやすい面があり、実際にリーマン・ショックにおいては大きな影響を受けた。このため、リーマン・ショック後は東アジアの域内需要に立脚した自立的な経済圏としての成長を期待する声が高まった。リーマン・ショック後、実際に貿易構造は変わったのか、最終財の輸出先の変化を見ることによって考察する。
まず、東アジアの消費財について見ると、東アジア、米国、EU向けともリーマン・ショック直後の2009年は輸出額が落ち込んだが、2010年以降は回復に向かい、特に東アジア向けが大きく上昇している(第Ⅱ-3-1-7図)。なお、債務危機に見舞われたEU向けは2012年に再び低下している。この結果、輸出先の地域別シェアを見ると、東アジアのシェアが上昇している。東アジアの中では、日本、ASEANのシェアが大きい。
第Ⅱ-3-1-7図 東アジアの相手別輸出の推移(消費財)
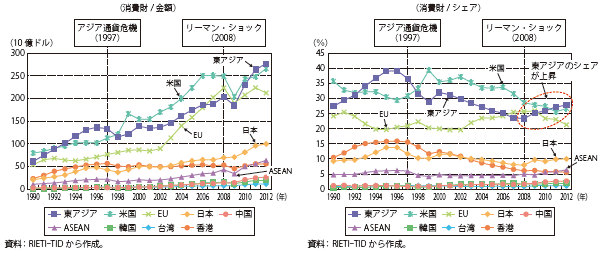
次に資本財について見ると、東アジア向けの輸出額は、1990年代から米国、EU向けをおおむね上回り、2000年代以降、伸びが大きくなっている(第Ⅱ-3-1-8図)237。特に中国、ASEAN向けが大きい。輸出額は2009年に減少するものの、2010年から再び増加している。輸出先の地域別シェアを見ると、米国向けが横ばい、EU向けが低下する中で、東アジア向けは上昇している。東アジアの中では、中国、ASEANのシェアが大きい。
237 資本財には、工作機械、建設機械のような設備投資、インフラ建設に関連した産業用機械が含まれる。アジアでは投資需要が盛んなことが資本財シェアの大きい要因と考えられる。
第Ⅱ-3-1-8図 東アジアの相手別輸出の推移(資本財)
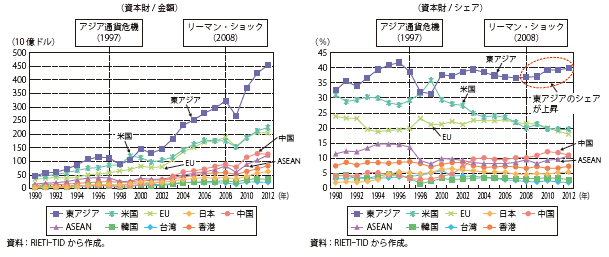
なお、同様に中間財の輸出先の地域別シェアを見ると、リーマン・ショック後、部品では、日本のシェアはわずかに低下し、中国、ASEANはやや上昇している(第Ⅱ-3-1-9図)。加工品では、日本はほぼ変わらず、ASEANは一旦低下した後上昇し、中国は一旦上昇した後低下している(第Ⅱ-3-1-10図)。
第Ⅱ-3-1-9図 東アジアの相手別輸出の推移(部品)
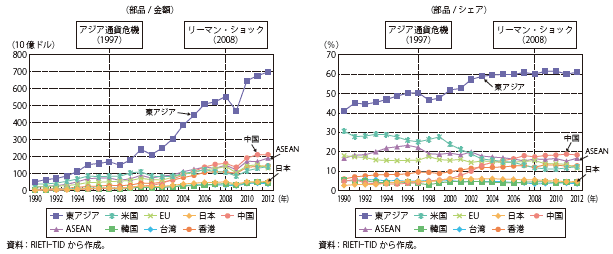
第Ⅱ-3-1-10図 東アジアの相手別輸出の推移(加工品)
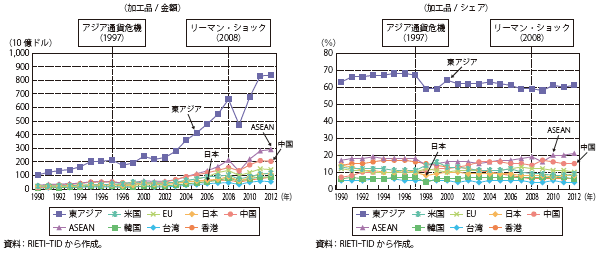
このように、最終財輸出における東アジアのシェアは緩やかではあるが上昇しており、域内の需要に基づく経済圏に向けた動きが見られる。
(2)東アジアの輸出国の変化
次に東アジアの中でどの国・地域が輸出を拡大しているのかを見ていく。
①域内向け
東アジアの輸入に占める各国・地域のシェアを見ると、NAFTAが1980年代に高いシェアを有していたが次第に低下し、かわって東アジア諸国がシェアを拡大している(第Ⅱ-3-1-11図)。まず日本がシェアを拡大したが1990年代中頃にピークとなり、それ以降は低下している。ASEAN、中国が1990年代にシェアを上昇させたが、2000年代に入り横ばいで推移している。
第Ⅱ-3-1-11図 東アジアの輸入に占める各国・地域別シェアの推移
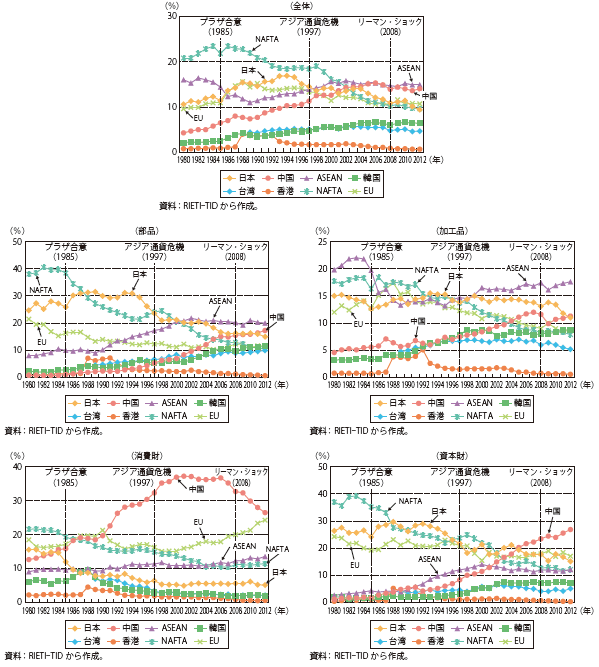
- Excel形式のファイル(全体)はこちら

- Excel形式のファイル(部品9はこちら

- Excel形式のファイル(加工品)はこちら

- Excel形式のファイル(消費財)はこちら

- Excel形式のファイル(資本財)はこちら

財別に見ると、域内で貿易額の多い部品については、日本が1990年代中頃までシェアを拡大したが、その後低下傾向となり、かわってまずASEAN、次に中国のシェアが上昇し、日本のシェアを追い抜いている。加工品についても、1990年代中頃まで日本が高いシェアを占めていたが、その後、ASEAN、中国に追い抜かれている。消費財については、近年低下傾向にあるものの中国のシェアが極めて大きくなっている。資本財については、日本のシェアが1990年代初めまで拡大したが、その後低下傾向となり、かわって中国のシェアが大きく上昇している。
②米国向け
域外への輸出について、米国向けを例にとって見ていく。米国から見た輸入相手国のシェアを見ると、日本のシェアはプラザ合意直後をピークに大きく低下している(第Ⅱ-3-1-12図)。これに対して中国のシェアは大きく上昇している。また、ASEANのシェアは1990年代中頃まで上昇し、その後緩やかに低下している。
第Ⅱ-3-1-12図 米国の輸入に占める各国・地域別シェアの推移
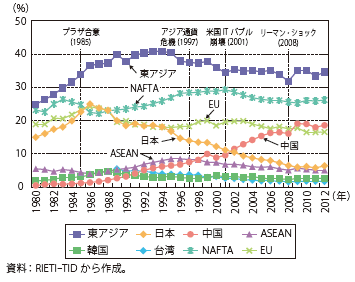
既に見たように、東アジアの米国向け輸出では最終財である消費財、資本財のシェアが高いことから、これらの財別の動向を見ていく。消費財については、日本のシェアはプラザ合意直後をピークに低下しており、対照的に中国のシェアが急上昇している(第Ⅱ-3-1-13図)。ASEANのシェアは1990年代中頃まで上昇し、その後はほぼ横ばいとなっている。消費財の中でも、家庭用電気機器及び輸送機械について見ると、日本のシェアは家電で急落している一方、輸送機械では低下しているものの1990年代末以後は横ばいないし緩やかな低下となっている。他方、中国のシェアは家電で大きく上昇している。ASEANは1990年代中頃まで家電のシェアが上昇したものの、その後は低調に推移している。韓国は輸送機械においてシェアを上昇させている。
第Ⅱ-3-1-13図 米国の輸入に占める各国・地域別シェアの推移(消費財)
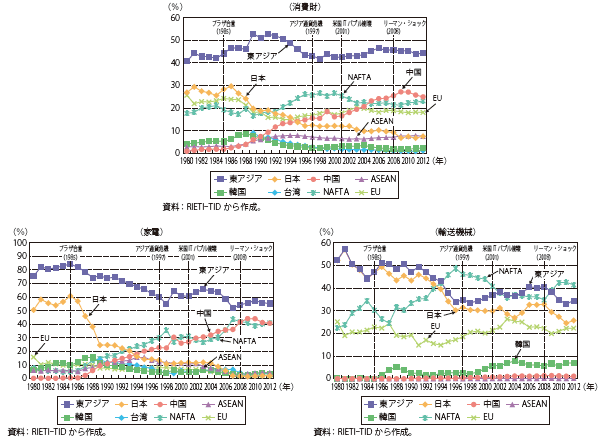
資本財については、米国の資本財輸入に占める日本のシェアはプラザ合意直後をピークに大きく低下している(第Ⅱ-3-1-14図)。これに対して、中国のシェアは大きく上昇し、特に2000年代に入って上昇が加速している。
第Ⅱ-3-1-14図 米国の輸入に占める各国・地域別シェアの推移(資本財)
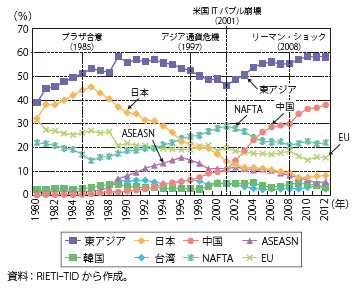
4.ASEANの域内貿易
ここまで、ASEANを一つの地域として、とらえてきたが、最後にASEANの域内貿易の動向について見ていく。
第Ⅱ-3-1-1図で見たように、ASEANの域外からの輸入は中間財のシェアが高く、域外への輸出は輸入に比べて最終財のシェアが高い。これはASEANで組み立てられた最終財が欧米へ輸出されることを示唆している。
そのASEAN域内においても、部品、加工品の中間財の貿易額が大きい(第Ⅱ-3-1-15図)。1990年代、部品の貿易額が拡大し、2000年代、加工品の貿易額も拡大している。
第Ⅱ-3-1-15図 ASEAN域内の財別貿易の推移
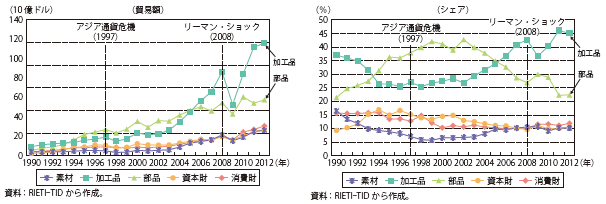
加工品と部品の内訳を見ると、加工品については、石油・石炭が大きな貿易額を占めており、石油精製品が貿易されていることがうかがえる(第Ⅱ-3-1-16図)。これを輸出国別で見ると、シンガポール及びマレーシアの輸出額が多い(第Ⅱ-3-1-17図)。
第Ⅱ-3-1-16図 ASEAN域内の中間財の貿易額の推移

第Ⅱ-3-1-17図 ASEAN域内の加工品(石油・石炭)の国別輸出額の推移
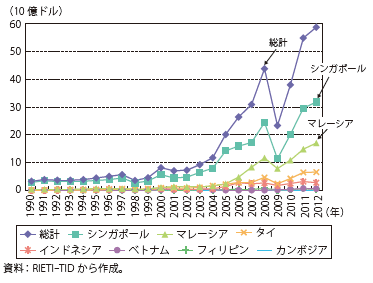
部品については、電気機械を始め、一般機械、輸送機械の部品が域内で貿易されている。これはASEAN諸国が部品を域外から受け入れるだけでなく、域内においても生産していることを意味する。
ここでは、2000年から2012年のASEAN域内の部品貿易額238の変化を概観する。第Ⅱ-3-1-18図は2000年、2012年のASEAN各国間の部品貿易額を示している(額が多いほど矢印の幅が広い)。また、第Ⅱ-3-1-19表は、同データと2000年から2012年の変化率(倍)(以下、「変化率」という。)をマトリックスで示している。
238 RIETI-TID2012の中間財(部品)のデータを使用した。対象国は同データを取得可能なインドネシア、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、カンボジアの7か国。
第Ⅱ-3-1-18図 ASEAN域内の部品貿易(2000年、2012年)
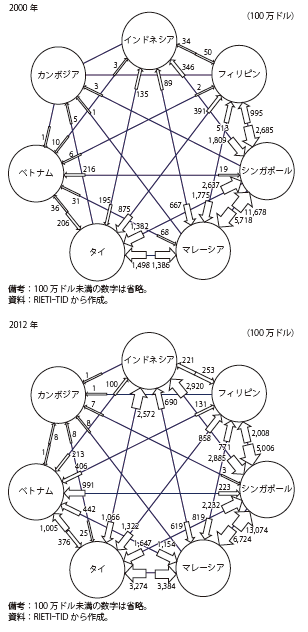
第Ⅱ-3-1-19表 ASEAN域内の部品貿易(2000年、2012年)
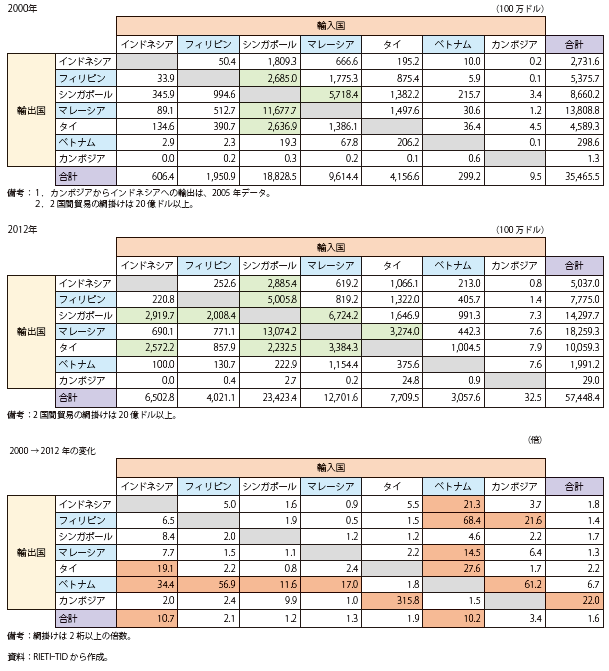
これらを見ると、第一に、2012年輸入額が最も多いのはシンガポールの234億ドルで、2000年時点と同じく首位を維持している。ただし、輸入額の変化率は1.2倍と、域内で最も小さい。同様に、2000年、2012年輸入額が2位であるマレーシアも輸入額の変化率は1.3倍と、域内ではシンガポールに次いで小さい。また、2012年輸出額が最も多いのはマレーシアの183億ドル、2位はシンガポールの143億ドルである。両国の輸出額の変化率はそれぞれ1.3倍、1.7倍と、域内では比較的小さい伸びとなっている。
第二に、インドネシアの2012年輸入額は65億ドルと第4位の水準であるが、輸入額の変化率は10.7倍と、域内で最も大きい。これはシンガポール及びタイからの輸入額が大きく増加したことが寄与している。シンガポールからの輸入は電気機械と一般機械で全体の86%を占め、タイからの輸入は輸送機械及び一般機械で全体の77%を占める。また、タイの2012年輸出額は101億ドルと第3位の水準であり、輸出額の変化率は2.2倍と、ASEAN主要国の中では比較的大きい伸びを示している。これらを含めて、インドネシア及びタイの輸出入額の変化率は、それぞれシンガポール及びマレーシアよりも大きい(インドネシア輸出1.8倍、輸入10.7倍、タイ輸出2.2倍、輸入1.9倍、シンガポール輸出1.7倍、輸入1.2倍、マレーシア輸出1.3倍、輸入1.3倍)。
第三に、ベトナムは輸出入ともに、各国との貿易額が大きく伸びている。輸出入額の変化率は多くの国で二桁にのぼり、特にフィリピンとの輸出入の変化率が大きい(輸出56.9倍、輸入68.4倍)。
最後に、カンボジアは、他国よりも貿易額の水準が著しく小さいが、2012年のタイ向け輸出が2,480万ドルと2000年の300倍超に急増している。これを産業別に見ると、99%は電気機械関連である。
以上から、2000年と比較した2012年のASEANの域内部品貿易についていえることとして、依然としてシンガポール及びマレーシアの貿易額が多いこと、他方でタイやインドネシアの貿易額はシンガポール及びマレーシアを上回るペースで伸びていること、ベトナムが域内各国との貿易関係を深めていること、カンボジアが電気機械のタイ向け部品供給地として貿易額を拡大していること、が挙げられる。
