第2節 我が国企業と東アジアの関わり
これまで見てきた東アジアの貿易構造の特徴、中間財貿易の拡大、中国、ASEANの輸出拡大には、日系製造業企業による海外展開と密接な関係がある。ここでは日本の直接投資の動向を確認し、日系海外現地法人の経済活動(売上げ、資材調達、日本への送金)の推移を概観する。
特に、日系海外現地法人の経済活動の分析に当たっては、①日本企業の稼ぎ方が変わったのか、②アジアの中での生産シフトがあるか、③国内と海外の分業体制に変化があるかという視点から考察する。
1.対外直接投資
(1)フローベース
我が国の長期的な直接投資の推移を見ると、まず、1980年代後半、プラザ合意後の円高方向の動きの中で大きく増加していく。1980年代後半は不動産など非製造業を中心とする米国向け直接投資が大きかったが、バブル崩壊後、米国向けが大きく落ち込み、かわって製造業を中心とするアジア向け投資が拡大していく。アジア向け投資は、アジア通貨危機で一旦縮小するものの、2000年代、再び拡大している(第Ⅱ-3-2-1図)。
第Ⅱ-3-2-1図 日本の直接投資の推移
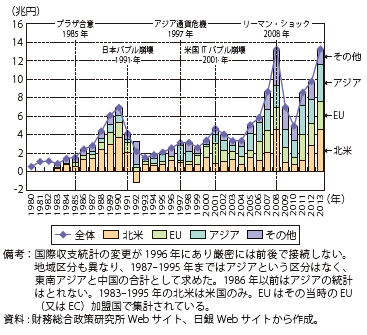
アジア向けと米国向けでは業種構成が大きく異なっている239。米国向けは不動産、サービス、金融・保険、卸・小売、そして最近では通信業等の非製造業が相対的に大きい(第Ⅱ-3-2-2図)。他方、アジア向けは、電気機械、輸送機械、一般機械、化学、鉄・非鉄金属等の製造業が相対的に大きく、生産拠点の海外展開を通じて、中間財の輸出に結びついている(第Ⅱ-3-2-3図)。なお、北米、アジアとも最近は非製造業が伸びてきている。
第Ⅱ-3-2-2図 日本の業種別直接投資の推移(北米)
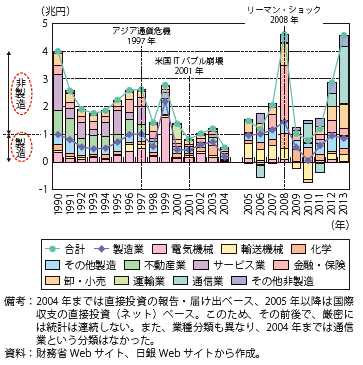
第Ⅱ-3-2-3図 日本の業種別直接投資の推移(アジア)
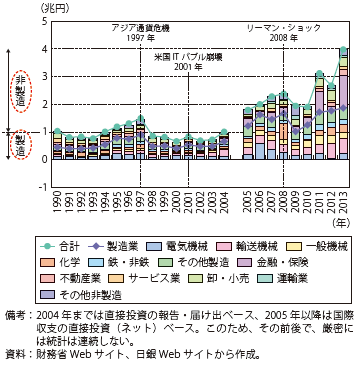
239 国際収支の直接投資統計で業種別が把握できるのは2005年以降のため、ここでは2004年までは直接投資の届出統計を利用した。ただし、届出統計は成約時の投資総額を表示したものであり、投資の回収は含まれない等の特徴がある。このため、その前後で、厳密には統計は連続しない。
(2)残高ベース(ストックベース)
次に直接投資を残高ベースで見ると、フローベースは年ごとの変動が大きいが、残高(ストック)ベースは安定的に推移している。我が国の直接投資残高は、リーマン・ショック等の影響による一時的減速はあるものの、すう勢的に増加してきている(第Ⅱ-3-2-4図)。地域別のシェアを見ると、北米が大きいものの、2000年代初め以降、シェアの低下が続いている(第Ⅱ-3-2-5図)。それに対して、アジアは、1997年の通貨危機の際は落ち込んだものの、2000年代に入ってシェアを拡大しており、直近では北米に匹敵する水準に達している。EUは依然として20%以上のシェアを維持しており、北米、アジア、EUの3地域で直接投資残高全体の約8割を占めている。
第Ⅱ-3-2-4図 日本の直接投資残高の推移

第Ⅱ-3-2-5図 日本の直接投資残高の地域別シェアの推移
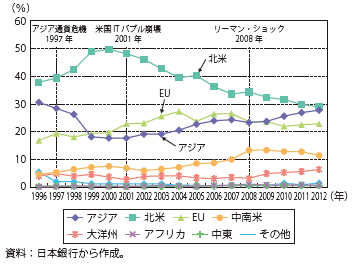
業種別には、2005年以降、製造業、非製造業共に拡大したが、非製造業の伸びが高い。近年は、特に金融・保険、卸・小売、鉱業、通信等が拡大している(第Ⅱ-3-2-6図)240。
第Ⅱ-3-2-6図 日本の業種別直接投資残高の推移
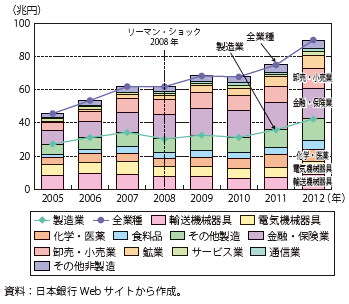
240 2005年から直接投資の業種別残高が公表されるようになった。
アジアでは製造業中心に伸びているのに対して、北米では金融・保険、卸・小売りなど非製造業が拡大している(第Ⅱ-3-2-7図)。
第Ⅱ-3-2-7図 日本の地域別・業種別直接投資残高の推移
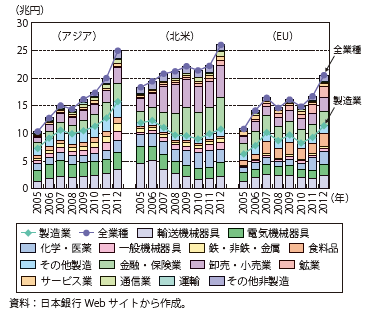
アジアの直接投資残高が拡大しているが、アジアの中ではASEANが緩やかにシェアを拡大するとともに、2000年代、中国のシェアがより速いペースで上昇しつつある(第Ⅱ-3-2-8図)。ASEANの中では、アジア通貨危機に際してタイ、インドネシアが大きく低下したが、2000年代、タイへの投資が急速に回復し、シンガポールと並ぶほどの水準となっている。また、リーマン・ショック後はインドネシアのシェアが緩やかに上昇し、ベトナムもシェアを拡大している。
第Ⅱ-3-2-8図 日本の国・地域別直接投資残高の推移(アジア)
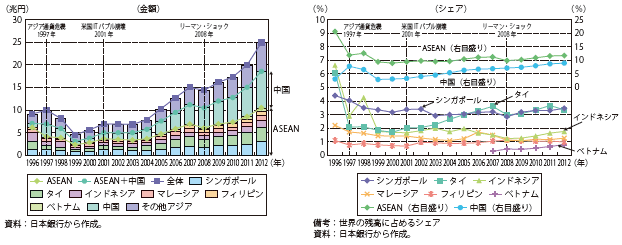
(3)我が国の輸出への影響
このような直接投資の動向を背景に、プラザ合意後、日本の輸出は東アジア向けを中心に増加した(第Ⅱ-3-2-9図)。東アジア向け輸出は、日系製造業企業の進出に伴って、電気機械を中心とした部品などの中間財が拡大しており、東アジア域内における国際的生産分業の展開を示唆している(第Ⅱ-3-2-10図)。一方、米国向け輸出は、直接投資の多くが必ずしも資材輸出を伴わない非製造業であることもあり、輸出の伸びは緩やかになっている。なお、消費財輸出については輸送機械が多くなっている。
第Ⅱ-3-2-9図 日本の相手地域別の輸出額の推移
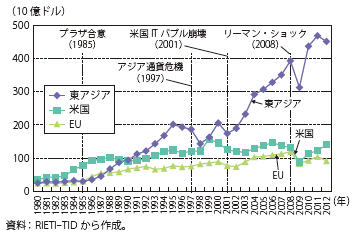
第Ⅱ-3-2-10図 日本の相手地域別・財別輸出額の推移
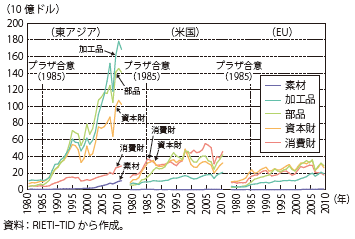
2.日系海外現地法人の活動
このような海外展開に伴って、我が国企業の稼ぎ方にも変化が生じている。貿易の面では、北米等への輸出に加えて、東アジアの国際的な生産分業に向けての中間財輸出が大きく拡大し、また、貿易以外の面では、海外現地法人の生産活動とそれに伴う配当金やロイヤリティ収入が拡大してきている。その様子を日系現地法人の統計などから見ていく。
まず、我が国企業の海外展開(現地法人数、売上高)を確認し、次に、稼ぎ方(日本からの資材調達、日本への配当・ロイヤリティの支払)を見ていく。その上で、国内と海外の分業体制の変化を考察する。
(1)日系海外現地法人数と売上高
まず、我が国企業が、主としてどこに展開し、どこで生産活動を行っているのかを確認する。我が国の海外現地法人数は拡大してきており、その主要地域別シェアを見ると、製造業のアジア展開に伴って、アジアのシェアが上昇している。アジアの中では特に中国の拡大が著しい(第Ⅱ-3-2-11図)。
第Ⅱ-3-2-11図 日系海外現地法人の推移(主要地域別シェア)
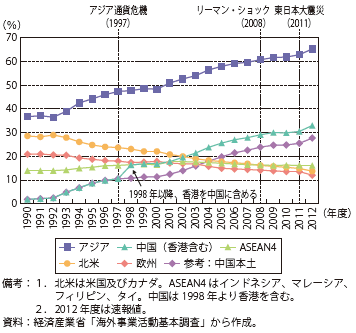
2012年度末の展開を見ると、日系海外現地法人数は23,351社であり、アジアが全体の65.2%を占めている。その内、中国(香港を含む、以下同じ)は同33.0%、ASEANは同23.2%と、北米(同13.8%)や欧州(同12.1%)を上回っている。製造業では全体の76.4%がアジアに集中しており、その大部分を中国(全体の39.7%)とASEAN(同27.7%)が占めている(第Ⅱ-3-2-12表)。
第Ⅱ-3-2-12表 日系海外現地法人数(2012年度末)

日系海外現地法人の売上高を見ると、リーマン・ショック等の影響により減速することはあったが、すう勢的に拡大している(第Ⅱ-3-2-13図)。主要地域別に見ると、アジアの成長が著しく、2006年度以降、製造業の展開が著しいアジアの日系現地法人が北米の日系現地法人を上回っている。売上高全体としてはリーマン・ショック前の水準を下回って推移しているが、アジアの日系現地法人はリーマン・ショック前の水準を上回っている。
第Ⅱ-3-2-13図 日系海外現地法人の売上高の推移(主要地域別)(左:額、右:シェア)
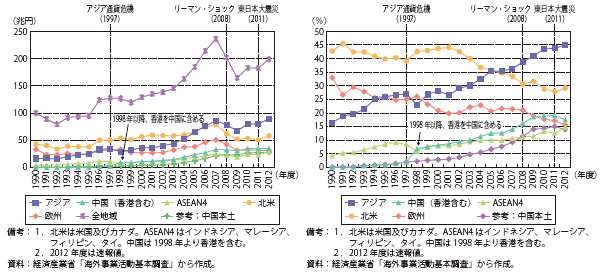
ここでアジアに焦点を当て、売上額の推移を見ると、日本や欧米への売上げのほかに、現地国内への売上げが拡大している(第Ⅱ-3-2-14図)。シェアの推移を見ると、現地販売比率が上昇していることがわかる(第Ⅱ-3-2-15図)。
第Ⅱ-3-2-14図 アジアの日系製造業現地法人の売上額の推移
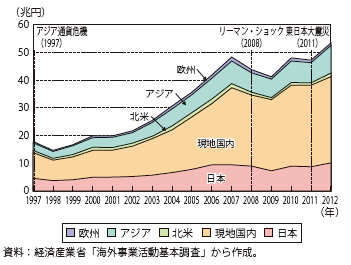
第Ⅱ-3-2-15図 アジアの日系製造業現地法人の地域別売上額シェアの推移
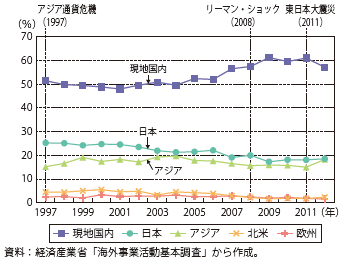
(2)我が国企業の稼ぎ方
我が国企業の直接投資による海外展開に伴って、日本の稼ぎ方、国際収支に与える影響が異なってくる。例えば、日系現地法人の日本からの基幹部品などの資材調達は我が国の貿易収支に現れ、日系現地法人の売上げは、配当収入として第一次所得収支に影響し、現地法人が支払う特許利用料、ロイヤリティはサービス収支に計上される。
①資材調達活動
我が国の製造業企業は、プラザ合意後の円高方向の動きの中で、アジアを中心に現地法人を設立し生産活動を営んできた。その生産に必要な基幹部品をはじめとする資材は親会社をはじめとする日本から調達するとともに、現地や第三国からも調達している。このような生産拠点間の調達の流れが、これまで見てきた東アジア域内の部品を中心とした中間財貿易の背景となっている。
まず、日系海外現地法人(製造業)の日本からの資材調達は、北米、欧州は低調に推移しているものの、アジアに立地する日系海外現地法人の調達額は拡大している(第Ⅱ-3-2-16図)241。
第Ⅱ-3-2-16図 日系海外現地法人(製造業)の日本からの資材調達額
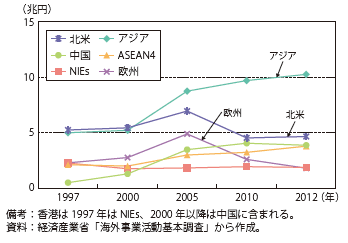
241 非製造業の分析は割愛した。もともと非製造業は資材調達が少なく、しかも約9割を卸売業(商社による貿易等が考えられる)で占め、製造業の資材調達と重複する可能性が高い。
ここでは、特にアジアに焦点を当てて日系製造業現地法人の調達活動の現状や最近の動きを見ていく。アジアの日系製造業現地法人は、生産額が拡大する中で、日本からの基幹部品等の資材調達額を拡大してきた(近年では、リーマン・ショック、東日本大震災の影響等による調達額の減少も見られた)(第Ⅱ-3-2-17図)242。他方、調達先別のシェアを見ると、現地調達率が上昇するとともに、日本からの調達率は緩やかに低下してきている(第Ⅱ-3-2-18図)。
第Ⅱ-3-2-17図 アジアの日系製造業現地法人の資材調達額の推移
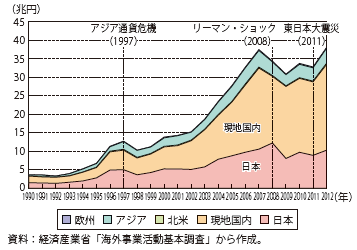
242 日系現地法人の活動については、経済産業省「海外事業活動基本調査」のデータを利用して分析を行う。その際の「アジア」とは、統計上、中東、オセアニアを除いたアジア全域の集計データを指す。なお、北米は、カナダ、米国の2か国、ASEAN4は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイの4か国である。
第Ⅱ-3-2-18図 アジアの日系製造業現地法人の資材調達先別シェアの推移
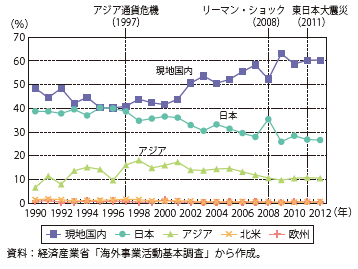
調達先の地域構成は業種によってかなり相違が見られる。電気機械では、現地国内や日本のほか、アジア域内第三国も一定のシェアを占めているのに対して、輸送機械では現地国内調達率が高くなっている(第Ⅱ-3-2-19図)。このような業種別の特徴は、部品の規格化の程度、生産過程におけるすり合わせの必要性、輸送コストの違い、技術水準等が影響していると考えられる。
第Ⅱ-3-2-19図 アジアの日系製造業現地法人の業種別の資材調達先シェア
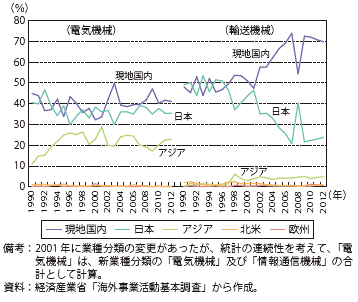
既に見たように日系製造業現地法人の現地調達率は上昇してきているが現地調達のうち約1/3は現地日系企業からの調達である(第Ⅱ-3-2-20図)。仮に日本からの調達(輸入)と現地日系企業からの調達を合計すれば約47%の調達率となる(第Ⅱ-3-2-21表)243。
第Ⅱ-3-2-20図 アジアの日系製造業現地法人の資材調達先別シェア(2012年)
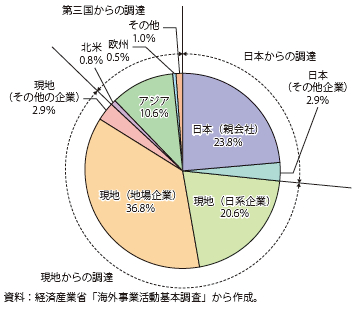
243 厳密には、第三国からの調達の中にも、第三国に立地している日系企業からの調達が含まれているはずであるが、データの制約から、第三国からの調達は日系企業とそれ以外の企業に分けることができないので、ここでは広義の日本からの調達に含めていない。
第Ⅱ-3-2-21表 アジアの日系製造業現地法人の資材調達先別シェア
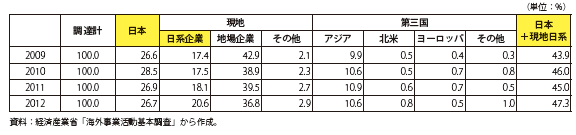
このような「広義の日本からの調達」(日本からの輸入+日系現地企業からの調達)に着目して、アジアの日系製造業現地法人の業種別調達をプロットしたのが第Ⅱ-3-2-22図である244。横軸は日本からの調達シェア、縦軸は現地日系企業からの調達シェアで、円は調達総額の大きさを表す。このグラフでは右上に位置するほど広義の日本からの調達率が高く、45度線より左上に位置するほど日本よりも現地日系企業からの調達の方が多いことを示している。
第Ⅱ-3-2-22図 アジアの日系製造業現地法人の資材調達(2012年)
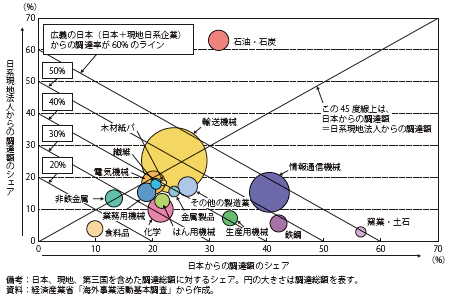
244 ただし、最終組立てに至るまでに、現地日系部品メーカーの間で何度か取引が行われる場合、重複計上が生じて現地日系企業の比率が過大評価されている可能性はある。
輸送機械では、日本からの調達率は低下しているものの、現地日系企業からの調達を合わせた「広義の日本からの調達」は調達総額の49%と半分近い。このように日本からの調達と現地日系企業からの調達がほぼ拮抗する業種としては、45度線近辺に位置している電気機械、業務用機械等が挙げられる。また、情報通信機械では、比較的日本からの調達率が高く、「広義の日本からの調達」は56%となっている。
次に、立地国によって調達行動に相違があるか見ていく。中国とASEAN4を比べると、日本からの調達率については大きな差がないが、中国に比べてASEAN4では、現地日系企業からの調達率が高く、反対に現地地場企業からの調達率が低い(第Ⅱ-3-2-23図)。また、データが取得可能な4年間に、ASEAN4では現地日系企業からの調達率は上昇している。
第Ⅱ-3-2-23図 日系製造業現地法人の資材調達先別シェア(中国とASEAN4)
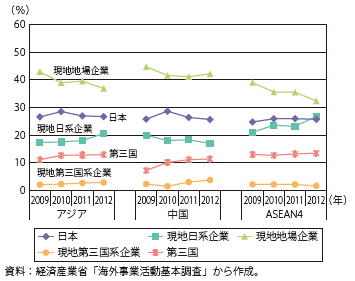
②配当金・ロイヤリティ
日系海外現地法人の活動によって得られた利益から日本の出資者に対して配当金が支払われる。また、本社の技術やブランドなどを利用する場合は、ロイヤリティが送金される。このような日本の出資者に対する支払額がすう勢的に増加している(第Ⅱ-3-2-24図)。製造業においてはアジアを中心に支払額が拡大し、非製造業においては北米等からの支払額拡大が著しい。
第Ⅱ-3-2-24図 日系製造業現地法人の日本出資者向け支払の推移
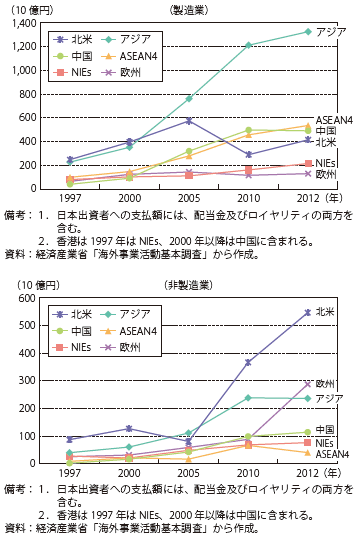
業種別には、製造業の割合が大きく、特に輸送機械、化学、情報通信機械、電気機械で全支払額の過半を占めている(第Ⅱ-3-2-25図)。非製造業の中では卸売業が大きな割合を占めている。
第Ⅱ-3-2-25図 日系現地法人の日本出資者向け支払(業種別/2012年)
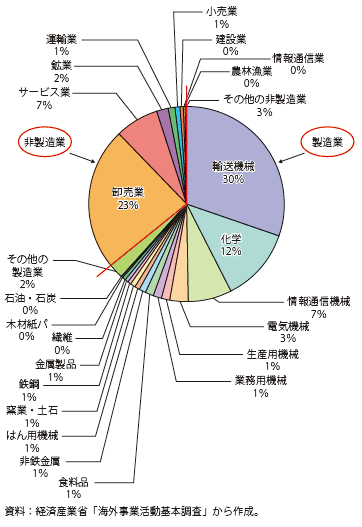
さらに地域・業種別のクロスでみれば、アジアは、輸送機械を筆頭に、情報通信機械、電気機械等の機械類や化学など製造業からの送金が多い(第Ⅱ-3-2-26図)。北米は、製造業は輸送機械、化学が多いが、むしろ非製造業の卸売業からの支払が目立つ。
第Ⅱ-3-2-26図 日系現地法人の日本出資者向け支払
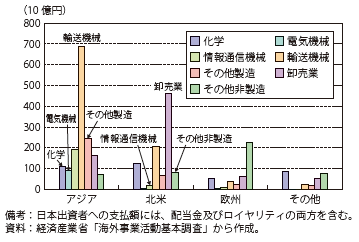
このように我が国の本社企業は、アジアの現地法人から最も配当・ロイヤリティを受け取っており、第一次所得収支(直接投資収益受取)においてアジアの比率が高いことに符合する(第Ⅱ-3-2-27図)。
第Ⅱ-3-2-27図 我が国の所得収支(直接投資収益受取)額(2012年)
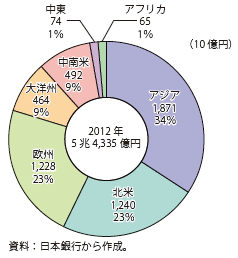
日系海外現地法人の「日本からの資材調達額」と「日本出資者への送金額(配当・ロイヤリティ)」の推移を比較すると、製造業においては、アジアは資材調達額、配当・ロイヤリティともに拡大しており、配当・ロイヤリティの資材調達に対する比率は上昇している(第Ⅱ-3-2-28図)。北米、欧州では資材調達額は減少傾向、配当・ロイヤリティは横ばいとなっており、配当・ロイヤリティの比率はアジアと同様上昇している。配当・ロイヤリティの比率の上昇は、現地法人の利益が拡大しているとともに、現地調達率の上昇も影響していることが考えられる。
第Ⅱ-3-2-28図 日系海外現地法人(製造業)に係る日本の収入
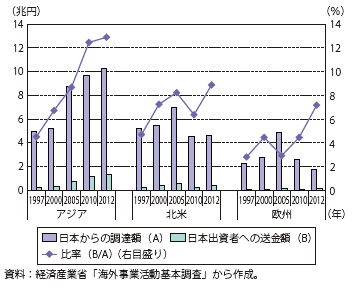
(3)アジアの中での生産シフト
日系現地法人の立地国別の売上げの推移から、アジアの中での生産拠点の変化を見ていく245。中国の売上げが大きく伸びているほか、ASEANのタイ、インドネシアの拡大が目立つ。また、まだ金額は小さいものの、ベトナム、インドも拡大しており、アジア全体に生産が拡大している様子が見られる(第Ⅱ-3-2-29図)。シェアで見ると、相対的にASEANが低下して、中国のシェアが大きく上昇している(第Ⅱ-3-2-30図)。ただし、直近では、ASEANの上昇、中国の低下と反転の動きも見られる。ASEANの中では、シンガポールのシェアが低下し、かわってタイ、インドネシアのシェアが上昇している。
第Ⅱ-3-2-29図 アジアの日系海外現地法人の売上額
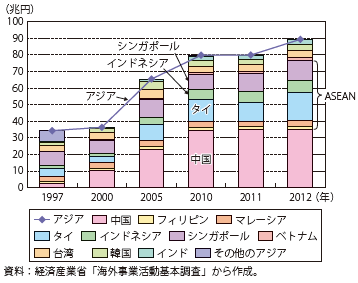
245 統計の関係から、生産額のデータがとれないため、売上額で代用する。
第Ⅱ-3-2-30図 アジアの日系海外現地法人の売上シェア
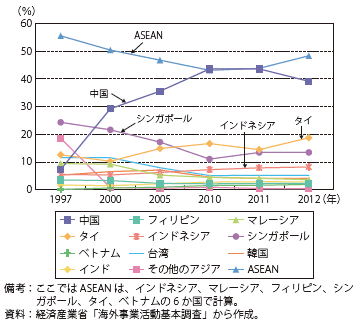
日本企業に対する有望投資先国の調査を見ると、2000年代初め、中国を有望な投資先と考える企業の割合が高く、先に見たような日系現地法人の売上げ拡大につながったと考えられる(第Ⅱ-3-2-31図)。ASEANの中では、タイを有望視する企業割合が安定的に推移しているほか、ベトナム、インドネシアも上昇している。このような企業から見た投資有望先としての期待が、海外生産のシフトに反映していると見られる。
第Ⅱ-3-2-31図 中長期的な有望事業展開先
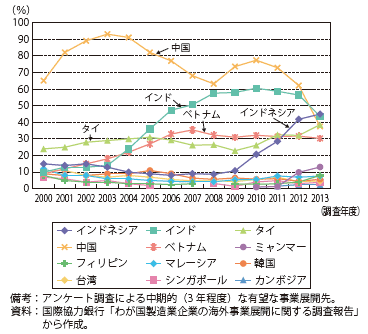
また、最近は中国を有望視する企業割合が低下してきているが、それまで安価な労働力を有望理由とする企業が多かったものの、むしろ労働コストの上昇等を課題として挙げる企業が増えてきている(中国を生産拠点からマーケットとして考える企業が増えていることも調査からは示されている)。それに対して、有望視する企業割合が上昇しているインド、ベトナム、インドネシアは、マーケットの成長性とともに、安価な労働力等も有望理由に挙げられている。我が国企業が、その時々の状況に応じて、アジアの中で最適な生産拠点を選定し、活動を行っていることがうかがえる246。
246 なお、インドについては期待が高いわりに、日系現地法人の売上額が少ないのは、インフラの未整備等を課題として挙げる企業が多く、このような課題が改善されれば投資が拡大していくものと予想される。
(4)国内と海外の分業体制の変化
このように我が国企業は、東アジアを中心に最適な拠点で経済活動を行っているが、日本国内との分業体制の変化を考える。
①海外生産比率
我が国企業の海外における生産活動は拡大し、海外生産比率は上昇している(第Ⅱ-3-2-32図)。特に輸送機械、情報通信機械で顕著である(第Ⅱ-3-2-33図)。
第Ⅱ-3-2-32図 海外生産比率の推移(製造業)
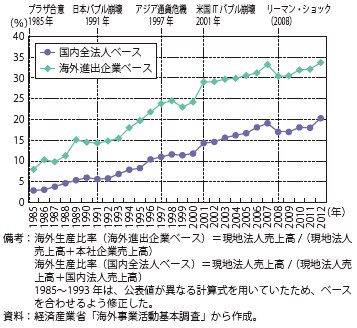
第Ⅱ-3-2-33図 業種別の海外生産比率(2012年)
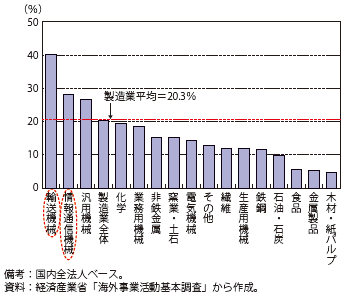
②設備投資額
日本における設備投資の伸びが緩やかな中で、海外における設備投資が活発化している。日系海外現地法人の設備投資額を四半期ベースで見ると、近年の円安方向への推移により、足下でドルベース(前年比減)と円ベース(前年比増)で傾向が異なるが、全体的に言えることは、2008年の水準を上回って推移している。特にアジアの伸びが大きい(第Ⅱ-3-2-34図)。アジアにおける設備投資額を業種別に見ると、輸送機械の投資額が大きく伸びる一方、電気機械は減少傾向が顕著となっている(第Ⅱ-3-2-35図)。
第Ⅱ-3-2-34図 日系海外現地法人の設備投資額の推移(主要地域別)
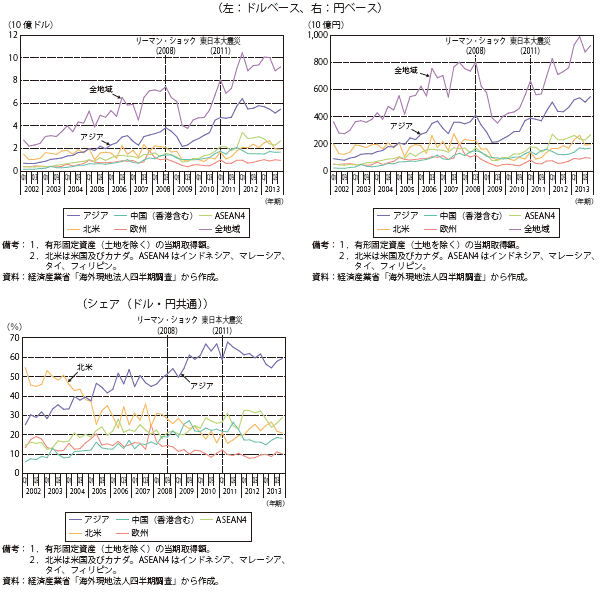
第Ⅱ-3-2-35図 アジアの日系海外現地法人の設備投資額の推移(主要業種別)
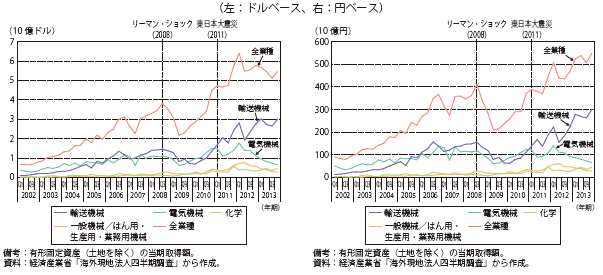
我が国企業の設備投資を国内・海外で分けて見ると、リーマン・ショック後、国内における設備投資が緩やかな伸びにとどまる中で、海外においては堅調に拡大している(第Ⅱ-3-2-36図)。その結果、設備投資の海外比率は、リーマン・ショック後に大きく上昇している。
第Ⅱ-3-2-36図 日本企業の海外及び国内の設備投資の推移
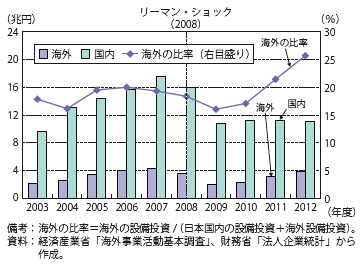
③研究開発活動
我が国企業は、国内で基幹部品を生産するための基礎技術を開発し、現地では現地マーケットの仕様に合わせるための研究開発を行ってきた。最近の研究開発費の推移を見ると、国内で研究開発を行うとともに、現地における研究開発も拡大してきている。特に製造業が展開するアジアの現地法人の研究開発費が大きく拡大し、総額では北米を追い抜くほどの規模になっている(第Ⅱ-3-2-37図、第Ⅱ-3-2-38図)。アジアでは輸送機械を筆頭に、情報通信機械、電気機械など機械業種での研究開発が活発に行われている。なお、北米は輸送機械、情報通信機械とともに、化学の研究開発が盛んなのが特徴的であり、欧州も化学が突出している。
第Ⅱ-3-2-37図 日系海外現地法人(製造業)の研究開発費の推移
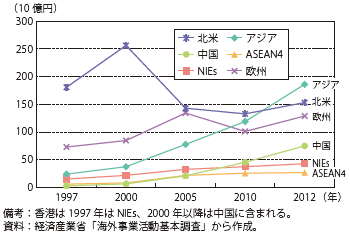
第Ⅱ-3-2-38図 日系海外現地法人(製造業)の研究開発費(地域・業種別/2012年)
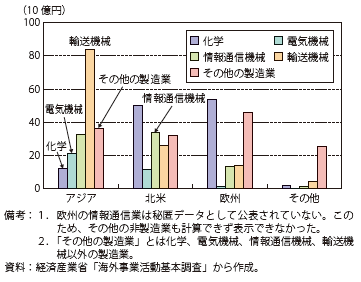
このほか、既に見たように、現地において組立て工程だけでなく、日系企業が進出し部材の生産や地場企業からの調達を拡大するなど、我が国と立地国との関係は深化している。このように我が国製造業企業は、アジアを中心に海外においても、生産、設備投資、研究開発、資材調達など積極的な活動を展開している。企業は最適な立地国を選択するとともに、立地国において、生産や設備投資活動を通じた経済発展、現地での研究開発や資材調達を通じた技術・ノウハウのスピルオーバーなど立地国への貢献も期待される。
本章では東アジアにおける貿易投資、我が国と東アジアの関わりがいかに深まってきたかを分析し、さらに我が国がアジア新興国の成長モデル転換に向けていかに貢献できるかを見ていく。
