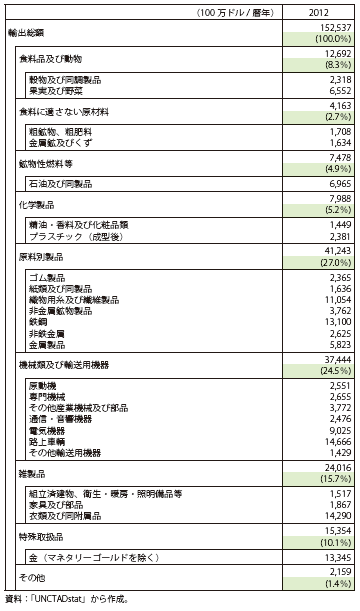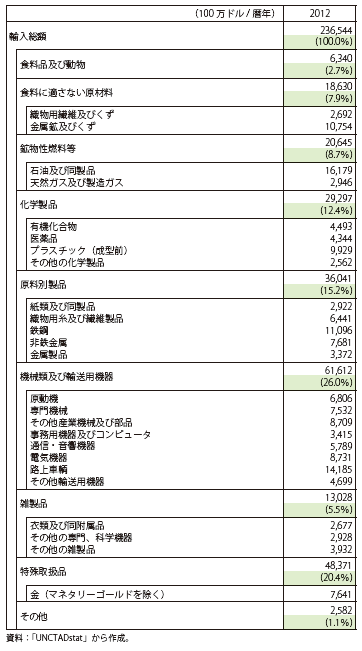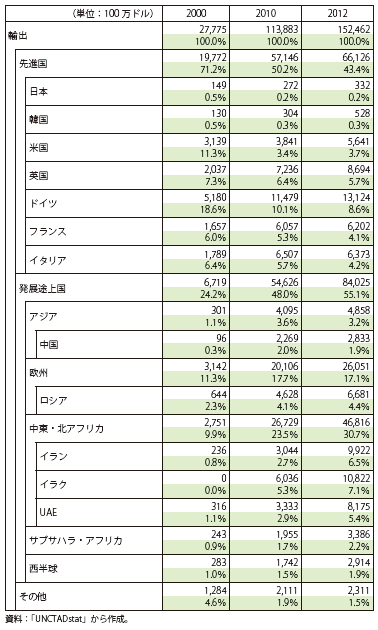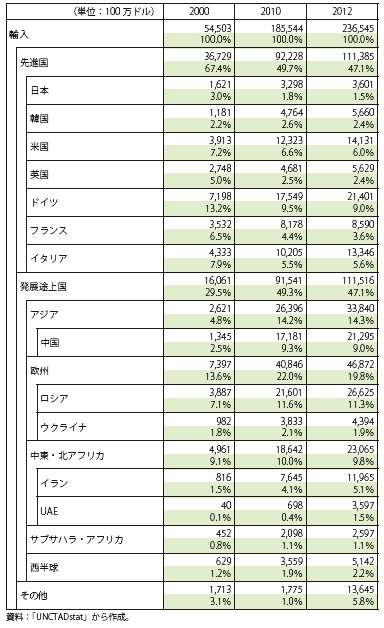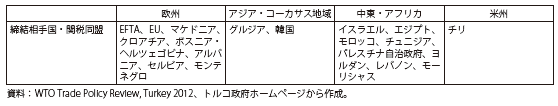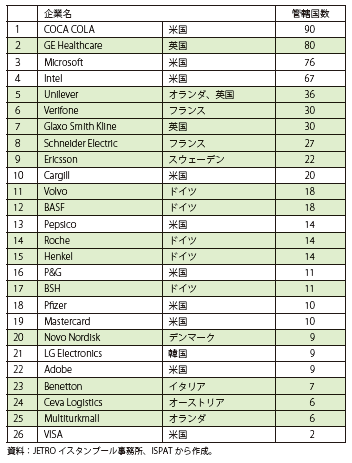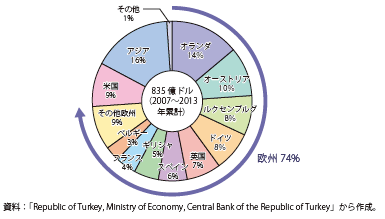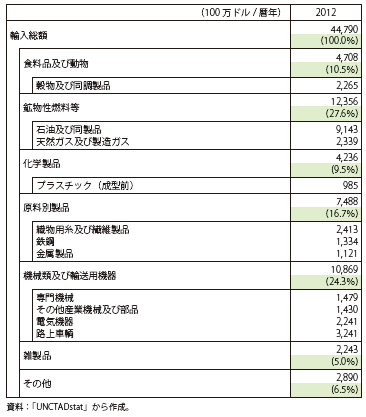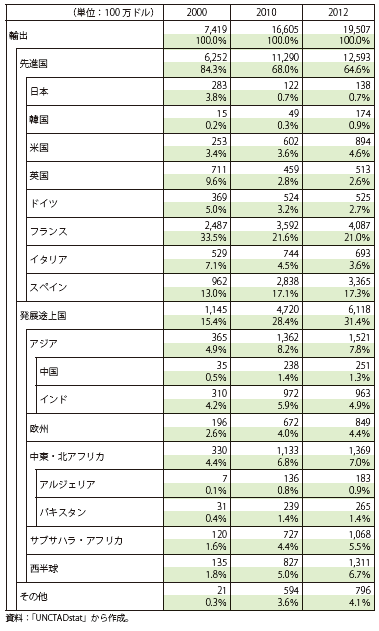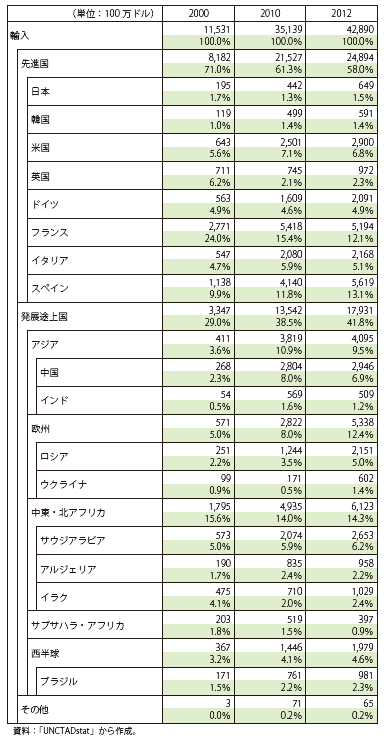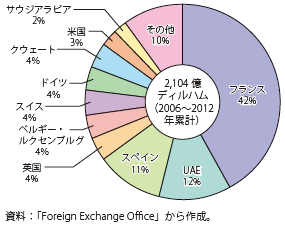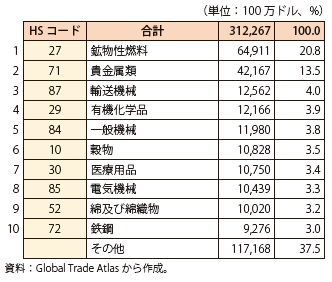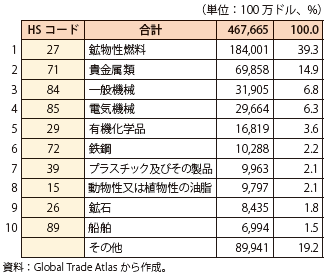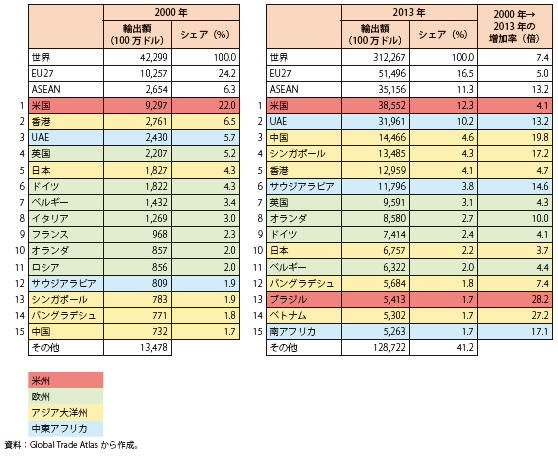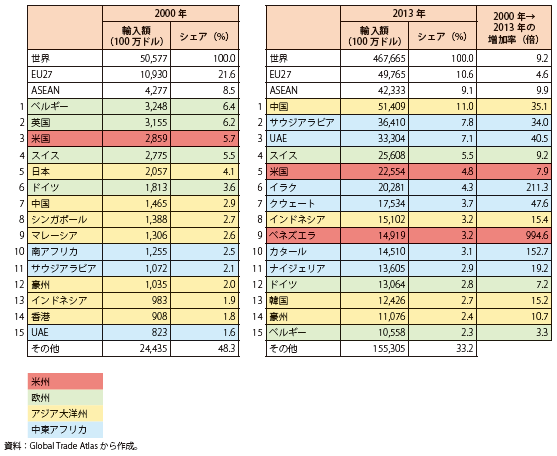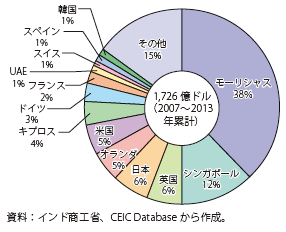第3節 我が国の貢献可能性
第1章では、2000年代の新興国の経済ファンダメンタルズの推移を確認した。各国のファンダメンタルズは全体で見れば差が小さくなる方向に移行していた。このことは、対象とした多くの国が、貿易や投資のグローバリゼーションの中に組み込まれていた結果と考えられる。中でも東アジア地域は、域内において高度な生産分業体制が構築され、世界貿易の拡大とともに成長してきた。(第Ⅱ-3-3-1図)
第Ⅱ-3-3-1図 アジアのGDPと輸出量推移
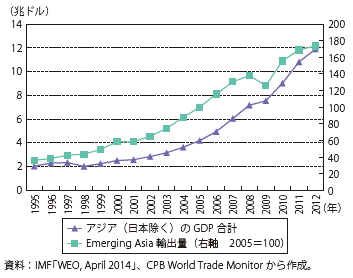
さらに、第2章では、リーマン・ショック以前の金融危機等の後に講じられた改革及びその効果や代表的な産業育成策を分析した。金融危機のような大きなショックは国内経済政策や通商政策を改革する契機になるものの、国内経済構造の改革の範囲や程度には差があり、それが効果の差をもたらした可能性が示唆された。また、分析対象とした国々において、対外経済政策の自由化は、自国産業の育成を優先させつつ漸進的に進んできているが、近隣諸国との経済連携の強化がより成長基盤の強化につながっている可能性も示唆された。
新興国における対外経済政策は、我が国企業の貿易投資行動にも大きな影響を与える。プラザ合意以降の我が国企業の東アジア地域における海外事業展開は、生産コストの低減を目的としたものが多かった247。しかし近年は、アジアの需要拡大をにらんだ海外展開が行われている。第1節及び第2節で明らかにしたように、東アジアにおいて日本からの調達額は低下しないものの、現地における調達や販売の割合も高まっている。JETROのアンケート調査によれば、2007年度から2013年度の間でみると海外で拡大する機能としては、販売機能の割合が圧倒的に高く、生産(高付加価値品)の割合が徐々に上がっている。(第Ⅱ-3-3-2図)
第Ⅱ-3-3-2図 海外で拡大する機能
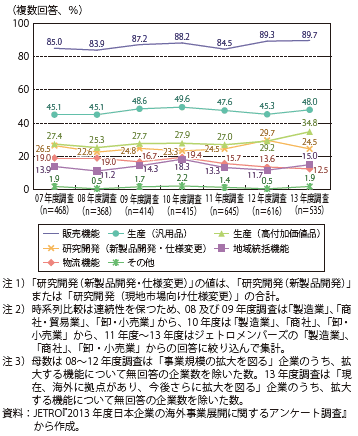
247 『通商白書2006』89ページ。
国内及び海外で拡大する機能を地域別に見ると、我が国企業は、国内において高付加価値品の生産及び新製品開発を重視しつつ、海外においては、アジア太平洋地域において、日本企業が高付加価値品の生産や現地市場向け仕様変更の拡大を積極的に行おうとしていることがうかがえる(第Ⅱ-3-3-3表)。
第Ⅱ-3-3-3表 国内・海外で拡大する機能(地域・国別)
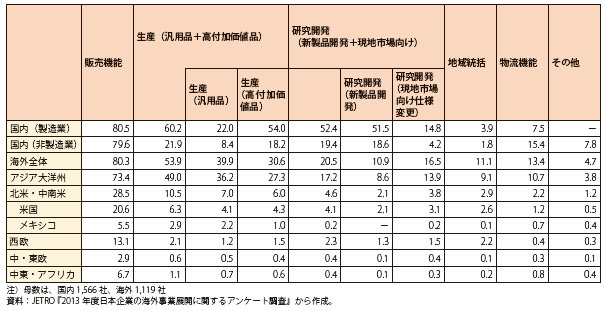
各国が長期的発展を遂げるために現在模索している成長モデルの転換においては、現地における裾野産業育成及び地場企業の能力強化のための高度人材育成、ハード・ソフトインフラ整備の促進、非関税障壁の撤廃による取引コストの低減等、企業の活力をいかすための事業環境整備を進めることが重要な役割を果たす。先に示した我が国企業のアジアにおける事業展開の深化は、技術、ビジネスモデルやノウハウを提供するかたちで事業環境整備に貢献するとともに、高度化する消費者のニーズにも応えることができると考えられる。
このような観点から、我が国の政府や企業による事業環境整備や高度化する消費者ニーズに答えるための具体的な事例を紹介する。
1.泰日工業大学(Thai-Nichi Institute of Technology)
第1章第4節で述べたように、タイは自動車及び電気・電子産業等の生産拠点となっている。更なる発展のためには優秀な技術者、中核産業人材を育成することが必要との考えに基づき2003年から様々な調査が行われ、2007年に泰日工業大学が開校した。同大学は、タイ日の友好とタイ産業界の人材育成を目的として設立された泰日経済技術振興協会を母体としている。履修課程は、①タイ産業界で需要の高い分野(特に自動車、電気・電子、ICT、生産技術)を重視、②日本のものづくりに直結する、実務かつ実践的な技術と知識を兼ね備えた学生を育成すること、③産業界、またタイ国内外の各種日本機関との強い協力関係をいかして、現場のインターンシップ教育を重視すること、④短大・高専卒等からの編入者や、社会人に対する土日、平日夜間の教育課程を用意すること、⑤日本語および英語でのコミュニケーション能力を有する学生を育成することを特徴とし、タイにおける産業人材の育成に貢献している。
2.マレーシア日本国際工科院(MJIIT)
マレーシアでは、知識集約的な生産拠点の構築を目指しているが、産業界が求める高度な知識を有する人材が不足している。この課題を克服するべく、2001年にマレーシア政府から日本政府に対し出された国際工科大学設置の提案を受け、日・マレーシア首脳会談にて構想を推進することで一致した。2010年にマレーシア政府は、マレーシア工科大学の下に日本型工学教育を導入し、高い生産性と競争力を有する人材育成を行う目的で、マレーシア日本国際工科院(MJIIT)を設立することを決定した。このプロジェクトでは、日本国内の大学を中心としたコンソーシアム等から、日本人教員の派遣、MJIITでの教育に必要な資機材の調達と、教育課程の整備を支援することにより、マレーシアの経済・社会の開発に貢献する、実践的で最先端技術の開発研究能力を備えた人材の育成を目指している248。
さらには、日本式工学教育を受けた優秀な人材を育成する場として、ASEANの工学教育のハブとなり、アジアをリードする高等教育機関に発展していくことが期待されている249。
248 JICA HP 「ODAが見える。分かる。マレーシア日本国際工科院整備事業」、(http://www.jica.go.jp/oda/project/MXXI-1/index.html![]() )。
)。
249 外務省HP 「マレーシア日本国際工科院(MJIIT)の開校」、2011年9月6日、(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/9/0906_06.html![]() )。
)。
3.トヨタ工業技術学校(インド)
我が国の自動車産業は、海外展開に際して進出先国の自動車関連産業の発展や人材育成に資するため、アジア諸国を中心に熟練技術者等専門家の派遣、セミナー開催、自動車整備学校への協力等、各種支援を政府と協力しつつ行っている250。例えば、JICAは自動車産業の競争力強化を目指すタイに対して、自動車裾野産業の人材育成のために専門家の派遣、人材育成・技能認定用機材の供与等を行うプロジェクトを実施した251。また、トヨタ自動車株式会社は、「産業報国の実を挙ぐべし」という考え方を新興国への取組の基本的なスタンスとしている。これは自動車産業を通じて、その国の経済、雇用、交通などの発展に貢献するために「裾野産業の育成、発展に貢献し、現地に根ざした活動を行う」という考え方である252。この考え方の下、インドにおいて2007年に「トヨタ工業技術学校(トヨタ・テクニカル・トレーニング・インスティテュート)」を設立した。当校は、能力はあるが、経済的理由等で高等学校への進学が難しい中学校卒業生を対象に、「モノづくり」の専門技術を習得することを目的としており、工業科目を履修すると共に、塗装、溶接、自動車組立て、メカトロニクスの4つの専門コースに分かれ技能を修得する他、トヨタのインド現地法人であるトヨタ・キルロスカ・モーター(TKM)での技能実習も行う。また、入学金や授業料についてはTKMが全額補助している253。
250 一般社団法人日本自動車工業会HP (http://www.jama.or.jp/intro/business_domain/business_domain03.html![]() )。
)。
251 JICA HP(http://www.jica.go.jp/project/thailand/003/![]() )。
)。
252 トヨタ自動車HP 「アニュアルレポート2012」、(https://www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/annual/pdf/2012/ar12_j.pdf![]() )。
)。
253 トヨタ自動車HP 「トヨタ自動車 インドで「トヨタ工業技術学校」の開校式を実施」、2007年8月1日、(http://www.toyota.co.jp/jp/news/07/Aug/nt07_0801.html![]() )。
)。
4.縫製産業生産管理技術人材育成支援(ミャンマー)
2008年に国際機関日本アセアンセンターの主催で、ミャンマー縫製業者協会(MGMA)と日本の生産管理等に係る専門家らがミャンマーの6工場を生産・品質管理等の視点から調査・分析し、生産性・品質レベルが低く、経営・技術上、改善の余地が大幅に残っていることが判明した。また、経営者の生産に関する理解不足、生産性・品質の向上の鍵となる人材(スーパーバイザー)が不足している点が問題とわかった。MGMA は、同ミッションが実施した分析結果を受け、生産・品質管理等の技術を会員企業に普及する指導責任者(インストラクター)を任命した。しかし、同指導責任者は、当該技術を普及指導する知識・ノウハウが十分とは言えないため、MGMA は日本の専門家を招聘し、指導知識・ノウハウの習得を希望した。これを背景に経済産業省の貿易投資円滑化事業(JEXSA)による専門家派遣がJETROにより2009年1月におこなわれ、経営者の意識改革のためのセミナーを実施するとともにAOTSも経営者向けセミナーを実施した。またMGMAは2009年3月にミャンマー縫製人材開発センター(MGHRDC)を設置し、JEXSAを活用した日本人専門家による経営者・管理者、スーパーバイザー(SV)向け生産管理技術普及講座(SV 講座)が開講した。同時にモデル企業を指導しつつ、インストラクターをOJT で育成し、2010 年12 月以降、専門家指導のもと、インストラクター自らがSV 講座を一通り教える経験を持つに至っている。継続的なインストラクター指導により一定の成果を挙げつつある専門家派遣を更なる成果に結びつけるために、縫製業界の生産管理、特に、製品品質に直接的な影響を及ぼす「検品」技術に絞り込んだ産業界の直接的人材育成の必要性が派遣専門家及び現地産業界より要望され、2012 年度、同分野の受入研修、海外研修を実施した。
このような日本の優れた技術・ノウハウをいかし、縫製産業を指導・育成することで、ミャンマーの輸出拡大・雇用創出を促し、経済発展に寄与している。
5.メコン地域諸国における担保法制、回収制度充実のための知的支援
アジア通貨危機後、ASEAN4か国の商業銀行セクターは、不良債権比率を低減させたものの、製造業向け貸出比率は低下していることが指摘されている254。また、世界銀行のDoing Business2014における融資の受けやすさ(Getting Credit)についての指標では、タイやベトナムはそれぞれ73位、42位と、マレーシア(1位)やシンガポール(3位)と比較すると低いランキングとなっている。このような資金調達環境の中で、自己資金が比較的少ない中小企業やメコン地域に事業展開する日本企業にとって、債権譲渡や動産担保などの担保法制が充実することは、取引の安全性に資すると考えられる。このため、AMEICC(日アセアン経済産業協力委員会)では、タイ政府関係者も含めた勉強会の開催等を通じて、日本の類似の民法改正の効果についての情報提供や、法制度の比較などの知的支援を行っている。
254 三重野文晴(2013)、「東南アジア4か国の金融システムをどうとらえるか―アジア金融統合への基本視角―」環太平洋ビジネス情報RIM Vol. 13 No. 49.
6.ERIA
ERIAは、東アジア経済統合推進を目的として、2008年6月にインドネシアのジャカルタに設立された東アジア地域の16か国(ASEAN10か国、日本、中国、韓国、インド、豪州及びNZ)で構成される国際的な機関である。ERIAは、「世界の成長センター」であるアジアで、豊かな経済社会を実現し、地域的な共通課題を解決するため「東アジア経済統合の推進」、「域内経済発展格差の是正」、「持続的な成長の実現」を3つの柱として、調査・研究、シンポジウム等を実施しており、東アジアサミット、ASEANサミット等に政策提言を行っている。例えば、ASEAN経済共同体やRCEP交渉に向けた政策提言、インフラ整備促進等に関する政策提言などを行っており、ERIAの諸活動については、ASEAN及び東アジアの経済閣僚及び首脳からも高く評価され、ERIAが引き続きASEAN首脳会合・東アジア首脳会合等に継続的に貢献していくことが奨励されている。2014年に、世界6,826機関を対象としてペンシルバニア大学が発表したシンクタンクのランキングでは、国際経済政策分野で世界30位に位置づけられている。2014年5月には、OECDとの間に研究協力のための覚え書きを締結し、今後、中小企業政策やインフラへの民間投資(パブリック・プライベート・パートナーシップの活用を含む)、付加価値貿易統計とGVC(グローバル・バリュー・チェーン)255を活用した分析、災害リスク評価と復興に向けた基金の分野において協力していくことに合意した。また、東アジア及び我が国の知見を活用した災害に強いインフラ整備等に向けた調査・研究を実施するなど、国際的な活動の幅を広げている。
255 貿易自由化の流れや情報通信技術の飛躍的向上を背景に、企業の一連の活動を比較優位の高い国・地域に分散させ、複雑な国際生産・流通ネットワークを運営することで最終財の国際競争力と付加価値を最大化すること。