第2節 新興諸国経済の現状と将来
1.経済成長率
まず、新興諸国経済の成長力について概観してみる。
新興諸国経済の2003年~2013年の平均成長率(実質GDP成長率)をみると、高所得国の年率1.5%に対して、新興諸国・地域は、いずれの所得階層も年率5%近い高成長を実現している(第Ⅰ-2-2-1-1図)。このうち、上位中所得国の平均成長率は4.9%と新興諸国の中では最も高くなっている。次いで、下位中所得国が4.8%、低所得国は4.7%である。
第Ⅰ-2-2-1-1図 所得階層別の経済成長率
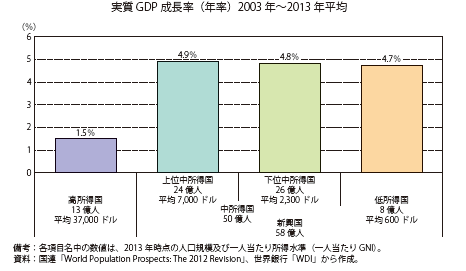
これら新興諸国・地域の一人当たり所得(GNI)の平均は、高所得国と比較すれば、その1/5以下という低い水準ではあるが、高所得国を大きく上回る人口規模や高い経済成長率を踏まえると、その経済的なポテンシャルは無視できないものと言える。
(1)平均成長率の期間変動
そこで、これら新興諸国経済について、各所得階層ごとに過去の経済成長率の長期的な推移を見てみると、経済のグローバル化が進展し始めた1990年を境に大きく変化していることが分かる(第Ⅰ-2-2-1-2図)。
第Ⅰ-2-2-1-2図 平均成長率の期間変動
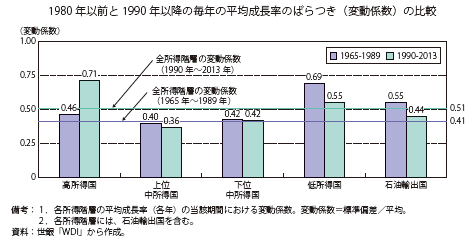
まず、1965年以降の各所得階層の毎年の平均成長率について、その年ごとの変動(ばらつき)を「変動係数(標準偏差÷平均)」でみると、高所得国では、世界経済のグローバル化が進展し始めた1990年以降変動係数は大きく上昇していることが分かる。これは、近年、高所得国において、平均成長率の年ごとの変化が大きくなっていることを示している。
他方、高所得国とは対照的に、上位中所得国及び下位中所得国の変動係数には大きな変化は見られない。上位中所得国、下位中所得国ともに1990年以降も1989年以前の水準をほぼ維持していることが分かる。このことから、上位中所得国及び下位中所得国は、長期的に安定した成長を続けていると言える。
さらに、低所得国を見ると、変動係数は1990年以降大きく低下しており、平均成長率の年ごとの変化は、1989年以前に比べ小さくなっていることが分かる。上位中所得国と比べれば、その水準は引き続き高いものの、1989年以前に比べれば、より安定的な成長軌道を実現しつつあると言える。
同様の動きは、石油輸出国9においても見られる。
このように、近年、新興諸国・地域や石油輸出国では、1990年以降、年ごとの景気変動の振幅が縮小する傾向にある一方、リーマンショックなどを経験した高所得国では、対照的に、1990年以降、年ごとの景気変動の振幅がそれ以前と比べ大きく拡大していることがうかがえる。
9 ここでいう石油輸出国とは、直近のデータで日量10万バレル以上の輸出実績を有している国(所得階層を問わない)。
(2)所得階層内の成長率格差
他方、各所得階層内の平均成長率の格差を、そのばらつき(変動係数)でみると、変動係数の大きさは、所得階層及び時期によって大きく変動していることが分かる。 石油輸出国も同様の動きをしている。ただし、リーマンショックのあった2008年以降は、石油輸出国及び各所得階層において、変動係数は大きく低下しており、これまでにない低い水準に収れんしていることが見て取れる(第Ⅰ-2-2-1-3図)。
第Ⅰ-2-2-1-3図 所得階層内の成長率格差
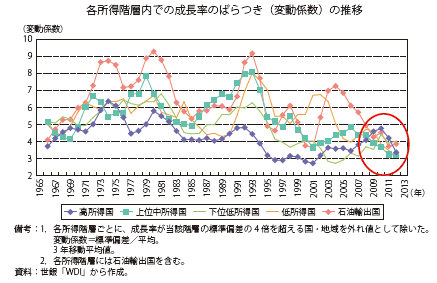
こうした動きは、新興諸国・地域や石油輸出国も含めた世界経済が、近年、互いに連動性を高めていることを示唆している。
世界経済の連動性が高まった背景には、さまざまな要因があると考えられるが、とりわけ、世界経済のグローバル化が新興諸国・地域も含め広く浸透したことが大きく影響している。
すなわち、グローバル化の進展によって、新興諸国・地域どうしの間、あるいは高所得国と新興諸国・地域間の経済的な相互依存関係が強まり、その結果、景気変動の波が時間差を伴わず各国・地域へと伝播するようになったことが、こうした連動性上昇の背景にあると言える。
2.一人当たり所得
既にみたように、新興諸国・地域の多くは、一人当たりの平均所得水準(GNI)が高所得国の1/5以下であるが、2000年代以降、その伸びは著しい。特に、上位中所得国で高い伸びが続いており、その平均所得水準は、2013年には、7千ドルを超える水準に達している(第Ⅰ-2-2-2-1図)。
第Ⅰ-2-2-2-1図 一人当たり所得の推移
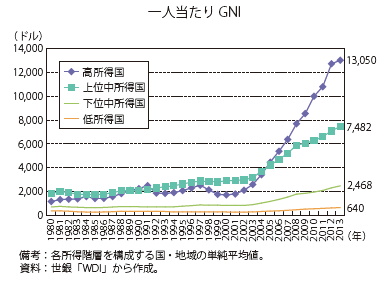
上位中所得国と高所得国の所得水準の分布を比較してみると、前者が4,000ドルから13,000ドルの比較的狭い範囲に分布しているのに対して、後者は下位の13,000ドルから上位は70,000ドル以上と非常に広い範囲に分布している。その結果、平均値でみた場合、両者の格差は非常に大きなものとなっている(第Ⅰ-2-2-2-2図)。
第Ⅰ-2-2-2-2図 所得階層別分布の比較(1)
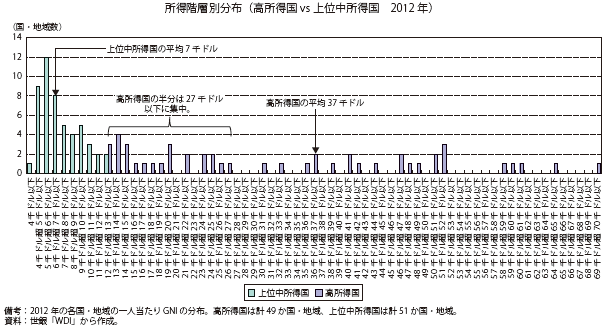
しかしながら、後者の場合、極めて広範な所得階層に分布している一方で、全体の約半分が27,000ドル以下の階層に集中しているから、一部の高所得国を除けば、両者の所得格差は平均値でみた場合ほど大きくはない。
ちなみに、下位中所得国と上位中所得国を同様にして比較してみると、両者の分布はほぼ似通っていることが分かる(第Ⅰ-2-2-2-3図)。
第Ⅰ-2-2-2-3図 所得階層別分布の比較(2)
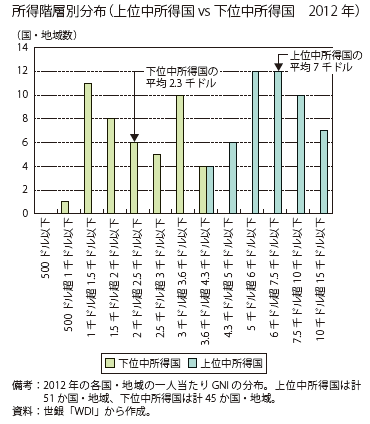
3.総人口
国連の推計によれば、2020年までは、新興諸国・地域の多くで、人口増加が続く見通しである(第Ⅰ-2-2-3-1図)。
第Ⅰ-2-2-3-1図 人口増加率の予測
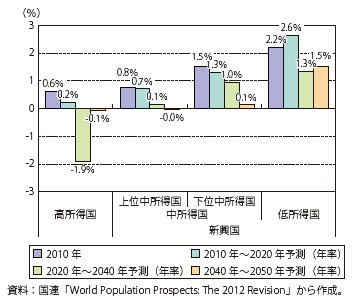
しかしながら、2020年以降は、まず、上位中所得国で人口増加がほぼ止まり、2040年以降には、下位中所得国でも人口増加は止まる見込みとなっている。2040年以降も人口増加が見込まれているのは低所得国のみである。
4.高齢化
高所得国のみならず、新興諸国・地域でも、今後、高齢化が急速に進むと見込まれている。
第Ⅰ-2-2-4-1図は国連のデータに基づき、各所得階層ごとに労働力人口と高齢者人口の将来予測を示したものである。
第Ⅰ-2-2-4-1図 労働力人口、高齢者人口の予測
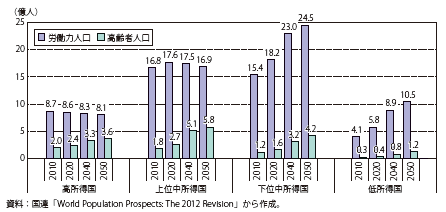
これを見ると、上位中所得国では、労働力人口の将来予測が今後横ばいから2040年以降は減少に転ずる見込みとなっている中、高齢者人口は今後急速に増加する見込みとなっている。
他方、下位中所得国及び低所得国では、労働力人口は引き続き増加を続けることが見込まれている中、高齢者人口も同時に増加することが見込みまれている。
この結果、今後、多くの新興諸国・地域では高齢者人口が急速に増加することが想定される。特に、上位中所得国では、労働力人口が横ばいから減少に転ずることから、今後、高齢化が急速に進むものと見られる。
そこで、次に、高齢化の進展度合いを所得階層ごとに見てみよう。
第Ⅰ-2-2-4-2図は国連のデータに基づき、所得階層ごとに高齢者人口比率の将来予測を示したものである。国連の報告書では、65歳以上の人口の割合(高齢者人口比率)が7%超で「高齢化社会」、14%超で「高齢社会」、21%超で「超高齢社会」と定義している。
第Ⅰ-2-2-4-2図 高齢者人口比率の予測
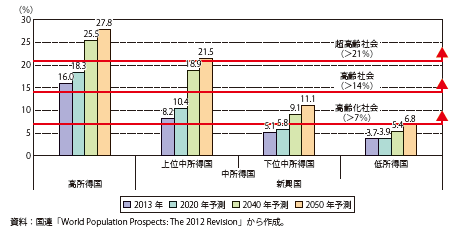
これを見ると、すでに「高齢化社会」に突入している上位中所得国では、今後、労働力人口の伸び悩みと高齢者人口の増加を背景に、2040年までには「高齢社会」に、そして2050年には「超高齢化社会」に突入すると見込まれる。下位中所得国では2040年までに、低所得国では2050年以降「高齢化社会」に突入する見込みとなっている。
こうした中、すでに高齢化社会に突入している上位中所得国の一人当たりの医療費支出額は、一人当たり所得が増加に転じた2000年代後半以降、急速に増加している(第Ⅰ-2-2-4-3図)。
第Ⅰ-2-2-4-3図 一人当たり医療費支出額の推移
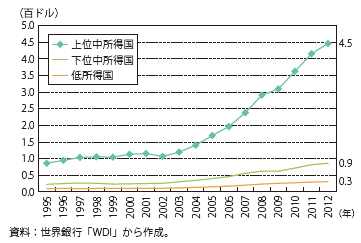
また、現在はまだ低い伸びにとどまっている他の新興諸国・地域においても、一人当たり所得の増加と高齢者人口比率の上昇を受けて、今後、医療費支出の急速な上昇が予想される。
5.都市化
新興諸国・地域においても、都市化が急速に進展している。
第Ⅰ-2-2-5-1図は、2013年時点の所得階層ごとの都市化率と都市人口増加率を示したものである。
第Ⅰ-2-2-5-1図 都市化率と都市人口増加率
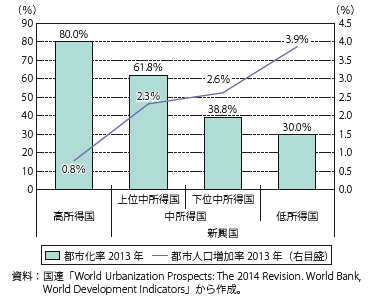
これを見ると、全人口のうち「都市」に住む人口の割合(都市化率)は、上位中所得国ではすでに人口の6割超が都市に居住していることが分かる。また、下位中所得国では4割近く、低所得国においても3割の人口が都市に居住している。
こうした背景には、急速な都市への人口流入がある。
都市への人口流入を都市人口の対前年比で見ると、高所得国は0.8%(2013年)と、ほぼその流入は止まっているのに対し、新興諸国・地域では、2.3%から3.9%の高い割合で流入が継続している。
国連の推計によれば、すべての所得階層で都市化率の上昇は続き、特に、上位中所得国では、今後、上昇が加速すると予測されている(第Ⅰ-2-2-5-2図)。
第Ⅰ-2-2-5-2図 都市化率の予測
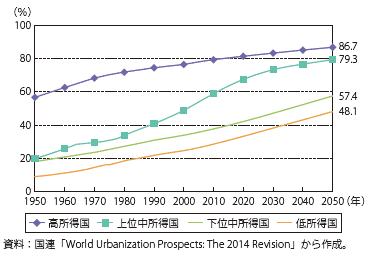
その結果、上位中所得国の都市化率は、2050年には80%に達し、高所得国の水準に迫る勢いである。
6.高齢化と都市化の同時進行
第Ⅰ-2-2-6-1図は、国連のデータに基づいて、各所得階層の都市化率と高齢者人口比率のこれまでの推移と2050年までの予測を示したものである。
第Ⅰ-2-2-6-1図 都市化率と高齢者人口比率の予測
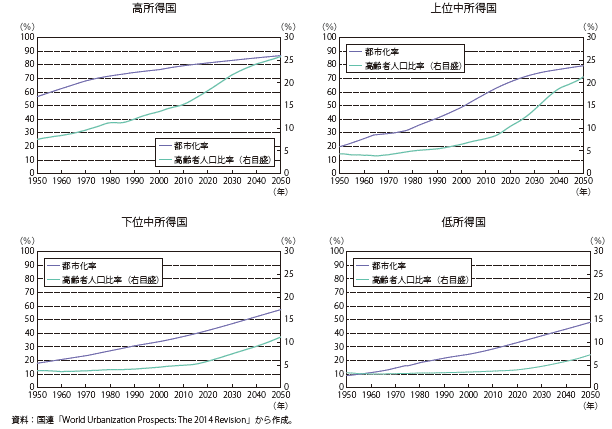
これを見ると、高所得国では都市化の進展が先行し、すでに、70年代を境に、都市化率の上昇ペースは緩やかになっていることが分かる。そして、高齢化は都市化に遅れる形で、今後、その進行が加速する見込みとなっている。
他方、新興諸国では、都市化の進展と高齢化が、今後、同時に進行すると見込まれている。
このうち、上位中所得国では、今後、2030年頃まで都市化が急速に進展する見込みであるが、高齢化は2020年以降加速し、その後も持続する見込みである。
下位中所得国では、都市化の進展が今後長期間にわたり継続すると見込まれる中、高齢化は2020年以降加速する見込みである。
低所得国では、下位中所得国と同様、都市化が長期間継続すると見込まれる中、2030年以降高齢化が進展し始める見込みである。
以上の結果、これら新興諸国・地域では、今後、高齢化と都市化という2つの問題に同時に対処しなければならないという難題に直面していると言える。
そのことは、同時に、高齢化対策としての医療・健康分野、都市化対策としての都市インフラ整備という2つの巨大な市場が新興諸国・地域に現れることも意味している。
