第3節 増え続けるインフラ需要
急速な経済発展を続ける新興諸国・地域では、国内における様々なインフラ整備の必要性が顕在化している。以下では、新興諸国・地域の電力、水道、港湾及び都市インフラの整備状況などについて概観する。
1.電力インフラ
第Ⅰ-2-3-1-1図は、新興諸国・地域の電力消費量の推移を見たものである。これを見ると、特に、工業化が著しい上位中所得国で2000年以降電力消費量が大幅に増加していることが見て取れる。上位中所得国の2011年の消費量は1990年当時の4倍近い水準である。下位中所得国の電力消費量も緩やかに増加しており、2011年の消費量は1.8億Kwと1990年当時の2倍を超えている。
第Ⅰ-2-3-1-1図 電力消費量の推移
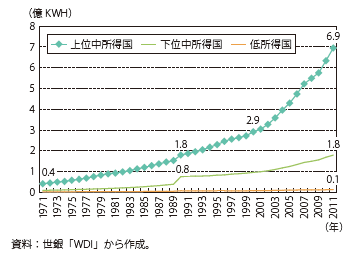
このため、これら新興諸国・地域では、急速な電力需要の増加に対応するため、発送電設備への投資を今後も積極的に進めていく必要がある。
2.水資源インフラ
国連のデータによれば、世界の水使用量のうち約70%が農業用、20%が産業用、10%が家庭用として使用されている10。
以下では、これらのうち家庭用として使用される水道水について、新興諸国・地域における普及状況等を概観する。
水道設備は、国や地域を問わず公衆衛生の向上や生活環境の改善に欠くことができない社会基盤である。2000年9月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言では、開発分野において2015年までに達成すべき国際社会共通の目標として「極度の貧困と飢餓の撲滅」など8つを掲げている11。そのうち「環境の持続可能性確保」という目標では、安全な飲料水と衛生施設を利用できない人口の割合を1990年と比べ半減させるという目標が設定された。
当該目標は世界全体では既に2010年に達成されている。東アジア、南東アジアなど中所得国の多い地域では、安全な水を利用できる人口は1990年以降大幅に増加している。その一方で、サブサハラ、オセアニア、コーカサス・中央アジア及び北アフリカなど低開発国が集中する地域では、2012年時点でも目標は達成されていない。さらに、コーカサス・中央アジア地域では安全な飲料水を利用できない人口の割合が1990年よりも逆に増加している(第Ⅰ-2-3-2-1図)。
第Ⅰ-2-3-2-1図 安全な飲料水を利用できない人口の割合(地域別、1990年→2012年)
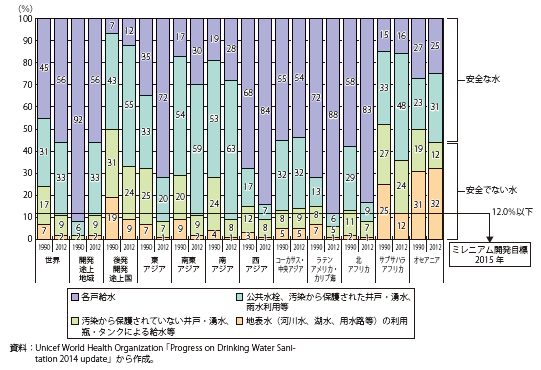
このように、一部の地域を除けば、安全な水を利用できる人々の数は多くの国・地域で着実に増加しているものの、2012年時点で、中国、インド及びナイジェリアをはじめ世界全体で約7億7,600万人が依然として安全な水の供給を受けることができない状況にあるとされている(第Ⅰ-2-3-2-2表)。安全な水を利用できない人々の数は、アジアやアフリカ地域の人口大国に集中している。これらの国・地域の中には、中国、インド及びインドネシアなどといった大きな人口を抱える中所得国も含まれている。特に、中国では1億人を超える人々がいまだに安全な水を利用できない状態にある。こうしたことから、各国・地域は、安全な水の供給を目指す努力を、引き続き行っていく必要がある。
第Ⅰ-2-3-2-2表 安全な飲料水を利用できない人口上位10か国(2012年)
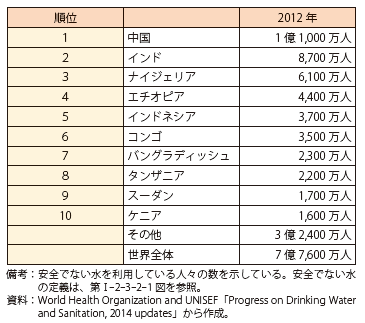
このことは、同時に、これまでもODAなどを通じて新興諸国における水道インフラシステムの構築を技術面あるいは資金面から支援してきた我が国は、今後も引き続きその支援を長期間継続していく必要があることを示している。
10 http://www.unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211812/![]()
11 8つの目標とは次に掲げるもの。極度の貧困と飢餓の撲滅、初等教育の完全普及の達成、ジェンダー平等推進と女性の地位向上、乳幼児死亡率の削減、妊産婦の健康の改善、HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止、環境の持続可能性確保、開発のためのグローバルなパートナーシップの推進。
3.港湾インフラ
次に、新興諸国・地域のインフラ整備の遅れを示す一例として、港湾インフラの整備状況を見てみる。
世界経済フォーラムが133か国を対象に毎年行っている調査では、実際に港湾設備を使っている企業から各国の港湾設備の整備状況を聴取している(第Ⅰ-2-3-3-1図)。
第Ⅰ-2-3-3-1図 港湾インフラの整備状況
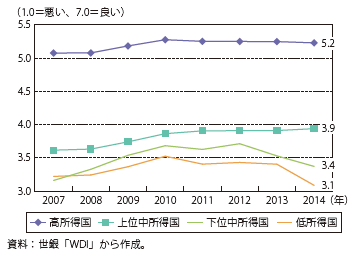
その結果をみると、高所得国の平均が7段階評価の上から2番目の5前後であるのに対し、新興諸国・地域は4未満と低い評価となっている。特に、下位中所得国と低所得国では、近年、その評価が低下傾向にある。港湾インフラの整備が急がれる状況にあると言える。
4.都市インフラ
新興諸国・地域における都市への人口集中は、国内における都市インフラ整備の重要性を高めている(第Ⅰ-2-3-4-1図)。
第Ⅰ-2-3-4-1図 都市人口上位25都市
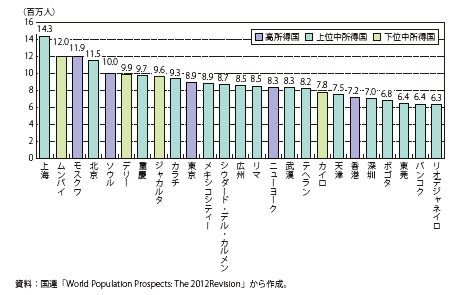
具体的には、共同住宅、上下水道、道路、港湾設備、発送電設備、通信システム、都市交通システム、教育施設、医療施設などの整備に係る需要が見込まれている。
例えば、中国・上海市の場合、インフラ投資は、1990年代後半から急増している。 2013年には4千億元を超え、1992年の240億元の17倍となっている(第Ⅰ-2-3-4-2図)。その中心となっているのは住宅投資である。2013年の不動産投資額は、インフラ投資額全体の約7割を占める。次いで、輸送(12%)、水利・環境・公共施設管理(10%)、電力・ガス・水道・熱供給(4%)となっている(第Ⅰ-2-3-4-3図)。
第Ⅰ-2-3-4-2図 中国・上海市のインフラ投資額の推移
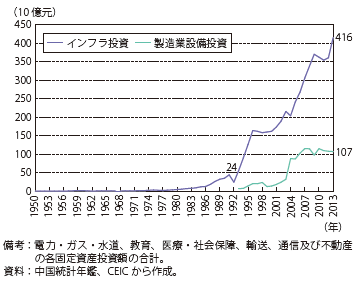
第Ⅰ-2-3-4-3図 中国・上海市のインフラ投資の内訳(2013年)

5.固定資本投資
増え続けるインフラ需要を受けて、新興諸国の固定資本投資は、近年、急速に増加している。特に、上位中所得国の増加は著しく、2013年には上位中所得国全体で合計3.7兆ドル12を投資している(第Ⅰ-2-3-5-1図)。
第Ⅰ-2-3-5-1図 固定資本投資の推移
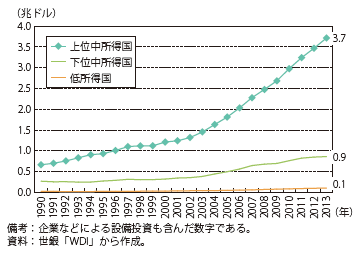
過去10年あまりの固定資本投資の伸びは、高所得国では経済成長率を下回る伸びにとどまっているが、新興諸国・地域では、いずれの所得階層においても経済成長率を上回る伸びである(第Ⅰ-2-3-5-2図)。
第Ⅰ-2-3-5-2図 固定資本投資の伸び率と実質GDP成長率(2003年~2013年、年率)
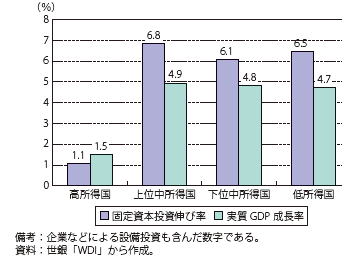
特に、上位中所得国では、年率7%近い伸びとなっており、インフラ投資も活発に行われていることを示唆している。
12 企業などによる設備投資を含んだ数字。
