第1節 先進国における総需要の伸び悩み
1.世界経済危機以降の先進国経済
世界経済危機以降における先進国経済は危機前と比較すると成長が鈍化している。世界経済危機前後の年平均成長率95を比較すると、ユーロ圏では2.2%から0.8%に、英国では3.0%から1.9%に、米国では2.7%から2.1%にそれぞれ減速している(第Ⅰ-2-1-1図)。
第Ⅰ-2-1-1図 世界経済危機前後の経済成長率
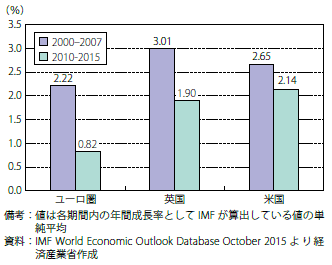
また我が国の「月例経済報告」によれば、2015年12月時点において米国は「景気は回復が続いている」、ユーロ圏は「景気は緩やかに回復している」、英国は「景気は回復している」とされているが、世界経済危機以降、景気拡大局面に入った旨の表現には至っていない(第Ⅰ-2-1-2表)。
第Ⅰ-2-1-2表 月例経済報告における米国・欧州の景気判断(各年12月のもの)
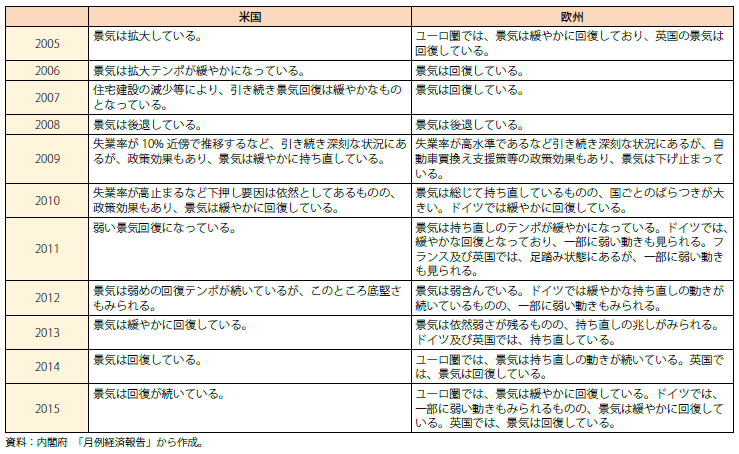
国際機関が定期的に公表している世界経済見通しも累次にわたり下方修正されている96。2010年10月版の「IMF世界経済見通し」基づけば、2015年の先進国の実質成長率は4.4%と予測されていたが、2015年10月版では2.0%まで下方修正されている(第Ⅰ-2-1-3図)。
第Ⅰ-2-1-3図 IMF世界経済見通しによる先進国の成長率見通し下方修正の変遷
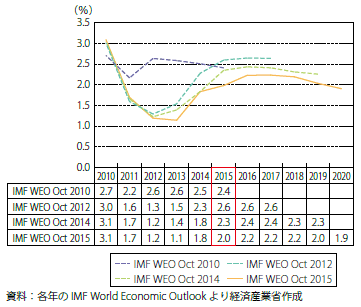
こうした先進国における実質成長率鈍化については、総需要の伸び悩みや潜在成長率の低下に伴う供給動向等が背景にあると考えられる。OECD加盟国における実質成長率と潜在成長率の差を示すGDPギャップの値は、近年マイナス幅は縮小しているものの、2009年以降マイナスの状態が継続している。これは、総需要が不足したことにより、資本ストックや労働力といった生産手段が十分に活用されていない状態にあることを示唆している(第Ⅰ-2-1-4図)。
第Ⅰ-2-1-4図 OECD加盟国のGDPギャップの推移
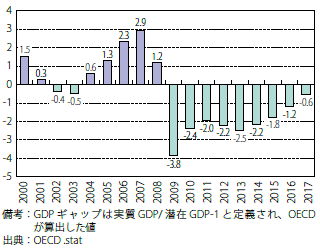
総需要が伸び悩んでいることの背景に対しては、これまで様々な説明が試みられている。ローレンス・サマーズ元米国財務長官の唱える「長期停滞論」によれば、先進国において貯蓄性向が上昇し投資性向が下降した結果、完全雇用を達成するための自然利子率が低下し、需要が減退していることが背景にある97。その際、貯蓄性向が上昇した理由としては格差拡大、将来不安の増大、借入余力の縮小、各国中央銀行やソブリンウェルスファンド等による資産購入の拡大などが、投資性向が下降した理由としては、労働力の拡大減速、割安な資本財の登場、信用の縮小(借入規制の強化による)、大型投資に頼らない新たな産業98などが挙げられている。
世界金融危機後の経済成長の停滞の要因としては、長期停滞論以外にも、累積債務の拡大99、生産性上昇率の低下100、経常黒字国からの資本流入とグローバルインバランスの拡大101、流動性の罠などの側面からの説明が試みられている。例えば借入れの増加に伴う家計債務の拡大により、借入制約が厳しくなり、結果として消費が抑制され総需要不足が長期的に発生するとの見解もある102。
次項では、我が国をはじめとする先進諸国の経済発展の原動力となってきた成長モデル、中間所得層の状況について分析する。
95 IMF World Economic Outlook Database October 2015より、「2000年から2007年まで」及び「2010年から2015年まで」の期間の実質GDP成長率を単純平均した値。なおユーロ圏については、購買力平価に基づくウェイト付けで各国の成長率を合成した値を用いて計算。
96 ここではIMFによる経済見通し(World Economic Outlook)を取り上げたが、OECDや国連など他機関による予測も累次にわたり下方修正されている。
97 Summers, Lawrence H. (2016), “The Age of Secular Stagnation”, Foreign Affairs, Volume 95 Number 2, March-April 2016, Council on Foreign Affairs
98 サマーズは大型投資に頼らない新しい産業(原文ではthe new economy tends to conserve capital)の例として、シェアリングエコノミーの登場によるホテル建設や自動車需要の抑制、電子商取引の台頭によるモール建設の抑制、情報通信技術の発展によるコピー機・プリンターやオフィススペースそのものに対する需要の縮小を挙げている。
99 Reinhart, Carmen M. and Rogoff, Kenneth S. (2011), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University PressやMian, Atif and Sufi, Amir (2014)を参照。
100 Gordon, Robert (2016), The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War, Princeton University Pressを参照。
101 Ben Bernanke元FRB議長による過剰貯蓄仮説(Global Saving Gult)を参照。
102 Kobayashi, Keiichiro (2016) “Presistent Demand Shortage Due to Household Debt”, RIETI Discussion Paper Series, 16-E-012, February 2016, Reearch Institute of Economy, Trade and Industry
2.雇用構造の変化
これまで先進諸国では、被雇用者層のうち特にその中核を占める中間所得層(Middle-class workers)の割合が持続的に上昇することによって一人当たり所得の増加を実現し経済全体の成長を支えてきた。
ところが、近年、その中間所得層の割合が各国で低下を続けていることが指摘されている103。また、その一方で低所得層と高所得層の割合は逆に上昇していることも指摘されている。こうした中間所得層の縮小と低所得層・高所得層の拡大は、雇用構造が低所得層と高所得層に二極化(Polarization)していることを強く示唆している。
労働力人口の減少に直面する中、人口減少に伴う需要後退圧力を一人当たり所得の増加によって補おうとする多くの先進諸国にとって、こうした雇用構造の変化は、これまでの成長モデルに大きなインパクトを与える可能性がある。
以下では、我が国を含めた先進諸国におけるこうした雇用構造の変化の実態を詳しく検証し、その要因について考察する。
103 例えば、2014年5月の米国ダラス連銀報告書Anton(2014)によれば、1980年以降米国労働市場では、中間所得層を形成する中位技術職(Middle-skill jobs)の割合が大きく低下し、逆に低位技術職(Low-skill jobs)と高位技術職(High-skill jobs)の割合が上昇していることが示されている。本報告書では、1981年時点で被雇用者数の58%を占めていた中位技術職の割合は2011年には44%まで低下し、逆に低位技術職(1981年:13%)と高位技術職(同:29%)の割合は2011年にはそれぞれ17%と39%に上昇したことが報告されている。
(1)米国、ドイツ及び我が国の雇用構造の変化
第Ⅰ-2-1-5図は、米国、ドイツ及び我が国の雇用者数の変化を職業別に見たものである。各職業の最新時点での賃金水準も併せて示してある。
第Ⅰ-2-1-5図 職別雇用者数の変化と賃金水準
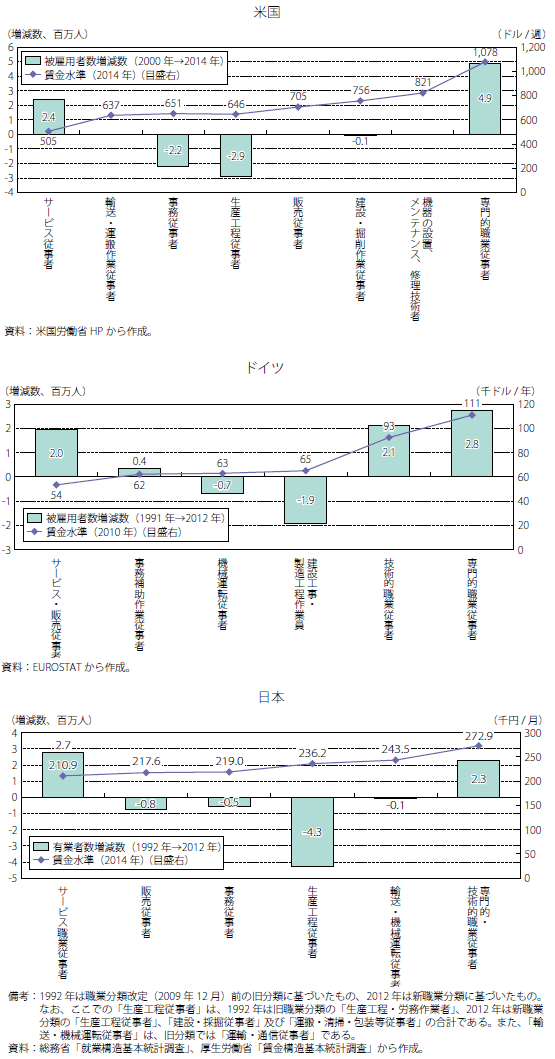
これをみると、データの制約で国によって被雇用者数変化の期間が異なるものの(米国は2000年から2014年、ドイツは1991年から2012年、我が国は1990年から2012年)、いずれの国においても賃金水準が中程度の職業である生産工程従事者や事務従事者などの数が減少していることが分かる。また、賃金水準が相対的に低いサービス従事者と、逆に賃金水準が相対的に高い専門的・技術的職業従事者の数が増加していることも分かる。
ただし、我が国の職業間の賃金格差は米国やドイツに比べ極めて小さい。米国やドイツでは、最も賃金水準の高い専門的職業と最も低いサービス職業の間には極めて大きな格差があるが、我が国の場合、両者の間の水準差はわずかであり、したがって、我が国においては、職種間での雇用構造の変化は生じていると考えるものの、米国やドイツのように大きな賃金格差を前提にした所得階層間での「雇用の二極化」を同列に論ずることは適切ではないと考える。
では、何故、このような現象が各国で共通して観察されているのであろうか。
(2)雇用構造変化の要因
第Ⅰ-2-1-6表は、一般的な「職業分類」と「業務分類」の対応関係を示したものである。業務(タスク)とは、職業を構成する最小単位であり、その職業で求められる具体的な仕事の内容や性質を規定したものである。職業分類では、各職業は「定型(Routine)業務」と「非定型(Non-routine)業務」に分類され、さらに「手仕事(Manual)業務」と「認知(Cognitive)104業務」に分類される105。
第Ⅰ-2-1-6表 職種分類と業務分類
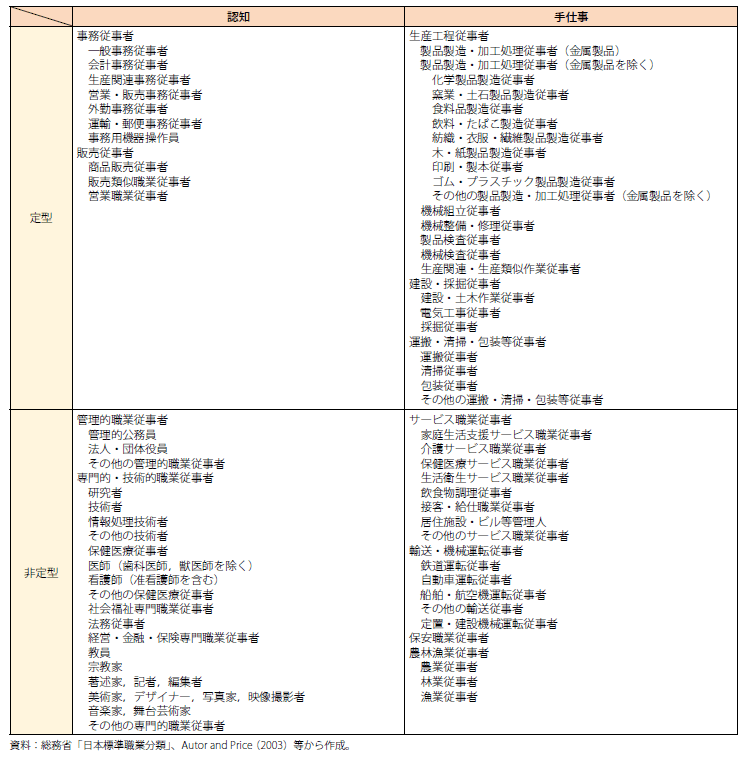
定型業務とは、あらかじめ定められた手順に従って同じ作業工程を反復して行うような業務を指す。製造工程の組立作業や事務作業などがこれに該当する。
そして、これら業務はあらかじめ詳細かつ綿密に作成された作業手順書に従って行われることが多いから、例えば、組立作業の手順書に記載された内容は、容易にコンピュータ・プログラムにコード化することができ、製造工程はコンピュータに制御された機械によって代替される可能性が高い。あるいは、経理業務のような一定の認知能力を求められるような業務であっても、伝票等の帳簿書類と経理手順書が電子化されて瞬時に海外に送付することが可能な現在では、新興諸国の低賃金労働者によって代替される可能性が高い。
なお、定型業務はさらに経理業務のような一定の認知能力を要する「定型・認知業務」と、データ入力のような「定型・手仕事業務」に分けられる。
他方、非定型業務とは、問題解決、説得、直感、想像力などが必要とされる高度な業務である「非定型・認知業務」と、状況適応性や視聴覚・言語能力、手先の器用さなどが要求される「非定型・手仕事業務」の二つで構成される。
前者には、医師・弁護士などといった専門的・技術的職業や、企業経営者などの管理的職業あるいは作家・芸術家といった創造的職業などが該当し、いずれも高度な教育水準、高い分析能力及び想像力などを要求される点が共通している。
他方、後者には、警備員、調理師やトラック運転手などおもにサービス業や運輸業に従事する者が該当する。
これら二つの業務のうち、非定型・認知業務は、業務を遂行する上で抽象的な要素が多く必要とされるから、現状ではソフトウェアでコード化して機械化することは困難である。他方、非定型・手仕事業務は、警備業や調理業務といったサービス業や運転業務などが主体となることから、労働の提供とその消費が同時かつ地理的に同じ場所で行われる必要があり、海外にアウトソースすることは物理的に困難である。
このように職業分類を4つの業務(タスク)に分類してみると、第Ⅰ-2-1-5図で被雇用者数が減少している職業の多くが、機械化や海外アウトソーシングが容易な定型業務に相当し、逆に増加している職業の多くは機械化や海外アウトソーシングが困難とされる非定型業務に相当していることが分かる。
したがって、先進諸国における雇用構造の変化は、IT化の進展や情報通信技術の普及などを背景に、機械化や海外アウトソーシングが容易な定型業務に位置づけられる職業が、実際に機械や海外の低賃金労働によって代替された結果生じたものであることが強く示唆される。
こうした推論を強く支持するデータとして、第Ⅰ-2-1-7図を見てみよう。
第Ⅰ-2-1-7図 世界の業務別被雇用者数シェアの変化
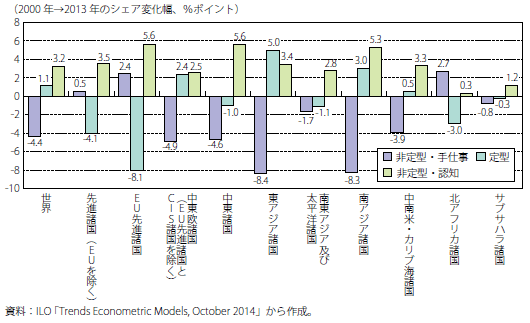
これは、世界各地の定型業務、非定型・手仕事業務及び非定型・認知業務の被雇用者数シェアの変化を見たものである。これを見ると、2000年以降、先進諸国では定型業務のシェアが大きく低下する一方、東アジアや南アジア、中・東欧諸国などの新興諸国・地域では、定型業務のシェアが大きく伸びている106。
104 ここでいう「認知」とは、知覚・判断・想像・推論・決定・記憶・言語理解などの能力を指す。
105 ここでの業務分類(定型、非定型、手仕事、認知)は、Autor, Levy, and Murnane(2003)及びAutor and Price(2013)によっている。Autor and Price(2003)は「スキル」と「タスク」を明確に分離し、タスクは仕事(職業)を構成する最小単位と、スキルは様々なタスクを実行するために個々の労働者が持つ能力の蓄積とそれぞれ定義している。そして、労働者は賃金と引き替えに自身のスキルをタスクに投ずるとしている。本分類はこのタスクに着目して行われている。
106 ILOは、東アジアや南アジアなど新興諸国・地域で非定型・手仕事業務のシェアが大きく低下しているのは、農林漁業業従事者の減少によるものであるとしている。
(3)我が国における雇用構造変化の現状
次に、我が国における雇用構造の変化の現状をもう少し詳しく見てみよう。
第Ⅰ-2-1-8図は、我が国の業務別就業数の長期推移を見たものである。
第Ⅰ-2-1-8図 業務別就業者数の推移
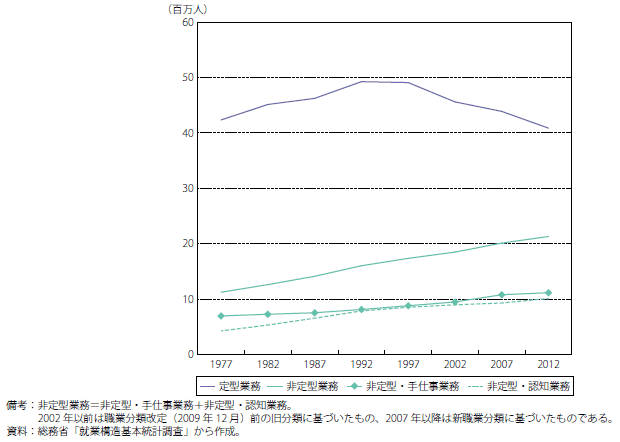
これを見ると、我が国の場合、定型業務従事者の減少は2000年前後から始まっていることが分かる。これは、我が国企業がアジア諸国等への海外展開の動きを加速させ始めた時期と一致する。また、インターネットが世界的に普及し始めた時期とも一致する。対照的に、非定型業務は、手仕事業務、認知業務ともに一貫して増加を続けている。
第Ⅰ-2-1-9図は、より詳細な職業別の就業者数の推移を見たものである。
第Ⅰ-2-1-9図 職業別就業者数の推移
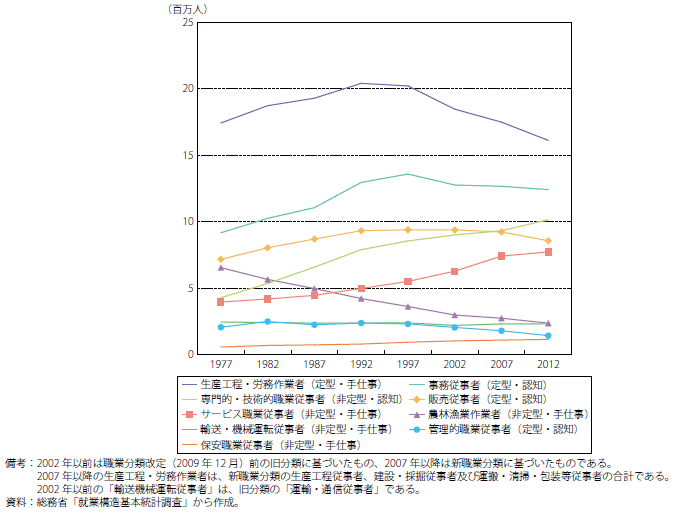
これを見ると、定型業務の減少は主に生産工程・労務作業者の減少によるものであることが分かる。1992年には2千万人に達した生産工程・労務作業者は、その後は急速な減少を続け、足下の2012年には16百万人に減少している。また、事務従事者や販売従事者も減少傾向にある。
他方、非定型業務の増加は、主に専門的・技術的職業従事者とサービス職業従事者の増加によるものであることが分かる。特に、専門的・技術的職業従事者の数は1977年以降一貫して増加を続けている。1997年にはわずか4百万人あまりだった専門的・技術的職業従事者の数は、足下の2012年には1千万人に達している。
ところで、こうした雇用構造の変化は、我が国においては、地域に関わりなく全国一律に進行しているのであろうか。それとも、例えば、都市部と地方では異なる状況が生じているのであろうか。
第Ⅰ-2-1-10図及び第Ⅰ-2-1-11図は、我が国の職業別就業者数の変化をそれぞれ政令市(東京都特別区を含む)と政令市以外の地域(以下「非政令市」という。)に分けて見たものである。横軸が各職業の就業者数を示し、縦軸は1992年から2012年の間の就業者数の増減率を示している。赤色の横線は、同期間における全職業合計の就業者数の増減率である。職業別の賃金水準(2014年中央値)は、おおむね左端の職業から右端の職業に向かい高くなる。
第Ⅰ-2-1-10図 職業別就業者数の増減(政令市、1992年→2012年)
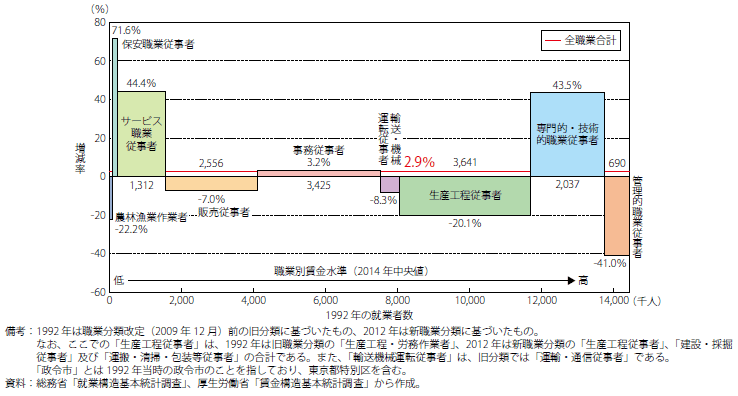
第Ⅰ-2-1-11図 職業別就業者数の増減(非政令市、1992年→2012年)
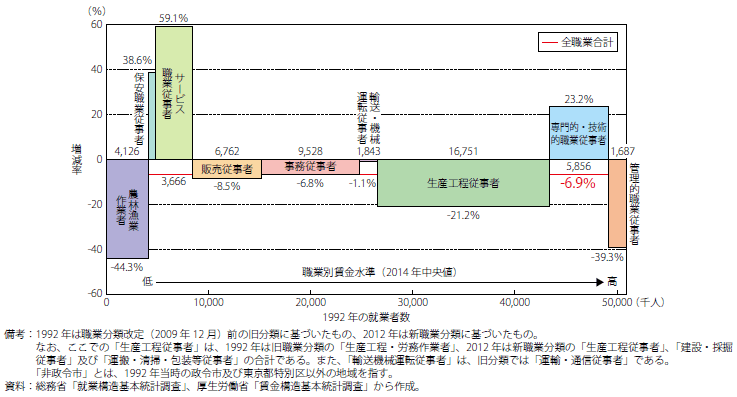
まず第Ⅰ-2-1-10図の政令市の職業別就業者数の増減を見てみると、就業者数に占めるシェアが最も大きい生産工程従事者は2012年までの20年間に20.1%減少している。
非定型業務に位置づけられる農林漁業作業者及び管理的職業従事者もそれぞれ▲22.2%、▲41.0%と大幅な減少となっている。なお、農林漁業作業者の減少は、主に作業者の高齢化や後継者不足による専業農家の減少などを反映したものと考えられる。
他方、管理的職業従事者の減少は、主に中小企業経営者の高齢化や後継者不足による廃業の増加が大きく影響したものと考えられるが、その一方で、情報技術の進展によって、従来、いわゆる中間管理職がおもに担ってきた企業内の情報、指示・命令、報告の仲介機能という定型業務がコンピュータによって代替されるケースが増加していることもその一因と考えられる。事務従事者はわずかながらではあるが増加している。
しかしながら、政令市では、非定型業務に位置づけられるサービス従事者及び専門的・技術的職業従事者がそれぞれ44.4%、43.5%と大幅に増加している。
政令市では、相対的に賃金水準が低いサービス業だけでなく、賃金水準が高い専門的・技術的職業の就業者もほぼ同じペースで増加していることが特徴と言える。そして、これら就業者数が増加している職業が、生産工程など就業者数が減少している職業の雇用を吸収する形で就業者数は全体で2.9%増加している。
他方、第Ⅰ-2-1-11図の非政令市を見てみると、就業者数に占めるシェアが最も大きい生産工程従事者は2012年までの20年間に政令市とほぼ同じ21.2%減少している。事務従事者、販売従事者もそれぞれ▲6.8%、▲8.5%と減少している。これらは、いずれも定型業務と位置づけられる職業である。
就業者数が増加している職業を見ると、最も大きく増加しているのがサービス職業従事者(59.1%)で、保安職業従事者(38.6%)及び専門的・技術的職業従事者(23.2%)の伸びを大きく上回っている。これらの職業はいずれも非定型業務と位置づけられているものである。
政令市とは異なり、相対的に賃金水準が低いサービス業が雇用増加の中心となっていることが分かる。
非政令市では、この20年間に生じた生産工程等の定型業務の余剰労働力を、専門的・技術的職業などの非定型業務型の職業の就業者数の増加によって吸収しきれなかったことが見て取れる。その結果、非政令市の就業者数は、政令市とは対照的に、この20年間で6.9%の減少となっている。
後継者不足などを背景にした農林漁業作業者や管理的職業従事者(中小企業経営者)の減少を除けば、我が国においても定型業務が縮小し、非定型業務委が増加するといった欧米諸国と同様の雇用構造の変化が起きていることを強く示唆している。
(4)まとめ
欧米諸国では中間所得層の雇用が減少する一方で、高所得層と低所得層の雇用が増加するといった雇用の二極化が進んでいることが分かった。
他方、我が国においては、業種間の賃金格差を背景とした二極化の進展が進んでいるかは、必ずしも明確ではないものの、欧米諸国と同様、定型業務の減少と非定型業務の増加が同時に進行するという雇用構造の変化が進んでいることが確認された。
とりわけ我が国では非政令市でこうした雇用構造の変化が顕在化していることが確認された。非政令市では雇用構造の変化の結果、地域雇用全体が減少していることが認められる。
他方、政令市ではこうした雇用構造の変化は部分的に認められるものの、専門的・技術的職業従事者の大幅な増加によって、地域の雇用全体は拡大していることも分かった。
非政令市では、今後、住民一人当たりの所得の維持・向上のため、相対的に賃金水準が高い専門的・技術的職業従事者をどうやって増やしていくかが課題となろう。
