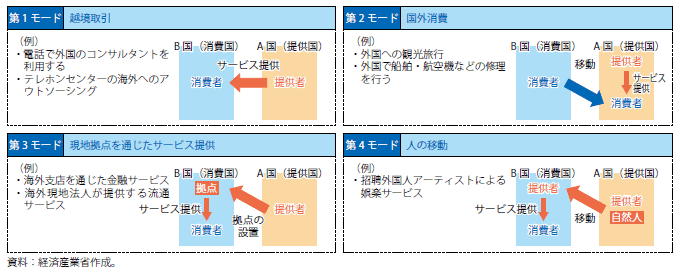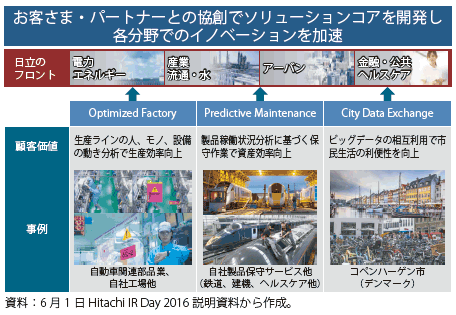第1節 サービス産業の興隆とサービス貿易の拡大
これまでの通商白書でも取り上げてきたように110、世界経済の成長に伴い、産業のサービス化が進展するとともに、貿易面でもサービス化が進んでいる。近年では、こうした産業・貿易のサービス化が先進国から新興国に拡大しつつあることに加え、情報通信技術の進展により、サービス提供における「消費者と生産者の近接性」111の制約が低下し、サービス貿易がますます活発化している。
各国は、強みのある分野に集中したサービス貿易を展開しているが、新興国よりも先進国において、海外からの収益を拡大する傾向が見受けられる。本節では、こうした動きを踏まえ、新興国における産業のサービス化の現状を、特にその動きが著しい中国を中心に分析するとともに、世界的に拡大するサービス貿易の現状について概観する。
110 産業のサービス化とサービス貿易は古くて新しい課題であり、通商白書でも過去数十年にわたり取り上げ続けてきた。目次に「サービス貿易」という文言が初めて登場したのは30年前の1986年通商白書においてであると考えられる。しかしながらその内実は変化しており、例えば10年前の2006年通商白書においては「実際の国際経済でも先進国を中心にサービス経済化の進展が見られる。経済的な発展を遂げつつある途上国では、先進国ほどに明らかではないものの、今後サービス化の動きは加速するものと考えられる。」との記述があるが、2016年現在では、既にそれが現実の動きとして顕在化している。
111 田中(2015)。
1.新興国におけるサービス産業の興隆
(1)サービス経済化の進展
経済発展に伴って経済活動の重点が農林水産業(第一次産業)から製造業(第二次産業)、非製造業(サービス業、第三次産業)へと移る現象は「ペティ=クラークの法則112」として知られている。これまで、産業のサービス化は先進国を中心として進展してきたが、近年、めざましい経済発展に伴い、新興国においても産業のサービス化が大きく進展している。
世界銀行の定義113に従い、世界各国・地域を所得水準に応じた5グループに分割し、GDPに占めるサービス業の付加価値シェアの推移を見ると、高所得国のうちOECD加盟国(G7やユーロ圏等のいわゆる「先進国」とされる国)は75%程度の高いシェアを保ったまま推移する一方、それ以外の全グループにおいて、サービス業のシェアが拡大している。特に、2011年以降、高所得国のうちシンガポールやサウジアラビア等のOECD非加盟高所得国、中国、メキシコ等の上位中所得国でサービス業の付加価値シェアが急速に高まっている(第Ⅰ-3-1-1図)。
また、過去の通商白書114で見てきたとおり、一人あたりGDPの額が大きな国ほど、サービス業がGDPに占めるシェアが大きくなる傾向にある(第Ⅰ-3-1-2図)。既にサービス化が進展した先進国に加え、新興国を中心に、経済発展に伴い産業のサービス化が進展していると考えられる。
第Ⅰ-3-1-1図 名目GDPに占めるサービス業の付加価値シェアの推移
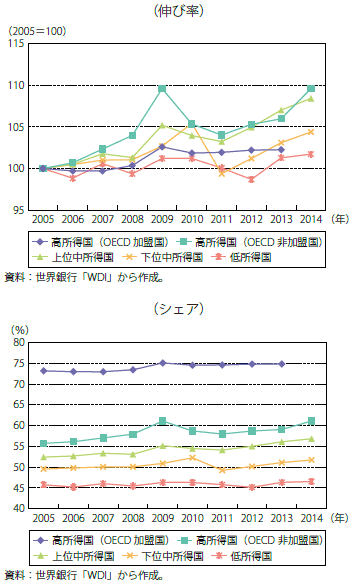
第Ⅰ-3-1-2図 一人あたり名目GDPとサービス業が名目GDPに占めるシェアの関係(2014年)
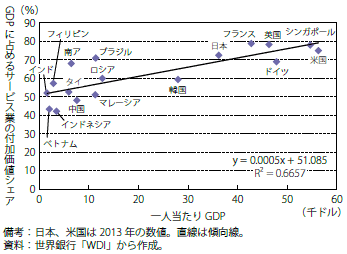
112 ①第一次産業に比して第二次産業の収益が高く、第二次産業に比して第三次産業の収益が高いことから、より収益の高い産業へ労働力が移動すること、②経済の発展に伴い、一定程度モノが行き渡ると食料品や工業品といった第一次・第二次産業の生産品の需要は飽和し、第三次産業が提供する各種サービスの需要が増加すること、といった要因から経済活動の重点が、順次、第三次産業へ移っていくことを示した。
113 世界銀行(2015)。
114 経済産業省(2013)、経済産業省(2015)等。
(2)中国におけるサービス産業の展開と需要構造の変化
新興国における産業のサービス化は特に中国において著しい。中国の産業構造の推移を見ると、経済のサービス産業化が進展し、第三次産業が、付加価値ベース、就業人員ベースともに、第一次、第二次産業を上回っている(第Ⅰ-3-1-3図、第Ⅰ-3-1-4図)。特に2015年は付加価値ベースで、第三次産業が50%を超えた。実質GDP成長率は、全体の伸び率が減速する中で、第三次産業は加速する傾向が見られる(第Ⅰ-3-1-5図)。
第Ⅰ-3-1-3図 中国の産業構造(GDP、就業人員)の推移
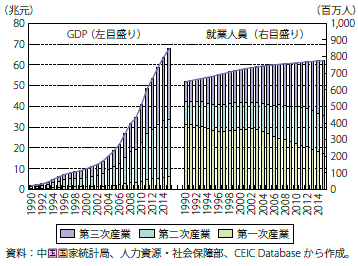
第Ⅰ-3-1-4図 中国の産業構造の推移(シェア)
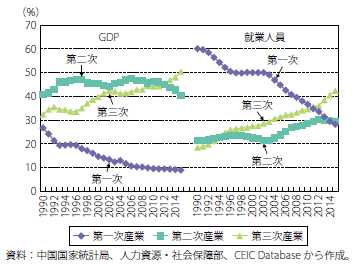
第Ⅰ-3-1-5図 中国の実質GDP成長率(業種別)の推移
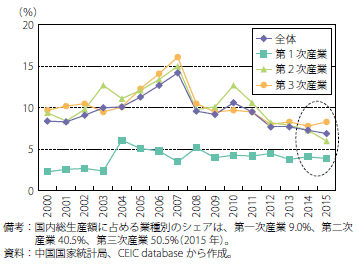
産業のサービス化と軌を一にして、これまで投資に過度に依存していた経済構造を是正するため、中国政府は「投資から消費」への構造転換を図っている。すでに見たように、中国は2000年代、投資・外需を主導とする経済成長を遂げた結果、主要国の高度成長期と比べても、GDPにおける投資シェアが極めて高く、反対に消費が盛り上がらない状況を招いている(第Ⅰ-3-1-6図)。現在の中国の投資シェアは同じ東アジアの我が国、韓国、台湾の過去最高値と比べても更に高い(第Ⅰ-3-1-7表)。
第Ⅰ-3-1-6図 中国のGDP構成比の推移

第Ⅰ-3-1-7表 GDPに占める資本形成のシェア
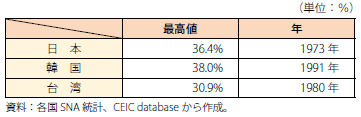
消費財の小売額は全体としては緩やかな伸びにとどまっているが、例えば、通信機器は2014年に伸び率が反転上昇に転じ、2015年もやや減速したものの、依然として高い伸びを見せている。また、スポーツ・レクリエーション等の娯楽も堅調である(第Ⅰ-3-1-8図、第Ⅰ-3-1-9図)。
第Ⅰ-3-1-8図 中国の品目別小売売上高伸び率の推移
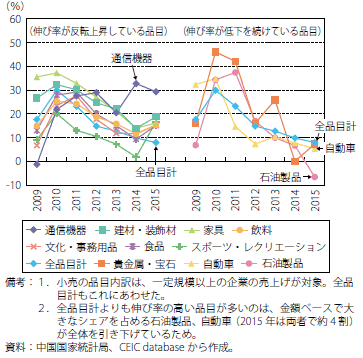
第Ⅰ-3-1-9図 中国の品目別小売売上高伸び率(2015年)
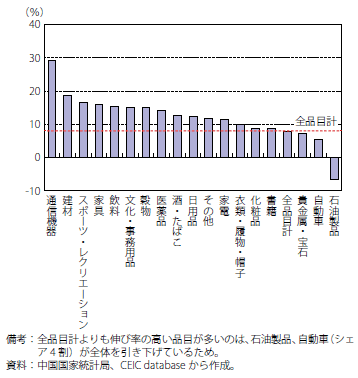
販売形態については、スマートフォン等の普及を背景にインターネットを通じた販売が急速に拡大しており、全小売売上高の約1割を占めるまでに至っている115(第Ⅰ-3-1-10表)。中国においてはインターネット環境の特殊性等を背景に、独自の通信販売、コミュニケーションプラットフォームが誕生しており、サービス経済の拡大に貢献している116。
第Ⅰ-3-1-10表 中国のネット販売額及び伸び率(2015年)
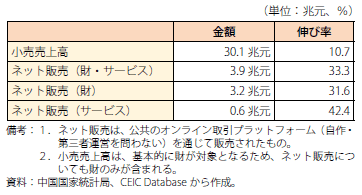
他方、マクロで見た場合、2015年初めまで消費は減速してきており、2015年半ば以降は伸びが上昇しているものの、緩やかな伸びにとどまっている(第Ⅰ-3-1-11図)。その原因のひとつとして、可処分所得の伸び率が鈍化していることの影響が考えられる(第Ⅰ-3-1-12図)。その他に、倹約令に伴う高額商品の萎縮や家計の貯蓄率の高止まり等も指摘されている。
第Ⅰ-3-1-11図 中国の小売売上高の伸び率(前年同月比)
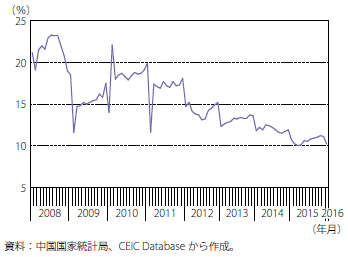
第Ⅰ-3-1-12図 中国の都市部一人あたり可処分所得の伸び率 (年初来累計・前年同期比)
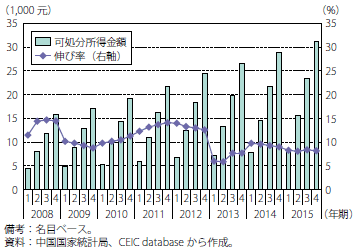
115 反対に急増し過剰となった実店舗の淘汰が進んでいるとの指摘もある。
116 新興国を含む産業のプラットフォーム化については、本章第2節参照。
2.世界的に拡大するサービス貿易
国境を越えたサービスの取引であるサービス貿易は、近年財貿易を上回るペースで拡大している。先進国よりも新興国において伸び率は高いが、財貿易とは異なり、先進国のシェアは依然高い水準にあり、比較優位も先進国側にあると想定される。市場規模は観光や研究開発・専門コンサルティングなどの業務サービスが大きいが、伸び率は通信・コンピュータ・情報サービスや建設サービスが顕著である。また、オランダの農業輸出のように、財輸出に対するサービスによる付加価値の割合が高く、財輸出が実質的にサービス輸出になっている場合もある。本項では、こうしたサービス貿易の在り方、成長分野について概観する。
(1)新興国を中心としたサービス貿易の拡大と先進国の「比較優位」
世界のサービス貿易は、金額では財に及ばないものの、直近10年の年平均伸び率は7.2%と、財の伸び率である6.8%を上回っている117。サービス輸出額の伸びの推移を見ると、2008年のリーマン・ショックを契機とした世界経済危機までは、財とサービスはほぼ同じペースで拡大しているが、2009年の落ち込みはサービス輸出の方が低い。その後、財輸出は2011年以降伸び悩む一方、サービス輸出は安定的に拡大している(第Ⅰ-3-1-13図)。
第Ⅰ-3-1-13図 世界の財・サービス輸出額の推移
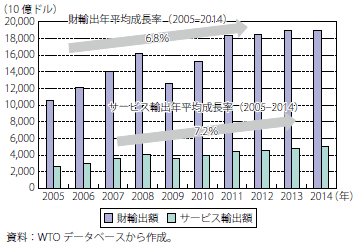
財サービス輸出の対GDP比についても、財貿易の方がサービス貿易よりも比率の水準が高いものの、2011年以降、財輸出において比率の低下が見られる118一方、サービス輸出は緩やかながらも引き続き比率の拡大を続けている(第Ⅰ-3-1-14図)。
第Ⅰ-3-1-14図 世界の財・サービス輸出額の推移(対名目GDP比)
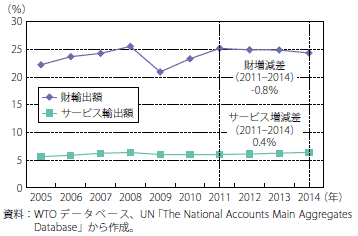
世界銀行の定義119に従って、所得水準別に見ると、中所得国におけるサービス輸出の伸び率は9.3%(2005年から2014年の年平均伸び率)と高所得国の8.9%を上回って拡大している。ただし、中所得国においては、財貿易の伸び率が10.3%とサービス貿易よりも高く、背景の一つとして、中所得国すなわち新興国において複雑な生産ネットワークが拡大し、中間財の国境を越えた往来が急拡大したことが考えられる。高所得国においてはサービス貿易の伸び率(8.9%)が貿易財の伸び率(5.6%)を上回り、特に高所得国において財からサービスへと、輸出の傾向が変化する兆しが見受けられる(第Ⅰ-3-1-15図)。
第Ⅰ-3-1-15図 財・サービス貿易増加率(輸出)
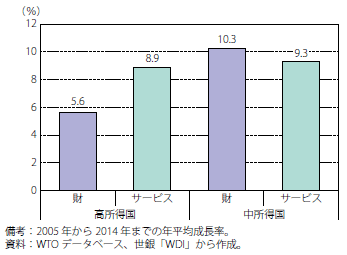
輸入についてもほぼ同様の傾向が見られるが、中所得国においてもサービス輸入の伸び率(11.2%)が財輸入(10.6%)を上回っていることが特徴的である。中所得国のなかでもより所得水準の高い上位中所得国でサービス輸入の伸び率が最も高く(12.0%)、サービス輸出先として、成長市場となっている可能性が考えられる(第Ⅰ-3-1-16図)。
第Ⅰ-3-1-16図 財・サービス貿易増加率(輸入)
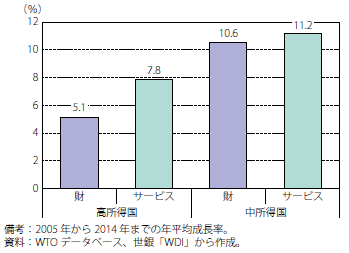
高所得国のサービス貿易収支は、恒常的に輸出が輸入を上回る黒字状態であることから、中所得国との比較において、サービス貿易に比較優位があると考えられる。また財輸出と比較しても、サービス輸出の世界シェアの落ち込みが緩やかであり、2012年以降は反転上昇していることから、サービス輸出は引き続き先進国が中心的役割を果たすと考えられる(第Ⅰ-3-1-17図)。
第Ⅰ-3-1-17図 高所得国における財・サービス輸出入の対世界シェア
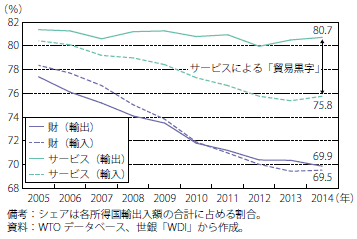
具体的な国別では、特に貿易赤字を抱える米国及び英国が、サービス貿易収支での黒字を拡大させている。我が国も東日本大震災以降、財貿易収支が赤字化する一方、サービス貿易収支は緩やかながら赤字が減少している(第Ⅰ-3-1-18図)。
第Ⅰ-3-1-18図 財・サービス貿易収支の主要国別推移
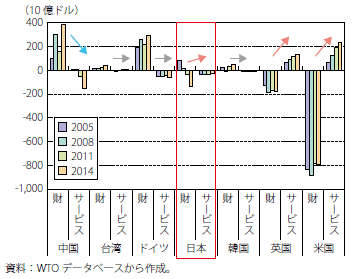
最大のサービス輸出国である米国は、世界のサービス輸出額シェアの約14%を継続的に確保し、その競争力の高さが現れている。米国に次いで英国・ドイツのシェアが高いが、近年はシェアを落としつつある。一方、中国、台湾、韓国は米国を上回る高い伸びにより、徐々にシェアを拡大させている。我が国は、シェア・伸び率ともに劣後しているが、足下でやや輸出の拡大が見られる(第Ⅰ-3-1-19図)。
第Ⅰ-3-1-19図 各国のサービス輸出国別シェアの推移
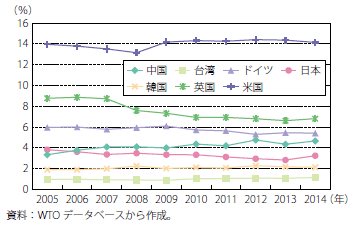
世界のサービス輸出の伸び率(2005~2014年平均成長率7.2%)に対する寄与度では、米国、中国、フランス、ドイツ、英国、インドの寄与が高く、我が国の寄与度は0.2%にとどまる(第Ⅰ-3-1-20図)。一方、世界のサービス輸入の伸び率に対する寄与度は、中国、米国、ドイツ、フランス、インドの寄与が高く、これらの国がサービス貿易に係る市場を新たに創出していることが分かる。これらの国々では、サービス貿易が輸出、輸入とも活発に行われつつ、市場が拡大していることが読み取れる(第Ⅰ-3-1-21図)。
第Ⅰ-3-1-20図 サービス輸出伸び率に対する国別寄与(2005-2014年)(上位20カ国)
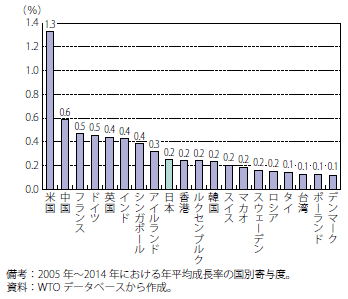
第Ⅰ-3-1-21図 サービス輸入伸び率に対する国別寄与(2005-2014年)(上位20カ国)
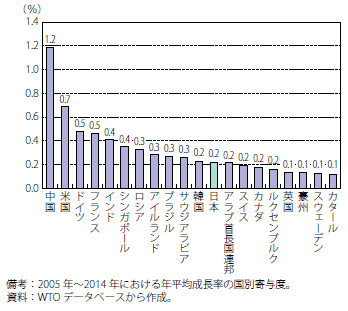
以上より、サービス貿易を巡る近年の変化としては、未だ財貿易に規模では及ばないものの、先進国に加え、産業のサービス化が加速する新興国のサービス需要も取り込みつつ拡大を続けていること、また、サービス貿易においては先進国に比較優位がある可能性が高いことが示される。
117 2005年から2014年までの財サービス貿易額は、財貿易が1.81倍増加したのに対し、サービス貿易は1.88倍増加した。
118 世界的な財貿易の対GDP比の低下の原因については、それが構造的な要因によるものか循環的な要因によるものかについて国際的な議論が行われている。例えばConstantinescu, Mattoo and Ruta (2014)を参照。
119 世界銀行(2015)。
(2)旅行・業務サービス・情報通信が牽引するサービス貿易
サービス貿易の市場規模を分野別120に見ると、世界のサービス輸出額では「旅行サービス」「その他業務サービス(以下「専門業務サービス」という。)」121「輸送サービス」が大きく、同伸び率では「通信・コンピュータ・情報サービス」「建設サービス」「専門業務サービス」の伸びが大きい(第Ⅰ-3-1-22図)。
第Ⅰ-3-1-22図 世界のサービス輸出額の項目別推移(2005-2014年)
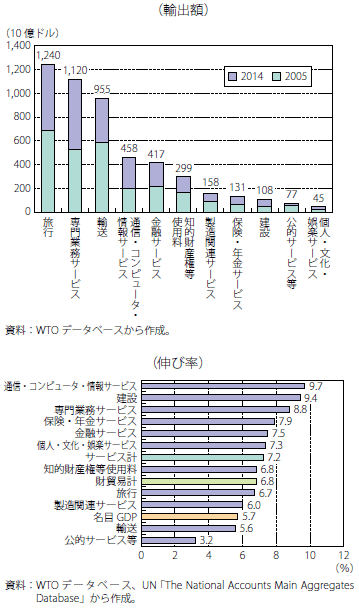
輸出額最大の項目である「旅行サービス」は、2014年に輸出額1.2兆ドルの規模となっている。2015年の世界の海外旅行客数は対前年比4.4%増の11億8400万人に達する見込み122であり、特に中国からの旅行者数の伸びが著しい。これに対し、トルコ(3.7%)・南アフリカ(2.7%)・豪州(2.2%)において「旅行サービス」輸出額の対GDP比が高く、海外からの観光客受入が当該国にとって主要産業の一つであることが窺える123(第Ⅰ-3-1-23図)。
第Ⅰ-3-1-23図 旅行サービス輸出額の対名目GDP比(2014年)
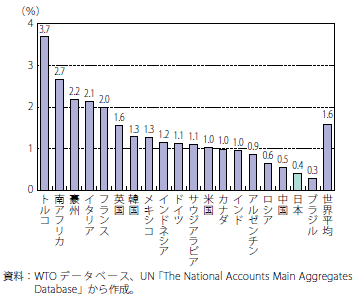
次いで、研究開発や専門コンサルティングサービスなど比較的高度なスキルが必要と考えられるサービスが計上される「専門業務サービス」が輸出額1.1兆ドル(2014年)となり、これまで「旅行」に次いで市場規模が大きかった「輸送サービス」124を抜いてサービス輸出額シェアで2位に上昇した(第Ⅰ-3-1-24図)。
第Ⅰ-3-1-24図 世界のサービス輸出額の推移(項目別シェア)
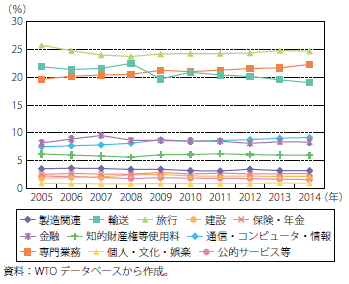
また、過去10年間の伸び率で年平均9.7%と、成長速度が最も早い「通信・コンピュータ・情報サービス」が、「金融」を抜いてサービス輸出額シェア4位に上昇しており、近年グローバルな取引が急拡大していることが読み取れる(第Ⅰ-3-1-24図)。輸出額の規模は大きくないものの、伸び率では「通信・コンピュータ・情報サービス」に次ぐ「建設サービス」の成長は、世界的なインフラ投資の拡大を反映しているものと推測される(第Ⅰ-3-1-22図)。
足下のサービス輸出額の前年比寄与度では、「旅行サービス」「専門業務サービス」「通信・コンピュータ・情報サービス」がサービス輸出全体の増加に大きく寄与している(第Ⅰ-3-1-25図)。このように、これまでサービス貿易で主流となってきた「輸送サービス」などの項目を上回る、新たな成長市場が出現し始めているという変化が見受けられる。これらの項目については、次項でその内容を確認する。
第Ⅰ-3-1-25図 世界のサービス輸出額の推移(対前年比寄与度)
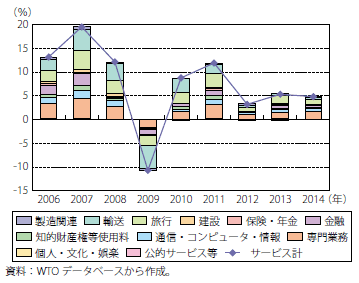
120 サービス貿易の分野別分類は、IMFが作成している”Balance of Payments and International Investment Position Manual, sixth edition”(「国際収支マニュアル」)に基づく。現在は第6版が最新となっている。
121 「専門業務サービス」は、IMF 「国際収支マニュアル」におけるOther Business Services (財務省「国際収支統計」における「その他業務サービス」)を指す。
122 World Tourism Organization (UNWTO)「2016年5月6日報道資料」(http://media.unwto.org/press-release/2016-05-03/exports-international-tourism-rise-4-2015![]() )による。
)による。
123 「旅行サービス」については、第2部第2章第2節における分析を参照されたい。
124 「輸送サービス」の規模は国際的な貿易数量と運賃に大いに依存するところ、最近の海運運賃の下落等により影響を受けていると考えられる。
(3)強みを生かしてサービス貿易を拡大させる世界の国々
拡大するサービス貿易市場に対し、2014年には世界全体のGDPに占めるサービス輸出の比率は6.4%に達している。この中で、G20各国を見てみると、英国(対GDP比11.4%)、フランス(同9.5%)、インド(同7.6%)などにおいて同比率が高く、英国の金融、インドの情報通信、韓国の輸送、中国の建設など、特徴的な分野でサービス輸出を拡大する国も見受けられる(第Ⅰ-3-1-26図)。
第Ⅰ-3-1-26図 G20各国のサービス輸出額対名目GDP比(2014年)
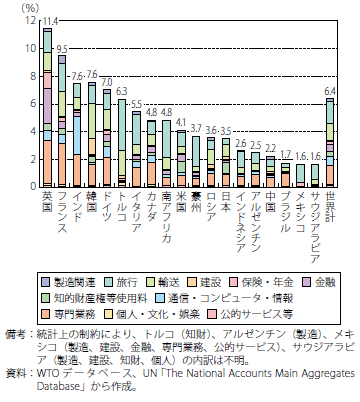
G20各国のGDPに占めるサービス付加価値シェアとの関係は、緩やかな正の関係となる傾向にあるが、英国、フランス、インド、韓国等のサービス輸出対GDP比の上位国は傾向線を上回っており、サービス産業の海外とのつながりが高いことが分かる(第Ⅰ-3-1-27図)。
第Ⅰ-3-1-27図 サービス輸出とサービス付加価値シェアの関係(対名目GDP比)(2014年)
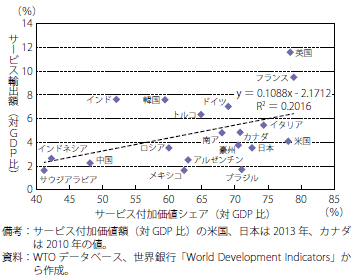
次に各国のサービス貿易の状況について、輸出額から輸入額を差し引いた収支で概観すると、経常赤字国である米英が中心となり黒字を拡大させている一方、経常黒字国であるドイツ・中国・我が国は赤字となっている。ただし、我が国はサービス輸出が輸入に比べて足下で増加しており、収支の赤字は縮小傾向にある。中国については2011年以降赤字を大きく拡大させている(第Ⅰ-3-1-28図)。
第Ⅰ-3-1-28図 主要各国のサービス貿易収支の推移
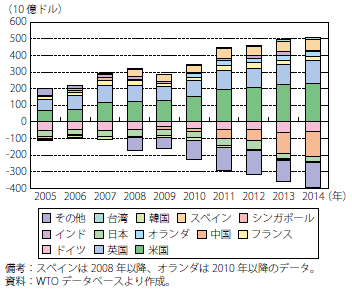
サービス貿易の内訳を各項目別に見ていくと、それぞれの項目に比較的特化してサービス輸出を行う国が見受けられる。サービス貿易収支の黒字を拡大する米国では、知的財産権等使用料、金融、専門業務サービスといった、新たなイノベーションによる高付加価値化が考えられる項目で黒字が拡大している(第Ⅰ-3-1-29図)。
第Ⅰ-3-1-29図 サービス貿易の推移(米国)
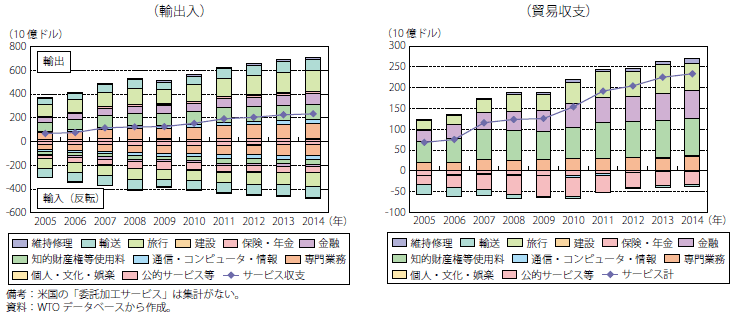
また、強みのある各分野で黒字を拡大する国も見受けられる。英国は従来から競争力の高い金融、韓国は公的支援の整備によりインフラ輸出を拡大する建設、台湾は当局によるイノベーション支援によって研究開発やビジネスサービス等を集中的に取り組んでいる専門業務サービスなどが、黒字を牽引している(第Ⅰ-3-1-30図~第Ⅰ-3-1-32図)。
第Ⅰ-3-1-30図 サービス貿易収支の推移(英国)
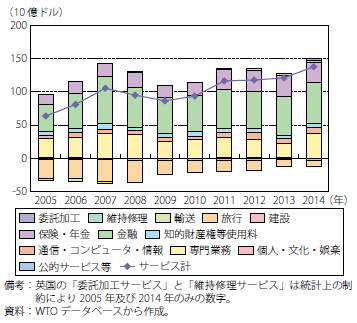
第Ⅰ-3-1-31図 サービス貿易収支の推移(韓国)
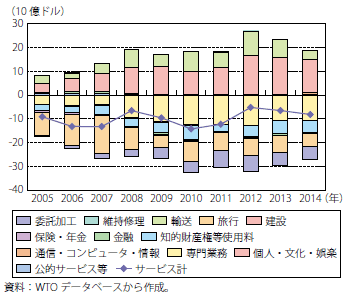
第Ⅰ-3-1-32図 サービス貿易収支の推移(台湾)
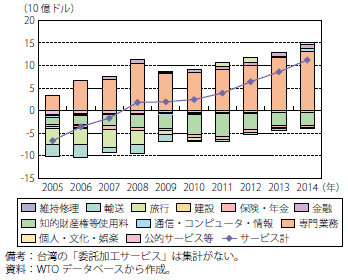
一方、中国は旅行需要の拡大を反映した旅行、輸送部門の支払の拡大により、サービス貿易収支の赤字が大きく拡大している(第Ⅰ-3-1-33図)。財の輸出において競争力の高いドイツも、サービス貿易収支では旺盛な旅行需要を反映して赤字が継続している(第Ⅰ-3-1-34図)。
第Ⅰ-3-1-33図 サービス貿易収支の推移(中国)
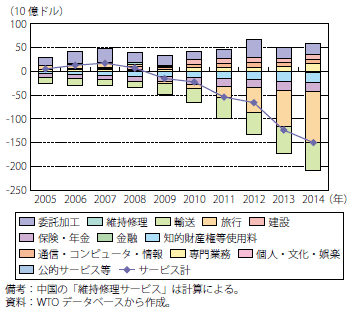
第Ⅰ-3-1-34図 サービス貿易収支の推移(ドイツ)
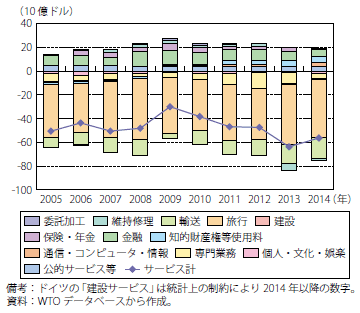
我が国は、旅行収支の赤字幅縮小や知的財産権等使用料収支の黒字幅拡大等により、足下で収支が改善するも、専門業務サービス等での輸入拡大が収支を引下げている(我が国のサービス貿易については第Ⅱ部第2章、インドのサービス貿易については同第4章第Ⅰ節で詳しく分析する。)(第Ⅰ-3-1-35図)。
第Ⅰ-3-1-35図 サービス貿易の推移(日本)
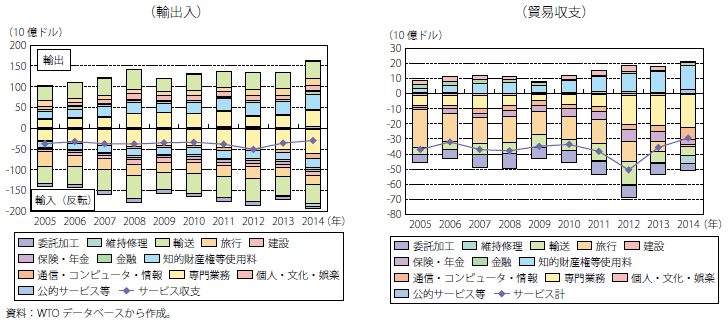
①インド・先進国を中心に成長する「通信・コンピュータ・情報サービス」
サービス貿易は基本的に消費者と生産者の近接性を必要とするが、情報通信技術の進展により、クラウドサービス等のようにその制約が薄まるビジネスも拡大している。
「通信・コンピュータ・情報サービス」(第Ⅰ-3-1-41表)125輸出額は過去10年間で年率9.7%の伸びを見せている。しかし、9.7%に対する国別寄与をみると、新たに誕生した市場の過半をIT分野の成長が著しいインド(2.0%)、当該分野で極めて競争力の高い企業が集中する米国(1.0%)、ドイツ(1.0%)、中国(1.0%)が占めている。一方、我が国の寄与は0.1%と極めて低い(第Ⅰ- 3-1-36図)。輸出額そのものはアイルランド(576億ドル)、インド(557億ドル)において高く126、輸出額の対GDP比で見るとインド(2.7%)が非常に高い状態となっている(第Ⅰ-3-1-37図、第Ⅰ-3-1-38図)。
第Ⅰ-3-1-36図 「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出伸び率(9.7%)に対する国別寄与(2005~2014年)(上位20カ国)
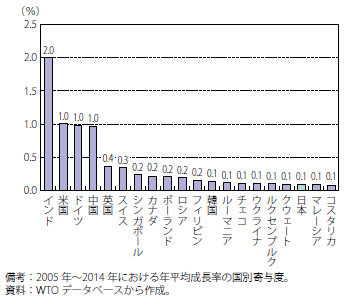
第Ⅰ-3-1-37図 「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出額(2014年)(上位20カ国)
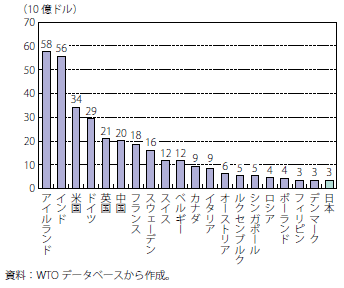
第Ⅰ-3-1-38図 「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
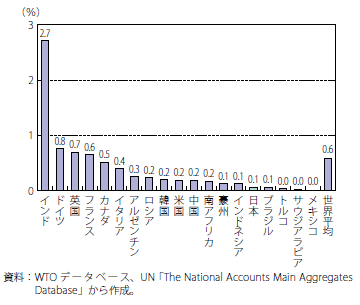
同分野では政府レベルにおいても情報通信技術を活用した新しい動きが進んでいる。エストニア、韓国等では政府システムの汎用性を高め、プラットフォームとして海外展開を進めている。これらのシステムにおいては、導入先のシステムと自国のシステムを連携させることにより、輸出円滑化や自国企業の海外での活用促進、海外からの投資を促進させることを意図する側面もあり、単なるサービス輸出に止まらない複合的な効果が想定される(第Ⅰ-3-1-39図、第Ⅰ-3-1-40表)。
第Ⅰ-3-1-39図 韓国・エストニアにおける「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出伸び率(2005~2014年)
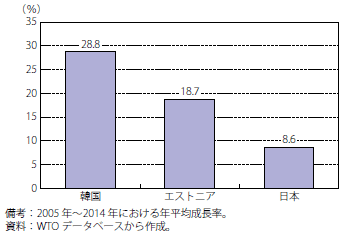
第Ⅰ-3-1-40表 韓国・エストニアにおける政府システム
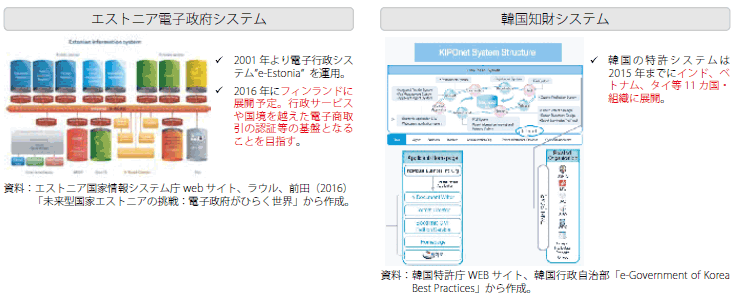
第Ⅰ-3-1-41表 「通信・コンピュータ・情報サービス」の定義
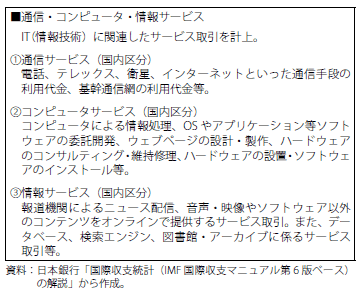
125 本節内で使用するサービス貿易各項目の定義は、日本銀行(2016)「国際収支統計(IMF国際収支マニュアル第6版ベース)の解説」(日本銀行Webサイト)から引用している。
126 アイルランドの「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出の過去10年間における伸び率はデータ制約により作成できず。
②先進国が強みを持つ「専門業務サービス」
研究開発サービスや専門コンサルティングサービスなどの「専門業務サービス」(第Ⅰ-3-1-53表)は、世界のサービス産業化や情報通信技術の浸透を背景に、近年のサービス輸出成長の一翼を担っている。
英国(3.1%)やフランス(3.0%)など先進国においてGDPに占める割合が高いほか、新興国でもインド(2.3%)において「通信・コンピュータ・情報サービス」(2.7%)と並んで比率が高い。ITを始めとする様々な分野におけるアウトソーシング受託業務が同国経済に大きな影響を与えていることが分かる(第Ⅰ-3-1-42図)。
第Ⅰ-3-1-42図 専門業務サービス輸出額の対名目GDP比(2014年)
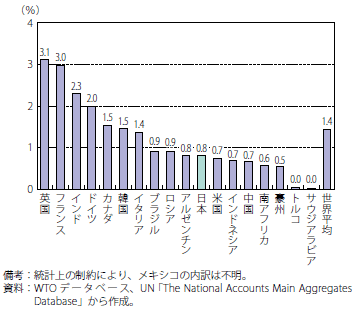
主要先進国(日・米・独・英)の2010年から2014年の間の年平均輸出伸び率を比較すると、米国(6.8%)、ドイツ(6.4%)、英国(6.1%)において高いが、我が国は4.2%と伸びが低い。
主要先進国による「専門業務サービス」の輸出を更に細かく分類すると、伸び率では「研究開発サービス」が最も高い。一方、日本を除く米国、英国、ドイツにおいては、2014年の輸出額は「専門・経営コンサルティングサービス127」が大きく、2010年から2014年までの全体の伸び率に対する寄与度も最大と、「専門・経営コンサルティングサービス」が「専門業務サービス」輸出の拡大をけん引している。なお、「技術・貿易関連・その他業務サービス128」は一定の輸出額は計上されているが、伸びは他と比較して高くない(第Ⅰ-3-1-43~46図)。
第Ⅰ-3-1-43図 主要国の「専門業務サービス」輸出伸び率と項目別寄与度(2010-2014年)
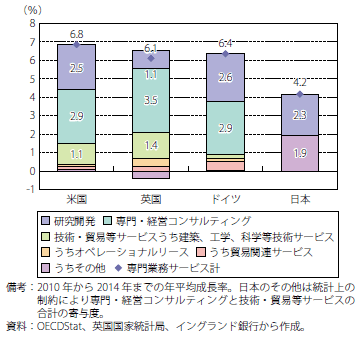
第Ⅰ-3-1-44図 主要国の「研究開発サービス」輸出額(2014年)と伸び率(2010-2014年)
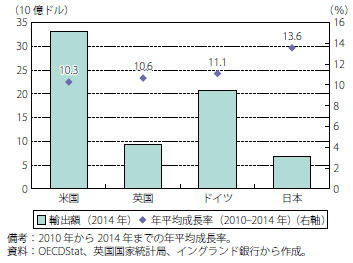
第Ⅰ-3-1-45図 主要国の「専門・経営コンサルティングサービス」輸出額(2014年)と伸び率(2010-2014年)
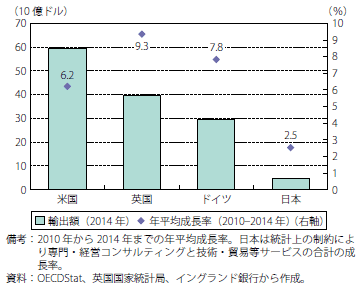
第Ⅰ-3-1-46図 主要国の「技術・貿易関連・その他業務サービス」輸出額(2014年)と伸び率(2010-2014年)
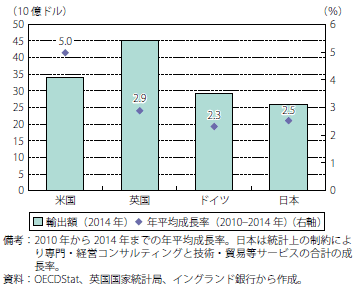
主要先進国の収支でも「専門・経営コンサルティングサービス」輸出の拡大により、米英において黒字が拡大傾向で、ドイツも赤字が縮小傾向にある。一方、我が国においては赤字幅が拡大する傾向にある(第Ⅰ-3-1-47~50図)。
第Ⅰ-3-1-47図 「専門業務サービス」貿易収支(米国)
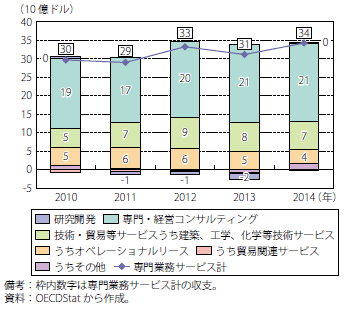
第Ⅰ-3-1-48図 「専門業務サービス」貿易収支(英国)
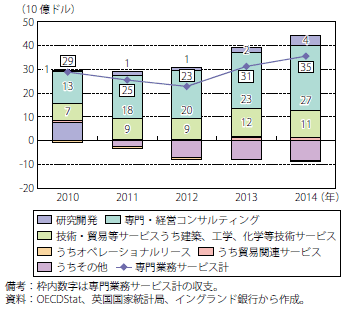
第Ⅰ-3-1-49図 「専門業務サービス」貿易収支(ドイツ)
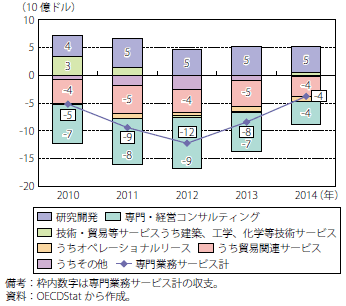
第Ⅰ-3-1-50図 「専門業務サービス」貿易収支(日本)
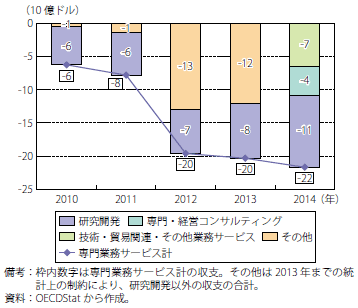
他方、世界の輸出額全体に占める主要先進国のシェアは、近年わずかながらも下げており、中国が大きくシェアを伸ばしている(第Ⅰ-3-1-51図)。
第Ⅰ-3-1-51図 「専門業務サービス」輸出額国別シェアの推移
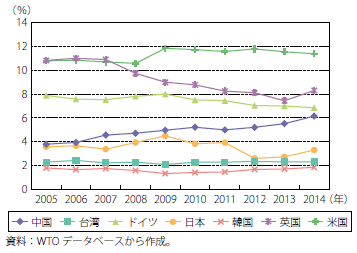
こうした対ビジネス分野のサービス輸入国は必ずしも先進国に限られず、中国などの新興国からの委託も大きなウェイトを占める。2005年から2014年にかけて「専門業務サービス」の輸入額は年平均8.8%増加したが、これに対する寄与は、米国(1.2%)、中国(0.8%)、ドイツ(0.7%)などにおいて高かった。先進国と新興国が互いの強みを活かしつつ、業務がグローバルにアウトソーシングされている様子が窺える(第Ⅰ-3-1-52図)。
第Ⅰ-3-1-52図 「専門業務サービス」世界の市場伸び率(輸入額伸び率)(8.8%)に対する国別寄与(2005~2014年)(上位20カ国)
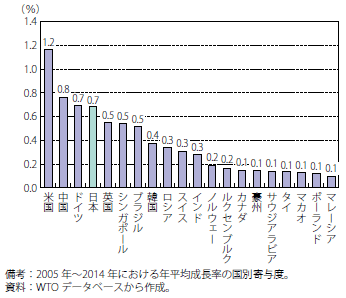
第Ⅰ-3-1-53表 「専門業務サービス」の定義
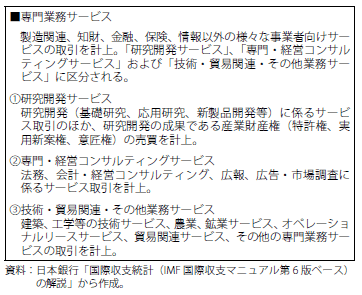
127 「専門・経営コンサルティングサービス」の我が国における伸び率(2.5%)は、統計上の制約から「技術・貿易関連・その他業務サービス」との合計値であることに留意が必要。
128 更にこの内訳として、「建築、工学、科学等技術サービス」、「オペレーショナルリースサービス」、「貿易関連サービス」等が含まれる。先進国における「建築、工学、科学等技術サービス」は高度な技術が要求される分野が該当すると考えられるが、米国、英国については、同項目が成長に寄与しており、2014年のその他業務サービス輸出におけるシェアも高くなっている(米国10%、英国15%、ドイツ17%)。なお、我が国については当該分類での集計がないため、傾向は把握できない。
③製品輸出を上回り成長する「製造関連サービス」(維持修理サービス)
「製造関連サービス」(第Ⅰ-3-1-59表)は、財貨に関連して発生するサービスが計上されており、フランス(0.6%)、ドイツ(0.3%)、韓国(0.2%)において対GDP比率が高い(第Ⅰ-3-1-54図)。
第Ⅰ-3-1-54図 「製造関連サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
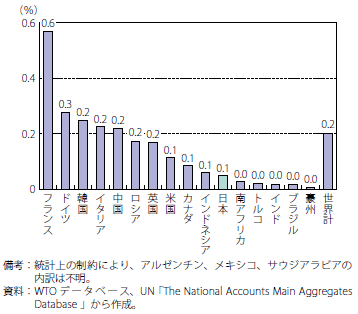
この項目の内訳の1つである「維持修理サービス」は、航空機等のメンテナンスや、財の売買契約に基づいて販売元が負担するアフターサービス等、国境を越えて行われる財貨の修理やアフターサービスが計上されており、IoT等の先端技術により得られたビッグデータの解析を活用しつつ、財の販売から、財から発生するサービスへ、付加価値が移行する例が含まれている可能性が考えられる(第Ⅰ-3-1-55図)。
第Ⅰ-3-1-55図 「維持修理サービス」輸出額と伸び率(2005~2014年)
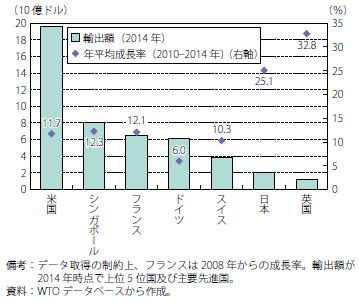
この「維持修理サービス」の国別の輸出額シェアを見ると、米国が全体の3割以上のシェアを保って推移しており、収支も黒字となっている(第Ⅰ-3-1-56図)。
第Ⅰ-3-1-56図 「維持修理サービス」輸出額国別シェアの推移
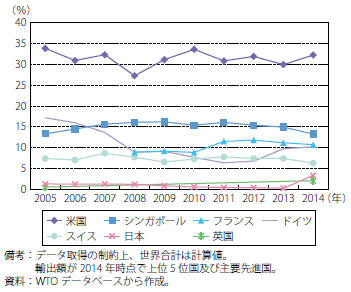
同項目に含まれる例として、航空機産業におけるMRO(Maintenance Repair Overhaul。航空機の受託整備事業)ビジネスが挙げられる。同ビジネスは、航空機本体の売買以降も継続的に需要が発生するアフターサービスのマーケットであり、その市場規模は拡大を続けている。MROサービスのうち、機体の整備等労働集約型のビジネスが新興国を中心に拡大する傾向にある。一方、航空機用エンジンについては、世界の主要エンジンメーカーが、航空会社に対し様々なサービス提供を進めている。エンジンの部品やメンテナンス代など、エンジンの使用に伴う費用が飛行時間単位で発生する「包括契約(Total Care)」の提供は、エンジン製造業のサービス産業への変化の例として知られている。
また、近年では、ビッグデータ解析等を通じて、エンジンの稼働状態や操縦状況等様々な状態をモニタリングすることで、予防的メンテナンスの観点での整備スケジュール構築、データ解析による運行効率改善のソリューション事業等が行われている。製造技術と情報通信技術を融合したビジネスが拡大する傾向が見受けられる。
国際収支における「維持修理サービス」では、産業別に貿易動向を把握はできないものの、産業用エンジンの主要メーカーが集中する米国で継続的に高いシェアを保っており、英国も足下で輸出が増加している。また、中国・台湾を除く主要製品輸出国で、製品輸出額の伸びをメンテナンスサービス輸出額の伸びが上回っており、製造業においても、新たなサービス提供の重要性が高まっていることを示唆している(第Ⅰ-3-1-57図、第Ⅰ-3-1-58図)。
第Ⅰ-3-1-57図 「維持修理サービス」輸出額伸びの推移
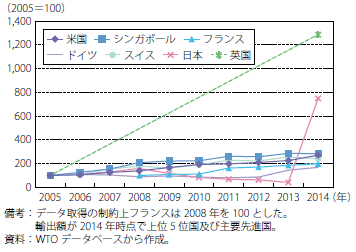
第Ⅰ-3-1-58図 「維持修理サービス」と製品輸出額の比較
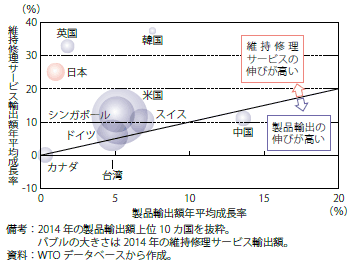
第Ⅰ-3-1-59表 「製造関連サービス」の定義
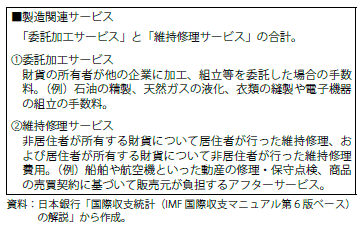
我が国においても、これまで世界の中でも高い競争力を持ってきた製造業等における強みとモノから得られるデータを戦略的に結びつけた、新たなビジネスモデルの構築の重要性が高まっている。これを受けて検討されている我が国の取組については、第Ⅱ部第2章第1節で取り上げる。
④日米が牽引する「知的財産権等使用料」
「知的財産権等使用料」(第Ⅰ-3-1-67表)は、我が国のサービス貿易収支を引上げる主要な項目であるが129、世界で見ると米国が最大のシェアを維持しており、同国の競争力が高い分野となっている。我が国は米国に次ぐシェアを保っており、伸びは緩やかだが足下で上昇する傾向にある(第Ⅰ-3-1-60図)。
第Ⅰ-3-1-60図 知的財産権等使用料輸出額の対名目GDP比(2014年)
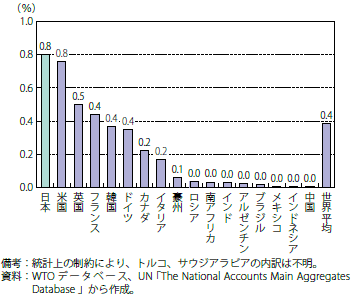
過去10年間の輸出額の伸びではシンガポール、中国、台湾等が成長しているが、これらの国は輸入も大きく拡大する傾向にある(第Ⅰ-3-1-61~64図)。
第Ⅰ-3-1-61図 「知的財産権等使用料」輸出伸び率(6.8%)に対する国別寄与(2005~2014年)(上位20カ国)
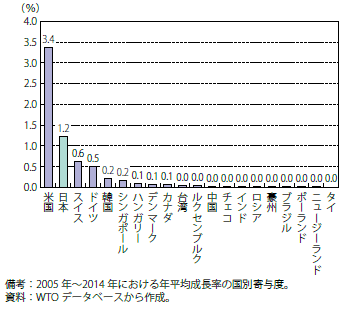
第Ⅰ-3-1-62図 「知的財産権等使用料」輸入伸び率(6.8%)に対する国別寄与(2005~2014年)(上位20カ国)
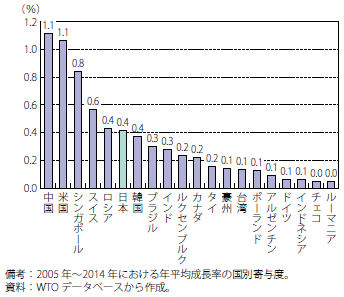
第Ⅰ-3-1-63図 「知的財産権等使用料」輸出額伸びの推移
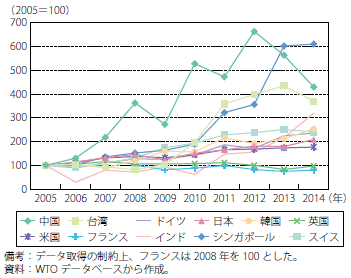
第Ⅰ-3-1-64図 「知的財産権等使用料」輸出額国別シェアの推移
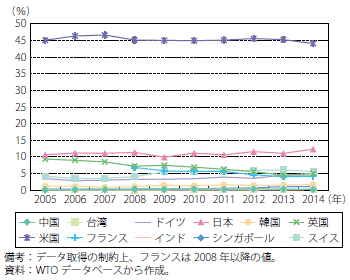
本項目で世界最大の輸出国である米国を詳しく見ると、輸出額では製造業等の海外進出に伴う工場建設及び子会社からのロイヤリティ収入である工業権使用料の割合が高い。一方、収支で見ると米国企業が強みを持つコンピューターソフトウェアや商標使用料が黒字を牽引している(第Ⅰ-3-1-65図)。
第Ⅰ-3-1-65図 米国における「知的財産権等使用料」の内訳推移
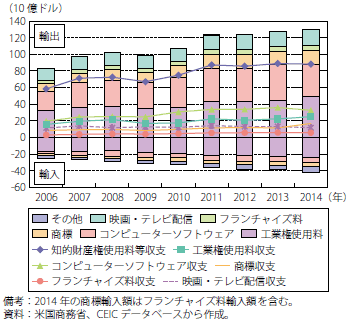
これに対し、我が国の知的財産権等使用料に関する収支の黒字は、そのほとんどが産業財産権等使用料のうちの輸送用機械関連によるものであり、我が国のこれまでの主力な産業の一つである自動車製造業の海外展開によるロイヤリティ等が拡大していることがわかる。一方、ソフトウェアの使用料等が含まれる著作権等使用料については、赤字となっている130(第Ⅰ-3-1-66図)。
第Ⅰ-3-1-66図 我が国における「知的財産権等使用料」の内訳推移
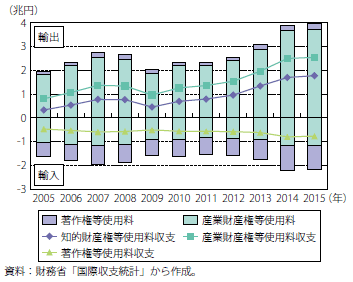
第Ⅰ-3-1-67表 「知的財産権等使用料」の定義
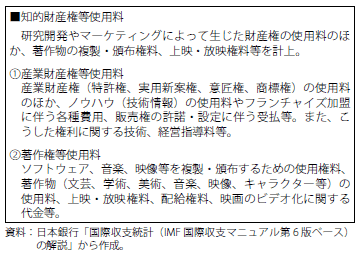
129 2015年通商白書で分析したように、海外展開した我が国企業の現地法人がその利益を還流させる際の支払い方法として、主に配当金とロイヤリティがあり、配当金は国際収支の第一次所得収支、ロイヤリティは国際収支のサービス収支内項目「知的財産権等使用料」に含まれている。
130 業種別の傾向を見るため、総務省「科学技術統計」を用いて「技術貿易」における収支を見てみると、収支黒字は製造業、中でも自動車等によるものであり、非製造業では収支は赤字となっている。特に、情報通信業の赤字が大きく、学術・研究機関等による黒字を打ち消している。
⑤その他のサービス
「金融サービス」や「保険・年金サービス」は英国において対GDP比が高く、金融機関等による対外サービスが同国の重要産業となっていることが分かる(第Ⅰ-3-1-68図、第Ⅰ-3-1-69図)。
第Ⅰ-3-1-68図 「金融サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
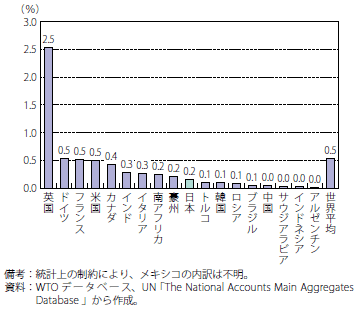
第Ⅰ-3-1-69図 「保険・年金サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
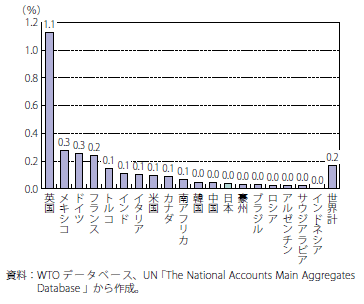
このほか「輸送サービス」は韓国(2.5%)において、インフラ受託などによる「建設サービス」は韓国(1.2%)において、「公共サービス」は英国(0.14%)においてそれぞれGDPに占める割合が高い(第Ⅰ-3-1-70~72図)。
第Ⅰ-3-1-70図 「輸送サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
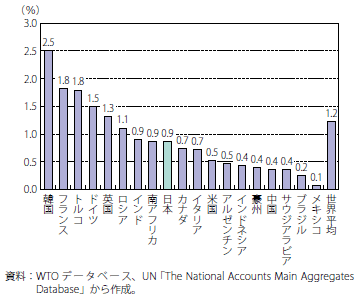
第Ⅰ-3-1-71図 「建設サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
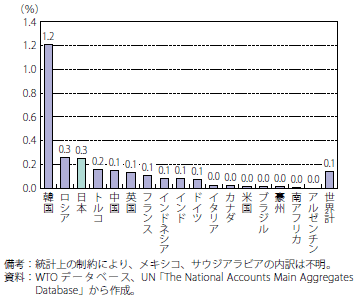
第Ⅰ-3-1-72図 「公共サービス」輸出額の対名目GDP比(2014年)
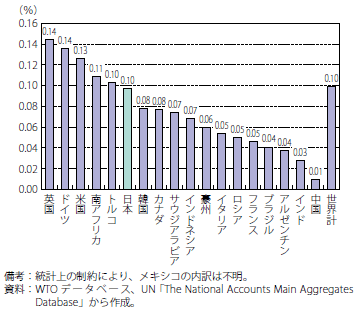
(4)輸出産業のサービス化
ここまで国境を越えるサービスの提供について概観してきたが、財輸出についても、特に先進国において、輸出に至るまでの過程において付与された、サービス業による付加価値の比率が上昇している傾向が見られる。製造業全体に係る輸出に占めるサービス業による付加価値の割合は、OECD加盟国において1995年には32.8%であったものが、2009年には35.9%まで上昇している。ただし、足下ではやや低下しており、OECD非加盟国においては90年代と比較しても減少トレンドにある(第Ⅰ-3-1-73図)。
第Ⅰ-3-1-73図 製造業輸出に占めるサービス業による付加価値の割合
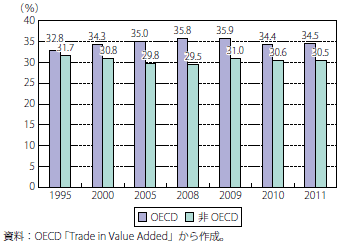
しかし、分野や国によってはサービス業による付加価値の割合が急上昇しており、それが生産性の上昇を通じて産業の発展や輸出の拡大に結びついている場合もありうる。その典型的な事例がオランダの農業輸出であり、農業輸出に占めるビジネスサービス131の割合は1995年時点ではOECD全体の平均を下回っていたが、その後急上昇し、2011年時点では35.2%に達している(第Ⅰ-3-1-74図)。オランダは国土の狭隘さにもかかわらず、世界第2位の食料品輸出国となっており、その原動力には流通機能の充実などサービス分野の充実があると指摘されている。
第Ⅰ-3-1-74図 農業輸出に占めるビジネスサービスによる付加価値の割合
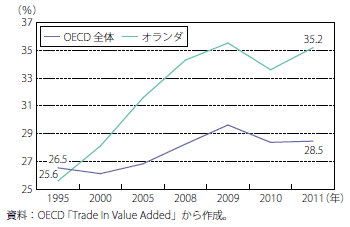
我が国との比較からは、そうした傾向がより顕著に現れており、オランダの農業輸出は、農産品の輸出ではなく、サービス輸出であると言っても過言ではない132(第Ⅰ-3-1-75図)。
第Ⅰ-3-1-75図 農業分野の輸出に関する付加価値の源泉
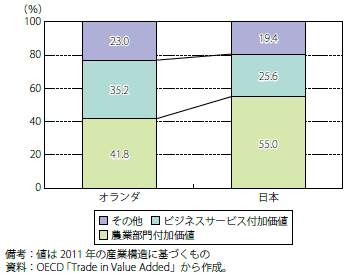
131 卸売、輸送、情報通信、研究開発などの合計であり、OECD Trade in Value Added (TiVA)の分類に従う。
132 オランダの農業輸出の具体的な動向については、第2部第3章において詳細に分析しているため、併せて参照されたい。
3.まとめ
世界経済の成長に伴う産業のサービス化は、先進国から新興国、特に中国において政府の方針も背景に大きく拡大している。これに伴い、財貿易が世界的に鈍化するなかでも、サービス貿易は新興国の需要も取り込みつつ堅調に拡大を続けている。未だ規模では財貿易に及ばないが、特に、先進国による輸出が拡大する傾向が高く、先進国に競争優位性が見受けられる。
また、これまで主な貿易項目であった旅行や輸送に加え、サービス貿易の成長分野も変化しており、通信・コンピュータ・情報サービスや業務サービス等、情報通信技術の進展を背景としてサービス提供における「消費者と生産者の近接性」 の制約を超える新たな分野で拡大を見せている。
このようにサービス貿易市場が拡大・変化する中で、各国は強みを生かしたサービス貿易を展開している。特に米英等の先進国を中心に、各国は新たな成長分野における競争優位性を高め、サービス貿易における収益を高めている。更には、オランダの農林水産品輸出のように、財輸出についても流通サービスや研究開発サービスなどを梃子に付加価値を拡大させ、輸出を拡大する国も見受けられる。
サービス貿易の重要性は、今後更に高まっていくと考えられるが、我が国のプレゼンスは必ずしも高いとは言えない状況にある。我が国のサービス貿易とその課題については第2部第2章で詳しく分析するが、今後とも更なるサービス輸出拡大に向けて様々な取組の必要性が高まっていくと言える。