第2節 プラットフォーム化と産業構造の変化
情報通信技術の発展により、世界のデータフロー136は年率数十パーセントという猛烈な勢いで飛躍的に拡大している137(第Ⅰ-3-2-1図)。この急速に進化する情報通信技術を実装し、プラットフォームを構築した米国を中心とするIT企業が、情報通信分野のみならず、自動運転、医療、金融、音楽などの他分野に積極的に入り込むなど、産業界の構造も変化する兆しがある。また、プラットフォーム化が引き起こしたシェアリングエコノミーの拡大によって、実社会への影響も生じつつある。本項では、これらの急速な変化の動向と、そのインパクトを探る。
第Ⅰ-3-2-1図 世界の情報通信量及びその将来推計
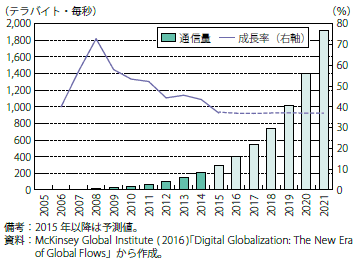
136 世界の情報通信量及びその将来推計は様々な機関が出しているが、ここではTeleGeography及びMcKinsey Global Instituteによる推計を引用する。ほかにもCISCOによるCisco Visual Networking Index: Forecast and Methodologyなどがある。
137 増大するデータフローがマクロ経済全体に与えるインパクトについても論考が行われているが、確たる説は確立していない。国際的なデータフローが長期的にはGDPを3%押し上げる効果があるとの試算 もあるが、逆にシェアリングエコノミーの拡大により資本ストックの形成が減速するとの指摘もある。なお、GDPの押し上げ効果はMcKinsey Global Institute (2016)による試算であるが、統計的な有意性を示すp値が十分に高くなく、モデルの更なる精緻化が期待される。
1.プラットフォーム化によるインパクト
近年のビッグデータ解析、IoTや人工知能技術の進化といった情報通信技術の発展により、様々な製品から収集されるデータを分析し、再び製品にフィードバックして製品の機能、性能を著しく向上させることが可能となった。この結果、製品の価値は、製品そのものから、製品の機能、性能から得られるサービスへと移行しており、製品から得られるデータがその価値の源泉となっている。
米国を中心としたIT企業は、付加価値の源泉であるデータを収集・分析・活用するプラットフォームを構築、これを基盤とした様々な産業を包含するエコシステムを形成し、国境を越えてその競争力を高めつつある(第Ⅰ-3-2-2図)。
第Ⅰ-3-2-2図 米国イノベーティブ産業の海外売上高推移
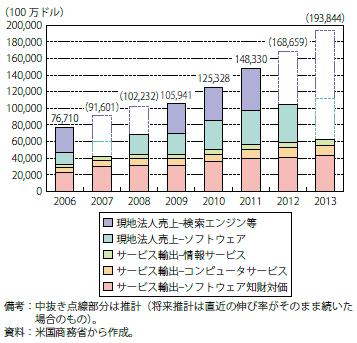
急速に進化する情報通信技術を実装して構築されたデジタルプラットフォームは、前述の間接効果によって、新たなビジネストレンドを拡大させている。
製品のサービス化の進展を背景に、製品の所有に代わって「共有」するシェアリングエコノミーは、デジタルプラットフォームによる需給調整コストの減少によって、米国のみならず新興国でも拡大が見られており、特に緩やかな規制やスマートフォンの普及等を背景に、新興国発のプラットフォームも誕生している(第Ⅰ-3-2-3表、第Ⅰ-3-2-4図)。
第Ⅰ-3-2-3表 新興国における新たなデジタルプラットフォームの動き
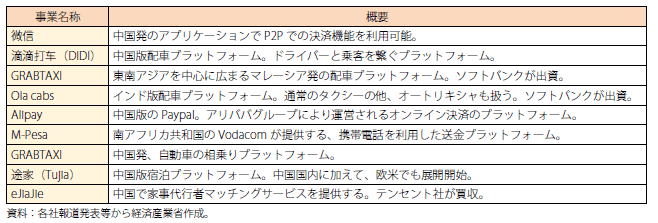
第Ⅰ-3-2-4図 米国主要オンラインプラットフォーム利用者の年間収入
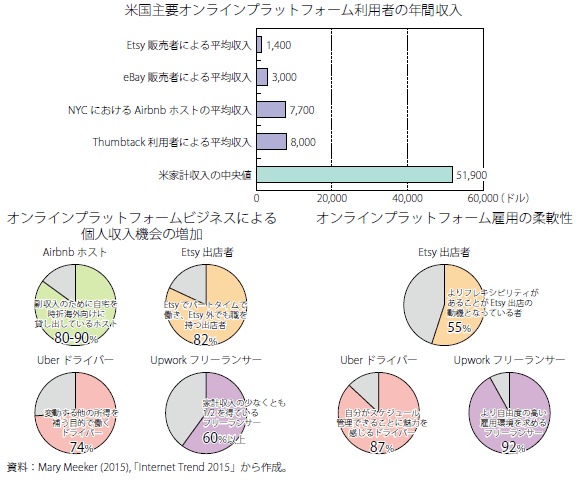
一方、シェアリングエコノミーの台頭により、旧来型のビジネスモデルとの競争が激化する事例も見られており、バランスのある形で技術の変化を社会に取り込むことが課題となっている。例えば米国では既に、大手タクシー会社がUber等新興の配車サービス企業との競争、雇用者の引き抜き等の影響により破産する例が発生している。
また、Airbnbは世界190ヶ国138に展開する宿泊事業者に成長しているが、ボストン大学の研究139によると、Airbnbの拡大によって既存のホテルの収益が減少していることが指摘されている。同レポートでは、Airbnbの影響によるホテル価格の低下は、シェアリングエコノミーを活用する消費者のみならず、それ以外の消費者も享受するものと指摘しているが、一方で、宿泊産業の例では供給コストの圧倒的な低下といったシェアリングエコノミーの優位性により、激化する競争の中で既存の産業はマーケットシェアを喪失しつつあるとされている。
138 同社ウェブサイトによる(https://www.airbnb.jp/about/about-us![]() )。
)。
139 Zervas, Proserpio and Byers (2016).
2.プラットフォームビジネスとIT化の影響
プラットフォームビジネスが何を指すのかについては、様々な定義が存在する140。本稿では、プラットフォームビジネスを「第三者に何らかの『場』を提供する業態」を指すものと幅広く捉えた上で、これに密接に関連すると考えられる「規模の経済」「直接ネットワーク効果」「間接ネットワーク効果」というミクロ経済学からのアプローチを取り上げ、これが情報通信技術の発展に伴いどのような影響を受けるのかについて考察する。
そもそも、このようなプラットフォームビジネスはIT産業に限らず従来から存在した。電気・ガス・水道などの公益事業は、送電線網やガス供給網という「プラットフォーム」を形成し、顧客に電気やガスという商品を供給する業態であるとも捉えることができる。こうした公益事業は発電所や送電網等の形成に巨額の初期投資が必要となり、これを参入障壁とした自然独占が発生する。こうした「規模の経済」による独占状態の下では、独占事業者が利益最大化を図るために、限界収入が限界費用と一致する点まで供給量を絞り込み、価格を上昇させる(第Ⅰ-3-2-5図)。
第Ⅰ-3-2-5図 独占状態における需要供給曲線
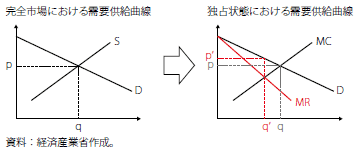
固定電話やファックス、ワープロソフトなどは、規模の経済とは異なる力学が働く。すなわちプラットフォームに所属する顧客数が増加することにより、顧客一人一人の便益も向上する場合、ある閾値を超えると爆発的に普及が進み、独占が生じる。これを「直接ネットワーク効果」といい、例えばワープロソフトを購入するに際しては、自分が作成したものを他人に読んでもらうことの可否が重要な決定要素となることから、結果として特定の商品に顧客が集中する傾向にあると言える。こうした「直接ネットワーク効果」の下では、顧客の効用が増えることから需要曲線・限界収入曲線が右方シフトし、元の均衡状態(独占状態)から価格が上昇するとともに、供給量も増加する(第Ⅰ- 3-2-6図)。
第Ⅰ-3-2-6図 直接ネットワーク効果の下における需要供給曲線
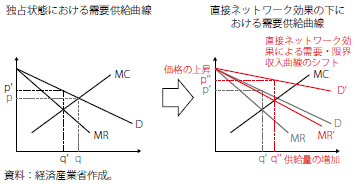
クレジットカードに対する消費者・小売店の関係に見られるように、顧客層が異なる2市場間にて、一方の市場における顧客層増加により他市場の顧客の便益が向上する場合、プラットフォームの提供者は一方の市場の価格を下げて独占を図るとともに、市場支配力を以て他市場の顧客に費用転嫁することが可能となる。これを「間接ネットワーク効果」といい、こうした特徴を持つ市場を「両面性市場」という。例えば、クレジットカードの利用者(すなわち消費者)は、より多くの小売店で利用できるクレジットカードを選択する力学が働く一方、店舗側としても、より多くの消費者が利用しているクレジットカードの決済システムを導入する力学が働く。
「間接ネットワーク効果」の下では、一方の市場(市場A)における戦略的割引と顧客数の増加を通じてもう一方の市場(市場B)における顧客の効用が増加し、需要曲線・限界収入曲線が右方シフトする。その結果、元の独占状態から価格が上昇するとともに、供給量は増加する。また、市場Aにおける割引は、市場Bの顧客に転嫁できる範囲内であればいくらでも可能となる(第Ⅰ-3-2-7図、第Ⅰ-3-2-8表、第Ⅰ-3-2-9図)。
第Ⅰ-3-2-7図 間接ネットワーク効果の下における需要供給曲線
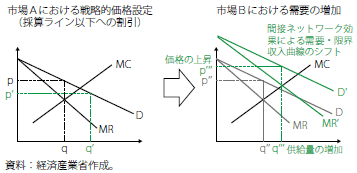
第Ⅰ-3-2-8表 プラットフォームビジネスを支えるミクロ経済学背景
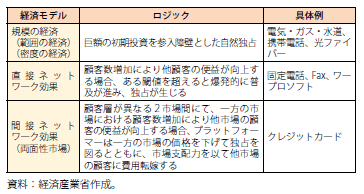
第Ⅰ-3-2-9図 「直接ネットワーク効果」「間接ネットワーク効果」の概念図
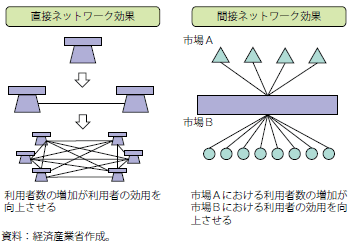
情報通信技術の発展は、限界費用の引下げを通じてプラットフォームビジネスをより強力に進める要因となる。「規模の経済」に関しては、ITシステムは電気・ガス・水道などのハードインフラと比較して複製のためのコストが低く、海外展開等を前提とした汎用システムは価格競争力を持つことになる。すなわち限界費用曲線のシフトを通じて供給量が増加するとともに、独占価格も低下する。前項で取り上げたように、エストニアや韓国などでは政府システムの汎用性を高め、プラットフォームとして海外展開する動きも生まれている(第Ⅰ-3-2-10図)。
第Ⅰ-3-2-10図 独占状態におけるIT化の影響
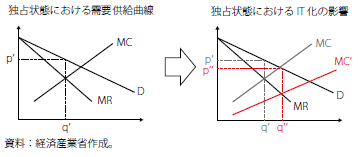
「直接ネットワーク効果」を背景としたプラットフォームがIT化すると、「規模の経済」の場合と同様、限界費用曲線のシフトを通じ供給量が増加するとともに、独占価格も低下する。ただし、顧客獲得のための限界費用は低くなるものの、NPO等により運営される場合を除き、顧客自身が一定の費用を負担する必要があるため、市場規模には限界があるケースが多いと考えられる(第Ⅰ-3-2-11図)。
第Ⅰ-3-2-11図 直接ネットワーク効果の下におけるIT化の影響
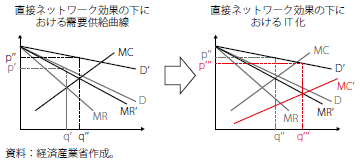
また、IoT、ビッグデータ、人工知能等の急速な技術革新により、データの蓄積自体がサービスの品質向上に貢献し、価値を持つようになると、「直接ネットワーク効果」が発生し、需要・限界収入曲線をシフトさせ、価格及び供給量を増加させる(第Ⅰ-3-2-12図)。
第Ⅰ-3-2-12図 データ蓄積を軸としたAI分野での直接ネットワーク効果の下における需要供給曲線
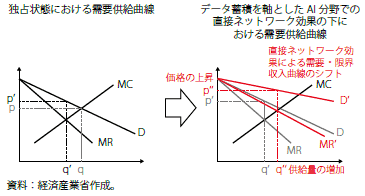
この場合、テクノロジーを軸とした企業間連携により、バリューチェーンの垂直・水平方向に事業領域を拡大した業種横断的なプラットフォームが形成される場合がある。こうしたプラットフォームの創出は、テクノロジー主導で進む場合と産業界主導で進む場合があり得る。テクノロジー主導型においては、人工知能などの高度な技術を有する企業が、自社の技術を活かし、異業種への参入を通じてプラットフォームを形成することから、革新的な技術・企業の育成・誘致、規制緩和を通じた参入障壁の緩和が政策課題となると言える。一方、産業界主導型においては、既に浸透している自社の製品や施設、サービスなどをインフラとして活用することで、自らプラットフォームを形成することから、企業の意識変革や高度な技術を有する企業とのマッチング、標準化等が政策課題となり得ると考えられる。いずれの類型の場合でも、全技術、製造・サービス工程を自社内に抱えるのではなく、オープンイノベーションを活用し、外部技術・リソースを積極的に取り入れることが重要となると考えられる(第Ⅰ- 3-2-13図~16図)。
第Ⅰ-3-2-13図 業種横断的なプラットフォーム形成
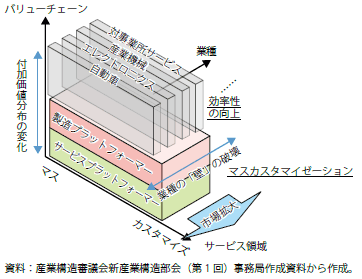
第Ⅰ-3-2-14図 競争優位を維持・強化する好循環のビジネスモデル
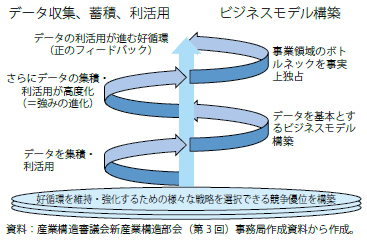
第Ⅰ-3-2-15表 IT化による限界費用を引き下げるプラットフォーム例
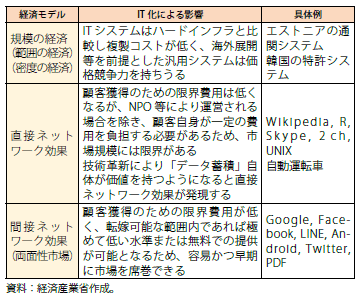
第Ⅰ-3-2-16図 業種横断型プラットフォーム創出のモデル
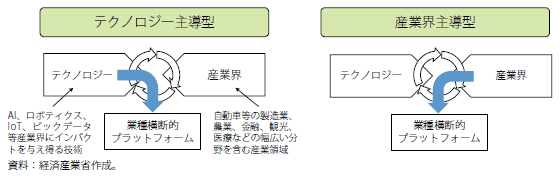
最後に「間接ネットワーク効果」を背景としたプラットフォームがIT化すると、一方の市場においてより低価格の価格設定が容易となり、顧客数を大幅に増やすことが可能となる。その結果、もう一方の市場の需要・限界収入曲線を更にシフトさせることにより、価格が上昇するとともに、供給量が増加する(第Ⅰ-3-2-17図)。
第Ⅰ-3-2-17図 間接ネットワーク効果の下におけるIT化の影響
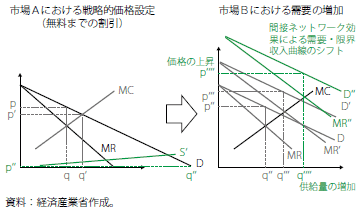
こうした効果は、検索エンジン、ネットワーキング、決済などの分野における普及を促すことに加え、需給調整コストを下げることにより、いわゆるシェアリングエコノミー141の基盤を形成することにも貢献している。
また、IT分野では、既存のプラットフォームの上に新しいプラットフォームが重層的に形成されており、今後とも技術・サービスの発展とともにプラットフォームが増え続ける可能性がある。その際、仮にある階層(例えばOS)において支配的なプラットフォームが存在している場合においても、新たな階層(例えば検索エンジン)が追加され、異なるプラットフォームが形成される場合は、元の階層においてプラットフォームの支配力が低下し、コモディティ化が進む可能性も指摘されている142。その程度は企業戦略や元々のプラットフォーム製品の支配力の強固さにも左右されるであろうが、今後とも、階層間でプラットフォームがダイナミックに力関係を変化させていくことは十分に予想できる。
このように、プラットフォームビジネスのIT化は従来のビジネスモデルを大きく変革する可能性があり、これに対応して、国際的なルール形成にも影響を与えることが考えられる。次項では、デジタル時代の技術進展に対応すべく新たな動きを見せる国際的なルール形成についての議論とその課題を見ていく。
140 プラットフォームビジネスの一形態であるMulti-Sided Platforms (MSP)の定義に関してはHagiu, Andrei and Wright, Julian (2015)に詳しい。本論文はMSPを「2以上の異なる立場の者による直接的な交流を可能にする」とともに「それぞれの立場の者が当該プラットフォームに所属している」状態であると定義している。
141 限界費用の低下とシェアリングエコノミーの普及が経済に及ぼす影響については、Rifkin, Jeremy (2014)などにおいて考察されている。
142 IT分野におけるプラットフォーム間のダイナミズムについては、加藤(2016)に詳しい。
3.ビッグデータ時代に対応する国際的なルール形成
近年のグローバルサプライチェーンの拡大、サービス経済化、インターネットビジネスやIoTの進展等は、クラウド技術の発展とモバイルデバイスの普及とあいまって、国境を越えるデータ量を増大させている。こうしたインターネット等を介した国境を越えるデータは、人々の日常生活、海外展開する企業の諸活動、さらには、世界経済の成長に不可欠な基盤となっている。しかしながら、このような国境を越えるデータの利活用が拡大する一方で、個人情報保護制度やセキュリティ対策など、各国の国内規制や関連制度との重なりをどう整理すべきかという課題が複雑化しつつあり、デジタル時代の技術進展に基づく新たな環境を踏まえた情報通信分野における国際的なルールを形成する必要性が高まっている。
(1)WTOや経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)における議論
①WTO
多角的貿易体制の中核として、国際的な通商ルール形成を担うWTOでは、1990年代後半から、インターネットの広がりとともに電子商取引が進展し、貿易の新たな機会を創出しはじめたことを背景に、WTOとしてどのように対応すべきかが議論されはじめた。
1998年の第2回WTO閣僚会議において、「グローバルな電子商取引に関する宣言」が採択され、グローバルな電子商取引に関連する全ての貿易関連事項を検討する包括的な作業計画の策定とともに、電子的送信に対する関税不賦課の慣行の継続(いわゆる「関税不賦課のモラトリアム」)について合意された。
グローバルな電子商取引に関する宣言を受け、1998年9月に策定された「電子商取引に関する作業計画」では、電子商取引について、「電子的手段によるモノ及びサービスの製造、流通、マーケティング、販売、配信(“electronic commerce” is understood to mean the production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means.)」という定義を置いた上で、関連する論点について、サービス貿易理事会、物品理事会、TRIPS理事会、貿易と開発理事会で議論を行った上で、各理事会の議論を一般理事会で取りまとめることが決定された。
WTOで議論されてきた主要な論点は、①デジタル・コンテンツのWTO協定上の取り扱いと、②電子送信に対する関税賦課等である。
①は、音楽、動画、プログラム等、インターネットの普及以前は媒体に化体する形で「モノ」として取引されてきた商品を「デジタル・コンテンツ」としてオンラインで配信する際、適用される規律によって取扱いに差異が生じる可能性があるという論点である。すなわち、デジタル・コンテンツ売買の対価を、モノの購買料と捉えれば関税及び貿易に関する一般協定(GATT)、サービスの対価と捉えればサービスの貿易に関する一般協定(GATS)、知的財産の使用料と捉えれば知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)がそれぞれ適用されうるが、特に、デジタル・コンテンツに適用される協定がGATTかGATSかという点で、最恵国待遇(MFN)、内国民待遇(NT)等に関して違いが生まれることから争点となった。
この点、競争力の強いソフトウェア産業を有する米国は、デジタル・コンテンツについて、MFN・NT等が一般的に適用されるモノとして取り扱うべきという立場を主張し、文化的な保護を必要とする音響映像産業を有するEUは、NT等の留保が可能なサービスとしての規律で十分とし、デジタル・コンテンツの概念を認めないとの立場を主張した。なお、我が国は、自由な電子商取引を志向する立場から、WTOの基本原則(MFN、NT等)の適用の確保を主張してきた。
②は、デジタル・コンテンツがオンライン上で取引された場合の課税を考えた場合、これらの取引を徴税機関が捕捉することは物理的に非常に困難であるという問題である。また、電子送信行為を課税の対象とし、送信量(通信ログ等により算出)に基づき課税しようとしても、デジタル・コンテンツそのものの価値と送信量は必ずしも比例しないことから、実際のコンテンツの価値の評価とは無関係に課税されるという問題が生ずる。このように、電子送信に対する関税賦課については、技術的な問題もあることに加え、電子商取引の発展のために、自由な取引環境を確保する必要があるとの観点から、インターネット取引に関税を賦課すべきではないとの国際合意を形成すべきとの声が高まってきた結果、1998年の第2回WTO閣僚会議において関税不賦課のモラトリアムが合意されて以降、基本的には閣僚会議のたびにモラトリアムが延長され143、2015年の第10回WTO閣僚会議においても、2017年までの延長が合意されたところである。
このように、WTOにおける議論は、既存の協定の枠組みを中心とした検討にとどまっており、各論点における各国の懸隔も大きいため、現時点で大きな成果は得られていない状態である。
143 第 3 回 WTO 閣僚会議(1999年)、第 5 回WTO閣僚会議(2003年)がそれぞれ決裂し、その間に、モラトリアムの合意がない状態が数年存在していたが、第6回WTO閣僚会議(2005年)以降はモラトリアムの延長が継続されている。
②EPA/FTA
このようなWTOにおける議論の停滞を受け、電子商取引をめぐる規律は、豪シンガポールFTA(2003年発効)を皮切りに、二国間におけるEPA/FTAにおいて、物品貿易章やサービス章とは異なる独自の「電子商取引章」という形で発展していくこととなった。特に、WTOで結論の出ていないデジタル・コンテンツの分類論に対応する形で、米シンガポールFTA(2004年発効)において、「デジタル・プロダクトの無差別待遇」(最恵国待遇及び内国民待遇が対象)という規定が置かれている点が注目に値する。ここで、「デジタル・プロダクト」とは、「コンピュータ・プログラム、文章、動画、静止画、音声録音、そしてその他の製品で、デジタル符号化がなされているもの」と定義され、電子的送信によるものだけでなく、CDなどの記録媒体に固定されたものも含まれている。また、同FTAでは、「デジタル・プロダクトの関税不賦課」という規定において、電子的送信を介するデジタル・プロダクトを恒久的な関税不賦課の対象とした上で、記録媒体に固定された形で輸入されるデジタル・プロダクトの課税価額については、記録媒体だけでのコストもしくは価値によって決定され、記録媒体に記録されているデジタル・プロダクトのコストや価値には関係がないと定め、WTOにおける関税不賦課原則より一歩進んだ内容を定めている。
我が国も、日スイスEPA(2009年発効)以降、電子商取引章を新たに設定している。特に、デジタル・プロダクトの無差別待遇や、関税不賦課のモラトリアムの恒久化を中心とした規律群を追及してきたが、アジア太平洋地域で高いレベルの自由化を目指して立ち上げられたTPPの電子商取引章においては、我が国が締結済みのEPAの電子商取引章と比較しても、包括的かつ高いレベルの内容が達成されている。具体的には、デジタル・プロダクトの無差別待遇、関税不賦課のモラトリアムの恒久化以外に、以下の内容が規定されている。
①情報の電子的手段による国境を越える移転:事業の実施のために行われる場合には、情報(個人情報を含む)の電子的手段による国境を越える移転を許可する。
②コンピュータ関連設備の設置:自国の領域において事業を遂行するための条件として、当該領域においてコンピュータ関連設備を設置すること等を要求してはならない。
③ソース・コード:他の締約国の者が所有する大量販売用ソフトウェア又は当該ソフトウェアを含む製品の自国の領域における輸入、頒布、販売又は利用の条件として、当該ソフトウェアのソース・コードの移転又は当該ソース・コードへのアクセスを原則として要求してはならない。
なお、①及び②の義務に関しては、「締約国が公共政策の正当な目的を達成するため、これに適合しない措置を採用し、又は維持することを妨げない」ことが確認されている。
これらの規律が導入されることにより、インターネット技術を用いたコンピュータネットワークを介して行う電子商取引の安全性と信頼性が確保され、多額の投資を伴わずに海外の消費者や企業と直接取引をすることができる環境の整備等が期待されている。
(2)デジタル環境に適応した国際的ルールを検討する際の諸課題
①データ・ローカライゼーション
国境を超えた、様々な種類のデータの自由な流通は、世界的な財やサービスの広まりや、新たな付加価値の創出に不可欠であり、世界の経済成長における重要な礎となりつつある。
しかしながら、近年、新興国を中心に、国内で収集されたデータを国外へ移転することを禁じる「データ・ローカライゼーション」と呼ばれる動きが見られている。また、その一環として、企業が自国領域内で事業を実施する条件として、コンピュータ関連設備の設置を要求する動きも増えつつある(第Ⅰ-3-2-18表)144。当該要求の目的は、プライバシー保護、セキュリティ対策や自国の産業保護など様々ではあるが、特に、サーバ設置に見合わない市場規模の場合には事業上の制約となり、グローバルな企業活動が阻害されることになる。さらに、サーバの設置が分散されることにより、集中的な管理ができなくなり、かえってデータのセキュリティが脆弱になるといった懸念も浮上している。なお、こうしたデータ・ローカライゼーション等の影響のコストとして、中国は616~638億米ドル、インドは31億~145億米ドル、インドネシアは27~37億米ドルの厚生損失があるとの研究もあり145、今後、世界的な対応策について検討が必要と考えられる。
第Ⅰ-3-2-18表 データ・ローカライゼーションの事例
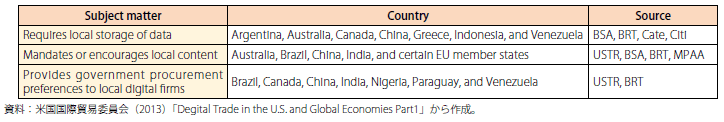
144 米国国際貿易委員会(2013)(https://www.usitc.gov/publications/332/pub4415.pdf![]() )。
)。
145 European Centre for International Political Economy, (2014), (http://www.ecipe.org/app/uploads/2014/12/OCC32014__1.pdf![]() ).
).
②個人情報保護
データの自由な流通と対立する懸念の一つとして、個人情報の流出、漏えい等の問題が挙げられ、世界各国において、個人情報保護に関する国内制度の整備や強化が進められている。我が国においても、改正個人情報保護法が2015年9月に成立し、個人情報の定義の明確化、個人情報保護委員会の新設、国境を越えた適用等の個人情報の取扱いのグローバル化等が新たに規定された。
諸外国では、欧州において、データの自由な流通の大前提として、個人データの保護が基本的権利として位置づけられ、厳格なデータ保護規制が導入されている点が特徴的である。1995年に制定されたEU個人データ保護指令では、第三国が十分なレベルの個人データの保護(adequate level of protection)を確保していると欧州委員会が認めた場合に限り、EU域内から当該第三国に対して個人データの転送を行うことが可能とされており、十分なレベルの保護の認定がない第三国へ転送を行う場合には一定の条件を満たす必要がある(詳細はコラム参照)。本指令については、その見直しが長らく議論されてきたところ、本指令に代わる新法令「個人データ保護規則」案について、2015年12月、欧州委員会、欧州理事会、欧州議会の三者で合意がなされ、今後、理事会及び本会議のそれぞれで採択されると法案が成立することになる。
他方、米国は、個人情報保護についての一般法はなく、政府部門、医療部門、信用情報、児童のプライバシー等、個別分野ごとに規制を行っており、自主規制を原則とした、欧州とは異なるスタンスを維持している。なお、米国が欧州委員会との間で2000年に締結したセーフハーバー協定は、米国企業による欧州からの個人情報の移転を容易にするための仕組みであったが、近年見直され、2016年2月に「EU-USプライバシーシールド」という新たな合意がなされており、今後の運用が注目される(詳細はコラム参照)。
過度の個人情報保護措置は、国境を超えたデータの円滑な流通を妨げる要因ともなり得るため、今後は、必要な保護措置と、流通・活用との両立に向けた国際的な議論をより深めていくことが求められる。なお、APECでは、データの保護と流通・活用を両立する観点からCBPR(越境個人情報保護規則)の認証制度を進めているが、採用している国はまだ少なく、欧州におけるデータ保護指令に基づく制度との相互運用等、さらなる利活用について検討の余地がある。
③セキュリティ対策
主に新興国の政府が、ソース・コード等の企業にとって重要なデータ等の開示や、国外へのデータの持ち出しを制限する理由の一つとして、国家安全保障をはじめとするセキュリティ保護が挙げられる。特に、ITの利活用拡大とともに、電力やガスなどの重要インフラへのサイバー攻撃や、安全保障上の機微技術、産業競争力上重要な技術や個人情報を保有する企業の営業秘密情報窃取への対策が、各国にとっての重要な政策課題となっているところ、真に必要な対策と、単なる隠れ蓑としたデータ・ローカライゼーション等の過剰な措置とのバランスについて、国際的な議論が必要と考えられる。
上記にみるように、国境を越えたデータの自由な流通の確保は、様々な国内政策と重なり合い、論点が複雑化してきているが、個人情報保護やセキュリティ対策の名の下に、データの自由な流通が過度に制限されることが懸念されている。むしろ、こうした政策との適切なバランス、すなわち両立する国際ルールを策定することは、データ利活用の安定的な環境・基盤となると考えられる。
4.まとめ
情報通信技術を実装し、プラットフォームを基盤とするエコシステムが実際に稼働している米国では、情報通信分野のみならず、自動運転、医療、金融、音楽などの他分野に積極的に入り込むなど、産業界の構造も変化し始め、シェアリングエコノミー等、実社会への影響も生じつつある。この動きは既にグローバルに拡大し始めており、世界の産業構造が急速に変化する可能性が考えられる。
競争優位を維持・強化するプラットフォームを構築していくためには、付加価値の新たな源泉となる「データ」を活用し、好循環のビジネスモデルを形成する必要がある。我が国は主にハード面において強みを有しているものの、ITをビジネスに活用する戦略的思考が欠如する等、ソフト面に課題があると指摘されている。
また、こうした新しい動きは、データ・ローカライゼーション、個人情報保護やセキュリティなど、従来の通商ルールの枠を超えた課題を惹起することから、このような分野におけるルールの形成に向けた国際的な取組が期待される。
