第2節 観光の現状と付加価値を高めていくための今後の課題
中国をはじめとする新興国の経済成長によって、世界的に海外旅行者が増加している。年々増加する観光客を国内に呼び込み、消費に繋げるために各国では様々な施策を行っており、例えばタイではプロモーション等の各種施策を行うことにより約10年間で観光収入が約5倍となった。他方で、我が国は足下では観光客数は急増しているものの、国際的な順位で見ると第22位(2014年)に留まっている(第Ⅱ-2-2-1表)。
第Ⅱ-2-2-1表 外国人旅行者受入数ランキング(2014年)
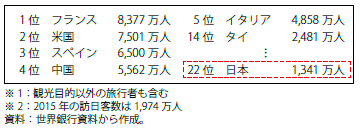
この節では、訪日観光の現状と課題について説明した上で、観光客数が世界で最も多いフランス、アジアの中で観光収入が中国に次いで高いタイの観光施策と比較することで、観光産業に経済効果を波及させるための施策の方向性について記述する。
1.観光の世界的動向と我が国の現状
(1)世界的な観光客数の増加
新興国の経済成長などにより、世界全体の観光客数は毎年5,000万人弱ほど増加しており、2015年には11億8千万人を突破した(第Ⅱ-2-2-2図)。また、我が国に関してもタイ、マレーシア及びインドネシアなどに対するビザの緩和及び、近年、為替が円安方向に動いたことなどの影響によって2015年の年間訪日客数が1,974万人になっており、2005年の673万人と比較して3倍近い観光客数となっている。伸び率に関しても、2005年付近では前年比約10%の伸びであったが、足下では同47%増となっている。中でも、アジア諸国からの伸びが大きく、中国に関しては過去最高の伸び(同107%)を記録している。他の国に目を向けても、観光客数と観光収入が増加しており、特に観光収入が世界一である米国は2003年(1,015億ドル)から2013年(2,148億ドル)の10年間で観光収入が2倍近くになっている。また、タイは10年間で観光収入が約5倍となっている。フランスに関しても年間観光客数は自国民数以上となっており(第Ⅱ-2-2-3図)、各国において観光は重要な産業の一つとなっている。
第Ⅱ-2-2-2図 世界全体の観光客数推移
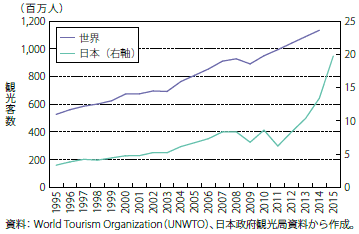
第Ⅱ-2-2-3図 各国の観光客数と観光収入推移(2004年~2013年)
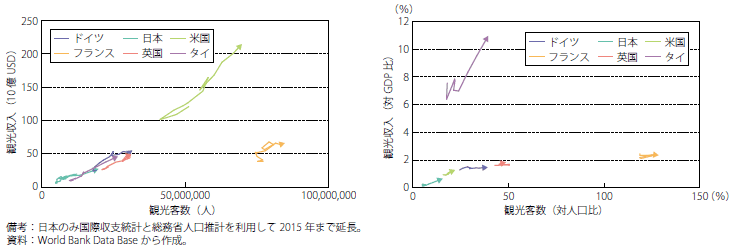
(2)我が国旅行収支の現状
我が国は2003年頃までは、出国者数に対して入国者数が大幅に少なかったため数十年に渡り、旅行収支は赤字となっていた。しかし、近年になって出国者数は横ばいであるのに対して、入国者数が大幅に増加しており(第Ⅱ-2-2-4図)、その影響によって2015年には旅行受取額が旅行支払額を上回り、53年ぶりに旅行収支黒字となった(第Ⅱ-2-2-5図)。
第Ⅱ-2-2-4図 我が国の入国者数、出国者数の推移
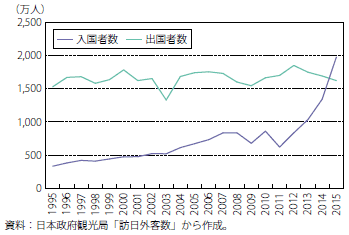
第Ⅱ-2-2-5図 我が国の旅行収支(対GDP比)推移
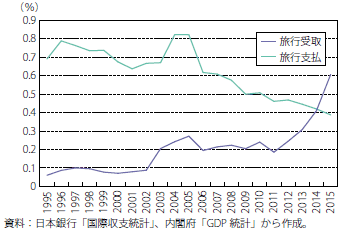
他方で、我が国の旅行支払額は年々低下しており、海外旅行における消費額が縮小傾向にあることを示している。出国者数についても概ね横ばいとなっており、約20年前の1995年と同程度の人数に留まっている。
旅行収支の推移を地域別で見ると、中国と中国を除くアジアにおいて2013年に入ってから急上昇していることが分かる(第Ⅱ-2-2-6図)。両方の地域において、旅行受取が急上昇しているのと同時に旅行支払についても下がってきていることが分かる。欧米については、受取額はほぼ横ばいとなっているが、支払額が少なくなっているため、足下の収支は黒字方向に進んでいる(第Ⅱ-2-2-7図)。他方で、支払額が下がっているということは我が国から欧米諸国へ行く観光客が減っていることを意味しており、人材交流の観点からも支払額についても今後は伸ばしていくことは重要である。
第Ⅱ-2-2-6図 地域別旅行収支(対GDP比)の推移
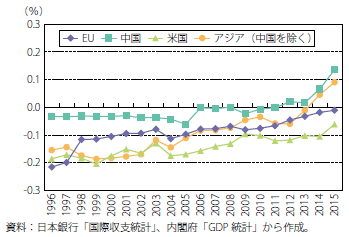
第Ⅱ-2-2-7図 地域別旅行受取・支払(対GDP比)推移
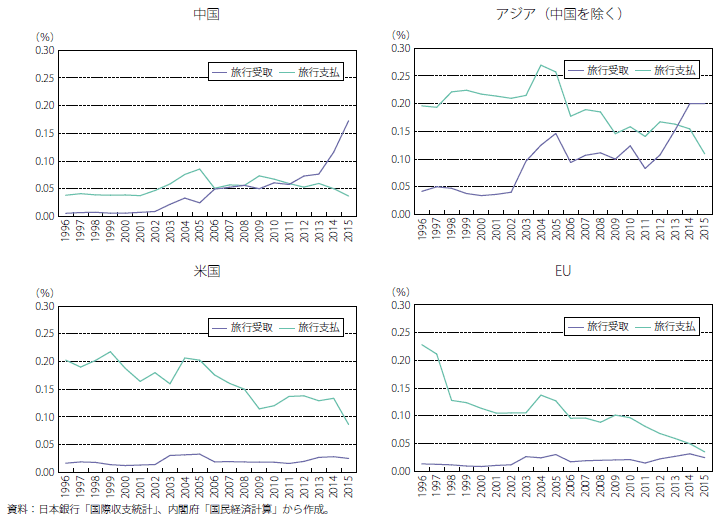
2.観光客数増加を地域産業へ波及させるための取組
(1)フランスにおける観光の裾野拡大のための工夫
観光客数を増加させるのみならず、その観光客による消費を地域産業へと波及させることが重要である。この項目では観光の地域産業への波及の誘導に取り組んでいるフランスの事例を見た上で、我が国への示唆について考える。
フランスは観光に関する様々な分析やプロモーションなどを行っているが、ここではその成功要因の一つである体験型観光について着目する。フランスは各地方において各種の体験型観光が行われており(第Ⅱ- 2-2-8図)、各地域がそれぞれの特産品を活用して観光客のリピーター化を図っている。
第Ⅱ-2-2-8図 フランスにおける体験型観光の事例
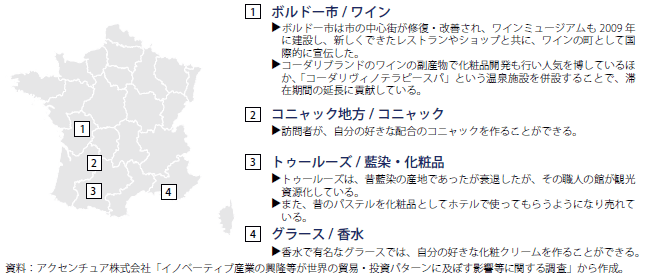
ボジョレーヌーヴォーで有名なボージョレー地方では、「毎年11月の第3木曜日午前0時に解禁になる」というストーリーとともにワインを売り出すことによって消費者の関心を喚起し、観光客を呼び込むとともに、一度来た観光客を体験型観光によってリピーターに繋げる施策を行っている。実際にボージョレーワイン解禁のタイミングで毎年行われる「サルマンテル祭」では、世界各国からボージョレーワインの愛好家が集まり、人で賑わうイベントとなっている。そのほか、フランス政府はワインテイスティングやワインの収穫体験などが行えるワインセラーに対してワインツーリズムの認証を行っており、ボージョレーでは200件近いワインセラーがこの認証を受けている。このような海外旅行者へのPRの影響もあり、ボジョレーヌーヴォーは出荷量の約45%が海外へ輸出されている(第Ⅱ-2-2-9図)。体験型観光以外の取組で言えば、高級ワインの産地であるボルドーでは観光客の呼び込みのために、市の中心街の修繕・改善を行い、2009年に元ワイン貯蔵庫を改造して作った「ワインとネゴシアン博物館」を開設するなどのインバウンド対応を行った結果、ボルドーのあるGironde県における観光客数は2009年以降増加傾向にある(第Ⅱ-2-2-10図)。またフランスのリヨンでは、観光と対内直接投資の関連性に着目して、「ONLY LYON」という組織を立ち上げ、観光客、対内直接投資、留学生誘致を目指して、一元的なプロモーションを推進している。3分野で共通するターゲット都市をキャンペーンの対象としており、キャンペーン、プレスリレーション、アンバサダー制度の推進に取り組んでいる。2014年の活動では58.5百万ページビューを獲得するなど、高い注目を集めている。また、ONLY LYON設立時の2008年と比較して2014年には対内直接投資件数16%増、外国人観光客15%増を達成した(第Ⅱ-2-2-11図)。
第Ⅱ-2-2-9図 ボジョレーヌーヴォーの国別出荷量
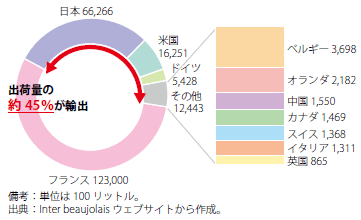
第Ⅱ-2-2-10図 Gironde県の外国人観光客数
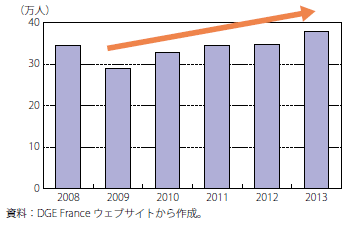
第Ⅱ-2-2-11図 ONLY LYONの取組と成果
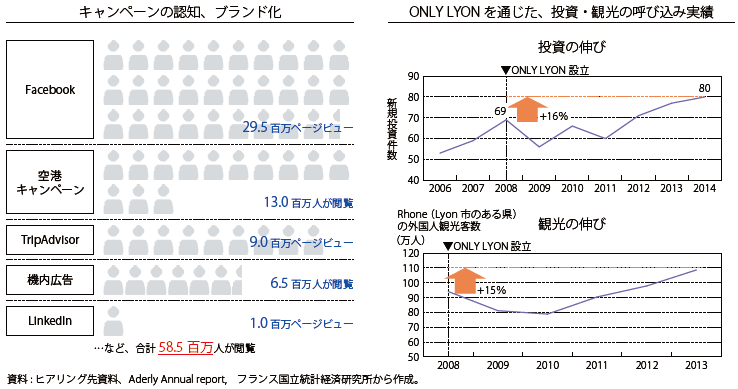
このように我が国に関しても各地域で体験型観光等に取り組むことによって、地域経済への波及へと繋げることができる可能性がある。
(2)国・地域として取り組むべき方向性
観光客数の増加は、観光関連産業に限らず、それ以外の産業についても対内直接投資を増やすことが報告されており59、我が国の対内直接投資を増加させるためにも今後は観光客数を増やすだけでなく、観光と対内直接投資の呼び込みに関して連携を取ることが重要である。例えば、フランスでは先述したようにONLY LYONのように対内直接投資と観光などを同一組織で行うことによって相乗効果を生む出す工夫を行っている。また、観光は対内直接投資だけでなく、地域特産品輸出にも相関性があることも報告されている60。他方で、その相関性の度合いはそれぞれの国が行う施策などによって変わってくる。沖縄県などでは観光と物産品のプロモーションを連動して行っているが、そのような取組は一部の地域に留まっている状況であるため、今後はこのような動きを増やしてくことが重要である。
59 Akinori T.(2016)より。
60 François V.(2011)より。
3.付加価値の高い観光産業の創造
欧州などの海外と比較した場合に日本の主要文化財は、入場料などが低い傾向にあり(第Ⅱ-2-2-12図)、付加価値の高いサービスを行えていないとの指摘がある。そのため、わかりやすい解説の充実・多言語化や、宿泊施設やユニークベニュー61等への観光活用の促進等により、観光コンテンツとしての質を向上させ、更なる観光客の呼び込みを行うことが必要となっている。また、訪日観光客は訪日旅行の前後で、観光客の期待がショッピング等から花見・スキー・温泉・文化体験等にシフトする傾向があり(第Ⅱ-2-2-13図)、このような需要に対する受け皿を作る意味でも付加価値の高い体験型観光の充実は急務である。それに加えて、富裕層が滞在するような高級宿泊施設やリゾート地が少ないため、このような施設の整備も重要となっている。
第Ⅱ-2-2-12図 日欧の主要文化財の入場料各国比較
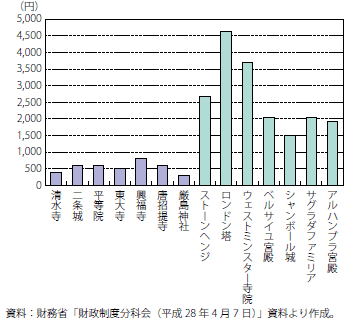
第Ⅱ-2-2-13図 訪日観光客による訪日前後の期待の変化と訪問回数別割合
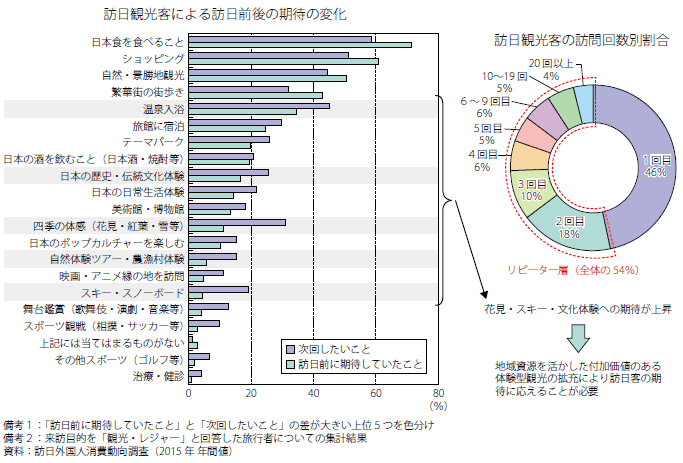
61 歴史的建造物や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場
4.訪日観光の課題と政府としての取組
(1)各国からの観光客に関する分析
我が国は足下では過去最高の伸び率で観光客数が増加しているが、その多くがアジア諸国から来ている観光客であり、2015年では東アジア及び東南アジアで8割以上を占めている。また、これらの国からの観光客消費額は買い物代が大きな割合を占めており、訪日客数が最も多い中国人の観光消費額は57.1%が買物代である(第Ⅱ-2-2-14図、第Ⅱ-2-2-15図)。このような、いわゆる「爆買い」は我が国にとって大きな収入となっているが、円安方向への動きなどにも影響を受けているため、今後の為替レート次第で変動する可能性もある(第Ⅱ-2-2-16図)。もう一つの特徴としては、欧米諸国からの観光客が少ないことが挙げられる。欧米諸国からの観光客は消費単価と宿泊日数が高い傾向がある(第Ⅱ-2-2-17図)が、例えば、我が国はタイや中国といった他のアジア諸国と比較して、英国からの観光客数は相対的に少ない(第Ⅱ-2-2-18図)。
第Ⅱ-2-2-14図 訪日外国人観光客の出身国構成
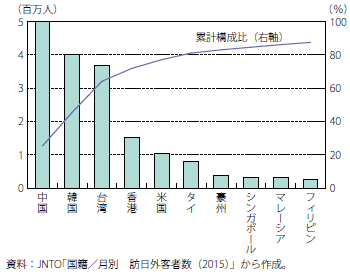
第Ⅱ-2-2-15図 中国人観光客の費用別消費単価
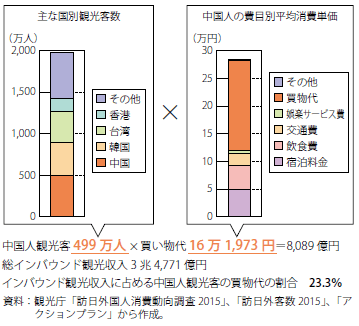
第Ⅱ-2-2-16図 足下の人民元/円の為替レート
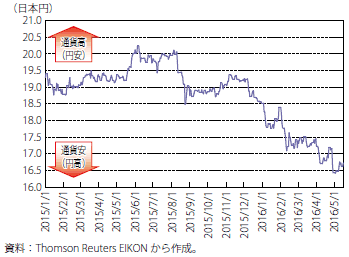
第Ⅱ-2-2-17図 訪日外国人の国別宿泊日数、消費単価
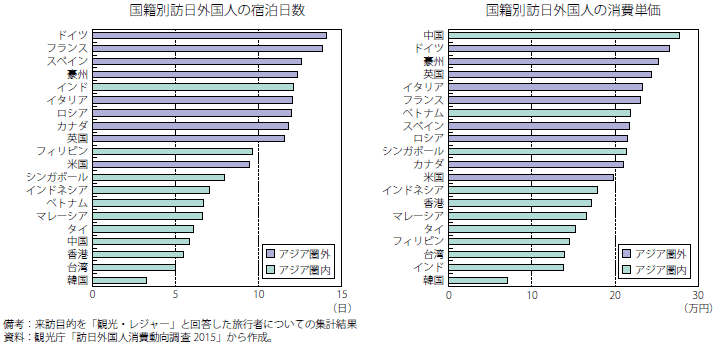
第Ⅱ-2-2-18図 アジア主要国における英国からの観光客数比較(2014年)
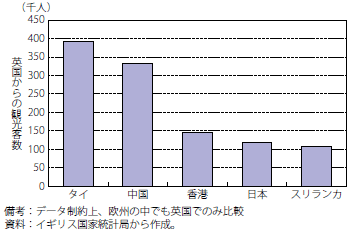
ここで各国別に、出国者数に占める我が国への観光目的の旅行者数の割合(以下、訪日選択度)と一人当たりの年間旅行回数(以下、海外旅行頻度)を見ていくことで、足下の訪日観光客数の増加が我が国を海外旅行先として選択する人が増加したことによるものか、一人当たりの旅行回数が増加したことによるものかを分析する。まず、訪日観光客数が最大の国である中国を見ていくと、中国人の訪日選択度は横ばいであり、海外旅行頻度のみ増加していることが分かる(第Ⅱ-2-2-19図)。すなわち、中国人観光客数増加は中国の経済的な豊かさが向上したことなどにより、海外旅行をする中国人が増えていることが主な要因であるといえる。米国、シンガポール、インドネシアなどの国でも同様に訪日選択度は横ばいとなっている。それに対し、タイ、香港、台湾については訪日選択度が上昇しており、これらの国では為替による影響や我が国の観光地としての魅力が向上したこと等により、観光客数が増加していることが示唆される。
第Ⅱ-2-2-19図 訪日観光客の訪日選択度と海外旅行頻度
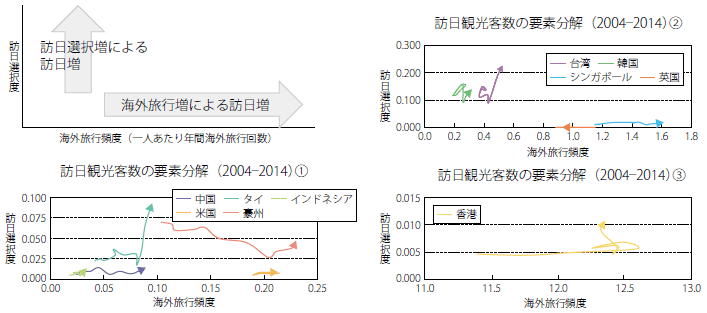
- Excel形式のファイル(訪日観光客数の要素分解(2004―2014)①)はこちら

- Excel形式のファイル(訪日観光客数の要素分解(2004―2014)②)はこちら

- Excel形式のファイル(訪日観光客数の要素分解(2004―2014)③)はこちら

一般的にどの国でも近隣諸国からの来訪者が多くなっているため、我が国においても、中国をはじめとするアジア諸国からの訪日旅行者が占める割合が高くなっている。加えて、こうした近隣アジア諸国の経済的豊かさの向上によって海外旅行の頻度が上がっていることが主な要因であるため、我が国の観光地としての魅力等をさらに向上させ、訪日選択度を向上させることによって更なる観光客の増加が見込めることが考えられる(第Ⅱ-2-2-20図)。
第Ⅱ-2-2-20図 各国の訪日選択度(2014年)
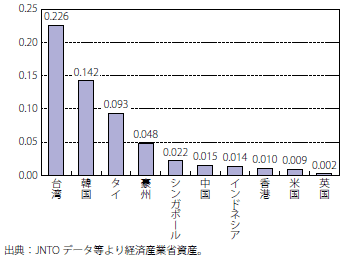
(2)訪日観光が抱える課題
訪日選択度を向上させる上での我が国観光産業の課題について考えていく。まず、我が国観光が抱える大きな課題の一つとして、欧州観光客からの観光客数が低いことが挙げられる。同じアジア地域であるタイと比較して約1/6となっている(第Ⅱ-2-2-21図)。タイは先進国からの観光客を呼び込むために、MICE誘致を対象とした金銭的支援や海外要人向けの警備員配置、空港送迎などの環境整備を行っており、これらの影響も大きいことが考えられる。
第Ⅱ-2-2-21図 各地域から日本、タイへ行く観光客の割合(2014年)
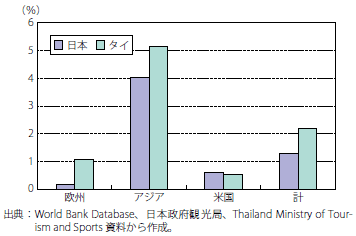
観光ビジョンにおいて、訪日数に関する目標だけでなくリピーター数に関する目標を設定している通り、長期的にはリピーター数を増加させていくことも必要である。近年、中国等のアジア諸国を中心に訪日客数が大幅に増加しており、その多くが新規に日本を訪れた方々であることを反映して、近隣国では香港、台湾、韓国、シンガポール・タイ以外の国は再訪率が約5割以下に留まっている(第Ⅱ-2-2-22図)ものの、我が国は長期的には更にリピーター数及び観光客数増加の余地があるといえる。また、二度目以降に我が国に来る観光客は地方へ訪問する意欲をもつ割合が高くなる(第Ⅱ-2-2-23図)ため、我が国へ再訪した観光客を上手く地方へ誘客していくことが重要となる。
第Ⅱ-2-2-22図 訪日外国人旅行者のリピート率(観光・レジャー目的)(2015年)
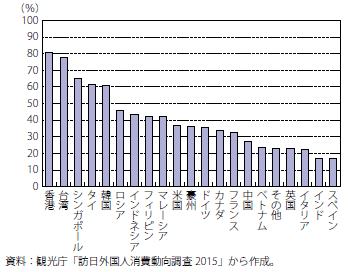
第Ⅱ-2-2-23図 東京と地方との訪問意欲推移
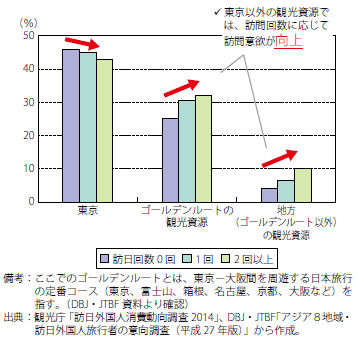
地方への誘客という観点でも、我が国は78%の観光客が上位約2割の県(8都道府県)に集中しており、地方への経済効果の波及が少ない(第Ⅱ-2-2-24図)。一方、フランスは、パリへの観光客が突出するものの、その他の地域にも観光客が分散している。観光客数上位20%への外国人観光客集中度をみると、フランスではRegion単位で見た場合61%となっている(第Ⅱ-2-2-25図)。フランスの場合は陸続きであるため、我が国と単純な比較できないが、地方への誘客は我が国が抱える課題の一つであるといえる。
第Ⅱ-2-2-24図 都道府県別外国人宿泊者延べ人数および上位の集中度
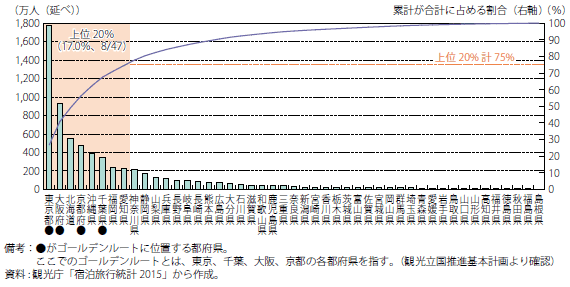
第Ⅱ-2-2-25図 州(Region)別外国人宿泊者延べ人数および上位への集中度
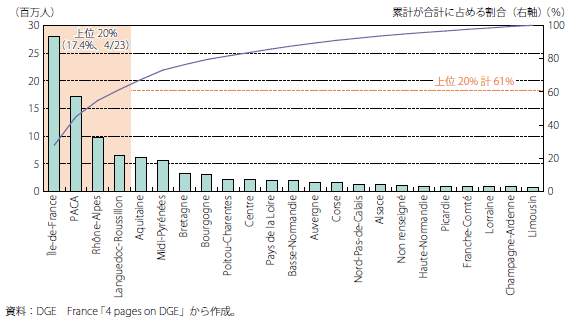
観光関連産業の中でも、ガイドサービスなどの消費額が低いことも課題である。演劇鑑賞などをはじめとする文化サービスの消費額はフランスと比較して我が国は約1/5となっており、文化への関心が高い観光客の来訪を消費に繋げられていない可能性が示唆される(第Ⅱ-2-2-26図)。諸外国では観光資源について数千円の鑑賞料金を課す代わりに、観光資源の質の保全やサービスの向上に取り組んでいるが、我が国では著名な寺院などの鑑賞にも料金が発生しない場合が多く、結果的に質の保全を行うための資金的余裕が無くなっている。我が国においても、観光資源の有料化を行うなど、観光客の満足度を向上させるような環境整備を行っていくことが必要である。
第Ⅱ-2-2-26図 日仏の観光消費構成の比較と訪日外国人の関心事項
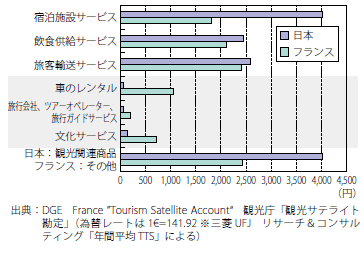
(3)課題に対する政府及び国内企業の取組
①政府の取組
訪日外国人旅行者数2,000万人の目標達成が視野に入ってきたことを踏まえ、次の時代の新たな目標の設定とそのために必要な対応の検討を行うため、昨年11月9日に「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」が設置された。有識者・関係府省庁等による精力的な議論を経て、本年3月30日に2020年に訪日外国人旅行者数4,000万及び同消費額8兆円などの新たな政府目標や、観光資源の充実、観光産業の競争力強化、旅行環境の整備を柱とする具体的取組がとりまとめられた(第Ⅱ-2-2-27図)。
第Ⅱ-2-2-27図 「明日の日本を支える観光ビジョン」の施策概要
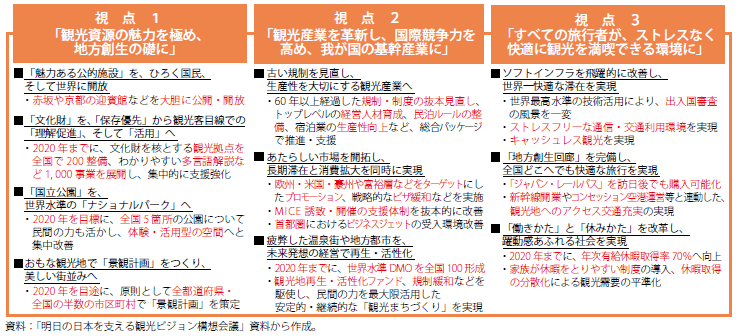
地域産業活性化のためには、訪日外国人による地域の伝統文化体験や工芸品輸出なども重要である。3月30日にとりまとめられた「明日の日本を支える観光ビジョン」においては、ビジット・ジャパン事業として、欧米豪の有力なオピニオンリーダー等や、富裕層向けの海外雑誌会社や旅行会社の社員を我が国に招聘し、我が国の伝統文化を体験してもらい、それを母国で発信してもらうプロモーション戦略を実施する等の施策が掲載されている。また、地域産品の輸出の側面では、外国人受入可能な伝統工芸品産地が100箇所以上になることを目指しており、今後は更なる受入環境整備が行われていく方針である。
②国内企業の取組
国内企業の取組について見てみると、足下では無料公衆無線LANや外国語のメニュー表示などの対応を行っている企業が多いが、長期的には海外人材の登用や海外向けの製品の開発などを試みたいという企業が多い(第Ⅱ-2-2-28図)。足下ではインバウンド対応を行える外国人人材がほとんどの企業において不足している(第Ⅱ-2-2-29図)。
第Ⅱ-2-2-28図 外国人旅行客をビジネスチャンスに取り込むための取組内容
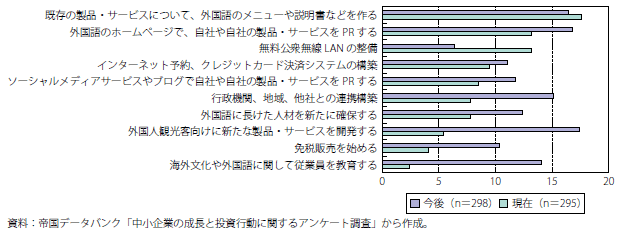
第Ⅱ-2-2-29図 インバウンド対応における人材の有無(n=1893)
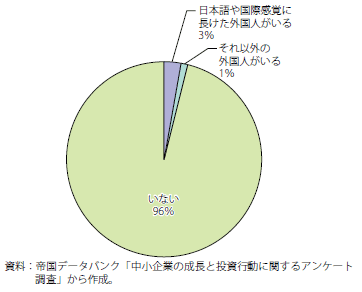
また、海外人材の活用のみならず、観光産業におけるトップレベルの経営人材から即戦力となる現場を支える人材を育成・強化することが重要であり、観光ビジョンにおいても、これら観光産業の担い手の育成や通訳案内士のサービス供給拡大措置を構築する方針が定められている。このような観光対応の人材は今後インバウンド対応に取り組んでいく企業においては重要な要素の一つとなることが考えられる。
(4)タイの観光客数増加への取組
タイは文化的遺産や観光用ビーチなどもあり、観光客にとって魅力的な資源を備えていたが、それに加えてプロモーションや受入環境整備を通じて、その資源を有効活用して観光客数を増加させるための取組を実施している(第Ⅱ-2-2-30図)。また、高級ホテルなども含めた富裕層用のリゾート地も整備もされている。GDP比における観光による収入(旅行サービス輸出)を見ると、タイでは観光が重要な産業の一つとなっていることが分かる(第Ⅱ-2-2-31図)。
第Ⅱ-2-2-30図 タイ政府が行っている観光に対する取組
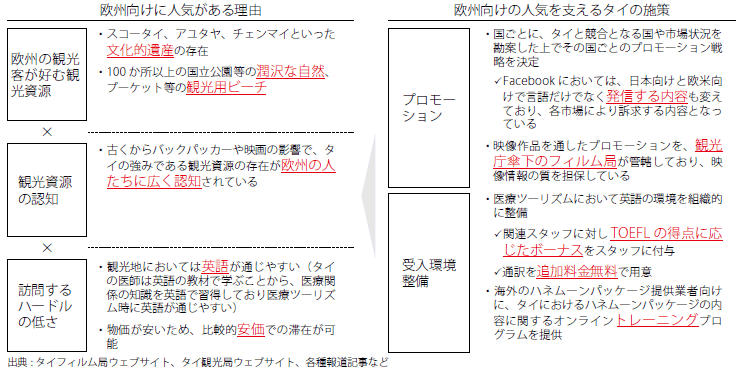
第Ⅱ-2-2-31図 旅行サービス輸出・対GDP比(2014年)
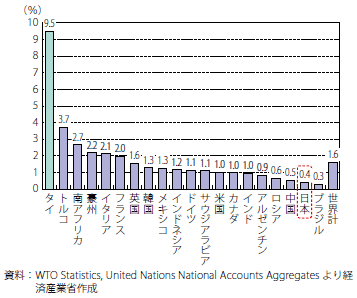
ここではタイの観光施策と観光産業の現状を見ることによって、我が国の観光施策の参考としたい。まず、タイは国ごとに、観光先として競合となりうる国や市場状況を勘案した上でプロモーション戦略を決定している。Facebookにおいては、日本向けと欧米向けで言語だけでなく発信する内容も変えており、各市場に訴求する内容となっている。そのほか宣伝などで使われる映像情報は、観光庁傘下のフィルム局が管轄しており、質を確保するための取込を行っている。
受入環境整備としては、英語に対応できる環境も整備している。例えば、医療ツーリズムに関して言えば、医師は英語の教材で学んでいるため英語が通じやすく、また関連スタッフに対しTOEFLの得点に応じたボーナスをスタッフに付与している。そのほか通訳を追加料金無料で用意しており、外国人が安心して医療を受けられる環境となっている。そのほかにも海外のハネムーンパッケージ提供業者向けに、タイにおけるハネムーンパッケージの内容に関するオンライントレーニングプログラムを提供している。
MICEに関しても、2004年に設立した政府専業公社TCEBを中心に、MICE関連の情報発信、インセンティブ提供を実施しており、その結果MICE観光収入を大きく伸ばした(第Ⅱ-2-2-32図)。約20億円の年間誘致予算(2012年)を設け、金銭的支援として市場ごとに支援メニューを設計している。例えば、日本市場向けに、ミーティング・インセンティブ目的でタイに3泊以上滞在する200人以上の団体に、助成金を支給する「ミーティング・ボーナス」制度を導入している。金銭面以外でも、空港からの送迎、海外要人向けの警備員配置、必要な企業・政府関係者との連絡仲介、イベント計画の補助、ビジネスマッチングのためのタイの産業地域訪問手配など、幅広く支援を実施している。
第Ⅱ-2-2-32図 タイのMICE観光収入の伸び、および内訳
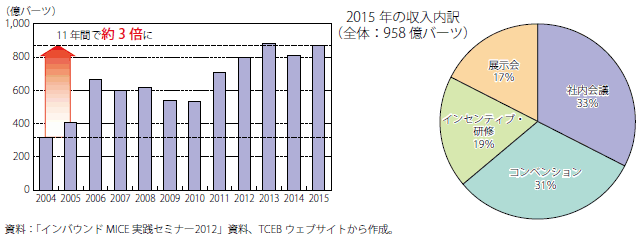
このような取組もあってタイは世界各国から観光客数を大幅に増加させている(第Ⅱ-2-2-33図)。また、タイは日本と比較して欧州からの観光客数が多い(第Ⅱ-2-2-34図)が、アジアへ来る欧州の観光客は距離が遠いこともあり、宿泊日数が長くなる傾向にある(第Ⅱ-2-2-35図)。そのため、タイは延べ宿泊日数の構成比を見ると、欧州の寄与が大きくなっている(第Ⅱ- 2-2-36図)。宿泊日数が長い観光客は観光における消費も高くなる傾向にあり、このような観光客を取り込めていることはタイの観光収入を向上させている一因であると言える。
第Ⅱ-2-2-33図 タイにおける各地域の外国人観光客変化(’07年-’15年)
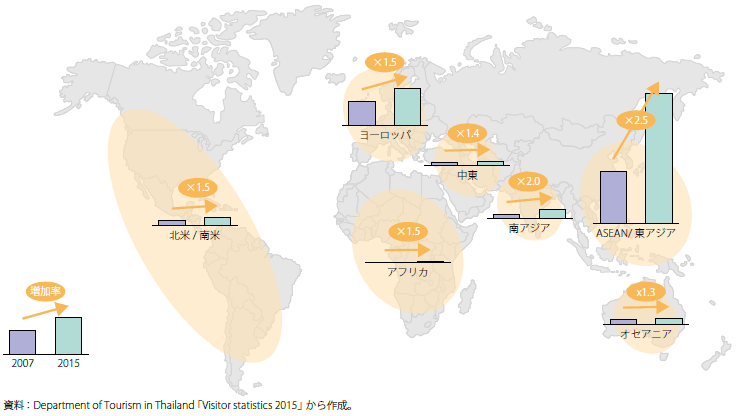
第Ⅱ-2-2-34図 タイと日本における国籍別訪問客数
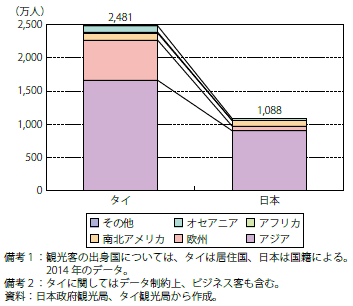
第Ⅱ-2-2-35図 訪タイ観光客の出身国別平均宿泊日数
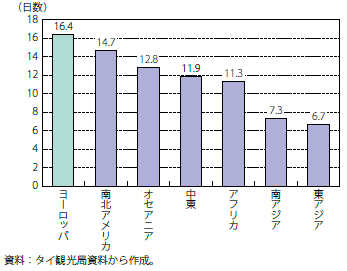
第Ⅱ-2-2-36図 訪タイ観光客数・延べ宿泊数に対する出身国割合(2014)
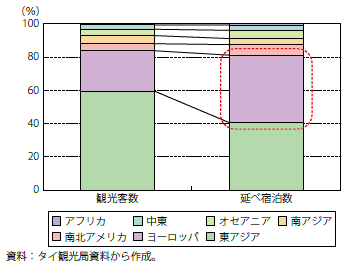
英国、米国及び中国に着目して、日本とタイで比較する(第Ⅱ-2-2-37図)。まず、英国と米国の観光客は日本とタイで比較すると一日当たりの消費金額は同程度であることが分かる。しかしながら、宿泊日数と人数が多いために総観光収入が日本と比較して大幅に高くなっている。特に英国からの観光客による観光収入は日本の7.5倍となっている。また、遠方からの観光客である欧米のみならず、中国についても長期滞在する傾向があり、これが総観光収入を高くしている要因の一つとなっている。このように観光客数だけでなく、長期滞在型の観光をしてもらうことが観光収入を向上させる上で重要な要素であると言える。
第Ⅱ-2-2-37図 訪タイ観光客の動向(2014年)(訪日観光客=1)
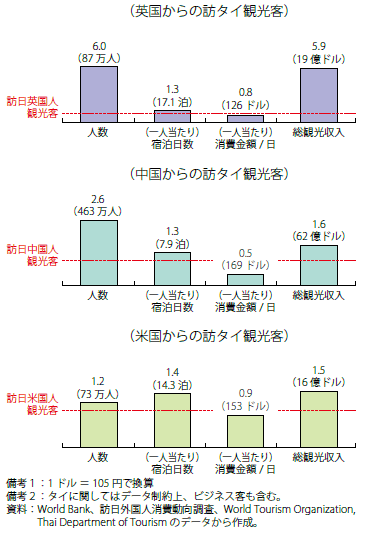
5.まとめ
我が国の観光客数は足下では急増しており、訪日客数は年間約2,000万人となっている。他方で、我が国の観光産業の裾野を広げ、かつ観光消費を持続的なものにするためにも、欧米などをはじめとするアジア以外の地域からの観光客を増やし、富裕層の消費を取り込むための受け皿を作っていくことも必要である。安倍内閣総理大臣を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」では、我が国が今後目指すべき新たなビジョンが取りまとめられた。観光ビジョンに盛り込まれた施策を着実に実施することで観光客数とその消費単価を伸ばしていくことが重要である。
また長期的には、外国人観光客に日本文化に関心を持ってもらい、リピーターを増やしていくことも必要となってくる。長期的には、別荘などの購入も視野に入れた長期滞在も増やしていくことによって、観光客消費の更なる向上を見込むことができる。
