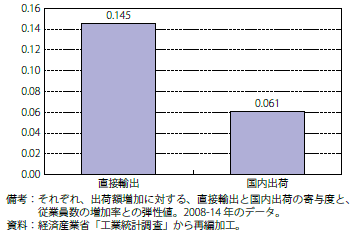第1節 我が国の地域輸出の現状と課題
1.我が国地域経済の現状と課題
地域経済の推移を確認すると、2000年代に世界経済の拡大に伴い経済が大きく拡大した地域は、関東、東海甲信、及び中国地域のみであった。世界経済危機後は、東海甲信と東北地域で顕著な伸びが見られるものの、他は緩やかな回復にとどまっている(第Ⅱ-3-1-1図)。
第Ⅱ-3-1-1図 地域別の県内総生産(名目)推移62
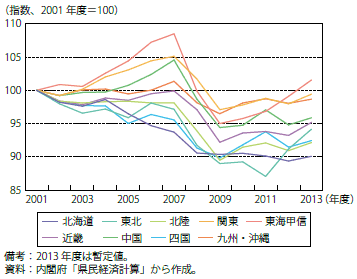
製造業の就業者数を見ると、2000年代に東海甲信地域をはじめとして多くの地域において大きく上昇した後、世界経済危機後に大きく落ち込み、その後は横ばい若しくは減少傾向で推移している(経済産業省「工業統計調査」ベース63)(第Ⅱ-3-1-2図)。
第Ⅱ-3-1-2図 地域別の従業者数推移(製造業)
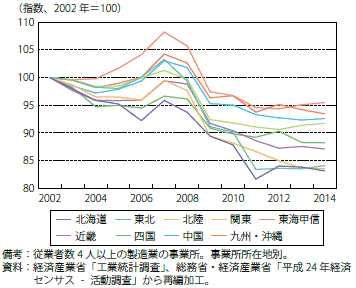
2002年と比較すると、就業者に占める製造業の比率は19%から16%に低下しており、特に世界経済危機後、我が国の雇用が非製造業にシフトしてきていることがうかがえる(第Ⅱ-3-1-3図)。
第Ⅱ-3-1-3図 製造業と非製造業における就業者数の変化
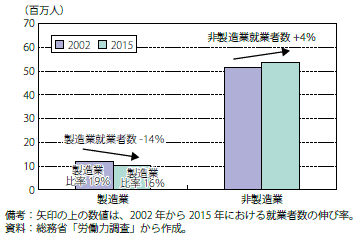
全産業ベースを見ると、製造業と比較して就業者数は緩やかに推移している(第Ⅱ-3-1-4図)が、若年人口は、地方をはじめとする全ての地域で減少傾向にストップがかかっていない(第Ⅱ-3-1-5図)。
第Ⅱ-3-1-4図 地域別の就業者数推移(全産業)
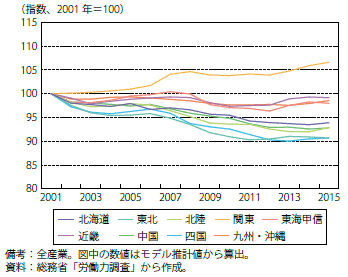
第Ⅱ-3-1-5図 地域別の若年人口推移
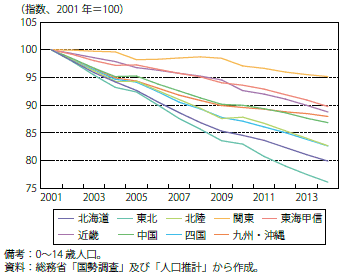
若年人口の減少が特に大きい地方では、今後外需を獲得する重要性が高まっていくと考えられるが、今、我が国の地方における輸出はどのような状況にあるのだろうか。以下では、我が国の地域別輸出の現状を確認していく64。
62 都道府県の地域区分は、特に断りのない限り、付表1に基づく。
63 工業統計調査に基づく製造業の従業員数の捕捉率は71%(総務省労働力調査に基づく製造業の就業者数に対する数値。2013年)。
64 本節では、経済産業省の「工業統計調査」及び「企業活動基本調査」を用い、製造業の直接輸出を確認する。両統計とも輸出が直接輸出に限定されるため、卸売商社等、他企業を経由する輸出は計上されない点に留意が必要である。
また、工業統計調査は事業所所在地別に数値が計上され、企業活動基本調査は本社所在地別に数値が計上される。前者は事業活動を実際に行っている地域に数値が計上される一方で、企業活動の全体は把握していない場合がある。後者は、事業活動の場所と本社所在地が異なる場合には、実際の事業活動を行っていない地域に数値が計上されてしまうものの、生産のみならず、研究開発や経営等も含めた企業活動全体を把握することができる。
両調査では対象も異なっており、前者が従業員数4人以上の事業所であるのに対して、後者の調査対象は、従業員数が50人以上、かつ資本金又は出資金3,000万円以上の企業に限定されるため、規模が小さい中小企業に関する数値は含まれない。
製造業の中小企業の定義について、本節では、企業活動基本調査に基づく分析においては、資本金3億円以下又は従業者数300人以下の企業とし、工業統計調査に基づく分析においては、資本金3億円以下の企業とした。大企業は、特に断りの無い限り、中小企業以外の企業とした。
2.我が国の地域輸出の現状
(1)概略
直接輸出の推移を地域別に確認すると、世界経済の拡大を背景に、2000年代には全体的に輸出が増加したが、2010年以降については、大きく拡大している地域がある一方で、輸出規模が大きい地域も含めて、全体的に伸びが弱く、一部に減少している地域も見られる(第Ⅱ-3-1-6図、第Ⅱ-3-1-7図)。
第Ⅱ-3-1-6図 地域別の直接輸出額(製造業)
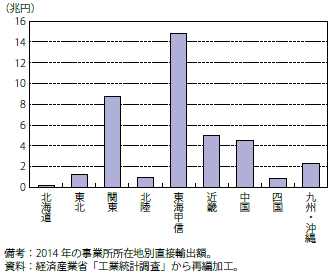
第Ⅱ-3-1-7図 地域別の直接輸出の伸び率の変化
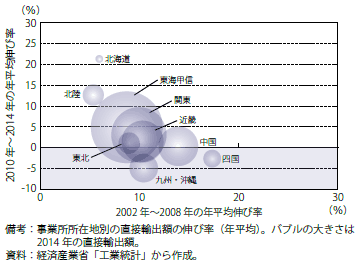
また我が国製造業に関して、業種別及び地域別に、全事業所に占める現に直接輸出を行っている事業所(以下「輸出事業所」という。)の割合をとったところ、その割合は2010年から2014年にかけて化学工業を除く全業種と全地域で上昇しており、輸出の裾野の広がりが起きたことが分かる。他方、輸出事業所の比率は業種間・地域間でばらつきが大きく、今後の裾野の広がりが期待される業種・地域も多い(第Ⅱ-3-1-8図、第Ⅱ-3-1-9図)。
第Ⅱ-3-1-8図 我が国製造業の輸出事業所比率推移(業種別)
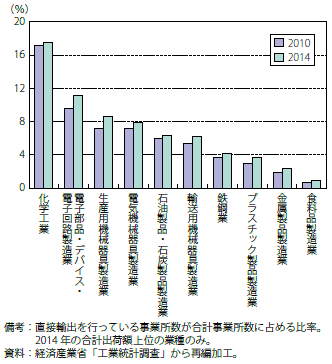
第Ⅱ-3-1-9図 我が国製造業の輸出事業所比率推移(地域別)
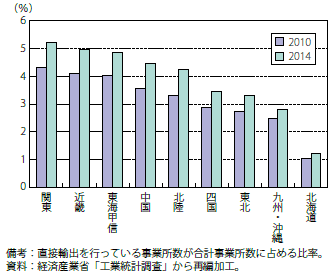
(2)地域の輸出依存度の現状と中小企業の動向
製造業の直接輸出依存度(対売上高比率)は、2000年代前半に比べて上昇している(第Ⅱ-3-1-10図)。
第Ⅱ-3-1-10図 輸出依存度の変化(製造業)
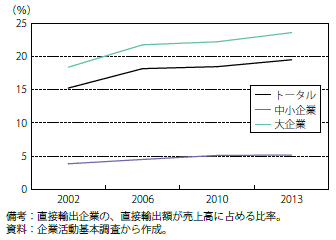
地域別に確認すると、2007・2008年をピークに伸びは鈍化しているが、足下で更に比率が上昇している地域も多い(第Ⅱ-3-1-11図)。
第Ⅱ-3-1-11図 我が国製造業の出荷額に占める輸出金額比率の推移(地域別)
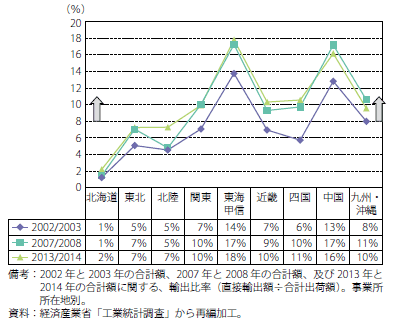
また、中小企業の輸出比率(対合計出荷額)は、水準では大企業を大きく下回っているが、2000年代前半と比べると多くの地域で上昇している(第Ⅱ-3-1-12図、第Ⅱ-3-1-13図))。
第Ⅱ-3-1-12図 企業規模別の製造業の輸出比率(2013/2014年)
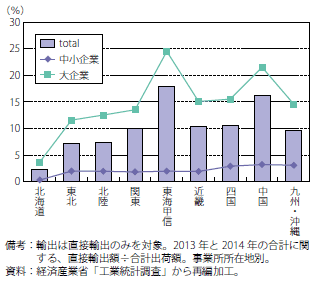
第Ⅱ-3-1-13図 製造業中小企業の輸出比率の変化(2002/03~2013/14年)
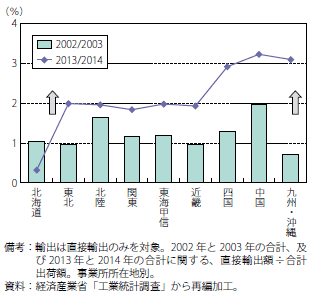
中小企業の輸出規模は大企業に比較して格段に小さいものの、直接輸出額の伸びは中小企業の売上高の伸びを大きく上回っており、さらには大企業の直接輸出額の伸びをも上回っている(第Ⅱ-3-1-14図、第Ⅱ-3-1-15図)。
第Ⅱ-3-1-14図 製造業中小企業の直接輸出と出荷額の伸び
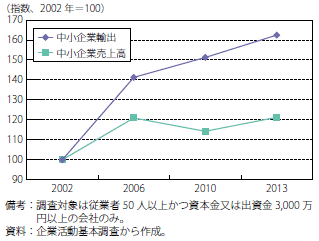
第Ⅱ-3-1-15図 製造業直接輸出の伸びに関する大企業と中小企業の比較
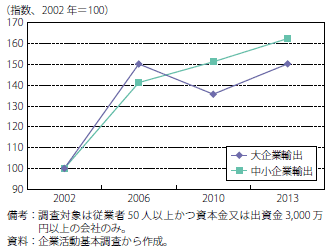
地域別に見ると、合計輸出額に占める中小企業比率は、東北と九州を中心に高まっている(第Ⅱ-3-1-16図)。
第Ⅱ-3-1-16図 製造業直接輸出に占める中小企業比率の変化
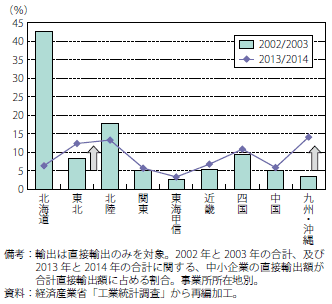
なお、大企業のうち資本金が100億円未満の企業を中堅企業として切り出すと、中堅企業・中小企業の輸出が地域の輸出をけん引している地域も見られる。2007年・2008年時点から2013年・2014年までの変化について見ると、北海道、北陸、近畿、九州・沖縄地域において、中堅・中小企業が輸出の伸びに対して寄与していることが確認できる(第Ⅱ-3-1-17図)。
第Ⅱ-3-1-17図 企業規模別の製造業輸出額増減への寄与度
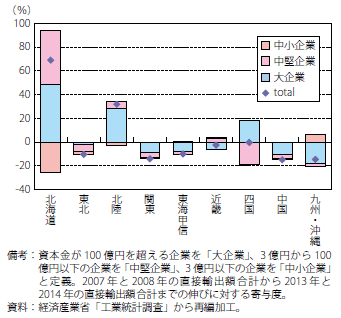
(3)輸出が増加した企業とその他企業の比較
我が国の多くの地域において、中小企業を含めて輸出比率が高まっていることを確認したが、輸出の増加は企業の業績に対して、どのような効果を有するのだろうか。
まず、輸出の増加と合計出荷額の増加の関係を確認する。2008年から2014年に輸出を実施した事業所の6割超が、直接輸出の増加額が国内向け出荷額の増加額を上回った(第Ⅱ-3-1-18図、第Ⅱ-3-1-19図)。
第Ⅱ-3-1-18図 直接輸出増加が国内出荷増加よりも大きい事業所の割合
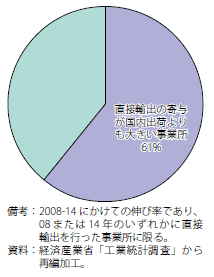
第Ⅱ-3-1-19図 直接輸出増加が国内出荷増加よりも大きい事業所の割合(業種別)
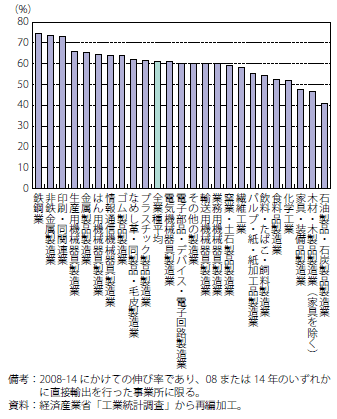
また、直接輸出の増加が合計売上高の増加に占める割合(寄与率)について地域別に確認すると、2010-2013年の数値は、ほぼ全ての地域において2002-2006年を上回っている65(第Ⅱ-3-1-20図)。出荷額を拡大するツールとしての輸出の重要性が、近年高まっていると言えよう。
第Ⅱ-3-1-20図 合計売上高の伸びに対する輸出の寄与率
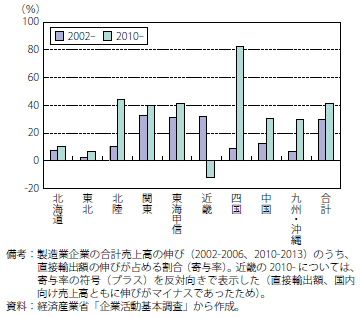
なお、輸出が伸びた企業群と非輸出企業群における給与総額伸び率に関する差について、期間を分けて比較すると、2006年までの期間では、非輸出企業の方が給与総額の伸び率が高い地域も見られたものの、2010年以降では、ほぼ全ての地域において輸出が伸びた企業の給与総額伸び率の差が大きい。また中でも九州と東北では、2006年までは、輸出が伸びた企業群と非輸出企業群における給与総額伸び率の差が小さかった(若しくはマイナスであった)にも関わらず、2010年以降の差が大きい(第Ⅱ-3-1-21図)。
第Ⅱ-3-1-21図 直接輸出が伸びた企業群と非輸出企業群における、給与総額伸び率の差の変化
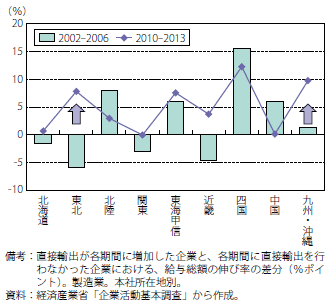
地方ほど内需に制約があることから、輸出による給与総額への寄与が、特に地方において以前よりも拡大している可能性がある。地方経済における輸出の重要性が増していると考えられる。
65 近畿の2010-2013では、直接輸出、国内向け売上高がともにマイナスであり、2002-2006年との比較ができない。
3.我が国の地域輸出の特徴と課題
(1)輸出伸び率
次に、我が国の地域輸出の特徴について、次節でその地域施策等を取り上げるドイツと比較しつつ確認していく。
まず輸出の伸び率を見ると、ドイツは我が国と比較して、輸出の増減に関して地域間のばらつきが小さく、また、世界経済危機を挟んだ2008年~2013年を見ても、ほとんどの地域で堅調に輸出を伸ばし続けており、我が国のように極端に輸出が減少している地域は存在しなかった(第Ⅱ-3-1-22図、第Ⅱ-3-1-23図)。またこの両期間において、我が国の地域間のばらつきに有意な差異はみられなかったのに対し、ドイツでは地域間のばらつきが時間の経過に従い、一段と縮小している(第Ⅱ-3-1-24表)68。
第Ⅱ-3-1-22図 日独・地域別の「輸出伸び率」の分布(2003→2008)
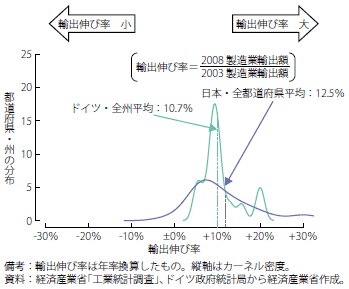
第Ⅱ-3-1-23図 日独・地域別の「輸出伸び率」の分布(2008→2013)
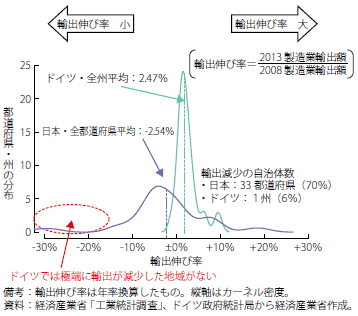
第Ⅱ-3-1-24表 地域輸出伸び率の平均と分散
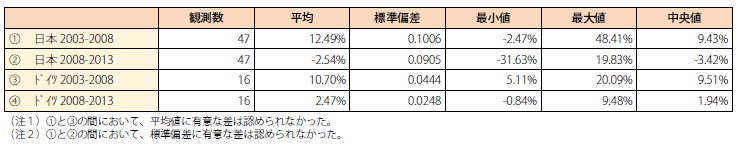
また、直接輸出規模が大きい地域(上位20都道府県)の中で輸出が増加傾向の地域は僅か6府県にとどまっており、輸出の伸びがドイツに比べ弱い要因となっている(第Ⅱ-3-1-25表)。
第Ⅱ-3-1-25表 都道府県別輸出状況(製造業)
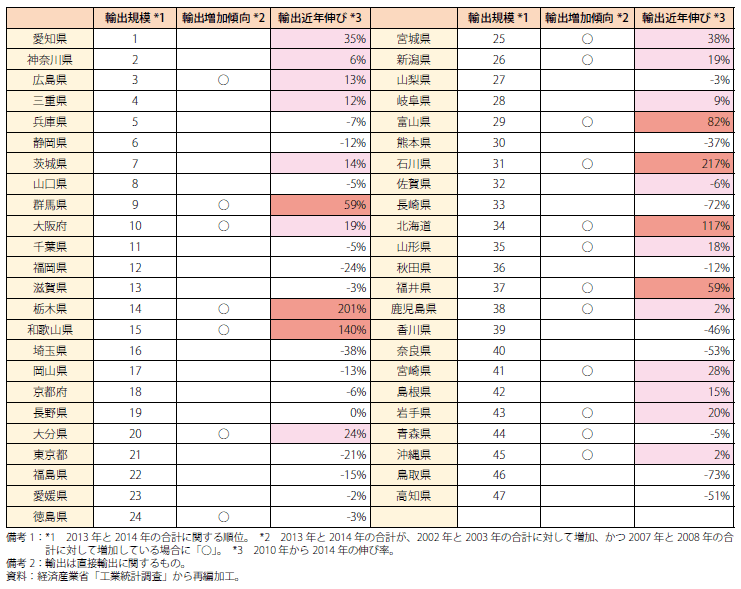
直接輸出規模が上位の都道府県と下位の都道府県について、その伸び率の平均値を比較すると、下位の平均値が、上位の平均値を上回る。なお、伸び率の起点を2002年と2003年の合計とした場合(第Ⅱ-3-1-26図)と、世界貿易が拡大していた時期に当たる2007年と2008年の合計を起点とした場合(第Ⅱ-3-1-27図)を比較すると、後者においては、特に輸出規模が上位の都道府県の平均伸び率が低い。
第Ⅱ-3-1-26図 輸出規模による地域の平均輸出伸び率 (2002/03→2013/14)
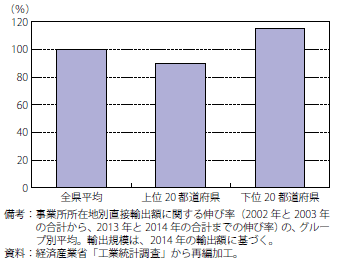
第Ⅱ-3-1-27図 輸出規模による地域の平均輸出伸び率 (2007/08→2013/14)
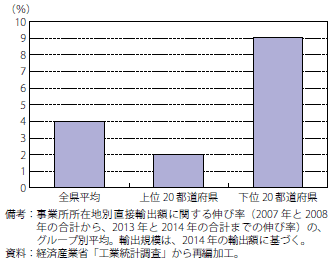
ドイツと比較すると、そもそも、ドイツの輸出比率(製造業輸出額の対製造業付加価値額比率)は高く、全州平均では1.56と、日本の0.38を大きく上回るが、地域別に見ても、日本では最も高い県でも1未満であるのに対し、ドイツでは最も低い州でも1を超えている(第Ⅱ-3-1-28図)。ドイツではほぼ全ての地域が、輸出を伸ばしているだけでなく、日本と比較して、より海外市場の獲得を志向していることが分かる。
第Ⅱ-3-1-28図 日独・地域別の「輸出比率」分布
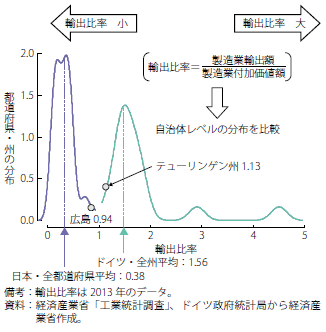
68 我が国の輸出は、製造業の直接輸出合計額(経済産業省「工業統計調査」に基づく)。ドイツの輸出は、非製造業(鉱業・エネルギー・農林水産業)も含む合計輸出額。ただし、2008年から2013年の伸びに関するドイツ製造業とドイツトータル(本項にて使用)の図の間には大きな違いは見られない。
(2)特定の地域・業種に対する集中
我が国の輸出は一部の地域に集中している。
2010年以降の製造業の合計直接輸出の伸び率に対する寄与度を地域別・業種別に確認すると、東海甲信地域の輸送用機械製造業の比重が際だって大きい(第Ⅱ-3-1-29図、第Ⅱ-3-1-30表)。
第Ⅱ-3-1-29図 我が国の合計輸出額の伸びに対する、地域・業種別の寄与度(製造業)
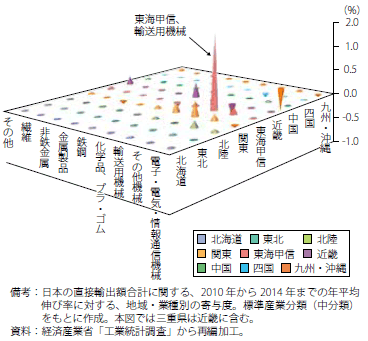
第Ⅱ-3-1-30表 我が国の合計輸出額の伸びに対する、地域・業種別の寄与度(製造業)
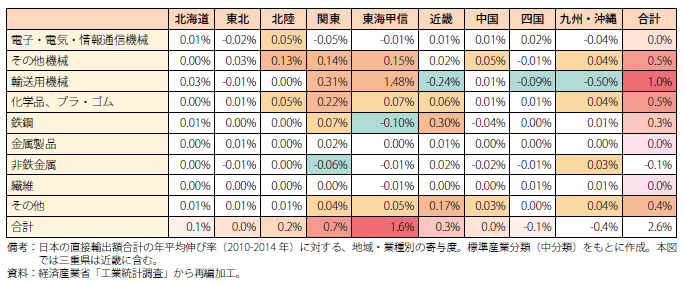
さらに、2008年以前とそれ以降を比較すると、2008年以降の方がより集中が高まっている。
第Ⅱ-3-1-30表を都道府県別、標準産業分類中分類別にしたものからプラス寄与分のみを抽出し(第Ⅱ-3-1-31図)、その累積をローレンツ曲線69で表したものが第Ⅱ-3-1-32図であるが、2010年以降の伸び率に関する同曲線が、2006年までの伸び率に関する同曲線よりもやや右下に位置しており、一部地域・業種への偏りが近年ではやや高まっていることが分かる。
第Ⅱ-3-1-31図 我が国の製造業直接輸出の伸び率(増加地域業種・減少地域業種別)
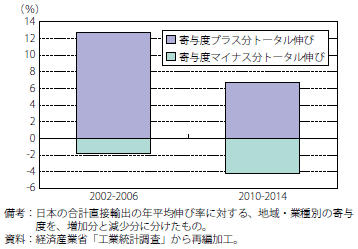
第Ⅱ-3-1-32図 我が国の直接輸出伸び率に対する増加寄与度の累積ローレンツ曲線
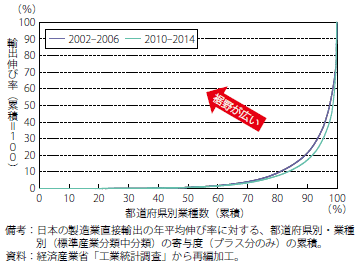
我が国の合計輸出は、世界経済の伸びの鈍化や我が国企業の海外移転等様々な要素が背景となって、その伸びがドイツを下回っているが、同図からは、国内で広く一様に伸びが鈍化しているのではなく、輸出をけん引する地域・業種が、より一部に集中してきている可能性がある。
〈特定の業種への依存〉
前項において、我が国の合計輸出の伸びが特定の地域・業種に集中していることを確認したが、我が国では地域の輸出も、伸びている場合も減少している場合も、特定の業種に大きく影響を受けている場合が多い。
世界経済危機を挟んだ2008年~2013年に関して、輸出が減少した地域における業種寄与度を確認すると、自動車関連や機械関連等、一部の業種による大幅な減少を他の業種でカバーできていない70(第Ⅱ-3-1-33図)。
第Ⅱ-3-1-33図 地域輸出額の伸びと業種寄与度(日本)
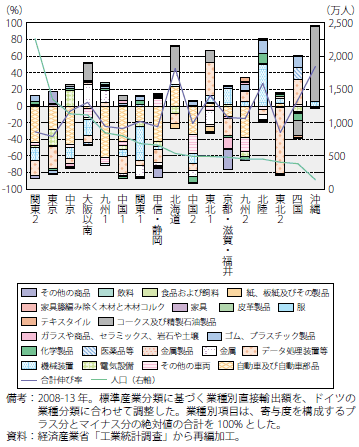
それに対し、ドイツの地域輸出における状況を確認すると、ブレーメンやハンブルク等、特定の品目に依存している地域が一部に見られるものの、全体的には、規模が小さい州も含めて多くの州が、多様な品目において輸出を伸ばしている。
例えば製造業の輸出額がドイツの州の中で最も小さいメクレンブルクフォアポンメルン州(MV)は、食品関連、化学製品、金属製品、機械装置等、多様な品目にわたって伸びが見られる(第Ⅱ-3-1-34図)。
第Ⅱ-3-1-34図 地域輸出額の伸びと品目寄与度(ドイツ)73
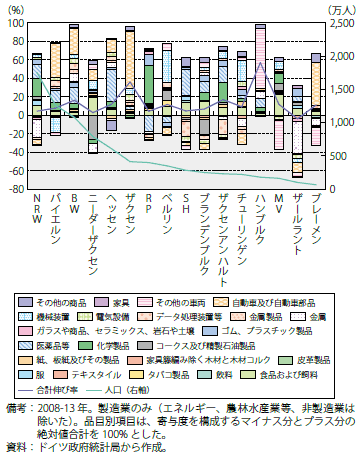
第Ⅱ-3-1-35表 (参考)2-3-1-35図における17地域対応表
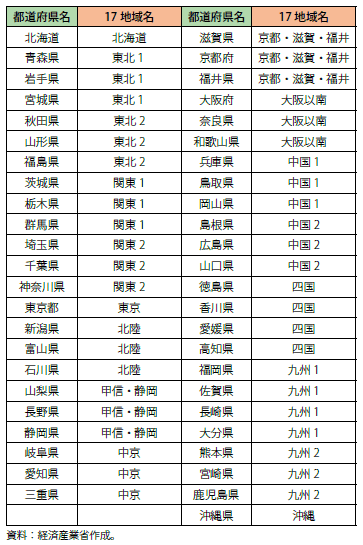
次に、2008年以降の製造業輸出の伸びに対する、増加した業種(品目)と減少した業種(品目)71による寄与度を確認すると、ドイツでは9割近くの州が、寄与度の変化が小さい区分(現状維持型)に収まっており、残りの2州は増加品目の寄与度が大きく減少品目の寄与度が小さい区分である(第Ⅱ-3-1-36図)。
第Ⅱ-3-1-36図 ドイツ州別製造業輸出の変化(増加品目・減少品目の寄与度別)
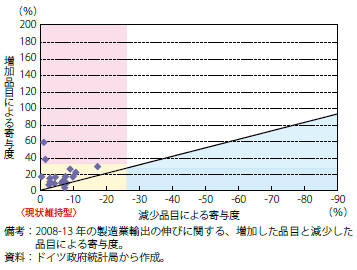
対して日本の都道府県は、現状維持型に加えて、増加業種の寄与度が大きく減少業種の寄与度が小さい区分(ハイパフォーマー)72に12都道府県、また減少業種の寄与度が大きい区分(減少業種寄与度大)に16都道府県と、それぞれ多くの都道府県が含まれており、地域によって違いが大きい(第Ⅱ-3-1-37図)。
第Ⅱ-3-1-37図 我が国の都道府県別製造業輸出の変化(増加業種・減少業種の寄与度別)
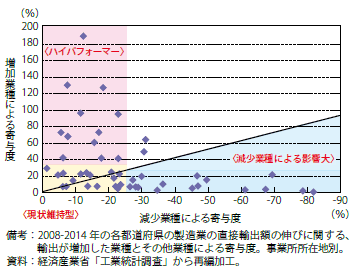
減少業種による影響が大きい区分は、一部の業種に地域輸出が偏重していた場合に、当該企業による撤退や、あるいは当該業種の市場の急な縮小が生じた地域である可能性がある。
一部業種による輸出のけん引は、地域経済に貢献する反面、リスクにもなり得ることに留意することが必要である。ハイパフォーマーに多くの我が国地域が含まれることは歓迎すべきである一方で、それらの地域が引き続き輸出を維持・拡大するためには、強みのある業種の裾野を拡大していくことも必要であろう。
なお、輸出が伸びている地域数が多い業種(品目)は、化学品関連や食品等、ドイツと我が国で共通している(第Ⅱ-3-1-38図、第Ⅱ-3-1-39図)。食品のように現時点で輸出規模が小さい業種であっても、輸送技術の発達や新しい市場の開拓によって、将来の輸出が大きく広がる可能性がある場合もある。将来性と地域の強みを考慮しつつ、輸出のすそ野を広げていくことが必要であろう。
第Ⅱ-3-1-38図 業種別の直接輸出増加地域比率(我が国)
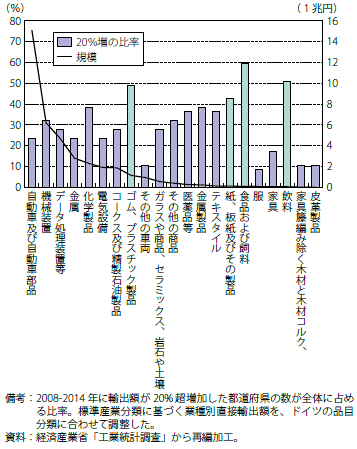
第Ⅱ-3-1-39図 品目別の輸出増加地域比率(ドイツ)
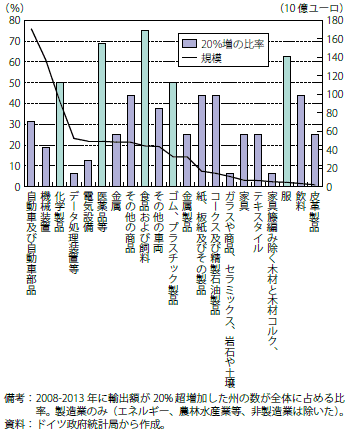
69 ローレンツ曲線とは、一般的には、所得格差を表すために用いられることが多い。ここでは、日本の地域別業種(日本の合計直接輸出の伸びに対してプラス寄与しているもののみ抽出)を、輸出規模の低い順番に並べ、横軸に輸出額の累積比をとり、縦軸に輸出伸び率(年平均)に対する寄与度の累積比をとって、地域別業種間による寄与度分布をグラフ化した。仮に、日本の地域において寄与度の格差が存在せず、全ての地域の輸出規模が等しければ、ローレンツ曲線は45度線と一致するが、分布に偏りがあるほど、ローレンツ曲線は下方に膨らんだ形となる。
70 第Ⅱ-3-1-33図では、日本の都道府県について、ドイツの州数及び人口規模と概(おおむ)ねそろうように17地域に区分した。都道府県の地域対応は第Ⅱ-3-1-35表のとおり。
71 図中のドイツ州名のうち、NRWはノルトライン=ヴェストファーレン州、BWはバーデン=ビュルテンべルク州、RPはラインラント=プファルツ州、SHはシュレースヴィヒ=ホルスタイン州、MVはメクレンブルク=フォアポンメルン州の略。
72 日本標準産業分類を、ドイツの品目分類に合うよう調整。
73 日本の増加/減少業種による寄与度の都道府県平均を基準として、増加寄与度・減少寄与度がともに平均を上回る場合に「ハイパフォーマー」。増加寄与度・減少寄与度がともに平均を下回る場合に、「減少業種による影響大」と区分した。日本は2008~2014年の伸び率、ドイツは2008年~2013年の伸び率。
(3)業種の多様性が見られる地域
地域経済の持続のためには、輸出の拡大のみならず製造業の出荷額を拡大する必要があるが、多様性を確保するためには、これが複数の業種で見られることが重要である。
2008年及び2010年に比べて製造業出荷額と輸出が共に拡大している業種の数が多いのは、富山県、北海道、埼玉県、三重県、広島県、香川県、宮崎県、福岡県などであった(第Ⅱ-3-1-40図)。
第Ⅱ-3-1-40図 製造業の合計出荷額・輸出額が共に増加している業種数
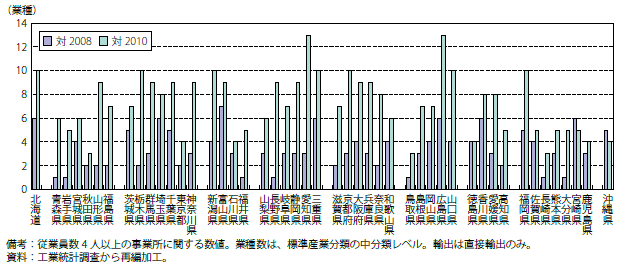
以下では、比較的多くの業種で出荷額と輸出額の増加が見られた地域のうち、富山県、宮崎県及び福岡県について、輸出の状況と取り組みを紹介する。
①3県における輸出概況
輸出が増加した業種による寄与度と減少した業種による寄与度を比較すると、富山県では、後者によるマイナス寄与は都道府県平均にかなり近いものの、前者によるプラス寄与が大きいために、全体での伸び率は70%を超えている。一部の業種の減少を他の業種の伸びでカバーしていると言える。
宮崎県は、減少業種におけるマイナス寄与が富山県や都道府県平均よりも大きいが、やはり前者によるプラス寄与が大きいために、全体では輸出増となっている。
福岡県は、減少業種におけるマイナス寄与が都道府県平均よりやや大きく、増加業種における寄与が低いため、全体で輸出が減少している(第Ⅱ-3-1-41図)。
第Ⅱ-3-1-41図 3県の輸出の変化(増加品目・減少品目の寄与度別)
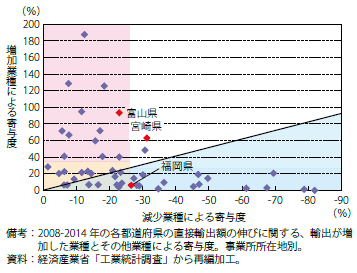
以下では、3県の製造業輸出を業種別に確認する。
まず富山県では、化学工業、プラスチック製品製造業、はん用機械器具製造業といった主要輸出業種に加えて、輸出規模が小さい繊維工業と食料品製造業においても、直接輸出と合計出荷額が共に増加している。最も輸出規模が大きい生産用機械器具製造業は、出荷は僅かに減少しているが直接輸出は大きく伸びており、同県の輸出をけん引している(第Ⅱ-3-1-42表)。
第Ⅱ-3-1-42表 富山県の業種別直接輸出の状況(製造業)
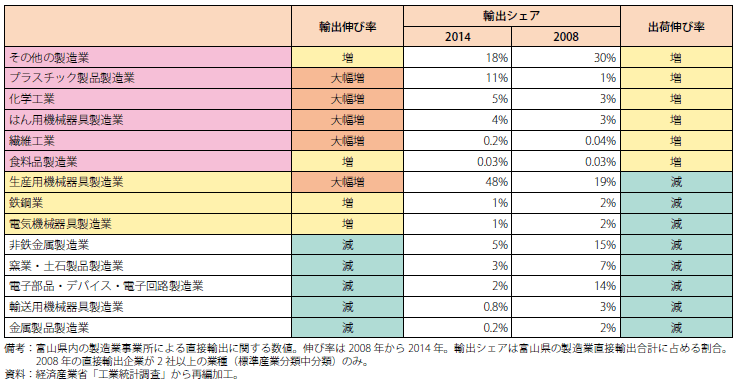
また、同県が強みを持つ医薬品製造業(化学工業に含まれる)は、輸出は減少しているものの出荷額は大きく伸びている。74
次に、宮崎県については、全体の輸出規模は小さいものの、電子部品・デバイス関連製造業をはじめとする、比較的規模の大きい業種の多くで輸出が増加しており、合計輸出の伸びをけん引している。さらに、輸出と出荷が共に増加している業種も多く(繊維工業、プラスチック製品製造業、生産用機械器具製造業、情報通信関連製造業、食料品製造業)、特に繊維工業、プラスチック製品製造業及び食料品製造業では伸びが顕著である(第Ⅱ-3-1-43表)。
第Ⅱ-3-1-43表 宮崎県の業種別直接輸出の状況(製造業)
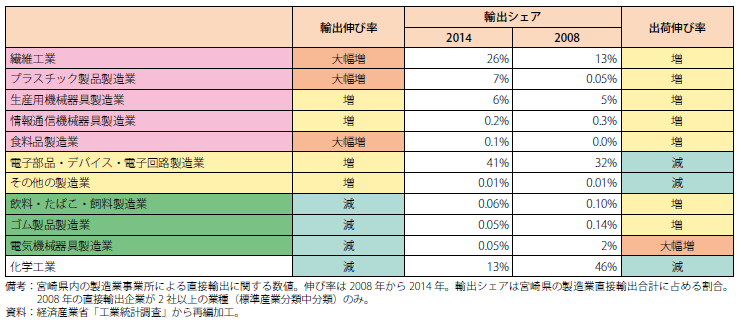
なお、同県が力を入れている医療用機械関連製造業では、直接輸出は確認できないものの、合計出荷額は堅調に伸びている。
福岡県については、輸出規模が大きい(2014年の輸出シェア2%以上)業種のうち、輸送用機械製造業と化学工業を除いて直接輸出が伸びている。
直接輸出と合計出荷額が共に減少している業種も見られるが、他方で、輸出と合計出荷額が共に増加している業種が複数確認できる(ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、金属製品製造業、プラスチック製品製造業、食料品製造業)(第Ⅱ-3-1-44表)。
第Ⅱ-3-1-44表 福岡県の業種別直接輸出の状況(製造業)
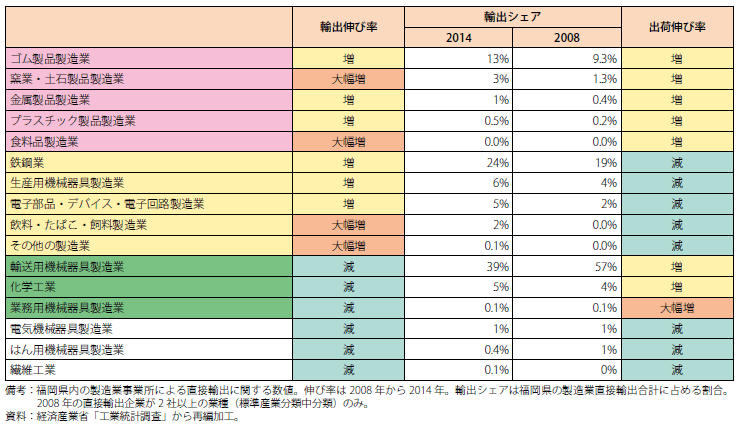
輸出規模が最大の輸送用機械器具製造業において、合計出荷額の伸びにも関わらず輸出が減少したために、結果として合計直接輸出額が減少しているものの、多様な業種が、世界経済危機以前と比較しても堅調に輸出を拡大していると言える。
74 輸出及び出荷の伸び率について、「大幅増」は100%以上、「増」は0~100%未満、「減」は0%未満とした。
②富山県の取組
富山県は「薬の富山」として伝統的に医薬に強みを持っているが、強みを更に強化するために海外との協力を進めるとともに、医薬だけでなく多面的な産業の成長促進や、独自の中小企業支援や起業支援策を実施している。
〈スイスバーゼル地域をはじめとする欧州各国との協力〉
同県は、「世界の薬都」と呼ばれるスイスのバーゼル地域と、海外訪問団の派遣などを内容とする交流を行っている。
2006年に同県薬業連合会(以下「富山薬連」という。)により開始された交流は、2007年からの3年間は日本貿易振興機構(JETRO)の事業(地域間交流支援事業(以下「RIT事業」という。))を活用して続けられ、2009年には富山県とスイスバーゼル地域の2州との医薬品等に関する交流・協力協定等が締結された。
RIT事業終了後も、両地域の企業による委受託生産や共同研究開発、富山県の助成による県内研究者のバーゼル大学への派遣、産学官の研究者の交流によるビジネスマッチングや共同研究の促進など、地域の交流は継続している。また、富山薬連はRIT事業を活用して、スイスに加えて2010年からはイタリア、2014年からはフランスとも交流を行っているほか、JETROの海外投資ミッション派遣協力事業の支援を受け、これまで東南アジアを中心に6か国との交流を実施している。
なお、富山薬連によるアンケート調査によれば、RIT事業参加企業の海外売上高は、2007年から2014年までに3倍以上に増加(第Ⅱ-3-1-45図)し、企業内の国際業務担当者の数は19人から57人に、英語を話すことができる担当者は14人から49人に増加するなど、各製薬企業における国際交流の取組体制が構築されている(各項目回答15社の合計)。
第Ⅱ-3-1-45図 富山県医薬品メーカーの海外売上高
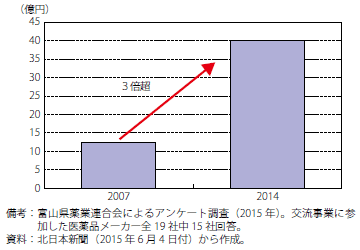
〈多面的な産業の成長促進〉
また、産業基盤強化の側面では、2014年に「富山県ものづくり産業未来戦略」、2015年に「とやま未来創生戦略」を策定した。これまで、分野横断的な技術の融合があまりなされていなかったが、強みである医薬品やアルミ素材などのコア技術を更に強化し、これを横に広げ、「八ヶ岳」状の産業構造へとシフトし、新たな様々な成長産業への多面的な展開が予定されている(第Ⅱ-3-1-46図)。
第Ⅱ-3-1-46図 富山県のものづくりの将来像
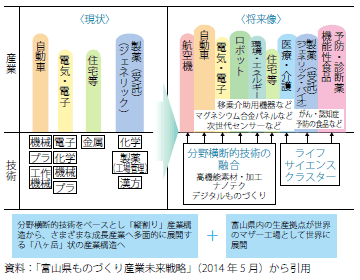
③宮崎県の取組
宮崎県は、企業のビジネスマッチングを重視し、海外における販路拡大支援に積極的に取り組んでいる。
宮崎県は、東アジアにおける海外拠点機能(上海事務所・香港事務所等)を活用し、県内企業の海外取引や販路開拓、輸出支援を行っているほか、海外の展示会・商談会への出展支援等による取引機会の提供を図っている。
また、企業の戦略的な海外展開を図るため、企業の相談対応、商談後のフォローアップを行い、企業の掘り起こしから取引の定着まで一貫した支援を行っている。
さらに、近年、東アジアに限らず、よりグローバルな事業展開を行う企業の動きが見えつつあることから、平成28年3月に「みやざきグローバル戦略」を策定し、今後は世界市場も視野に入れ、県内生産品の輸出をはじめとする海外との経済交流の拡大に取り組むこととしている。
なお、宮崎県から大分県に広がる東九州地域は、血液・血管に関する医療機器の世界的な生産・開発拠点であることから、両県は東九州メディカルバレー構想75に取り組んでおり、宮崎県では県内の医療関連企業の振興を図っている。
具体的には、県内企業による医療機器分野への参入や取引拡大を促進するため、医療関連産業への新規参入や取引拡大を目指す県内ものづくり企業による技術の展示会を東京都で実施し、医療機器メーカーとの連携促進を図るイベントや、県内ものづくり企業向けに医工連携による事業化の進め方についてのセミナーを実施している76。
76 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/shoko/kogyo/medical_valley/study/26/261120.html![]()
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/shoko/kogyo/medical_valley/study/26/261022.html![]()
④福岡県の取組
福岡県による企業の国際展開支援の取り組みは多岐にわたるが、2011年に国際戦略総合特別区域に指定された「グリーンアジア国際戦略総合特区77」では、環境負荷の低減に貢献する産業について、研究開発と生産の集積拠点化を進め、国際競争力の強化を図る事業を実施している。
具体的には、環境配慮型自動車及び関連製品、太陽光・風力発電用コンバータ等再生可能エネルギー利用に関する製品、産業用ロボット・高効率ロボット、低電力損失パワーモジュール、スマートコミュニティ関連のシステム及び機器、次世代燃料電池及び関連製品、有機EL関連製品、と環境を軸に幅広い分野において、産学官の連携が図られた先進的な技術開発や研究が行われている。
また、研究開発と生産の集積拠点化に関する事業に加えて、北九州市が設立した「アジア低炭素化センター」を中心に官民が連携し、都市環境インフラや水ビジネスにおける官民の技術・ノウハウをパッケージ化してアジアに展開する事業を実施している。
環境分野は世界的に市場が拡大する可能性が高いことから、同分野での国際競争力向上が、外需獲得によって地域経済に貢献することが期待されている。
また、福岡アジアビジネスセンター(福岡ABC)は、海外展開を目指す中小企業に対する情報提供や現地サポート等をワンストップで支援するために2012年に開設された。
海外でビジネス経験を重ねた常勤マネージャーが国別・分野別の登録アドバイザーと連携しながら、国内や現地において、具体的な案件をサポートし、中小企業の国際展開を支援している。
また、県内企業を関係機関が連携して支援するとの福岡県の政策を背景に、2015年3月には日本貿易振興機構(JETRO)が福岡ABCの隣に移転し、現在では、案件を紹介しあうなど連携して事業が実施されている。
77 福岡県、北九州市及び福岡市から構成される。
(4)まとめ(「新輸出大国コンソーシアム」による支援と今後の課題)
我が国の近年の輸出は、東海地方の自動車関連製造業にけん引されていると言ってよい。しかし一部の地方では規模が小さいながらも輸出志向が高まり輸出が堅調に拡大している。また、輸出が伸びている企業は、輸出を行わない企業と比べ、給与総額が増加する比率が高い等、輸出が地域経済に寄与しうる状況が確認できた。
少子高齢化が進む中、地域経済を活性化するために、引き続き、中堅・中小企業を中心として輸出の拡大を図ることが必要である。
なお、特定の業種の輸出縮小によって輸出が大きなダメージを受けた地域が多いことを考慮すると、強みのある業種を活(い)かしつつも、食料品や医療関連等、新しい分野を含めて輸出のすそ野を広げていくことが必要であろう。
2016年2月26日、中堅・中小企業の海外展開支援のため、官民の関係機関を結集した「新輸出大国コンソーシアム」78が設立された。同コンソーシアムの下では、TPPを契機として海外展開を図る中堅・中小企業に対して、支援機関相互の連携による支援に加え、海外ビジネスに精通した専門家が個々の企業の担当となって、海外事業計画の策定や現地での商談・海外店舗の立ち上げなどの支援を行う。個々の企業のニーズに応じた製品開発、国際標準化、販路開拓に至るまでの総合的な支援がきめ細かく図られることで、我が国中堅・中小企業の海外展開が促進されることを期待する。
78 第3部第2章第1節1。