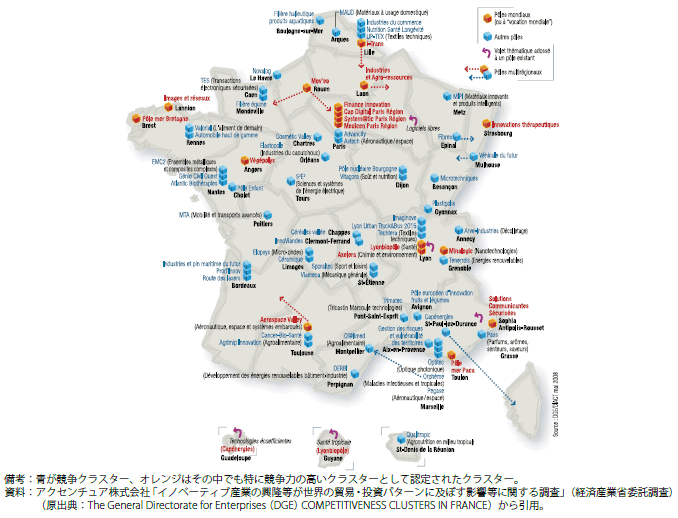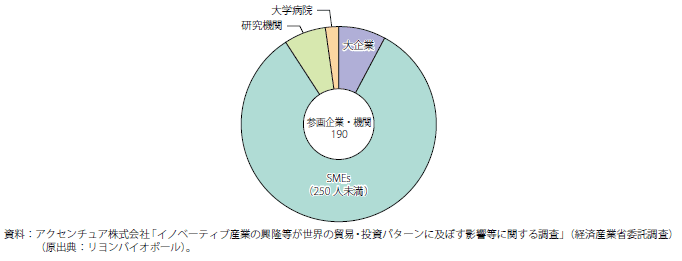第2節 ドイツをはじめとする地域産業・地域輸出拡大の要因・要素
1.主要国の輸出推移
はじめに、1990年代以降の各国の輸出推移を確認する。
ドイツ及び米国は、中国をはじめとする新興国が競争力を向上する中で、世界経済の拡大とともに輸出を大きく伸ばしており、世界輸出規模で中国に次ぐ水準を維持している(第Ⅱ-3-2-1図)。
第Ⅱ-3-2-1図 輸出上位国の輸出推移
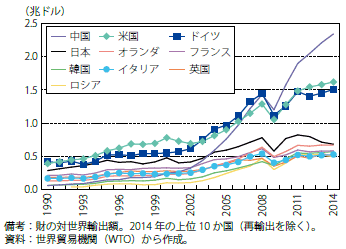
ドイツについては、1999年の通貨ユーロの誕生によりユーロ圏向け輸出が行いやすくなったことも事実であるが、2000年代半ば以降、EU域内のみならず、非EU向けの輸出も大きく伸ばしている(第Ⅱ-3-2-2図)。
第Ⅱ-3-2-2図 主要国の輸出推移(EUは非EU向けのみ)
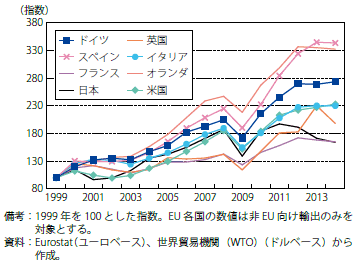
通貨がユーロに統一されたことで、実際の経済の強さに比べて通貨安の環境で輸出を行えるようになったことがドイツの輸出を拡大した可能性は高い。しかし、ドイツの製造業の労働コストは我が国よりも高く、さらに実質実効為替レート79については、他のユーロ圏加盟国に比べて低下しているものの、低下幅は緩やかであり、ドイツはコスト以外の点で輸出競争力を向上していると考えられる(第Ⅱ-3-2-3図)。
第Ⅱ-3-2-3図 主要国の実質実効為替レートの推移
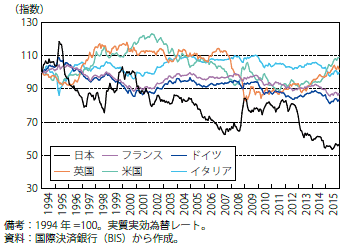
79 各国の消費者物価、為替、及び貿易額に基づく実質実効為替レートは、一国の貿易財の価格競争力を測る指標としてよく用いられる。
2.ドイツの地域産業・地域輸出を支える要因・要素
(1)ドイツの雇用と地域格差
ドイツでは、先に見たようにほぼ全ての州において輸出額が伸びているだけでなく、製造業の付加価値も1州を除き全ての州で増加しており80、堅調な輸出を支える活発な製造業の存在が確認できる(第Ⅱ-3-2-4図)。
第Ⅱ-3-2-4図 業種別付加価値の増減(ドイツ州)81
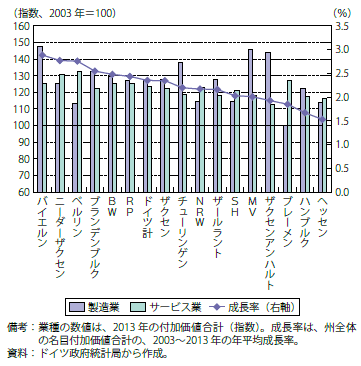
雇用の伸びは、付加価値の伸びをはるかに下回るものの、輸出規模が大きいバーデン=ビュルテンブルク州とバイエルン州では伸びが大きいほか、足下で雇用が上向いている州が多く見られる(第Ⅱ-3-2-5図)。
第Ⅱ-3-2-5図 ドイツ製造業の就労者数伸び(2010年以降)
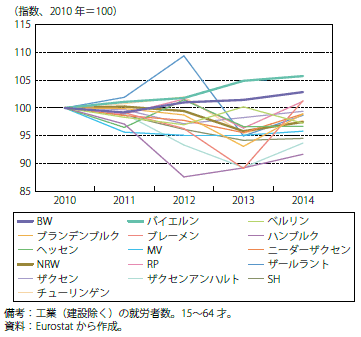
製造業の雇用が低迷する一方、サービス業も含めた産業全体では、2000年から2012年の期間、全ての州で雇用の増加が確認できる(第Ⅱ-3-2-6図、第Ⅱ-3-2-7図、第Ⅱ-3-2-8図)。ドイツでは、製造業の競争力を高めつつ、雇用が製造業からサービス業にシフトすることで地域経済が維持・発展したと言えるのではないだろうか。
第Ⅱ-3-2-6図 ドイツ製造業の付加価値と就労者数の伸び率
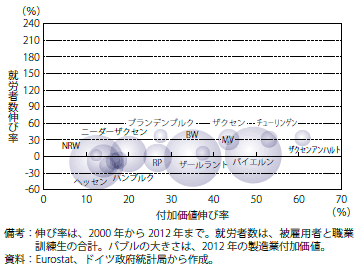
第Ⅱ-3-2-7図 ドイツ製造業の生産性と就労者数の伸び率82
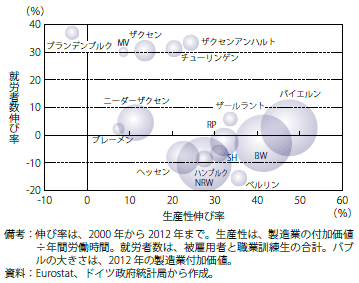
第Ⅱ-3-2-8図 ドイツの産業全体の生産性と就労者数の伸び率比較
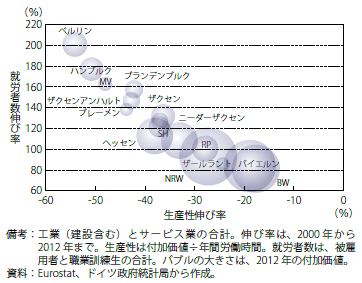
また、ドイツでは地域間の経済格差や就労者数の偏りが欧州主要国と比べて小さい。雇用が国内に広く分散していると言える(第Ⅱ-3-2-9図、第Ⅱ-3-2-10図)。
第Ⅱ-3-2-9図 一人あたりGDPの地域格差(欧州各国)
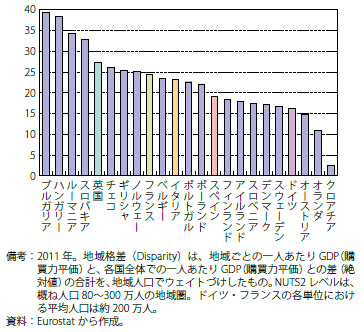
第Ⅱ-3-2-10図 被雇用者数の地域による偏りの大きさ(欧州主要国)
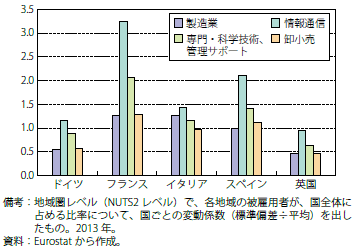
80 ドイツの製造業の付加価値は、対2002年では全ての州で増加、対2003年(第Ⅱ-3-2-4図)ではブレーメンで僅かに減少。
81 図中のドイツ州名のうち、NRWはノルトライン=ヴェストファーレン州、BWはバーデン=ビュルテンべルク州、RPはラインラント=プファルツ州、SHはシュレースヴィヒ=ホルスタイン州、MVはメクレンブルク=フォアポンメルン州の略。
82 図中のドイツ州名のうち、NRWはノルトライン=ヴェストファーレン州、BWはバーデン=ビュルテンべルク州、RPはラインラント=プファルツ州、SHはシュレースヴィヒ=ホルスタイン州、MVはメクレンブルク=フォアポンメルン州の略。
(2)地域産業・地域輸出を支える要因・要素
①ドイツのイノベーション
輸出する際に強みとなる主な要素は、労働コストや法人税などビジネスコストが低いといったコスト競争力に加えて、差別化された製品を生むためのイノベーション、効率的な販路確保の取り組み等が考えられる。
先進国では、国内ビジネスコストの高さから製造拠点を国外へ移す企業がある一方で、近年では新興国における労働コストが上昇していることから、後者の比重が以前より高まっていると言われ、製造業のリショアリングも見られている。
中でもドイツは、我が国よりも労働賃金が高く社会保障費用の企業負担も高いにも関わらず輸出が大きく伸びており、コスト競争力以外の要素が大きな役割を果たしていることがうかがえる(第Ⅱ-3-2-11図、第Ⅱ-3-2-12図)。
第Ⅱ-3-2-11図 主要国の時間当たり賃金(製造業)
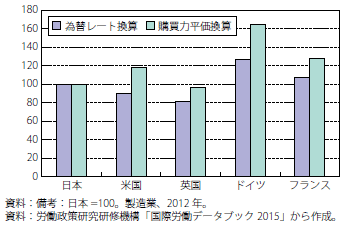
第Ⅱ-3-2-12図 主要国の社会保障費用(使用者側負担比率)
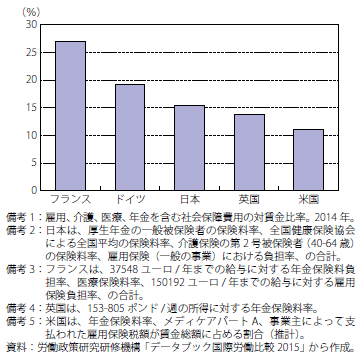
そこで、ビジネスのしやすさに関して各国をランク付けしている世界銀行のDoing Businessを確認すると、ドイツは英国や米国を下回るものの我が国よりも高い。同指標においてビジネスのしやすさを構成する項目についてドイツと我が国を比べると、ドイツは税支払と貿易のしやすさにおいて我が国を上回っている(第Ⅱ-3-2-13図)。
第Ⅱ-3-2-13図 主要国のビジネスのしやすさ比較
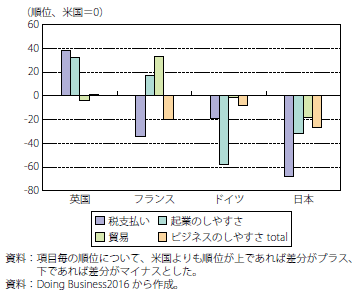
同様にイノベーションについて各国をランク付けしている世界知的所有権機関(WIPO)のGlobal Innovation Indexを確認すると、ドイツはやはり英国や米国を下回るものの、我が国よりも高い。同指標の構成項目の中で、ドイツは、クラスターの広がり、外国資金による研究開発、流通の項目において米国を上回っている(第Ⅱ-3-2-14図)。
第Ⅱ-3-2-14図 主要国のイノベーション比較
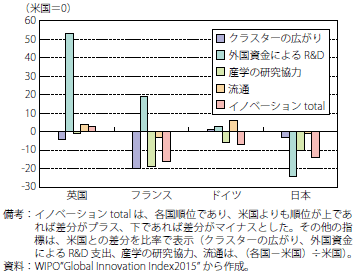
イノベーションは、業種や人種における多様性から生まれると言われている83。ドイツの地域クラスターは、複数の業種が一箇所に集積していることが特徴的であり、また一部の州においては、異業種が集積しているために企業が繋(つな)がりやすく、イノベーションを可能にしているとも言われる。
外国資金による研究開発比率の高さに関しては、第二次世界大戦以降、英米資本が積極的に進出しており、外国資本の企業比率が高いことに加え、大学が外国企業に対してオープンであることが背景として考えられる。
なお、ドイツでは、人口あたりの特許申請数(住民当たり数)が欧州の平均値より高い州が多い(第Ⅱ-3-2-15図)。特許申請数が多い地域ほど製造業の付加価値の伸び率が高い傾向にあり、特許申請と産業が結びついている可能性がうかがえる(第Ⅱ-3-2-16図)。
第Ⅱ-3-2-15図 欧州の特許申請比率が高い都市又は州の比率
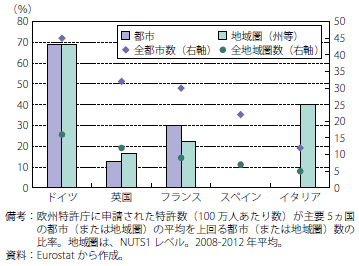
第Ⅱ-3-2-16図 ドイツ州の特許申請数と製造業付加価値成長率
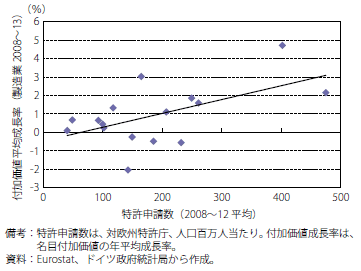
さらにドイツは、科学技術分野の就労者が労働力に占める比率が高く、またその地域格差が他国よりも小さい(第Ⅱ-3-2-17図、第Ⅱ-3-2-18図)。多くの科学技術人材が各地に広がり、地域産業の発展に貢献している可能性が考えられる。
第Ⅱ-3-2-17図 科学技術分野の就労者が労働力に占める割合(欧州主要国)
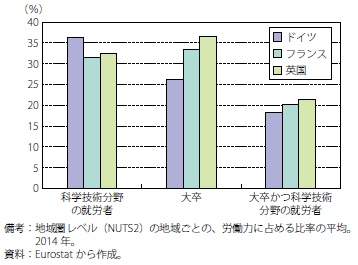
第Ⅱ-3-2-18図 科学技術分野の就労者に関する地域格差(欧州主要国)
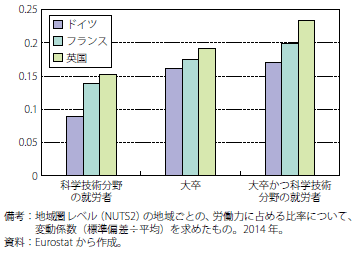
このようにイノベーションにおいて地域格差の抑制が働いている主な要因としては、①19世紀後半まで君主国が割拠する体制であったために各地域に一定の産業基盤が存在しているという歴史的な背景、②産業応用を目的とするフラウンホーファー研究機構84が各地に分散して立地していること、また③州立の研究所や工科大学等が各地に設立されていること等が考えられる。
なお、各地に立地するフラウンホーファー研究機構や多くの工科大学は、産業界との繫(つな)がりが強い。産業界との人的な繋(つな)がりを背景として、大学や研究機関における研究開発のテーマは産業のニーズに応える内容が選択され、また技術移転も効率的に行われることで、地域のイノベーションが支えられている。
83 藤田(2005)。
84 ドイツ国内に67の研究所を有する。http://www.dwih-tokyo.jp/ja/research-germany/research-organisations/fraunhofer-gesellschaft/![]()
〈事例~大学の人材活用による産業との連携(NRW州アーヘン工科大学)〉
ノルトライン=ヴェストファーレン州(以下「NRW州」という。)の医療クラスターの一部を構成するアーヘン工科大学は、注力すべき19分野を設定し、学内で産学が協力する「クラスター」として、研究からビジネスまでの展開の加速を図っている85。
中でも人工心臓の分野においては、同大学がドイツにおける研究の最先端の知見を有しているという強みを活(い)かして、研究者だけでなく、製造技術担当者、品質管理担当者、血液ラボなどを一箇所に集めた効率的なプロジェクトを進めている。
博士課程後期以降の学生は、教授が集める外部資金を給与として、大学のシーズを元に事業化を目指すベンチャー企業のプロジェクトをベンチャー企業の職員とともに遂行する。また、工学部のスタッフが、キャリアアップの過程で大学と企業を行き来することで産業界との密接な関係が構築され、プロジェクトの内容はビジネスニーズを踏まえたものとなる。大学が得意な分野から効率的にビジネスに貢献するために、専門分野の人材を活用した体制をつくり、教授をはじめとする大学スタッフの人脈によって産業界と連携することで、プロジェクトのスピードアップが図られていると言える。
85 アーヘン工科大学ウェブサイト(http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Wirtschaft/Campusprojekt/~eli/Forschungsschwerpunkte/lidx/1/![]() )参照。
)参照。
②地域への企業立地と大学・研究機関
ドイツでは、特定の地域だけでなく各地に異業種の集積が見られるが、異業種、あるいは多様な国籍の企業集積の一部は、各地に広く立地する大学や研究機関が起点となっていると考えられる。
一般に、研究開発機能を有する企業の立地は、労働コストや法人税等ビジネスコストの低さといったインセンティブの他に、①大学や研究所からの技術移転に期待が持てること、②市場があること、③労働力が確保されていること、が前提となる。その後、当該地域で成功事例が現れれば、他の企業がイノベーションを期待して立地することで、徐々に企業が集積していく。
ドイツにおいては、各地域に一定水準以上の大学や研究所が立地し、またそれらの多くが産業界に貢献しようとする姿勢を明確に打ち出しており、企業の立地を後押ししている。
例えば、産業界からの資金獲得が大きいほど、政府から得られる基盤的運営経費が増すという「フラウンホーファーモデル」は、フラウンホーファー研究機構のみならず、産業応用を担う工科大学でも採用されている。また工科系の教授は産業界の経験を有していることが多く、研究内容はビジネスにとって有益なものが採択される傾向が高いため、研究成果がビジネスに移転されるスピードも速まると考えられる。
大学の多くは国内企業だけでなく外国の企業との研究協力も積極的に進めており、我が国企業を含めた多くの外国企業がドイツに拠点を設ける背景ともなっている。
また、大学を卒業した若者は、地元の企業に就職するため、当該地域の外に若者が流出する割合が低いと言われる。加えて専門大学は、実践的な教育を行うことを特徴としており、企業において即戦力となる、理論と実践力を身につけた若者が輩出されるため、地域の企業が労働力を確保しやすい環境となっている。
ドイツの州政府は、産業政策の観点から大学を立地するとともに、企業のビジネス展開を支援するための環境を整えており、結果として企業が立地し若者が地域企業に就職するという経済発展の好循環が成立していると言える。(第Ⅱ-3-2-19図)
第Ⅱ-3-2-19図 ドイツ地域における大学を起点とするイノベーション企業の立地(イメージ図)
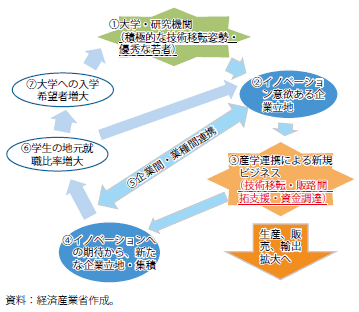
〈事例~大学やクラスターを起点とした産業構造の転換(NRW州)86〉
ノルトライン=ヴェストファーレン州(以下「NRW州」という。)は、旧西ドイツの首都ボンを擁しドイツ最大の人口を抱える。ドイツの中でも特に大学が集中する地域の一つであり、大学生数は最も多く、2005年以降の学生数の伸びが最も高い州の一つである(第Ⅱ-3-2-20図、第Ⅱ-3-2-21図)。主要産業は、機械、化学品、鉄鋼、金属、自動車、エネルギーであるが、一方で石炭・鉄鋼産業にルーツを持つ同州は、20世紀後半以降、産業構造の転換を継続している。旧西ドイツ地域の中では比較的高い失業率を背景に、現在でも、地域雇用増加のため、重点となる産業分野を定めて地域の競争力強化に取り組んでいる(第Ⅱ-3-2-22図)。
第Ⅱ-3-2-20図 ドイツ地域の大学数87
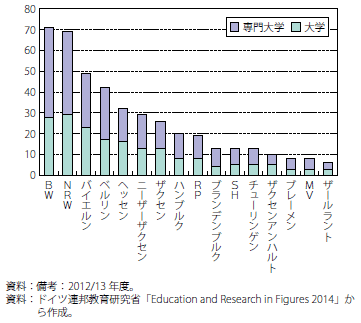
第Ⅱ-3-2-21図 ドイツ地域の学生数の推移
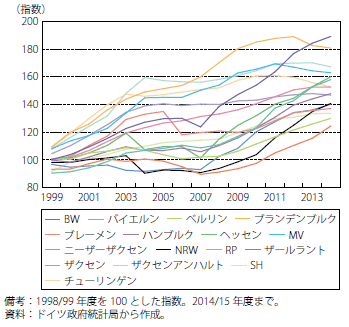
第Ⅱ-3-2-22図 ドイツの州別失業率
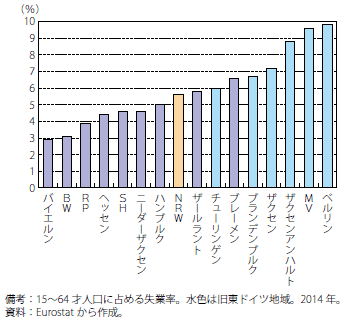
1960年代、地域経済を支えていた石炭・鉄鋼産業の衰退を受けて、NRW州政府は地域の雇用を守るためにNRW州経済振興公社(NRW. INVEST GmbH) を設立し、産業構造の転換を図った。さらには、1970年代に大学と、初となる専門大学を設立し、優秀な人材の育成と、知的側面からの経済発展が図られたが、当時設立された総合大学のうち一部88は、地域志向を高めることと、理論と実技を共に行うこと等が目的とされた。さらに専門大学については、若者の職業訓練を大学レベルで学ばせることが目的とされ89、炭鉱労働者の家庭に生まれた若者等に教育の機会を与えることとなった。若者に新たな産業の知識と技術を身につけさせることによって、衰退する産業の労働者を敗者とせず、地域の雇用を維持したこのやり方は、産業構造転換の成功例とされている。
また産業構造の転換についてはその後も重点的に取り組まれている。2000年代には省庁間で議論を重ね、州民や州経済に寄与すると考えられる重点8分野(ライトマルクト)90が2011年に閣議で決定された。各分野については、競争的資金プロジェクト(ライトマルクトコンテスト)によって、よりイノベーティブなプロジェクトが選定、実施される仕組みとなっている。
州としてのクラスター91は重点8分野を中心に16あり、同コンテストへの参加をはじめとして活発な取り組みが行われている。
重点8分野の中でも特に健康関連分野については、高齢化によりニーズが高まる中でコンピテンシー(能力)強化を図ることが重要課題の一つに掲げられ、州内各地でクラスターが活発に活動している。
そのうち高齢化が進むルール地域に位置するボーフムの医療クラスターでは、ルール大学ボーフム校を中心として、中小企業等のためのラボや、医療関連企業を対象とした施設が設けられているほか、2009年より「ボーフムヘルスケアキャンパス」として、大学、研究機関、ヘルスケアに関する行政機関、及び企業が立地するキャンパスの設立が開始された。
ヘルスケアと医療の研究開発で国際レベルのイノベーションを達成するために、企業のみならず行政庁も近くに立地させており、行政上の許可や制度上の問題の調整などがスムーズに行われ、研究からビジネス展開までのスピードが加速することが期待されている。
また、同ヘルスケアキャンパス内に2010年に開校したヘルスケア大学92では、作業療法、言語治療、介護等の分野で職業資格と学位を共に取得できるコースが設けられていることが特徴で、高齢化社会を背景に需要が高まる職業人材を輩出している。
86 NRW州経済省に対するヒアリング調査(アクセンチュア株式会社(2016))、株式会社エヌ・アール・ダブリュージャパンに対するヒアリング調査、及び同州ウェブサイトによる。
87 図中のドイツ州名のうち、NRWはノルトライン=ヴェストファーレン州、BWはバーデン=ビュルテンべルク州、RPはラインラント=プファルツ州、SHはシュレースヴィヒ=ホルスタイン州、MVはメクレンブルク=フォアポンメルン州の略。
88 Siegen, Wuppertal, Essen, Duisburg, Paderborn大学(Siegen大学ウェブサイトより)。
89 http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulen-in-nrw/fachhochschulen-in-nrw-staerken/![]()
90 機械プラント工学、新素材、移動・物流、情報通信、エネルギー・環境科学、メディア・クリエイティブ産業、健康、生命科学の8分野。
91 地域クラスターとは、東大総研によれば、「地理的に近接する産学官の各種主体の集まりであって、その中にノウハウや知見、標準といった価値あるものが蓄積されており、それら構成要素の間に網の目のような情報の流通と協働のための横方向ネットワークが発達した状態」(東大総研(2003))。
③ビジネスマッチングを重視した販路確保及び国際展開支援
ドイツの地域における輸出支援は、その多くがビジネスマッチングを図るものとなっている。国外のビジネスパートナー確保については、国外90か国に駐在するドイツ在外商工会議所が個々の企業ごとにサポートを行っているほか、幾つかの州では国外のコンタクトポイントが地域企業の国外販路確保を具体的に支援している。
また、州レベルの取り組みとして、例えばバイエルン州経済省では、中小企業の輸出を促進するため10を超える様々な取り組みを行っているが、その多くは、国内外の見本市への出展支援や企業のビジネスマッチングを支援するものである(第Ⅱ-3-2-23表)。
第Ⅱ-3-2-23表 バイエルン州による中小企業の輸出促進施策
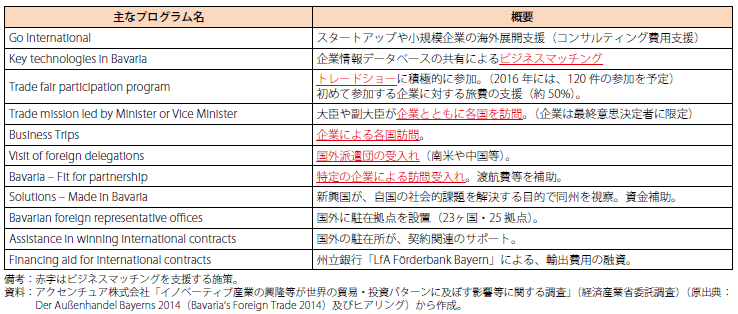
見本市発祥の地であるドイツにおいて、従来、見本市への出展は企業紹介ではなく商談の場と捉えられており、企業からは主に意思決定権者が参加する。IfMBonnによるドイツ企業に対するアンケート調査によれば、輸出における市場を拡大する手段として、全企業の約3割が見本市について重要と回答している(第Ⅱ-3-2-24表)。中でも従業員数が10~49人の小企業においては、その比率が4割と高い。
第Ⅱ-3-2-24表 ドイツ企業アンケート(輸出の市場を拡大する手段)
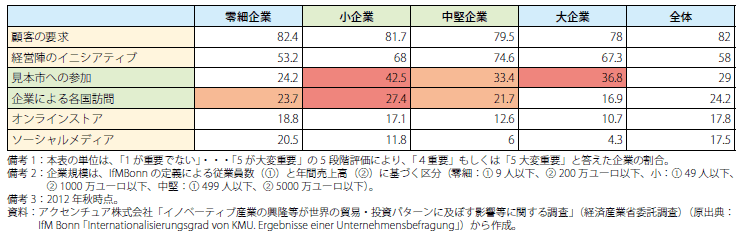
また、企業による国外訪問については、大企業を除いて2割以上が重要と回答している。
国内外の見本市への参加や、企業による国外訪問等に関する支援が、中小企業をはじめとするドイツ企業のビジネスパートナーや販路確保に繫(つな)がっていると考えられる。
なお、ドイツでは地域クラスターもビジネスマッチングの機能を果たしている。
ドイツでは、1990年代よりクラスター政策が開始されており、主要なクラスターは他の欧州諸国よりも早く、概(おおむ)ね1990年代末を中心に設立された。2011年時点では、EUより一定の評価を受けたクラスターの数がEU加盟国の中で最も多く、各地で多くのクラスターが活発に活動している。
2012年に行われた調査を踏まえた欧州委員会のレポート93によれば、ドイツのクラスター経営の重点は、クラスター内におけるビジネスマッチング及び情報や経験の共有、あるいは共同技術開発・技術移転に置かれている比率が比較的高い。
同レポートによれば、ドイツの主なクラスター94の資金ソースは民間割合が6割弱と高く、またそのうち約4割が会員サービス収入となっているが、これらは提供されるサービスの内容が適切であればこそ獲得できるものである。クラスター経営の重点が置かれているビジネスマッチングや情報・経験の共有、また技術移転等において、効率的なサービスが提供されていることを示唆していると考えられる。
なお、ドイツのクラスターでは、公的資金が年々減額されることでクラスターの自立が促される仕組みとなっていることが多く95、そうした仕組みもクラスターによる会員サービスの改善に役立っている可能性もある。
クラスターにおけるビジネスマッチングに関しては、クラスターの運営責任者であり、かつ当該地域・当該業種の企業を広く把握するクラスターマネジャーが、ニーズに応じてクラスター内外のコンタクトポイントを効率的に繋(つな)ぐことが評価されている。
幾つかのヒアリングの内容を踏まえると、クラスターマネジャーは、内外のネットワークの要として企業のビジネス展開を加速するほか、積極的に域外や国外に出かけてネットワーク作りとともに情報収集を行い、会員企業に最新の情報を提供する。
こうした役割を担うクラスターマネジャーは、個人の場合もあれば組織である場合もあるものの、産業界と学術界の経験を有し、中立の立場で、当該業種に関する知見に加えて経営に関する知識も備え、高い営業能力を持つ場合が多いようである。なお、州政府が、クラスターマネジャーの選定や評価を重視する一方で、クラスター運営はクラスターマネジャーに一任されるという例が見られており、クラスターマネジャーの重要性がうかがえる。
また、クラスターマネジャーの他にも、クラスター企業が海外へ輸出・進出する際に必要となるパートナーや顧客へのリーチと、現地の情報取得のためのネットワークを構築しているケースもある。
近年の産業のモジュール化や、大学が持つ知の重要性の高まりといった産業の変化は、企業間における柔軟な横の連携の必要性や、大学や研究機関における企業や外部の専門人材と連携することの必要性を高めている。クラスターマネジャー等により構築されたネットワークは、そうした中で企業のビジネス展開の加速に貢献していると考えられる。
クラスターにおけるビジネスマッチングは、従来は主にクラスター内を重視していたようであるが、近年では、ドイツ連邦政府はクラスターの国際化の重要性を強調している。最近の連邦教育研究省の資料によれば、2016年以降にクラスターの国際化プロジェクトを選抜し、5年間でそれぞれ最大400万ユーロの助成を行うことが公表されている96。州レベルでも、クラスター内部の運営がある程度成熟したことを受け、これまで重点としていなかった国際展開にステージを進めるという形で、最近になってクラスターの国際化を重点に置いたところも見られる97。
93 European Secretariat for Cluster Analysis (2013).
94 同レポートのアンケート調査は、ドイツの優良なクラスターの代表として、Kompetenznetze、及びLeading Edge Clusterから合計60のクラスターを対象としている。
95 Institute for Innovation and Technology (2009).
96 https://www.bmbf.de/de/cluster-netzwerke-international-547.html![]()
97 バイエルン州。
〈事例~バイエルン州のクラスターマネジャー〉
バイエルン州のバイオテクノロジークラスターを運営するBioMは、連邦政府による競争的資金プロジェクト「BioRegio98」で1996年に採択された同州ミュンヘン地域のプロジェクトを実施するため1997年に設立された、ネットワーキングのためのエージェンシーである。2006年以降はそれまでの事業に加えて、州内の5つのバイオテクノロジークラスターを包含する形で新たに設立された「バイエルンバイオテクノロジークラスター」の運営も担当している99。
クラスター運営の主眼が明示的にネットワーク機能に求められている事例と言え、BioMは、ネットワーキングに資する複数の会員向けサービス(国際見本市への参加、クラスター内外企業とのマッチング、関係企業や機関・大学とのネットワークとなるデータベース、経営層や科学者・技術者といった人材の公募ウェブページの提供など)を提供している。
なお、同州におけるクラスター運営は、クラスターマネジャーの知識・経験・手腕及びネットワークに一任されており、クラスターマネジャーの果たす役割は大きい。特にBioMの代表は、産業界の情報に通じ、コミュニケーション能力が高く、ネットワークの要として精力的に活動を行っていると言われている。
高いネットワーク機能と充実した大学や研究機関を背景として、BioMが運営するプロジェクト「”m4-personalized medicine” for the region of Munich 」は、2010年に連邦政府の「Leading Edge Cluster」に認定されたほか、同州のバイオテクノロジークラスターの雇用は、2009年の24,529人から2013年には26,476人に増加している(第Ⅱ-3-2-25図、第Ⅱ-3-2-26図)100。
第Ⅱ-3-2-25図 クラスターマネジャーが繋(つな)ぐ内外ネットワークの例(イメージ図)
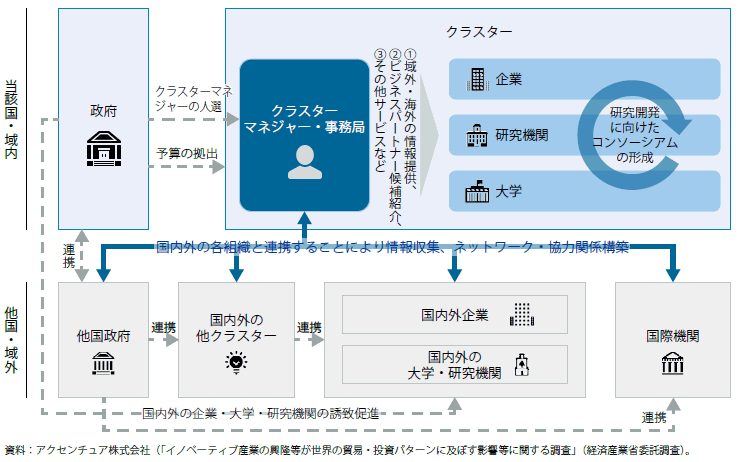
第Ⅱ-3-2-26図 クラスターマネジャーのキャリアモデルの例(イメージ)
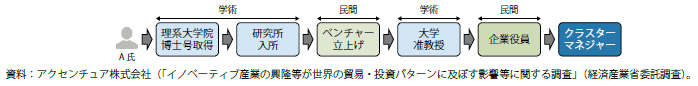
98 ドイツ連邦教育研究省による、バイオ産業の競争力強化を狙いとしたプロジェクトコンペ。既存集積地域3か所が採択された(三菱総合研究所(2014)参照)。
99 BioMウェブサイト(http://www.bio-m.org/en/about-biom/history.html![]() )。
)。
100 Cluster Biotechnology Bavaria (2014)、及びBioMに対するヒアリング調査(アクセンチュア株式会社(2016))による。
〈事例~ハンブルク市クラスターの「パーソナライズド・アンバサダー」制度〉
ハンブルグ市はベルリンと同じく、市一つで州と同じ権限を持つ「特別市」である。ハンブルグに立地するエアバスの最終組立て工場を中心として、多数の企業が集積し、大規模な航空産業クラスターが立地しており、航空機関連が輸出の半分以上を占めている。
航空機関連産業がけん引する同市に立地する再生可能エネルギークラスターは、2010年に設立された。大学・研究所が隣接し、再生可能エネルギーに係るR&Dやサービス拠点が集積する地域性を活(い)かしたクラスターであり、約180の企業・大学・研究機関等が在籍している(平成27年2月時点)。
同クラスターは、以前から世界各国とのネットワークづくりを積極的に推進しているが(2012年には15か国、30の派遣団を受入れ)、これらの派遣団を通じて、2013年にクラスター企業の輸出促進を図るため、パーソナライズド・アンバサダー制度(Personalized Ambassador。以下「PA」という。)を構築した。
PAは、国外に駐在所を設けるのではなく、ハンブルクと何らかの繋(つな)がりのある人が、国外においてハンブルクとのネットワークの接点となる制度であり、58か国・35名から成る(2016年2月時点)。これによって、クラスター企業が他国へ輸出・進出する際に必要となる現地パートナーや顧客へのアクセスと現地の情報取得を容易にしている。アンバサダーの活動をサポートし、またハンブルクとの繋(つな)がりを継続するためとして、年に一回、ハンブルクにおいてアンバサダーを集めたミーティングが実施されている。
なお、同市では、市場動向は常に急激に変化するとの考えに基づき、ターゲット市場は決めておらず、再生可能エネルギークラスターのアンバサダー制度についても、多くの国と偏りなくネットワークを持つことによるリスク分散がその目的の一つとなっている。輸出品は航空機関連が半分以上を占めている一方で、輸出先については、EU域内のみならず、中東やアジア等にも広がっている(第Ⅱ-3-2-27図)101。
第Ⅱ-3-2-27図 ハンブルグ市の主な輸出先
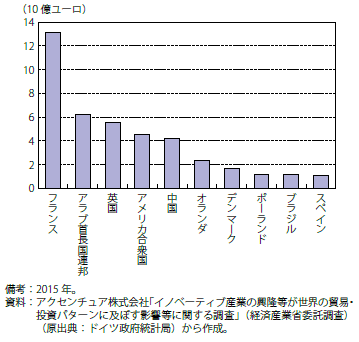
101 自由都市ハンブルク経済・交通・イノベーション省に対するヒアリング調査(アクセンチュア株式会社(2016))による。
(3)ドイツの高度外国人材の活用
本節では、我が国の地域における財の輸出について考察した。ドイツの各州における輸出との比較では、ドイツの各州それぞれが輸出を伸ばしつつ、一極に集中しない地域経済が創出されている状況について指摘してきた。そのような中、ドイツの地域経済に貢献する企業の輸出を支える要因として、前節では産業構造の転換や大学や研究機関の在り方、企業の集積、ビジネスマッチングといったドイツの取組について考察した。これらに加えて、ドイツの産業を支える大きな要素に「産業における高度外国人材の獲得」があると考えられる。
第2部第1章にて、高度外国人材の獲得に関する我が国および各国の状況や取組の比較について紹介したが、ドイツは非英語圏のなかでも多くの高度外国人材の獲得に至っている。産業における高度外国人材の獲得については、国内の人材を育成する、または国外から高度外国人材を呼び込むという2つのパターンが考えられるが、ドイツでは国外から高度外国人材を呼び込むという2つ目についても、比較的積極的に取り組んでいる傾向にあることが伺える。
ここでは、これらの背景を踏まえ、ドイツにおける高度外国人材の呼び込みに関する取組に至った背景や現状をもとに、特色ある制度の活用、公的研究機構の人材戦略、大学の国際化といった事例について考察し、我が国への示唆を得る。
①高度外国人材獲得の気運の高まり
前段で述べたように、国境を超えた人材の流動性の高い欧州においても、ドイツは特に高度外国人材の獲得に成功していると言われている。ここでは、それに至るまでの背景について述べる。
欧州では、第二次世界大戦後、戦後復興のため急激に高まった労働需要に対応すべく、ドイツや英国、フランスを中心に移民の受け入れが行われた。この際、言語面において対応のままでいいですが可能であるといった理由から、旧植民地諸国からの移民が相次いだ。これに対して、1970年代のオイルショック時の景気後退を機に停止処置がとられた。
停止処置が緩和されはじめたのは1990年代後半のことである。ドイツはおいては1998年に成立したシュレーダー政権によって、高度外国人材の受け入れの方針が出され始めた。この傾向は、国際化が進展し、企業における「人材のグローバル化」が求められるようになったこと、各国において一部の職種や高度な専門的職種において労働需要が高まったこと等が原因であるといわれている。
2000年代には、移民法を制定することで滞在資格等を整備し、移民難民庁を設置することにより外国人や移民に関する業務を集約させ、より円滑な外国人の呼び込みを目指した。2008年には、ドイツ版「グリーンカード」省令を導入し、欧州でも先駆けてIT技術者の獲得を促進した(第Ⅱ-3-2-28表)。
第Ⅱ-3-2-28表 欧州の外国人受け入れ政策の変遷
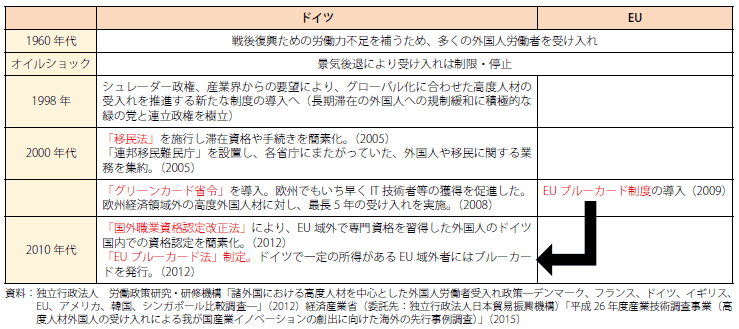
これらの改正は、ドイツへ渡る高度外国人材を増加傾向にさせた要因のひとつと考えられる。シュレーダー政権においては人材受け入れに関する産業界からの要望があったことや、実際に人材を呼び込むにあたって企業において需要があること等が要因として指摘されている。
(a) 高度外国人材の需要の上昇
第2部第1章第3節で確認したように、ドイツは非英語圏のなかでフランスと並ぶ受け入れ水準にある。これは、前段で確認した欧州における制度改革の時期と重なっている(再掲第Ⅱ-1-2-1図)。
第Ⅱ-1-2-1図 高等教育修了者の流入人口の推移(対人口比)
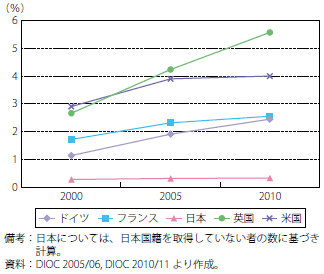
高度外国人材を国外から獲得することにより、ドイツの産業における高度分野の人材は補われている可能性が考えられるが、輸出企業に関していえば今後も高度人材の需要増加が予想されている。
第Ⅱ-3-2-29図を見てみよう。これはドイツ商工会議所(DIHK)によって行われている輸出企業調査の結果であり、「経済的に成長するために、最も大きなリスクは何か(Biggest risks for the economic development)」という問いに対する回答をまとめている。2011年2月の調査では、「高度外国人材の不足(lack of skilled workers)」について指摘した企業は全体の約30%であり、選択項目のなかでは少ない回答数であった。他方、2016年2月の調査をみると、「高度外国人材の不足」は43%まで上昇した。これは、多くの企業において高度人材の不足が最も重要な課題のひとつとして認識されるようになっており、その需要は高度外国人材にも影響する可能性がある。(第Ⅱ-3-2-29図)。
第Ⅱ-3-2-29図 高度外国人材受け入れ要望に関する輸出企業への調査
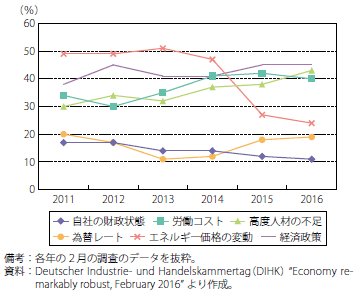
ドイツ企業における高度外国人材の需要について確認するため、ドイツ連邦経済エネルギー省(the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy)が運営する高度外国人材のためのポータルサイト「Make it in Germany」を見てみると、高度外国人材の採用を希望する多数の求人情報が掲載されている102。
102 Make it in Germany〈http://www.make-it-in-germany.com/en![]() 〉は、ドイツ経済エネルギー省によって運営されている高度外国人材、彼らの採用を希望する企業のためのポータルサイト。「Mechanics, energy and electronics」や「IT, data processing, computing」といった7種(さらに詳細に検索することも可能)の業種によって求人情報を検索できる。また、検索の際には104の言語に自動翻訳することができる。
〉は、ドイツ経済エネルギー省によって運営されている高度外国人材、彼らの採用を希望する企業のためのポータルサイト。「Mechanics, energy and electronics」や「IT, data processing, computing」といった7種(さらに詳細に検索することも可能)の業種によって求人情報を検索できる。また、検索の際には104の言語に自動翻訳することができる。
(b) 幅広い分野からの留学生の呼び込み
ドイツにおける高度外国人材の呼び込み増が予想されるなか、高度外国人材の卵として留学生の呼び込みと定着の重要性が指摘されている。
第Ⅱ-3-2-30図は、ドイツの高等教育機関(大学、大学院、専門大学含む)において、夏セメスター、冬セメスターの1年間通した在籍人数をドイツ国籍、外国国籍に分けて外国人学生比率を算出した。ドイツでは、この10年間で外国人学生比率が10%に近くまで上昇しており、多くの外国人留学生を呼び込めていることが伺える(第Ⅱ-3-2-30図)。
第Ⅱ-3-2-30図 ドイツにおける大学生・大学院生・専門大学生の外国人学生比率
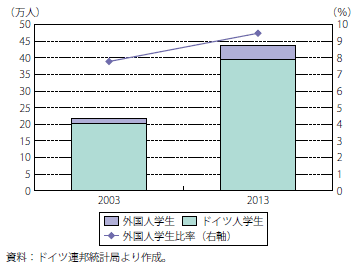
さらに、ドイツの外国人留学生の構成について考察する。ヒトの移動において、欧州およびEUという地理的、環境的なハードルの低さはあるものの、ドイツへ流入する留学生はアジア(32.7%)やアフリカ(8.3%)、中南米(5.1%)出身の学生も多く、欧州(43.6%)にとどまらない幅広い構成となっている。また、専攻別にみてみると、人文科学(19%)、社会科学(26%)に加え、工学・建築学(25%)、理学(15%)といった理系分野を専攻する学生も多い。理系の留学生は、将来的に調査・研究分野やイノベーションに貢献しうるとされており、そのような学生の呼び込みにも成功していることがわかった(第Ⅱ-3-2-31)。
第Ⅱ-3-2-31図 ドイツの外国人留学生の構成(国籍別・専攻別)
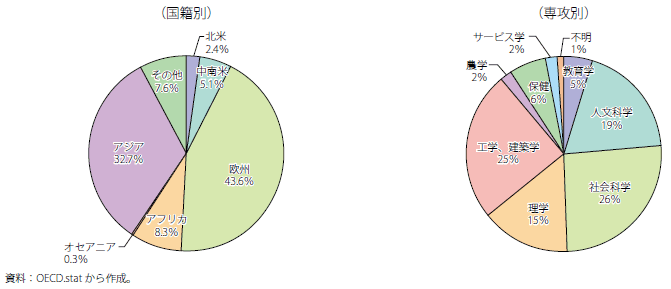
以上のように、ドイツでは幅広い国籍、分野の学生の呼び込みに成功している。多様な国籍や、幅広い専攻の学生を呼び込むことは、企業における様々な人材需要に対応できる可能性が高まると考えられる。
「統合と移住のためのドイツ諸財団専門家協議会」の調査によると、ドイツに留学し、修士課程で学んでいる留学生のうち約80%、博士課程の学生のうち約67%が、卒業後もドイツに残り、就職したいと回答している(第Ⅱ-3-2-32図)103。
第Ⅱ-3-2-32図 ドイツと日本における留学生の定着意思
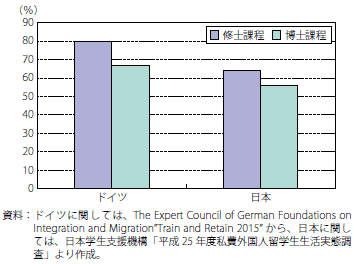
前述の報告書104によれば、9割以上の企業が中程度~高度なスキルを持った外国人を採用した経験があるとされており105、ドイツにおける豊富な高度外国人材を含めた労働市場と、彼らを雇用する企業方針が見て取れる。
以上のことから、ドイツにおいては多くの高度外国人材や高度外国人材の卵である高等教育機関の留学生を呼び込み、彼らを企業が採用していることがわかった。高度な頭脳を獲得することは、ドイツの産業にとって、グローバル化する競争への対応を容易にしたり、新たなイノベーション創出へのきっかけになる可能性があると考えられる。
103 EU域外出身の留学生に対する調査。
104 DIHK(2016)
105 Economy remarkably robust, February 2016, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
②人材の獲得および活用に向けたドイツ国内の取組
前段で確認したように、すでに専門知識を持つ高度外国人材に加え、今後期待される留学生まで獲得が促進されていることが分かった。ここでは、そのような人材獲得に向けたドイツにおける取組について紹介する。
(a) 人材の定着に繋がる在留制度の活用
欧州においては各国がそれぞれ人材獲得の戦略に取り組み始めた。その後、EU全体で人材獲得についての取組が検討されるようになり、設定されたのがEUにおけるブルーカード制度である106。EUブルーカードは、EU域外者に向けて発行される在留資格制度である107。
この制度を利用するため、各国では国内法を整備する必要がある。ドイツでは、2012年にEUの高資格外国人労働者指令を実施する法律108が整備され、制度利用者が大幅に増加した。EUにおけるブルーカードの発行件数を見てみると、2012年のドイツにおけるブルーカード発行数は2,584件であり、2013年には11,580件に増加している。これは、EUにおける全体の発行件数のうち、約9割をドイツで発行していることを示している(2013年は約89%、2014年は約87%であった)(第Ⅱ-3-2-33図)。
第Ⅱ-3-2-33図 EUブルーカードの発行件数(国別)
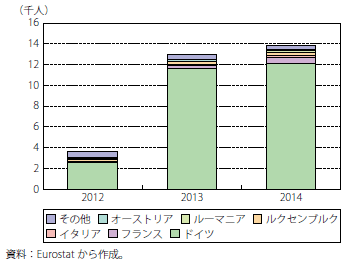
ドイツにおけるEUブルーカードの発行条件は以下のとおりとなっている109。
①大学卒業以上の学歴を有すること。ドイツの大学を修了するか、それに相当するような海外の大学を修了する必要がある。
②一定の収入があること(年収49,600ユーロ以上、2016年3月現在)
③数学、IT、自然科学、工学を専門にした高度外国人材や医師などは、特に高度外国人材の受け入れを強化すべく、一般よりも低い年収を設定している。(年収38,688ユーロ以上、2016年3月現在)
この「EUブルーカード」の制定により、特に恩恵を受けたのはドイツ域内の高等教育機関を卒業したEU域外者である。卒業後、ドイツ国内における就職には在留制度の条件を満たす必要があったが、ブルーカードにより、在留資格の取得およびドイツへの定着が容易となったことにより、それまでとりこぼしていたドイツの外国人材を定着させる効果が期待される。また、卒業後の求職期間も12ヶ月から18ヶ月に延長されている。
ドイツ移民・難民庁の調査110において、ドイツの留学生がブルーカードを取得する傾向にあることが示されている。ドイツにおける元留学生の追跡調査を行ったものであり、人材不足分野で取得されたEUブルーカードの40.5%の取得者が元留学生であった。卒業後、見通しをもって就労することができる同制度は、留学生のドイツへの就職、定着を増加させる一因となっていることが示唆される。(第Ⅱ-3-2-34表)
第Ⅱ-3-2-34表 ドイツの高度外国人材在留資格保有者に占める元留学生の割合111
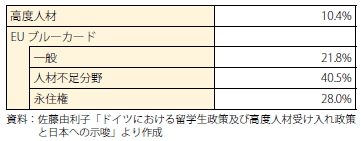
また、留学生の在留条件について、大学在学中の副業制限が年間90日から120日に緩和され、副業の拡大が卒業後の定着に結びつくように配慮されたことも特徴であるといえる。
106 高資格外国人労働者指令 COUNCIL DIRECTIVE 2009/50/EC
107 渡辺富久子「【ドイツ】 EUの高資格外国人労働者指令を実施する法律」(http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3507785_po_02520109.pdf?contentNo=1![]() )
)
108 BGBl. I S.1224
109 ドイツ連邦外務省(Federal foreign office) HPより。 http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/120731-BlueCard-node.html![]()
ブルーカードはEU域外出身者に対して発行されているため、域外出身者である必要がある。
110 Hanganu & Hess 2014
111 「人材不足分野」とは、数学、IT、自然科学、工学を専門にした高度外国人材や医師などの分野を指し、EUブルーカード取得のための年収要件が緩和されている等、特に高度外国人材の強化が計られている。
(b) 産官学の連携と人材の流動化
ドイツにおける人材獲得について、公的研究所であるフラウンホーファー研究機構について紹介する。
ドイツのフラウンホーファー研究機構は、公的研究機関のひとつで全世界に支部を持つ。応用研究機関として、研究成果の実用化やスピンアウト・ベンチャーの創出、若手研究人材の産業界への供給など、産業界と学会を結びつける触媒としての機能を果たしている。約24000人のスタッフが従事しており、あらゆる科学技術分野における応用研究でドイツの中小企業や海外の企業、大学とも連携している。イノベーション創出に貢献しているとして2015年も3年連続でトップ100グローバルイノベーターに選出された。
同研究機構においては、「社会に役立つ実用化のための研究」を行うことを理念としており、応用研究・開発における実用的な成果を創出すべく様々な人材の獲得及び輩出にも貢献している。例えば、全体の勤務者の約30%は若手人材もしくは若手研究者であり、大学生を対象としたインターンシップへも積極的に取り組んでいるほか、海外にも目を向けており、海外の研究者の受け入れも歓迎している。さらに、同研究機構では、マーケティングなどを行う駐在所と、研究を行うプロジェクトセンターを国内外に設置している。駐在所のメンバーは、同研究機構と産業界、アカデミックの世界との橋渡し役を担っており、プロジェクトセンターは地域の大学にて研究を行い、同研究機構との橋渡し役を担っている(なお、本内容は、経済産業研究所岩本晃一上席研究員の「『独り勝ち』のドイツから日本の『地方・中小企業』への示唆―ドイツ現地調査から―」のP16~17 に詳しいため、参照されたい)。
こうした産業界およびアカデミック分野とのつながりの創出は「人材の流動化」を促進し、より高度な人材の育成や確保に貢献していると考えられる。また、魅力ある研究環境や将来的に活かせるキャリアづくりへのサポートは、国内外の研究者を呼び込む材料となる可能性がある(第Ⅱ-3-2-35図)。
第Ⅱ-3-2-35図 フラウンホーファー研究機構の人材構成
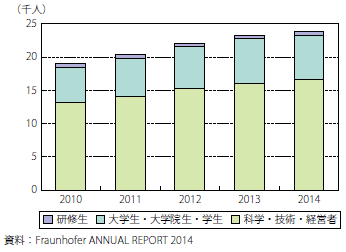
(c) 大学における留学生受け入れ体勢の強化
これまで、在留資格の改善、研究機構の活用について紹介したが、ドイツでも課題が指摘されている。将来高度外国人材となりうる留学生の獲得に関しては、実際に受け入れを行う大学の取組が重要となってくる。
ここでは、留学生の呼び込み環境を整備する取組を積極的に行っている、ミュンヘン工科大学(Technische Universitat Munchen : TUM)の国際化への取組について紹介する。
ミュンヘン工科大学は、ドイツの「エクセレント・イニシアチブ」 に選ばれた名門校であり、理系人材の育成や研究開発の促進に注力する総合大学である。学生のうち、22%は海外出身の学生であり、中国やインドを中心としたアジアに加え、イタリア、トルコやギリシャ、イランなどからも学生を受け入れている(第Ⅱ-3-2-36図)。
第Ⅱ-3-2-36図 ミュンヘン工科大学の学生構成
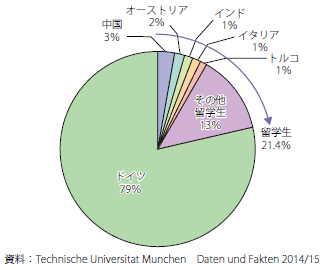
TUMにおいては、大学自身の海外オフィスが北京、ムンバイ、カイロ、サンパウロ、サンフランシスコなど世界各国に設置されており、ドイツへの留学に関するリクルーティングなど、大学と海外の直接的なコンタクトポイントとなっている。また、北京では、入学試験等が実施されている。
また、在学中の留学生へのケアやサポート、特別な取組を実施することは、在学中及び卒業後の学生の質を高め、大学のイメージの向上につながる可能性がある。
TUMでは留学生に対して、語学などの事前準備コースや個別指導、また、住居の探索なども含め、ミュンヘンで暮らし始めるためのサポートなどを行う「バディプログラム」など様々な留学生向けサービスを提供している。バディプログラムでは、このプログラムをサポートするドイツ人学生に対して、大学側から文書でその貢献を証明することで、ドイツ人学生のサポートを促進している。また、ドイツ人学生も積極的に留学生向けのアクティビティを企画するなど、大学側とドイツ人学生側双方から留学生のケアを行っている。
留学生にとって課題のひとつとなるのが言語スキルであるが、TUMの場合、大学院の講義は多くが英語で実施されており、また、ほぼすべての教授が国際経験を積んでいるなど、グローバルな人材をそろえている。
③まとめ
ここでは、ドイツの産業を支える高度外国人材の獲得について、その背景から現状、獲得のための取組について確認した。多数の高度外国人材を呼び込むことは、彼らの出身国とのビジネスを円滑にしたり、多様な人材の交わりを創出し、今後のグローバル競争に勝ちゆくイノベーションのきっかけとなる可能性もあるとされる。我が国においても、企業の国際進出に伴うグローバル人材の需要は高まっており、高度外国人材の獲得については、今後も議論すべき課題と考えられる。
また、彼らが定着するための制度づくりを行い、彼らが活躍するために企業の雇用環境が整うこと、さらに、多くの高度外国人材を惹きつける魅力ある国づくりが求められる。
(4)我が国へのインプリケーション
ドイツでは、ほぼ全ての州において多様な業種の輸出が伸びているが、それは各地域における産官学連携等を通じたイノベーション環境の整備や、中小企業に対するビジネスマッチングを重視した販路確保の支援に支えられている。また、特定の業種に依存せず、将来の地域の強みとなるような分野を選択し注力していくことが地域経済の持続的発展に必要との考えが、輸出における競争力の維持にも役立っていると考えられる。また、多数の高度外国人材を呼び込むことが、グローバル競争において、イノベーションと販路確保の両面を支えている可能性がある。
我が国においても、中小企業に対するアンケート調査によれば、現地パートナー企業や商社等の確保が、輸出の際に直面する第一の課題とされており、ビジネスマッチング等による販路確保の支援の必要性が確認できる(第Ⅱ-3-2-37図)。
第Ⅱ-3-2-37図 我が国の輸出企業が直面している課題(2015)
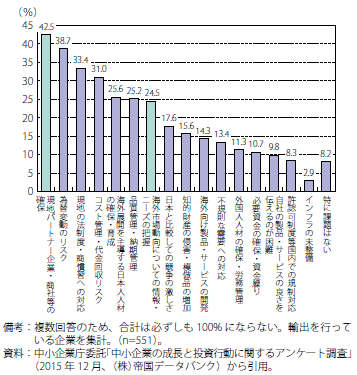
また、輸出が伸びた企業群と伸びていない企業群に占める項目別の外部委託比率の差を見ると、どの項目においても中小企業では両企業群での差は大きくない。一方、研究開発の外部委託については、大企業では両企業群の差が大きく、また大企業と中小企業との差も大きい(第Ⅱ-3-2-38図)。一般に、経営資源が限られる中小企業では、研究開発にあたって顧客や大学等の外部リソースを活用することの有用性が指摘されているところである112が、輸出に際しても、変化の速い世界市場の需要を獲得するため、研究開発における大学等の外部リソースの活用を促進する必要があると考えられる。
第Ⅱ-3-2-38図 我が国の輸出が伸びた企業と伸びていない企業における、委託比率の差
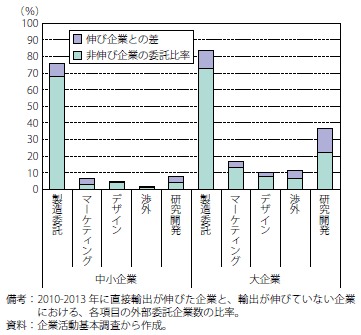
グローバル需要の獲得は、内需が縮小傾向にある地方経済の発展に貢献する可能性がある。地域の潜在力をうまく活かすことで、多様な業種における輸出が拡大することを期待したい。
112 中小企業庁(2009)。