第3節 輸出ポテンシャルの高い企業群へのアプローチ
1.商社・卸売業者を活用した地域の移輸出力の向上
地域の活性化のためには、地域資源や地域のノウハウをいかに移輸出に結びつけて域外から「外需」を獲得するかが重要となる。その際、相対的に生産性が低く、資金力や域外市場の情報にも乏しい地域の中小企業をはじめとした企業の多くにとって、商社・卸売業者の活用は重要なポイントとなる。
一般に商社・卸売業者は、移輸出に伴う様々な経費を負担し、また、内外に展開する販売ネットワークを通じて域外市場の最新の情報を入手できる。したがって、資金力が乏しく販売力も低い中小企業者にとっては、商社・卸売業者を活用することで自社製品・サービスの顧客を大きく増やすことができる可能性が高まる。特に、国内市場の成長が見通しにくい中、成長が見込まれる海外市場への輸出は、地域の中小企業者にとって大きな成長のチャンスとなる。
しかしながら、中小企業者による移輸出、特に、国内向けと比較し経費負担が大きく販売先の情報を得ることも困難な海外市場への輸出(直接輸出)を行っている中小企業の数は伸び悩んでいるのが現状である(第Ⅱ-3-3-1図)116。
第Ⅱ-3-3-1図 輸出を行っている中小企業(製造業)の数
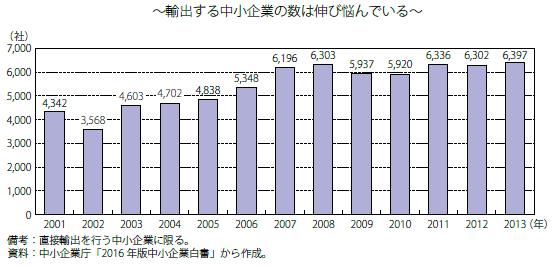
このように輸出企業数が伸び悩んでいる要因としては、例えば、中小企業者にとって自社製品・サービスの販売に興味を示してくれる商社・卸売業者を見つけることが難しいことや、たとえ自社の製品・サービスに興味を示してくれる商社・卸売業者が見つかっても販売価格・数量や仲介手数料などの条件面で折り合えないなどといったことが考えられる。
そこで、以下では、商社・卸売業者を活用することのメリット・ディメリットを理論的に整理した後、中小企業者へのアンケート調査に基づいて、地域の中小企業者が商社・卸売業者の活用によって実際に海外市場への輸出が可能となった例はあるのか、商社・卸売業者を活用するとどのような経費が削減できるのか、中小企業者は商社・卸売業者の活用に関してどのような課題に直面しているのかなどを明らかにする。
商社・卸売業者は貿易取引において重要な役割を果たしている。
一般に、製造業を営む企業(製造業者)が海外へ商品・サービスを直接輸出しようとする場合は、新たに海外市場に自社製品・サービスの販売ネットワークを構築するために相応の固定費を支出しなければならない。
他方、商社・卸売業者はこのような一般の製造業者とは大きく異なる機能を有している。これは「範囲の経済(Economies of scope)」と呼ばれている。
「範囲の経済」は企業活動に係る「経済性」を表す指標の一つで、企業が複数の事業を同時に行ったり、異種の商品・サービスを同時に扱うことで、より経済的に事業を行うことができることを指す117。この場合、異なる商品・サービス間で経営資源を共有することによって生ずるメリットが、異なる商品・サービスを扱うために生ずる追加的コストを上回れば、範囲の経済が成立することになる。輸出を仲介する商社・卸売業者の場合、既に保有している輸出ネットワークがこの共有可能な経営資源に相当する。商社・卸売業者は既に扱っている商品・サービスの輸出ネットワークを利用して新しい商品・サービスを流通させることができるから、追加的な費用をほとんど生じさせずに、売上だけを増加させることが可能となる。
これを製造業者の側から見ると(第Ⅱ-3-3-2図)、自ら輸出しようとする場合(直接輸出)には、輸出ネットワークを構築するための固定費(図では▲FX )を負担しても利益が確保できるだけの高い生産性を有する企業しか輸出できない。図では、直接輸出企業の営業利益曲線Πxが横軸と交差する点ΦYより右側に生産性の水準が位置する企業だけが輸出を行うことができる。それ以外の企業(図ではΦYより左側に生産性が位置する企業)は、直接輸出に伴う固定費を差し引くと営業利益がマイナスとなってしまい輸出では利益が得られない118。
第Ⅱ-3-3-2図 直接輸出と間接輸出
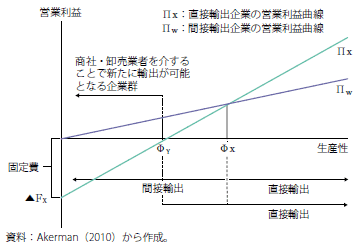
他方、商社・卸売業者を介して輸出しようとする場合(間接輸出)は、輸出ネットワークを構築する固定費▲FX が不要となる結果、それまで輸出することができなかった相対的に生産性の低い企業であっても輸出が可能となる。図では、営業利益曲線がΠxからΠWにシフトすることで、ΠxとΠWが交差する点Φxより左側に生産性が位置する企業は間接輸出によってより多くの利益が確保できるようになる。特にΦYより左に位置する企業群は、それまで生産性が低いため直接輸出では全く利益が確保できなかった企業群であり、商社・卸売業者を介することではじめて利益が確保できるようになり輸出が可能となる企業群である。なお、間接輸出企業の営業利益曲線ΠWの傾きが直接輸出企業の営業利益曲線Πxよりも緩やかなのは、間接輸出の場合、商社・卸売業者へ支払う仲介料が発生し、その分営業利益が減少するためである。
では、こうした理論モデルは、実際の企業活動の現場においても成立しているのであろうか。以下では、統計データやアンケート調査などを使ってこの理論モデルの実証を試みる。
第Ⅱ-3-3-3図は、我が国の工業統計調査を使って、全国の製造業事業所の労働生産性の分布を表したものである。これを見ると、輸出を行っている事業所の分布が、輸出を行っていない事業所の分布の右側に位置しており、平均値で見たときの事業所の生産性は、直接輸出を行っている事業所の方が、直接輸出を行っていない事業所を上回っていることが分かる。
第Ⅱ-3-3-3図 輸出と労働生産性(1)
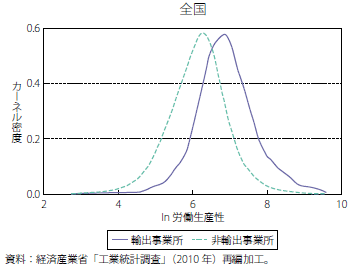
さらに、今回は、全国の中小企業約30,000社へのアンケート調査を行い、間接輸出も含めた輸出と労働生産性の関係をより定量的に検証することも試みた。
第Ⅱ-3-3-4表はその結果である。
第Ⅱ-3-3-4表 輸出と労働生産性(2)
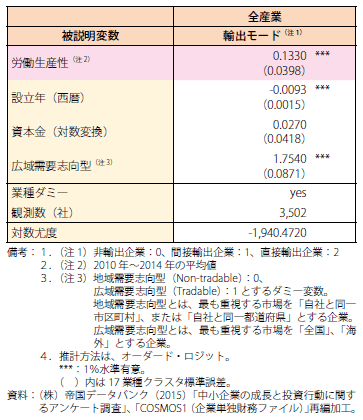
アンケート調査中、直接輸出企業の数は回答企業約4,600社中わずか470社あまりであるが、間接輸出企業の数を含めると輸出企業の数は全体で900社近くに達する。
推計では、アンケート調査結果に基づいて各企業を非輸出企業、間接輸出企業及び直接輸出企業の3群に分け、これを労働生産性、設立年、資本金などに回帰するオーダード・ロジット分析を行った。
結果を見ると、労働生産性の係数は正で統計的に有意となっており、労働生産性が高くなるに従い、非輸出企業から間接輸出企業へ、間接輸出企業から直接輸出企業へと輸出モードが変化する傾向があることが示されている。
このことは、商社・卸売業者を介することで、中程度の生産性の企業が輸出できるようになることを示しており、輸出と生産性の関係を表す第Ⅱ-3-3-2図のモデルが実際の企業行動によっても裏付けられたと言える。
では、商社・卸売業者を活用することで輸出企業が得られるメリットには具体的にどのようなものがあるのであろうか?アンケートでは、商社・卸売業者を活用することで節約できた費用や得られたメリットなどについて詳細な質問を行った。さらにアンケートでは、商社・卸売業者を活用していないとする企業群に対しても、活用していない理由を尋ねて、商社・卸売業者の活用を促進する際の課題等を明らかにした。
まず、商社・卸売業者を介することで節約できた費用の内訳を見ると、多くの中小企業が、現地販売拠点・サービス拠点の設置費用といった固定費だけでなく、現地での販売促進等のマーケティング経費をはじめとする各種経費が節減できたとしている(第Ⅱ-3-3-5図)。特に、現地販売拠点・サービス拠点の設置費用は回答企業の7割以上がほとんど若しくはかなり節約できたとしている。
第Ⅱ-3-3-5図 節約できた費用とその割合
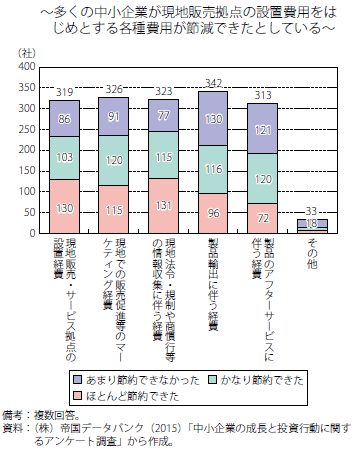
また、得られたメリットについては、製造業でおよそ5割の企業が、商社・卸売業者を介することで新たな輸出先が得られたとしている(第Ⅱ-3-3-6図)。また、輸出仲介を行っていない中小卸売業者においても、輸出仲介を行っている商社・卸売業者を介することで、約4割の卸売業者が新たな輸出先が得られたとしている。
第Ⅱ-3-3-6図 商社・卸売業者を介することによる新たな輸出先の確保
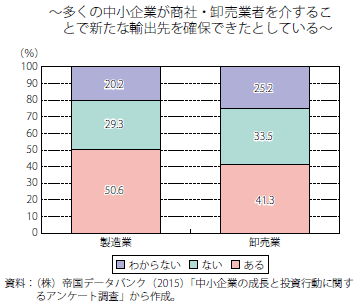
このように、商社・卸売業者を介することで、多くの中小企業が費用や顧客獲得の面でとメリットがあったとしていることが分かった。
他方、こうして商社・卸売業者を活用して一定の成果を挙げている企業が存在する一方で、商社・卸売業者を活用することができていない企業も多数存在することも事実である。今回のアンケート調査でも、回答企業4,600社のうち約3,700社が直接輸出も間接輸出も行っていなかった。その一方で、第Ⅱ-3-3-3図で見たように、直接輸出している企業の平均的な生産性の水準を上回っている非輸出企業も一定程度存在することも事実である119。
第Ⅱ-3-3-7図は、これらの非輸出企業に対して商社・卸売業者を活用しない理由を尋ねた結果である120。これを見ると、活用しない理由として最も多かったのは「自社に適した商社・卸売業者を見つけられない」とするもので全体の4割近くに達している。次いで、「仲介料が高額」、「生産量・価格などの条件で折り合えない」などとなっている。これまで商社・卸売業者を介した自社製品の輸出を試みた非輸出企業の多くが、結局、自社に適した商社・卸売業者を見つけられずに断念している実態が浮かび上がってくる。
第Ⅱ-3-3-7図 輸出に商社・卸売業者を活用しない理由(製造業)
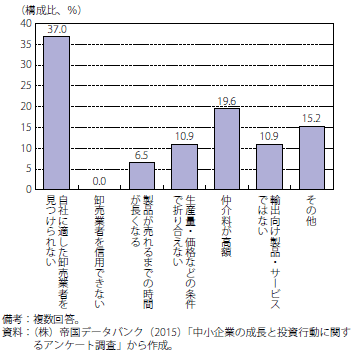
116 ここでは、データの制約から、直接輸出を行っている企業のみを集計している。
117 経済性にはこのほか「規模の経済」や「密度の経済」がある。
118 従来の貿易理論に企業の異質性を取り入れたいわゆる新々貿易理論を提唱したMelitz(2003)によれば、貿易を通じて海外との競争にさらされている産業では、最も生産性の高い企業が輸出を行い、より低い生産性の企業は国内市場向けにのみ生産を行うとしている(メリッツ・モデル)。そして、最も生産性の低い企業は市場から退出させられるとしている。ここで紹介するモデルは、このいわゆるメリッツ・モデルに商社・卸売業者を明示的に取り入れて拡張したものである。
119 戸堂(2011)では、こうした企業のことを「臥龍企業」と呼んでいる。
120 得られた回答のうち、商社・卸売業者を活用しない理由として、直接輸出または国内販売で十分収益が確保できているからと回答した企業は集計から除いてある。
2.輸出ポテンシャルの高い非輸出企業群
次に、生産性の観点から輸出ポテンシャルが十分にあるものの、実際には輸出至っていない企業群が業種別、地域別にどの程度存在するのかについて検討する。
前項において論じたとおり、企業が輸出をするに際しては一定の費用を負担する必要があることから、生産性が一定程度以上の企業でないと輸出ができないことが理論的には論じられている121。しかしながら現実には、同等の生産性を有する企業であっても、輸出の有無は分かれるところであり、輸出企業よりも高い生産性を有する企業であっても、経営判断により輸出しない場合もある。
本項では、前項と同様に工業統計の個票データ122を用い、業種別・地域別、に非輸出123事業所であっても輸出をおこなっている事業所の平均的な生産性124を超える生産性を有する者を特定するとともに、こうした輸出ポテンシャルの高い非輸出事業者が業種別・地域別にいかに分布しているのかについて分析する(第Ⅱ-3-3-8図)。
第Ⅱ-3-3-8図 輸出ポテンシャルの高い非輸出事業者(黄色部分)
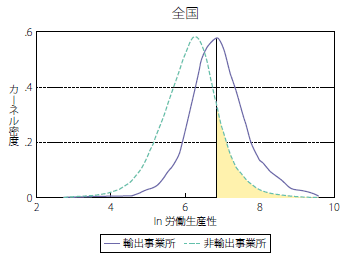
121 いわゆる新々貿易理論でいうところの「メリッツモデル」。
122 本項の執筆に際しては、2014年のデータを用いた。
123 データの制約から直接輸出に係るデータを用いた。
124 従業員一人当たりの付加価値を用いた。
(1)業種別分布
まず、業種別125に全事業所を直接輸出の有無により「輸出事業所」及び「非輸出事業所」に分類した上で、各業種における「輸出事業所」の平均生産性との比較において、「非輸出事業所」を「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」と「その他事業所」に分類するとともに(第Ⅱ-3-3-9表)、各業種の全事業所に対する比率を求めた(第Ⅱ-3-3-10図)。
第Ⅱ-3-3-9表 直接輸出の有無及び生産性による事業所の分類(業種別)
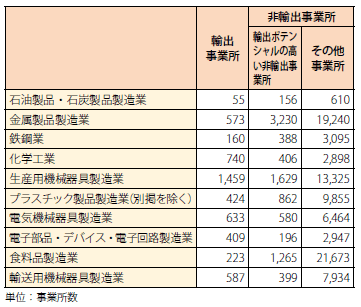
第Ⅱ-3-3-10図 全事業所に占める「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」比率(業種別)
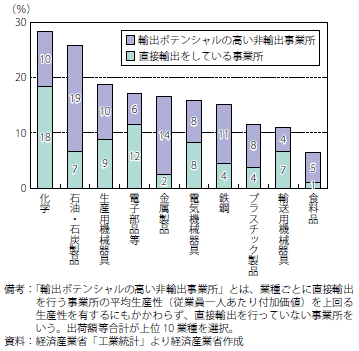
その結果、「石油製品・石炭製品製造業」や「金属製品製造業」において輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所の比率が高いことが分かった。また、食料品製造業は、現に直接輸出を行っている事業所は全体の1%に過ぎないが、その5倍程度の輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所が存在することが分かった。
125 ここでは出荷額等合計から上位10業種を選び分析をおこなった
(2)地域別分布
次に、国内の地域別に同様の分類・分析を行った(第Ⅱ-3-3-11表、第Ⅱ-3-3-12図)。その結果、特に北海道において輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所が数多く存在することが分かったが、全国の全ての地域において、現に輸出している事業所よりも多くの数の事業所が「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」として位置づけることができることが分かった。
第Ⅱ-3-3-11表 直接輸出の有無及び生産性による事業所の分類(地域別)
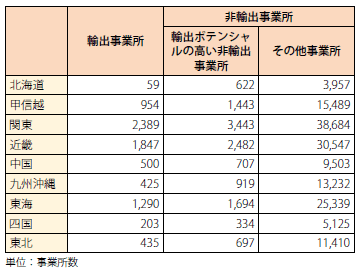
第Ⅱ-3-3-12図 全事業所に占める「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」比率(地域別)
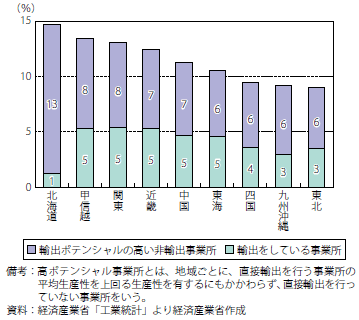
(3)まとめ
生産性が高く輸出ポテンシャルを有しているものの、実際には輸出に踏み切っていない事業所は、全ての業種・地域において相当数存在し、輸出の裾野拡大の余地はまだまだ高く、特に地域別では北海道、業種別では石油関連や金属製品製造業において高いことが分かった。
一方、こうした事業者に対して如何なるきっかけが与えられると輸出に踏み切るのかまでは本分析では示すことができていない。例えば、経営者の考え方により左右される面もあれば、事業所ごとに、国内外への供給について役割分担を設定している場合もあるであろう。個別の業種、地域ごとに、特有の課題もあると考えられるが、本分析は輸出裾野拡大に関する施策に関して、地域ごとあるいは業種ごとのアプローチのあり方を検討する際の一助となるであろう。
