第4節 農林水産物・食品輸出の拡大
政府は2015年6月に改定された「日本再興戦略」において、2020年に農林水産物・食品126の輸出額1兆円目標の前倒し達成を掲げるなど、我が国の農林水産物・食品の海外市場への販路拡大を目指している。実際に、我が国の農林水産物・食品の輸出額は堅調に推移しており、2015年には7,451億円まで達し、3年連続で過去最高額を更新している(第Ⅱ-3-4-1図)。
第Ⅱ-3-4-1図 我が国の農林水産物・食品の輸出額の推移
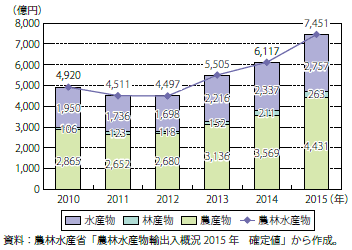
我が国の農林水産物・食品は安心、安全といった高い品質と評価を得ているものが多く、更なる輸出の伸びが期待できる産業である。また、地域産品の輸出は、地域活性化の側面からも期待されており、我が国の農林水産物・食品輸出の促進について、その動きが注目を集めている。
そこで本項では、農林水産物・食品輸出において国際比較の概観を行い、食料産業クラスター127の視点から、オランダ「フードバレー」を下支える組織群の事例、ドイツのメクレンブルク=フォアポンメルン州(以下「MV州」という。)の取組、北海道十勝「フードバレーとかち」の事例を取り上げ、農林水産物・食品輸出を下支える食料産業クラスターの強みについて考察していく。
126 農林水産物・食品には「農産物(加工食品、畜産品、穀物等、野菜・果物等、その他農産物)」、「林産物」、「水産物(水産物(調整品除く)、水産調整品)」が含まれる。
127 食料産業クラスターとは、「コーディネーターが中心となり、地域の食材、人材、技術その他の資源を有効に結びつけ、新たな製品、販路、地域ブランド等を創出することを目的とした集団。」と定義されている。(http://www.maff.go.jp/j/study/tisan_tisyo/h18_03/pdf/data7.pdf![]() )
)
1.世界の農林水産物・食品輸出と輸出入型分類
(1)世界の農林水産物・食品輸出の概観
世界の食料品等128の貿易額は増加傾向にあり、2013年には輸出額が13,974億ドルまで達しており、今後も輸出入額は共に堅調に増加していくことが予想される(第Ⅱ-3-4-2図)。
第Ⅱ-3-4-2図 世界の食料品等の輸出入額
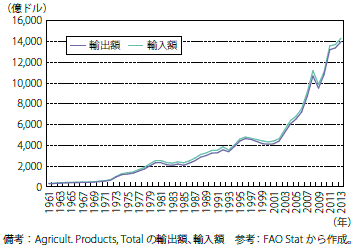
2015年の国別では、米国(1,242億ドル)、オランダ(814億ドル)、ドイツ(675億ドル)、ブラジル(639億ドル)、中国(636億ドル)、フランス(601億ドル)及び日本(51億ドル)となっている(第Ⅱ-3-4-3図)。
第Ⅱ-3-4-3図 主要食料品等輸出国による輸出額推移
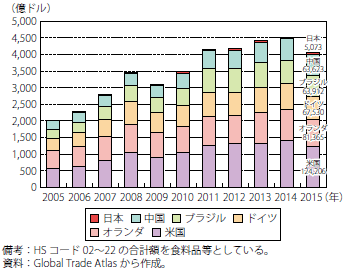
また、名目GDPに占める食料品等輸出額割合はオランダが他国に比べて極めて高いことが分かる(第Ⅱ-3-4-4図)。
第Ⅱ-3-4-4図 各国の名目GDPに占める食料品等輸出額割合の推移
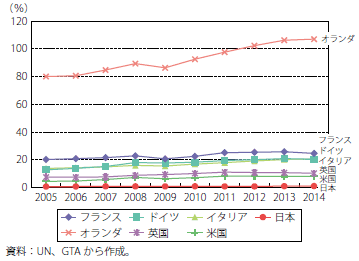
次に、各国の食料品等の輸出入額を見ると(第Ⅱ-3-4-5図)、米国、オランダ、フランスは輸出額が輸入額を上回る輸出超過となっており、中国、日本、イギリスは輸入超過となっている。オランダの場合、食品加工業が盛んなため、原材料や飼料の輸入も多く、2013年ではおよそ2億9,200万ドルの飼料の輸入を行っている129。
第Ⅱ-3-4-5図 各国の食料品等の輸出入額(2012年)
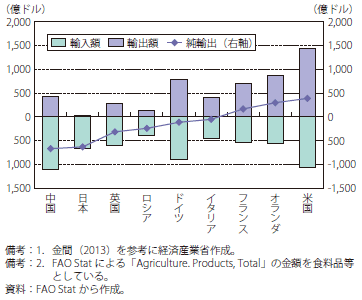
また、オランダでは輸出超過の額がおよそ300億ドルとなっていることから、同じように欧州域内で農業国として知られるフランスの2倍である。この値から、オランダの食品加工業の付加価値の高さがうかがえる130。
128 本項における「食料品等」には、「農産物」、「林産物」、「水産物」の他、動植物性生産品や素材・飼料等が含まれる。各資料元によって詳細な定義が異なるため、注意されたい。
129 FAO Stat Detailed trade matrixによれば、オランダは飼料をおよそ2億9,200万ドル輸入し、1億4,500万ドル輸出しているのに対して、フランスでは、8,800万ドルの飼料の輸入に対して、2億1,000万ドル輸出している。
130 金間(2013)
(2) 各国の農林水産物・食品の輸出入型分類
ここでは食料品等の主要輸出国の特質を反映することを目的として、素材、食料品(加工品・消費財)を軸として輸出入についての類型化を行った131。
貿易産業分類で定義された食品産業について、各国の素材、食料品の貿易特化係数を用い、類型化すると、一般的には以下のような類型を行うことができる132(第Ⅱ-3-4-6図)。
第Ⅱ-3-4-6図 各国の食料品等の輸出入型分類の見方
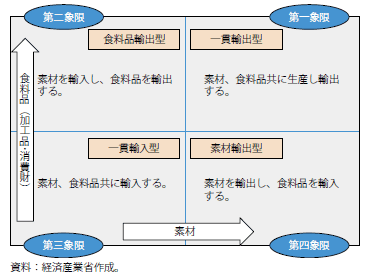
各国ごとに素材、食料品の輸出入についてその特徴を見ると、オランダは食料品輸出型であり、近年ドイツとイタリアがオランダ型に加わりつつある。日本は一貫輸入型で素材、食料品を共に輸入する特徴を持ち、韓国は近年、日本に近い一貫輸入型へと移行しつつある。中国は大きな動きを見せており、近年、一貫輸出型から、食料品輸出型への移行が見られた。ブラジルは素材、食料品を共に輸出している一貫輸出型で食料産業が国内の基幹産業であるのに対して、米国は比較的素材輸出の割合が高く、食料品を輸入している素材輸出型となっている。またフランスは、素材輸出型から一貫輸出型へと移行しつつある(第Ⅱ-3-4-7図)。
第Ⅱ-3-4-7図 各国の食料品等の輸出入型分類(2013年)
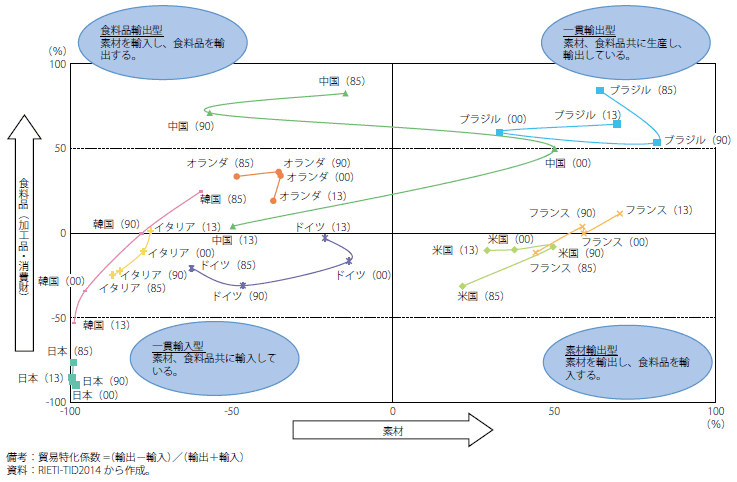
第Ⅰ部第3章第1節で見たように、財である食料品等にもサービスの付加価値がついており、各国ごとに食料品輸出付加価値に占める研究開発サービス比率を国内付加価値と海外付加価値に分けて見てみると、オランダは海外比率が高く、海外の研究事業の成果を積極的に取り込んでいるのに対して、ドイツ、フランス、米国、イタリア、ブラジル、日本では国内比率が海外比率を上回っており、オランダに比べて国内の研究事業を積極的に行っていることが分かる。また、アジア諸国に比べ、欧州諸国では海外比率が高いことも指摘できる(第Ⅱ-3-4-8図)。
第Ⅱ-3-4-8図 食料品等輸出付加価値に占める研究開発等サービス比率(2011年)
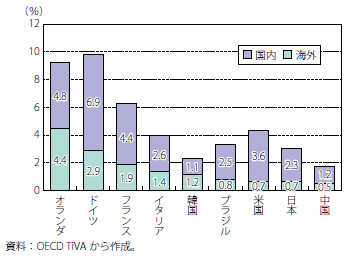
131 生産分業を念頭に、貿易を生産工程別の財(素材、加工品・消費財)に分けて分析を行った。その基礎データとしては、独立行政法人 経済産業省RIETI-TID2014を用いた。各財の定義はRIETI-TIDによる。
132 ここでは通商白書2005年を参考に貿易特化係数を用いて、類型化を行った。
2.欧州の輸出拡大の先進事例
(1) オランダの農林水産物・食品輸出拡大への取組
次に、オランダ農業と食料品等輸出の特徴及び「フードバレー」を支える組織群について見ていく。
① オランダ農業と食料品等輸出の特徴
オランダは面積41,526 km²と九州(35,640 km²)よりやや大きい国土で、人口約1,680万人である。2015年の名目GDPが7,384億ドルと、世界17位の経済規模である。オランダ経済は政府による1980年代以降の開放経済政策によって、国際貿易を中心とし経済成長を遂げてきた。最大の国内産業は貿易、運輸業、金融・流通等のサービス産業である。
オランダの特徴として、ロッテルダム港は毎年、1,200万TEU133を取扱う欧州最大の港であり、運輸・物流分野に力を入れている。オランダは欧州貿易の窓口としての役割を担っている。また、狭い国土に異文化・異民族を受け入れてきた歴史を持つことから、国民の言語能力の高さも特徴の一つとして指摘できよう。
加えて、オランダは更なる競争力強化を目指して9分野の「トップセクター」(「農業・食品」、「ハイテク」、「園芸・育種苗」、「生命・健康科学」、「水」、「化学」、「エネルギー」、「クリエイティブ産業」、「物流」)を作り、官民協力、イノベーション強化などを通して一層活発なビジネス展開を目指している。中でも、「農業・食品」はオランダ経済の基幹産業の一つとして、何十年も国際競争を牽引しており、食品、花き、植物の生産供給を最重点に置き、農家と生産者が協調している。
オランダ農業の特徴の1つは、財政的な支援がなされていることである。温室栽培にはエネルギー税を減税しており、食料品及び花きに対しては、通常21%のところ、6%と低い税率を課している。また、イノベーションについての財政的サポートを積極的に行っており、農業だけにとどまらずフードチェーン全ての中でイノベーションを起こしやすいサポート体制があり、オランダは立地条件だけでなく、政府一体となった支援策により食料品産業を育成しているといえる。
続いて、オランダの食料品等輸出の特徴について見てみると、オランダの食料品等輸出額は814億ドルで、米国に次ぐ世界第2位の食料品等輸出国であり(第Ⅱ- 3-4-3図)2015年のオランダからの輸出品目の中でも最も構成比が高い(第Ⅱ-3-4-9図)。
第Ⅱ-3-4-9図 オランダの輸出額に占める品目割合の推移
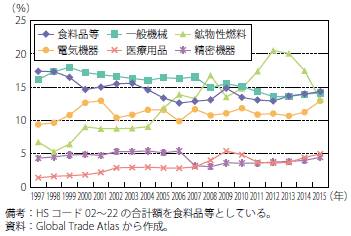
オランダの食料品等輸出の内訳では、輸出上位品目は増加傾向にある。その割合(2015年)を見ると、花き11%、牛肉11%、酪農品10、野菜9%、果物7%で食料品輸出のおよそ5割を占めている(第Ⅱ-3-4-10図)。オランダの農業は土地資源の少なさから、土地利用型の穀物は近隣の欧州諸国から輸入しており、園芸や畜産等の土地節約、労働・資本集約型部門に特化した構造となっている134。
第Ⅱ-3-4-10図 オランダの食料品等輸出品目の推移と割合
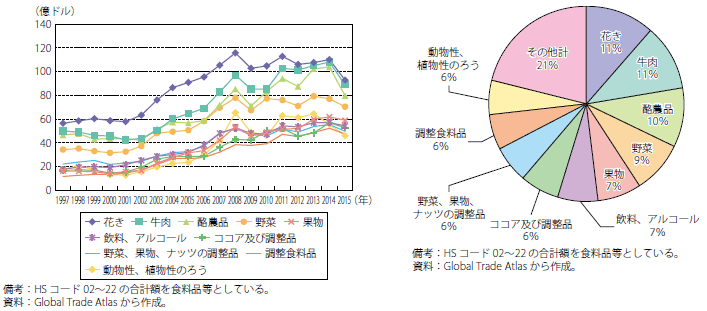
オランダの食料品等について主要輸出先国を見ると、ドイツ135、英国、ベルギー、フランス、イタリアの欧州諸国が上位を占めており、オランダの食料品等の輸出先は欧州諸国であることが分かる136(第Ⅱ- 3-4-11図)。
第Ⅱ-3-4-11図 オランダの主要輸出先国(食料品等)
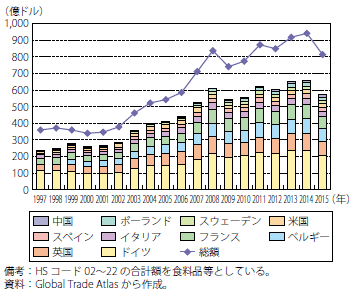
133 TEU (twenty-foot equivalent unit、20フィートコンテナ換算)はコンテナの単位。
134 オランダ農業の特徴として、花き、野菜の温室栽培が盛んであり、オランダでは天然ガスが産出するため、温室栽培には好条件とされている。
135 オランダの多くの品目がドイツ向けの輸出であるものの、それ以外では、アルコール類はビールを米国、魚類はベルギー、たばこ類はフランス、ミルクパウダーは中国や香港への輸出が多くなっている。
136 オランダの立地が貿易に適しており、ドイツに送る場合にはロッテルダム港を通す輸送方法や電車での輸送のほか、川を使ったボートでの輸送もあり、ライン川などを通って輸出される。
②オランダ「フードバレー」を下支える組織群
次にオランダの食料品産業の中心的役割を担う「フードバレー」について見ていく。
オランダの農業の強さを下支えしているのが、オランダの中東部、ヘルダーランド州の州都アーネムに隣接するワーヘニンゲン市にある「フードバレー」と呼ばれる食の技術、科学、ビジネスが集結した産業集積である。
フードバレーには農業食品関連の産業が多く集まっており、ワーへニンゲン大学を中心としてワーへニンゲン大学リサーチセンター、ワーへニンゲン財団があり、アグリフード企業が1,440社、企業研究所が70社、研究拠点が20拠点以上集中し、およそ15,000人の研究者が働いている。農産物の栽培、加工に関するコスト削減や付加価値に関する技術開発だけでなく、保存、流通、販路開拓といったバリューチェーンの全要素が産学官一体となって研究されており、農業に関する知の集積地が形成されている。
(a) フードバレー事例①:大学(ワーへニンゲン大学リサーチセンター)
ワーへニンゲン大学リサーチセンター(以下「ワーへニンゲンUR」という。)は産学官が一体となってワーへニンゲンに集積したのが始まりとされる。ワーへニンゲン大学とその近隣に集まる研究機関を統合し、ワーへニンゲンURが設立された137(第Ⅱ-3-4-12図)。ワーへニンゲンURの特徴として、数多くの専門研究機関と、ワーへニンゲン大学、ファンハル・ラーレスティン応用科学大学校(Van Hall Larenstein University of Applied Sciences)とが共同していることである138。
第Ⅱ-3-4-12図 ワーヘニンゲン大学リサーチセンター
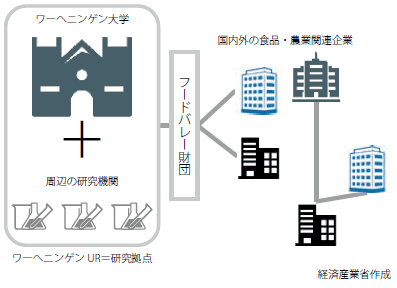
ワーへニンゲン大学はオランダの唯一の農業に特化した国立農業大学であり、オランダの農業の成長において中心的な役割を果たしている。ワーへニンゲン大学は農業技術・食品科学部(Agrotechnology & Food Sciences)、動物科学部(Animal Sciences)、環境科学部(Environmental Sciences)、植物科学部(Plant Sciences)、社会科学部(Social Sciences)の5学部で構成されており、およそ9,000人の学生が学んでいる。
さらに、開発研究を行う専門機関として、食品研究所、農業経済研究所、畜産研究所等がある(第Ⅱ-3-4-13図)。
第Ⅱ-3-4-13図 ワーへニンゲンURの組織構成
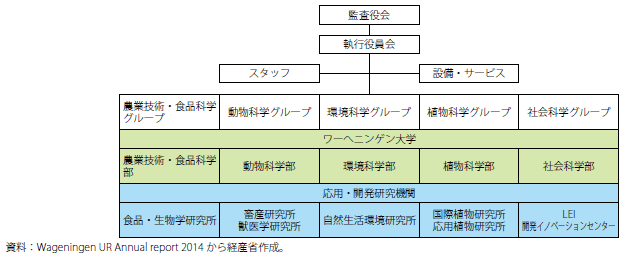
ワーへニンゲンURの戦略としては、応用研究機関における市場価値を高めること、新たな研究分野への投資、教育や研究の質を高めることなど、が挙げられる139。
またリサーチセンターの中に研究と実践の場としてユニークな「未来レストラン」(Restaurant of the Future)という施設もある。学生や職員、近隣住民などが利用しており、その販売データを分析するとともに、利用者の飲食行動をビデオカメラやセンサーを通じて観察し、研究開発にフィードバックしている140。
オランダのフードバレーは、アグリフードと栄養分野に特化しており、世界各国から人材が集まる国際的環境や最良の人材を呼び込む人材交流プログラムやワーへニンゲンURを中心とした食品、栄養、農業分野の世界レベルの研究者が最先端研究を行っている。地域内の3大学141付属メディカルセンターと緊密に連携しており、R&D専門プログラムや補助金も豊富、という産学官ネットワークの強みに特徴を持ち、ビジネスに繋がる研究を積極的に行っていることが強みといえよう。
137 金間(2013)
138 Netherlands Foreign Investment Agency(オランダ経済・農業・イノベーション省企業誘致局)(2010)
139 Wageningen UR (2014)
140 Wageningen UR ” About The Restaurant of the Future” http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Restaurant-of-the-Future-4/About-The-Restaurant-of-the-Future.htm![]()
141 ワーへニンゲン大学(Wageningen University, 食品)を中心にナイメーヘン・ラドバウド大学(Radboud University Ni jmegen, 健康)、トウエンテ大学(University of Twente, 技術)が連携している。
(b) フードバレー事例②:ネットワーク(NIZO食品研究所/NIZO Food Research)
フードバレーには大学、研究所の他にも多くの研究施設が存在する。ここではオランダのフードバレーの代表的な企業を紹介する。
NIZO食品研究所(NIZO Food Research、以下「NIZO」という。)は1948年に複数の小規模酪農企業が共同出資したことで設立した。その後、企業の製品開発における委託研究に特化した企業となった。
NIZOで行われる研究のテーマ選択は、企業の目的に沿った委託研究142から、NIZOがテーマを設定でき、研究開発を企業に提案するといった形など、柔軟に研究テーマを決定することができる。また、NIZOでは、食品関連研究施設と生産のための試験用パイロットプラントを保有しており(第Ⅱ-3-4-14図)、委託企業は、生産設備に本格投資を行う前に製造のための種々のテストを実施するなど、生産直前の産業化支援を受けることができる。NIZOの収入のほとんどは企業から依頼される新たな商品の研究開発や、製造に伴うプロセス開発になる143。
第Ⅱ-3-4-14図 試験用パイロットプラント

第Ⅱ-3-4-15図 NIZOが研究開発に携わった製品

NIZOの事業内容を見ると、柔軟にテーマ選択を行い細分化したプロセスを慎重に進めていく姿勢から、生み出されるサービスの質の高さがうかがえる。クライアントと関係を構築しながら、提供するサービスに最先端の研究を取り入れていることが特徴といえよう。
NIZOの人材について見れば、職員は125人在籍して、80%は研究開発部門、20%はバックオフィスやビジネスサイド(企画営業)である。修士号・博士号を持つ人材が多く、ポストドクターの最初の就職先となることもある。研究者だった者が、NIZOではビジネス(企画営業)に転向したり、NIZOから大学へ再転職した人など、アカデミアとの人材交流は盛んであり、最先端の動向をつかむことができる。
オランダでは労働市場が柔軟であり、職を変えることが一般的であるため、アカデミアと産業界を行き来しやすく、双方の知識を身に着けやすい。NIZOにとって、NIZOから転職した人は「アンバサダー」という位置づけにあり、転職先で新しい人脈を作り、機会があれば転職先の組織とNIZOの架け橋になる役割も持つ。オランダの場合、柔軟な労働市場のため、最先端の研究や情報が横断的に入ってきやすい環境であるのに対して、日本の労働市場は人材の移動が硬直的なため、人材を通じた横断的ネットワークが形成されにくいといった特徴を持つ。ここにフードバレーのネットワークの強みを見ることができる。
以下では産学官連携をスムーズするためのコーディネーション機関の事例を紹介する。
142 特に企業からの委託研究としては、近年、低脂肪低糖食品を使った際の食品の香味、食味、食感等に関する研究などがある。企業に提案するため、自社内においても、牛に与える餌と生乳内の細菌繁殖の関係、腸内環境、プロバイオティクスなど乳酸菌関連の研究開発を行っている(第Ⅱ-3-4-15図)。
143 委託研究の過程で発生したライセンスや特許は、個々のプロジェクトにてクライアントと相談しながら最終決定を行うが、基本的にはクライアントが有する。このため、特許等によるライセンス収入は少額であるものの、自社にて研究開発したツールや製品等のライセンスは、自社にて保有し、それを利用し複数企業相手の問題解決に利用している。
(c) フードバレー事例③:産学官連携(TIFN/Top Institution Food and Nutrition)
TIFNは1998年に設立されたオランダの食品産業の官民共同パートナーシップで設立された研究のコーディネーション機関である。
TIFNは官民パートナーシップから成る組織であり、4つの研究テーマを持つ144。それぞれにテーマディレクター145を置き、チーム体制で研究に取り組んでいる。長年の共同研究による研究蓄積、及び最新の論文動向など、登録されている研究員がプロジェクトごとにアサインされている。共同研究のパートナーは民間企業と大学、研究機関などが登録しており、オランダにR&D拠点を置くグローバル企業もパートナーとして登録されている。また大学については、オランダ全土の複数の大学がパートナーとなっている。
TIFNでの研究開発のテーマは、テクノロジーや市場のニーズによって決められ、産業界とアカデミア両方の動向を考慮して検討するが、産業界の強い意向が反映される146という特徴を持つ。
TIFNの特徴は、TIFNの研究が産業に適応可能で、且つ科学的に価値の大きい研究を実施できていることにある。また、異なる立場にある組織同士がオープン議論を交わすことができる環境が作り出されており、柔軟な横の連携が構築されている点を指摘できよう。
144 “Nutrition& Health”, “Microbes& Function”, “Sensory& Structure”, “Sustainable Food Chains& Dynamics”
145 例えば、Nutrition and Health分野のテーマディレクターはFriesland Campinaの社員で、週二回TIFNの仕事をして、残りは社員としての仕事をしている。他三人はアカデミアの人材である。
146 大学が教育、論文といったアカデミックワークを優先するのに対して、TIFNではまず産業界との連携が最優先であることが特徴である。
③ 物流の強み(ロッテルダム)
次に、オランダの物流について見てみる。オランダのロッテルダム港は欧州最大の港であり、「ブルーバナナ」と呼ばれるドイツ、イタリア、オーストリアなどを含むEUの中心的な場所への窓口を担っている。
港湾運営では、効率性が最も重視されることから、ITの活用、および海と陸とをデータで繋げることは重要な課題となっている。現行のシステムで見れば、船が遅れているなどの情報を基にトラックの向かう時間を調整可能にし、どれだけデータの汎用性を高めていくかが課題となっている。ロッテルダム港では、現行のシステムにとどまることなく、よりリアルタイムで双方向的なシステムにしていくことを目指しており、次世代のシステム開発を積極的に行い、積荷の自動化だけにとどまらず、データの利用や法規制緩和の面からも効率化を目指している。
(2) ドイツ(MV州)の農林水産物・食品輸出拡大への取組
① MV州の概要
これまで、農林水産物・食品の輸出大国であるオランダのフードバレーを下支える組織群の事例を中心にその特徴を見てきたが、以下ではドイツMV州の食品産業の高度化を目指すサポート機関であるFood Academyから農林水産物・食品輸出を下支える仕組みを見ていく。
ドイツMV州はバルト海に面したドイツの中で最も人口密度の低い州であり、州面積は23,173 km²にも関わらず、近年、農林水産物・食品輸出を伸ばしている。
MV州における農林水産物・食品輸出の割合を見ると、上昇傾向で推移しているものの、16%にとどまっている(第Ⅱ-3-4-16図)。主な輸出品は魚、ビール、乳製品であり、生鮮食品は他国の農林水産物・食品と差別化している。中小企業の海外展開はパートナーを見つけることによって海外企業との取引が始まることが多い147。
第Ⅱ-3-4-16図 ドイツの州別品目別寄与148
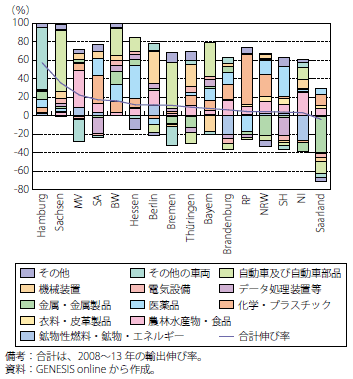
147 実際に30-40社の輸出に成功している企業はユニークで他社が真似できない領域を持っている企業である。
148 図中のドイツ州名のうち、NRWはノルトライン=ヴェストファーレン州、BWはバーデン=ビュルテンベルク州、RPはラインラント=プファルツ州、SHはシュレースヴィヒ=ホルスタイン州、MVはメクレンブルク=フォアポーメルン州、SAはザクセン=アンハルト州、NIはニーダーザクセン州の略。
②MV州事例:MV州の食品産業の高度化を目指すサポート機関(Food Academy)
MV州の輸出拡大を下支える取組に食品産業の高度化を目指すサポート機関であるFood Academyがある。Food Academyでは食品業界における若年層の確保、先端テクノロジーに対応するスペシャリストを育成、食品産業の人材の問題を解決することによって州内企業が成長することを目指しており、食料産業クラスターの形成および成長、輸出の促進、対内投資の促進につなげることを目的としている。
Food Academyは、大学や職業訓練学校では教えないビジネスの基礎や食品関連の機材の使い方を指導しており、食品関連企業が、食や会社の運営に関するための知識を従業員に教えられるように始めた取組である。食品業界のテクノロジーの進化の早さに対応できる人材を増やし、地域の若い層をつなぎとめることを目的としている。また、食品産業の就業イメージを変えること、異業種から食品産業へのキャリアチェンジをサポートする、といった取組も行っている。
Food Academyのカリキュラムは多岐に渡り、構成員の企業の要望を取り入れ編成している。「中学を出た15-16歳程度のデュアルシステムにより働き始める人材にソーシャルスキルを教える。」、「新しく食品業界を自分の専門としようとする(転職者を含む)人向けのトレーニングを行う。」、「10-15年目の中堅社員向けに、新しい製造用機械を導入する際の効果的なオペレーション方法を教える。」、「マネージャー向けトレーニング」等を実施している149。多くの場合、トレーナーを雇い授業は会社で実施している。
組織形態はMV州の食品企業6社が創業し、その幹部が組織の代表を務めるなど、地域の食品企業が主体となり、メンバーのほかに協力パートナーの支援を受け運営を行っている。
149 今後は輸出関連トレーニング、言語や異文化の講習の開始も検討している。
(3) 我が国へのインプリケーション
ここまで、オランダのフードバレーを下支える組織群、ドイツのMV州Food Academyといった欧州の事例から農林水産品・食品輸出を下支える仕組みを見てきた。
オランダでは、食料品等輸出国として成功している背景にオランダで唯一の農業大学であるワーへニンゲン大学と、産業界からのニーズを汲み取り、最先端の技術を用いたリサーチセンターの存在を指摘できる。また、企業と連携した研究開発が産業政策としても推進されており、研究と産業とが結びつきやすい環境にある。また、企業間の横断的な繋がりが起こりやすいことから、研究開発も促進されるといった相互作用が生じている。
また、オランダの国内組織だけでなく、物流の面から見ても、ロッテルダム港のデジタル化など鮮度が必要な食料品等を輸出しやすい環境を持つことにオランダの食料品等輸出の強みを見ることができる。
ドイツでは、ドイツの中でも農林水産品・食品輸出を伸ばしているMV州ではFood Academyが設立され、食品業界のテクノロジーに対応する人材の育成、輸出の促進、対内投資の促進などを目指した、食料産業クラスターがまさに形成されようとしている。
欧州の輸出拡大の先進事例から見れば、農林水産品・食品輸出を下支える仕組みとしての食料産業クラスターについては、先端研究と産業との結びつき、人材育成、共同研究のし易いコーディネーターの存在などの必要性や物流の強みが指摘できる。
3.我が国の農林水産物・食品輸出の動向と方向性
これまで欧州の事例から農林水産物・食品輸出を下支える仕組みについて見てきた。以下では、我が国の農林水産物・食品輸出の動向について見ていくとともに、我が国の食料産業クラスターについて、北海道帯広市の「フードバレーとかち」の事例から、その取組を見ていくこととする。
(1) 我が国の農林水産物・食品輸出の動向
①我が国の農林水産物・食品輸出の動向
まず、我が国の農林水産物・食品について、主要輸出先国・地域(上位10か国・地域)を見ると香港が1,794億円(24%)と最大の輸出先である。次いで、米国、台湾、中国と日本の主な輸出先はアジア及び米国が中心である(第Ⅱ-3-4-17図)。次に日本の農林水産物・食品の主要輸出品目(上位15品目)の内訳を見ると、「ホタテ貝」、「アルコール飲料」、「真珠」、「ソース混合調味料」が上位を占める(第Ⅱ-3-4-18図)。
第Ⅱ-3-4-17図 我が国の農林水産品・食品輸出先国・地域(2015年)
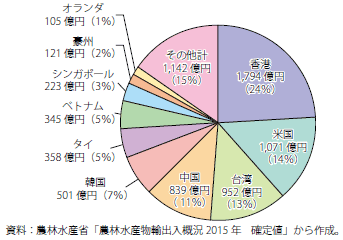
第Ⅱ-3-4-18図 我が国の農林水産品・食品輸出品目(2015年)
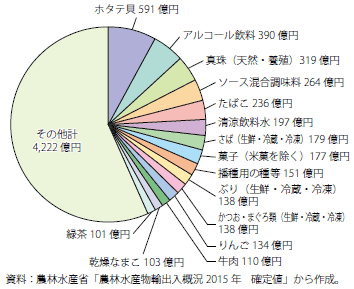
工業統計調査から日本の食品製造業について企業規模別に直接輸出額を見ると、大企業は輸出額が徐々に低下傾向であるのに対して、中堅企業、中小企業は輸出額を伸ばしている。特に中小企業は2014年に大きく輸出額を伸ばしている(第Ⅱ-3-4-19図)。
第Ⅱ-3-4-19図 企業規模別輸出額(食品製造業)
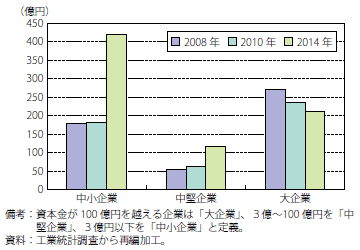
次に、都道府県別に農林水産物の輸出の状況について、2003年(平成15年)と2013年(平成25年)のコンテナ貨物輸出から見てみると、農林水産物の輸出規模が大きいのは北海道、東京都、青森県となっている(第Ⅱ-3-4-20図)。
第Ⅱ-3-4-20図 コンテナ貨物輸出(生産県別)農林水産品(上位10県)
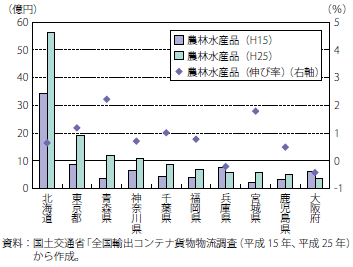
②北海道の食料品輸出を支える物流等
日本の農林水産品輸出について、都道府県別に見てみると、2013年(平成25年)で北海道が最大で、その伸び率も全国平均値より高いことから、以下では、北海道の物流と商社についてその取組、課題について見てみる。
まず、北海道の農産品輸出について見てみると(第Ⅱ-3-4-21図)、その68%を水産物が占める。また、割合は小さいものの、野菜類(HS07)の輸出額はその推移を伸ばしている(第Ⅱ-3-4-22図)。
第Ⅱ-3-4-21図 北海道の輸出産品(2015年)
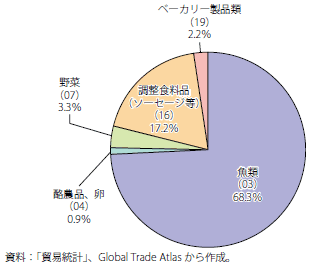
第Ⅱ-3-4-22図 北海道の輸出産品の推移
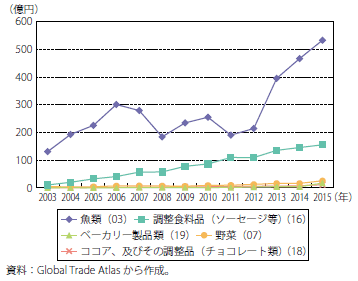
近年、海外では和食ブームが広がっており、最近の特徴として中国・香港等のアジア圏に向けて、全国のほたて漁獲量のほぼ100%を占める北海道産の活ホタテの輸出が飛躍的に増加している。
活ホタテの輸出においては、国際航空貨物の拠点となる新千歳空港において荷役・保管・運搬を行う第3セクター「札幌エアカーゴターミナル(SIACT)(以下「SIACT」という。)」の担う役割が大きくなっている。
(a)北海道事例①:物流(札幌エアカーゴターミナル)
SIACTは新千歳空港における国際航空貨物の荷役・保管・運搬を担う第3セクターで1986年に設立された(第Ⅱ-3-4-23図)。
第Ⅱ-3-4-23図 札幌エアカーゴターミナル

輸出入別の推移を見ると、近年、輸出が急増している(第Ⅱ-3-4-24図)。輸出取扱品目の75%が生鮮類で、その内訳は65%がホタテである。またホタテ以外で見れば、機械部品類の輸出がある(第Ⅱ-3-4-25図)。
第Ⅱ-3-4-24図 SIACT輸入・輸出別の推移
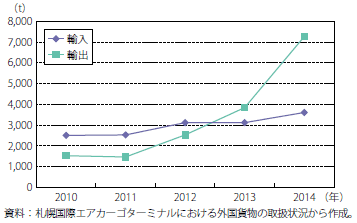
第Ⅱ-3-4-25図 SIACT輸出取扱品目
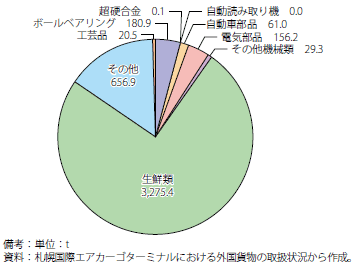
SIACTでは、共同上屋を持ち、荷主から荷物を受け取ると、爆発物検査等をSIACTの上屋で行うことが可能となっている。共同の上屋を持つことで、代理店上屋から航空会社上屋への貨物移動がなく、貨物へのダメージを軽減している。取扱荷物が急激に増加したことから、作業スペースが十分に確保されておらず、施設の拡充が不可欠となっている(第Ⅱ-3-4-26図)。
第Ⅱ-3-4-26図 SIACTの貨物取扱の流れ
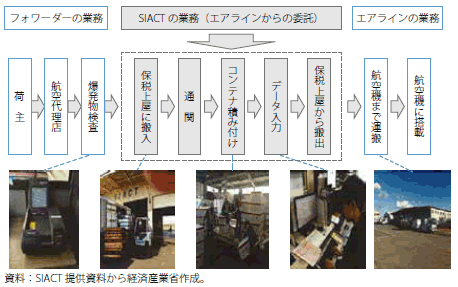
また、輸出における取扱貨物がホタテ一品目に偏っており、ホタテの輸出状況により取扱貨物量が不安定となることから、取扱貨物の多品目化が必要である。
現在、SIACTでは道庁と連携し、欧米線の誘致を行っている。特に米国線が増えることで機械部品類の増加が期待されている。
また、国際貨物の増加に対応するため、設備拡充に加えて、国際貨物ハンドリングの最適化、荷役サービスの向上、高鮮度輸送への対応等、輸出機能強化のための取組が期待されている。
このように輸出では物流が重要な役割を担っている一方で、北海道の農林水産品・食品の輸出においては、地域の産品を海外市場へ輸出する「地域商社」の果たす役割が期待されている。
(b) 北海道事例②:商社(キョクイチ)
北海道旭川市に所在する株式会社キョクイチは、昭和24年に「旭一旭川魚菜市場株式会社」としてスタートし、水産、農産、畜産の生鮮三品を1社で取り扱うとともに、卸売市場を運営する生鮮食品卸企業である(第Ⅱ-3-3-27図)(第Ⅱ-3-3-28図)。
第Ⅱ-3-4-27図 物流センター

第Ⅱ-3-4-28図 水産セリ場

オホーツク海、日本海、太平洋からの水産物、隣接する大産地の青果物など、あらゆる農水産物が集荷可能であり、グループには加工や物流を担う企業を有していることから、生鮮食品から加工品まで幅広い商品を取り扱うことに強みを有している。
同社はこの幅広い調達・供給能力と市場、加工、物流のワンストップ機能を活かした競争力の高さで、香港、シンガポール、台湾、タイ等における海外の市場や卸売企業との商流形成を目指している。
また、輸出への取組としては、輸出拠点として利便性の高い地元の旭川空港から初となる国際貨物輸送を実施し、今後も定常的な輸出を目指し取組を進めている。
今後は、産地の農協等と連携し、輸出向け農産物の生産や輸出専用の加工食品の開発を計画しており、アジア圏での北海道産農水産物の地位確立や、ブランド化を目指し取組を進めている(第Ⅱ-3-3-29図)(第Ⅱ-3-3-30図)。
第Ⅱ-3-4-29図 旭川空港での富良野メロンの積み込み
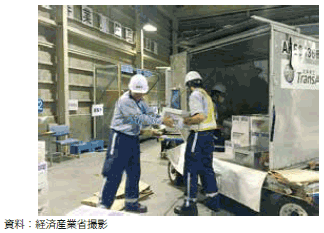
第Ⅱ-3-4-30図 最適な食味の実現に向け試作開発中の冷凍スイートコーン

(2) 香港市場における我が国の農林水産物・食品について
我が国の食料品等輸出を見ると、輸出先国・地域は香港が第1位(2015年時点で11.6億ドル)であるにも関わらず、香港の輸入先国・地域(食料品等)を見ると、第1位は中国(49.2億ドル)であり、日本は第6位となっている(第Ⅱ-3-4-31図)(第Ⅱ-3-4-32図)。
第Ⅱ-3-4-31図 日本の食料品等の輸出額の推移(上位10か国・地域)
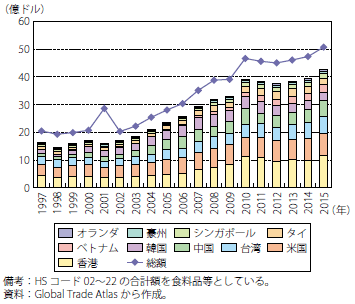
第Ⅱ-3-4-32図 香港の食料品等の輸入額の推移(上位10か国・地域)
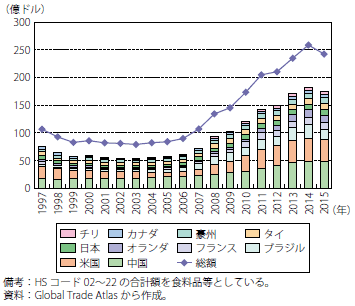
では、香港市場から日本食材はどのように見えているのだろうか。以下では、日本食品を輸入し、香港に日本食文化を広めてきた味珍味有限公司から見た日本食品を取り巻く香港市場について紹介する。
味珍味有限公司は1981年に創立し、日本食材の輸入のために同社を立ち上げて以来、マグロ・和牛・ホタテフライ・ラムネ等を香港に紹介し、日本の食文化を香港へ広く浸透させてきた。また、従来の船便輸送に加えて80年代後半には、新鮮な食材を運ぶために航空便による輸送を開始し、現在も船便と航空便により新鮮な野菜や果物、乳製品や卵などを香港市場へ届けている企業である。
味珍味有限公司へのヒアリングによれば香港で日本の食料品の輸入が増えている背景には、「距離が近い」、「関税がない」、「嗜好が近い」、「食文化が近い」、「為替が安い」といったメリットがあるという。嗜好の近さについては、日本は真面目にものを作っていることから、他国よりも安心・安全と評価されており、安心の中には「まずいものはない」と言った美味しさに対する安心も含まれている。そのため、素材として利用する際には消費者が気付くように「日本産米を使っている」といった店頭PRを行いレストランにとってのメリットを表示するなどの工夫を行う店もある。
また、香港で日本食が伸びているのは、消費者が身近に感じるような日本側の地域・企業努力も大きい。香港のスーパーマーケット等で日本食材のプロモーションを積極的に行うことで、日本食材を扱うローカルスーパーが増加してきている。また香港の日系スーパーなども増えてきており、香港市場に日本食品が浸透してきている。
香港市場から見た、日本が抱える課題として自治体のプロモーションが各自で行われている点が挙げられる。他国ではまとまったプロモーションを行っているものの、日本は自治体ごとの短期的なプロモーションにとどまっている。そのため、自治体間の競争が激化していき、日本産のシェアが広がらない懸念がある。日本のシェアを広げていくためには、日本の各県ごとの競争ではなく他国との競争によって日本のシェアを獲得していく必要がある。農産物について見れば、産地ごとの違いは香港消費者には理解しづらいこともあり、各県に分かれたブランディングよりも、体制面で担当者が変わらない長期的な関係を構築していけるような息の長いブランディングが求められている。
(3)「フードバレーとかち」の取組
これまで、我が国の農林水産品・食品輸出の動向と我が国の食料品等を積極的に受け入れてきた香港の市場について見てきた。
以下では、我が国の食料産業クラスターについて、北海道の「フードバレーとかち150」について、その事例から我が国の農林水産品・食品輸出を下支える取組について見ていく。
150 フードバレーとかちは帯広市役所が中心的役割を果たしている北海道十勝地域にある食料産業クラスターであり、帯広市の米沢市長のマニュフェストから始まった。
①「フードバレーとかち」の展開の特徴
帯広市は618.94km²で東京23区とほぼ同じ大きさである。気候は最高34.8℃最低が-21.0℃と寒暖の差が激しい特徴を持つ。日照時間は年間平均で2,015時間であり、全国平均(1,881時間)を上回っており、きれいな水・空気と併せて良質な自然環境がある。加えて、土壌改良による、農業に適した良質な土壌、農業由来のバイオマスの豊富さがある。
次に、安全安心力・ブランド力について見れば、HACCP151対応の選果施設整備や生産履歴開示の取り組みによって、「十勝の食=安全」といったイメージを生み出している。現在、日本では中小企業でもHACCP認証を取得しやすいように、都道府県レベルで独自の認証制度を設ける地域もある。北海道で認証が行われている北海道HACCP152認証施設数を見ると、十勝地域は15件となっている(第Ⅱ-3-4-33図)。
第Ⅱ-3-4-33図 北海道HACCP認証施設数(H27年度)
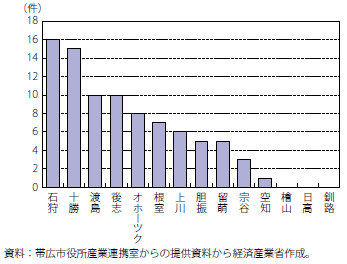
また、豊かな生産力と研究開発力を有しており、ヨーロッパの農業国に匹敵する、一戸あたりの耕地面積39.4haは全国平均(2.2ha)の約18倍で全国トップクラスの生産量を誇り(第Ⅱ-3-4-34図)、フードバレーとかちでは、農業に関する各種研究機関が集積している153(第Ⅱ-3-4-35図)。
第Ⅱ-3-4-34図 農家一戸当たりの平均耕地面積
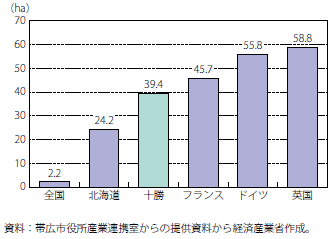
第Ⅱ-3-4-35図 フードバレーとかちの集積
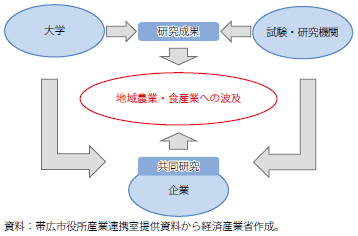
151 HACCPとは、米国のNASA(アメリカ航空宇宙局)で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理システム。
152 HACCPの手法を取り入れた衛生管理を行っていることを北海道が認証する制度を設け「北海道HACCP」としている。
153 研究開発力では、帯広畜産大学、農業大学校、北海道農業研究センター芽室研究拠点、種苗管理センター十勝農場、家畜改良センター十勝牧場、十勝農業試験場、十勝圏地域食品加工技術センター、十勝産業振興センター、十勝農協連農産化学研究所、日本甜菜製糖(株)総合研究所など、農業に関する各種研究機関が集結している。
② フードバレーとかちにおける輸出の成功事例
ここでは、フードバレーとかちの中で、中心的事業の役割を担っている組織を紹介する。
JAかわにし(帯広市川西農業協同組合)は北海道の東部・十勝平野の中央部に位置する帯広市を区域としており、12,600haの農用地に小麦、馬鈴薯、てん菜、豆類、長いもを基幹として畜産を含め多岐にわたる野菜類を生産している。近年、長いもの輸出を成功させたことでも知られている154。選別施設は国内最大級で多くの行程で、オートメーション化しているとともに、SGSの認証を取得している(第Ⅱ-3-4-36図)。
第Ⅱ-3-4-36図 JAかわにしの選果場の様子
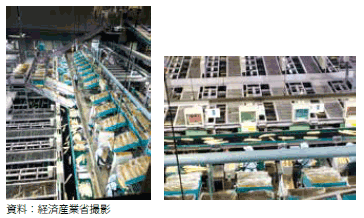
長いも栽培が始まったのは1965年頃、畑作物の自由化で離農が相次いだ時期に夕張市から種子を導入し栽培が始まった。当初、全てが手作業であったが気候風土にマッチし栽培が定着した。長いも産地化に成功した理由として、①野菜栽培の不利地だったことにより生産者が結束したこと。②競合の少ない道外移出品目の選定、③生育の遅さ、種子増殖率の悪さといったデメリットをメリットへと変化させた。④共同計算・販売制度により生産者への所得配分を行ったことによる生産者品質の向上が挙げられる(第Ⅱ-3-4-37図)。
第Ⅱ-3-4-37図 長いも導入による一戸当たり生産額の推移
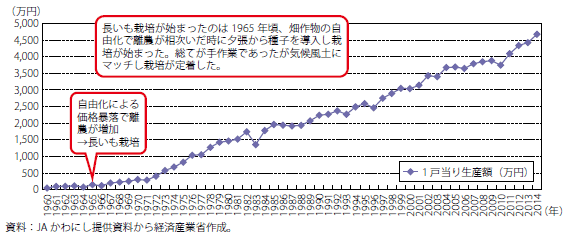
「十勝川西長いも」はJAかわにしを含む8JAで生産されており、全国で見ても最大規模の産地である。豊作時にもかかわらず価格が低下し、生産者の所得が低下することや、規格外が国内市場で敬遠されることから、生産者の所得を安定化させるため、台湾で漢方食品としての長いもの需要を聞きつけ、1999年より輸出を始めた。さらに2007年より米国の中華系スーパー向けの輸出をスタートさせた。SGS認証を取得していることにより、海外での信頼を得て、現在では全出荷量の15%を海外に輸出している(第Ⅱ-3-4-38図)。
第Ⅱ-3-4-38図 十勝川西長いも 輸出数量と輸出額の推移
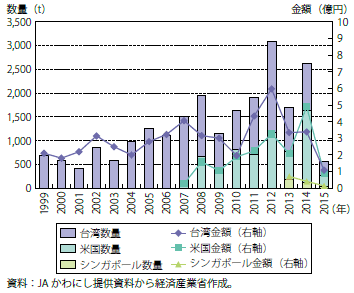
JAかわにしの長いも輸出による経済効果を見ると、台湾輸出により10ha当たりの収入の改善は図られたが、4,000kgを越える豊作になると従来の収入水準に下落していた。米国などの販路の拡大により豊作時の価格下落が緩和し10ha当たりの収入が安定化した(第Ⅱ-3-4-39図)。海外販路拡大による国内需給の適正化が農家所得の向上に貢献している。
第Ⅱ-3-4-39図 長いも10a収量と収入の相関図
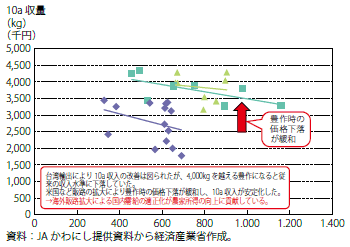
JAかわにしの輸出への取組は豊作による農家の収入低下を防ぐことに成功した取組であると言える。輸出へのきっかけは、貿易商が台湾ニーズをいち早くつかみ、国内の規格外の長いもを台湾へ輸出したことで、国内需給の安定化に繋がっていくといった好循環を生み出している点にある。現在、長いもの生産のうち15%が輸出されているが、「取組の目的はあくまで、国内供給を疎かにせず、国内農家の所得安定化、向上である。」としている。JAかわにしの取組は優れた輸出戦略により、販路拡大に成功している一方、我が国にも高品質なものを生産しながら、まだまだ海外市場に進出に取り組めていない農家も数多く存在している。このような農家や企業の持つポテンシャルを十分に取り込み、その農家や企業を後押しする仕組みが必要となる。その観点から、以下では農林水産物・食品輸出促進についてその取組を取り上げる。
154 日本の野菜の輸出額の推移について見れば、2005年の27.6億円から2015年には55.0億円へと増加傾向にある。野菜の輸出額のうち32.4億円(およそ6割)を長いもが占めている。
(4)農林水産物・食品の輸出促進
我が国の多様な主体がその活力を活用し、農林水産物・食品の輸出に取り組むことを後押しする観点から、政府において、経済再生担当大臣を座長とし、官房長官、農林水産大臣、経済産業大臣等関係閣僚や、民間有識者からなる「農林水産業の輸出力強化ワーキンググループ」を設置し、オールジャパンで政策の検討が行われた。当該ワーキンググループでは、海外市場のニーズの把握、需要の掘り起し、販路開拓、供給面の対応、物流、輸出環境の整備といった課題が取り上げられている。
更に、輸出促進のための先行的な取組として、ジェトロにおける、コンビニエンス・ストアと連携した日本製食品の販路開拓支援や、専門家を通じたマッチング・アドバイスなどのきめ細やかな個別企業支援、クールジャパン機構による、中東やベトナムでの冷蔵物流の整備支援や、日本食レストランを集積させた日本食フードタウン等の出店支援、補助事業を通じた、生産から海外販売までのバリューチェーン構築支援、農林漁業者と中小企業者の連携による機械化・IT化促進を通じた生産性向上など、農商工連携・地域資源活用による商品開発や販路開拓の支援等を実施している。
4.まとめ
これまで農林水産物・食品輸出を下支える食料産業クラスターの視点から欧州の事例を見てきた。
オランダのフードバレーでは、農業分野の研究に特化した大学を中心としたリサーチセンターの存在により、研究施設、研究者、関連企業が集積していることで、オランダの食品産業の活性化へと繋がっている。オランダの食品産業の強みは大学の研究組織の存在だけではなく、そこでのネットワークを通じた柔軟な研究テーマ選択が挙げられよう。これは委託先の企業からのテーマ提案を取り入れたりする柔軟なテーマ設定ができることで研究発展にも繋がっていることが背景にある。またネットワークの強さだけではなく、オランダの物流面の強化など、立地環境においてもオランダの優位性が発揮されており、輸出に強みを持つ環境にあることが指摘できる。
ドイツの取組では、農林水産物・食品輸出を伸ばしているMV州でFood Academyが設立され、人材育成による産業発展から輸出促進、対内投資を目指したクラスター形成が農林水産物・食品輸出を促進する背景にあると考えられる。
欧米諸国に対して、我が国のフードクラスターの事例を見れば、「フードバレーとかち」は、恵まれた環境力を活かした農地利用型で収穫量を伸ばしている。長いもの事例では、収穫量の増加に伴い、所得が不安定化していたが、海外需要の取り込みに成功し、台湾への輸出、続いて米国への輸出に成功している。成功までには国際認証の取得などの工夫が積極的に行われている。
日本の農林水産品・食品は今後も伸びが期待できる産業である。重要なことは、農林水産品・食品の輸出を伸ばしている欧州の事例を参考にしつつ、その中から日本にとって独自に有益な知見や取組を峻別し、輸出に適した地域や品目などを強化していくことが求められよう。



