第2節 ベトナム・インド・イラン
1.ベトナム
(1)期待される経済成長
ASEAN第3位の人口で、今後も人口増加が見込まれること164、ASEAN経済共同体の深化による域内貿易の活発化、TPPに署名したこと等から、同国の経済成長が期待されている。IMFの見通し165では、2016年が6.3%、2017年は6.2%と予想されている。現在のベトナムの年齢別人口を見ると、高度成長期である1970年の日本と同じように、20代人口の割合が高い。また、一人当たり名目GDPが、消費市場の拡大が加速すると予想される目安の2,000ドルを超えている166ことから、今後、同国の中間所得層が拡大することが予想される(第Ⅱ-4-2-1図)。
第Ⅱ-4-2-1図ベトナム(2015年)と日本(1970年)の年齢別人口
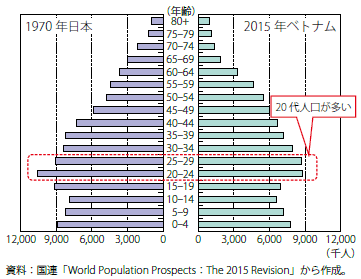
ASEAN先発国が成長鈍化を見せる中、ベトナムの2015年の実質GDP成長率は6.7%と高かった。これは、外資企業の進出による生産拡大・輸出増加と、それによる雇用拡大・所得増加が主因の一つと考えられる。ベトナムでは、リーマンショック後の大規模な景気刺激策により、経常赤字の拡大(2008年の経常収支対GDP比はマイナス11%)と、高インフレ(2008年の23.1%がピーク)に見舞われた。2011年、政府が引き締め政策をしたことで、2012年、2013年と成長率は5%台に鈍化したものの、同年、外資系企業167が携帯電話工場の生産ラインを大規模に増設したことで、輸出が拡大した。外資系企業の投資増加により、同国の雇用が拡大したことや、インフレ率の低下により、家計購買力が向上し、消費拡大に繋がったことなどが、2012年以降の成長を押し上げる結果となった一因と考えられる(第Ⅱ-4-2-2図、第Ⅱ-4-2-3図、第Ⅱ-4-2-4図)168。
第Ⅱ-4-2-2図ベトナムの実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移
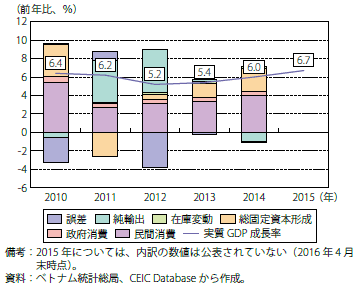
第Ⅱ-4-2-3図ベトナムの輸出の推移(国内セクターと外資セクターの内訳)
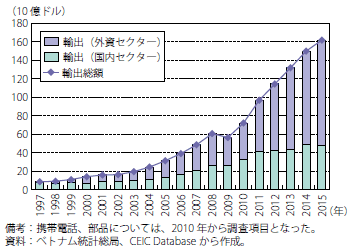
第Ⅱ-4-2-4図 ベトナムの輸出の推移(上位5品目)
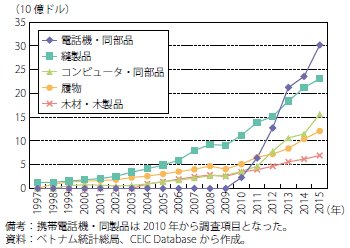
164 国連「World Population Prospects: The 2015 Revision」の中位推計によれば、同国の生産年齢人口のピークは2035年であり、総人口のピークは2055年となっている。
165 2016年4月公表分。
166 世界銀行によれば、同国の2014年の一人当たり名目GDPは2,052ドルとなっている。
167 現在、韓国のサムスン電子・LG電子、フィンランドのノキア、米国のマイクロソフトなどが、ベトナムに携帯電話・部品の生産工場を稼働させているが、特に、韓国のサムスン電子が同国の生産や輸出に大きく寄与している。
168 ベトナムは、現地調達率の低さゆえに、外資系企業からベトナム国内企業への生産面での波及効果が少ないと思われる。外資系企業の生産拠点として成長していくことは、雇用面でのメリットが大きく、内需の拡大につながるが、ベトナムの国内産業の育成が大きな課題になっている。そのため、外資系企業による大企業への投資だけではなく、中小企業等、川上工程への投資を通じて、国内産業の育成に波及することが期待されている。
(2) TPPにより高まる投資先としてのベトナムの魅力
ベトナムはこれまで、米国、カナダ、ペルー、メキシコとの間ではFTAを締結していなかったが、TPPの締結により、これらの国との間で初めて協定を締結することとなる。ベトナムからTPP加盟国への2014年の輸出金額は、約623億ドルであり、輸出全体の41.5%を占める。TPPによる関税撤廃や原産地規則の完全累積制度の導入によって、TPP域内向け製品の生産拠点としてのベトナムの魅力が高まる。
また、ベトナムはこれまでWTO政府調達協定に参加していなかったが、今般、TPPに政府調達に関する規律が導入されることにより、ベトナムにも政府調達のルールが導入されることから、インフラ市場や政府関係機関の調達市場へのアクセスが改善し、我が国企業にとってもベトナム政府調達市場への参入機会が広がることとなる。
加えて、TPPにより、コンビニエンス・ストア等一部の小売業への外資規制の大幅緩和をはじめ、劇場やライブハウスなどクールジャパン関連、旅行代理店など観光関連、広告代理店などビジネス関連、といった幅広い分野での外資規制の緩和が行われることとされており、我が国の様々なサービス業にとっても、新たな進出先としての魅力がある。
(3)我が国とベトナムの経済関係強化
我が国とベトナムとの二国間関係は極めて良好であり、お互いが重要なパートナーと認識している。最近の二国間動向をみると、2015年7月にズン首相が来日し、「広範な戦略的パートナーシップ」の下、両国の協力関係を引き続き強化することで一致した。その際、安倍首相からは、「質の高いインフラパートナーシップ」の下、インフラ整備を質・量両面で支援することや、都市開発プロジェクト等に我が国として積極的に参画を検討すること、日越大学構想の更なる進展に向けた協力を行うことを表明し、ズン首相からは、我が国企業による投資促進のため、投資環境整備を行うと表明した。また、2015年9月には、6年ぶりにベトナム共産党のチョン書記長が公賓として来日し、首脳会談において、今後の関係発展の基礎となる「日越共同ビジョン声明」を宣言している。
2016年3月、林経済産業大臣がベトナムに出張し、主に、TPPを見据えた両国の経済関係の更なる連携を進めるため、フック前副首相(同年4月7日付で首相に就任)を始めとするベトナム政府首脳等と会談を行った。また、ベトナム商工省と、第1回「日越産業・貿易・エネルギー協力委員会」を開催し、繊維産業、模倣品対策、原子力・高効率石炭火力等エネルギーの分野で新たな協力を行うことに合意した169(第Ⅱ-4-2-5図)。
第Ⅱ-4-2-5図第1回「日越産業・貿易・エネルギー協力委員会」の様子

また、我が国にとって、優れた産品を作る中堅・中小企業やコンビニエンス・ストアなどの小売・流通業が、TPPによる関税撤廃や小売・流通分野の外資規制緩和などのメリットを最大限活用することは重要である。林経済産業大臣は、同出張において、ホーチミンで開催されたJETRO主催「ベトナム市場セミナー」に出席し、本年1月に設立した「コンビニエンス・ストアとジェトロの連携推進に関する協議会」の支援策の第一弾として、本年秋に、現地コンビニエンス・ストア最大200店舗で「ジャパンフェア」を開催し、我が国の優れた産品をテスト販売する事業を実施することとした。また、我が国企業が現地展開を進めるに当たって直面する課題を共有し、その解決を図るべく、我が国企業とJETROをはじめとする支援機関の連携を強化するための「ホーチミン海外展開協議会」を設立することとしている。
169 繊維産業については、TPPのメリットを最大限活用し、両国の繊維業界が連携して海外市場獲得に繋げることを後押ししてゆく目的で、「繊維産業政策対話」の立ち上げに合意した。また、模倣品対策協力においては、日本企業の正規品の輸出拡大の目的で、2012年度以降、水際や市場で模倣品を摘発する執行機関に対し、日本の権利者企業が自社製品の真贋の見分け方をトレーニングするセミナーを実施している。
(4)我が国とベトナムの持続的な成長~人材面での協力~
上述の通り、我が国がベトナムとともに持続可能な成長をするためには、今後、同国が必要としているインフラ整備、裾野産業の育成の分野に積極的に貢献していくことが有益であろう。同国は、「早期に工業国になる」ことを国家目標に掲げているが、2015年の実質GDPの産業別内訳を見ると、農林水産業と製造業が16%と同じ割合を占めており、産業構造の高度化の余地が大きいと思われる(第Ⅱ-4-2-6図)。
第Ⅱ-4-2-6図 ベトナムの実質GDPの産業別内訳
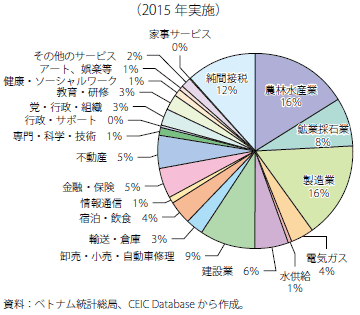
両国の持続的な成長の礎として、両国の人材の交流が重要である。現在、ベトナムから日本への留学生は約3万人を超えており170、過去約1万人がAOTS(海外技術者研修協会)171の研修を受けている。また、越日工業大学では、日本のものづくりを取り込んだ教育をしている。同国の識字率の高さからも、我が国にとってベトナムとの人材面での協力が大きく期待できるところである(第Ⅱ-4-2-7表)。
第Ⅱ-4-2-7表 ベトナムの識字率
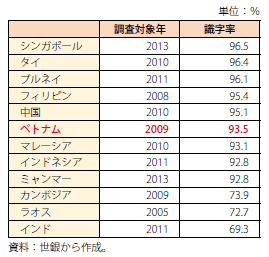
経済産業省は、我が国企業への就職を希望するベトナム人学生が、我が国企業で活躍できるように、インターネット上に新たに「NIN2(ニンニン)ベトナム就職」というコミュニティを2016年7月より設置するとともに、実際に人が集うイベントとして、現地大学から我が国企業への就職を後押しするためのジョブフェアを実施し、マッチングを強化する予定である。
このような両国の人材交流の促進を通じ、更なる日越経済関係の発展が期待される。
170 ベトナムから日本への留学生数(27年度):38,882人
(出典)独立行政法人日本学生支援機構(JASSO):平成27年度外国人留学生在籍状況調査結果
http://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_e/2015/index.html![]()
171 現HIDA(海外産業人材育成協会)
2.インド
(1)インド市場の高い潜在力
インドの人口は、現在約12億6000万人であり、中国に次いで2番目に多く、2022年には中国を抜いて世界一になることが予想されている172(第Ⅱ-4-2-8図)。国民の平均年齢が20代半ばと若年層が多く、富裕層・中間層も増加している。また、GDP(購買力平価)の世界に占める割合を見ると、2008年に我が国を抜いていることがわかる(第Ⅱ-4-2-9図)。また、同国は、豊富な天然資源に恵まれており、石炭、ボーキサイト、鉄鉱石の埋蔵量は世界有数である173。
第Ⅱ-4-2-8図 インドの人口の推移予測(中国との比較)
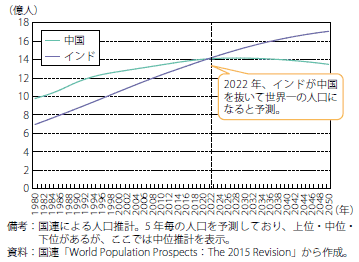
第Ⅱ-4-2-9図 インドのGDP対世界比(購買力平価換算)の推移
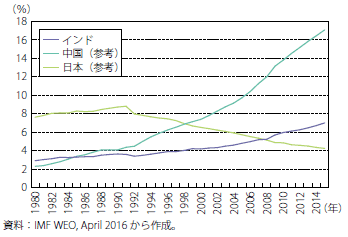
172 国連「世界人口予測」による。
173 天然資源の多くは、オディシャ州で産出されている。
(2)我が国企業の進出促進
インド進出日系企業は年々増加し、2016年2月時点で1229企業、4417拠点となっており、特に、北・北東インドに1490拠点と多く進出している174(第Ⅱ-4-2-10図、第Ⅱ-4-2-11図)。4417拠点の業種別内訳は、金融業・保険業が1449拠点と一番多く、次に、卸売・小売業(575拠点)、サービス業(398拠点)と続いている(第Ⅱ-4-2-12表)。
第Ⅱ-4-2-10図 インド進出日本企業数の推移
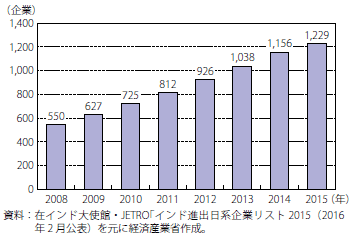
第Ⅱ-4-2-11図 日本企業の進出分布
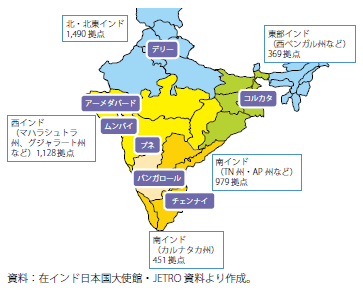
第Ⅱ-4-2-12表 日本企業の業種別拠点数
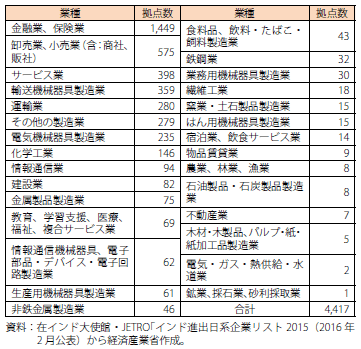
なお、経済産業省がインドに既に進出している日系企業に対し実施した、インド進出にあたり直面した課題や改善を要望する制度についてのアンケート175では、特に、①土地取得の難しさ、②不十分なインフラ、③許認可の煩雑さ、④複雑な税制という4点が挙げられた(第Ⅱ-4-2-13表)。
第Ⅱ-4-2-13表 進出日系企業が直面した課題
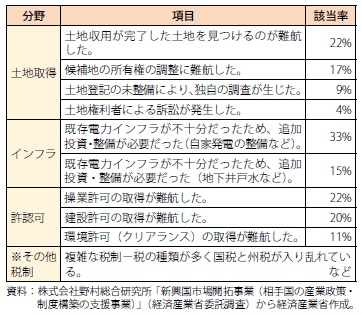
上記のような問題を解決するため、2015年4月に日印間で署名された「日印投資促進とインド太平洋経済統合に向けたアクションアジェンダ」では、既存の枠組みである経済特区(SEZ:Special Economic Zone)や国家投資製造区(NIMZ:National Investment and Manufacturing Zones)に劣らない投資インセンティブと世界最高水準のインフラを備えた、日本工業団地(JIT:Japan Industrial Township)を開発することで合意した。現在、日本工業団地として12の候補地点(第Ⅱ-4-2-14図)を整備していくことになっている。経済産業省とインド商工省や重点州政府との間で、日本企業が投資を行いやすくなるようなインセンティブ措置(電力の安定供給策、税制優遇措置、州の許認可窓口の一元化、円借款を効果的に使った周辺インフラ整備等)について継続的に協議を行っている。なお、日本工業団地の建設はそれぞれ進捗段階が異なるが、例えば、ラジャスタン州に建設されたニムラナ日本企業専用工業団地は、2016年1月時点で、入居企業数は46社(操業中43社、建設中3社)であり、分譲可能区画が全て売り切れの状況になっている。
第Ⅱ-4-2-14図 「日本工業団地」12の候補地点
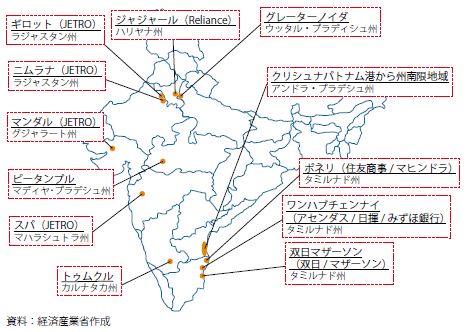
その他、ビジネス環境整備に関連する州政府の大きな権限を鑑み、経済産業省としては、日系企業が集積する戦略州との連携を強化している176。また、インド日本商工会では、2009年より毎年インド政府に建議書を提出するなど、インドに進出している日系企業がスムーズにビジネスを進められるよう交渉を継続している。このような日本からの働きかけにより、ビジネス環境が確実に改善していくことで、今後も日系企業によるインド市場への進出がより活発化すると思われる。
174 在インド大使館とJETROの取りまとめる「インド進出日系企業リスト2015(2016年2月公表)」から引用。企業数は①本邦企業(インド現地法人化されていない企業)の駐在員事務所、支店等、②現地法人化された日系企業(100%子会社および合弁会社の本店)、③日本人がインドで興した企業の合計。
175 経済産業省平成26年度新興国市場開拓事業(相手国の産業政策・制度構築の支援事業(インド:対インド投資・貿易促進に関する調査))における企業アンケート。直面した課題として該当する項目についてチェックをする方式で、複数回答可としている。詳細は、同報告書(http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000212.pdf )を参照されたい。
176 経済産業省は、アンドラプラデシュ州、グジャラート州、カルナタカ州、ラジャスタン州、タミルナドゥ州、マハラシュトラ州、マディヤ・プラデシュ州等と政策対話の枠組みを設け、日系企業の投資・進出促進、ビジネス環境整備について議論を行っている。
(3)日印新時代
2015年12月、安倍総理はインドを訪問し、モディ首相と日印首脳会談を実施した。安倍総理は、「強いインドは日本のためになる、強い日本はインドのためになる。モディ首相と協力して、アジアや世界の平和と反映を牽引していく。」「今日、ここから、『日印新時代』が始まる。」と日印新時代の幕開けを謳うとともに、モディ首相からも、「日本ほどインドの経済変革に決定的な役割を果たしてきたパートナーはいない。日本ほどインドの経済的な夢を実現する上で重要となる友はいない。」と述べる等、日印関係が今後更に緊密かつ強固になっていくことを象徴する首脳会談となった(第Ⅱ-4-2-15図)。
第Ⅱ-4-2-15図 安倍首相を迎えるモディ首相の様子

我が国企業のインドへの直接投資やインドでの事業活動やインフラ整備等を幅広く支援するための「日印Make in India特別ファシリティ」の創設、「日本工業団地」周辺のインフラ整備(道路、電力、水等)の推進、インド高速鉄道プロジェクトへの日本の新幹線方式の採用、インドにおける鉄道協力の推進と我が国企業のビジネスチャンスの拡大、メトロ建設計画への協力、民生用原子力分野における協力、高効率石炭火力及び再生可能エネルギー分野における協力、インドから我が国へのIoT関連分野の投資を促進するための「日本・インドIoT投資イニシアティブ」の設立や若手インド人材による学生交流、IT研修、短期交流の推進等を両国首脳で合意し、今後とも日印経済関係の一層の強化を行っていくこととしている。
3.イラン
(1)資源国の中でもポテンシャルが高いイラン
イランは資源国の中でも特に経済が大きく伸びる余地がある国であり、市場としてのポテンシャルが高い。まず人口に関して言えば、中東地域の中でも特に高く、世界的に見ても18位の人口数となっている。他の産油国と比較しても多くの人口を抱えている(第Ⅱ-4-2-16図)。2035年までは主要産油国の中でも最も生産年齢人口が高い国の一つである。以降、生産年齢人口は下落していくものの、他の産油国と比較しても多い値を維持することが推測されている(第Ⅱ-4-2-17図)。
第Ⅱ-4-2-16図 中東各国の人口比較(2015年)
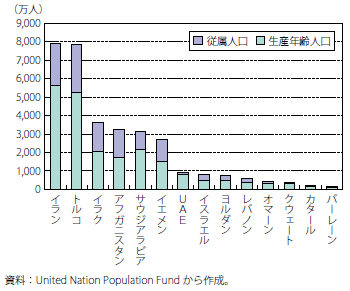
第Ⅱ-4-2-17図 主要産油国の生産年齢人口推移
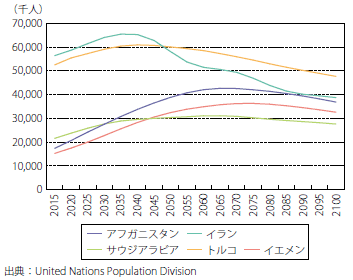
イランは豊富な資源埋蔵量を持っており、天然ガスの確認埋蔵量は世界第1位(世界シェア18%)であり、原油に関しても世界第4位(世界シェア9%)である(第Ⅱ-4-2-18図)。資源が豊富な国では資源依存度が高く、非資源分野の産業が育っていないことが多いが、イランの場合には歳入に占める石油由来収入は約4割に留まっており、歳入の約8割をエネルギーに依存しているバーレーン等とは対照的である(第Ⅱ-4-2-19図)。産業では特に自動車産業が強く、2010年の経済制裁前ではロシアや英国を生産台数で上回っていた(第Ⅱ-4-2-20表)。
第Ⅱ-4-2-18図 イランの資源埋蔵量の世界比較
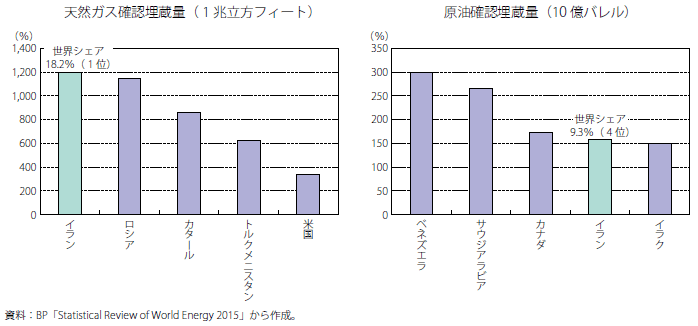
第Ⅱ-4-2-19図 各国の歳入に占める非石油収入の割合(2012-2014の平均)
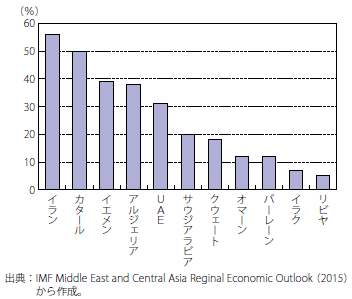
第Ⅱ-4-2-20表 自動車生産台数ランキング(万台)

制裁下で生産量は下落していたものの、もともと豊富は天然資源を持っており、原油以外の産業も強いことから、資源下落によって他の資源国は経済成長の落ち込みが予想される中、イランは制裁解除によって大幅に経済成長する見通しもある177。
177 IMF World Economic Outlook, October 2015より。
(2)イランが抱える課題
イランは制裁が緩和されたばかりであり、足下の経済情勢は不安定な状況である。原油生産量は欧州が制裁によって原油輸入を停止した2012年以降は大きく下がっており、また資源価格の下落によって2015年は2014年度比較して石油収入が約240億ドル程度落ち込んでいる(第Ⅱ-4-2-21図)。他の産油国と比較しても対GDP比に占める歳入は低い値となっており、イランの財政収支は急速に落ち込んでいるため、財政健全化が急務となっている(第Ⅱ-4-2-22図、第Ⅱ-4-2-23図)。
第Ⅱ-4-2-21図 イランの原油生産量
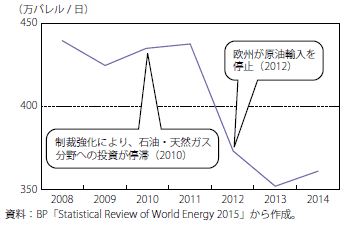
第Ⅱ-4-2-22図 主要産油国の歳入(対GDP比)
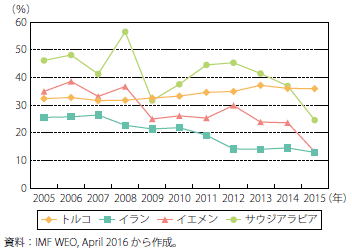
第Ⅱ-4-2-23図 イランの財政収支の推移
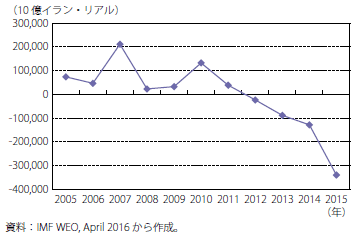
(3)他国のイランへの市場参入状況
イランは、足下は財政収支の悪化などがあり、不安定要素を抱えているが、依然として投資先としては魅力的であり、既に我が国以外の中国、韓国、欧州などの52か国と投資協定を結んでいる。また、イランの石油・天然ガス資源のポテンシャルについて、国際石油開発企業や我が国企業も強い関心を有しており、イラン政府は2015年11月に石油・天然ガス開発プロジェクトに関する新たな契約方式の概要について、発表を行った。今後、明らかにされる当該契約方式の詳細情報に国内外の企業が注目している。
