第2節 通商ルールを巡る動き
1.多角的自由貿易体制の要としての世界貿易機関 (WTO)
本節では、WTO12に関わる最近の動きとして、ドーハ・ラウンド交渉の状況、①ITA(情報技術協定)拡大交渉、②環境物品交渉、③TiSA(新たなサービス貿易協定)交渉といったラウンド外のプルリ交渉のほか、保護主義抑止に向けた取組、WTO協定の実施、我が国の紛争解決手続の活用を概観する。
12 1930年代に蔓延した保護主義が第二次世界大戦の一因となったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し、1948年に、最恵国待遇・内国民待遇を大原則とするGATT(関税及び貿易に関する一般協定)が発効した。GATT締約国は、数次のラウンド交渉 を含む8度の多角的交渉を経て、相当程度の関税削減及び関税以外の貿易関連ルールの整備を実現し、1995年には、GATTを発展的に改組してWTO(世界貿易機関)を設立した。現在162か国が加盟するWTOは、①交渉(ラウンド交渉などによるWTO協定の改定、関税削減交渉)、②監視(多国間の監視による保護主義的措置の抑止)、③紛争解決(WTO紛争解決手続による貿易紛争の解決)の機能を有し、多角的な貿易を規律する世界の通商システムの基盤となっている。具体的には、①WTOの交渉機能については、2001年、WTO設立後初のラウンド交渉として「ドーハ開発アジェンダ」が立ち上げられ、14年経った現在に至るまで交渉が継続されている。ラウンド交渉が進まない中、ITA拡大交渉のほか、環境物品交渉や新たなサービス貿易協定交渉といった有志国による個別ルール・分野毎の複数国間交渉(プルリ交渉)が積極的に行われている。②WTOの監視機能は、保護主義を抑止し、自由貿易体制の維持に重要な役割を果たしている。近年、世界経済の減速等を受けて、保護主義的な動きが活発化しており、保護主義監視、保護主義抑止のための政治的コミットメントが重要となっている。③WTOの紛争解決機能は、二国間の貿易紛争を政治化させることなく中立的な準司法的手続によって解決するシステムである。WTOにおいて、協定(ルール)の実施に係る紛争解決手続が有効に機能しており、新興国を含め、紛争解決手続の活用件数が増加している。我が国もルール不整合である他国の措置による自国の不利益を解消し、先例の蓄積によってルールを発展させることを目指し積極的に活用している。
(1)ドーハ・ラウンド交渉(多角的交渉の推進)
2001年にカタールのドーハで行われた第4回WTO閣僚会議においては、WTO設立後初のラウンド交渉として途上国の要求に配慮する形でドーハ開発アジェンダ(以下「ドーハ・ラウンド」)が立ち上げられた。同ラウンドは農林水産物など鉱工業品の貿易のみならず、サービス貿易の自由化に加え、アンチ・ダンピングなどの貿易ルール、環境、途上国問題のほか、ルール作りを検討すべき分野として投資、競争、貿易円滑化なども含んでいた(第Ⅲ-1-2-1表)。
第Ⅲ-1-2-1表 ドーハ・ラウンド 一括受諾の交渉項目と主要論点
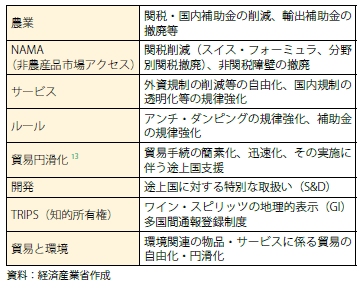
ドーハ・ラウンドは、全加盟国一致(コンセンサス)を原則としているため、先進国と新興途上国の間の利害対立により交渉がなかなか進まず、2001年の立ち上げ後一進一退を繰り返したが、2008年7月の閣僚会合に決裂した後、交渉が停滞した(第Ⅲ-1-2-2図)。2011年12月の第8回閣僚会議では、議長総括における「政治ガイダンスの要素」として、ドーハ・ラウンドについて、近い将来の一括受諾の見通しがないことを認めつつも、「新たなアプローチ」を見出す必要性を共有し、進展が可能な分野で、先行合意を含め議論を進めることが合意された。その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発が進展可能な分野であるとの共通認識が形成され、2013年12月にインドネシア・バリで開催された第9回WTO閣僚会議(MC9)において精力的な交渉の結果、WTO設立後初のマルチ協定である貿易円滑化協定を含むバリ・パッケージが合意された。
第Ⅲ-1-2-2図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯
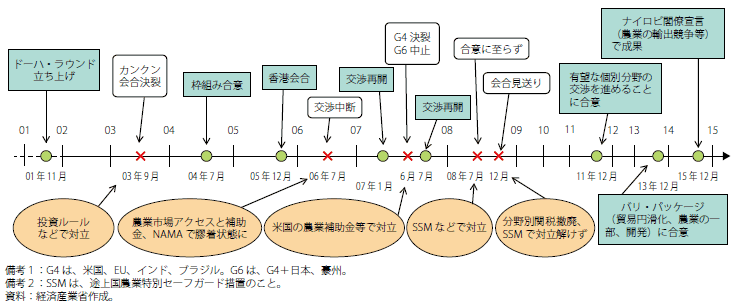
その後、第10回WTO閣僚会議(MC10)における成果につき、加盟国で検討が進められたが、14年間の長期の交渉にも関わらず十分な成果を出せていないドーハ・ラウンド交渉に代わる「新たなアプローチ」が必要であるとする先進国と交渉継続を主張する途上国の間での見解の懸隔が明らかになった。また、グローバル・バリュー・チェーン(GVC)の深化やIT技術など時代の変化に対応するための新たな課題についても、米、EU、日本等の先進国と新たな課題への取組に慎重な姿勢を示すインド、中国等の途上国の間で意見は対立した。
このような中、2015年12月にケニア・ナイロビで開催された第10回WTO閣僚会議(MC10)においては、農業の輸出競争(輸出補助金撤廃、輸出信用の規律強化等)、開発分野で合意を得るとともに、ITA拡大交渉の妥結をみた(詳細後述)。ドーハ・ラウンドの今後の扱い及び新たな課題への取組については、最終的に見解は一致せず、閣僚宣言にドーハ・ラウンド交渉についての双方の主張が両論併記され、時代に即した新たな課題への取組を求める国があることも明記された。
13 ラウンド立ち上げ当初は、投資、競争、貿易円滑化、政府調達の透明性のいわゆる「シンガポール・イシュー」が検討の対象として含まれていたが、カンクン閣僚会議で貿易円滑化のみにつき交渉を始めることとされた。
(2) ITA(情報技術協定)拡大交渉
第10回WTO閣僚会議(MC10)の重要な成果の一つがITA(情報技術協定)の拡大交渉の妥結であった。201対象品目の全世界年間貿易額約1.3兆ドルは総貿易額の約10%を占める規模であり、2016年7月1日から関税撤廃が順次開始され、2019年7月には約90%の関税が、2024年1月には全品目の関税が完全に撤廃される。
①拡大交渉の背景
ITA拡大交渉に先行して合意された IT製品の関税撤廃に関する ITA (情報技術協定)は、1996年12月のシンガポールWTO閣僚会議の際に日米EU韓など29メンバーで合意され、1997年に発効した。その後の参加国拡大の結果、2016年3月末現在、対象品目17の世界貿易総額の97%以上を占める82メンバー(中国、インド、タイが含まれているが、 メキシコ、 ブラジルや南アフリカ等は未参加) が協定に参加している。ITAは世界貿易総額の約15%(5.3兆ドル(2013年))の関税撤廃に貢献している。主な対象品目は、半導体、コンピュータ、通信機器、半導体製造装置等である。
現行協定の発効からの技術進歩を受け、現行協定の品目リスト拡大と品目リストの対象範囲の明確化に対する各国産業界からの期待の高まりもあり、新たにITAの対象とする品目リストの拡大や、対象品目の明確化を目的として、2012年5月にITA拡大交渉が立ち上げられた。
②拡大交渉妥結までの経緯
交渉立ち上げ以降、月に1回の頻度で交渉会合がジュネーブで開催され「品目候補リスト」の作成が進み、2012年秋からは、フィリピン、シンガポール、中国が参加し、品目候補の絞り込みが始まったが、中国が多くの対象品目の除外を主張したため、交渉はしばしば中断された。
2014年11月のAPEC北京首脳会議の際に行われた米中首脳会談における米中間の対象品目合意の後、2015年7月、交渉参加メンバーは拡大対象品目201品目(新型半導体、半導体製造装置、デジタル複合機・印刷機、デジタルAV機器、医療機器等)に合意し、同月、関税撤廃期間や実施スケジュール等の合意に関する宣言文とともに、WTO一般理事会で報告・公表された。
同年9月からは、我が国がITA拡大交渉の議長を務め、個別の対象品目の関税撤廃期間等に関する交渉を行った。そして、2015年12月、ケニア・ナイロビで開催された第10回WTO閣僚会議(MC10)において、林経済産業大臣が議長を務め、対象品目の世界貿易額の90%以上をカバーする、53メンバー(EU加盟国28か国を含む)で交渉妥結に至った。
201対象品目の全世界貿易額は年間1.3兆ドルを上回り、世界の貿易総額の約10%に相当し、自動車関連製品が世界貿易に占める割合4.8%を大幅に上回る規模である。日本からの201対象品目の対世界輸出額は約9兆円と総輸出額約73兆円の約12%を占め、関税削減額は約1700億円と試算される。
(3)環境物品交渉
①議論の背景
2001年のドーハ閣僚宣言において、「環境関連物品及びサービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削減」に関する交渉の立ち上げと、貿易と環境に関する委員会特別会合(CTESS)の設置が盛り込まれたことを受け、CTESSにおいて関税削減・撤廃の対象となる環境物品リストに関する議論が行われてきた。
その後、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中、APECに場を移して環境物品の関税削減・撤廃が議論された。2011年11月のAPECホノルル首脳会議で、2015年末までに対象物品の実行関税率を5%以下に削減する旨合意され、2012年9月のAPECウラジオストク首脳会議で、その対象品目として54品目に合意した。
②交渉立ち上げまでの経緯
APECで環境物品54品目の関税削減が合意されたことも受け、2012年11月、環境物品の自由化推進国で形成する「環境フレンズ」メンバー(日本、米国、EU、韓国、台湾、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー)は、WTOでの今後の環境物品自由化の交渉の進め方について議論を開始した。
その後、2013年10月のAPECバリ首脳会議で、APEC環境物品リストを基にWTO で前進する機会を探求する旨合意したことも受け、 ジュネーブにおける議論が加速した。2014年1月、ダボスのWTO非公式閣僚会合の開催にあわせ、有志の14メンバー(日本、米国、EU、中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、コスタリカ)は、WTOにおける環境物品交渉の立ち上げに向けた声明を発表した。
2014年7月、有志の14メンバーで環境物品交渉を立ち上げ、APECで合意した54品目より幅広い品目で関税撤廃を目指すことを確認した。
③交渉の現状
2014年7月以降、2か月に1~2回程度のペースで交渉会合がジュネーブで開催され、各メンバーからの要望品目の積み上げ作業が行なわれた。
2015年4月以降、積み上げが行なわれた品目について、環境クレディビリティの観点から議論が行なわれ、対象品目の絞り込み作業が進められた。
2015年11月の交渉会合では、同年12月のケニア・ナイロビで開催された第10回WTO閣僚会議(MC10)での品目合意を目指し議論が行なわれたものの、結局合意には至らなかった。交渉参加メンバーは、2015年1月にはイスラエル、5月にはトルコとアイスランドが加わり、2016年3月末現在、17か国・地域が参加している。
2016年5月に開催されたG7伊勢志摩サミットの宣言文において、「9月のG20杭州サミットまでに、広範な環境製品に対する障壁を撤廃する、野心的な環境物品に関する協定(EGA)の妥結を目指す」ことで一致し、G20杭州サミットまでの妥結を目指すこととされるところであり、交渉が続けられている。
(4) TiSA (新たなサービス貿易協定)交渉
1995年のGATS発効から長期間が経過し、この間にインターネットの普及を始めとする技術革新の影響を受け、サービスの提供・消費の態様が大きく変化してきていることを背景に、WTOにおいても状況変化に対応した約束表の改訂や新たなルールの策定が求められてきた。しかしながら、ドーハ・ラウンドが膠着し、急速な進展が見込めない状況となり、各国はFTAやEPAの締結等を通じてサービス貿易の自由化を推進してきた。
こうした中、2011年12月の第8回WTO閣僚会議(MC8)の結果を受け、2012年初頭から、「新たなアプローチ」の一環として、有志国・地域によるサービス貿易自由化を目的とした新たな協定の策定に関する議論が開始された。我が国を含む有志国・地域は、自由化の約束方法、新たなルールなど、21世紀にふさわしい新たなサービス貿易協定に向けた議論を重ね、2013年6月には、本格的な交渉段階に移ったことを確認する共同発表を行い、2か月に1回程度の頻度で交渉を行っている。2016年3月末現在のメンバーは、23か国・地域(日、米、EU、豪州、カナダ、韓国、香港、台湾、パキスタン、イスラエル、トルコ、メキシコ、チリ、コロンビア、ペルー、コスタリカ、パナマ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン及びモーリシャス)である。
(5)保護主義の抑止
世界経済危機以降、自国産業支援や雇用確保を目的とした保護主義的措置の導入を求める政治的圧力が各国で高まった14。そうした国内の圧力を受けて保護主義的措置をとる国があると、他国の追随や報復などの連鎖を招き、世界全体に保護主義が蔓延し、世界貿易・経済に悪影響を及ぼすことが懸念された。そうした中で、多角的貿易体制を体現するWTOは保護主義を抑止し、自由貿易体制の維持に重要な役割を果たしている。近年、世界経済の減速等を受けて、保護主義的な動きが活発化しており、下記に述べるような保護主義監視、保護主義抑止のための政治的コミットメントが重要となっている。
2015年11月に公表されたG20諸国・貿易投資措置に関する報告書(第14版)は、調査期間中にG20諸国が新たに導入した貿易制限的措置数が前期同様高い水準にあるとして、G20諸国が保護主義に対抗する努力を強化するよう訴えている。こうした報告書は、各国の貿易措置の監視を強化し、保護主義的措置の拡散を防止する効果が期待される。
また、G20やAPECの場では保護主義抑止を求める国際的な高いレベルの政治宣言がなされてきた。加盟国はWTO協定を遵守する義務を負うが、政治合意により協定以上のコミットが表明されるという意義がある。昨年10月の日中韓経済貿易大臣会合、11月のAPEC閣僚会合、G20アンタルヤ・サミット、12月の第10回WTO閣僚会議(MC10)の成果文書において、保護主義抑止の必要性について再確認した。
G20、APECにおける保護主義抑止の政治宣言については、保護主義抑止の実効性を高めるため、WTO整合的であっても重大な保護主義的影響を及ぼす措置の最大限の自制に加えて、2つの大きな要素が存在する。一つは、「スタンドスティル(現状維持)」のコミットメントであり、新たな保護主義的措置を実施しないことを約束している。もう一つは、既に導入された保護主義的措置を是正すること、即ち、「ロールバック」のコミットメントである。2015年11月にトルコ・アンタルヤで開催されたG20アンタルヤ・サミットでは、2018年までの「スタンドスティル」約束及び「ロールバック」のコミットメントを再確認した15。
14 『通商白書2009』第2章第3節参照
15 2014年のG20ブリスベン・サミットでも、2013年のG20サンクトペテルブルグ・サミットにおけるスタンドスティル及びロールバックのコミットメントが再確認された。
(6)WTO協定(ルール)の実施
WTO協定は、加盟国・地域間に通商摩擦・紛争が生じた際に、ルールの解釈・適用を通じてその解決を図る紛争解決手続に係る規律を備えている。この紛争解決手続による措置の是正勧告は、履行監視手続や履行されない場合の対抗措置等も用意されており、履行率が高く実効性が高いものとなっている。また、通商摩擦を政治問題化させずに解決することができるという点でも有益である。1995年のWTO発足以来、紛争解決手続が利用された案件は504件(2016年3月末現在)に上っている。
我が国が当事国としてWTO紛争解決手続に付託している案件のうち経済産業省が関与して、解決を図っている最近の事例の詳細は、第2章7.WTO紛争解決手続きを活かした取組を参照されたい。
2.経済連携協定
(1)経済連携 (EPA/FTA) を巡る状況
経済連携の推進は、輸出企業にとっては、関税削減等を通じた輸出競争力の維持又は強化の面で意義があり、他方で、外国に投資財産を有する企業やサービスを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義がある。
1990年代以降、国際経済環境や各国の開発戦略の変化により地域統合の動きが加速し、EPA/FTAの締結数が年々増加してきている。その背景としては、① 欧米諸国が経済的関係の深い近隣諸国との間で貿易・投資の自由化・円滑化等による経済連携を図る動きを活発化させたこと(例:米国がNAFTA(1994年発効)、EC(1993年にEUへ発展)が単一市場の構築への取組を加速させる等)、②NIEsやASEANがいち早く経済開放を推し進めることにより高成長を果たす中、チリ・メキシコ・ペルー等の新興国が貿易・投資の自由化や市場メカニズムの導入へと経済政策を転換させ、その中でEPA/FTAを活用する戦略を採ったこと、さらに、③ 2000年代後半以降、WTOドーハ・ラウンド交渉が停滞する中、世界の主要国が貿易・投資の拡大のために積極的にEPA/FTAを結ぶようになったこと等が挙げられる。GATT第24条等に基づく地域貿易協定 (RTA)16の通報件数は、1990年には27件に満たなかったが、2016年2月1日時点で625件まで増加している17。
16 地域貿易協定(Regional Trade Agreement):EPA/FTAや関税同盟を含む特定の国・地域の間での貿易の自由化等を約束する協定の総称。
17 WTOウェブサイト(http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm![]() )参照。
)参照。
(2)アジア太平洋地域の経済統合と世界のFTA動向
東アジア・アジア太平洋地域では、2002年に我が国がシンガポールとのEPAを発効させたことを受けて、FTAを結ぶ動きが活発化した。2000年代後半にかけてシンガポール、マレーシア、韓国、中国等が東アジア地域内外の国・地域との間で多くのFTAを発効させた。
ASEANにおいては、2010年、ASEAN原加盟国6か国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ)の間で関税が原則撤廃されるとともに、物品分野については全ての「ASEAN+1」のFTAが発効し、東アジア地域のFTAが新しい段階に進んだといわれる。「ASEAN+1」のFTAとは、ASEANと周辺6か国(日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)が個別に結んだFTAであり、ASEANをハブとして東アジアにFTA網が張り巡らされた形となった。
こうしたFTA網の整備も手伝って、東アジア地域、あるいは最終消費地も加えてアジア太平洋地域では、工程間分業、生産拠点の集約化及び最適配置は相応に進展してきている(第Ⅲ-1-2-3図)が、広域経済連携によって更に統一的なスケジュールで関税を削減し、ビジネス活動に関する様々なルールを共通化することができれば、企業がこの地域全体にまたがるサプライチェーンの高度化に取り組むことを一層後押しすることとなる。
第Ⅲ-1-2-3図 東アジア地域におけるサプライチェーンの実態
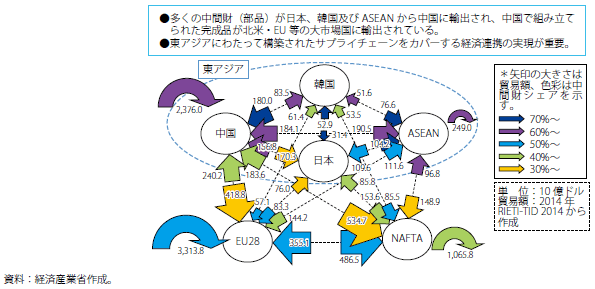
特に、アジア太平洋地域では、APEC参加国・地域の間で、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP:エフタープ)の実現が目指されており、そのための道筋として、TPP(環太平洋パートナーシップ)、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)、日中韓FTA等の広域経済連携の取組が同時に進行している(第Ⅲ-1-2-4図)。
第Ⅲ-1-2-4図 FTAAPへの道筋
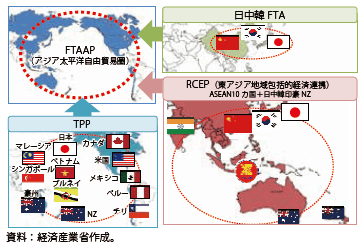
2013年3月には日中韓FTA、4月には日EU・EPA、5月にはRCEPについてそれぞれ交渉が開始され、米国とEUとの間でも2013年7月に環大西洋パートナーシップ(TTIP) 協定交渉が開始した。2014年5月現在、北米、欧州、アジア太平洋の各地域をつなぐ様々な経済連携の取組が同時並行で進行している(第Ⅲ-1-2-5図)。これらの取組が相互に刺激し合うことで高い相乗効果を生み、先進国間でも高いレベルのEPA/FTAの締結が進むことで世界全体の貿易投資に関するルール作りが進むことが期待されている。
第Ⅲ-1-2-5図 世界のFTA動向
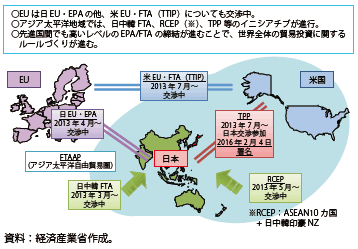
3.投資関連協定
(1)世界の投資関連協定を巡る状況
1980年代以降、世界の海外直接投資は急速に拡大しており、世界経済の成長をけん引する大きな役割を果たしている。海外直接投資残高の対GDP比は、1980年には対外直接投資額で5.8%、対内直接投資額で5.3%であったのに対し、2014年にはそれぞれ33.4%、33.6%に伸びている18。
海外直接投資の拡大を踏まえ、世界各国は、投資先国における差別的扱いや収用(国有化も含む)などのリスクから自国の投資家とその投資財産を保護するため、投資協定を締結してきた。投資ルールは、貿易におけるWTO協定のような多国間協定がなく、二国間もしくは地域協定が中心となっている。
世界の投資協定数は大きく増加しており、2014年時点で2,926件に達している(第Ⅲ-1-2-6図)。国別では、ドイツ、中国、英国、フランスといった国々が100件前後の投資協定を締結している。
第Ⅲ-1-2-6図 世界の投資協定数の推移
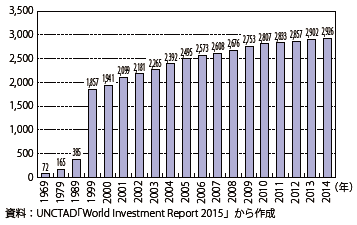
18 UNCTAD「World Investment Report 2015」
(2) 投資関連協定の主な規定内容
従来の投資協定は、投資受入国における投資財産の収用や法律の恣意的な運用等のカントリー・リスクから投資家を守り、投資家を保護することを主目的として締結されてきた。こうした内容の協定は「投資保護協定」と呼ばれ、投資財産設立後の内国民待遇や最恵国待遇、収用の原則禁止および合法とされる収用の要件と補償額の算定方法、自由な送金、締約国間の紛争処理手続、投資受入国と投資家との間の紛争処理等を主要な内容とする。1990年代に入ると、そのような投資財産保護に加えて、投資設立段階の内国民待遇や最恵国待遇、パフォーマンス要求19の禁止、外資規制強化の禁止や漸進的な自由化の努力義務、透明性確保(法令の公表、相手国からの照会への回答義務等)等を盛り込んだ投資関連協定(「投資保護・自由化協定」)が出てきた(第Ⅲ-1-2-7表)20。
第Ⅲ-1-2-7表 投資関連協定の内容
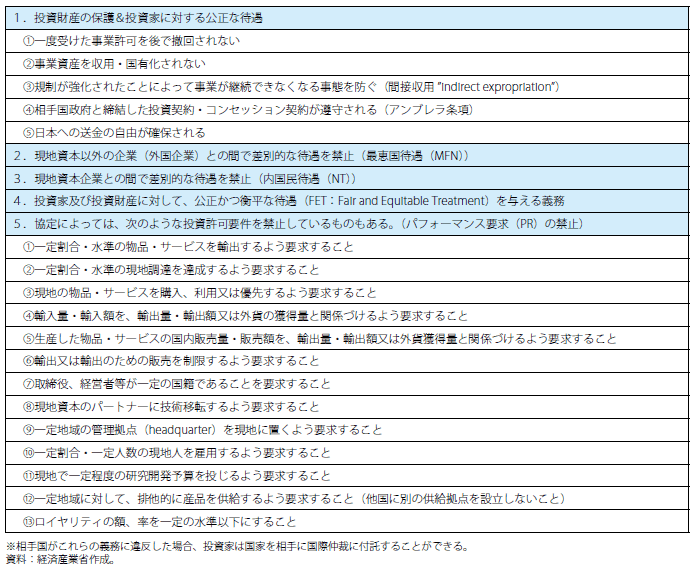
19 例えば、一定の現地部材(ローカルコンテンツ)比率を満たすことや、製造したものの一定の比率を輸出すること等、投資活動に関する条件として課される特定の要件。
20 代表的なものとしてNAFTAの投資章があり、我が国の場合、二国間EPAの投資章や、日韓、日・ベトナム、日・カンボジア、日・ラオス、日・ウズベキスタン、日・ペルー投資協定等がこのタイプにあたる。
(3) エネルギー憲章条約の主な規定内容
投資関連協定と同じように、国際仲裁への付託を可能とする条約としてエネルギー憲章条約がある。1998年に発効したエネルギー憲章条約は、旧ソ連及び東欧諸国におけるエネルギー分野の市場原理に基づく改革と企業活動の促進を目指すものである。エネルギー分野における投資の自由化及び保護に関し、一般的な二国間の投資保護協定と類似の内容(締約国が外国投資家の投資財産に対して内国民待遇 (NT)又は最恵国待遇(MFN)のうち有利なものを付与すること、一定の要件を満たさない収用の禁止、送金の自由、紛争解決手続等)について規定している。エネルギー憲章条約の締約国は、2016年1月現在で東欧やEU諸国等48か国及び1国際機関である。ロシアや豪州は署名はしたものの未批准であり、また、オブザーバー参加にとどまる国(米国、カナダ、中国、韓国、サウジアラビアなど)も存在する。
