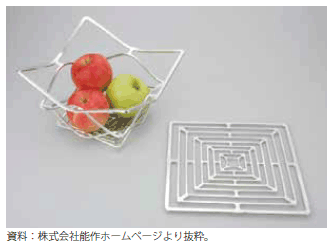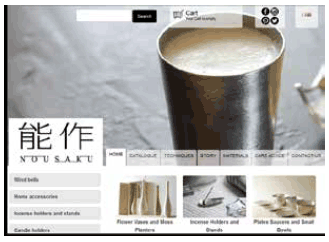第1節 通商協定をはじめとしたルール形成
本節では通商協定をはじめとしたルール形成について扱う。TPPの大筋合意・署名やそれを受けた「総合的なTPP関連政策大綱」の策定など経済連携協定をめぐる動きのほか、APEC、投資関連協定などについて扱う。
1.TPPの署名と活用
(1)環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の署名
我が国は、環太平洋パートナーシップ協定(以下、TPP)に関し、平成25年3月に参加を表明、同年7月から豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの11か国との交渉に参加した。その後の交渉を経て、2015年10月に米国アトランタで大筋合意に至り、2016年2月4日に署名がなされた21。世界のGDPの約4割、日本の輸出の約3割を占める市場で、関税撤廃のみならず、幅広い分野で新しいルールを構築する(第Ⅲ-2-1-1、2図)。
第Ⅲ-2-1-1図TPP協定交渉参加国が世界のGDPに占める割合(2014)
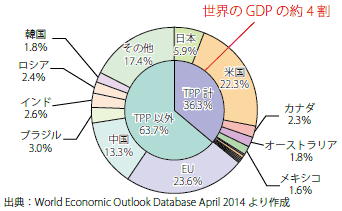
第Ⅲ-2-1-2図日本の輸出に占めるTPP協定交渉参加国の割合(2014)
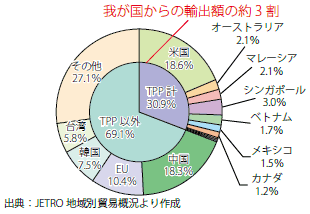
TPPにより、我が国が輸出する工業製品について、協定発効時に輸出額で見て76.6% 22の関税が撤廃され、最終的には99.9% 22の関税が撤廃されることとなる。例えば、自動車部品については、米国(現行税率主に2.5%)への輸出において、輸出額の8割以上の即時撤廃で合意しており、カナダ(現行税率主に6.0%)への輸出についても、輸出額の9割弱の関税が即時撤廃されることで合意している。このような関税削減は、中堅・中小企業を含む我が国企業の輸出拡大のみならず、取引先企業の輸出拡大を受けた受注増加を通じても、中堅・中小企業に大きなメリットをもたらす。加えて、TPPでは、繊維・陶磁器等、地方の中堅・中小企業に関連する品目についても関税撤廃を実現している(例:陶磁器は対米輸出額の75% 22を即時撤廃。タオルは米国の現行税率9.1%を5年目に撤廃、カナダの現行税率17%を即時撤廃)。
また、原産地規則においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制度(第Ⅲ-2-1-3図)が採用された。これにより、1か国だけではなく、TPP域内における付加価値等の足し上げにより原産地規則を満たすことができるため、より多様な生産ネットワークでTPPを活用することが可能になり、日本国内から部品等を輸出する企業にもメリットがある。
第Ⅲ-2-1-3図 完全累積制度のイメージ
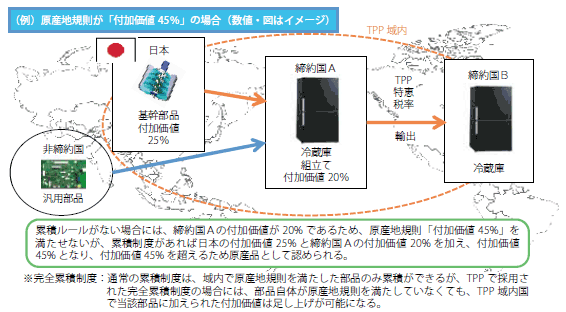
さらに、TPP協定では、投資や国境を越えるサービスの自由化を実現している。例えば、投資受入国が、投資活動の条件として、投資家に対し、技術移転要求(特定の技術、製造工程や財産的価値を有する知識を自国内の者に移転するよう要求すること)やロイヤリティ要求(ライセンス契約に定める使用料を一定の率又は金額にするよう要求すること等)などを行うことが禁止される。加えて、「国」対「投資家」の紛争解決手続(ISDS)の導入により、我が国企業が相手国政府から不当な扱いを受けて損害を被った際に、直接、国際仲裁へ訴えることが可能になる。
また、ベトナム及びマレーシアでは、コンビニ等小売業への外資規制の緩和が行われることとなっているほか、ベトナムでは、劇場・ライブハウス等のクールジャパン関連、旅行代理店等の観光関連といった幅広い分野での外資規制の緩和が行われることとなった。これらの規制緩和を契機に、例えば、食品や日本各地の特産品などを生産する中堅・中小企業がコンビニと連携することで海外展開を行うなど、サービス産業も含めた幅広い分野での海外展開へのメリットが期待できる。その他、TPPによりもたらされるメリットの例を第Ⅲ-2-1-4表にまとめた。
第Ⅲ-2-1-4表 TPP協定のメリット例
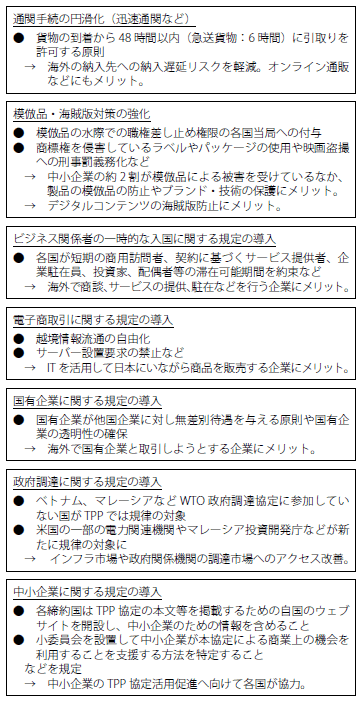
21 我が国の交渉参加に至るまでの経緯は次のとおり。2010年3月、ニュージーランド、シンガポール、チリ、ブルネイ(環太平洋戦略的経済連携協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement、通称P4協定)加盟4か国)、米国、豪州、ペルー、ベトナムの8か国で環太平洋パートナーシップ(Trans-Pacific Partnership)協定交渉が開始した。その後、さらにマレーシア(2010年10月)、メキシコ(2012年10月)、カナダ(2012年10月)が交渉に参加し、我が国は2013年7月に交渉に参加した。
22 2010年における各国の日本からの輸入額に基づき計算。
(2)「総合的なTPP関連政策大綱」の策定
TPPの大筋合意を踏まえ、TPPの実施に向けた総合的な政策の策定等を行うため、2015年10月9日に「TPP総合対策本部」が設置された。2015年11月25日に開催された第2回TPP総合対策本部において、「総合的なTPP関連政策大綱」を決定した。
「総合的なTPP関連政策大綱」では、工業品だけでなく、農林水産物・食品も、また、モノの輸出だけでなくコンテンツやサービスなども積極的に海外展開する「新輸出大国」の実現や、TPPを契機として、我が国を貿易、投資、生産、観光、研究開発など様々な領域において、世界経済を牽引する拠点とする「グローバル・ハブ」の実現などを目標に掲げ、これらを実現するための施策が盛り込まれている(第Ⅲ-2-1-5図)。
第Ⅲ-2-1-5図 総合的なTPP関連政策大綱の概要
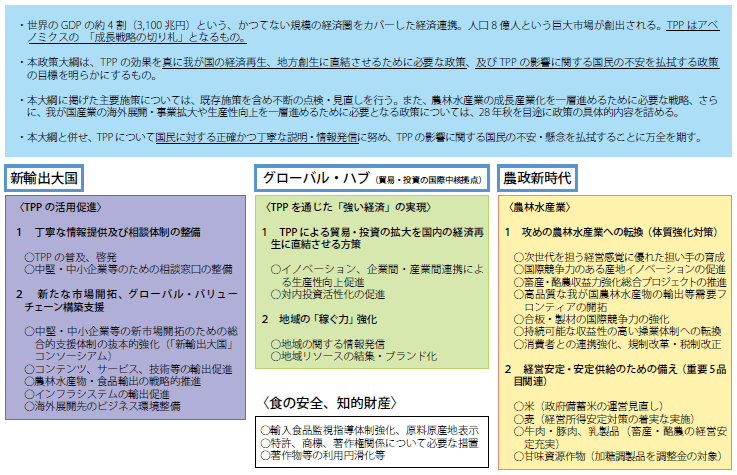
(3)TPPの活用促進
上述のとおり、TPPは大企業のみならず中堅・中小企業にも大きなメリットをもたらすものである。TPPを契機とした中堅・中小企業の海外展開を支援することは、我が国の経済成長にとっても重要である。
以下で、政府が行うTPP活用支援の取組を紹介する。
①TPP活用のための情報提供
中堅・中小企業の海外展開支援に当たり、まず重要となるのが、情報提供である。経済産業省では、経済産業局、JETRO、商工会議所等が主催するセミナーに職員を派遣し、TPPの合意内容について説明を実施している。大筋合意以降、全国47都道府県で、100回を超える説明会を開催している(2016年3月末時点)。さらに、ベトナム、シンガポール、マレーシアにおいて開催されたJETRO主催の現地日系企業向け説明会にも職員を派遣し、説明を行っている。また、経済産業局、JETRO、中小機構の全国65か所にTPP相談窓口を設置し、昨年10月以降、さまざまな企業の相談に対応してきた。
②新輸出大国コンソーシアム
「新輸出大国」実現のためには、その担い手となる中堅・中小企業の海外展開を支援することが重要である。
他方、我が国の中堅・中小企業は多様な事業を行っており、海外展開の際に直面する課題も様々である。JETROが行ったアンケート調査によると、海外展開に向けた課題として、多くの企業が、現地でのビジネスパートナーや海外ビジネスを担う人材の確保(「ヒト」の確保)、海外の制度情報や現地市場に関する情報の入手(「情報」の入手)など、様々な課題を挙げている(第Ⅲ-2-1-6図)。
第Ⅲ-2-1-6図 海外展開の課題についての企業アンケート結果
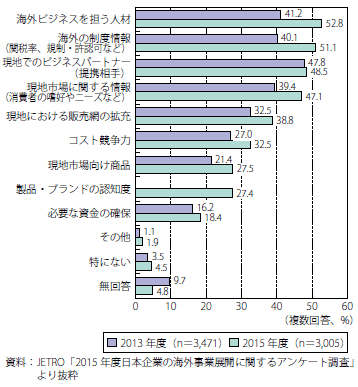
したがって、中堅・中小企業の海外展開支援に当たっては、個々の企業にニーズに応じて、製品開発、国際標準化から販路開拓に至るまでの総合的な支援をきめ細かく行うことが必要である。こうした背景から、2016年2月26日、官民の関係機関を結集した「新輸出大国コンソ-シアム」が設立された。
「新輸出大国コンソーシアム」の下では、TPPを契機として海外展開を図る中堅・中小企業に対して、以下の支援を行う。
1)支援機関相互の連携による支援
新輸出大国コンソーシアムの支援を希望する企業に対し、新輸出大国コンソーシアムの会員証を発行し、その会員証を提示することにより全ての機関が連携して円滑な支援を行えるようにする(第Ⅲ-2-1-7図)。
第Ⅲ-2-1-7図 新輸出大国コンソーシアムの下での支援機関相互の連携による支援
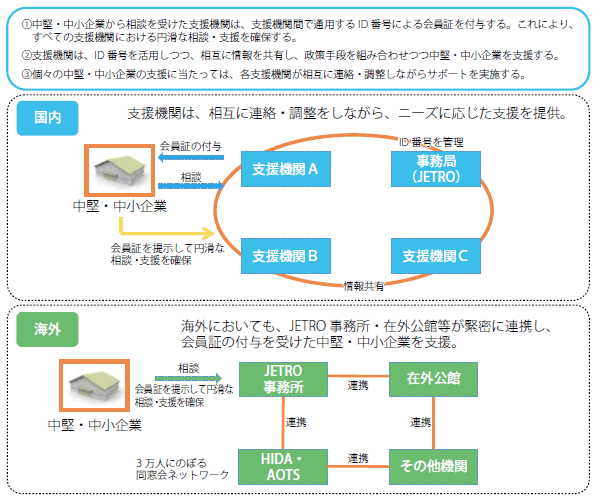
2)専門家による支援
海外ビジネスに精通した専門家が個々の企業の担当となり、海外事業計画の策定、支援機関の連携の確保、現地での商談や海外店舗の立ち上げなどの支援を行う。また、企業が専門家による支援を志望する場合には、金融機関や商工会議所等、支援機関の窓口を通じて、JETROに応募できるようにする(第Ⅲ-2-1-8図)。
第Ⅲ-2-1-8図 新輸出大国コンソーシアムの下での専門家による支援
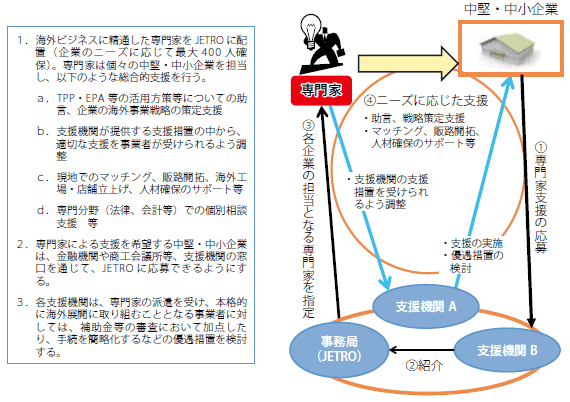
③コンビニエンス・ストアとJETROの連携推進に関する協議会
TPPを契機として、流通を始めとするサービス業にとっても、海外展開の大きなチャンスが拡大することが期待される。
特にコンビニエンス・ストアについては、今後、TPP協定により外資規制が緩和され、アジアを中心に更なる海外展開が期待できる。これにより、単独では輸出等が困難である我が国の中堅・中小企業が、コンビニエンス・ストアのネットワークを使っての販路開拓が可能となれば、そのメリットは極めて大きい。
このような背景から、コンビニエンス・ストアが海外展開に当たり抱える課題を解決し、中堅・中小企業の販路開拓を促進するため、コンビニエンス・ストアとJETROとの連携推進に関する具体策をまとめることを目的として、2016年1月18日、「第1回コンビニエンス・ストアとJETROの連携推進に関する協議会」が設立された。今後、本協議会でまとまった具体策をJETROが中心となり実行に移し、一つでも多くの成功事例の創出に取り組むこととなっている。
2.我が国の経済連携を巡る取組
我が国は、2016年2月現在、20か国との間で16の経済連携協定を署名・発効済みである。また、現在日EU・EPA、RCEP、日中韓FTA等の経済連携交渉を推進中である(第Ⅲ-2-1-9図、第Ⅲ-2-1-10図)。
第Ⅲ-2-1-9図 日本のEPA交渉の歴史
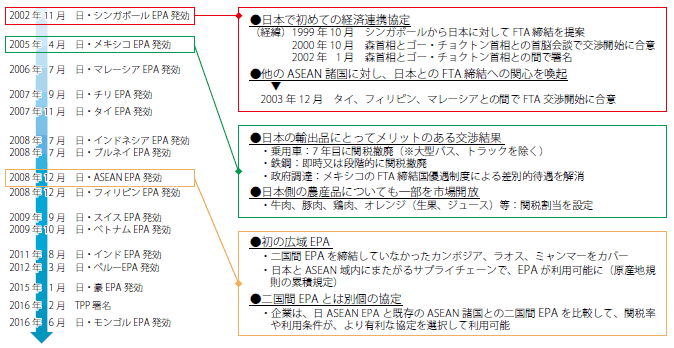
第Ⅲ-2-1-10図 日本の経済連携の推進状況(2016年6月現在)
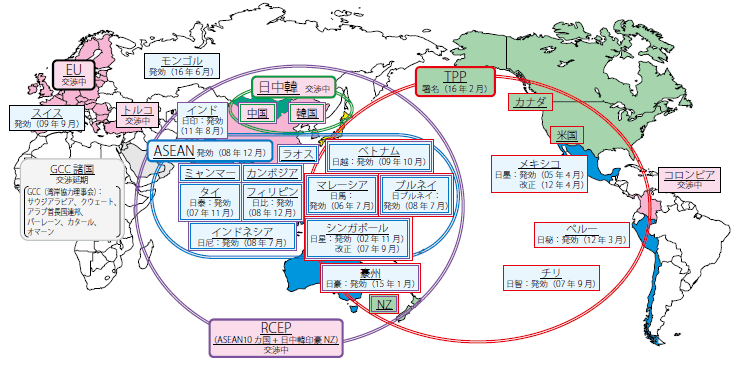
自由貿易の拡大、経済連携の推進は、我が国の通商政策の柱であり、世界に「経済連携の網」を張り巡らせることで、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくことが、我が国の成長にとって不可欠といえる。
「日本再興戦略2016 ―第4次産業革命に向けて―(平成28年6月2日閣議決定)」においても、「TPPの速やかな発効及び参加国・地域の拡大に向けて取り組むとともに、日EU・EPA、RCEP、日中韓FTAなどの経済連携交渉を、戦略的に、かつスピード感を持って推進する。我が国は、こうした新しい広域的経済秩序を構築する上で中核的な役割を果たし、包括的で、バランスのとれた、高いレベルの世界のルールづくりの牽引者となることを目指す。」こととしている。また、引き続き「2018年までに、FTA 比率 70%(2012年:18.9%)を目指す」ことを目標としており、交渉を進めているところである。(第Ⅲ-2-1-11図)
第Ⅲ-2-1-11図 各国のFTAカバー率比較
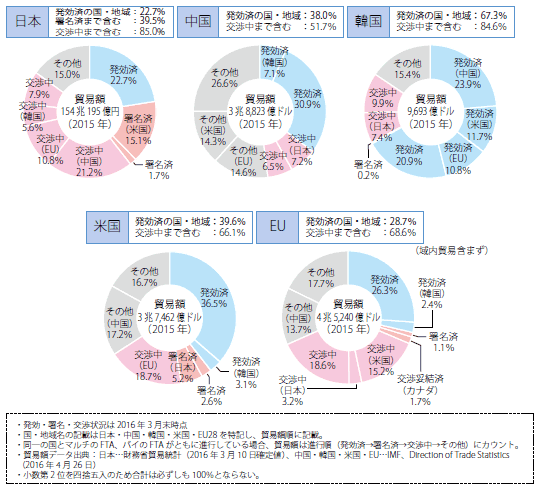
以下、現在の我が国の経済連携を巡る取組について、(1)経済連携協定の効果、(2)複数国・地域との経済連携、(3)二国間での経済連携の取組に分けて紹介する。
(1)経済連携協定の効果
経済連携の推進は、我が国企業にとって大きなメリットをもつ。
輸出の面では、関税削減によって我が国からの輸出品の競争力を高められる。メキシコでは乗用車に20%、マレーシアではエアコンに30%、インドネシアではブルドーザーに10%の関税が課されているが、EPAを利用した場合、これらの関税がゼロになる。また、複数国・地域間で結ばれる広域のEPAでは、EPAごとにバラバラに決められている要件・手続を統一し、企業が地域内でのEPAをより使いやすくするメリットがある。例えば、EPAを利用して関税削減の恩恵を受けるために必要な要件・手続(原産地規則と呼ばれる)を地域内で統一することは、企業の事務コストを削減し、EPAの活用対象国を広げやすくする効果がある。このほかにも、広域のEPAのメリットとして、地域内の複数国で生産された製品に対してEPAを使いやすくなること、地域内の物流拠点(ハブ)に貨物を集約し、物流拠点からの分割輸送が可能となること等が挙げられる。
海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、海外事業で得た利益を我が国へ送金することの自由の確保、現地労働者の雇用等を企業へ要求することの制限・禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約の金額及び有効期間への政府の介入の禁止等の約束を政府同士で行うことにより、海外投資の法的安定性を高めている。
また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で安心して事業を行なうためのルールを定めている。
この他にも、我が国のEPAでは、締約国のビジネス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環境の整備に関する委員会」の設置に係る規定を設けている。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点について、相手国政府関係者と直接議論することができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関する委員会」の成果として、メキシコとは模倣品取り締りのためのホットライン設置に合意し、マレーシアとは治安向上のためパトロールの強化や監視カメラの増設等を実現してきている。
(2)複数国・地域との経済連携
①日EU・EPA(交渉中)
アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組として、EUとのEPA交渉が挙げられる。我が国とEUは、世界人口の約1割、貿易額の約3割(EU域内を除くと約2割)、GDPの約3割を占める重要な経済的パートナーであり、日EU・EPAは、日EU間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの先頭役を果たすものといえる。
EUは、近隣諸国や旧植民地国を中心としてFTAを締結してきたが、2000年代に入り、韓国等の潜在的市場規模や貿易障壁のある国とのFTAを重視するようになった。さらに、米国とも2013年7月から環大西洋貿易投資パートナーシップ(TTIP: the Transatlantic Trade and Investment Partnership)協定の交渉を行っており、2014年9月には先進国であるカナダとの包括的経済・貿易協定(CETA: the Comprehensive Economic and Trade Agreement)交渉が妥結するなど、先進国とも通商関係強化に向けた動きをみせている。
日EU・EPAについては、2009年5月の日EU定期首脳協議において、日EU経済の統合の強化に協力する意図が表明され、翌2010年4月の日EU定期首脳協議では、「合同ハイレベル・グループ」を設置し、日EU経済関係の包括的な強化・統合に向けた「共同検討作業」を開始することに合意した。合同ハイレベル・グループにおける幅広い分野での作業の結果を踏まえ、2011年5月の日EU定期首脳協議において、交渉のためのプロセスの開始についての合意がなされ、日本政府と欧州委員会との間で、交渉の大枠(交渉の「範囲(scope)」及び「野心のレベル(level of ambition)」を定める「スコーピング作業」を実施することとなった。
翌2012年にかけて実施したスコーピング作業の終了を受け、同年11月のEU外務理事会において、欧州委員会が加盟国より交渉権限(マンデート)を取得した。これを受けて、2013年3月に行われた日EU首脳電話会談において、日EU・EPA及び政治協定(現在の戦略的パートナーシップ協定(SPA))の交渉開始に合意した。2014年5月から6月にかけて、EU側の内部プロセスとして、欧州委員会が交渉開始1年後の「見直し(レビュー)」を行い、交渉の継続が決定した。2013年4月の交渉開始以降、2016年5月末現在までの間、計16回の交渉会合が開催されており、2016年のできる限り早い時期に大筋合意を実現することを目指している。
参考 日EU首脳会談プレスリリース(2015年11月5日 於:アンタルヤ)
日EU関係について、ユンカー委員長から、戦略的パートナーである日本との戦略的パートナーシップ協定(SPA)、経済連携協定(EPA)の交渉を重視している、交渉の加速化が必要である旨述べ、安倍総理から、一定の進展があったが今後議論を進展させるべき分野が残っている旨述べました。両首脳は、双方の首席交渉官に交渉を加速化し、引続き年内の大筋合意実現に向け最大限努力を求め、仮に実現できなくとも来年のできる限り早い時期に実現するよう指示することにて合意しました。
出典:外務省ホームページ
また、2016年5月3日に安倍総理は、ドナルド・トゥスク欧州理事会議長、ジャン=クロード・ユンカー欧州委員会委員長と日EU首脳会談を行った。日EU双方の首脳は、戦略的パートナーである日EU間で交渉中の経済連携協定(EPA)の本年のできる限り早期の大筋合意が実現するよう、両交渉担当者に交渉の加速化を指示することで一致した。2016年5月26日、G7伊勢志摩サミットに際し、安倍総理は、ドナルド・トゥスク欧州理事会議長、ジャン=クロード・ユンカー欧州委員会委員長、フランソワ・オランド・フランス共和国大統領、アンゲラ・メルケル・ドイツ連邦共和国首相、マッテオ・レンツィ・イタリア共和国首相、デービッド・キャメロン英国首相と共に、日EU経済連携協定(EPA)に関する共同ステートメントを発出し、日EU・EPAの本年のできる限り早期の合意を目指すとの強いコミットメントを確認した。
参考 日EU経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)に関する共同ステートメント(2016年5月26日 於:伊勢志摩)
我々、日本、EU、フランス、ドイツ、イタリア及び英国の首脳は、G7伊勢志摩サミットの機会に、本年5月3日の日EU首脳会談の際に両首脳がそれぞれの交渉官に日EU経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)交渉を加速することを指示することで一致したことを歓迎するとともに、本年のできる限り早期に大筋合意に達するとの我々の強いコミットメントを確認した。
我々は、我々の交渉官の過去3年間の作業及びこれまでの大きな進展を称賛する。我々の全面的な後押しを得て、交渉官は、我々の強固な貿易経済パートナーシップを更に確固たるものとする、包括的で、レベルの高い、かつ、バランスの取れた協定に向け、先に述べたタイムラインに沿って、建設的な姿勢で相互信頼に基づき、全ての種類の関税及び非関税措置等のあらゆる主要課題を含む合意に達するための道筋をつけて交渉を前進させるため、今後数か月にわたり、必要な努力を行うことを付託される。
我々は、日EU・EPA/FTAの戦略的な重要性を認識しつつ、より強固で、持続可能な、かつ、均衡のとれた成長を促進し、並びに日本及びEUにおけるより多くの雇用及び経済的機会の創出並びに国際競争力の強化に資する、自由で、公正な、及び開かれた国際貿易経済システムの構築に引き続きコミットする。
出典:外務省ホームページ
②東アジア地域包括的経済連携 (RCEP(アールセップ):Regional Comprehensive Economic Partnership) (交渉中)
RCEPは、世界全体の人口の約半分、GDPの約3割を占める広域経済圏を創設するものであり、最終的にはFTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)の実現に寄与する重要な地域的取組の一つである。
東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築されているが、この地域内における更なる貿易・投資の自由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。
この地域全体を覆う広域EPAが実現すれば、企業は最適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワークを構築することが可能となり、東アジア地域における産業の国際競争力の強化につながることが期待される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によってEPAを活用する企業の負担軽減が図られる(第Ⅲ-2-1-12図)。
第Ⅲ-2-1-12図 RCEP参加の意義
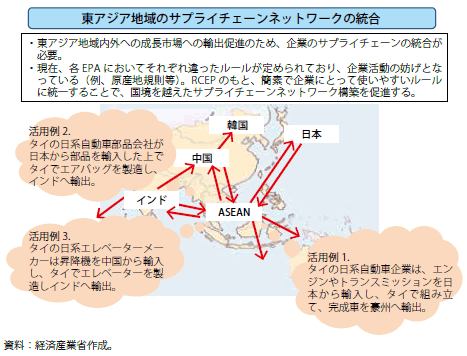
2012年11月のASEAN関連首脳会議において、「RCEP交渉の基本方針及び目的」が16か国(ASEAN10か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)の首脳によって承認され、RCEPの交渉立ち上げが宣言された。
基本方針には、「現代的な、包括的な、質の高い、かつ、互恵的な経済連携協定」を達成すること、物品・サービス・投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決を交渉分野とすること、が盛り込まれている。第1回RCEP交渉会合は、2013年5月にブルネイで開催され、高級実務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易および投資に関する各作業部会が開催された。
第1回交渉会合が開催されて以降、2016年2月までに11回の交渉会合と4回の閣僚会合(1回の中間会合を含む)が開催されている。2014年8月にミャンマーで開催された第2回閣僚会合では、物品貿易に関するイニシャル・オファーの進め方やサービス・投資の自由化方式について議論が行われ、2015年8月24日の第3回閣僚会合では、物品貿易のイニシャル・オファーの水準に合意された。同年10月に行なわれた第10回交渉会合以降は、閣僚会合の成果を受け、物品、投資、サービスの主要3分野において、具体的な交渉が開始された。現在、貿易交渉委員会(Trade negotiating Committee)に加え、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産、競争、経済技術協力、法的制度的事項、電子商取引、STRACAP(貿易の技術的障害)、SPS(植物衛生検疫)、原産地規則、貿易円滑化・税関手続、金融、電気通信等、幅広い分野について交渉が行われている。交渉立ち上げ時に掲げた「2015年末の交渉完了」目標は実現が困難な状況にあったため、2015年11月のASEAN関連首脳会議において、2016年内のRCEP交渉の妥結を期待する旨の共同声明文が発出された。
③日中韓FTA(交渉中)
日中韓3か国は、世界における主要な経済プレイヤーであり、3か国のGDP及び貿易額は、世界全体のGDP及び貿易額の約2割を占める。日中韓FTAは、3か国間の貿易・投資を促進するのみならず、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の実現にも寄与する重要な地域的取組の一つである。
2013年3月に交渉を開始して以降、計9回の首席代表による交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、税関手続、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投資、競争、知的財産、衛生植物検疫(SPS)、貿易の技術的障害(TBT)、法的事項、電子商取引、環境、協力等の広範な分野について議論を行っている。
また、2015年10月の日中韓経済貿易大臣会合及び同年11月の日中韓サミットでは包括的かつ高いレベルの協定の実現を目指し交渉を加速化していくことが確認された。
④日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定(サービス貿易章・投資章実質合意)
ASEAN全加盟国とのEPAである日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)は、2004年11月の首脳間での合意に基づき2005年4月より交渉を開始し、2008年4月14日に各国持ち回りでの署名を完了し、加盟国との間で順次発効している。2010年10月より交渉が行われていたAJCEPのサービス貿易章・投資章については3年にわたる交渉を経てルール部分について実質合意に至り、2013年12月の日・ASEAN特別首脳会議において同成果は各国首脳に歓迎された。今後も引き続き残された技術的論点等の調整を行っていく。
⑤日GCC・FTA(交渉延期)
バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦からなるGCC(湾岸協力理事会)諸国とのFTAについては、2006年9月に交渉が開始され、2009年3月までに2回の正式会合と4回の中間会合が実施された。しかし同年7月に、GCC側の要請により交渉が延期されており、現在、我が国は交渉再開に向けて働きかけを行っている。
この地域は、我が国の原油輸入量全体の約77%(2014年)を占め、また我が国からの総輸出額も約2.6兆円に達する(2014年)。さらに、人口増加に伴う大規模なインフラ整備の需要があり、各国による、官民一体となった売り込みが積極的に展開されている。貿易・投資拡大及び我が国のエネルギー安全保障の観点に加えて、同諸国との間で経済関係を含めた友好的な関係を形成・維持することが重要である。
(3)二国間での経済連携の取組
①日・モンゴルEPA(2016年6月7日発効)
日モンゴルEPA交渉は、2014年7月の日モンゴル首脳会談において、大筋合意が確認された。また、2015年2月の日モンゴル首脳会談において、両国首脳の間で日・モンゴルEPA及び同協定の実施取極への署名が行われ、2016年6月7日に発効した。豊富な天然資源に恵まれるモンゴルと我が国の関係は極めて緊密かつ重要であり、本協定は、今後の両国間の貿易・投資を促進するための重要な枠組みである。また日・モンゴルEPAはモンゴルにとって初めてのEPA/FTAとなり、2010年11月の日本・モンゴル共同声明に掲げる「戦略的パートナーシップ」を一層強化するための重要なステップとなる。
②日・カナダEPA(交渉中)
日・カナダEPA交渉については、2011年3月から2012年1月までに4回の共同研究が開催され、共同研究報告書が作成された。共同研究の報告書を受け、2012年3月の日・カナダ首脳会談において、両国の実質的な経済的利益に道を開く二国間EPAの交渉を開始することで一致した。第1回交渉会合は2012年11月に行われ、最近では2014年11月に第7回交渉会合が開催された。
③日・コロンビアEPA(交渉中)
コロンビアは、高い成長率(今後5年間で平均4%強)が見込まれる人口4,600万人の市場であり、EPAを通じた貿易・投資環境の改善により輸出入拡大が期待される。コロンビア政府は経済の自由開放政策を掲げるなか、発効済みの中南米諸国・米国・カナダ・EUとのFTAに加え、韓国とのFTAに署名済みである。
2011年9月の日・コロンビア首脳会談において、日・コロンビアEPAの共同研究の立ち上げが合意されたことを受けて共同研究が開始され、2012年7月にあり得べきEPAは両国に多大な利益をもたらすことに資するとの報告書が取りまとめられた。同報告書を踏まえ2012年9月に行われた日・コロンビア首脳会談にて、両国はEPA交渉を開催することで一致し、2012年12月に第1回交渉が開催された。
その後、2014年7月に行われた日・コロンビア首脳会談において、両首脳は、できる限り早期の合意を目指し交渉を加速化することを確認した。2016年3月末までに、13回の交渉会合が開催された。
④日・トルコEPA(交渉中)
トルコは高い成長率(今後5年で平均5%強)が見込まれる人口7,700万人の魅力的な市場を持つ。貿易・投資環境の改善による輸出入拡大が期待され、我が国企業の関心は高い。日・トルコ間の投資・ビジネス環境の改善や、第三国に劣後しない貿易の自由化や規律の策定を目指している。
トルコと我が国は2012年7月に第1回日・トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日・トルコEPAの共同研究を立ち上げることにつき合意した。これを受けて、同年11月に第1回、2013年2月に第2回の共同研究が開催され、同年7月に日本・トルコの両政府にEPA交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。
共同研究報告書を受けて、2014年1月に行われた日・トルコ首脳会談にて、両国はEPA交渉を開始することで一致し、同年12月に第1回交渉会合が開催され、最近では2016年1月に第4回交渉会合が開催された。日・トルコEPAによって、欧州企業や韓国企業といった競合相手との競争条件の平等化を早急に図ることを通じ、トルコへの日本企業の輸出を後押しするとともに、周辺国への輸出・新規参入を狙うハブとしての競争力を高めるべくトルコの投資環境関連制度の改善を図ることを目指す。
⑤日・韓EPA(交渉中断中)
韓国とのEPA交渉は2003年12月の交渉開始後、2004年11月の第6回交渉会合を最後に中断しているが、2008年の日韓首脳会談を受け、交渉再開に向けた実務協議が開催されてきた。2011年10月に行われた日韓首脳会談では、交渉再開に必要な実務的作業の本格的実施につき一致し、課長級実務協議が行われるなど、引き続き交渉再開に向けた調整が進められている。
(4)EPAの活用と見直し(ライフサイクル)
以上、現在交渉中、交渉開始に合意したEPA/FTAを紹介したが、グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、このような新たな協定締結に向けた取組に加えて、EPA/FTAの円滑な利用促進、既存EPAの見直しも重要である。
現在、我が国の発効済みEPAにおいては企業による活用も浸透し始め、「活用・運用段階」にあるといえる。今後、
①政府のみならずJETRO 24、日本商工会議所25、業界団体等による積極的なEPAの普及啓蒙・利活用率の向上・着実な執行、
②「ビジネス環境の整備に関する委員会」等の場を通じた両国政府・民間企業代表者を交えた協議26
③EPAの利活用実態やニーズを踏まえた協定見直し27
等、いわば「EPAのライフサイクル」にわたって、EPAを活用し、見直すことを通じて質を高めていくことが重要であるといえる。
24 EPA利活用相談(日本企業の方)https://www.jetro.go.jp/services/advice/![]()
アドバイザー等海外進出企業の支援サービス(在海外企業の方) https://www.jetro.go.jp/services/advisor/![]()
25 第一種特定原産地証明書の指定発給機関 http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/![]()
26 ビジネス環境の整備に関する委員会http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/about/business.html![]()
27 日・シンガポールEPAは2002年発効、2007年改正。日・メキシコEPAは2005年発効、2012年改正。
3.APECを通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進
フィリピンが議長を務めた2015年の閣僚会議・首脳会議では、多角的貿易体制、FTAAPを始めとする地域経済統合の進展、APEC成長戦略、サービスにおける協力等に関する議論が行われた(第Ⅲ-2-1-13図)。多角的貿易体制については、同年12月のナイロビでの第10回WTO閣僚会議の成功に向けた独立文書を発出し、貿易円滑化協定の早期批准を促した。地域経済統合の進展については、FTAAPは現在進行している地域的な取組を基礎として包括的な自由貿易協定として追求されるべきことや、FTAAPが質の高いものであるとともに次世代貿易投資課題に対処すべきとする「FTAAPへの道筋」のビジョンが再確認された。これに関連し、TPP交渉の大筋合意等の進捗に留意し、またRCEP交渉の早期妥結を慫慂した。サービスについては、「APECサービス協力枠組み」が策定され、APECにおけるサービス協力の原則や方向性が示されたほか、2025年までに取るべき行動、達成すべき指標及び目標を含めたロードマップを2016年に策定することが首脳から指示された。また、我が国が主導して取りまとめた製造業関連サービス及び環境サービスの各行動計画が歓迎された。
第Ⅲ-2-1-13図 2015年APECにおける閣僚会議・首脳会議の模様
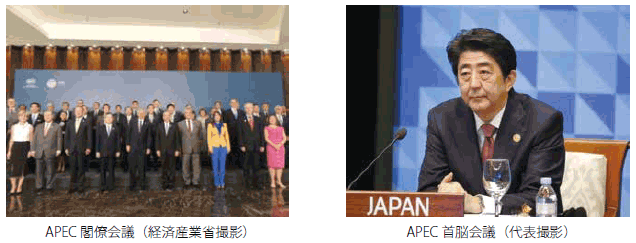
APEC成長戦略については、2010年に策定された「APEC成長戦略」を基礎として、制度構築、社会的一体性、環境影響の観点を加えた「質の高い成長の強化に向けたAPEC戦略」が採択された。
包括的な連結性については、我が国は、「質の高いインフラ」を推進し、地域の連結性強化に貢献すべく取組を実施。特に、各エコノミーのインフラ開発投資に係る関連法制度を「インフラの質」等の観点からレビューし、これにより判明した能力構築のニーズに合わせて能力構築を提供する仕組みを提案し、閣僚声明で歓迎された。
2016年はペルーが議長を務め、「質の高い成長と人間開発(Quality Growth and Human Development)」をテーマに、(1)地域経済統合の推進と成長(2)地域フードマーケットの促進、(3)アジア太平洋の零細・中小企業(MSMEs)の近代化、(4)人材開発促進の4つの優先課題の下に議論を進めており、その成果は11月にリマで開催されるAPEC首脳会議・閣僚会議で取りまとめられる予定である。
我が国としては、2010年の「横浜ビジョン」を基礎とした議論の流れを着実に引き継ぎつつ、製造業関連サービスや環境サービス等のサービス貿易の自由化・円滑化や質の高いインフラ開発・投資の促進等に係る具体的な取組を進め、アジア太平洋地域の貿易・投資の自由化・円滑化を促していくことで、FTAAPを始めとする同地域の地域経済統合の推進と更なる発展に取り組んでいく。その上で、この地域の力強い成長力、インフラなどの旺盛な需要や巨大な中間層の購買力を取り込むことで、我が国に豊かさと活力をもたらすような通商政策を実現していく。
4.我が国における投資関連協定
(1)我が国の投資関連協定を巡る状況
海外に拠点を構える日系企業の数は近年増加してきており、2014年時点で68,573拠点を数えるに至った。また、我が国の対外直接投資は2000年時点に比べ、約2.6倍となり、2005年度以降、所得収支と貿易収支が逆転した。
このように、我が国から海外への投資が一層進んでいる。同時に、新興国を中心に世界の市場が急速な勢いで拡大を続ける中、日本企業や日系企業は、熾烈な海外市場の獲得競争に晒されている。我が国の経済成長をより強固で安定的なものにしていくためには、貿易投資立国としての発展を目指し、世界のビジネス環境をより一層整備していく必要がある。かかる観点から、投資家やその投資財産の保護、規制の透明性向上、機会の拡大等について規定する投資協定及び投資章を含む経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)(以下、投資関連協定)は、投資支援のツールとしての重要性を一層増している。租税条約、社会保障協定と合わせて、国境をまたぐ資本・人・物の移動に係る課題の解決のために重要であり、企業のニーズも高い。
投資関連協定は、海外における我が国投資家の適切な保護を確保するとともに、国内外の市場に跨がる投資環境を整備し、日本企業の海外展開及び対日直接投資を促進する役割が期待されており、日本政府は、他の経済政策と並び、既存協定の改正を含む投資関連協定の締結を一層加速し、投資環境の整備を進めていく方針である。
我が国は、1978年、エジプトとの間で初の投資協定が発効し、以降、これまで重要な経済関係を有するアジア地域の国々を中心に、投資関連協定を締結してきた。現在、41件の投資関連協定に署名し、うち35件が発効している。(2016年6月現在)(第Ⅲ-1-2-1-1表)。我が国は比較的近年になってから投資関連協定の締結に取り組んできたが、産業界のニーズや相手国の事情に応じながら、新規協定の締結及び既存協定の改正に向けた交渉を一層積極的に進めていく必要がある。
第Ⅲ-2-1-14表 我が国の投資関連協定締結状況
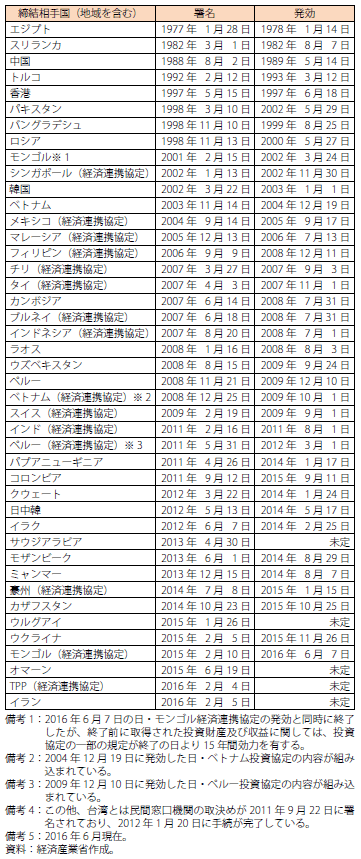
(2)投資関連協定を巡る新たな取組(投資関連協定に係るアクションプランの策定)
本年5月、「投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン」を策定し、今後は当該プランに基づいて投資関連協定の締結を始めとして、投資環境の整備を促進していくこととなった。その主な内容として、第一に、我が国として、投資関連協定の締結促進に集中的に取り組み、2020年までに、投資関連協定について、100の国・地域を対象に署名・発効することを目指す。第二に、交渉相手国の選定に当たっては、毎年度、我が国から相手国・地域への投資実績と投資拡大の見通し、我が国産業界の要望、我が国外交方針との整合性、相手国・地域のニーズや事情等を総合的に勘案の上、方向性を検討していく。第三に、投資関連協定の締結交渉に当たっては、投資市場への新規参入段階から無差別待遇を要求する「自由化型」の協定を念頭に、高いレベルの質を確保することを不断に追求する。同時に、産業界の具体的なニーズや相手国の事情等に応じながら、スピード感を重視した柔軟な交渉を行う。第四に、我が国は、二国間又は複数国間の投資関連協定の交渉を積極的に進めると同時に、多数国間フォーラムなどにおける投資環境整備に向けた国際的な議論に積極的に貢献していく。第五に、協定を締結するに当たっては、従来からの投資協定の内容のみならず、近年の経済・社会状況の変化も踏まえ、サービスや電子商取引等の分野を含めることも検討するなどして、新たな企業活動にも対応した投資環境を作り上げることにより我が国の経済成長を目指すこと等について盛り込まれている。
(3) 今後の課題
投資関連協定の規定に関する紛争は、それぞれ一定の条件下で国家対国家の紛争処理手続き(SSDS)又は投資家対国家の仲裁手続き(ISDS)の対象となる。我が国の投資関連協定におけるSSDSでは、投資関連協定の解釈、適用等に関する締約国間の紛争についての解決手続きを規定している。
ISDSは、投資家が投資先国政府の投資関連協定違反により自らの投資財産に損害を受けた場合、ICSID 28仲裁規則やUNCITRAL 29仲裁規則に基づく国際仲裁に付託することを可能としている。
UNCTADによれば、投資関連協定に基づくISDSの件数(仲裁機関へ案件付託の数)は、1987年の最初の事案30以来、1998年までは累計で14件にとどまっていたものの31、1990年代後半から急増し32、2014年末現在で累計608件に上っている。一方、我が国企業が投資仲裁に訴えた事例は、公表されている中では2件33のみである。また、民間の調査34によれば、国際商事仲裁の経験がない日本の大手企業の割合は、8割に上るという結果が出ている。日本企業の現状として、未だ国際投資仲裁、国際商事仲裁が積極的に利用されているとは言いがたい状況にある。
投資関連協定に基づく国際仲裁において、仲裁判断は先例として拘束力があるものではないものの、仲裁廷は過去の同様の仲裁判断を参考にする傾向がある。投資関連協定に基づく国際仲裁は2000年以降、急増しており、仲裁判断例が蓄積される一方で、判断の分かれる論点も少なからずある。国際投資仲裁において下された判断は、今後の我が国の投資関連協定交渉戦略に影響を与えうるものである。また、我が国企業が投資先国との紛争解決手段として国際仲裁を積極的に活用できる環境を構築することも今後の課題である35。国際的な企業活動のルールは固定的なものではなく変動的であり、国際投資仲裁や国際商事仲裁はそのルールが形成されるフィールドとしての意味を持つ。国際ビジネスルール形成に影響を与えていくという観点からも、我が国の学者・実務家が国際投資仲裁や国際商事仲裁に積極的に関与することが望まれる。
国際仲裁の活用においては、仲裁ルール及び仲裁場所の整備も重要である。これまで、シンガポール36と香港がアジアにおける主な仲裁地であったが、近年は韓国も国際仲裁環境の整備に力を入れており、2013年5月には「ソウル国際紛争解決センター」を設立している37。これらの国は、仲裁環境の整備を国際的なビジネス拠点であるために不可欠なツールと位置づけ、振興に努めている。
28 International Centre for Settlement of Investment Disputes(投資紛争解決センター):世界銀行グループの1機関である常設の仲裁機関。所在地はワシントンD.C.。
29 United Nations Commission on International Trade Law(国際連合国際商取引法委員会):所在地はオーストリア(ウィーン)。
30 Asian Agricultural Products Limited対スリランカ政府の事案(ICSID Case No.ARB/87/3)。
31 UNCTAD(2005) ”INVESTOR-STATE DISPUTES ARISING FROM INVESTMENT TREATIES:A REVIEW”。
32 1996年、NAFTAにおける「エチル事件」(米国企業がカナダ政府による環境規制がNAFTA上の「収用」に当たるとして提訴。カナダ政府が米国企業に金銭を支払って和解)をきっかけに、投資仲裁に対する関心が高まったとされる。
33 1件目は、1998年、我が国の証券会社の在ロンドン子会社が、オランダ法の下で設立された法人を介して買収したチェコの銀行に対してチェコ政府がとった措置に関し、チェコとオランダ間の二国間投資協定に基づき、国連商取引委員会(UNCITRAL)仲裁規則による仲裁に付託したケース。2件目は、2015年、我が国企業が、スペイン政府による再生可能エネルギー関連制度の変更について、エネルギー憲章条約に基づき、投資紛争解決国際センター(ICSID)に仲裁を申立てたケース。
34 日本経済新聞 2014年1月20日 16面
35 ISDS条項に関しては、公益が制限されるとの懸念を強調する意見も多く見受けられるが、これらの意見が仲裁判断などに関する正確な理解に基づかないと評価する意見もある。ISDS条項と公益制限論を結びつける議論について、引用されることの多いエチル事件及びメタルクラッド事件の概要を紹介した上で当該議論が一定の問題を有していることを指摘する資料として、日本弁護士連合会ADR(裁判外紛争解決機関)センター国際投資紛争特別部会作成「投資協定仲裁制度(ISDS)を巡る議論に関する報告書」(p.31-33)参照(なお、当該資料は上記特別部会が日本弁護士連合会内の討議資料として作成したものであり、同連合会としての見解を示すものではない)。
上記資料では「二つの事件を精察すればわかるように,ISDS条項,あるいは,これを含む投資保護協定それ自体は,投資家の利益を無条件に公益に優先させるようなことは何ら目的としていない。ただ,前者の事件では,環境保護を達成するための規制手段が内外の事業者に差別的なものであったため,後者の事件では,特に国内法上で権限を与えられていない機関が規制を行ってしまったため,投資保護協定との関係で問題が発生してしまったのである。したがって,これらの二つの事件の特殊性を無視して,事件の最終的な結末のみからISDS条項を公益制限論に結び付けてしまう議論には,一定の問題があると言えるであろう。」との分析が行われている。
36 シンガポールは2015年1月に、シンガポール国際商事裁判所(SICC)を設立した。SICCはシンガポールの裁判所として開設されたものであるが、その審理手続は国際仲裁に類似した特徴を有している(外国の裁判官による訴訟指揮が可能、外国法弁護士による訴訟代理が一定範囲で許容されている、証拠調べに関するルールが柔軟に適用されうる等。)。「シンガポール国際商事裁判所(SICC)の創設及び関連する諸問題(上)」(国際商事法務Vol43, No.10, 2015 p.1471-1479)参照
37 このような取組もあり、韓国における仲裁件数は増加傾向にある。
5.租税協定/社会保障協定
(1)租税条約
①租税条約の役割
租税条約は、国際的な二重課税を回避するため、両国間の投資・経済活動に関し、課税できる所得の範囲等を調整するものである。また、その締結によって、両国の税務当局間の相互協議や情報交換、徴収共助等の枠組みが構築され、租税に関する紛争の解決や脱税及び租税回避行為の防止が図られることとなる。
租税条約の締結により、海外進出企業に対する課税の法的安定性が確保されるとともに、我が国企業が海外で稼いだ収益の国内環流の円滑化にも資するなど、健全な投資・経済交流が一層促進されることが期待される。
②租税関連条約の新規締結・改正状況
我が国は、2016年3月1日現在 、65の租税関連条約を締結し、96か国・地域との間に適用されている。
近年、中東等資源国との租税条約の新規締結や先進国との改正、及び国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資する情報交換を主体とした租税協定の締結が進められている。特に、ニュージーランド、米国、スウェーデン、英国、ドイツなどの先進国との改正については、税務当局による相互協議の開始から一定期間が経過しても事案が解決されない場合に、税務当局以外の第三者の関与を得て解決を促すための仲裁制度を導入するとともに、投資所得(配当、利子等)に対する源泉地国における課税を軽減または免除とする内容になっている。また、2010年のOECDモデル租税条約の改訂に合わせ、外国法人・非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得の算定に際して、本支店間の内部取引を独立企業原則に基づき、より厳格に認識することを規定した条文が、英国及びドイツとの条約に導入されている。
今後とも、我が国産業界のニーズや我が国課税権の適切な確保等の観点を総合的に勘案し、企業の海外展開の支援に資する租税関連条約のネットワーク拡充の取組を加速することが重要である。具体的には、未締結国との新規締結を進めるとともに、既存条約を改正し、海外での事業活動に対する課税所得の範囲の明確化、投資所得に対する源泉地国における限度税率の引下げ、仲裁制度の導入など、内容を充実させることが必要である。
(2)社会保障協定
我が国企業の海外進出拡大に伴い、国際的な人的交流の活発化が進む中、外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される外国人について、①公的年金制度等に対して二重に加入することにより保険料の二重払いが生じること、②受給資格要件である一定の加入年数を満たすことができない場合に相手国で負担した保険料が掛け捨てになることもある。社会保障協定は、このような問題について①日本と外国の公的年金制度等の加入の調整(適用調整)を行うことにより、保険料の二重払いを防止するとともに、②年金の受給資格期間の計算に際して、日本と外国の年金制度への加入期間を相互に通算し(保険期間の通算)年金の受給資格の確保を図っている。これにより、海外に進出する日本企業や国民の負担を軽減し、ひいては相手国との人的交流が円滑化され、経済交流を含む二国間関係がより一層緊密化することが期待される。
これまでの社会保障協定では、主に以下の二つの内容を定めている。
(a) 適用調整
相手国への派遣の期間が一定期間(通常5年)を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、その期間を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
(b) 保険期間の通算
両国の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
なお、社会保障制度は各国それぞれの固有の事情を反映して設計されるものであり、各国ごとにその制度内容が異なることから、二国間協定が対象とする制度の範囲や内容もそれぞれ異なる。企業が自社の人材を海外に派遣するにあたって、社会保障協定の内容と日本の国内制度及び派遣先国の相手国制度の内容の確認が必要となる。
6.ルール形成
(1) 国際的なルール形成の高まり
近年、企業の海外展開の拡大に伴い、WTOやEPAなどの国際協定にとどまらず、外国の国内法や業界団体の自主取決め、グローバル企業等の調達基準などの国際ルールが企業活動に与える影響が大きくなっている。そのため、欧米等では、企業活動に影響する幅広い国際ルールを企業が自ら積極的に形成することにより、競争優位を獲得しようという動きが活発化している。特に、製品・サービスの質といった企業が有する「非価格競争力」がより適切に評価されるような国際ルールの形成に戦略的に携わることにより、新興国を中心とした海外市場の獲得を目指すものが数多くみられる。(コラム19参照)
(2) 国際的なルール形成のアプローチ
国際的なルール形成は、各種の課題を発見し、概念・理念を通じてこれを定式化し把握するところから始まることが多く、仮にこうした議論の初期段階から関与することができなかった場合には、ルール形成の過程に実質的に参加することは出来ない。その場合、優れた製品・サービスを有していたとしても、既に作られた国際ルールを所与のものとせざるをえないため、その強みを十分に発揮できない可能性がある。したがって、こうした事態を避けるために、我が国は、政府・企業の双方が、課題設定やコンセプト構築などの制度設計の初期の段階から議論により積極的に参画し、自らの製品・サービスが適切に評価されるような制度や仕組みを構築する必要がある。その際には、経済的価値のみならず、環境や安全といった社会課題の重要性が国際的に高まっていることを受けて、そのような社会課題の解決に貢献する製品・サービスの「非価格競争力」が適切に評価される国際ルールを策定することが重要となる。
(3) 我が国の事例
このような国際的なルール形成を実践している我が国の事例として、ここではエアコン冷媒ガスの表示に係る国際分類の変更をとりあげる。オゾン層保護のためにエアコン冷媒ガスは代替フロンへの転換が進められているが、地球温暖化係数(GWP: Global Warming Potential) は代替フロンの種類によって異なる。化学品の輸送・貯蔵・建築・労働安全等に関する各国の法規制において参考にされている国連の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」(GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)では、着火する濃度のみを可燃性の分類基準にしているため、着火しても燃焼速度が遅く容易に燃え広がらない危険性が低いガスであっても、燃焼速度の早く危険性の高いガスと同じ分類となっている。これが各国における過剰な規制を促し、危険性が相対的に低く地球温暖化係数も低い一部の冷媒ガスの普及の妨げとなっている。そこで、GHSにおける可燃性ガスの区分を燃焼速度も考慮したものへと変更するため、日本企業等の要請を受け、2014年に日本政府・ベルギー政府の共同提案により国連にWGを設立し、現在、議論を進めている。このような新たな国際ルールを形成することにより、日本企業が強みを有する地球温暖化係数の低い冷媒ガスの競争力が強化されることが期待される。
(4) 小括
こうした国際的なルール形成の視点を経営に取り入れることは、日本企業が今後の世界市場を生き残るための重要なカギの一つである。より具体的に言えば、国際的なルール形成の動向把握、ビジネスと国際ルールの関係分析、国際的なルール形成を経営戦略に位置づけ最適な内部体制を構築すること、国際的なルール作成に向けたアジェンダの提起、ステークホルダーとのコンセンサス形成などが必要とされる。一方、企業だけでは活動に限界があり、政府によるアプローチも不可欠である。そのため、今後とも日本政府は、国際的なルール形成の重要性を啓発するとともに、フェーズに応じて外国政府を含む多様なアクターへの働きかけを行い、我が国の企業活動を後押ししていく。
7.WTO紛争解決手続きを活かした取組
我が国は、ルール不整合である他国の措置による自国の不利益を解消すること、また、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中で先例の蓄積によってルールを発展させることを目指して、二国間交渉のほかWTOの紛争解決手続を積極的に活用してきた。我が国が当事国として協議を要請した案件は21件あり、近年では対新興国の案件が多い。係争中の3件を除く18件のうち、17件は我が国の主張に沿った解決がなされている(2016年3月末現在)。また、我が国は、先例形成を通じたルールの発展の観点から、第三国としても多くの案件に参加(第三国参加)し、重要な論点に関して我が国の立場を述べている。
我が国が当事国としてWTO紛争解決手続に付託している案件のうち、経済産業省が関与して、解決を図っている最近の事例は以下のとおりである。
(1)韓国の日本製空気圧伝送用バルブに対するアンチ・ダンピング措置
2014年2月、韓国政府は我が国からの空気圧伝送用バルブの輸入に対するアンチ・ダンピング調査を開始し、2015年8月に課税措置が開始された。
本措置は、ダンピングによる国内産業への損害及び因果関係の認定等に関し、アンチ・ダンピング協定に違反する可能性があるため、2016年3月、我が国は、韓国に対して協議要請を行った。
(2)ブラジルの自動車等に対する内外差別的な税制恩典措置
ブラジル政府は、2011年12月、自動車に対するIPI(工業製品税)を30%引上げるとともに、翌年、新自動車政策(イノバール・アウト)を発表し、国内の自動車メーカーに対し、一定の生産工程の実施及び国産部品の使用等を条件にIPIを最大30%減税することとした。また、情報通信分野においても、一定の部品の製造及びこれを使用した最終製品の組立て等の国内実施を要件として、当該産品にかかる間接税を大幅に減免する措置を導入している。
これらの措置は、 WTO 協定上の内国民待遇義務等に違反する可能性があるため、2015年7月、我が国はブラジルに対して協議要請を行い、同年9月、パネル設置を要請した。現在、パネルにおいて審理が行われている(EUは、2014年10月にパネル設置要請を実施。)。
(3)中国の日本製ステンレス継目無鋼管に対するアンチ・ダンピング措置
2011年9月、中国政府は日本、EUからの高性能ステンレス継目無鋼管の輸入に対するアンチ・ダンピング調査を開始し、2012年11月に課税措置が開始された。
本措置は、 ダンピングによる国内産業への損害の認定等に関し、 アンチ・ダンピング協定に違反する可能性があったため、同年12月、我が国は中国に対して、協議要請を行い、同年4月、パネル設置を要請した(その後EUもパネル設置要請)。2015 年2月、 中国の違反を認めるパネル報告書が配布されたが、 一部の論点について我が国の主張が認められなかったことから、 同年5月、我が国は上訴し、 中国、EUも続いて上訴を行った。同年10月、我が国の主張を全面的に認める上級委報告書が公表された(現在、 中国による履行期間中)。
(4)ウクライナの自動車セーフガード措置
2011年7月、ウクライナ政府は、輸入乗用車(排気量1000cc~1500cc及び1500cc~2200ccの乗用車)に対するセーフガード調査を開始し、2013年4月に課税措置が開始された。
本措置は、 発動要件の一部を明確に認定していない点や調査期間中の輸入量の大幅減少にも関わらず輸入増加を認定した点等に関し、 セーフガード協定等に違反する可能性があったため、同年10月、我が国はウクライナに対して、協議要請を行い、2014年2月、パネル設置を要請した。2015年6月、 日本側の主張を全面的に認めるパネル報告書が公表され、ウクライナは同年9月末日にセーフガード措置を撤廃した。
(5)アルゼンチンの輸入制限措置
2008年11月、アルゼンチン政府は、非自動輸入ライセンス制度を導入し、その後、輸入者に対する輸出入均衡要求等を実施した。また、2012年2月には、輸入者は輸入品について事前申請し承認を得ることが必要となったが、承認要件が示されず、当局の裁量によって恣意的に運用されている点で問題があった。2013年1月に非自動輸入ライセンス制度が撤廃されたが、その他の措置は存続した。
これらの措置は、WTO協定上の輸出入制限の禁止に抵触する可能性があったため、我が国は、2012年8月、二国間協議を要請し、同年12月、米国・EUとともにパネル設置を要請した。2014年8月、日米EUの主張を全面的に認めるパネル報告書が発出され、2015年1月には、パネル報告書を支持する上級委員会最終報告書が発出された。我が国は、引き続き、アルゼンチンがWTO協定に不整合な措置を速やかに是正するよう注視していく。