第2節 市場獲得に向けた取組
1.新興国戦略
我が国の市場が世界市場の中で相対的に小さくなる中、新興国展開の重要性はますます高まっている。新興国の需要の獲得は、我が国企業が世界で拡大する需要を捕捉して我が国に富を還流するため、また、我が国からの製品輸出・部素材調達を促進する基盤づくりのために必要である。
もっとも、一口に新興国といっても、経済発展の度合い、我が国企業の進出の程度、他国企業との競争環境等、それぞれ状況は各地域によって様々である。
新興国の成長を最大限に取り込んでいくために、それぞれの新興国の状況を理解した上で、戦略的取組を進めていく必要がある。
(1)地域ごとの方針と進捗状況
これまでは、日本再興戦略2013(2013年6月閣議決定)に基づき、以下の3類型で市場分析を行ってきた。
①「中国・ASEAN」では、既に現地で相当程度の産業集積、サプライチェーンを形成していたため、消費市場が拡大してきていることを踏まえ、サービス業など「更に幅広い」産業の進出(『フル進出』)により需要を取り込んでいくことを目指してきた。
②「南西アジア、中東、ロシア・CIS、中南米」では、日系企業の進出が欧米に劣後していたため、戦略的に『クリティカル・マス到達』を目指す有望分野に絞って、集中的に取り組んできた。
③「アフリカ」については、進出企業拠点数が657(世界全体の進出日本企業拠点数の1%程度)とかなり限定的であったため、1つでも多くの『成功事例』を創出し、我が国企業の事業展開のフィールドとして位置づけられるような状況まで土壌作りを行ってきた。
以下では、各地域ごとの今後の方針及び現在の進捗について概観する。
①中国
〈今後の方針〉
中国は世界第2位の経済大国であり、相対的に高い経済成長を続けている。日本にとって最大の貿易相手国であり、既に多数の日本企業が進出していることを踏まえれば、日中間の貿易投資関係をさらに深化させ、日本企業のビジネス環境の改善を図るとともに、日本の強みを生かした新たな市場獲得を支援することが重要である。
具体的には、日中韓経済貿易大臣会合や日中省エネルギー・環境総合フォーラムなど、政府レベルの各種協議・交流を推進し、民間レベルの互恵的なビジネス協力に向けた環境整備を図る。
〈進捗状況〉
2015年4月にジャカルタにおいて安倍総理と習近平国家主席との日中首脳会談が実施された。また、同年11月、韓国・ソウルにおいて安倍総理と李克強国務院総理との日中首脳会談が実施され、経済を始め各分野の交流と協力をさらに強化していくこと等が確認された。その直前の10月末には、林経済産業大臣が参加して、約3年半ぶりに、「日中韓経済貿易大臣会合」がソウルで開催され、日中韓三カ国間で、物流・通関の円滑化等による「サプライチェーンの連結性向上」など、多面的な協力強化に向けた取組をさらに進めることが合意された。また、省エネルギー・環境分野における日中協力の促進に向けて、「第9回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」が11月に東京で開催され、林経済産業大臣、高木経済産業副大臣等が参加した。本フォーラムでは新たに26件の日中協力案件が合意され、これまでの協力案件の累計は285件となった。
②ASEAN
〈今後の方針〉
ASEANには、基礎的なインフラや産業人材が不足している段階の国から、産業集積が相当程度進んでいる一方でコスト面の優位性を失いつつある段階の国まで存在する。消費市場としては、今後、中間層・富裕層の更なる増加が見込まれており、ASEAN全体として、引き続き魅力が高まっている。発展段階に応じて、ビジネス環境整備、インフラ整備、経済統合等の支援を通じ、生産ネットワークの強化・ASEAN市場の獲得を目指す。
例えば、インドネシアにおけるビジネス・投資環境整備に向けたインフラ整備や制度の透明性向上、ミャンマーにおける都市と地方の好循環による均衡ある発展や、産業振興のために必要なインフラ、エネルギーミックス、ダウェー経済特別区開発等に関する検討、またベトナムにおける戦略6業種の育成を図る工業化戦略の実施の支援といった各国別の取組と、ASEAN全体においてERIAを通じたインフラの質の概念の普及が挙げられる。
また、幅広い産業における市場獲得が必要である。例えば、ASEANにおける省エネの制度整備による競争環境の整備が挙げられる。また、サービス産業において、ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)の枠組みを活用したASEANの産業高度化や、ビジネス環境整備を進めることによって市場獲得を目指す。
〈進捗状況〉
ミャンマーにおいては、「ティラワ経済特区開発」について、開発を担う日ミャンマー共同事業体を2013年10月に設立、同年11月には起工式典を開催、2015年9月には開業式を行い、周辺インフラ整備、ワンストップ・サービス構築支援に官民一体で取り組んでいる。また、インドネシアでは、従来、インフラ整備を含む投資環境改善を図るMPA(ジャカルタ首都圏投資促進特別地域) 構想を両国官民で進めてきた。2014年10月に新政権が発足し、2015年3月に開催された日インドネシア首脳会談において、官民による新たな閣僚級対話の枠組みの下で、ビジネス・投資環境整備やインフラ整備、経済産業協力等を両国間で進めて行くことで一致し、2015年11月の首脳会談では、質の高いインフラ整備への協力を表明した。
また、幅広い産業における市場を獲得するため、ASEAN地域におけるクールジャパンにおける取組を強化した。
③南西アジア
〈今後の方針〉
インド、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ等南西アジア地域の国々は、人口規模(上記4カ国で現状約16億人、2030年には約20億人まで増大するとの見方あり)、GDP成長率、拡大する中間層といった要因から、世界有数のポテンシャルを秘めており、インフラ案件をはじめとして、日本勢による市場獲得の必要性が高い。
また、南西アジア諸国とアジア太平洋地域との経済関係・産業ネットワークを強化していくことも重要である。東アジア地域包括的経済連携(RCEP)、インドにおけるデリー・ムンバイ産業大動脈(DMIC)やチェンナイ・バンガロール産業大動脈(CBIC)の開発等との連携により、南西アジア地域及び周辺地域の連携を強化し、域内連結性強化の実現を狙う。
〈進捗状況〉
インドについては、2014年5月に誕生したモディ政権は「Make in India」イニシアティブによる製造業誘致等、外資誘致に積極的な姿勢を見せている。同年9月にモディ首相が訪日して行われた首脳会談において、今後5年以内に我が国の対印直接投資とインドに進出する日系企業数を倍増する等、さらなる日印経済関係の強化に資する事項が合意され、日本企業のこれらに対する期待は高い。
さらに、2015年12月には安倍総理がインドを訪問。日本企業の投資・進出促進に向けて、「日印メイク・イン・インディア特別金融ファシリティ」の創設、「日本工業団地」周辺のインフラ整備(道路、電力、水等)等のための「特別パッケージ」の付与等について合意した。日本工業団地については、昨年、日印で12の日本工業団地候補地について合意しており、今後、周辺インフラ整備等の投資環境整備や投資インセンティブ等の検討を日印両国間で推進し、日本企業の投資・進出促進を図る。さらに、インド政府内に日本企業専門のインド進出支援組織として「Japan Plus」を設置。経済産業省、JETROから職員を派遣し、月平均20~30社程度の日本企業のインド進出支援や既進出企業の課題解決を実施したところ。
また、インドは州政府の権限が強いことを踏まえ、日系企業の集積する戦略州との協力強化を目指し、アンドラ・プラデシュ州、グジャラート州、カルナタカ州、ラジャスタン州、マハラシュトラ州、マディヤ・プラデシュ州と経済産業省の間で協力に係る覚書を署名した。当該覚書において設置された政策対話等を通じ、インドにおける投資環境整備、個別案件の促進による日系企業の投資促進を実現すべく州レベルでの協力も強化していく。
特に、インド南部のアンドラ・プラデシュ州(AP州)は、新州都の開発、港湾・工業団地整備などが急速に進み、従来の主要産業である農業に加え、州内の新たな産業振興が進む機運が生まれている。このような状況の下、経済産業省とJETROは、関係省庁・機関とともに、日本企業との情報交換を行うAP州官民協議会を設立。今後、AP州における新州都開発、産業協力・投資促進、インフラ整備等の各種プロジェクトについて、日本企業が有する知見、経験、技術等を活かすため、情報の共有、潜在的な案件形成に資する情報交換、ネットワーキング等を行うプラットフォームとしてAP州官民協議会を活用し、日本企業の投資・進出を促進していく。
バングラデシュについては、2016年4月に東京において官民合同経済対話を実施した。日本企業の進出及びビジネス促進のため、ビジネス環境の整備、産業の多様化、人材育成と技能開発等について議論。3つのワーキング・グループ(税金・銀行サービス、産業の多角化、投資環境整備)の設置が合意され、今後、両国で定期的に対話のフォローアップを行うこととなった。
パキスタンは、昨年11月に官民合同経済対話を実施した。今後は、同対話の成果文書である、ニュー・フロンティア・アクション・プラン(ビジネス環境整備・インフラ整備による投資促進、自動車産業政策の策定、産業技術協力の推進)を着実にフォローアップしていく。パキスタンに進出している日系企業の黒字率は他のアジアの国々と比較し高い。日本企業のマーケット拡大・維持を図るべく、日本勢が活動しやすい投資環境の整備を推進していく。
スリランカは、昨年発足したシリセーナ政権は、ラージャパクサ前政権の過度の中国依存を見直し、欧米、日本、インド等と均衡の取れた関係構築を目指している。スリランカは、東・東南アジア、南アジア及び中東・アフリカ地域を結ぶ物流のハブとして重要な役割を果たし、インドへのアクセスも良好。内戦終結以降7%程度の高い経済成長、コロンボ港等の大規模ハブ港湾の存在といった地理的優位性、英語が堪能で質の高い労働力等の同国の特性に留意しつつ、昨年10月のウィクラマシンハ首相訪日時の共同声明で合意した日スリランカ経済政策対話(於スリランカ)等も活用しつつ、両国間の貿易・投資の促進を目指す。
④ロシア・CIS
〈今後の方針〉
ロシア・CIS地域は、石油・石炭・天然ガスをはじめ、ウラン、レアメタル、レアアース等の鉱物・エネルギー資源が豊富である。一方、旧ソ連時代に建設されたインフラは老朽化が進んでおり、インフラ設備等の新規建設及び更新プロジェクトが多数存在し、これらを促進するため、我が国企業から、投資環境の改善ニーズが高まっている。
大統領や政府高官に権限が集中している国が多いことから、要人往来の機会を捉えたトップセールスが重要。特に、ロシア・中央アジア地域等においては、後述の「日・露・中央アジア交流促進会議」においてプロジェクトの適切なフォローアップを行っていくとともに、今後の外交の機会を捉え、互恵的な経済関係の構築とともに、インフラプロジェクト等を始めとした経済案件の着実な進展を目指す。
〈進捗状況〉
2015年11月、林経済産業大臣がウリュカエフ経済発展大臣と会談し、日露間の経済関係強化に向けて引き続き協力していくことを確認するとともに、中小企業協力に関し、両省間の協力覚書の延長に合意した。また、2016年2月、林経済産業大臣がマントゥロフ産業商務大臣と会談を行い、産業分野における協力を推進するため、両省の高級事務レベルによる産業政策対話を定期的に行うことを内容とする覚書を締結した。中央アジアとの関係では、2015年6月、山際経済産業副大臣が、経済ミッションの同行を得てトルクメニスタンを訪問し、ベルディムハメドフ大統領等と会談を行った他、両国から約100名の参加を得て、ビジネスフォーラムを開催した。また、2015年10月、安倍総理が、経済ミッションの同行を得て、総理大臣として初めて中央アジア5カ国(トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン)全てを公式訪問し、各国大統領と首脳会談を行った他、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンにおいてビジネスフォーラムと日本技術の展示会を開催した。総理中央アジア訪問の成果を一過性のものとせず、日本・中央アジア間の交流を一層促進するため、従来の「日露経済交流促進会議」を「日・露・中央アジア交流促進会議」に改組し、関係省庁が適切なフォローアップを行っていくこととなった。
また、ウクライナとは、2015年6月、ウクライナの独立以来、初の我が国の現職総理大臣として安倍総理が訪問し、ポロシェンコ大統領と会談を行い、高効率の石炭火力発電技術の導入について協力していくことを確認した。また、両首脳立会いの下、角茂樹駐ウクライナ大使とズーブコ副首相兼地域発展・建設・公共サービス大臣の間で、ボルトニッチ下水処理場の改修を行うための円借款に関する書簡の交換が行われた。
⑤中南米
〈今後の方針〉
中南米は、重要な天然資源の調達先である。そのため、天然資源の調達を引き続き確実なものにするとともに、拡大する中間層マーケットやインフラ事業の拡大という戦略のもと、中南米市場を取り込んでいくことを目指す。
また、安倍総理訪問を引き続きフォローアップを行っていくとともに、資源国との関係強化・安定的なエネルギー供給源確保のため、資源国の産業多角化や人材育成に資する日本企業による現地進出・投資を含めた分野での協力関係を深めていく。
〈進捗状況〉
メキシコでは、2015年2月には、関経済産業大臣政務官が訪墨し、「太平洋同盟インフラセミナー」を開催した。メキシコ経済省副大臣も出席するなど、約140名の聴衆が出席し、高い注目を集めた。2013年度に作成した「太平洋同盟インフラマスタープラン」を紹介し、関経済産業大臣政務官は高い技術力を有する我が国の官民がメキシコのインフラ整備において貢献することへの期待を表明した。
ブラジルでは、2015年9月、第3回日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会を開催し、安倍総理の訪伯のフォローアップ、ブラジルにおけるビジネス環境の改善及び両国の発展のための産業協力について意見交換を行い、同委員会の継続的な開催が重要であることが確認され、同委員会にかかる中間会合の開催を提案した。2016年2月、日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会中間会合が開催され、スマートコミュニティや医療分野での我が国の協力、「更なる投資実現に向けた行動計画(AGIR)」の策定によるブラジルのビジネス環境整備の課題及び対ブラジル投資促進について意見交換を行った。
2015年3月、宮沢経済産業大臣はカブリサス閣僚評議会副議長と会談を行い、外国貿易投資法の改正における我が国からの投資誘致、貿易保険の見直し、今後の二国間関係の構築について意見交換を行った。
2015年9月、安倍総理は総理大臣として初めてジャマイカを公式訪問し、シンプソン=ミラー首相と3年連続3回目の首脳会談を行い、昨年の日・カリコム首脳会合で表明した「日本の対カリコム政策」の三本柱(第一の柱:小島嶼国特有の脆弱性克服を含む持続的発展に向けた協力。第二の柱:交流と友好の絆の拡大と深化。第三の柱:国際社会の諸課題の解決に向けた協力。)に沿って「日・ジャマイカ・パートナーシップ」を構築し、協力を強化・促進していくことが確認された。また、安倍総理が省エネ、防災分野での技術協力や日本企業が投資するジャマイカ電力事業への支援と、それに対する電力管理の人材育成を行うことを表明した。
⑥中東
〈今後の方針〉
中東地域は、我が国にとってエネルギーの安定供給に欠かせない地域である。そのため、同地域における産業多角化や巨大インフラ事業等への参画を通じて、中東地域における市場の開拓と経済関係の強化を目指す。
具体的には、引き続き安定的なエネルギー確保に向けた議論を先述のLNG産消会議等を通じて働きかけを行っていく。また要人往来の機会を活用し、我が国企業のインフラ輸出を始め、経済関係の更なる進展を目指す。
〈進捗状況〉
中東諸国との間でも、経済関係の強化に向けて頻繁な往来がなされた。イランについては昨年7月にEU3+3(英仏独米中露)とイランの核問題に関する最終合意を受け、山際経済産業副大臣がイランとの経済関係を強化すべく日本企業とともに訪問した。また今年1月にイラン核問題最終合意の「履行の日」が到来したことを受け、我が国も国連安保理決議に従い、これまで累次に講じてきた制裁緩和を行った。さらに今年2月にはタイエブニア経済財務大臣が訪日し、イラン投資協定の署名を行ったほか、林経済産業大臣との間でファイナンス面での協力を行う協力覚書の署名も行った。トルコについては、2015年10月のエルドアン大統領の訪日に続いて、同11月には安倍総理がG20サミットを前にイスタンブールを訪問、首脳会談を実施したほか、日本・トルコビジネスフォーラム(主催:JETRO、共催:DEIK(対外経済評議会))を開催し、JETROが現地経済団体との協力関係強化に関する覚書を締結した。また、同年10月には高木経済産業副大臣がG20エネルギー・貿易大臣会合のためトルコに出張、ゼイベキチ経済大臣と会談したほか、同年12月、林経済産業大臣のケニア出張(WTO閣僚会合)の機会を捉えて後任のエリタシュ経済大臣と会談を行い、投資・貿易関係強化に向けた意見交換に加えて、日本企業によるトルコのインフラプロジェクトへの更なる参画に向けた働きかけを行った。イスラエルについては、2015年5月から日イスラエル投資協定交渉が開始され、同年12月に実質合意に達した。また、一昨年来の要人往来を踏まえ、同年7月にはイスラエル経済省との間で第1回日イスラエル経済政策対話を開催し、両国間の投資・貿易促進に向けた方策、研究開発(R&D)やサイバーセキュリティ分野での協力、ベンチャー政策等の幅広い分野で意見交換を行ったほか、2016年1月に開催されたサイバーセキュリティ分野の展示会「サイバーテック2016」(於テルアビブ)にJETROがジャパンブースを出展、参加した日本企業に多くのビジネスマッチング機会を提供したほか、各種報道でも採り上げられた。パレスチナについては、2016年2月にアッバス大統領が訪日、随行したオウデ経済庁長官の参加を得てパレスチナ・ビジネスフォーラム(主催:JETRO、JICA、パレスチナ自治政府)が開催され、パレスチナのビジネス環境や、近年発達が著しいICT産業、JICAが支援しているジェリコ農産化工団地の概要等が民間企業に紹介された。エジプトについては、2016年2月にエルシーシ大統領が訪日し、日エジプト首脳会談が行われ、二国間関係の新たな段階への飛躍のための協力に関する共同声明が出された。3月2日には両国の経済界が参加する経済合同委員会において、各協力文書の署名式が行われた。
加えて、エネルギー協力を基礎としつつ、幅広い分野での協力に関するやりとりも活発に行われた。2015年5月には宮沢経済産業大臣が、訪日したファキーフ・サウジアラビア経済企画大臣との会談を通じて両国の経済関係強化を確認した。2016年1月には高木経済産業副大臣がサウジアラビアを訪問し、主要閣僚との会談を通じて原油の安定供給に向けた協力を含め、両国の経済関係を更に発展させるべく取り組むことを確認した。カタールとの間では、同年9月のアル・サダ・エネルギー工業大臣訪日時に開催されたLNG産消会議2015や日・カタール合同経済委員会といった場を通じて、我が国への天然ガスの安定供給を始めとする経済関係の更なる強化に向けた意見交換が行われた。また、2015年1月の宮沢経済産業大臣のUAE(アブダビ)訪問、同年2月の高木経済産業副大臣の同国訪問での協議を含む累次の働きかけを通じて、同年4月には、UAE(アブダビ)の陸上油田権益の獲得に至った。同年9月には、マンスーリUAE経済大臣が訪日し、宮沢経済産業大臣が会談、インフラプロジェクトへの日本企業の更なる参画に向けた働きかけ等を行う貴重な機会となった。さらに、同年11月、2016年1月には高木経済産業副大臣がUAEを訪問し、アブダビ国際石油展示会議(ADIPEC)やワールド・フューチャー・エナジー・サミット(WFES)など世界最大級の展示会に参加するとともに、政府要人との間で、エネルギーを始めとする幅広い分野での協力を一層推進していくことを確認した。加えて、2015年5月には山際経済産業副大臣がクウェートを訪問し同国ジャサール電力・水省との間で電力・水分野の協力覚書の署名が行われ、さらに同年11月には高木経済産業副大臣が同国を訪問し、アブル住宅担当兼公共事業大臣及びブーシャハリー電力・水省次官との会談を通じて、インフラプロジェクトへの日本企業の更なる参画に向けた働きかけ等を行う貴重な機会となった。
⑦アフリカ
〈今後の方針〉
アフリカは、豊富な天然資源を有するほか、人口増、GDP成長が著しく、興市場としてもポテンシャルが高い地域となっている。そのため、旺盛なインフラ案件の獲得や消費財等の新たな市場開拓を目指す。
具体的には、2016年8月に開催が予定されているTICADⅥを最大限活用し、日本製品・技術のPRや本体会合での各国との議論を通じて、対アフリカへの投資促進や貿易振興を図る。また、一つでも多くの成功事例を創出するための国際見本市への出展支援、投資環境整備を目的とした投資的協定の促進など、官民一体となって市場開拓に取り組む。さらに、治安情勢や危機管理を含めた形でのリスクへの対応として、在外公館とのさらなる連携の強化、安全対策に関するセミナーを開催する。
また、必要に応じて資源国に対する人材育成支援・金融支援等の実施を検討する。
なお、アフリカ進出に際しては、既存の商業網を持つ現地企業との連携や、現地に根ざした販売手法の確立、製品開発、事業運営、状況に応じて既にアフリカ進出を果たしている欧州・インド等の第三国企業との提携等、現地の動向を見ながら柔軟な展開を図ることが肝要である。
〈進捗状況〉
2013年6月のTICADⅤにおいて表明した、我が国がアフリカの「信頼できるビジネスパートナー」として更なる発展貢献していくための施策のうち、今後5年間のアフリカにおけるJETRO事務所の倍増(5か所→10か所)に関しては、これまでに、モロッコ、エチオピアの新規事務所が開設された。
2016年3月には、JETROを通じて、「第2回アフリカ投資誘致機関フォーラム」を開催。本フォーラムには、アフリカ8か国(コートジボワール、エジプト、エチオピア、ケニア、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア)の投資誘致機関の代表を招聘し、日本企業向けの投資セミナー、招聘8か国の投資誘致機関の連携を深めるための会合、日本企業視察等を実施した。
資源の安定供給確保や資源・インフラ関連のプロジェクト獲得のため、2015年5月に第2回日アフリカ資源大臣会合等を開催しアフリカ資源国との更なる関係強化を図った。
なお、アフリカ市場の現状や将来性については、第2部第4章第1節にて分析しており、詳細についてはそちらを参照されたい。
(2)企業支援施策
次に、企業支援施策の進捗と今後の方針について示す。
①トップセールス・各省連携体制の強化
第Ⅲ-2-2-1表は、安倍政権発足後の首脳・閣僚によるトップセールスの実績について表したものである。
第Ⅲ-2-2-1表 首脳・閣僚によるトップセールスの実績(2016年2月時点)
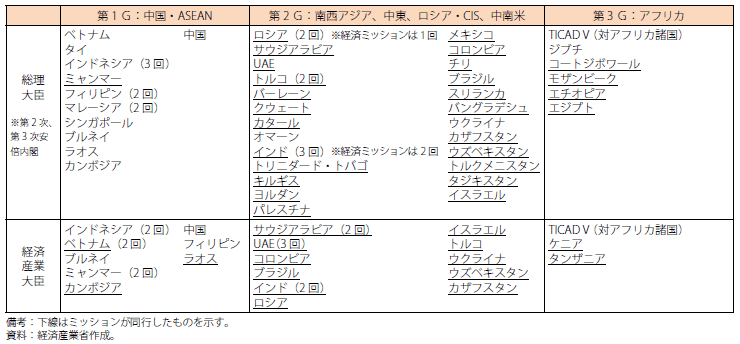
我が国企業の進出環境整備、資源確保・インフラ案件獲得に向けて、首脳・閣僚によるトップセールスから民間レベルでの交流まで総動員して、官民一体となったオールジャパンの取組を実現するため、安倍総理を始めとする閣僚によるトップセールスがなされた。例えば、中央アジアについては、2015年10月、安倍総理が総理大臣として初めて中央アジア5カ国(トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン)全てを公式訪問し、官民合わせて87件の署名文書に調印が行われた。その結果、豊富な天然資源の有効活用プロジェクト等に対する日本企業の協力・参画に寄与した。カンボジア、ラオスについては、2014年4月の経済産業大臣訪問時に、我が国の医療技術を活用した救急救命センターの設立(カンボジア、ラオス)、石油鉱区開発(カンボジア)や水力発電所(ラオス)、の整備等における協力推進で一致するといった成果があった。
引き続き、トップセールス、ミッションの派遣、投資協定・租税条約の締結・改正、ODA、リスクファイナンス、技術協力等、あらゆる政策ツールを動員して、可能性を見いだしていくことが重要である。
②投資協定・租税条約・社会保障協定の締結・改正
海外に進出した我が国企業の安定的な操業を行うためのビジネス環境を確保し、投資財産の保護、現地進出・資金還流の障壁を撤廃するため、投資協定の締結を促進している。新興国を中心に保護主義的、外資差別的な措置が増えつつある中、投資協定については、東南アジア諸国との交渉を一通り終え、現在、中東・アフリカを中心に交渉を進めている。
2015年度においては6月にオマーン、2月にイラン、2月にウクライナとの投資協定に署名した。現在、交渉中のものとして、カタール、アラブ首長国連邦、ガーナ、モロッコ、タンザニア等が挙げられる(2016年4月1日時点)。加えて、RCEP、日中韓FTA等のEPA/FTAにおいても、投資章の交渉を行っている。我が国の投資関連協定(投資協定及びEPA/FTAの投資章)の締結数は、欧米中韓などの主要国に比べ少なく、我が国企業のニーズや相手国の事情も踏まえ、投資関連協定交渉の取組みを一層加速していく必要がある。
また、両国の課税所得の範囲等を調整する租税条約を新規締結・改正することにより、海外進出企業に対する課税の法的安定性の確保、我が国企業が海外で稼得した収益の国内環流の円滑化等に資することが期待される。
2015年度には、12月にカタール国との租税条約が発効するとともに、12月にはドイツ及びインドと、2016年1月にはチリとの租税条約に署名した。今後とも、我が国産業界のニーズや我が国課税権の適切な確保等の観点を総合的に勘案し、企業の海外展開の支援に資する租税関連条約のネットワーク拡充の取組みを加速することが重要である。
我が国は2000年にドイツとの間で最初の社会保障協定が発効して以来、2016年4月現在15か国との間で社会保障協定が発効済み、4か国との間で署名済みであるほか、現在、複数国との間で政府間交渉や予備的な協議等を順次行ってきているところである(第Ⅲ-2-1-2図)。
第Ⅲ-2-1-2図 社会保障協定の締結状況(2016年4月時点)
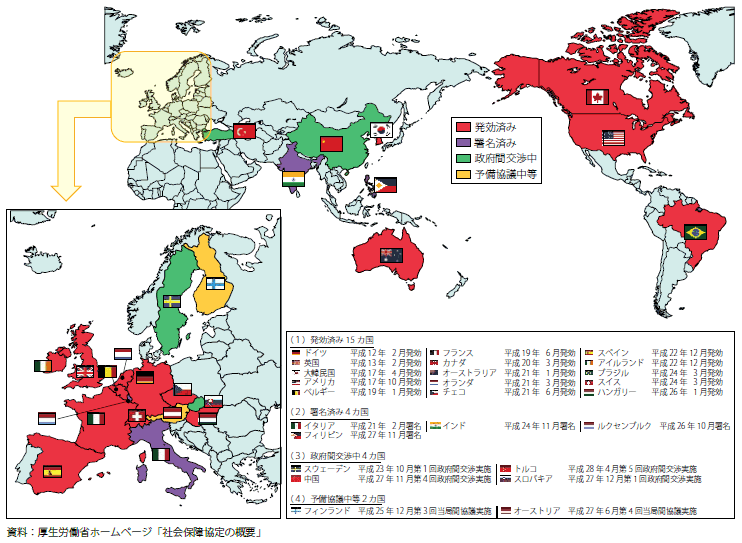
③公的ファイナンスの制度拡充
2015年11月には、「質の高いインフラパートナーシップ」のフォローアップに際し、円借款の手続の迅速化、新たな借款制度の創設など円借款や海外投融資の制度改善、ADBとの連携強化、JBICによるリスクマネー供給拡大、NEXIの機能強化を含む公的金融の抜本的制度拡充を行うことを発表した。詳細については、本節の「2.インフラシステム輸出(1)リスクマネー供給拡大」を参照されたい。
また、貿易保険制度をより効率的かつ効果的に運営するため、貿易保険の審査・引受を担う、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)について全額政府出資の特殊会社への移行等を措置する「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」が2015年7月10日に成立した(2017年4月1日施行予定)。
④技術協力の深化
新興国とのWin-Winの関係構築が鍵となるため、新興国の課題解決やマーケット・インのアプローチが必要である。そこで、従来から実施している人材育成に加え、現地社会課題を解決する製品・サービスの開発を、現地の大学・研究機関・NGO・企業等と共同で取り組む日本企業を支援した。また、元留学生、元HIDA研修生など親日・知日人材とのネットワークを構築するため、SNS等のオンラインツールの活用やビジネスコンペ等の開催を通じ、「親日・知日コミュニティ」を形成した。
さらに、日本人の海外インターン派遣だけでなく、海外からのインターン受入を開始し、日系企業の開発途上国におけるビジネス開拓を支援した。
2.インフラシステム輸出
これまで見てきたように、中国の成長鈍化等の経済情勢変化も踏まえ、今後は、アフリカ、インド、ASEAN等の成長地域における需要開拓を一層推し進める必要がある。とりわけ、これら新興国では、急速な経済成長・都市化に伴い膨大なインフラ需要が見込まれており、我が国が強みとする質の高いインフラの輸出に官民一体となって取り組むことが重要である。本節では、成長地域におけるインフラ需要獲得のための今後の取組について概説する。
(1)リスクマネーの供給拡大
まず、新興国の膨大なインフラ需要に対応するためには、莫大な資金が必要である。そこで2015年5月、安倍総理は、「質の高いインフラパートナーシップ」を発表し、機能強化したアジア開発銀行(ADB)と連携し、両者で合わせて5年間で約1,100億ドルの「質の高いインフラ投資」をアジア地域に提供するとともに、これを触媒として民間部門の資金・ノウハウを動員し、質・量ともに十分なインフラ投資の実現を目指すことを掲げた。さらに同年11月、安倍総理は、「質の高いインフラパートナーシップ」のフォローアップに際し、抜本的な制度拡充を発表し、質の高いインフラ投資を一層推進する姿勢を表明した。主な拡充策は以下のとおりである。
〈「質の高いインフラパートナーシップ」の更なる拡充策(2015年11月)〉
①JICAの支援量拡大・迅速化
JICAによる支援の魅力を高めるため、以下の施策を含む合計12項目からなる円借款や海外投融資の制度改善を実施することとした。
(ア)円借款の政府内の手続きの迅速化
通常約3年かかる円借款の政府関係手続期間について、重要案件については最大約1年半まで、それ以外についても最大約2年まで短縮することとした。
(イ)新たな借款等制度の創設
円借款の利便性を向上させるため、「ドル建て借款」や「ハイスペック借款」を創設した。また、事業・運営権獲得型円借款や実証・テストマーケティング事業、特別予備費枠を導入した。加えて、海外投融資では、民間金融機関との協調融資を可能とし、「先導性」要件を見直した。同時に、迅速化策として民間企業等の申請から原則1ヶ月以内に審査を開始することに加え、JBICに案件照会があった場合の標準回答期間を2週間とした。
(ウ)自治体や公社などへの政府保証の例外的免除
開発途上国の自治体や公社等(サブ・ソブリン主体)に円借款を直接供与するに当たり、相手国の経済の安定性や相手国政府の十分なコミットメントなど各種要件が満たされる場合には、政府保証の例外的な免除について、関係閣僚会議でケース・バイ・ケースで決定することとした。
②ADBとの連携
JICAが出資してADBに信託基金を新設し、ADBと協調して質の高いPPP等民間インフラ案件に対し、今後5年間で最大15億ドルを目標に投融資を実施することとした。また、公共インフラ整備についても、JICAとADBが共働して長期支援計画を策定し、政府向け技術協力・融資を協調して行い、今後5年間で、JICA・ADB合わせて100億ドルを目標に融資を実施することとした。
③JBIC等によるリスクマネーの供給拡大
民間の資金・ノウハウを活用した海外のインフラ・プロジェクト等について、日本企業の海外展開を一層後押しするため、JBICに、期待収益は充分だがリスクを伴う海外インフラ事業向けの投融資を行う「特別業務」を追加し、更なるリスク・テイクを可能にした。また、現地金融機関からの長期借入を解禁することにより、途上国のインフラ事業で需要が大きい現地通貨建て融資を拡大したほか、海外インフラ事業への支援手法を追加(例:海外のインフラ事業に係る銀行向けツー・ステップ・ローン、債券(プロジェクト・ボンド)の取得、イスラム金融等)した。
また、NEXI(日本貿易保険)についても、海外におけるインフラ事業が大型化・長期化・高リスク化していることを踏まえ、インフラ導入国の多様なニーズや企業からの要望に対応して、投資保険期間の大幅な長期化(現状15年から30年に延長)、ドル建て貿易保険の創設、政府保証のない自治体や公社等(サブ・ソブリン向け)案件への積極的な対応(サブ・ソブリン対応保険創設)、融資保険の非常危険(注:戦争・テロなどのカントリーリスク)100%カバーなど、合計8項目からなる制度改善を実施することとした。
さらに、アジア地域以外も含めて拡大する世界のインフラ需要に対し、我が国の質の高いインフラ輸出で貢献をするため、本年5月、安倍総理は「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」を公表し、G7伊勢志摩サミットにおいても、同イニシアティブを通じて質の高いインフラ展開に一層貢献していく旨を表明した。同イニシアティブの主な内容は以下のとおりであり、今後、各施策について迅速に実施していく。
〈質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ(2016年5月)〉
①世界全体に対するインフラ案件向けリスクマネーの供給拡大
膨大なインフラ需要等に対応し、資源価格低迷による世界経済の減速及び将来の資源価格高騰リスクを低減させ、日本企業の受注・参入を一層後押しするため、今後5年間の目標として、資源エネルギーを含む広義のインフラ分野に対して約2,000億ドルを供給。
②インフラ輸出のための更なる制度改善
(ア)迅速化の更なる推進
①重要案件における協力準備調査の早期実施、②詳細設計の部分先行実施による着工・部分開業の迅速化、③コンサルタントの能力向上、④迅速化インセンティブが働くランプサム契約のコンサルタント業務への導入、デザインビルド方式等の積極活用等コンサルタントが行う調査の迅速化を図り、F/S調査開始から着工までの期間(注:案件の規模・内容等によって異なるものの、5年程度を要している案件が多い)を最短1年半に短縮する等、円借款の更なる迅速化を推進。
(イ)民間企業の投融資奨励
JICA海外投融資の柔軟な運用・見直しやユーロ建て海外投融資の検討、NEXI貿易保険の機能拡大(海外投資保険・輸出保険の非常危険のカバー率を100%(上限)に拡大等)、JOIN・JICTの出資基準・運用の緩和、JBICと市中銀行の協調融資における市中優先償還の柔軟な適用を実施。
(ウ)その他
途上国の地熱開発支援、大規模インフラ案件に対するF/S支援、無償資金協力の制度・運用改善、人材育成支援の更なる強化を実施。
③JICA、JBIC、NEXI、JOGMECその他の関係機関の体制強化と財務基盤確保
(2)戦略的人材育成の展開・川上からの関与
ファイナンス支援の魅力を高めても、インフラ導入国が調達時に初期コストばかりを重視し、ライフサイクルコストで見た経済性や安全性・強靱性、環境社会配慮等、日本が強みを有する「質の高いインフラ」が正当に評価されない場合、インフラビジネスの獲得は困難となる。そこで、産業界と連携し、特に重要なインフラ市場となる相手国の政府関係者トップや企画・評価を担当する中堅幹部等の日本への招聘・研修等を通じた人材育成を戦略的に展開することにより、日本が強みを持つ「質の高いインフラ」が正当に評価される環境づくりを進めていく。
また、インフラ受注を巡る熾烈な国際競争を勝ち抜くためには、案件が形成される前の段階から相手国政府にアプローチをしていくことが有効である。このため、マスタープラン策定や事業実施可能性調査(F/S)による支援、政策対話等を通じ、川上段階から我が国の技術の優位性・信頼性を示し、我が国企業の受注率を高めていく。
(3)「質の高いインフラ」の国際的スタンダード化
また、新興国をはじめとするインフラ導入国に質を考慮に入れたインフラがより広く普及する素地をつくるため、個別の相手国へのアプローチのみならず、「質の高いインフラ」の国際的スタンダード化にも取り組んでいる。
例えば、これまで、国連やG7/G20及びAPEC等、様々な国際枠組みにおいて、途上国の包摂的な成長を導く質の高いインフラ投資の重要性が度々言及されてきたことを踏まえ、日本が議長国として本年5月に開催したG7伊勢志摩サミットでは、①効果的なガバナンス、信頼性のある運行・運転、ライフサイクルコストから見た経済性及び安全性と自然災害、テロ・サイバー攻撃のリスクに対する強靱性の確保、②現地コミュニティでの雇用創出、能力構築及び技術・ノウハウ移転の確保、③社会・環境面での影響への対応、④国家、地域レベルにおける、気候変動と環境の側面を含んだ経済・開発戦略との整合性の確保、⑤PPP等を通じた効果的な資金動員の促進、の5原則からなる「質の高いインフラ投資の推進のためのG7伊勢志摩原則」を採択した。今後、G7以外の国や国際開発金融機関(MDBs)等に対し、同原則に沿ったインフラ投資を行うよう促していく。
また、APECにおいては、各エコノミーのインフラ開発投資に係る関連法制度を「インフラの質」等の観点からレビューし、これにより判明した能力構築支援のニーズに合わせて能力構築を提供する仕組みを我が国の提案により立ち上げ、本年より実施することとしている。さらに、中長期的に電力インフラニーズの大幅な増加が見込まれるアジア太平洋地域において、質の高い電力インフラを普及させることを目的に、我が国が主導して発電所の質を担保するための評価指標や測定方法を示したガイドライン策定に取り組んでいる。本年度中にガイドラインをとりまとめ、その普及に向けたキャパシティビルディングを実施するとともに、ガイドラインをベースとした国際標準の策定に向けた検討も進めていく。
(4)インフラ海外展開を担う日本企業の競争力の強化
欧州企業がアジア地域でのシェアを拡大させ、新興国のプレーヤーも台頭するなど、インフラ受注獲得競争が激化する中、我が国企業がインフラシステムの更なる受注を獲得するためには、価格競争力の強化、膨大な需要に対応するための製造・設計キャパシティの増強、インフラ導入国における国内生産品の優遇や使用を推奨する政策への適応等が必要であり、これらに対処するため、インフラシステム導入国等での現地生産を行うことが有効である。
このため、経済産業省では、政府間対話等を通じた相手国政府との関係強化や、ビジネス環境整備等に取り組んでいる。例えば、州政府の権限の大きいインドにおいては、戦略州と協力覚書を締結し、政策対話等を通じて中央政府のみならず州政府レベルとも関係強化しているほか、日本工業団地の整備や、インド政府内に設置した「Japan Plus」を通じてビジネス環境の改善を図り、日系企業の現地進出を促進している(「第2節1.新興国戦略」参照)。
また、日本企業による現地生産・販売のための資金調達について、公的金融を通じて支援していく。さらに、現地拠点においては人材の育成・確保が重要な課題であることから、研修生の受け入れや専門家派遣を通じ、日本企業の現地生産拠点における調達、設計、製造、運営、保守、管理等に携わる現地中核人材の育成を支援していく。
これらの施策も活用しながら、日本企業としても競争力強化を図ることが肝要であり、今後も官民一体となった取組を進めていく。
