第2節 貿易による所得格差への影響
これまでに示したように、貿易に代表されるグローバル化の進展には、生産性改善などの経路を通じて、経済成長を促すというメリットがあることが理論的・実証的にも示されている。しかしながら、グローバル化の進展により、一部の地域・産業において雇用への影響等しわ寄せが生じ、格差の拡大につながっているという批判も中には見られる。
そこで本節では世界全体で所得格差がどう推移してきたかを概観し、その上で特に先進国における所得格差がどう推移してきたか、その要因は何か、について分析していくことにする。
1.世界の所得格差の現状
所得格差を表す指標としてジニ係数(税・再分配後)がよく使われる。ジニ係数を用いて世界の所得格差の現状を見ていくこととしたい。
世界全体での所得格差については、第Ⅱ-1-2-1-1図にあるとおり、1990年には0.703だったものが、2010年には0.623へと減少しており、特に2000年以降の格差縮小のペースは急速だ18。その主な理由としては中国の経済成長が特筆されるが、他にもインドやアジアの新興国によるキャッチアップが急速に進んでいることが背景にあるとされている。中国の影響の大きさについては、中国を除いた場合、同期間のサブサハラアフリカ及びラテンアメリカの低成長により世界の格差は若干増加したとの分析にも現れている19。
第Ⅱ-1-2-1-1図 世界全体での格差の傾向(ジニ係数)
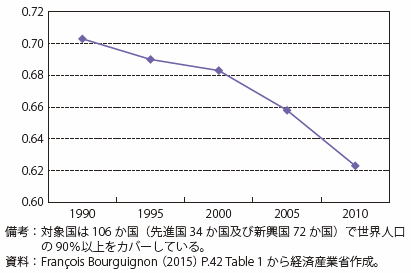
ただし、傾向としては減少傾向にあるものの、直近の2010年の世界全体のジニ係数の0.623は先進国のジニ係数がおおむね0.4以下であることと比べるとまだかなり高い水準にある点は留意が必要と思われる。
また、ジニ係数が国内全体の格差を示すのに対し、上位所得層が下位の所得層と所得格差があるかを表す所得の上位10%が下位90%の何倍かを表す指標でも、ジニ係数と同様に上位と下位の格差は減少傾向にあることがわかる(第Ⅱ-1-2-1-2図)。それでも2010年の世界の上位10%の所得は下位90%の所得の63.5倍にもなる。
ジニ係数の推移及び所得の上位10%と下位90%の所得比率の推移から世界における国際間の格差は縮小傾向にあることが分かったが、その理由として中国やアジアをはじめとした新興国の台頭が挙げられている。
第Ⅱ-1-2-1-2図 世界全体での格差の傾向(所得の上位10%と下位90%の所得比率)
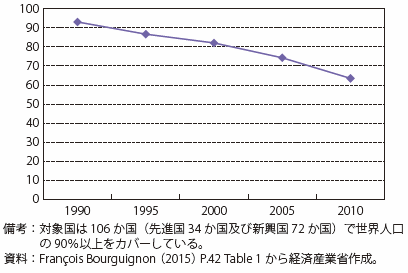
第Ⅱ-1-2-1-3図は新興国(ブラジル、ロシア、インド及び中国)、OECD加盟国及び世界の一人当たりGDPの推移を示したもの。世界全体の一人当たりGDPは1990年から2015年までに2.37倍に拡大しているが、BRIC(ブラジル、ロシア、インド及び中国)の平均一人当たりGDPは同期間中に1,812ドルから6,917ドルへと3.82倍と世界平均を上回る伸びを示している(第Ⅱ-1-2-1-4図)。OECD加盟国平均一人当たりGDPは同期間中に17,473ドから36,095ドルへと2.07倍となっていることからBRIC諸国の伸びはOECD加盟国の伸びも上回っていることがわかる。中でも中国の同期間中の伸びは25.4倍とその他と比較して突出した伸びとなっており、さらに、人口の大きさを鑑みると世界全体の格差縮小に大きな影響を与えていることが推測される。
第Ⅱ-1-2-1-3図 新興国、先進国及び世界の一人当たりGDP の推移
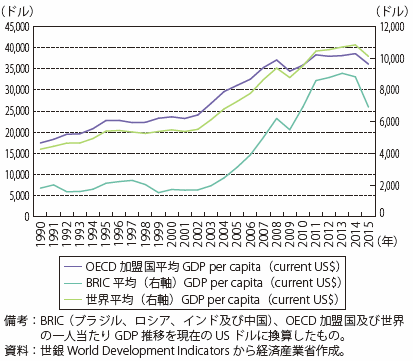
第Ⅱ-1-2-1-4図 一人当たりGDP(1990年~2015年)における伸び率比較
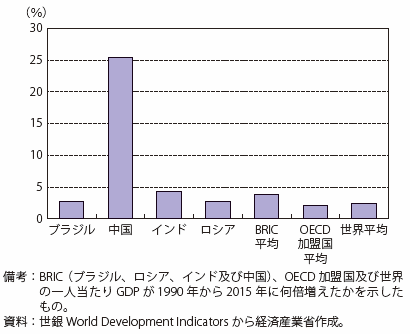
世界全体の所得格差を見る際、各国間の格差と国内格差の両方に分けて見ることができる指標としてタイル指数20がある(第Ⅱ-1-2-1-5図)。このタイル指数の国際間格差については1990年に0.734だったものが、2010年には0.479と同期間中に0.255減少しており、特に2000年以降の減少率は高い。一方、国内間格差については1990年に0.215だったものが、2010年には0.244と2000年以降徐々にではあるがしかし確実に増加傾向が見られる。国際間格差の縮小については、ジニ係数の動向でふれたように中国やアジアをはじめとした新興国のキャッチアップがその背景にあることは変わらない。国内間格差の増加傾向に関し、フランソワ・ブルギニョン氏はその著書21の中で、いくつかの国(特に先進国)では国内間格差が大きく拡大しているのに対し、新興国を中心としたその他の国では減少していて、全体としては緩やかな増加に留まっているためと分析している。
第Ⅱ-1-2-1-5図 世界全体での国際間及び国内間格差の傾向
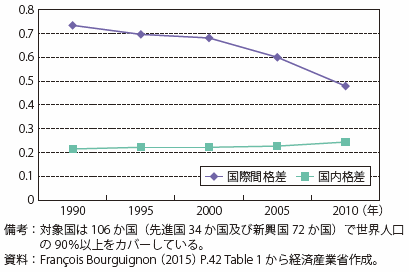
さらに世界銀行は格差の指標の1つとして貧困率を使っている。貧困率は2011年の購買力平価に基づき、1日1.90ドルの所得以下の人口割合を示す。1990年に世界の貧困率は37.1%だったものが2012年には12.7%に減少、貧困層の数でも、1990年に19億5800万人だったが、2012年には8億9600万人に減少している22。
これまで見てきたように代表的な格差の指標を見る限り、世界的な国際間の所得格差については1990年以降減少傾向にあるようだ。
18 世界全体のジニ係数については、先進国と新興国のデータソースの違い、為替、PPP、所得の定義の違い、人口による加重平均調整等、統計上の課題があり、Branko Milanovic( 2006)によると1988年~2002年の期間で世界全体のジニ係数は安定的ないし若干の増加傾向を示しているとの分析もある。
19 François Bourguignon(2015), p. 36.
20 ジニ係数と同様に格差を表す指標の1 つ。ジニ係数があるグループ全体の格差を示すだけなのに対し、タイル指数はグループ全体を相互独立した要素(性別、所得階層別等)に分解することが可能な点が特徴。ここでのタイル指数は、国際間格差と国内間格差に分解したもの。両方を足したものが全体の指数となる。係数は0と1の間の値で示され、完全に平等なとき最小値0 をとり、不平等度が大きいほど1に近づく。オランダ計量経済学者タイル(H. Theil 1924-2000)が考案。
21 François Bourguignon(2015)
22 http://www.worldbank.org/ja/news/feature/2014/01/08/open-data-poverty
2.先進国における国内格差の現状
次に先進国における国内の格差を示すジニ係数(税・所得移転後)について国際比較した結果が第Ⅱ-1-2-2-1図となる。米国は1990年の0.35から2014年には0.39まで上昇してきている。英国も1990年の0.36から世界経済危機以降いったん減少したものの上昇傾向に戻り2013年には0.36まで戻している。日本はデータの制限があり毎年のデータではないが、1995年の0.32から2012年には0.33と多少の増減はあるもののほぼ一定の水準を維持している。ドイツは1990年の0.26から2013年には0.29と緩やかに上昇している。フランスは1996年の0.28から2013年には0.29とドイツよりもさらに緩やかな上昇傾向にある。そして比較的格差が少ないといわれる北欧のスウェーデンは1991年の0.21から2013年には0.28と最も格差が低い水準にあるものの、2004年以降増加傾向が顕著になっている。全体として見れば日本を除く先進国では格差が拡大傾向にあることが見てとれる。
第Ⅱ-1-2-2-1図 可処分所得に関するジニ係数(所得移転後)
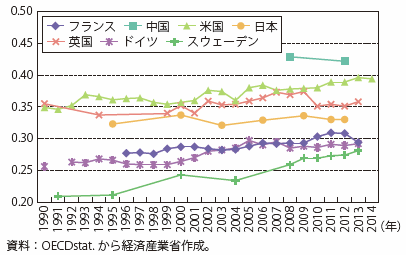
なお、出典が異なるため正確な比較とは必ずしも言えないが、世銀のデータによれば中国は2008年の0.43から2012年には0.42へと若干下落しているものの、先進国の中では最も高い水準の米国や英国よりもさらに数値が高く、国内格差が大きいことがわかる。
次に上位1%及び10%の所得比率を見たものが第Ⅱ-1-2-2-2図及び第Ⅱ-1-2-2-3図となる。特に米国は唯一20%を越えており、かつ、上位10%の所得層も50%に迫る水準まで上昇が続いているなど、上位1%及び10%の所得層がいずれも所得が伸びていることがうかがわれる。フランスは上位1%の所得層のシェアは1990年以降10%を下回る水準を維持しており、同時に上位10%の所得層でも同様に30%近辺の水準を維持しているなど、主要国の中では比較的格差は安定して低い水準にあると言える。ドイツもフランスほどではないものの、上位1%及び10%の所得階層の格差はそれほど拡大していない。日本の上位1%の所得層のシェアは1992年に10%を下回った後、2007年まで上昇傾向が見られたが、その後2010年までほぼ横ばいを示している。上位10%の所得層のシェアも1%所得層と同じような推移を示している。
第Ⅱ-1-2-2-2図 上位1%層の所得比率(所得移転前)
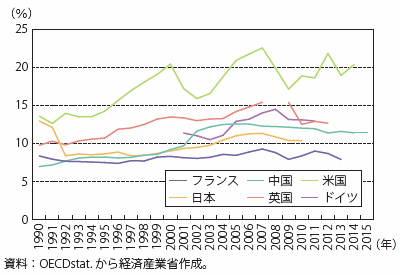
第Ⅱ-1-2-2-3図 上位10%層の所得比率(所得移転前)
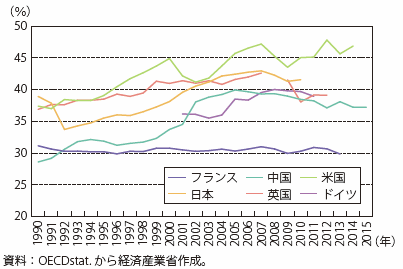
3.IMF(2007年)による所得格差の要因分析
貿易と賃金の関係に関する理論として、先進国において豊富な高技能・高学歴労働者の賃金が上昇し、新興国と競合する低技能労働者の賃金が低下することで両者の賃金格差が拡大することを示したStolper-Samuelson定理23があげられる。また、2000年以降米国においては中国からの輸入が急激に増加したことにより、一部地域の製造業の雇用が減少したことを定量的に示した研究成果24も示されており、貿易による格差拡大に対する不安が高まっているものとみられる。
一方で、賃金格差の決定要因には貿易などのグローバル化以外にも、技術革新や労働政策、教育水準など、多様な要因が指摘されており、それぞれの要因がどの程度の影響を与えているかを分解するのは極めて困難だが、エコノミストの間では労働賃金プレミアム(高技能者の賃金が低技能者の賃金よりも高い)の主要因は技術革新ととらえるのが通説とみなされている25。
複数の要因を比較する形での研究はそれほど多くなく、以下、その代表例として、IMFによる“Economic Outlook 2007”での研究成果26を紹介する。IMFでは、1980年~2006年の期間において、先進国20か国、新興国31か国により構成される51か国を対象にしたパネルデータを用いて、グローバリゼーションの指標(対GDP比輸出、対GDP比対内直接投資受入額など)、技術革新の指標(対総固定資産形成比ICT投資額)、その他の指標(教育水準、労働者の産業別構成比など)を用いてジニ係数の水準を比較検討する分析を実施している。なお、IMFは対象地域によって用いる説明変数を変えている。
主な推計結果は、第Ⅱ-1-2-3-1図のとおり。なお、モデルは固定効果を用いている。
第Ⅱ-1-2-3-1図 IMF2007によるジニ係数拡大の要因分析(先進国及び新興国)の結果
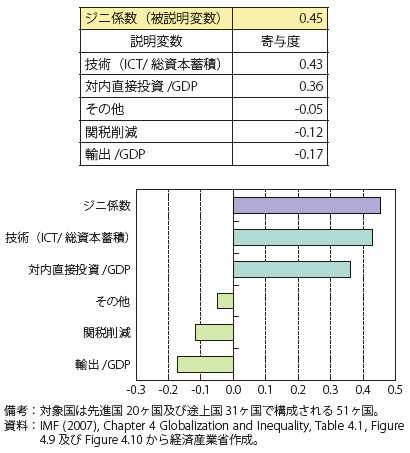
ジニ係数の変化に関する要因分解を行った結果として、IMFは「格差に対する影響が最も強いのは技術革新」と結論付けている。
但し、先進国だけに限ると、グローバリゼーション(対外直接投資)の影響が技術革新の影響よりも高いとの結果が示されている(第Ⅱ-1-2-3-2図)。グローバリゼーションの内訳の中で最も影響が強いのは対外直接投資で、次いで対内直接投資となっている。他方、輸出や新興国からの輸入は格差縮小に効いている。
主な推計結果は、第Ⅱ-1-2-3-1図のとおり。なお、モデルは固定効果を用いている。
第Ⅱ-1-2-3-2図 IMF2007によるジニ係数拡大の要因分析(先進国のみ)
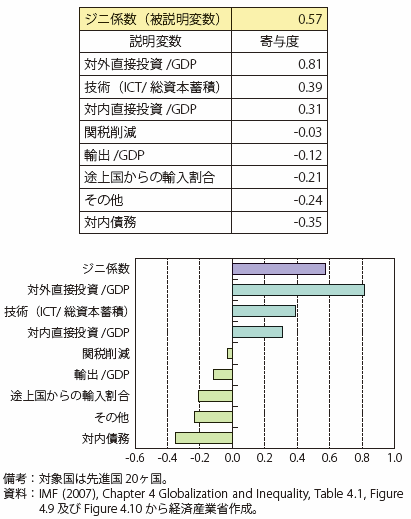
新興国だけの場合、技術革新の影響が全世界よりもより大きく出ていることに加え、グローバリゼーション全体(対内直接投資、関税削減及び輸出の合計)が格差縮小に出ている点が違う。なお、グローバリゼーションを対内直接投資、関税削減及び輸出に分解すると、対内直接投資が格差拡大に、それ以外の関税削減と輸出が格差縮小に効いている(第Ⅱ-1-2-3-3図)。こうした違いは先進国と新興国の間でグローバル化の経路が、先進国では金融面でのグローバル化拡大の影響がより早く生じるのに対し、新興国では貿易によるグローバル化拡大の影響がより早く出るという違いによると説明されている。
主な推計結果は、第Ⅱ-1-2-3-1図のとおり。なお、モデルは固定効果を用いている。
第Ⅱ-1-2-3-3図 IMF2007によるジニ係数拡大の要因分析(新興国のみ)
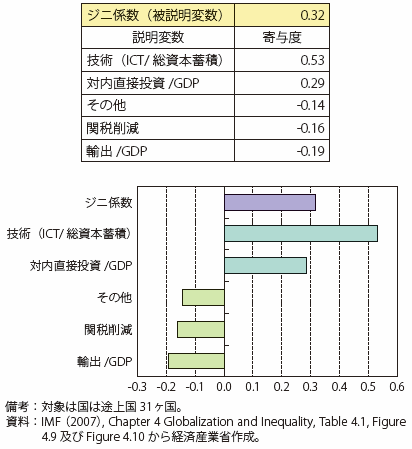
なお、対内直接投資が格差拡大に効いている点については、先進国において外資は高技能産業に参入するケースが多いと考えられることから、高技能・高学歴労働者の賃金が上昇すると思われる。
他方、世界全体では高収入のビジネスを誘致しようと競争が激しく行われている中、仮にこうしたビジネス誘致がうまくいかない場合、日本には高収入ビジネス産業がなくなってしまうリスクがある。反対に、対内直接投資による利益として企業ベースの生産性向上、当該産業全体の生産性向上、オープンイノベーション促進等が得られる。また、格差への対応については、貿易・投資政策とは別の国内政策手段(労働政策、教育政策等)で行うことも可能であり、我が国としては対内直接投資は積極的に受け入れていく必要がある。
23 Stolper, W.F. and P.A. Samuelson(1941), p. 58-73.
24 David H. Autor, David Dorn, and Gordon H. Hanson.(2013), p. 2121-2168 など
25 Douglas A. Irwin(2015), p. 142.
26 個別の指標の詳細については、IMF(2007), Chapter 4, Appendix 4.1.Data Sources and Methodsを参照頂きたい。
4.近年の格差拡大の要因分析
上記3.のIMF(2007)の研究は1980年~2006年の期間を調査対象としており、2001年の中国のWTO加盟に伴う中国の輸出拡大の影響が本格化した時期を十分に捕捉しきれていない可能性があることなどから、2001年~2014年の期間27を対象に新たな推計を行った。横軸は各指標が1%変化したときの、ジニ係数の変化率を表す。
調査対象の国について、IMFの分析は新興国を数多く含むサンプルを対象に分析を行っているが、格差の要因は先進国と新興国とで異なる可能性を排除できないことから、本分析においては先進国のみに絞ったパネルデータをもとに分析を行った28。また、今回の調査においては、グローバル化の内数となっていた関税と対内直接投資を説明変数から削除する一方、労働政策や大卒比率を説明変数として追加して分析を行った。
なお、被説明変数はIMF(2007)同様、再分配前のジニ係数を用いており、F検定とハウスマン検定を行い、それらの検定結果を踏まえて、ランダム効果モデルを採用して分析を実施した。
その結果、先進国の格差拡大の主な要因は技術革新(ICT投資)であり、貿易は、むしろ教育政策等と共に、格差縮小要因であることが明らかになった(第Ⅱ-1-2-4-1図)。
主な推計結果は、第Ⅱ-1-2-3-1図のとおり。なお、モデルは固定効果を用いている。
第Ⅱ-1-2-4-1図 近年の格差拡大要因分析の結果
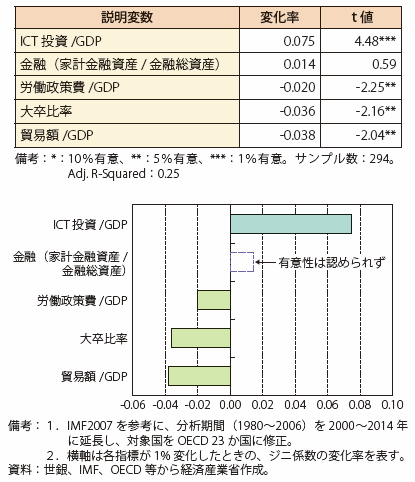
ただし、ICT投資の推進は、第4章で詳述するが、我が国の経済成長力の向上のために必要不可欠であるため、仮に我が国でICT投資が十分に行われない場合、国際競争力の低下を招き、国内には低賃金の職業しか残らなくなってしまう事態にもなりかねないことから、格差への手当は貿易・投資政策とは別の国内政策(労働政策、教育政策等)を講じることとし、ICT投資はこれからも積極的に進めていかなければならない。
なお、一部先進国では上位所得層が保有する金融資産が格差拡大の要因として挙げられることもあり、説明変数として個人金融資産を加えて分析したものの、今回の調査では有意性は認められなかった29。
27 なお、調査対象国の中には調査期間を通じてデータの欠損値が生じる場合がある。本調査の分析においては、IMF(2007)に沿って、データ欠損値から最も近いデータが6年以内の場合は年平均成長率(CAGR)をもとに推計し、データを補足している。
28 調査にあたっては、データの制約などを踏まえて、オーストラリア・オーストリア・ベルギー・カナダ・チェコ・デンマーク・エストニア・フィンランド・フランス・ドイツ・アイルランド・イタリア・日本・ルクセンブルグ・オランダ・ポルトガル・スロバキア・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス・アメリカの22か国を対象とした。使用した指標詳細については補論3参照。
29 金融資産の所得格差への影響については補論1参照。
5.OECD(2011年)による賃金格差の要因分析
OECDは2011年に、IMFがジニ係数を被説明変数としたのに対し、労働賃金(週給)の上位10%と90%の比率を被説明変数とし、貿易、技術、金融規制緩和(海外直接投資制限指数)、労働組合組織率、製品市場規制、雇用保護規制、税を説明変数として回帰分析を行っている30。
主な結果は、第Ⅱ-1-2-5-1図のとおり。貿易及び金融は賃金格差に有意な影響を及ぼしていないという結論になっている。他方、技術(科学技術活動への費用増加)については、IMFと同様、大きな影響があるという有意な結果が出ており、賃金格差における要因として、貿易や金融規制緩和(FDI制限指数)よりも技術革新の影響の方が大きく、また、教育が格差縮小に影響を与えるとの結論を示唆している。
主な推計結果は、第Ⅱ-1-2-3-1図のとおり。なお、モデルは固定効果を用いている。
第Ⅱ-1-2-5-1図 OECD(2011)による賃金格差の要因分析
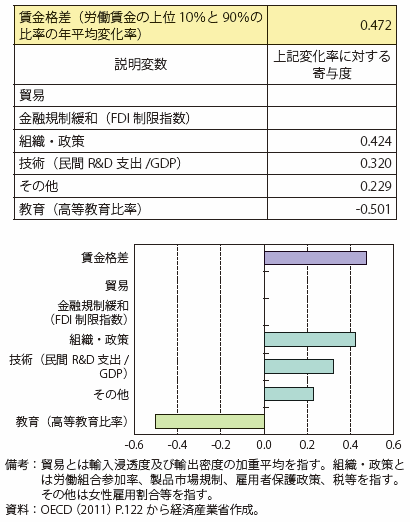
30 OECD(2011)
6.まとめ
我が国にとって自由貿易は経済発展の大前提であり、そのメリットは国民に広く理解されている。他方、昨今の国際情勢を見ると、自由貿易のメリットは必ずしも自明のものでなく、むしろ、格差を拡大させるものではないかといった不安・不満の声も出てきている。
自由貿易は経済のパイを拡大させるのみでなく、消費者にとっては購買力向上、生産者にとっては生産性の向上、というマクロ及びミクロ経済面でのメリットを確認した。また、「貿易が格差を拡大しているのではないか」との主張に対しては、IMFやOECDの分析を参考に分析を行ったところ「所得格差拡大は技術革新によるところが大きい」こと、また、「貿易は労働政策、教育政策と並び格差縮小に寄与する」との調査結果を示した。
他方、自由貿易が格差の要因でないとしても、現実に不安・不満を抱えている人達の理解を得るためには、格差縮小に寄与すると思われる労働政策、教育政策等を適切に組み合わせていくことで多くの人が貿易のメリットを得ることが可能な仕組みを構築していくことが必要である。
