第1節 我が国の経常収支の動向とインプリケーション
1.我が国の経常収支動向
(1)2016年の我が国の経常収支動向
2016年の我が国の経常収支は前年比+4兆1,070億円で20兆3,421億円の黒字となり、2年連続で黒字額が拡大した。本年の経常黒字額は比較可能な統計が取得できる1985年以降、2007年に次いで高い値となった。黒字額拡大の主な要因は貿易収支が前年比+6兆4,113億円で5兆5,251億円の黒字となり、東日本大震災が発生した2011年以降、初めて黒字転化したことである。加えて、サービス収支が前年比+7,827億円で▲1兆1,480億円となり、4年連続赤字額が縮小したことも影響している。サービス収支も比較可能な1996年以降で赤字額が最小となった。また、第一次所得収支は18兆1,011億円で前年比▲2兆9,177億円で18兆1,011億円の黒字となり、4年ぶりに黒字額が縮小した(第Ⅱ-2-1-1-1図)。
第Ⅱ-2-1-1-1図 我が国の経常収支の推移
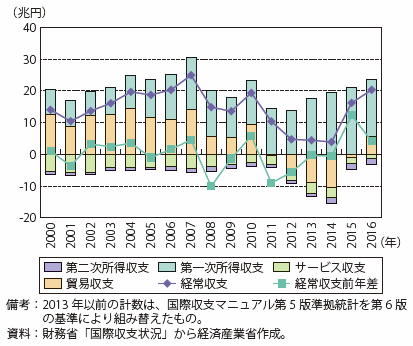
2016年の貿易収支を通関ベースで輸出と輸入のそれぞれについて見てみると、輸出額は70兆358億円で前年比▲7.4%、輸入額は66兆420億円で前年比▲15.8%となった。このことから、2016年の貿易収支の黒字転化は輸出が牽引したものではなく輸入額の減少に起因している(第Ⅱ-2-1-1-2図)。
第Ⅱ-2-1-1-2図 我が国の輸出入額の伸び率推移
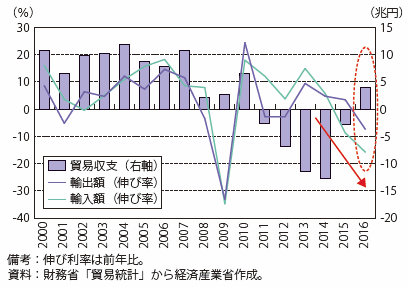
ここで、伸び率を大きく減少させた輸入額を品目別で見てみる。輸入額の減少分である前年比▲15.77%のうち、約半分の▲7.86%を鉱物性燃料が占めている(第Ⅱ-2-1-1-3表)。この背景には世界的な原油価格下落の影響があり、WTI原油先物価格の推移を見ると2014年から2016年にかけて▲68.1%と著しく下落している(第Ⅱ-2-1-1-4図)。この影響を受け、我が国でも原粗油輸入価格が大幅に下落し、輸入数量はあまり変化しないにも関わらず輸入金額は前年比▲32.4%下落した。加えて、半導体等電子部品を初めとする電気機器(寄与度▲1.56%)、衣服等のその他品目(同▲1.46%)等、全ての品目で前年比輸入額が減少したことも、輸入金額を下押しした要因である(第Ⅱ-2-1-1-5図)。
第Ⅱ-2-1-1-3表 我が国の品目別輸出入額の寄与度(2015年→2016年)
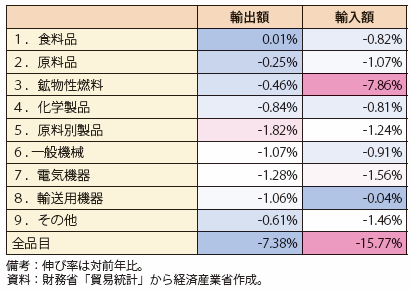
第Ⅱ-2-1-1-4図 WTI原油先物価格の推移
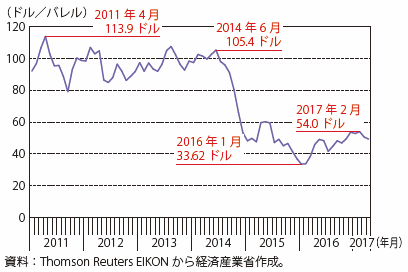
第Ⅱ-2-1-1-5図 原油及び粗油輸入金額の伸び率推移
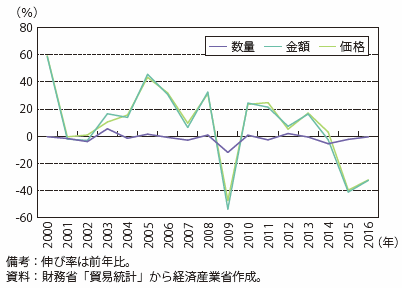
一方で輸出額を見ると、前年比▲7.38%とこちらも減少している。その内、特に原料別製品(同▲1.82%)、電気機器(同▲1.28%)が輸出額を下押した。輸入と同じくほぼ全品目で前年比輸出額が減少したものの、食料品は輸出額の前年比伸び率の内+0.01%と唯一増加に寄与している。特にアジアNIEsや中国向け輸出が増加しており、アジア圏における日本産の食品需要が徐々に向上していることが伺える(第Ⅱ-2-1-1-6表)。
第Ⅱ-2-1-1-6表 我が国の主要国・地域別、品目別輸出額の寄与度(2015年→2016年)
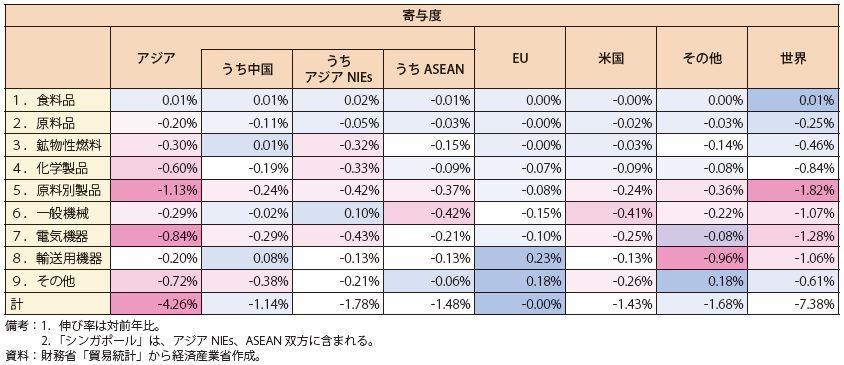
サービス収支の赤字額縮小の要因としては、昨年に引き続き、旅行収支と金融サービス収支の黒字額が拡大したことに加え、その他業務サービス収支が前年比+6,816億円と赤字額が縮小し、▲2兆5,764億の赤字となったことである(第Ⅱ-2-1-1-7図)。
第Ⅱ-2-1-1-7図 サービス収支の項目別推移(日本)
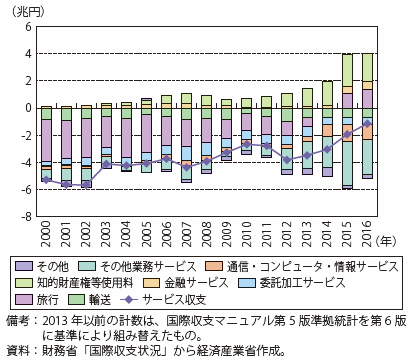
サービス収支全体では赤字額が縮小しているものの、さらに収支を受取と支払に分けると、受取額は全体で前年比▲3.9%と4年ぶりに減少している。一方で、支払額も全体で前年比▲7.2%と4年ぶりに減少しており、サービス収支も、貿易収支と同じく、支払額が受取額以上に減少したことで赤字額を減少させている。項目別で受取額を見ると、サービス受取が全体で前年比▲3.9%減少しているところ、旅行受取額が+1.6%の寄与を占めている。前年より伸び率は減少しているものの5年連続で増加しており、全体の受取額減少の歯止めに最も貢献をした項目である(第Ⅱ-2-1-1-8図)。支払額を見ると、全体の伸び率が前年比▲7.2%であるところ、その他業務サービス支払額が▲2.8%の寄与で5年ぶりに全体を下押しした。また、受取額、支払額に共通して輸送の伸び(受取額で▲4.3%、支払額で▲3.9%の寄与)が最も減少しており、前述した2016年の我が国の貿易額減少が輸送受取・支払額減少の一因であると考えられる(第Ⅱ-2-1-1-9図)。
第Ⅱ-2-1-1-8図 我が国のサービス収支受取の項目別伸び率寄与度の推移
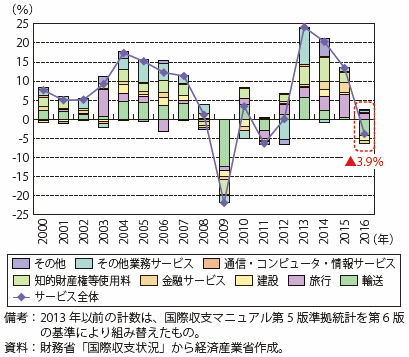
第Ⅱ-2-1-1-9図 我が国のサービス収支支払の項目別伸び率寄与度の推移
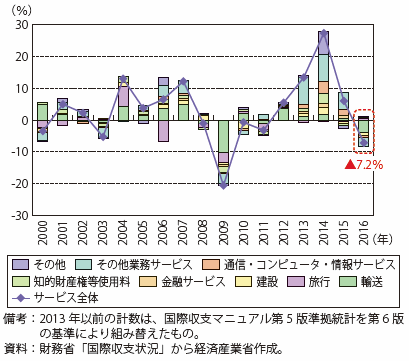
2016年の第一次所得収支は、全体の受取額減少によって、4年ぶりに黒字額が縮小した。この背景としては、2016年中の為替相場が前年に比べ円高方向に推移したことから、外貨建て受取に係る円換算額が目減りしたこと等が影響しているものと考えられる(第Ⅱ-2-1-1-10図)。
第Ⅱ-2-1-1-10図 我が国の第一次所得収支の項目別推移
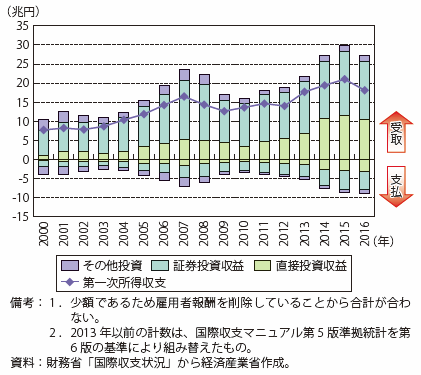
(2)足下及び今後の貿易収支動向
次に、我が国の貿易収支の足下及び今後の動向に関して概観していく。2016年は資源価格の下落等による輸入額の減少によって、貿易収支の黒字額拡大に至った。しかし2016年8月頃より、輸出額、輸入額ともに伸び率の下落幅が縮小していき、輸出額伸び率は2016年12月、輸入額伸び率は2017年1月にプラス転化した。輸出額に関してはその後順調に回復を続けており、2017年3月には7兆1,659億円と前年比+13.1%の伸びとなった(第Ⅱ-2-1-1-11図)。
第Ⅱ-2-1-1-11図 我が国の貿易収支、輸出入額の前年比推移
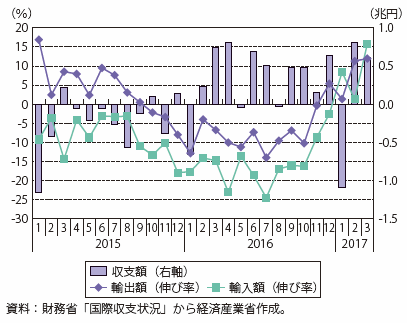
通関ベースで品目別に我が国の足下の輸出額を見ると、2016年第1四半期と2017年第1四半期を比較した際、輸出額全体の伸び率が前年比+8.51%となった。その内一般機械輸出額の寄与が+2.39%を占めており、特にアジアNIES向けで+1.14%の寄与と大きく伸びていることがわかる。さらに、一般機械を含めた全品目の輸出額でも、アジアNIEs、中国、ASEAN等のアジア新興国向けで輸出額が回復傾向である(第Ⅱ-2-1-1-12表)。
第Ⅱ-2-1-1-12表 我が国の主要国・地域別、品目別輸出額の寄与度(2016年第1四半期→2017年第1四半期)
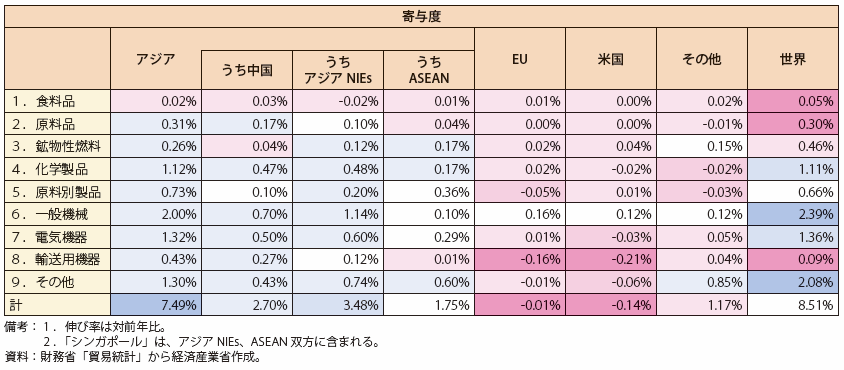
また、輸入(通関ベース)に関しては、2016年初頭まで大きく下落を続け、輸入額の下押し要因であった原粗油輸入価格が2017年2月時点で前年同月比+75.7%と、足下で回復傾向であり、輸入額の増加要因になっている(第Ⅱ-2-1-1-13図)。
第Ⅱ-2-1-1-13図 我が国の原粗油輸入額、価格、数量の伸び率推移
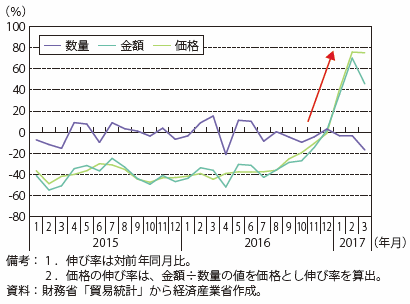
また、日本企業の外国での現地生産化や価格設定行動の変化といった構造変化を背景として、2012年以降の大幅な円安局面でも、輸出数量は対世界では横ばいで推移、対米国では減少している。このように最近は、輸出数量に対する為替の影響はほとんどなくなってきている(第Ⅱ-2-1-1-14図)。
第Ⅱ-2-1-1-14図 為替と輸出数量の関係
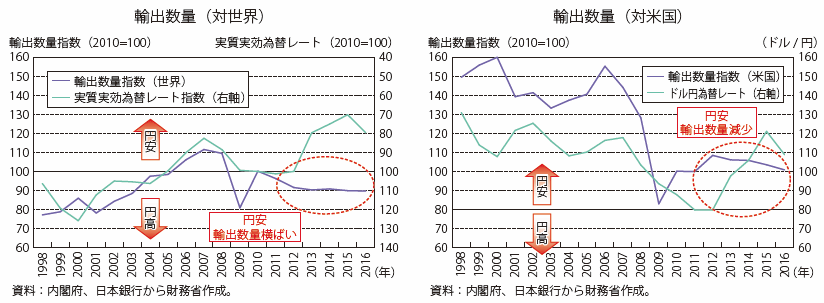
加えて、景気動向の先行指数であるPMIも、製造業、非製造業ともに2016年後期より世界全体で50を大きく超えて推移46しており、2017年は、先進諸国向けも含め我が国の輸出は拡大し、貿易額全体としては2016年比拡大していくことが予想される(第Ⅱ-2-1-1-15図)。
第Ⅱ-2-1-1-15図 地域別PMIの推移(製造業、非製造業)
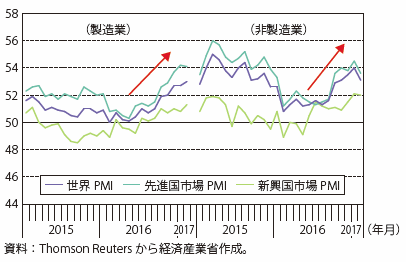
46 景況感の改善と悪化の分岐点となる値が50で、通常、50を上回ると景気拡大(景気が上向き)、50を下回ると景気後退(景気が下向き)を示唆すると言われる。(「金融情報サイトiFinance」から引用。)
