第2節 我が国の通商政策の方向性
この節では、我が国の通商政策を取り巻く環境がどのように変化してきたのかを述べるとともに、我が国として進むべき通商政策の方向性について述べていく。
1.我が国の通商政策を取り巻く環境の変化
我が国の通商政策を取り巻く環境は、経済活動の現実と国際貿易理論の発展の両面において大きく変化した。経済活動の現実に関しては、1980年代末から、情報革命によってアイデアの移動・貯蔵・加工に関する技術革新が起こり、コミュニケーションコストが劇的に低下することによって変化が現れた。
リチャード・ボールドウィン47によれば、これによって従来は複数工程が物理的に一箇所で行われなければ非効率であった状態が変化し、企業は各工程を「アンバンドル化48」して最適なサプライチェーンを構築することになった(第Ⅱ-2-2-1-1図)。また、工程の「アンバンドル」に伴い、中間の製造工程は途上国の低廉な労働力にオフショアリングされることとなった。結果的に、スマイルカーブの形状が変化し、中間の製造工程は相対的な低下を余儀なくされた(第Ⅱ-2-2-1-2図)。
第Ⅱ-2-2-1-1図 製造工程のアンバンドリング
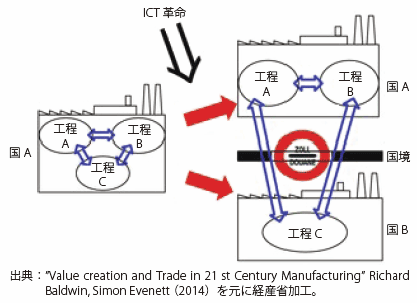
第Ⅱ-2-2-1-2図 スマイルカーブの変化
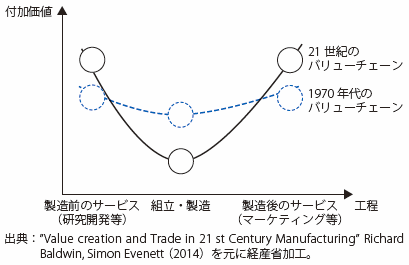
一方、国際貿易理論においても、クルーグマンの「新貿易理論49」を土台にして、メリッツが「企業の異質性モデル」(新々貿易理論)を提唱。
企業の異質性を前提とし、輸出に参入するのに必要なコスト、しかも輸送費用などの可変費用のみでなく固定費用(情報収集費用、販路開拓費用、流通網整備費用等)が支払える企業でなければ輸出に参入しないとして、同一業種内でも企業によって輸出企業と非輸出企業の差を説明した(第Ⅱ-2-2-1-3図)。逆に言えば、これまでグローバル経済への参入という恩恵を享受していない企業の中には政策的工夫でグローバル企業になれる企業が多数存在することを明らかにした。
第Ⅱ-2-2-1-3図 貿易の自由化と輸出企業・非輸出企業の増減
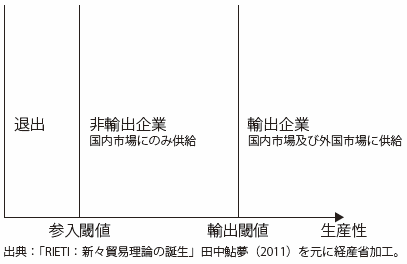
以上の経済活動の現実と国際貿易理論の発展の両面の変化が、これまで自由貿易を推進してきた国・地域の政策にも大きな影響を及ぼしつつある。
47 ジュネーブ国際高等問題研究所教授(1991~)。専門は国際経済であり、90~91年には米ブッシュ政権下において大統領経済諮問委員会エコノミストに指名されている。
48 アンバンドル化:ここでは、製造工程の細分化と複数国への分散及び相互ネットワーク化と定義。
49 新貿易理論:貿易発生の契機を各国の要素賦存の差異に求めるリカルドモデルから脱却し、企業が規模の経済を享受し輸送費用に守られて「輸出者」となることが貿易発生の契機とする理論
2.自由で公正な高いレベルの通商政策
ボールドウィンが主張するように製造が工程毎に「アンバンドル」され、従来は自国の法制度の下で展開されていた工程がオフショア化され、またスマイルカーブが変形し、両側がより高く、中間がより低くなった。このような時代では、製造を含め、企業が様々な事業を、国境をまたいで自由に行うことができるよう、人材、金、材料、情報ができるだけ自由に流通する環境を創出することが、企業活動の活性化にとって必要である。そのため、単に関税を削減撤廃するだけでなく、経済活動に影響を及ぼしうる他国(特に新興国)の制度が我が国と同等かそれに近いものであることを確保し、我が国企業が諸外国企業と同等な競争条件の下で国内外の事業を行う環境を整備することが、通商政策の主要目標となる。
将来にわたって自由、透明、安定、公平なビジネス環境を確保するためには、「自由で公正な通商ルール」を世界に広げていく必要がある。各国では、外資出資比率の制限、技術移転の要求、情報移転の制限等、外国企業の活動に制約を課す規制が数多く残されている。また、知的財産権保護の強化、通関手続の円滑化等、各国政府が企業活動の円滑化のために主体的に取り組むことが期待される規制もある。さらに、自国企業に対する市場歪曲的な補助金の交付など、市場の調整機能を妨げる制度も存在する。
こうした事業障壁を克服するための「自由で公正な通商ルール」の例がTPPである。TPPは、関税の撤廃に加えて、投資の自由化、模倣品・海賊版対策の強化、貿易の円滑化等のための規律を設けており、また、電子商取引、政府調達、国有企業等に関する規定も盛り込まれている。このように自由な経済活動を可能にする通商ルールの交渉や執行を通じて、自由で公正な経済圏を、アジア太平洋地域をはじめ世界に広げることにより、新しい時代に対応した貿易環境を整備していくことが重要である(第Ⅱ-2-2-2-1表、第Ⅱ-2-2-2-2表)。
第Ⅱ-2-2-2-1表 事業障壁となる措置の例
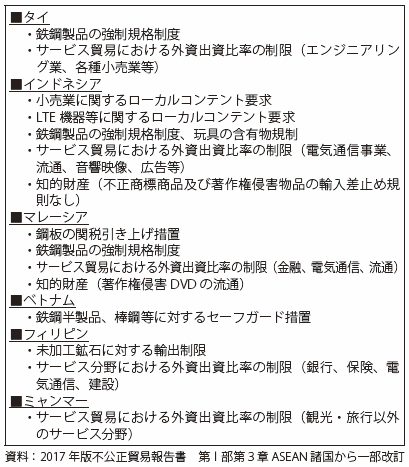
第Ⅱ-2-2-2-2表 TPPの主な合意内容
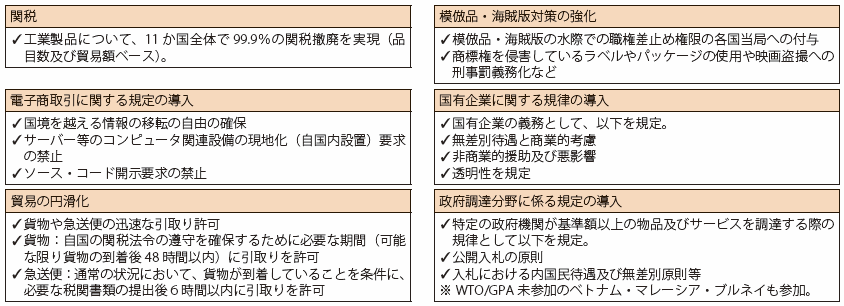
3.イノベーションを生み出す新たな産業社会の創造を支える通商政策
IoT、ビッグデータ、人工知能、ロボット等の技術革新による産業横断的な「第4次産業革命」のうねりは、革新的な製品やサービスの実現という形で国境を越えて社会の隅々に変化の兆しをもたらしつつある。こうした変化に対して我が国産業がグローバルな「勝ち筋」を見出していくためには、我が国の強みである高い「技術力」や高度な「現場力」を活かした、ソリューション志向の新たな産業社会の構築を目指していく必要がある。
本年3月に開催されたドイツ情報通信見本市(CeBIT)50に我が国がパートナー国として参加した際、我が国が目指す産業の在り方として、「Connected Industries」のコンセプトを世界に向けて発信した。これは、従来ともすると独立あるいは対立関係にあったモノとモノ(IoT)、人と機械・システム、人と技術、異なる産業に属する企業と企業、世代を超えた人と人、製造者と消費者など、様々なものがつながることで、新たな付加価値を創出し、社会課題を解決していくような産業のあり方である。この実現に向けて、国内において個別産業分野における取組やデータ流通の環境整備等を進めるとともに、通商政策の観点からも、人材投資の促進やオープンイノベーションの推進、高度人材の受入れ等の取組を進めて行くことが重要である。
また、我が国の対内直接投資フローは他の先進国と比較すると非常に低い値を推移しており、直接投資先としての魅力に関しても法規制などが要因となっており低い数値であるため、これらを改善していくことが重要である。また、高度外国人材のより積極的な受入れを図るためには、我が国の生活環境や本邦企業の賃金・雇用人事体系、入国・在留管理制度等が魅力的なものとなるように更なる改善を図る必要がある。
第Ⅱ-2-2-3-1図 対内直接投資フロー(対GDP比)
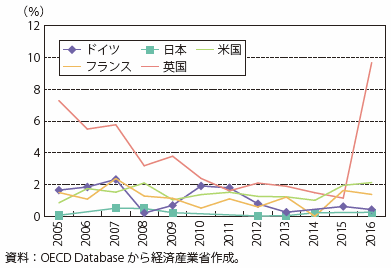
第Ⅱ-2-2-3-2図 直接投資先としての各国の魅力(スコア)
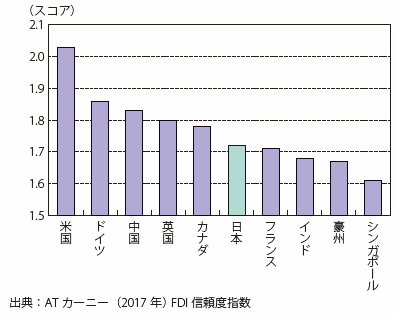
第Ⅱ-2-2-3-3図 日本の在留管理制度に対する回答
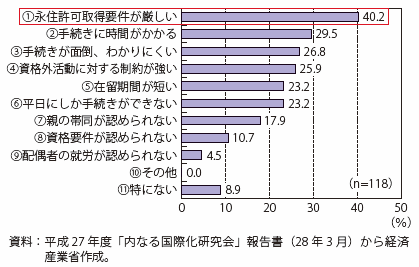
50 ドイツ情報見本市(CeBIT)に、我が国はパートナー国として参加。過去最大規模の118 社の日本企業が出展し(過去最大規模)、安倍総理大臣、世耕経済産業大臣他が出席。
